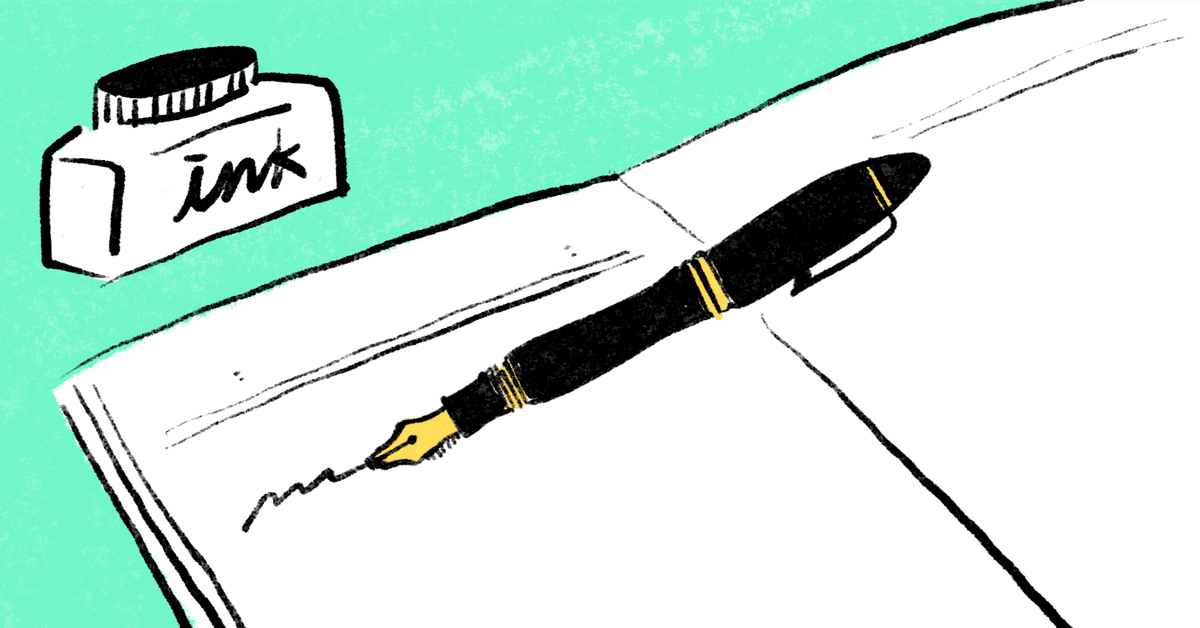
自分専用の「200の行動指針」をつくったら、人生がうまくいきはじめた
年末になると必ずやることがあります。
それは「行動指針」の見直しです。
行動指針というと、会社の「バリュー」のようなものをイメージすると思います。僕はあれを、自分専用につくっています。「自分のためだけの行動指針」をつくっているんです。
200項目ぐらいの行動指針を、手帳に書いて、毎朝見る。
たったそれだけなのですが、人生を根底から変える力がある目標管理の方法だと、個人的には感じています。
今回はその方法について紹介してみたいと思います。
いちいち考えて動いていたら間に合わない!
「行動指針をつくろう」と思ったきっかけは、職場でマネージャーになり、見るべき範囲が広がったことでした。
自分だけではなく、メンバーのことも見るようになった。そうすると、本当にいろんなことが同時に、たくさん起こります。「人と話す予定が1日に10件ある」みたいな状況です。
自分の場合、そうやって余裕がなくなると、柔軟な判断ができなくなりがちです。「えーっと、こういうときはどうするのが正解だっけ?」と考えるので精一杯になって、目の前のメンバーやクライアントに集中できなくなってしまう。
「これは、いちいち考えて動いていたら全然間に合わないな……」と思いました。
マネージャーとして、人として、気をつけたいことはたくさんある。でも、毎回頭で考えてそれを実行していたら、とてもじゃないけど間に合わない。
だったら、もっと自分の無意識に「行動の方針」をすり込めたらいいんじゃないか? そうすれば、考えなくても自動的にいい動きができる。心に余裕ができて、目の前のことにもちゃんと集中できるんじゃないかーー。
そう思って「行動指針」をつくってみることにしたんです。
手帳に書いて毎日見るだけ
こちらが実際の行動指針です。

運用のしかたは以下のような感じです。
①持ち運べる手帳に、行動指針を箇条書きで書く。
②毎朝、通勤中などに行動指針を読む。
③1日の終わりに、行動指針を見てふりかえりをする。
④1週間ごとに新しい行動指針を書き加える。
あとは②〜④を繰り返すだけ。とても単純です。
手帳はいろいろ試したのですが、常に携帯できるように、ポケットに入るサイズのものがいいなと思っています。
あと、スマホのメモではなく紙の手帳がやっぱりいいです。スマホだとSlackの通知が来たりして、行動指針を見ようと思ったのにDMを見てしまったりするので、疲れてしまうんですよね。
紙だと集中できるし、一覧性も高いので、結局いちばん効率的な気がしています。
ちなみに僕は「トラベラーズノート」という手帳のパスポートサイズを使っています。
年に1回、手帳を変えるタイミングで、新しい手帳に行動指針を書き写します。その際に項目をまとめたり、あらためて精査したりしています。
行動指針に照らし合わせて、1日をふりかえる
あと最近は、ふりかえり用のシートもつくって運用しています。

こんな感じで、日別のカレンダーに記録したい内容(「体重」や「歩いた歩数」など)を書いているのですが、そのなかに「行動指針」の項目もつくっています。
行動指針に照らして「今日は何点だったか?」を、5点満点で記録しているんです。評価はあくまで感覚なので「これができた気がする」みたいな感じなんですけどね。
忙しい時はチェックできないこともあります。でも、このシートがあることで「あ、できていないな」と気づけるのがいいんです。「いまは異常事態だぞ」ときちんと自覚できる。まずい状態を、無自覚に放置せずにすみます。
こうやって毎日フィードバックをして、行動指針を自分の無意識にすり込んでいくイメージです。
「永続的な態度」にしたいことを書く
行動指針に書き加えたいことがあったら、毎週末にまとめて書いています。
気づいたときにその場で書く、というわけではないんです。いったんは別のところにメモとして、ふんわり書いておきます。行動指針に入れるかどうか、あとから精査する感じです。
もちろん行動指針に入れないこともあります。
書かないものは2つ。ひとつは当たり前ですが、すでに書いたものと内容が重複しているものです。あと、個々別々の具体的すぎる内容も書きません。
行動指針には、ちょっと抽象度の高いことを書くようにしています。ToDo リストとは違うので、普通のタスクっぽいことは書きません。
たとえば、経営なら「一石三鳥を目指そう」、マネジメントなら「弱みより強みに目を向けよう」……といったことです。
どちらかというと、マインド面のことや「永続的な態度」にしたいと思うようなことを書いています。書籍で読んだ好きな格言や、尊敬する人に言われた言葉。あとは「背筋を伸ばす」などの、習慣にしたいことなどです。
「両極端なこと」を書く
行動指針を追加していくと「前に書いた指針と、新しい指針が矛盾している」こともけっこうあります。なんなら矛盾ばかりです。
でも、矛盾していても全然OKだと思っています。
というのも、思想や行動って「片方に偏り過ぎない」ことが大事だからです。
たとえば「目標達成のために数を追わないといけないけど、質も同時に達成しないといけない」みたいなことってありますよね。数と質、どちらかを捨ててどちらかを選ぶのではなく、なんとか両立できないか考える。
そうやってギチギチに負荷がかかった状態が、いちばんクリエイティブになれると僕は思っています。普通になにも考えずやったら偏ってしまうところを、両取りするには頭を使わないといけないので。
だから、矛盾したことが書いてあるのはむしろ「いいこと」なのかなと思います。
「数を追いかける」も「質を追求する」も両方書いておく。常に両極端なことを意識することで、結果的にフラットになる。これが一番いい状態だと思っています。
これさえ読んでおけばいい
「そんなにたくさん行動指針があったら、混乱するんじゃないか?」と思われるかもしれません。
でも逆に「これさえ読んでおけば、あとはなにも考えなくていい」ので、気持ちとしてはすごく楽なんです。
丸暗記する必要もありません。ただ毎日読むだけでいい。すると、自然と無意識が処理してくれるようになります。
だから僕はふだん、行動指針に書いてあることを、そんなに気にしていないんです。「朝に読んでいる」というだけ。あとは安心して、肩の力を抜いて過ごせます。その切り分けができるので、すごく楽なんですよね。
一流の人は、複雑なことを無意識にやっている
よくある習慣化のセオリーは「行動のハードルを極力下げる」ことだと思います。なるべくシンプルに、すぐやれるようにする。
それでいうと、行動指針は真逆かもしれません。複雑で難しいことを書いているし、どんどん項目が増えていきます。
でも僕はそういう「複雑なこと」を身につけたくて、行動指針をやっています。
一流のスポーツ選手って、すごく複雑なことを、無意識にやっていますよね。
たとえば野球なら、ボールをとって、1塁に投げる。その一瞬のあいだに、気をつけるべきことは大量にあります。フォームや握り方、力のこめ方……。いちいち頭で考えながら1塁に投げていたら、間に合いません。
しかも、常に同じ角度や力加減でやればいいわけでもなくて、状況に応じて臨機応変に動くことが求められます。
一流の人は、複雑なことを無意識にやっている。
これは仕事でも同じだと思います。その状態を目指すために「行動指針」というやり方をとっているんです。
「反復練習」が大切
複雑なことを身につけるために欠かせないのが「反復練習」だと思います。
野球なら、素振りやキャッチボールなどの基礎練習を、毎日くり返しやりますよね。反復練習をめちゃくちゃやって、1つ1つの複雑な所作やルールを覚えていく。
これは、マネジメントや仕事でも同じです。たくさん反復練習をしないと、クオリティは上がらないんですよね。
仕事には「練習とフィードバック」が少なすぎる
ただ、仕事はスポーツと違って、練習できる機会がとても少ないです。
だから仕事で成長するのって、すごく難しいんですよね。
たとえば「1on1のとき、これに気をつけて話そう」といったことは、やっぱり素振りとは違います。「素振り100回」は1時間もあればできるかもしれません。でも「1on1を100回」はものすごく時間がかかります。
100回やり終えるまで、ずっと変なやり方で1on1をしていたら絶対にダメですよね。
かつ、仕事だとフィードバックをもらえないこともたくさんあります。
スポーツならコーチがいます。やり方が間違っていても、見ればわかるので「フォームがおかしい」などと言ってもらえます。
一方で、仕事は密室で行われていたり、自分の画面や頭の中だけで行われていたりします。誰からも見えないので、指摘が入りにくい。上司であっても言いにくいです。行動の答え合わせも、放っておくと半期に1回しかありません。
上司や市場からのフィードバックが届く頃にはもう遅く、すでに信頼を失ってしまっていたりします。
その結果、みんな生まれながらのセンスだけで勝負して「よかった/悪かった」でキャリアが決まって終わり、になっていることが多い気がします。最初から器用な人はうまくいくけど、そうじゃない人はうまくいかない。
現状、ビジネスの世界って、そういうシビアすぎる環境なんです。
だからこそ、反復練習とフィードバックの機会を「自分で」つくるのがとても大切だと思います。
行動指針があれば、1日に何度も素振りができる
行動指針がいいのは「自分で自分にフィードバックできる」ことです。
「1on1で気をつけること」があるなら、もう少し抽象度を上げて「部下と話すときはこれに気をつける」ぐらいにして取り組む。そうすれば、1日のなかで何度も実践して、気づきを得られます。素振りと同じような練習が、仕事でもできるんです。
そうなると、スポーツが上手くなるように仕事も上手くなる。
逆にこうやらないと、仕事って上手くはならないんです。フィードバックがないので、なんとなくやって、なんとなく終わり。それで結果が出ずに「やっぱり俺、才能がないんだ……」という感じになってしまいます。
スポーツでいえば、練習せずに試合に出て「なんとなく負けちゃった」で終わり、みたいなことです。そんなことをしていたら、成長機会を得るより前に、信頼を失うほうが早いですよね。
行動指針をもつことで、日々の仕事のなかで何度も素振りができる。自分で自分を改善していけるので、すごく助かるなと思っています。
これがないと生きていけない、だから継続できる
僕は冗談抜きで「いま仕事ができているのは、行動指針のおかげ」ぐらいに思っています。これがないと生きていけない。持病の薬みたいなもので、もう手放せません。
ここまでくると、特に意識しなくても、自然と継続できます。
僕は毎朝1時間半、歩いて出社しています。そのときに行動指針を見ています。
この時間は自分にとってすごく大切です。業務中はなかなか考えられない長期的な経営のことも、そのときにしっかり考えるようにしています。この時間がなくなったら、たぶん大変なことになります。
そのぐらい本気で「こうありたい」と思っていることを書くのが大事だし、それが一番の継続のコツなのかなと思います。
お経や聖書のようなもの。生き方が変わる
行動指針をはじめて3年ほどになりますが、自分はめちゃくちゃ変わったと思います。実際、書いてある通りに振る舞うようになりました。
苦手だったマネジメントや、長期的な思考もできるようになってきて。今年からはありがたいことに、会社の代表を務めさせていただいています。
つねに意識してやっているというより、あとから振り返ったときに「ちゃんとできてたな」とわかる感じ。そう思える瞬間が増えてきました。
仏教のお経や、聖書に近いのかなと思います。日々の行動に方向づけをしてくれる。すると結果的に、生き方が変わる。
行動指針は「聖典を自分でつくる」みたいなことなのかもしれません。
劇薬ですが、個人的にはかなり効果があると感じています。もしピンときたら、自分だけの「行動指針」ぜひ試してみてください。
最後に
僕の「200の行動指針」を、見せられる範囲で載せておきます(できていないことも大いにあるので、かなり恥ずかしいのですが、、)。もし気になる言葉だったり、参考になるところがあれば幸いです。
経営
・心の中の違和感を見逃さず言葉にする
・関わる人数が多いことはゆっくりやる
・経営者は「A4用紙1枚」を信じるしかない
・部分最適をシナジーに変えよう
・一石三鳥を目指そう
・10倍を目指そう
・バーベル戦略、反脆弱性
・短期1年、中期10年、長期100年で考える
・人をプロデュースしよう、戦略を持とう
・それで最高幹部が育つのか?
・代表取締役が言わないと、誰も言ってくれる人はいない
・今自分が死んだとして、アイディアを誰かが引き継げるようになっているか
・ハレーションのある意思決定をきちんとしよう
・じっくり変化を待つ
・忙しくても採用と集客を止めない
・自分自身が次のステージに行く
・まずは自分がやる。自分なりの成功イメージ、方針を持つ
・1番大切な仕事を引き継ぐ
・進退を賭ける
・機密情報は決して漏らさない
・推奨とルール設定を活用
・引き継げる職責
・心の油断は10年後に組織に発露する
・短期の利益のために長期の資産を切り崩さない
・長期の施策で利を焦らない
・最悪パターンを想定し、2の矢、3の矢を
・きっかけではなくシステムの脆弱性を探す
・求心力のある太く力強い柱を立てよう
・次代で生み出す独自の「価値」を決めよう
・経営者は「旗」を立てることしかできない
・私の「心の中のできあがった塔」の熱いイメージを示す
・芯が太く懐が深い、良い意味の曖昧さがある「原型」を示す
・開発など中長期の仕事は経営トップにのみ許された大仕事である
周囲の制止を振り切ってでも庇護し、進退を賭けて進める
・反対意見を融合させる
・思考のねじれを正す
・適切な枠組みを作る
・研修は「1つのインパクト」に集中
・ベストソリューションであり続けられるか?
・顧客満足と評価、売上は関連するか?
・破壊的イノベーションが起こっていないか?
・内製化やリプレイスが増えていないか?
・これまでに無い新しいビジネスモデルが生まれていないか?
・価値のコアはどれだけの耐性があるか?
・人材の問題をリーダー達は自分の責任ととらえているか?
・価値連鎖、時間連鎖、情報連鎖、戦略連鎖、マインド連鎖
・上司が部下の強みを殺すバイアス
・「ものの見方」を見て プラスにつなぐシナジーを作る
・命令は脆弱、指摘されず実行されない
・社長の発言はメンツをつぶす。客観的事実に語らせる
・数字で考え、定性は補助
・検討会、評価会を挟み、会社の総意に
・骨子と実行を区別し、骨子は一緒に考える
・かすかな違和感、見て見ぬふりせずすぐ話す
・トレーニングは市場より厳しい水準で
・顧客、部下、私を最高に保つ
・希望を示す、ビジョンや旅の日程
・現在位置を明確にする
・上司がボトルネックにならない
・アベイラブルは最悪
・ガラスの壁を取り除く
・聖或を破壊する
マネジメント
・同じことは10回伝える
・後出しジャンケンマウンティングしない
・人は仕事の話しかしない人を信頼しない
・厳しいことの言える距離感を保とう
・やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば人は育たず。やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。(山本五十六)
・自分の過去の当たり前でマネジメントすると、レベルが低すぎてチームが死ぬ
・部下は自分より遥かに優秀
・「できないと困る」と「高みを目指す」を分けて伝える
・「褒める」「評価する」「承認する」を区別する
・今はできずとも「このままだと好ましくない」はフィードバックする
・大ざっぱに提案し、考え工夫する余地を残す
・部下の輝かしい未来を心から信じる
・弱みより強みに目を向ける
・フィードフォワード
・アドバイスを受け入れた理由を聞く
・強権発動を控える
・緊急時は断ったうえで介入する
・任せる判断は熟考の末、慎重に
・1個飛ばしNG
・まずは考えを聞く、初校をつくってもらう
クライアントとの向き合い方
・目上こそズケズケと接する
・なぜですか? 深堀りを徹底しよう
・即レス即対応
・期待を越える
・顧客ならでは、私ならではの提案
・小さな顧客こそ大切に
・事前に言えば説明、後から言えば言い訳
・エレベーターピッチ
・ヒアリングは最終提案のつもりで
・沈黙に怯まず1分黙る
・五感を総動員し観察する
・相手の仕事をリスペクトする
・自分がぱっと思いつくことは相手もすでに考えている前提で話す
・自分は無知で学びたいという態度で
・とがった提案は根回ししてからやる
・プロジェクトを成功させないとどうにもならない
・顧客の事業を本当に抜きん出て強くする支援
習慣
・「なんか」禁止 政治家のスピーチのつもりで
・ハーフパンツNG、襟付きの服
・スマホやPCを遠ざけ、目の前の人に集中
・メモ魔になろう
・フィードバックを求める
・集中する
・体脂肪率15%のお腹締め
・鼻腔共鳴
・全身ぐにゃぐにゃにゆるませる
・みぞおちを引っぱり上げる
・肩を落とす、あごを引く、肩甲骨を下げる
・腕を後ろに大きく引く
・つむじから上に引っぱり上げられる
・片足立ちで足ぐるぐる
・口を大きく開けて笑顔で
・横隔膜を下げる 肩もセットで下げる
・足裏の外側を踏み込み、土踏まずを上げる
・頭はスクワットのダンベル、潰されないようまっすぐ支える
・腕はデッドリストのダンベル、脇で支えないとつぶされる
・第四腹直筋の収縮
・7時間寝る
・クリアな頭を維持
・毎日ストレッチ
・家でPCを開かない
・1日1万歩歩く
・家で酒を飲まない
・最初のビールで最後まで粘る
・飲んだ後ラーメンを食べない
・18:00と21:30のアラーム
思考、マインドセット
・最高に変態的でやばい仕事はある。目の前で作れるはずである
・相手ボールか自分ボールかメリハリをつける
・相手も自分も翌朝目覚めないかもしれない。後悔のないよう振る舞う
・1番得意で楽しい視点で思う存分楽しく語ろう
・頭フル回転でドーパミンどばどば
・戦略家・ハッカーを極める
・膜をはらない しなやかな心
・1つの考えにすがり付かない
・深呼吸と脱力、心臓をテーブルに置く
・どんな時間も楽しく有意義な時間にする努力をする
・下調べして能動的に楽しむ
・大きい石から入れよう
・常に自己破壊しよう
・99%正しいは危険(無知の知)
・毛皮以外捨てるアメリカでなく、内臓まで活かすアイヌであれ
・直感を大切に
・何かをする理由が2つ以上あるなら、しない方がいい
・大事な決断はリスクを3つ考えたうえで
・尊敬する人を召喚する
・仕事はチャレンジ要素を入れる
・賭け要素は1つに絞る
・「順調」は水面下のリスクに気付いてないだけ
・私と会社は別で、私は会社に仕えている
・押す、引く、止まる、方向転換する、変化が起きる可能性を待つ
・逆境を糧とする
・コアなアイデンティティを肯定する
・直感を磨く
・一貫性を持つ
・正直でいる、心臓をささげる
・すべてを優先したくなる包摂性、リスク回避バイアスを避ける。必要不可欠なただ1つに集中する
・6:4で悪くないは天職
