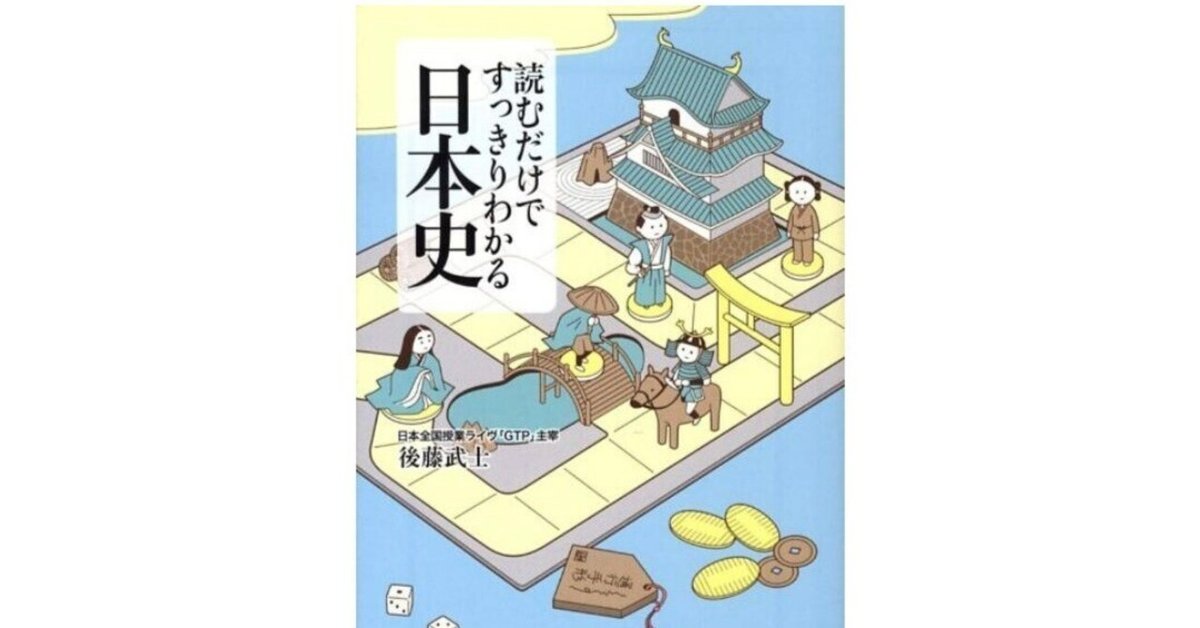
歴史マニアが粘着質に日本史入門書に噛みついてみた話
書店に行くと、素人向けの教養本が数多く平積みされている。
私も割とよく読むほうだ。哲学、金融、地政学、暗号資産などなど。
なじみのない分野について、軽く知識を仕入れるにはあの手の本が最適だ。
大学教授なんかが書いた専門書はひどく読みにくく、ハードルが高い。素人には素人向けの本が必要だと思う。
そういう教養本大好きな私が、唯一、手に取って来なかった分野がある。
日本史である。
私にとって日本史は、専門ではないがまあ詳しい分野だ。
いまさら素人向けの本を手に取る必要もあるまい。
だから、書店の日本史コーナーに行くと、私が手に取るのは・・・

こういう感じのマニアックな本。
武田なのに信長。
一般の人が「誰やねん」と思うような人物の伝記を買うことが多い。
しかしそんな私が、素人向けの日本史入門書を買ってしまったことがある。
帯が気になる日本史の入門書
もう10年ほど前のこと。コンビニにこんな本が置かれていたのだ。
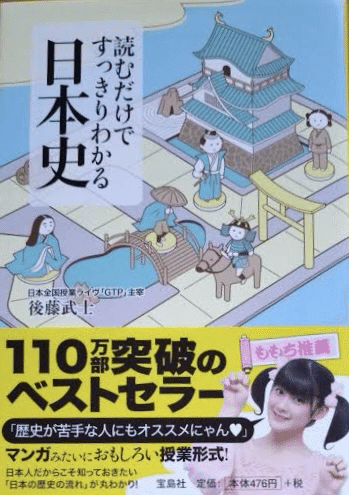
ももち推薦。
およそ日本史の本の帯に載るような人物ではない。というか、本当に読んでいるのか怪しい。
「110万部突破」との文言を見て、
「へえ、そんなに売れてるんだ」
と思いつつ、私の手が伸びることはなかった。
この本のターゲットは明らかに私ではないからだ。
しかしその2年後。
私はまた別のコンビニで、同じ本の進化バージョンを目の当たりにする。
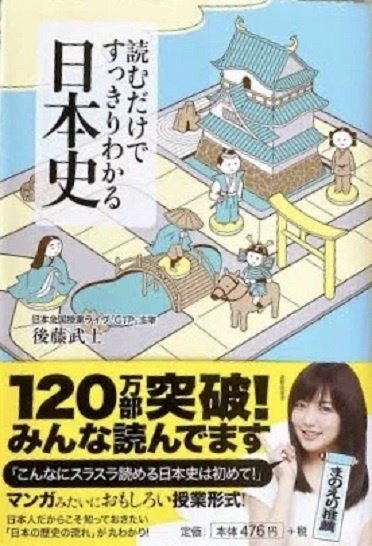
次は、まのえり推薦である。
いやー、ももちも読んでないだろうけど、まのえりも読んでないだろ。
「こんなにスラスラ読める日本史は初めて!」
とか言ってるが、本当にスラスラ読んだのか???
しかも、あれから2年で110万部が120万部になっている。
「なるほど、売れてるんだな」
とは思ったが、やはり私がその本を手に取ることはなかった。
さらにその2年後。この本は更なる進化を遂げた。

まゆゆもイチ押しである。
いつの間にか135万部売れている。
ここに来て、私は遂にこの本を手に取った。
中身をペラペラめくってみる。
まあ、読みやすい。
いま私が連載している「30年日本史」よりもはるかに読みやすい。
今後、何かに使えるかもしれないし、600円で買える。安いものだ。
買ってみるか。
と、私は軽い気持ちでその本を持ってレジに向かった。
あれから早5年。
せっかく買ったこの本、何かに使えないものか。
そう思いながらページをめくっていると、うーん、何だか間違いが多いのが目につく。
というわけで、これから私はこの本の誤りを一つ一つ指摘していきたいと思う。
とりあえず第1章「旧石器~古墳時代」を見ていこう。
①相沢忠洋の生年の表記が変
1926年、昭和元年に東京で生まれた彼は、子供の頃から考古学に興味をもち、独学でつまり学校に頼らず、自分の力で考古学を学んだ。
相沢忠洋が生まれたのは1926年6月21日。
この年は大正15年でもあり、昭和元年でもある。
しかし昭和に改元されたのは年の瀬も迫った12月25日なので、ここは「昭和元年」ではなく「大正15年」と書くべきだ。
②相沢忠洋は軍隊に入隊させられていない
両親の離婚があったり、奉公に出されたり、軍隊に入隊させられたり、苦労を重ねていたけれど、それでも彼の考古学への情熱は冷めなかったんだ。
相沢忠洋は自伝「岩宿の発見」の中でこう書いている。
昭和十八年、さびしくなった三社さまの夏祭りを最後として、七月初旬、青年学校の先生や旦那のすすめもあって海軍に志願することとなり、桐生へ一応帰ることにした。
つまり、相沢忠洋は軍隊に入隊させられたのではなく、自ら志願したのだ。
召集軍人ではなく職業軍人というわけだ。
③モースが大森貝塚を発見した日が違う
日本で最初に発見された貝塚は東京の大森貝塚という貝塚だ。これは日本人ではなくアメリカ人によって発見された。彼の名は「エドワード=シルベスタ=モース」。動物学者だったモースは明治初期の日本にやってきて東京大学の教授なども務めたのだけれど、なんと日本に来た翌日に大森貝塚を発見している。
一方、モースの回顧録『日本その日その日』にはこう書かれている。
横浜に上陸して数日後、初めて東京に行った時、線路の切割に貝殻の堆積があるのを、通行中の汽車の窓から見て、私は即座にこれを本当のKjoekkenmoedding(貝墟)だと認識した。
翌日のことを「数日後」とは言わないだろう。モースによる大森貝塚発見は、少なくとも日本に来た「翌日」ではなさそうだ。実際、モースの回顧録には上陸翌日に横浜を散策した旨が書かれており、東京に行く暇はなさそうだった。
④ハート型土偶の説明が変
頭がハートを逆にしたような形のハート型土偶や、眼鏡をかけたような顔の遮光器土偶などが有名だね。
「ハート型土偶」とは、群馬県で出土した顔がハート型の土偶のことだ。
こういうやつ。

頭がハートを逆にしたような・・・?
逆・・・?
逆じゃない。
⑤最初に日本について記した歴史書が違う
中国の歴史書に最初に日本のことが記されるのは紀元前1世紀頃、つまりキリストが生まれる数十年前、今から二千数十年前のことだ。この当時、中国は漢という王朝が支配していた。
著者は漢書地理志のことを想定しているのだが、実はもっと古い文献で日本について書かれたものがある。「山海経」という紀元前4世紀から紀元後3世紀にかけて多くの人々によって書き継がれて来た地理書があり、そこに「倭は燕に属す」との記述があるのだ。
まあ、これが後世に付け足された可能性も否定できないので、微妙なところだが。
⑥魏に使いを送っていた国の数が違う
さてその「魏志」倭人伝によると、邪馬台国には卑弥呼という女王がいたとのこと。当時の日本の中で30数ヵ国の国が魏に使いを送っていたらしい。
これは実に惜しい。魏志倭人伝の記述は次のとおり。
漢のとき朝見する者あり。今、使訳通ずる所三十國。
そう、「30数ヵ国」ではなく、ぴったり30ヵ国が正しい。
⑦漢字変換ミス
特に有名なのが大阪の堺市にある大仙古墳(大山古墳)で世界最大級の古墳だ。長さ486メートル、高さは30数メートル。外堀の周囲はなんと3キロ弱もある。あまりの大きさに近くで見るとただの森にしか見えない。周囲を歩いても見えるのは一番外側の堀(策で囲われていて水は濁ってきたない)だけだ。
これは単純ミス。
「策で囲われていて」→「柵で囲われていて」
⑧古墳に埴輪が置かれた目的が違う
これらが置かれた目的についてははっきりはわかっていないけれど、かつて王が亡くなったときに生きたままその召使らが一緒に墓に埋められたが、それはあんまりなので代わりにこうした埴輪を使うようになったという説が有力だ。
この情報はちょっと古い。
ここに書かれた埴輪の由来は、日本書記の記述によるものだ。
日本書記によると、垂仁天皇は叔父・ヤマトヒコが死去したときに、近習の者が生き埋めになって泣きうめいた声を聞き、心を痛めた。次に皇后・ヒバスヒメが死去したときに、垂仁天皇が
「殉死はもうやめさせたい。他に方法はないか」
と述べたところ、野見宿禰が
「実際に人や馬を埋めるのではなく、人や馬の形を作って埋めてはどうでしょう」
と提案したのが埴輪の誕生だとされる。
しかし、人を生き埋めにした墓は発掘されていないので、このエピソードはフィクションだというのが現在の考古学の定説だ。
間違いだらけの入門書?
以上、第1章(15~32ページ)だけで8箇所の誤りがある。2ページに1箇所のペースで誤りがある計算になる。
この本は間違いだらけだ! 読んではいけない!
・・・と言いたいところだが、いやまじでどうでもよく、指摘するほうが恥ずかしいくらいの些末な誤りばかりだった。
入門書としては何の問題もない。
せっかく買ったのでネタに使おうと思ったが、結局「歴史マニアが粘着質な感じで入門書にガンガン突っ込んでいくとどうなるのか」という実験にしかか使えなかった。
体力があればこんな感じで第2章以降の誤りも指摘していこうかな。
