
世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?
みなさんご機嫌よう。もーやんです。
本日は『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?~経営における「アート」と「サイエンス」~』について感想を綴ります。
一言で表すなら「美意識が必要なのはエリートだけじゃない」。
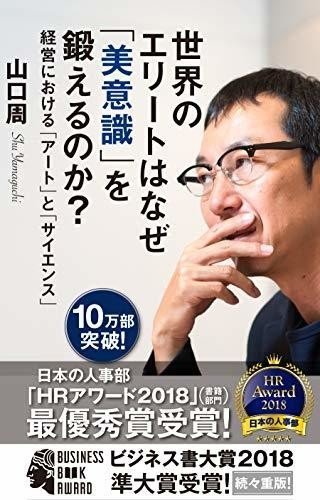
私が気になった点はこちら。
○『真・善・美』をモノサシとする
まず、この本で一番言いたかったのではないか、ということです。それを私なりに噛み砕いて感じたのは次のこと。
◆生産性や効率のアップで素晴らしいものはできるだろうか?
生産性や効率のアップは喫緊の課題として取り沙汰される昨今。でも、果たして本当にそうだろうか。という問題提起。
私自身は、『働く時間を減らして好きなことをしたい派』なので、職場の生産性向上は大賛成です。
でも、すべてにおいて画一的にムダ(と一見思われるもの)を省いたところで、優れた商品・システム・サービスは生まれるのだろうか?という点については考えちゃいます。
例えば、職人さんが途方もない時間をかけ、自身の美意識で磨き上げた作品。そこにかける時間にムダは1つもないけど、質を落として大量生産する場合、省かれる工程は増えるかもしれません。
でもそれで職人さんが淘汰された先に、新たな逸品が生まれる兆しはあるのでしょうか?
コピーは簡単だけど、秀逸なモデルを生み出す機会がなくなるかも。優れたモノって、生産性や効率という時間の枠外で誕生するのでは。
◆社員の人間らしさを消す会社って必要?
次に、そもそも私みたいに「働く時間は短い方が良い」って何故思うのか、ということ。
私は、『好きな仕事』と『必要だと思う仕事』は喜んでやります。それこそ残業も気にならないし、仕上げた成果には誇りも感じます。
でも、好きになれない・必要じゃない仕事ってありますよね?その時間を省くと、8時間(以上)×5日も捧げるのってどうなの?って思う会社もあるんです。
嫌気に拍車をかけるのが、本書でも触れている世界の問題。『人の貴重な時間を捧げて、労働を搾取して、蜜を享受するのはトップだけという構造』。
で、あれば。
自走できるスキルを身に付けて、会社を離れようとする最近の気運も納得。「この人間に付くぐらいなら、自分でやりたい」。そんな思いを抱く社員が増えたのは、経営者やリーダー達に美意識を求めている現代の表れかも。
○本の要約を読んでも無駄
話題の本を、要約だけ読んで分かった気になること、たまにあります。そんな私にグサッと刺さったのがこちら。
要約の知識を得ても、こけおどし。
真に学ぶべきなのは、その提言に至った著者の体験や思考プロセスなのだから。
○美意識を鍛え、直観力を鍛える世界のリーダー達
優れたリーダー達は瞬時に『モノ』の美しさを選定し、ブラッシュアップし、消費者を魅了します。あまりにも美しいそれは、魅了というか『欲情させる』に近いのかもしれません。iPhoneとか典型。
失読症の傾向も認められるような天性のリーダー達に近づき、超えるために、世界のリーダー達は『美意識』を磨いているそうです。
仕事に関係ないように思えるけど、文学、絵画を含むあらゆる芸術のワークショップに参加しているうちに、審美眼が鍛えられ、『モノ』の美を瞬時に判断する能力=直観力に繋がるのかも。
高尚で煙たい一派だけど(笑)、そうでもないと私は思いました。
だって、人間らしく生きたいなら、芸術は切っても切り離せないから。絵画を見ない人でも、誰でも、自然界の造形・在り方の『何か』に不変の美を感じますよね。歯車の一部であることに居心地が良くなるにつれ、無くしやすい感覚・感性。
その大切な感性を取り戻す作業が、芸術鑑賞なのではないかしら。そう思えた本書でした。
ちょっと意識高い系な感じだけど、私が続けるのは本を読むこと・機会ある限り芸術に触れること。この2つ。
それでは、今回はこの辺で。
まだまだご紹介したい本はたくさんあるので、これからも続けますよ(*'▽')
