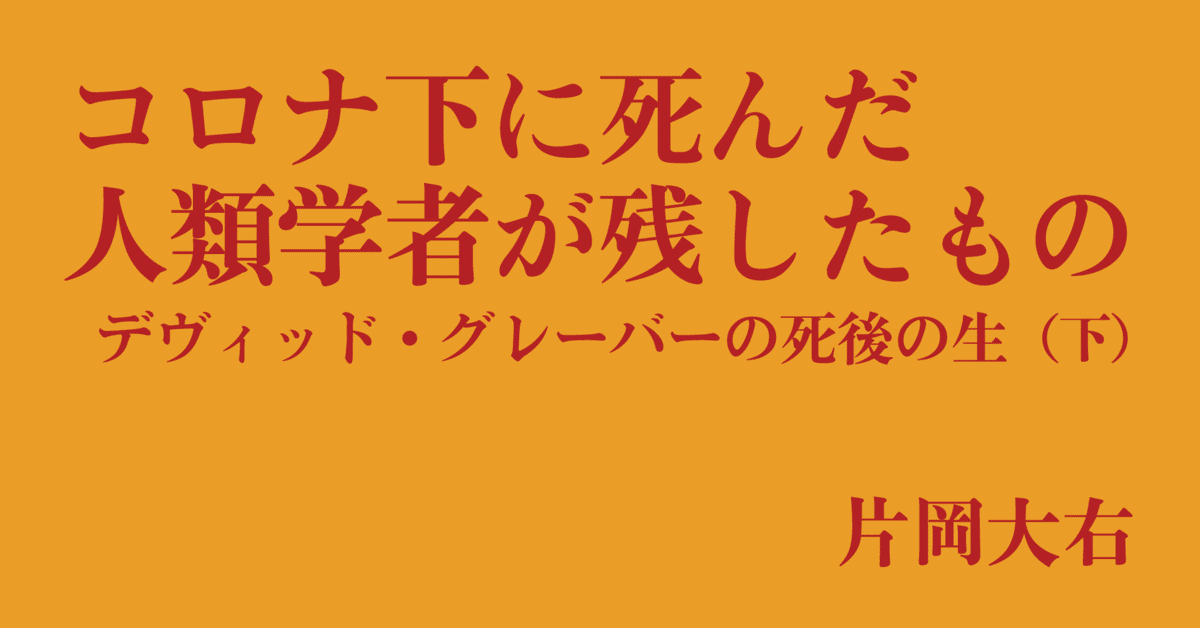
コロナ下に死んだ人類学者が残したもの デヴィッド・グレーバーの死後の生(下)|片岡大右
亡きあとも、わたしたちやこれからの世界に与えてくれるところの大きいデヴィッド・グレーバーの言葉と思想。「アナキスト」としての自己規定について分析した(上)に続き、グレーバーの死について、そして死の直前に脱稿した共著“The Dawn of Everything”について、片岡大右さんが考察します。(編集部)
3 突然の死の背景
3-1 アナキズムの2つの次元
本稿(上)に掲載の「2」で見たように、グレーバーは出版活動の初期に指導教官の気まぐれな提案に応じて執筆した『アナーキスト人類学のための断章』のタイトルをのちに後悔して、ツイッターアカウントのプロフィール欄で10年近くにわたり、「わたしをアナキスト人類学者と呼ぶのはやめてください」と強調しながら死んだ。
政治的信念と学問は別だというのが理由のひとつだけれど、そればかりではない。「アナキズムというのはやることであってアイデンティティになるようなものではない」と上記プロフィールにあるように、グレーバーは誰もの行為のなかに「アナキスト」な次元を見出しうると考え、そうした次元が社会全体に広がっていくことを展望する一方で、自称しようがしまいが、フルタイムの「アナキスト」は存在しないとみなしていた。
こうしたわけで、彼は、前掲『断章』(原著2004年)や『民主主義の非西洋起源について』(初出2005年)といった初期著作を除き、著作において「アナキズム」の立場をほとんど説いていない。また、「アナキスト」の自称を保持しながらも、それを強調することには慎重になっていたように見える。
そのうえで述べるなら、だからといって、グレーバーにとってアナキストとしての自己規定が、それほどの意味を持たなかったというわけではない。つねにそれを表立って掲げるかどうかとは別に、彼がアナキズムの原理を貴重なものに思い賛同を示し、自らその原理を生きようと努めたことは明らかだ。しかも彼のアナキズムは、しばしば相互に無関係ないし対立的なものとみなされる2つの次元を自覚的に統合した、その意味で真に十全なものだったように思われる。
この2つの側面を、アナキストとして出発した米国の社会理論家マレイ・ブクチンは、集団志向の「ソーシャル・アナキズム」と個人志向の「ライフスタイル・アナキズム」として定式化した。ブクチンは両者を「架橋不能」とみなしつつ後者を非難し、やがて彼が支持する前者の方向性を「コミューン主義」と名付けてアナキズムから離れてしまう。グレーバーはそれに対し、『直接行動――ある民族誌』(原著2009年、未訳)のなかで、現実の活動家を見るなら、2つの側面はしばしば同じ個人のなかに共存しているのだと指摘している[1]。
一般的に見ても、個人志向と集団志向の関連付けは重要な課題であって、この点では例えば、2021年6月に倉敷市で開催され、東京をはじめ各地に巡回された川上幸之介による企画「PUNK! The Revolution of Everyday Life」が、「騒がしい音楽に派手なビジュアル、暴れる観客といったイメージ」に代表されがちなパンクを、「相互扶助」のような他者とのつながりの原理との関係で捉えなおすものとして注目に値する。この展覧会のカタログに、グレーバーの重要論考のひとつ、「ポスト労働者主義の悲哀」の翻訳が掲載されているのも偶然ではない[2]。
グレーバーに戻るなら、「アナキスト」の主張として読まれたくはないという断りにもかかわらず、彼の全著作には一貫して、上記の2つの次元の統合ないし両立の努力を読み取ることができる。とはいえ、もちろん、両者の完全な調和を持続的に実現させることは不可能だろう。グレーバー自身、「架橋不能」だというブクチンの主張には反対するものの、個人と集団のあいだの緊張がまったく消え去ってしまうような未来を展望していたのではない。
この点について、本稿「2」で触れた没後刊行の対話集を再び取り上げるのは有益だろう。グレーバーはそこで、「アナキズムに対する標準的な非難が、人間本性を素朴に信頼しているというものであるのはまったく皮肉だと思う」と述べる。アナキストの反国家主義は、強大な権力を誰かに委ねるなら恣意的行使は免れがたいという醒めた見方によるものなのだから、むしろ「アナキズムは徹底して、人間をあるがままに受け入れている」のだという。
アナキズムは人間本性をあるがままに受け入れる。そしてそのうえで、人間の人間としての輝かしさと悲惨の両方を見据えながら、よりよい社会のあり方を構想する。興味深くもあれば悲しくもあるのは、グレーバーのあまりに早すぎた死それ自体が、この人間本性の両義性と深く関わる出来事だったように思われることだ。以下ではその点を、最も身近で彼の死にゆく過程を見届けた人物の証言を通して見ることにしたい。
3-2 コロナ下の死をめぐる「陰謀理論」
デヴィッド・グレーバーの最初にして最後の夫人であり、2019年4月の結婚ののち、彼と様々な共同作業に取り組み始めていたアーティスト、ニカ・ドゥブロフスキーは(2人の共同作業がどれほど豊かなものとなりえたかは、既訳の『パラサイト』論を一読するや直ちに了解されるだろう)、夫の突然の死から数週間を経た10月17日、夫妻が昨年5月に開いたばかりの「みんなの人類学」のページ中に「デヴィッドの死因についての私見」を公開した。「膵炎による壊死に起因する大量内出血」という検死報告を紹介したのちに、ドゥブロフスキーは以下のように続ける――「わたしはわたし自身の陰謀理論を付け加えたいと思います。わたしは、彼の死がコロナと関係していると確信しているのです。」冒頭のこの言明は、全体を読む十分に説得力をもって響いてくる。
前半を読んでわかるのは、ドゥブロフスキーが当初から――3月末に自ら感染する以前のボリス・ジョンソン首相が、「集団免疫」を掲げ放任政策を続けていた頃から――パンデミックを深刻に受け止め、自己隔離生活を入念に準備していた一方、グレーバーは、英国の多くの人びとと同様、生活スタイルの急激な変更をたやすく受け入れようとはしなかったという事実だ。しかも2人は、賑やかな市場街として有名なロンドンのポートベロー通りに住んでいたのだった。
ポートベロー・マーケットはいつもどおり開いていました。ロンドンっ子はマスクも手袋もしていませんでした。わずかな例外を除き、パンデミックに対する人びとの態度は一般に、高を括ったようなものだったのです。〔…〕隔離生活のルールに従い、カフェに行かず隣人に会わないでいるのは、デヴィッドにはつらいことでした。彼はマスクを嫌い、使い捨て手袋を再利用しようとし続けました。
彼は友人たちに、妻から受けている「虐待」について穏やかに不平をこぼした。そして彼女は、「頑固に立場を変えず、すぐに2人でロンドンを離れ、どこか遠い村で完全な自己隔離生活を送るべきだと主張することもできた」のに、そうしなかった。「支配魔にも厳しい妻にもなりたくなかった」からかもしれないと彼女は振り返っている。
ともあれ、ロンドン生活を続ける2人は、「3月に奇妙な症状に苦しみ始める」。「おおよそ週に1度、頭痛と筋肉痛、肺のうずき、極度の疲労(電話で話せなくなるほどの)がやってきた」のだという。ひどい眠気を伴うこうした症状は一旦消え去るのだけれど、数日後には同じ症状が戻ってくる。やがて妻はすっかり回復した。しかし夫の症状は新たな展開を見せる。グレーバーは「口のなかになんとも言えない奇妙な石鹸のような味」を感じ始めた。新型コロナ感染を疑って抗体検査を受けたものの、結果は陰性。その後しばらくすると、彼は指先のうずきに苦しむようになった。「ギターの練習しすぎ」が原因だろうか? しかしやがて、うずきは足指と脚にも広がっていく。「疲労。穏やかな、けれどいつまでも続く腹痛。消化器系の疾患」。ロンドンとベルリンで何人もの医者にかかり、検査を受けるが、どの医者も「ウイルス感染後症候群」を診断しつつ、ただ待つことを求めたのだという。「待つことです。そうすればすべてが解決します。」ドゥブロフスキーは、「それでわたしたちは待ったのです」と続けている。その結果はどうなったか。
様々な関係者への取材を経て人類学者の生涯をたどる『ニューヨーク・マガジン』ウェブサイトの記事(2021年11月9日)によると、健康回復を期待して訪れたヴェネツィアで、グレーバーは妻や友人と浜辺で泳ぎを楽しんだものの、その後に容態を悪化させて病院に運び込まれた。病室での最期の様子は、以下のように記されている。「「彼はわたしにジョークを言っていました」、ドゥブロフスキーはそう振り返った。大したことはない、きっとよくなる、というのだ。「すると突然、医者に彼は死んだと告げられたのです。」」
最期に再び「デヴィッドの死因についての私見」に戻り、ドゥブロフスキーの述懐を読むことにしよう。
デヴィッドはヴェネツィアの病院でコロナの検査を受けたのですが、結果は陰性でした。彼の死がコロナと関係している可能性について尋ねると、医者はこう答えました。「検査をして陽性なら、コロナに感染しているということです。けれども、検査で陰性でも、感染していないということにはなりません。」わたしも医者と同じように感じています。わたしとしては、彼がこのまったく奇妙な病気をこんなにも早く悪化させてしまった理由のひとつはコロナだろうと感じているのです。それでわたしが非難したいのはボリス・ジョンソンのふざけた政権であり、人間一般の愚かしさと自己過信です。
デヴィッドは壊死性の膵炎と内出血で死にました。けれども、健康で、まったくアルコールを飲まないデヴィッドが、どうして突然こんな病気になったのでしょう? どうしてこんなに突然で、こんなに急速に悪化したのでしょう? どうしてこんなに奇妙な色々な症状が併発したのでしょう? どうしてこの病気は、わたしたちがコロナにかかったと思ったその直後に始まったのでしょう?
こうして見ると、デヴィッド・グレーバーがいわゆる「偽陰性者」としてパンデミックの犠牲となったと考えることは、それなりに妥当な見解であるように思われる。
3-3 人間本性の還元不能の愚かしさ
いずれにせよ、ここで確認しておきたいのは、グレーバーが新型コロナ感染の脅威を過小評価し、国家の統制のもとで日常生活を制限されるのを容易には受け入れなかったという事実だ。先ほど参照した『ニューヨーク・マガジン』の記事にはこうある。「パンデミック下のロンドン生活は、グレーバーにとっては難題となった。彼は気質的に、隔離生活に反発を感じていたのだ。」
2020年春、ジョンソン英首相が厳格なロックダウン実施へと転換したロンドンで外国メディアの取材を受けたグレーバーは、パンデミックの脅威に対抗すべく多くの国で採用されたこの措置が、わたしたちに現実の真の姿を見せてくれたと主張していた。このような主張は――本稿の筆者が当時記したように(「魔神は瓶に戻せない」、以文社ウェブサイト)――、「ロックダウンに際して国家権力が発動する一連の強制的措置の告発を(例えばジョルジオ・アガンベンのように)最優先の課題とするのではなく、それを積極的に称賛しないまでも多少とも脱問題化」することを前提としている。
しかしそうした主張を唱えながらも、グレーバーは強いられた隔離生活に我慢ならないものを感じていた。文字通りに致命的なものとなったのかもしれないこうした感じ方と振る舞いを、ドゥブロフスキーが「人間一般の愚かしさと自己過信」に結びつけているのは正当というほかない。
けれども、ひとりのアナキストにとって、危機的事態を前にして「リヴァイアサン」の力に易々と身を委ねるというのもおかしな話だろうと思う。深刻な帰結を招きかねないことを承知のうえで自らが望む生き方を貫こうとするこうした姿勢は、先ほど取り上げたアナキズムの一側面、ブクチンの言う「ライフスタイル・アナキズム」のひとつの表れとみなすことができる。グレーバーは、他者との協同とコンセンサス形成を志向する「ソーシャル・アナキズム」の方向性を強調する一方で、個人主義的な自由への渇望を、それが集団的秩序をかき乱し、自己の生命を脅かしかねない局面においてさえ、必ずしも抑制することがなかったように思われる。彼はそのために最も高い代価を支払うことになった。
しかしこの痛ましい出来事は、輝かしい積極面とともに様々な意味での愚かしさをも含んだ人間本性の変わりがたさを受け入れ、こうしたありのままの人間本性をあらゆる社会構築の企ての土台とみなしていた人類学者の生涯には、ふさわしいものだったと言えるかもしれない。
ここではさらに、グレーバーにおける国家の位置づけの両義性についても確認しておきたい。
ベーシックインカムへの賛同、またより一般的に言うなら、過去の福祉国家体制およびその再建の試みへの一定の評価からは、グレーバーがアナキズムの原理を柔軟に捉えていたことがうかがえる。このような姿勢は、アナキストにとって必ずしも当然のものではない。例えばブレイディみかこは、グレーバーと同質の柔軟性をもってアナキズムと「反緊縮」の経済政策(それは国家による一定の統制への期待を前提とする)を同時に支持する自らの議論への反発の声として、「アナキズムは国家と経済を破壊する革命」だと説くメールが届いたことを証言している(本稿(1)前掲『ブロークン・ブリテンに聞け』、「『負債論』と反緊縮」)。
ロックダウン実施の是認についても、こうした流れのなかで捉えることができるだろう。しかしすでに見たように、グレーバーは同時に、この国家権力の強制による日常生活の制約に対して「気質的」と言えるほどの反発を示していた。本稿の筆者は以前、スラヴォイ・ジジェク――元来国家の役割を重視し、グレーバーにこのうえなく嫌われていた――のパンデミックをめぐる立場とグレーバーのそれの近接性を強調したことがある(前掲「魔神は瓶に戻せない」、注2)。ロックダウンの是認という点ではたしかにそうなのだけれど、やはり両者のあいだには、単にニュアンスの問題で片付けることのできない深い不一致が見出されることを指摘しておかなければならないだろう。
ジジェクはアガンベンに対する論争的文脈を繰り返し前景化しつつ、「十分に人間らしくあり続けるためには、(感染の危険に身を晒すという)命のリスクを冒さなければならないのか」と問いかける一方、ロックダウン下の静かな日々のうちに、「疎外なき穏やかな生活、と臆面もなく呼べるような何か」の表れを認めた。ところがグレーバーにとって、隔離生活はまさしく、耐え難い疎外の経験と感じられていたようなのだから[3]。
ともあれ、新型コロナ感染の後遺症と思われるものの苦しみのなか、『負債論』と並ぶ代表作となるはずの大著、考古学者の友人デヴィッド・ウェングロウとの共同作業の成果であるThe Dawn of Everythingが急逝の直前――ひと月足らず前――に脱稿されたことは、せめてもの僥倖だったと思うほかない。
4 永遠の夜明けを開く
4-1 ルソーを継ぐ者としてのグレーバー?
本稿の「2」で取り上げた2018年の「略歴」のなかで、グレーバーは自らの生涯を簡潔に振り返ったのち、著作家としてのキャリアの叙述を考古学者の友人デヴィッド・ウェングロウとの共著の予告で締めくくっている。
現在は、考古学者デヴィッド・ウェングロウとの共著として「社会的不平等の起源」の問題に取り組み、この問題の出発点がどこに定められてきたのかを問い直すことから始めて、一連の仕事にまとめようとしています。その後のことは、誰にわかるでしょう?
そして彼は、『ブルシット・ジョブ』に続くこの最新の中心的プロジェクトの第一作を2020年夏に脱稿した直後、わたしたちのもとを去った。新たな代表作となることは間違いないこの著作の刊行に目処がついた頃、あるいは刊行後の喧騒のさなかに、「略歴」は更新されたはずだ。しかし人類学者の突然の死は、「その後のことは、誰にわかるでしょう?」という彼の自問を決して解きえない謎に変えてしまった。
ところで上記の引用では、遺作となってしまったこの著作の主題が、「社会的不平等の起源」の問題だとされている。それではグレーバーは、ジャン=ジャック・ルソーが『人間不平等起源論』によって切り開いた道を引き継ぎ、さらにその先へと進むべく、考古学者の友人との共同研究に着手したのだろうか。こうした予断はおそらく、彼の仕事をめぐる通念的イメージに適ったものではあるのかもしれない。例えば経済人類学者キース・ハートは、「ルソーの足跡をたどって」と題する『負債論』の書評を著し、この18世紀思想家の21世紀における継承者としてグレーバーの肖像を描き出していた。
ところが当のグレーバーにとって、こうしてルソーになぞらえられるのは、控えめに言っても戸惑いを引き起こす事実であったようだ。先輩格の同業者の称賛的書評に対し、彼はわざわざ以下のような留保をツイートしている。「キース・ハートはわたしをルソーだと思っている! わたし自身がルソーについてどのように感じているのか、確証が持てないのですけれど」(2012年7月5日)。
いったいルソーに例えられることの何が不満だったのか。本稿のこの「4」では、この点を皮切りに、2021年冬に原著が刊行された遺作、The Dawn of Everything: A New History of Humanity(さしあたり『あらゆるものの夜明け――新しい人類史』のように直訳できるが、以下ではDoEと略記する)の若干の紹介を試みたい。というのも、本書の中心主題はまさしく、『人間不平等起源論』の遺産の清算にあるからだ。
グレーバーと親交があったカナダのSF作家コリン・ドクトロウが指摘するように、この大著は評者がどのような角度から論じるかに応じ、まるで別の書物の紹介であるかのような相互に異なった相貌を示す。筆者のアプローチも様々にありうるなかのひとつにすぎない。それでも筆者としては、本書の中心的な主題と思われるものを、その独自性を浮き彫りにするかたちで伝えられたらと考えている[4]。
4-2 原始主義の逆説
本稿の筆者は『朝日新聞』に掲載された追悼記事のなかで、事前に与えられていた情報からするなら、やがて刊行されるグレーバーの遺作は「実に五万年の時空を探索し、『サピエンス全史』の歴史学者ハラリに典型的な、陰鬱な未来像を打ち破ろうとする野心的な仕事」となるだろうと記した。実際、彼はDoEにおいて、考古学者の共著者を得て『負債論』のおよそ10倍におよぶ時間の広がりに向き合い、まさに「新しい人類史」の提案にふさわしい視野の拡大を実現している。しかし、この遺作の中心的主題自体は、彼の初期からの持続的な関心を展開したものにほかならない。それは第1章において「ジャン=ジャック・ルソーの永遠回帰」を終わらせることとして定式化されているけれど、別の言い方をすれば、「原始主義」の克服の試みということになる。
「原始主義」(プリミティヴィズム)は、原初の――「文明」に先立つ「自然状態」を生きるものとされる――人びとの境遇を理想化し、この始原の生活を規範として以後の人類社会を告発するたぐいの精神的態度として理解できる。学術世界においてこうした精神的態度に呼応する顕著な出来事としては、グレーバーの母校シカゴ大学において1966年に開催されたシンポジウム「狩猟人」(Man the Hunter)が記憶されている。さらに指摘すべきは、1960年代末以降の米国および世界中で、原始主義的発想を活気づけ理論的根拠として引き合いに出されてきたのが、彼のシカゴでの指導教官マーシャル・サーリンズの有名な論文「原初のゆたかな社会」だったという事実だ[5]。
上記シンポジウムでの報告に基づき、旧石器時代の狩猟採集民の生活の厳しさという当時の通説を転覆させたこの1968年の論文は、DoEによるなら(第4章)、「おそらくこれまでに書かれたなかで最も影響力を持った人類学の論考」となって、「お手軽な議論や論争を生み出し、社会主義者からヒッピーまでに刺激を与え」てきた。同じ箇所では、「ある種の思想潮流(原始主義、脱成長)はそもそも、この論考なしでは出現しなかったかもしれない」とさえ示唆されている[6]。
アナキズムを含むラディカルな政治的想像力と親和性が高いこうした立場をグレーバーが厄介に思うのは、原始の平等と以後の堕落という対比を前提とするなら、大規模に組織化された今日の社会における自由の追求が望み薄になってしまうからだ。こうした感受性に基づいて行動する人びとの熱意がいかなるものであれ、彼らの望みがそのまま現代の都市化した社会の新たな発展のビジョンとなることはできない。原始主義のラディカリズムは、逆説的に、近代社会の達成の先に解放を展望する努力を無効化する傾きを持つ。この種の想像力に発する社会変革の野心は、以下のような反論に出会わずにはいないからだ(第1章)。
あなたがピグミーやカラハリ砂漠のブッシュマンであれば、ほんとうに平等な社会に生きることができるのかもしれない。しかし今日において真の平等社会をつくりたいのなら、あなたはまずもって、ほぼ私有財産なしの小規模な狩猟採集集団に再び戻るにはどうすればよいのか、その方法を見つけ出さなければならないだろう。狩猟採集にはかなり広大な土地が求められるのだから、世界人口を99.9%ほど減少させる必要があるはずだ。
真の自由と平等を過去のモデルに求めることは、そうしたモデルを再現不能な現代における自由と平等の断念を帰結してしまう。DoEではこのことが、ルソー的な自然人とその無垢喪失の神話の運命として主題化されている。ルソーは人間の不平等に特定の起源――とりわけ定住農業の開始に伴う私有財産制の成立――を見定めた。それはつまり、この歴史的時点の以前と以後に人類の生活を分割し、前者には真の平等を、後者にはその決定的な不可能性を認定することだ。
ルソーがひとつの思考実験として提示したこうした図式的見立ては、21世紀においてなお、歴史的事実の装いのもとに流布されて、人びとの集合的想像力を支配している。例えば――DoEで言及されるなかでも際立った事例を引くなら――ジャレド・ダイアモンドは「農業こそは人類史上最悪の誤り」だと説き、ユヴァル・ノア・ハラリは農業革命を「小麦の視点から」語り直すと称して、1万年ほど前には気楽な狩猟採集生活をしていた人類が、取るに足らない野草にすぎなかったこの小麦に操られて、それが惑星中を覆い尽くしていくための道具として奉仕することで自由を喪失する次第を物語ってみせる、といった具合だ。
4-3 1968年の遺産に向き合う
しかしこうした図式は、政治的展望として陰鬱であるのみならず、そもそも事実に反していると著者たちは言う。トルコのギョベクリ・テペ遺跡から米国ルイジアナ州のポヴァティ・ポイントを経て青森市の三内丸山遺跡に至る世界各地の考古学的成果を渉猟しつつ、2人のデヴィッドは「農業革命」によってすべてが変わったわけではなく、階層化を含んだ都市形成の痕跡は、農耕定着以前のあちこちの遺跡にすでに認められることを読者に告げ知らせる(第6章)。
出発点にはエデン的な状態があり、そこから最初の農民たちが不平等への道への第一歩を踏み出していった、などという事実はないのだから、社会階級や不平等や私有財産の起源をなすものとして農業を語ることにはなおさら意味がない。
要するに、不平等に特定の起源を定めることはできない。過去のいかなる時代においても、人類が絶対の自由と平等を享受していたためしはなかった。この醒めた認識は、わたしたちの現在と未来を、冷静にかつ希望を持って見つめることの条件をなす。かつての人類が無垢ならざる境遇のなか、創意を発揮して自由と平等の維持・発展に努めていたのであれば、高度に組織化された現代社会の現実を踏まえたうえで、今日のわたしたちもまた、創造的努力によって未来を切り開く余地が十分にあるはずだからだ。
グレーバーは、本稿「2」で触れたようにサーリンズの促しにより書かれた初期作『アナーキスト人類学のための断章』においてすでに、師の仕事に活気づけられて生まれた原始主義の潮流を全面否定しないまでも意義を相対化しようと努め、「人間は一度たりともエデンの園に住んでいたことはないと認知して、われわれが失うものはほとんど何もない」と記していた。「エデンの園を決定的に捨て去ること」(第1章)を説くDoEは、2004年のこの小著をまっすぐに引き継ぎ、ほとんど「父殺し」と言うべき議論を展開して、共著者の一方の師の両義的な遺産を振り返っている。ここでは、この点を論じた第4章の一節の、内容紹介的な表題を引くにとどめよう――「本節でわれわれはマーシャル・サーリンズの「原初のゆたかな社会」を論じ、きわめて洞察力にあふれる人びとでさえ、根拠なしに先史学を語るならどんな事態を引き起こしうるのかを考察する」。
両義性を見定めるという同じ身振りは、本書ではサーリンズの論文が発表された当時の時代状況――フランスの〈1968年5月〉に象徴される――それ自体にも向けられていると言えるだろう。「原初のゆたかな社会」は、サルトルの雑誌として知られる『レ・タン・モデルヌ』の1968年10月号に、英語原文の公表に先立ち仏訳掲載された。60年代末のサーリンズは、レヴィ=ストロースにより創設された「社会人類学研究所」に招かれパリに滞在し、『国家に抗する社会』を準備中のピエール・クラストルをランチ仲間としていた。DoEでは、〈68年5月〉の蜂起的状況に対するレヴィ=ストロース(「尊大な中立性」)とサーリンズおよびクラストル(「熱狂的な参加者」)の態度が対比されているけれど(第4章)、興味深いのは、本書全体を通し、後2者の仕事が両義性において検討される一方、前者の仕事の理論的意義が、今日では忘れられがちな論点――後述の「季節性」――の再評価を含め、一貫して重視されていることだ。
とりわけクラストルへの明確な批判は、グレーバーの仕事がしばしばこの夭折したフランスの人類学者の後を継ぐものとみなされてきただけに注目に値する。例えば、『民主主義の非西洋起源について』のフランス語版(2014年)に紹介的な「まえがき」を寄せた社会学者アラン・カイエは、同書に代表されるグレーバーの著作の意義を、「アナキズム的な歴史のヴィジョン、歴史の政治哲学に捧げられた、ピエール・クラストルの著作以来最も重要な成果」と評している。独自の「共生主義」を構想しアナキズムとは一線を画す立場のカイエにとって、これは最大限の称賛であると同時に限界の指摘でもある。
グレーバー自身はと言えば、すでに2005年のカイエへの私信において(上記「まえがき」の注3に引用)、「クラストルが祝福する政治空間が、強姦で脅しつつ女性たちを制度的に排除することを基盤としているのは明らか」だと指摘し、ジェンダー問題への深い無関心を論難することで一定の距離を取っていた。しかしDoEではさらに進んで、いっそう根本的なクラストル批判が展開されている。以下、この点をめぐる第3章の議論を簡単に紹介しておこう。
4-4 ピエール・クラストルが見ようとしなかったもの
クラストルは、指導教官だったレヴィ=ストロースを含む先行世代の人類学的伝統が保持してきた「未開」社会観の重要な一要素を、決定的に忘れさせてしまった――批判の眼目はこのように要約することができる。DoEではこの要素こそが人類の全歴史を読み解く鍵のような何かとして重視されているだけに、クラストルによるその閑却はなおさら深刻なものだと言える。問題の要素とは「季節性」、すなわち同一集団が季節によりまったく別の社会構造に従うという、周期的な交替性である。
マルセル・モースは20世紀初頭に、夏には狩猟採集のため小規模集団に分かれて強力な指導者に従い、冬には大きな建物に集住して富の共有に基づく平等な集団生活を営むイヌイット社会の「二重の形態構造」を論じた。レヴィ=ストロースは1944年の論文で、雨季には高地に集住して栽培に従事し、乾季には小規模集団に散らばって狩猟を行うナンビクワラ社会の季節性に注目した。ここではすでに、狩猟採集民の小規模集団を自由な平等者の集まりとして想い描くルソー的神話の非現実性が示唆されているが、問題はこの点にとどまらない。
グレーバーとウェングロウにとってこの季節による社会構造の交替が重要なのは、何より、それがルソーの同時代にテュルゴーらによって確立された文明の発展段階論や、その伝統に連なる人類学的理論を無効化する現実を明かしてくれるからだ。ナンビクワラ族は、「進化人類学者なら(テュルゴーの伝統に従い)まったく別個の社会発展段階として考えることに固執するはずの2つの社会形態の間を、すなわち狩猟採集民から農民へ、またその反対へと、1年のうちに行き来する」。この点に注目し、両社会形態それぞれにおける首長の役割(狩猟に従事する小集団では決然と命令を下す強力な指導者、栽培を営む集落では穏和なまとめ役)を検討することで、レヴィ=ストロースはナンビクワラの首長を「小規模の萌芽的な福祉国家を運営する近代的政治指導者」のような存在として捉えることができた。「未開」に見える人びとが直面している課題は、「文明」のもとに生きるわれわれが抱える課題と決して異なったものではないと、フランスの人類学者は真剣に考えていた。
ところが、レヴィ=ストロース自身は第二次大戦後に世界的な名声を得たにもかかわらず、人類学という学問全体の動きは、彼のこうした発想とは反対の方向に展開していった。すでに言及したシカゴ大学の「狩猟人」シンポジウムに典型的な新しい動向は、「ブッシュマン」のような狩猟採集民の研究を通してルソー的神話を再生させることで、ナンビクワラの社会と近代的な産業社会の類似性に注目するレヴィ=ストロースのアプローチを場違いなものとしてしまう。
DoE第3章では、こうした人類学研究の動向を残念に思う観点から、クラストルの仕事が両義的に評価されている。クラストルは『国家に抗する社会』(1974年)に結実する研究を通し、「未開」とされる社会は無垢ないし無知ゆえに無国家状態にあるのではなく、恣意的権力への服従を強いる国家という抑圧的制度の到来を妨げるべく意識的に抵抗しているのだと主張した。ルソー的神話と縁を切るこのような主張を、グレーバーとウェングロウは高く評価する。
さて、クラストルのこの論争的な仮説に対しては、国家という制度を経験したことがないのに予め抵抗を示すとは、「未開」の人びとに過度の想像力を期待しているのではないかという反論が提出された。グレーバーとウェングロウによれば、こうした反論には季節性をもって応じるのが最善である――つまりナンビクワラ族のような人びとは、狩猟人として小集団を組む際に指導者の強力な指導を受け入れているのだから、現に恣意的権力がいかなるものであるかを経験済みなのだ、と答えればそれでよいはずだ。けれども、クラストルの著作中にこのような応答を見出すことはできない。
クラストルはこの季節性の観点を知らなかったわけではない。実際、彼が参照する人類学者ロバート・ローウィの先行研究は、南北アメリカの先住民社会の大部分が持つアナキスト的性格を論じつつも、そうした社会もまた、季節的周期に従い「警察」や「兵士」を備えた社会形態に移行するのであって、そこにはトップダウンの権威的秩序の「進化的萌芽」が認められるのだと指摘していた。ところがクラストルは、ローウィの研究に依拠しながらも、この季節性への言及を完全に素通りしてしまう。著者らはこの決定的な過失を、以下のように嘆いている。
この点を閑却することで、クラストルは実のところ、マルセル・モースからロバート・ローウィに至るまで保たれてきた、人類学の初期の伝統を終わらせてしまったのだ。「未開」の諸社会を内在的に柔軟なものとして、とりわけ多様な組織形態により特徴づけられるものとして扱う伝統が、ここで終わりを告げる。
2人のデヴィッドによれば、「未開」の人びとをルソー風の無垢において理解する進化人類学の立場であれ、国家に自覚的に抗する平等主義者として捉えるクラストルほかラディカル派の立場であれ、「そうした人びとが単一の、きわめて単純な社会生活様式へと固着されているのだと当然のように考える」という点では変わらない。それにしても、クラストルはなぜ、ローウィによる季節性への言及を無視して済ませたのか。
答えはおそらく単純で、季節性は混乱を招くからだろう。実際、季節性は一種のワイルドカードだ。
季節性を持ち出し、複数の社会形態の周期的交替という現実を認めるなら、人間の社会は何でもあり――とは言わないまでも、数多くの可能性に開かれたものとなってしまう。そうなると、国家の成立を食い止め自由を保持すべく小規模集団を守り続ける人びとというクラストル的ビジョンは、多少とも調子を狂わされずにはいないだろう。国家権力の抑圧的な力は相対化され、その恐るべき到来を全面的に阻止すべき何かというよりもむしろ、たしかに警戒の対象であるとは言え、暫定的・制限的なかたちで適度に関わりうる何かとみなされるようになるからだ。
この第3章では、人類は数年前の後期旧石器時代からずっと、自由の享受と権威への服従の間を行き来する多元的な社会的・政治的生活を営んできたのだと主張される。
「人類の幼年期」という発想に別れを告げよう。そして(レヴィ=ストロースが説いたように)われわれの原初の祖先は単に認知能力の点でわれわれと同等だったばかりでなく、知的な対等者でもあったのだと認めようではないか。〔…〕彼らは無知な未開人ではなかったし、自然の賢明なる息子や娘でもなかった。〔…〕彼らはわたしたちと同じく、単に人間だったのだ。同じ程度に明晰で、同じ程度に頭を混乱させた、わたしたちと同じ人びと。
こうして、「氷河時代を解凍する」という鮮烈な表題を与えられたこの第3章に典型的な議論を通し、DoEは数万年の時空に蝟集する全人類を一挙にわたしたちの真の同類にする。人類はみな、権威的秩序の受け入れとそこからの解放のいずれをも経験し、両者の間を行き交いながら生を営んできた。石器時代から続く両極性は、ヨーロッパ中世では封建制度下の日常生活とカーニヴァルにおけるその転覆といったかたちで経験されたのだし、今日においても、著者らが請け合うところによれば、「季節性はなおわたしたちのもとにある――たとえかつてに比べ弱々しく、縮こまった影のようなものとなっているにしても」。モースが言及する夏のヴァカンスがその一例だと著者らは言う。
4-5 ラディカルさと穏当さの再定義
こうした主張は、日々の現実に根ざした解放への呼びかけとして受け止めることもできる一方で、いささか拍子抜けする議論だと受け取る向きもあるかもしれない。実際、DoEをめぐっては、ラディカル志向の読者からの失望や不満の声が聞かれることは事実だ。例えばガブリエル・クーン――『アナキストサッカーマニュアル』と『海賊旗を掲げて』の日本語訳があるこのオーストリア出身の著述家は、グレーバーの仕事のドイツ語圏への導入者でもある――は、個人ブログに投稿した書評を「これはわたしの人生で最も失望させられた読書だったかもしれない」と書き起こし、「アナキズムがまったく出て来ないし、革命的変革に関するどんな理論も出て来ない」ことを嘆いている。人類はこれまで様々な社会形態の間を行き来してきたと言われても、「そんなものは世界を揺るがす大発見とは言い難い」のだし、何ら前向きな展望を与えてはくれない、というのだ。
かねてよりグレーバーの論敵として振る舞ってきた「ラディカル人類学」グループのクリス・ナイトは[7]、『タイムズ・ハイアー・エデュケーション』誌に寄せた書評の中で、DoE の「中核をなす政治的メッセージには切れ味がない」と断じている。本書が「位階的秩序と平等性は、相互補完的なものとして同時に出現する傾向がある」(第5章)などとこともなげに記し、国家権力からの全面的な解放の可能性を放棄しているのに納得がいかないようなのだ。「国家の存在の不可避性を受け入れるというのは、どんな人びとにもまして、ひとりのアナキストの意見としては逆説的なものに思えるかもしれない。ところが本書はこのようなメッセージに重みを与えている。」
ジョン・ザーザン――サーリンズとアドルノの影響を受けた米国の著名な原始主義的アナキスト――は、米国の文芸誌『ワールド・リテラチャー・トゥデイ』掲載の書評で、「このパンデミックの時代、人口密集それ自体が問題視されているというのに」、都市文明の罪を免責するこのような書物が刊行されたことに憮然とした様子を隠さない。都市化は必ずしも恣意的権力への服従を帰結しないと説くDoEは、近代国家の暴力を軽視するスティーブン・ピンカー『暴力の人類史』を思わせる書物だとザーザンは評する。
こうしたラディカル志向の人びとの反応は、一面的であるだけにかえって、DoEの企ての意義を照らし出してくれるものだとも言えるだろう。そしてこの共著を貫く問題意識は、すでに示唆したように、グレーバーの最初期からの問いかけを引き継ぐものであって、ラディカルな研究者が公共知識人としての名声を得て穏当な立場へと移行した結果、というわけではない。DoEにおいても依然として、ラディカルな探究は継続されている。ただしラディカルであることはグレーバーにとって、一般の人びとからの孤立を帰結するものではなく、むしろ表面的な対立や分断の基底にあるものを見定めることにより、人びとのつながりを結びなおすという努力と関わっている。このラディカルであることの再定義は、DoEと並び最後の著述のひとつとなったクロポトキン『相互扶助論』への序説(アンドレイ・グルバチッチとの共著)の中で、明確に打ち出されている。
『相互扶助論』のある重要な段落で、クロポトキンはひとつの提案をしている。ラディカルな学者の役割とは、「抗争と連合の間の現実的な均衡を回復させること」なのだという。これでは曖昧に思われるかもしれないが、彼はさらに詳述している。ラディカルな学者たちは、「過去からの残存物の中に偶然保たれた無数の事実とおぼろげな徴候を詳細に分析し、それらを現代の民族学の助けを借りて解釈するのを務めとする。そうして彼らは、何が人びとを分断してきたのかについて、多くの意見に耳を傾けた後に、人びとを結びつけてきた諸々の仕組みを再建していかなければならない。一つひとつ石を積み上げるように。」
このように定義されたラディカルさは、グレーバーが別のところで定義する穏当さと重なり合うもののようにも思われる。経済学者トーマス・セドラチェクとの2013年の対話を以下に引こう(『改革か革命か――人間・経済・システムをめぐる対話』三崎和志・新井田智幸訳、以文社、2020年、第7章)。
穏当さというのはどういうことでしょう? 穏当さというのは通約できない価値のあいだで折り合いをつける能力です。そう、それには共感、そして理解が含まれます。またそれには、理解できないことがあっても、どのみちそれを考慮に入れなくてはいけない、ということを受け入れることが含まれます。
ブレイディみかこは『他者の靴を履く――アナーキック・エンパシーのすすめ』(文藝春秋、2021年)の「あとがき」でこの一節を引用し(「共感」の原語が「empathy」であることに注意を促しながら)、「穏当さ(reasonableness)」とは「アナキストがもっとも言いそうになかった言葉」ではないかと印象を書き添えている。たしかに、先ほど取り上げたDoEをめぐる戸惑いや失望を見るなら、穏当さのこのような強調もまた、アナキストを含むラディカル志向の人びとの少なからずにとって、あまり好まれないだろうことは容易に察せられる。
けれども、この「穏当さ」の説明が、先ほど見たクロポトキンの参照と響き合っているのは明らかだろう。グレーバーがアナキズムの伝統からつかみ取った最も貴重なものは、ラディカルであることと穏当であることとを結びつけること、そうして、人びとを分かつものに目を向けつつもそこに乗り越えがたい断絶を認めるのではなく、相互のつながりを再建していくことへの意志だったように思われる[8]。
4-6 「分裂生成」の罠
グレーバーの全仕事を支えてきたこのような意志は、DoEではとりわけ、グレゴリー・ベイトソンの「分裂生成(schismogenesis)」の概念の活用のうちに強く表れている。まずは第2章におけるその説明を見てみよう。
1930年代に、人類学者グレゴリー・ベイトソンは「分裂生成(スキズモジェネシス)」なる言葉を造語した。この言葉は、互いを対照的な存在として定義し合う人びとの傾向を記述するためのものだ。議論を開始した2人の人物を想像してみよう。きっかけとなったのは、何かささいな政治的不一致にすぎない。ところが1時間経つと、彼らはそれぞれまったく妥協不能の立場に固執するようになっており、そのためお互いを、何らかのイデオロギー対立の正反対の側にいるものと考えるようになる。相手の見解がまったく受け入れられないことを示したいというただそれだけの理由から、ふつうの状況でなら決して選ばないだろう極端な立場に身を置くようにさえなるのだ。話し始めた時の2人は、わずかに趣が異なるだけの穏健な社会民主主義者だったというのに、加熱した数時間が終わる頃には、一方はレーニン主義者に、他方はミルトン・フリードマンの思想の擁護者になっている。周知のように、議論においてはこうしたことは珍しくない。
ベイトソンは1935年の論文「文化接触と分裂生成[9]」において、「対称的」と「相補的」の2種の分裂生成を論じている。前者は、AとBとが同種の行動を取りながら対立関係を強化する場合(自慢合戦や軍拡競争)。後者は、AとBとが相互に対比的な行動を取り、相補的な存在として対立関係を形成する場合であって、DoEで取り上げられているのはこの相補的分裂生成のほうだ。ここで注目すべきは、相補的分裂生成のプロセスにおいては、本来それほど全面的なものではなかった両者の差異が誇張されていくという事実である。
どんな人間にも「男性的」とみなされる特徴と「女性的」とみなされる特徴が多少とも備わっているにもかかわらず、ジェンダー規範を受け入れながら成長することで、男性はより「男性的」に、女性はより「女性的」に振る舞うようになっていくというのがその一例だ。この分裂生成のプロセスは、ほどほどのところを超えて進展するなら――例えば男性は全面的に「男性的」に、女性は全面的に「女性的」に振る舞うよう厳格に求められるなら――社会に耐え難い緊張をもたらさずにはいない。ベイトソンが調査したニューギニアのイアトムル族のもとでは、「ナヴェン」と呼ばれる男女の役割交替の儀式が頻繁に行われていたが、これは彼らの社会では両性を縛るジェンダー規範が極度に厳格であることから、爆発を予防するための緊張緩和措置と考えることができる。
対称的であれ相補的であれ、分裂生成を抑制しなければ社会は崩壊する。こうしたベイトソンの問題意識を、グレーバーとウェングロウも共有している。先ほどの引用の例では、取るに足らないきっかけで論争を始めなければ、2人の人物はおおむね意見の一致する仲間であり続けられたはずだ。対話は時として、このような不幸な分裂を引き起こしてしまう。DoEはこうした不幸な展開の一例として、18世紀におけるアメリカ先住民とヨーロッパ人のある対話とそれが後にたどった運命を取り上げている(第2章)。
ラオンタン男爵は、17世紀後半に北米に滞在して先住民と交流し、ヨーロッパに戻って刊行した『著者と旅行経験を持つ良識ある未開人との興味津々の対話[10]』(1703年)で大成功を収めた。そこでヒューロン(DoEでは今日より好まれる「ウェンドット」の呼称が採用されている)族の首長アダリオが展開するヨーロッパ社会の批判は、従来著者自身の思想の投影として語られがちだったけれども、DoEでは、そこには多少とも現実の先住民――とりわけ、実在のウェンドット族の首長カンディアロンク――との対話の記憶が反映しているに違いないと説かれている。ここでその論拠のすべてを検討することはできないが、少なくとも言えるのは、ラオンタン自身に限らず、外部からの忌憚ない声に率直に耳を傾ける人びと、同じような発想を共有する人びとが、当時のヨーロッパに少なからず存在したということだ。
けれども、DoEでは同時に、ラオンタンとアダリオの作中の対話が大西洋を挟んだ2つの社会を極度に対比的に描き出していることに注意が向けられ、この明快に過ぎる対照が以後の集合的想像力にもたらした負の効果が指摘される。「彼の主張の多くは明らかに誇張されている。ウェンドット族であれ他のアメリカ先住民社会であれ、いかなる法律もなく、どんな諍いも見られず、富の不平等など存在しない、というのはそれほど真実ではない。」こうした小説的誇張は、『対話』を著したラオンタンの演出意図によるのかもしれないが、グレーバーとウェングロウは、ひとは自己演出をすることがあるものだし、カンディアロンクは卓越した弁論家だったのだからなおさらだとして、ここでも現実の反映の可能性を強調している。
本稿の観点からは、いずれの解釈がより真実に近いのかはさほど関心の対象とはならない。重要なのは、2人のデヴィッドが、こうした誇張を通して構築されるヨーロッパ社会/アメリカ(先住民)社会の調停不能の対比関係を、(相補的)分裂生成の顕著な事例とみなしていることだ。実際には、北米先住民の諸社会にも法律があるのだし、私的所有がまったく存在しないわけでもない。にもかかわらず、議論のプロセスを通して、私的所有ゆえに自由と平等の制限を受け入れなければならない一方の社会と、私的所有の断念を条件として自由と平等を享受する他方の社会という二者択一が成立してしまう。こうなると、すでに指摘した原始主義の逆説に従い、歴史的発展のすべてを打ち捨てるのでなければ事実上、わたしたちは自由と平等については多くを諦めなければならないことになる。
17世紀北米のフロンティア社会では、「2つの矛盾するプロセス」が展開していたと著者たちは言う。一方では、「互いから学び、互いの思想や習慣や習慣や技術を採用し合う」という混成化のプロセス。しかし他方では、それと同時に、「互いの対照的な点を取り上げ、そうした点の誇張や理念化を行って、ついには可能な限り新たな隣人とは異なった振る舞いをすべく努める」という正反対のプロセスも見られた。前者のプロセスは、『民主主義の非西洋起源について』において「あいだ」の空間でなされる民主主義的実践の典型として描き出されたものにほかならない。しかしDoEにおいて、2人のデヴィッドは同じ空間で同時に展開されていた後者のプロセスに注目する。それにより彼らは、出会いと対話が分裂生成のプロセスを始動させるなら、社会は望まざる緊張を抱え込むことになりかねないという厄介な事実に読者を向き合わせるのだ。
ある種の条件のもとでなされる出会いと対話は、別の条件のもとでなら融和できたかもしれない人びとを――時には、先ほど引いた2人の社会民主主義者のように、おおむね意見を一致させていたはずの人びとをさえ――致命的な対立関係に陥らせてしまう。ウェングロウが示唆的にツイートしているように(2022年2月3日)、DoEがベイトソンから借り受けた分裂生成というアイディアは、現代民主主義を苛む過酷な緊張に光を当て、人類史全体の中での考察を促す際立って有用な概念だと言えるだろう。
4-6 永遠の夜明けを開く
哲学者クワメ・アンソニー・アッピアは、『ニューヨーク・レヴュー・オブ・ブックス』に寄せたDoEの書評を「ユートピアのための発掘調査」と題した。ここで「ユートピア」という言葉が用いられているのは一種の皮肉であって、アッピアは本書を、著者(の少なくともひとり)の「アナキズム的ビジョン」を過去に投影した書物として批判している。
グレーバーが生前に危惧し続けた通り、アナキストとしてのプロフィールから先入観を与えられて、彼が著作で説くところをありのままに理解できない読者は少なからず存在するようだ。残された共著者のウェングロウは――彼自身はアナキストを自認したことはない――、DoE刊行直前に受けた『ニューヨーク・タイムズ』の取材記事(2021年10月31日)においてすでに、新刊の内容と「グレーバーのアナキストとしての信念」の関係について問われて、「研究の成果にレッテルを貼ることから始まる議論には、あまり興味が持てません」と応えていたし、アッピアの上記書評をめぐっては、『ガーディアン』の記事(2022年6月22日)で以下のように語っている。「アンソニー・アッピアはこの本をユートピア的書物として読んでいる。理解しがたいことです。こんなに非ユートピア的な書物もないと思うのですけれど。」
この点からすると、すでに幾つかの例を上げたラディカル志向の読者からの批判のほうが、彼らの仕事の一面を正確に理解したうえでなされているという印象を受けなくもない。例えばクリス・ナイトは――以前別稿で取り上げたように(前掲「デヴィッド・グレーバーの人類学と進化論」)――、「原始コミュニズム」をユートピアとして退け、国家なき平等社会の展望を放棄しているとしてグレーバーを論難する時、『負債論』の著者による「基盤的コミュニズム」――資本主義社会を含めあらゆる社会を根底で支える一原理である一方、それのみに基づき形成される社会は存在しないものとされる――の提案が何を意味するのかを正しく理解していたと言える。
その意味で、ウェングロウがDoEの深い非ユートピア的性格を語るのは大いに納得がいく。しかしもちろん、そのことは、彼らの研究が単なる現状追認の書であることをまったく意味しない。むしろ反対に――すでに見たように――本書の要点はまさに、原始主義的傾向こそが、一見してのラディカルさとは裏腹な保守性を持つという逆説の指摘にあった。この点は極めて重要で、だからこそ最終章に当たる第12章では、第3章で展開されたクラストルの限界の指摘が改めて繰り返されている。
ピエール・クラストルやのちのクリストファー・ベームのように、人類にはつねにオルタナティブな社会の様々な可能性を想像することができるのだと主張する稀な人類学者でさえも、実に奇妙なことに、その同じ人類が、種の歴史のおよそ95%の期間ずっと、平等者たちからなる小規模社会という唯一の例外を除くあらゆる社会的世界の可能性を前にして、恐れをなして縮こまっていたのだと結論付けている。
クラストルは、「未開」とされる人びとのもとに先行世代の人類学者たちが観察してきた季節性の経験、明白に異なる社会的・政治的秩序の周期的交替の経験を閑却し、自由と平等を維持したいなら小規模集団のうちに閉じこもるしかないかのような発想を説き広めた。こうした発想は、小規模集団における強権の可能性を見ていない点でも問題があるが、より深刻なのは、大規模に組織化された社会を前提としての前向きな発展のビジョンを見失わせることで、逆説的に保守的機能を果たすということだ。
DoEは何より、こうした後ろ向きの発想を転換するために書かれている。最終章が書物全体と同じく「あらゆるものの夜明け」と名付けられ[11]、それが最後の結論部分で言及される古代ギリシアの時間概念「カイロス」と響きを交わしているのは、そのことと関わっている。時計によって刻まれる線的な時間「クロノス」と対比され、「神話と歴史、科学と魔法のあいだの境界線が曖昧になって――そうして、ほんとうの変化が可能になる」時としてのカイロス、この〈出来事〉の時間は、全面的な刷新の経験をイメージさせるだろう。
しかしグレーバーにとっては同時に、先ほど引いたクロポトキンの引用にあった緩慢に――「一つひとつ石を積み上げるように」――しか進まない粘り強い取り組みと交渉の時間も重視されている。既存の諸条件に繊細に配慮した修復と再建の時間、「分裂生成」を抑制し人びとの関係を結び直すためのコンセンサス形成の時間は、「あらゆるものの夜明け」の輝かしい時間とどのような関係にあるのか。奇しくも、グレーバーが序説を寄せた『相互扶助論』が「カイロス」叢書の一冊として刊行されている事実は、2つの時間のあいだの緊張を象徴しているかのようだ。
ここでは、この点を考えるための参考に、DoEでは言及がない〈夢時間(ドリームタイム)〉、アボリジニにとっての神話的創造の時間をめぐるグレーバーの議論を紹介しておきたい。本稿「3」で触れた2008年の重要論考「ポスト労働者主義の悲哀――《芸術と非物質的労働》」において、彼はラディカルな社会変革の可能性が潰えたように見える現在の閉塞を確認したうえで、それでもなお輝かしい明日を諦めることのできないわたしたちにとって、「〈未来〉は現在になだれ込み始めている」のだと指摘している。
いわば〈未来〉は現実の隠れた次元になったのだ。世界の世俗的表層の背後にある内在的現前であり、小さく不完全な閃きとしてであれ、いつでも不意に表に出てくるポテンシャルを有している。〔…〕〈未来〉は私たちの〈夢時間〉になったのだ。
〈夢時間〉は神話的過去における創造の時間でありながら、夢やトランス状態を通してアクセス可能であり、現実を生きる者の叡智の源泉として現在時と共存している。グレーバーはアボリジニにおけるこの2つの時間の共存に類似した感覚を、現代を生きるわたしたちは過去よりも未来との関係で生きているのではないかと示唆する。もちろん、SF好きの彼はこうして未来志向を強調しているけれども、だからといって過去はどうでもよいというわけではない。
すでに見たように、原始主義的想像力を断固として退けることで、DoEは過去数万年の全人類の経験を、わたしたちの日常に役立てることのできる貴重な糧として取り戻すことができた。こうして――2008年の論考の結論部から引くなら――「歴史を永久の可能性の領野として把握」し、過去の途方もない遺産に向き合いながら現在を生きることでこそ、わたしたちは不意に訪れるカイロスの時間を迎えることができるのかもしれない。あらゆるものの夜明けは、たぶん、いつでもわたしたちの傍らに潜んでいるのだ。
いずれにせよ、一度は『未来――5万年の序文』という仮題が示されたこともあったこの著作に促されてどのような未来を開いていくのかは、グレーバーを読むわたしたち一人ひとりに委ねられている。「Rest in Power」という最近の祈り――「安らかに眠れ(Rest in Peace)」に代わる新たな「RIP」として口にされる――がこれほどふさわしいひともいないだろうと思うけれど、彼の仕事が今後も力を保ち、わたしたちの社会を少しずつ変えていけるのだとしたら、そのようにしてでしかない。
[1] もう少し詳しくは、本稿(2)に既出の「「神秘的な、楽しい未来」に向けて」を参照。
[2] デヴィッド・グレーバー「ポスト労働者主義の悲哀――《芸術と非物質的労働》」(上尾真道訳、川上幸之助編『パンク!日常生活の革命』に所収)。ネグリ、ビフォら「非物質的労働」の画期性を説くラディカル派に幾分か冷ややかな眼差しを注ぎつつ、グレーバーはここでマルクス(また重要度はやや劣るけれどフーコー)の批判者としての本領を発揮して、「全面的システム」としての資本主義の仮説も「エピステーメー」の断絶の仮説も退け、そのうえでネグリらと自らの仕事の共通点を探っている。
[3] ジジェクの引用の典拠はそれぞれ、『パンデミック2』(岡崎龍監修・解説、中林敦子訳、Pヴァイン、2021年、第3章)、『パンデミック』(斎藤幸平監修・解説、中林敦子訳、Pヴァイン、2020年、補遺/ただし訳文は本稿の筆者による)。なお後者第9章には本稿の筆者による先行訳と解説もある(「人間の顔をした野蛮がわたしたちの宿命なのか」/「解説 生き延びのための「狂気」の行方」、『世界』2020年6月号)。ところで、書き添えておくなら、ドゥブロフスキーは、2020年6月末、ケンジントン公園のエドワード・ジェンナー像の脇のベンチに腰掛けアガンベンの著書を読むグレーバーの様子をツイートしている(これとこれ)。
[4] なお、以下の論旨の一部、とりわけグレーバーの反ルソー、反原始主義という論点は、本稿の筆者による前掲「未来を開く」、「「神秘的な、楽しい未来」に向けて」(『群像』2020年9月号、11月号)でも素描的に取り上げられている。
[5] 法政大学出版局刊の『石器時代の経済学』(山内昶訳、新装版2012年)には「始原のあふれる社会」として収録されているが、この表題(“The Original Affluent Society”)はJ・K・ガルブレイスの著名な現代資本主義社会論『ゆたかな社会』(The Affluent Society ; 鈴木哲太郎訳、岩波現代文庫、2006年、原著1958年)を踏まえているため、このように訳しておく。
[6] グレーバーは――空飛ぶ車がいまだ実現されていないことへの失望を繰り返し語ってきた元SF少年としては当然のことながら――「脱成長」の潮流に対しても、控えめに言っても両義的な姿勢を示していた。元来彼が親近感を覚えてきたのは、米国の社会理論家マレイ・ブクチンが1970年代初頭に打ち出した「ポスト希少性のアナキズム」、すなわち科学技術の飛躍的発展の先に自由な社会の可能性を探究するビジョンであって、近年の思想動向のなかでは、英国のジャーナリスト、アーロン・バスターニが提唱する「完全自動のラグジュアリー・コミュニズム」の展望がお気に入りだった。こうした点については、本稿の筆者による前掲「「神秘的な、楽しい未来」に向けて」および以下を参照。「暗黒×IDW×海賊…「啓蒙」の後で何を信じるのか? ランド・ピンカー・グレーバーの戦争」講談社現代新書ウェブ、2020年7月10日。
[7] ナイトらの「ラディカル人類学」グループは、現代の進化人類学の成果の独自の解釈を通してエンゲルス『家族・私有財産・国家の起源』の学問伝統の再生を企てる研究集団で、彼らの観点からするなら、原初の平等を神話として退けるグレーバーとウェングロウの研究がまったく受け入れがたいものであるのは無理もない。この点については以下を参照。片岡大右「デヴィッド・グレーバーの人類学と進化論」『現代思想』2021年10月号。
[8] 筆者はこの「4−5」および続く「4−6」の議論を、筆者の別の主要な研究対象である加藤周一のうちに認められる(しかしそれほど注目されてこなかった)コンセンサス志向と関連付けて、本稿校正中に日仏会館で開催された民主主義をめぐるシンポジウムの席上で取り上げた。「「分裂生成」をどうするか――デヴィッド・グレーバーと加藤周一から出発して」、「これからの民主主義を考える(日仏文化講座)」(2022年10月8日)。
[9] ベイトソン『精神の生態学』佐藤良明訳、改定第2版、新思索社、2000年。なお分裂生成については、ベイトソン『精神と自然――生きた世界の認識論』(佐藤良明訳、岩波文庫、2022年)にも言及がある(第IV章、第VI章)。またモリス・バーマン『デカルトからベイトソンへ――世界の再魔術化』(柴田元幸訳、文藝春秋、2019年)第七章における解説も参照のこと。
[10] 『ユートピア旅行記叢書』第4巻(岩波書店、1998年)に所収(川合清隆訳)。
[11] この言葉はこの第12章に、ミルチャ・エリアーデ(『神話と現実』)が諸神話における万物創造の時を表すべく用いる「かの時」の言い換えとして、本文中では一度だけ現れる。
片岡大右(かたおか・だいすけ)
批評家、社会思想史・フランス文学。東京大学、早稲田大学ほか非常勤講師。最近の雑誌寄稿に「アジアの複数性をめぐる問い――加藤周一、ホー・ツーニェン、ユク・ホイの仕事をめぐって」(『群像』2022年7月号)、「『鬼滅の刃』とエンパシーの帝国」(『群像』2021年11月号)、「デヴィッド・グレーバーの人類学と進化論」(『現代思想』2021年10月号)、「「惑星的ミサ」のあとで――『ゲーム・オブ・スローンズ』覚え書き」(『文學界』2020年2月号)、ウェブ上で読める最近の仕事に「多様性と階級をめぐる二重の困難――HBO版『ウォッチメン』とそのコンテクスト」(文化庁メディア芸術カレントコンテンツ)、「「魔神は瓶に戻せない」――デヴィッド・グレーバー、コロナ禍を語る」(以文社ウェブサイト)、「人生の時間とその後――展覧会「クリスチャン・ボルタンスキー Lifetime」に寄せて」(図書新聞/以文社ウェブサイト)、「「世の中の裂け目」はいつだって開く――小沢健二が帰ってきた」(図書新聞/以文社ウェブサイト)など。本noteにて「長い呪いのあとで小山田圭吾と出会いなおす」を全5回連載、そこから派生した小山田圭吾の炎上事件をめぐる記事を集英社オンラインに掲載した(前編・中編・後編)。
