
【痛みゼロの日】高齢者の関節痛を予防・改善する方法
はじめに:本日は痛みゼロの日
こんにちは、おばあちゃん子のパーソナルトレーナーいってつです。
本日1月30日は1(い)た3(み)0(ゼロ)の日で、主に高齢者の方々が抱える節々の痛みをゼロにすることを目指す日です。
江戸川区の鍼級マッサージ院の活動により制定され、2022年に始まったかなり新しい取り組みのようです。ってことは僕ら人の体に関わる業界にとっては毎日が1月30日…ってコト!?
最近は時間がある時は勉強や趣味🎮優先ですが、こりゃ記事にしてぇ!と思い取り急ぎカタカタしました。ということで、今回はパーソナルトレーナー視点で痛みゼロの日運動に貢献していこうと思います。
節々が痛む原因
節々の痛み(以後、「関節痛」)を抱える要因は様々で、主に
①筋肉量や骨密度の低下
②変形性関節症による骨端の磨耗(①と繋がる)
③関節性リウマチなどの膠原病(②の原因にもなる)
などが挙げられますが、パーソナルトレーナー的に力になれるのは①と②になるので、主にそこに焦点を当てて解説していきます。
骨の磨耗が原因
筋肉量・骨密度の低下や変形性関節症により関節痛が発生する理由は単純明快で、関節の骨と骨同士が近づきすぎて摩耗することにあります。
あゝ恐ろしきペニア兄弟
まず、筋肉量・骨密度の低下については、運動や必要な栄養素の不足により骨密度が低下するオステオペニアと、同じ要因で筋力量・筋力が低下するサルコペニアのペニア兄弟(仮称)の仕業です。
サルコペニアによって筋肉量や筋力が低下すると筋肉が持つ「骨を動かし、適正な位置に保つ」作用が低下します。それだけでも関節への負担は大きくなるのですが、生活習慣によってサルコペニアが起こっている場合、必然的に骨密度が低下するオステオペニアも牽連していることが多く、骨の強度が低下しているという、骨にとってはまさに泣きっ面にハチ状態です。
結果、関節(骨と骨の境目)における骨同士の適切な距離が保てなくなり、骨も脆くなってしまっているため、末端の軟骨同士が磨耗して痛みの原因となってしまうというわけです。☠️
原因色々、変形性関節症
変形性関節症は、関節の噛み合わせが変形することで骨の軟骨が摩耗し、痛みや浮腫が起こる症状です。
関節変形性には様々な原因があり、上記の筋肉量や骨密度が原因であることもあれば、リウマチなどの膠原病(炎症)やスポーツや事故の外傷によるものまで様々です。
その他間接的な要因
その他間接的な要素として、
・架橋
・姿勢の悪化
・過体重
などがあります。
架橋とは、筋膜(筋肉を覆う膜)のコラーゲンの繊維同士が癒着することで弾力がなくなる現象で、体が硬くなってしまう要因になります。運動不足や血行不良、加齢によるコラーゲン合成能力の低下が原因です。
姿勢が悪く、体重が重いと関節への負荷が増えるのはイメージしやすいですね。姿勢が悪ければ関節の骨同士の噛み合わせも悪くなりますし、体重が重いと主に下半身の関節に大きな負担になります。
レジスタンストレーニングのよる予防・改善
ここから関節痛の対策・改善方法を解説していきます。まずは運動編です。
骨と筋肉を強く保つためにはレジスタンストレーニング、つまり筋トレをおススメします。パーソナルトレーナーだから...というよりは骨と筋肉に対するアプローチがシンプルisベストだからです。
筋トレと骨
筋トレは筋肉を維持することはもちろんですが、同時に骨トレでもあります。骨の長軸(縦方向)への刺激は、骨の成長を促す骨芽細胞を活性化します。

例えばスクワット中は大腿骨や下腿骨(脛)に長軸方向の刺激が入りますし、バーベルを担いでいるなら脊柱も同様に刺激されます。
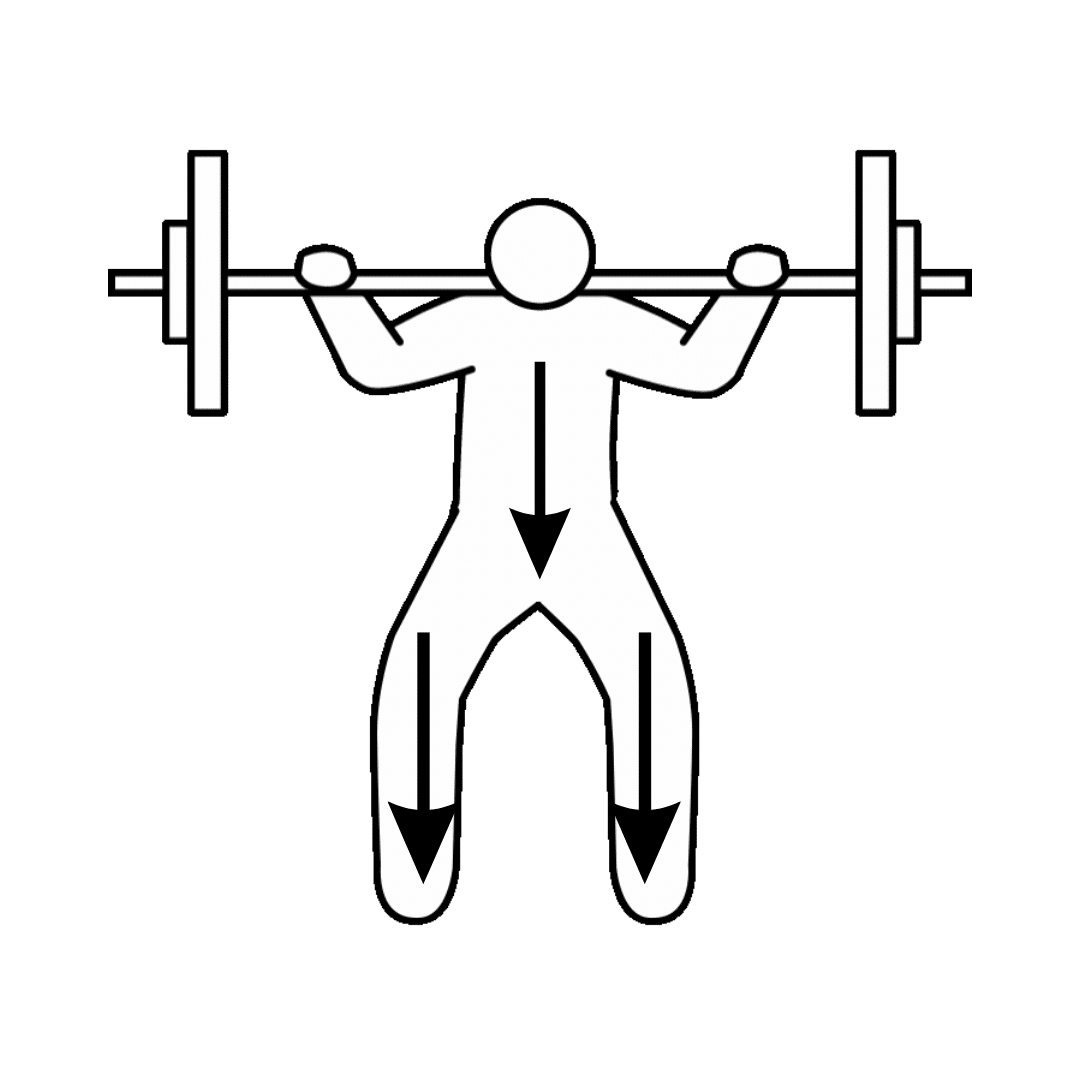
運動不足で骨が脆くなる理由は、骨の新陳代謝サイクルに置いて合成が分解に追いついていないことにあるので、その点筋トレは骨の強度を維持・改善するために有効な運動と言えます。

筋肉と骨
筋肉と骨にも密接な関係があります。
筋肉は骨に付着しており、身体を動かす役割以外にも骨の位置を正常に保つ働きがあります。

例えば、大腿四頭筋は、大腿骨や膝蓋骨(膝の皿)の正常な位置を保っています。なので、大腿四頭筋の筋力が著しく弱化すると大腿骨と腓骨の隙間が狭くなり摩耗しやすくなりますし、大腿四頭筋がガチガチに硬くなると膝蓋骨が上に引っ張られてしまい膝蓋骨炎などの原因になります。
筋トレは鍛えたい部位を選択的に刺激することができるので、下半身や肩関節などの硬くなりやすい部位を中心に筋トレを行うことで、骨を守ることに繋がります。
強度の調節とストレッチ・筋膜リリース
筋トレが骨・筋肉の維持や改善に有効なことが分かりましたが、高齢者の方にガチ勢がやっているような本格的な筋トレは難しいことがほとんどです。また、すでに身体が硬くなっている場合は本来有効である種目すら行えない可能性もあります。
筋トレは大きく分けて
・ダンベル、バーベルを用いるフリーウエイト
・マシントレーニング
・自重トレーニング
に分けられますが、個人で行う場合は関節への負担が少ないマシントレーニングから始めることを推奨します。最終的にフリーウエイトまで行えると身体全身単位でのボディバランスを養うことが出来ます。
また、種目に関わらず、硬くなっている部位のストレッチや筋膜リリースを行い代償行為(身体の拘縮した部位や動かない部位を庇う動き)を防ぎ正しいフォームで行うことが重要です。この点は専門家に相談し、重点的に行うべき種目と今やってはいけない種目もきちんと分別する必要があるといえるでしょう。
食事による予防・改善
次に食事よる予防・改善方法です。
簡潔に骨と筋肉に重要な5大栄養素を列挙していきます。
必要な栄養素
①タンパク質
身体を構成する全ての部位や体液、ホルモンなどの材料になる。
目安:体重のg数×1.5/日
②ビタミンB群
あらゆる代謝(体内での合成や分解)を円滑に行うために必要。
目安:B1やB6などで摂取量は異なり、尿と共に排出されてしまうので毎食で肉、魚、卵、大豆などから摂取する。
③ビタミンC
コラーゲンの合成(筋肉や骨の材料)に必要。
目安:基準は100mg/日だが、健康効果を高める場合は1食ごとに500㎎~1gを毎食(サプリメント推奨)。
④ビタミンD
骨のミネラル(カルシウムやリン)沈着や筋肉の合成を促す。
目安:800~4000IU/日
⑤ビタミンK
骨芽細胞の働きを活性させ、破骨細胞の働きを抑制する。
目安:300mg/日
⑥亜鉛
細胞の分裂や増殖に必要
目安:10~30mg/日
⑦鉄分
コラーゲンやビタミンDの体内合成に必要。
目安:10mg/日(ほうれん草やプルーンなどの植物性食品に含まれる鉄分はほとんど吸収されないので注意)
⑧カルシウム
骨の基質になる。筋肉の収縮に必要。
目安:700mg/日(必ずマグネシウムも摂る)
⑨マグネシウム
カルシウムが骨や筋肉に吸収される量を調節する。筋肉の拘縮を和らげる。
目安:350mg/日(カルシウムの1/2程度)
おすすめ食材
これでも最低限なので、必要な栄養素はかなり多いですよね。
そこで上記の栄養素を概ね網羅できる食材をピックアップしておきます。
※太字は特に豊富
魚:タンパク質、ビタミンB群、ビタミンD、カルシウム、マグネシウム
卵:ビタミンC以外
レバー:タンパク質、ビタミンB群、ビタミンC、亜鉛、鉄分
大豆:タンパク質、ビタミンB群、ビタミンK、鉄分、マグネシウム
キノコ:ビタミンB群(ナイアシン、ビオチン)、ビタミンD
イモ:ビタミンB群(B6)、ビタミンC、マグネシウム
海藻類:ビタミンK、マグネシウム
これらの食材を積極的に取りいれて元気な身体をつくっていきましょう。
量が難しい場合は、プロテインやマルチビタミン&ミネラルなどのサプリメントを活用しましょう。
栄養素を簡単に調べられるサイト↓
最後に:健康は自分で守るもの
今回は「痛みゼロの日」に因んで高齢者の方の関節痛を予防、改善する方法を解説しました。
こちらの記事でも述べていますが、日本は医療充実しているが故にどこか「健康を損なっても医者にかかればいい」という考え方が根付いているように感じています。しかし、既に医療や介護の現場はひっ迫していることを考えるとこれからはより自律的な健康管理が求められる時代になるでしょう。
実際、この記事では皆さんに投げかけることしかできませんし、パーソナルトレーナーとしても申し込みをしてくる方の健康しか救えません。今の年齢に関わらず健康に対するアクションを積極的に起こしていきましょう。
これからも皆さんの体と心の健康を後押ししていきます!👍
以上、元警察官パーソナルトレーナー
「いってつ」がお送りしました。
また気づけば3000字を超えてしまった件。
