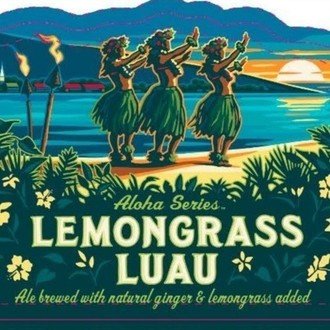日記のこと
更級日記、蜻蛉日記、土佐日記等々、日本の古典文学には文学にカテゴライズされる日記がいくつもある。
他にも公家が宮中での業務記録としきたり等の知識を合わせて記した日記も多く、紙に書いて残す文化がいかに長く続いてきたかよくわかる。
日記はその日の出来事に筆者の注釈や感想を付け加えたものなのだから、前提として個人の記録なわけだが、公家の日記には後世に伝えることを宮中での自分の仕事にするための道具として使われていたフシもある。猟官の道具とまでは言わないけれど、公にすることが前提のものだったと考える方が正しそうだ。
そうなれば当然、記録に残しては都合の悪いことは書かれないままに終わり、書いてあることも何らかのバイアスがかかっていると考える方が真っ当で、本当にあったことや筆者の本音を探すのは難しい。
これまでにも公にされないままの個人の記録としての日記はおそらく数え切れないほどあるはずだが、史料として扱われるものでも更級日記や土佐日記と並んで、誰もが知っているような有名なものはない。公にされていない個人の日常が記録されていたらきっと面白いはずなのだが。
ひるがえって現代社会では日記は晒すのが前提。300年ぐらいしたら「平安の頃以来の「見せる日記」文化が花開いた時代」と言われるようになるかもしれない。
情報過多でその日の出来事が同時進行で消費されていく世の中で、日記の存在理由が奈辺にあるのかは見当もつかないが、記録はないよりあった方が良い……と普通なら思うだろう。でもそれは間違いなんだそうだ。
読書記録に挙げた『世界の辺境とハードボイルド室町時代』に出てきた話だが、史料には適正な量というものがあって、江戸時代は史料過多すぎて読みこなせないんだそう。
その点、室町時代は適量と言える程度に残った史料が限られていて、研究するにはちょうどいいのだそうだ。
もちろん史料が多くて困るのは、崩し字を読めないからという理由だそうだが、WEB全盛の現代社会では読みにくさが減った分、数が増えすぎて、史料に溺れるなんてことになるんじゃないかと300年後の歴史家に同情してしまう。
僕は永井荷風の『断腸亭日乗』が好きで、暇があると今でも拾い読みをする。荷風の日記は簡潔でいい。
今日と同じ日付の大正6年10月14日の日記を見ると「十月十四日。空始めて快晴。小春の天気喜ふべし。八ツ手の芽ばへを日当りよき処に移植す。午後神楽阪貸席某亭に開かれたる南岳追悼発句会に赴く。帰途湖山唖※(二の字点、1-2-22)の二子と酒楼笹川に飲む。」とある。
前日の13日は「十月十三日。秋陰夢の如し。夜庭後君再び訪来り文明編輯の事を相談す。」。これだけである。
日記などこの程度で十分な気がする。
昨日の僕の出来事を断腸亭レベルの簡潔さで書いたらこんな感じになる。
「秋雨。夏以後初めて長袖を着る。大学病院にて定期検査。近隣を散歩。夜友人らと会う」。
文学の燃えかすの臭いすらしない。
いかに永井荷風の文が優れているかよくわかる。
いいなと思ったら応援しよう!