
終の棲家(ショートショート)
ここへ来るのは何年ぶりだろうか。
北陸のある港町。私はここで生まれ、育った。
だがこの町に住んでいた両親が他界した後は、ここを思い出すこともなかった。数年前にあのネットニュースの記事を見るまでは。
『 最後の住民がお引越し。人口ゼロの町に 』

ニュースによると、町に最後まで残っていたある高齢者が施設に移ることになり、そこに住む人がとうとうゼロになったという。古い建物はそのままにし移住者を募集するらしい。
「移住者募集か。しかし何もないあの町では… 残念ながら今後は廃れていく一方だろうな」
その時はそう思っただけだった。
あの記事を見てから4年がたった今。
妻を亡くした私は、ふとこの町が恋しくなった。
気ままな年金暮らしといえば聞こえはいいが。朝起きて、朝ご飯を食べ、テレビを見て、昼ご飯を食べ、散歩をし、夕ご飯を食べて寝る。毎日毎日、それだけが繰り返される。
そしてきっと、私はこのままここで、一人で死ぬ。
そう考えるとだんだんと私の人生の最期はここでいいのだろうか、と思うようになっていった。自分の人生の最期は、あの両親と過ごした、あたたかい記憶がたくさんある、あの町で。あの町を私の 終の棲家 に、そう思うようになっていった。
「たしか移住はまだ募集しているはずだ。両親の家も残っていることだし、一度聞きに行ってみよう」
だが、町に着いてすぐに私の考えが間違っていたと思い知らされた。
「なんだこれは… 若い人達がたくさんいるぞ。これはいったい…」
駅を降りた瞬間から、町は活気にあふれていた。
この町の新しいロゴマークなのか、所々にたくさんの青い鳥が描かれている。それが古い建物に意外にマッチしていて、洗練されたイメージすらある。
カップル、子供を連れた家族、ソフトクリームを片手に笑顔で歩く女の子たち。
「そこのお父さん! 獲れたてのホタルイカはどうだい?!」
魚屋の前を通ると声をかけられた。見ると大学生のような若者が元気よく声をあげている。
魚屋だけじゃない。見渡せばクレープを売っているお店もあれば、洋服のお店もある。それらのお店のどこを覗いてみても店員も若ければ、お客も若い。
これじゃまるで渋谷… いや、違う。たしかこの感じ、どこかで見たような… 思い出した。80年代の原宿だ。
どうしてこんなことに…
戸惑いながらも事前に調べておいた『移住政策案内所』へと向かった。
それはすぐに見つかった。ここは昔は駄菓子屋だった。懐かしい。『移住政策案内所』の看板が掲げられているものの、建物はそのままその姿は昔のまま変わっておらず、私は少し安心感を覚えた。
だが玄関をくぐるとその中の景色は私の想像とは違っていた。
たくさんの大型モニタ、インカムに向けて話す若い女性、Tシャツに短パンの男たち、部屋には軽快な音楽が鳴り響いている。最新のIT機器に囲まれたここはいったい…
私の姿を確認した男性が笑顔で近寄ってきた。
「こんにちは。 ご用件は? 」
「ええ、まあ。あの、私はこの町で生まれた者でして。移住のことをお聞きしたいのですが」
「あ、移住ですか? あー、そうですか。へぇーなるほどねぇ。あなたが? わかりました。私、ここの責任者をしていますチョーローと申します」
「チョーロー… さん?」
「ああ。長いに老人の老で『長老』です。僕のアカウント名」
そういうと彼はスマホを私に見せた。
「あなたが責任者? 失礼ですがまだお若いですよね」
「ええ、まあ。でもこの町では僕は最初の移住者の一人でして。それで『長老』なんですよ」
「最初の移住者… 」
まだ20代であろうこの青年が移住政策の責任者だなんて。態度も横柄だ。それに初対面の人にニックネームを教えるとは。あまりにも非常識すぎる。
この町にいったい何があったんだ。
「あの、この町に移住者はたくさんいらっしゃるんですか」
「はい。この町は豊かですから。漁業もあって、山には自然がたくさんあります。食べるものが美味しくて、見える景色はインスタ映えするものばかりだし、グランピングも最高。魅力的な町ですよ。あ、すいません。ここで生まれ育ったのなら、ご存じですよね」
「でも、それだけでは。みなさんお仕事はどうされているのですか?」
「僕の場合は、この移住政策案内所の仕事もいわゆるダブルワークってやつでして。本業はIT企業の社員をやってて半年に一回は東京に行ってます」
「そうなんですか」
「僕以外にもこの町の人達はそれぞれに仕事を持ってます。駅前に魚屋があるんですけど、彼は株取引で儲けてるんですが、魚が大好きみたいで。魚屋になるのが小さい頃からの夢だったんですって」
「ああ、あの魚屋の彼」
「あとはサーファーとか。ここは海がきれいでしょ? 毎日サーフィンをしてドローンで動画撮って、Youtubeに上げると世界中から反応があります」
「Youtubeですか・・・」
「はい。モデルやってる女の子もいますよ。自分の画像売ったりして、けっこうみんな自由に仕事してます」
時代は自分が思っている以上のスピードで進んでいる、ということなのだろうか。
私の世代には憧れだった東京が、今の若い世代には見向きもされていない。
パソコンで仕事をし、物はAmazonで買う。海で山でカラダを動かし、新鮮な魚介を食べ、仲間たちがやってるお店で呑み、インスタで自分たちの生活を世界に発信をする。
これが彼らの ”豊かな生活” らしい。
これで十分、いや、これが彼らの理想なのだろう。
「しかし。全国にも移住を促進している町はたくさんあるのに、なぜこの町だけはこんなに成功したんでしょう」
「それよく聞かれるんですけどね。この町の移住政策は他の町にはない魅力があったんですよ。何かわかります?」
「いいえ… 」
「では逆に。移住に失敗した例を聞いたことありますか? 都会から田舎へ引っ越したけど、結局うまくいかずに都会に戻ったとか、そういう話です」
「あ、はい。聞いたことはあります。のどかに暮らしたいと思って行ってみたら、現地の人に受け入れられずに人間関係で… あ… 」
「そういうことです。これまでの移住政策は、失敗すべくして失敗してきました。移住をしても移住先に自由なんてなかった。地元に人にペコペコ頭を下げてなんとか仲間に入れてもらい、嫌われないように、妬まれないように、早くなじめるように、都会にいる時よりも窮屈に生きていかなくちゃならなかった」
「 ・・・ 」
「だが、この町は違う。僕達はここでは他の誰にも気遣いをせずに暮らしていける。なにしろこの町には住んでいた人はゼロ。老人もゼロ。あなた達みたいな年寄りが、全員出て行ってくれたおかげでね」
「年寄り… 」
「この町では僕達は僕達の価値観で、僕達の距離感で人と接して暮らしていっている。お互い隣に住んでいる人の本名も知らない。だけどそれでいいんだよ。楽しい事だけ共有して。もちろん深い話もするけれど、本音よりも配慮を大切にする。そういうことって理解できます?」
「いや… はい… ええ…なんとか 」
私の時代とは違う。いや、私の考え方とは違う。
だが、私たちの方が若者の価値観を理解しなければならないのだろう。
「そうですか。 で?この町に住みたい? もし住みたいならまずアカウント名教えてよ。フォローするから」
「アカウント名?」
「はい。あれ? ひょっとしたらやってないの? ツイッター」
「やってません… 」
「あちゃー。残念。じゃあ、移住なんてやめておいた方がいい。アンタはきっとこの町にはなじめないだろうから」
どうやら私はこの町には歓迎されてないようだ。
この町は私の終の棲家ではなく
彼らの『ツイの棲家』なのだ。
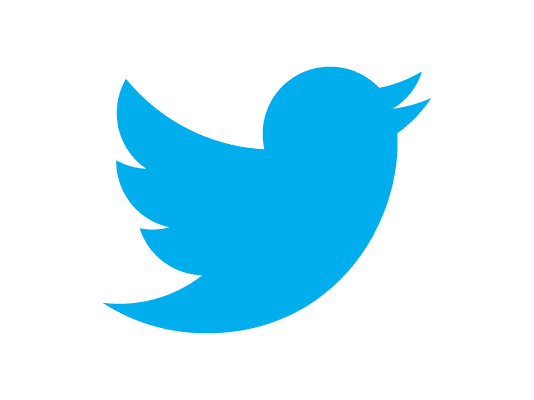
こちらの企画の参加作品です。
