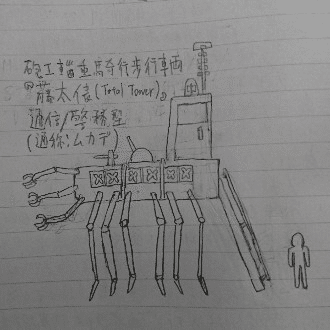随筆(2020/10/26):「共感と問題解決」というモデルは、「存在と真理」というモデルに、さらに単純化できる(2)
2.未知なる驚異の感情は、別に常に脅威であるとは限らない
感情の仕組みの話をすると、なんか注意すべきと感じたものがあったときに、「止まって」凝視する。聞き耳を立てる。ということが驚きの基本となります。
(『グラフィック心理学』か? 懐かしいけどだいぶ古い教科書じゃね?)(ウルセー俺の大学生の頃はこれだったんだよ)
それは、たいてい、未知のもの、分かんないもの、不確定要素、すなわちリスクです。
それらは、だからこそ、注意すべきものです。上記のものは、それなりに注意しないと、対処できないようなものでもあるのだから。
***
もちろん、解明すればリスクは下がりますが、それは驚きの感情と言う観点からは、副次的な話にすぎません。
そして、もちろん、不明なものがいったん解明されたら、驚く理由は減るので、驚きの感情そのものが弱くなります。
不明と解明は、対応してはいますが、基本的には別のものです。
もし、不明と解明を脳内でセットにしすぎて切り離せなくなると、トラブルの元になります。
***
何でトラブルの元となるかというと、その驚きが不快なものであるとも別に限らないのに、他人に不快と決めつけられて薄められるからです。
そりゃあ揉めるに決まってる。
***
今から言うことを、どうしても理解してもらえない場合が、しばしばあります。
なので、
「理解出来なくてもいい。実際にこうなんだ。
じゃあ、そう振る舞った方が、生きていきやすいんですよ。
納得は行かないでしょうが、実際にそうなりがちなんだから、これはもうしょうがない」
という水準で受け止めて下さい。
***
さっきも言ったように、驚きというものが、不快なものであるとも別に限らない。
単に驚いただけ。ということもある。
むしろ、驚きは、不快感が含まれていないものは、しばしば感情を揺さぶる感動をもたらしてくれる。
具体的に言うと、シャキッとしたモードになる。あれはあれでいいものです。
***
というか、未知のものにいちいち不快感を抱いていたら、多分その人、ストレスだけで簡単に衰弱死するからな。
未知のものでも安全であることはよくある。特に、治安のよくなった社会では。
驚きと不快感を切り離せるようになることで、人はそういった安全な環境に適応できる。
そうなれないのなら、こんなもん、注意力や忍耐力の浪費だ。損に決まってる。
驚く度にいちいち不快にならない。そういう人間の脳の仕組みは、適応上ももっともなところがある。そういう話です。
***
そんな訳で、未知なる驚異の感情は、別に常に脅威であるとは限らないということが分かってくる。
場合によっては、シャキッとしたモードになることもあり、それはそれでいいものだったりする。
***
で? それを? シャキッとしたモードを? 他人が薄める? しかも、良かれと思って?
揉めるってば。そんなの。
そういうことです。
(続く)
いいなと思ったら応援しよう!