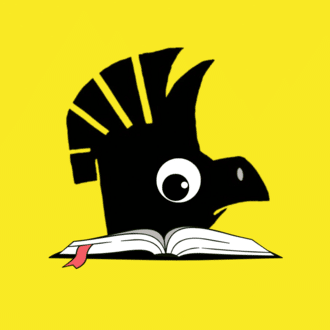【読書】 わたしという概念を広げる 『はみだしの人類学』
昨年読み、ひさびさに興奮した作品がカポーティの『冷血』。
ニュージャーナリズムの代表作で、カンザス州の片田舎で起きた一家4人惨殺事件を綿密に再現しています。
ニュージャーナリズムとは、「あえて客観性を捨てることによって、取材対象に積極的に関わり、より濃密に、より深く対象を描こうとする手法」です。
そしてこの手法は、文化人類学の調査方法と同じなのではないかと思い、文化人類学に興味を持ちました。
そもそも文化人類学とは、どんな学問なのか。
そんな文化人類学の「きほん」を、わかりやすく解説してくれるのが本書となります。
99ページと短く、文化人類学のことを学ぶとっかかりとして最適な入門書で、巻末のブックガイドも充実しているので、この本を起点に、さらに深掘りすることも可能。
そして、「わたし」とその「つながり」に関して学べるので、普段の生活を生きやすくするために、「違い」を乗りこえたいという人にもオススメです。
「学びのきほん」シリーズを読むのは『ブッダが教える愉快な生き方』から2冊目です。(この本もブッダについてわかりやすく解説してあり、興味のある方にはおすすめです)
内容もわかりやすく、大き目のフォントや、読みやすいレイアウトも工夫されています。
著者が提示する文化人類学のキーワードは、タイトルにもついている「はみだし」。
「はみだし」とは、「境界線を越えて交わりが生まれることに注目する視点」と定義されています。
ここでいう「境界線」は、他者に気づき、自己に気づくという過程をへて形成された「自己と他者の境界線」のこと。
境界線の維持は、自己と他者、あの世とこの世、敵と味方といった区分し、人間が存在することにおいて必要なものでもあります。
文化人類学では、人びとの生活のなかに入り込み、長い時間を一緒に過ごすフィールドワークを通じて、「わたし」と「他者」の境界線が薄くなり、「他者」の存在へと「はみだし」ていくような経験をします。
その「はみだし」を通じて、自分を変え、他者の視点を獲得し、真に他者を理解することにつなげるのが文化人類学。
著者は1975年に熊本県生まれ、京都大学大学院の人間・環境学研究科博士課程を修了しています。
現在は岡山大学文学部准教授をつとめ、専門は文化人類学で、本書の他にも、『基本の30冊 文化人類学』や『うしろめたさの人類学』を書いています。
そして、著者自身がいままで研究した結果や経験をもとに、読みやすい文章に仕上がったのが本書。
文化人類学では「他者」よりも、はみだす「わたし」が大事なのだと教えてくれました。
そもそも境界線は、「わたし」という存在を守るためにひいたものなので、よほどの意識をしないと、境界線からはみだすことはとても難しいこと。
相手との違いを認識することは、無意識でできる簡単なことですが、多様な人々と生きていくうえで、文化人類学で重要な「自分の境界線をはみだす力」は、自分の凝り固まった頭を柔軟にし、転職や、海外移住といった、住む環境を変えようと考えている人にも、役立つものだと思いました。
いいなと思ったら応援しよう!