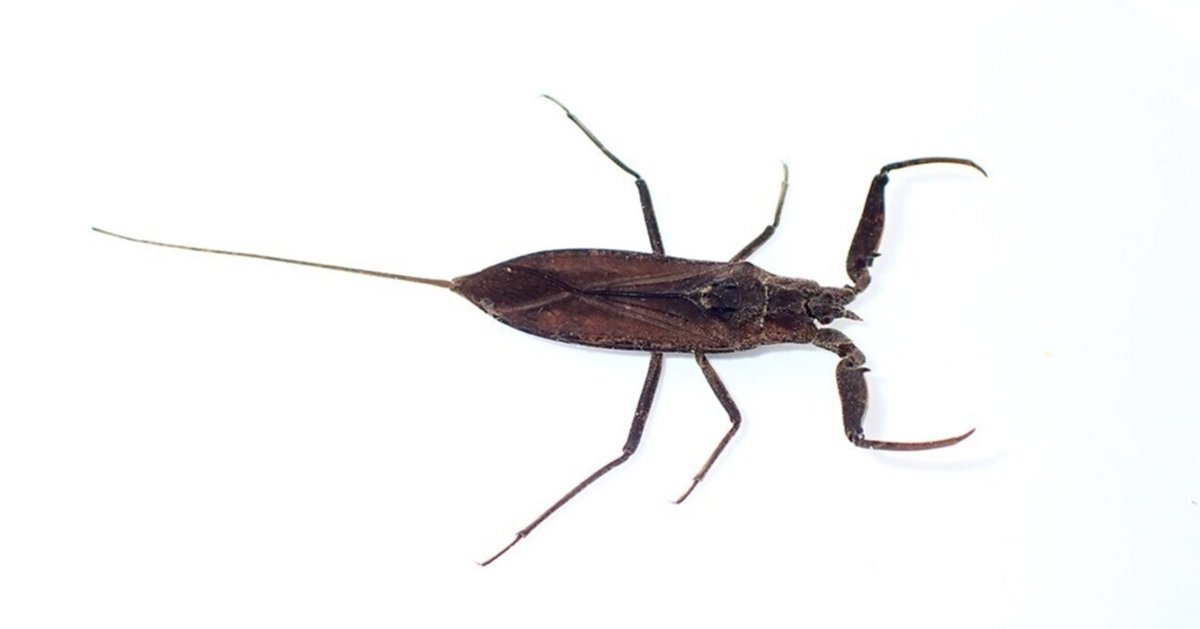
タイコウチのすむ池
下の前回の記事の続きです。
山梨県の水生昆虫採集。
最後にもう一つ、別の池に行きました。
そこには、ナミゲンゴロウやミズカマキリ、タマガムシ、セマルガムシ、マツモムシ、いろいろなヤゴがすんでいました。

そして、埼玉県ではとても珍しいタイコウチも暮らしていました。
タイコウチ $${Laccotrephes japonensis}$$
カメムシ目 タイコウチ科

タイコウチは脚を使って、上手に泥や砂を背中に乗せていました。
呼吸管を水面に伸ばしています。

幼虫には翅がありません。

英語でタイコウチ科のことを「water scorpion(水サソリ)」と言うそうです。
強そう。

立派な鎌で生きた魚を捕まえます。
とてもカッコいい水生昆虫なので、埼玉県でも数が増えるといいなと思いました。
おまけ
江戸時代の虫類の図鑑「栗氏千虫譜」にタイコウチの説明がのっているのを見つけました。


千虫譜ウィキの現代語訳をはります。
(右頁上段)
水蠆 ミガラ ヤガラムシの一種である
ユリノハナスイ
池塘*1水中にいて、魚の子を食べる。
夏日の晴天の時、石の上に羽をさらして、
髙く飛ぶ。夜になれば、また水中に飛んで入る
吻の上の両手はカマキリのようで、その体は
薄平たく、肉がない。その為、
身殻空ミガラという。
(右頁下段)
ミガラ 太鼓打ともいう
丙子年四月二十日に写す
湿地の水たまりの中にいて、魚の子を食べるところや、石の上で翅を乾かしてから飛ぶところとか、よく調べているなーと思いました。
僕も昔の人に負けないように、観察したいと思います。
下は、国立国会図書館デジタルコレクションの栗氏千虫譜のページと、千虫譜ウィキのページです。
下は、うちで飼っているタイコウチの記事です。
