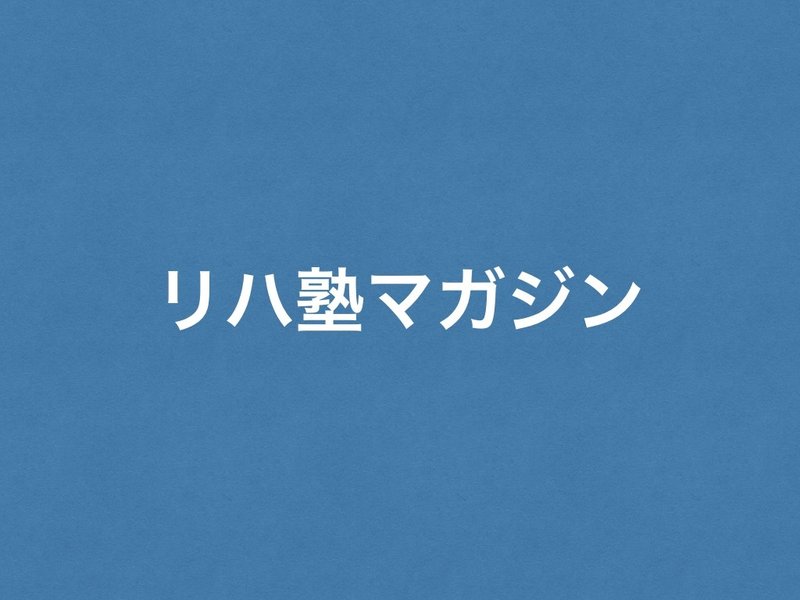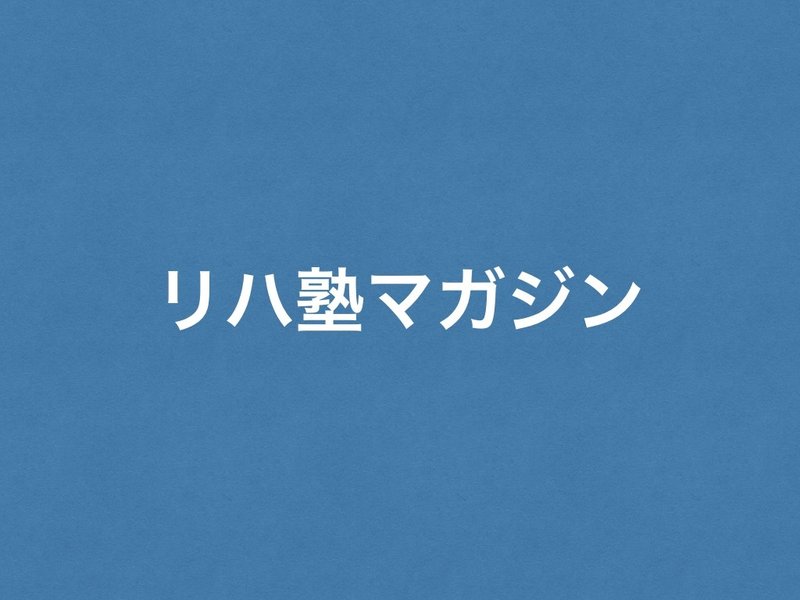神経に影響を与える3つの要因
リハ塾の松井です!
坐骨神経領域の痺れや痛み、足底や手指の痺れなど、末梢神経の影響が疑われるこれらの症状は臨床的にも非常に多い訴えだと思います。
何か背景に原因となる要因がはっきりしていれば解決もできるかもしれませんが、原因がはっきりしていない症状はアプローチも難しく、中々改善してこないですよね。
そんなはっきりしない症状の原因の1つに末梢神経の滑走の問題があります。
筋骨格系で考えるのは簡単ですが、神経も脊髄から分岐して、四肢を走行しているわけなので、神経による影響