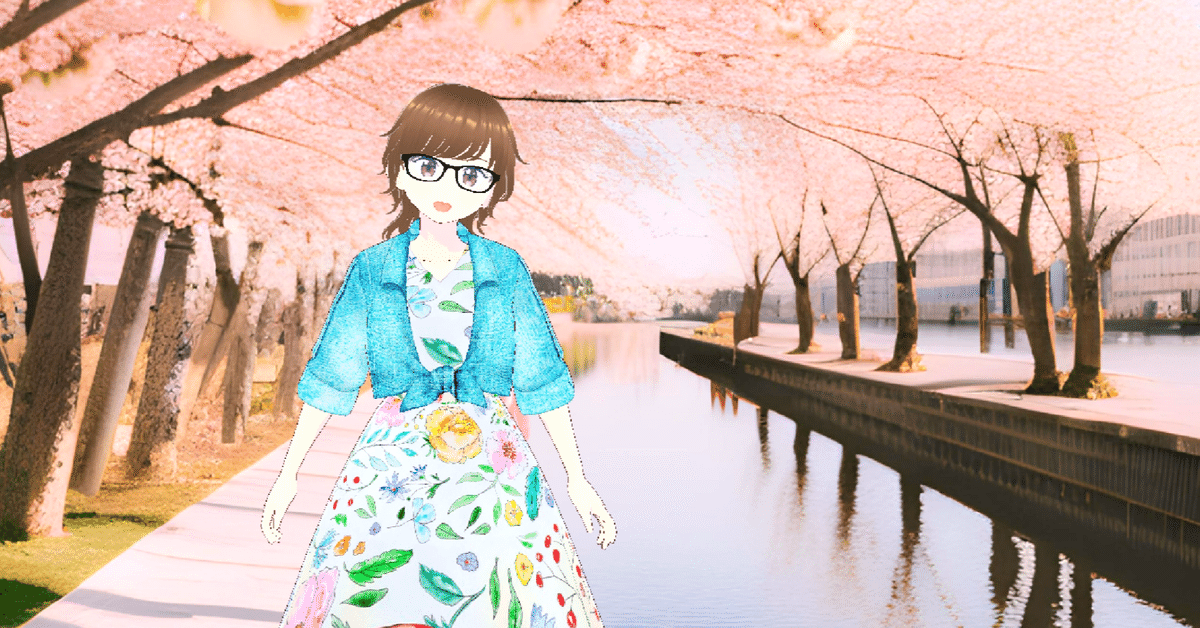
鈴木健「個人(individual)という幻想」人は自分の意志で行動したつもりでも・・・。だから成田さんの言葉に共感したのかも。
「何が良いことで何が悪いことなのか、わからないような状態に耐えることこそが生きることなのではないか」
本を読んだり、動画を見たりして複雑で変化の速い世界を俯瞰する努力?をし、「気づき」から生まれる表現をとりあえず書いてみるということをやっていると、いつも思うのは、そのことに関しての別の見方があり、考え方があるということ。
しかも、自分自身が今書いたばかりの事柄にすぐ疑問を感じてしまうことも多々ある。
人間が「世界」を理解しているつもりでいても、全くそんなこともなく、最近の研究だと、自分の行動に対しての理由付けは、その行動の後に行われているものであるとのこと。
何か一つの社会問題を「良い」と「悪い」の二元論で考えても全く意味がない。
そもそも日々の生活の中で、人が知り得る情報や認知できる範囲などほんのわずか。
いや、ここまで複雑な社会を、何か解っていると思うことのほうが幻想だと学ぶほどに思う。
6. 2. 4 個人(individual)という幻想
近代民主主義は,一貫した思想と人格をもった個人(individual)が独立して存在している状態を,事実論としても規範論としても理想として想定している.
個人に矛盾を認めず,過度に人格の一貫性を求める社会制度は,人間が認知的な生命体としてもつ多様性を失わせ,矛盾をますます増幅させてしまう.
そして,一貫性の強要は,合理化,言い訳を増大させ,投票結果を歪めることになる.
鈴木健
「通常の社会が,「良い制度」と「悪い制度」を峻別し,一方を採用して他方を排除するのに対して,分人民主主義の社会では,何が良いか悪いかは政策の種類やそのときどきの社会情勢との相性によって決まるのであって,絶対的に正しい制度があるわけではないことを示唆している.民主主義は,人々の意見の一致を完全に求めることや,正しい政策を絶対的な方法で決定することはできないという,ある種の諦念のうえに成り立っている.分人民主主義は,これが政策レベルだけではなく,制度レベルにおいても同様であることを主張している.したがって,このシステムは政府によるシステムではなく,政府をつくるためのシステムである.」
鈴木健
人それぞれ関心のある社会問題は異なり、日々変化する。
今の選挙の方法では、人々の考えを反映することは出来ない。
分人民主主義という考え方は、とても理解できる。
「何が良いことで何が悪いことなのか、わからないような状態に耐えることこそが生きることなのではないか」
という成田悠輔さんの言葉は、日々矛盾を感じている私に響いた。
分人民主主義というシステムを技術の進化で取り入れられたら、少しは生きやすい社会になるのだろうか。
