
「一隅を照らす」は、座右の銘のキングオブキングである
昔、東京のJRの駅中にある散髪屋をよく利用しておりました。
住んでいる所から近く、1000円強で安く、10分で終わる、というところが自分の散髪ニーズに合っておりました。
子どもの頃に、近所の叔父さんからバリカンで坊主頭にされ、学校でついたあだ名が「ハゲ」でした。
椎葉小学校の6年間と椎葉中学校の3年間、私は「ハゲ」というあだ名で同級生から呼ばれました。
理不尽なのは、中学校は、男子生徒は全員坊主頭だったのに、ハゲのあだ名はそのまま継続されたのです。
椎葉村を離れて宮崎市の高校に行って初めて、私は「ハゲ」の呪縛から解放されました。
宮崎市は私にとっては、ハゲからの脱却、解放の街で、自由と希望そのものでした。
かような幼少期の「トラウマ」があり、今でも散髪が嫌いで、なかなか髪をきらずに、髪の毛がぼうぼうなのはそのせいです。
防衛省の衛生監のときに、自衛隊大規模接種センターの件で国会質問が相次いで、委員会で何度も答弁に立ちました。
そのときの答弁風景を、YouTubeで見たことがあります。
「衛生監は髪を切れ」、「いや、髪を切れないほど忙しいのか」というコメントがありました。
すいません。
髪を切られるのが嫌いなだけでした。

さて最短の時間でカットしてくれる散髪屋で待っていたときに、散髪屋さんとお客の会話が聞こえてきました。
「お久しぶりですね」
「健康診断で肺に陰が見つかって、PETを撮ってもらったら、肺がんでしかもリンパ節転移もあり、ステージⅣだと言われたよ。幸いにも抗がん剤が合ってよく効いたので、退院となった。髪もあまり抜けなかったので、散髪に来たよ」
「以前、うちの親父が見つかったときは、もう肺がんの末期で、抗がん剤を何クールも使ったけど、髪は抜けて、口の中に潰瘍ができて食事がとれなくなってからは早かったね」
「しかし、今はひとりひとりの状態にあった抗がん剤を出すらしいね。進歩してんだね」

二人が、明るく気軽にこうした会話を交わしているのが信じられませんでした。
約30年前、病院に勤務していたときには、私が主治医をしていた一歳下の患者M君に、がんの告知をすることはできませんでした。
年が近くて、しかも名前は同じでした。
こっちは新米の研修医です。
治療法がなく、病室に行くのが本当に苦痛でした。
関西から父と母が出てきて、付き添っておられました。
ご両親には、もう助からないと説明をしていましたが、本人にはいえませんでした。
骨に転移するがんで、どんどん悪くなっていき、いくら隠しても状況は悪化していることは明らかでした。
私が病院にいた時期は病気の進行が遅く、亡くなったのは私の後任の主治医のときです。
日曜日の午後に、主治医からの留守電が入っており、千葉から神奈川県川崎市にある病院まで駆けつけましたが、ご臨終には間に合いませんでした。
私が病院についたときには、すでに病理解剖が行われていました。

環境省にいたときに、水俣病被害者の救済策を担当しました。
熊本の原因企業のチッソとの交渉は何度もありましたが、新潟の原因企業の昭和電工とはやっておりませんでした。
時間がないので、昭和電工の社長を環境省に呼んで、副大臣から直接社長に説明をしていただくことになりました。
社長と二人で副大臣室の前の部屋で、副大臣が来られるのを待っておりました。
ふとM君の顔が頭に浮かび、「病院で医者をやっていたときに担当した患者のM君は、社長の会社の社員でした」と話をしました。
会社の寮にご両親が泊まっており、毎日病院に通っていました。
M君は、会社に誇りを持っていて、私に「城山三郎さんの小説にも出てくる会社」だと教えてくれたことがあります。
会社は、M君とご家族を最後まで面倒をみてくれました。
「すいません。本の名前は忘れてしまいましたが……」
「男たちの好日」と社長は言いました。
「そうですか。あなたは、うちの社員の主治医だったのですか……」
その後、副大臣室で救済策の説明を受けました。
社長が帰るときに、エレベーターの中で、随行してきた社員に言っておりました。
「環境省の副大臣は、私の血液型も座右の銘も知っておられた。しかし私は、副大臣のことは何も知らなかった。これでは勝負にならない。救済策のことは環境省と詰めてくれ!」
トップダウンで即決されたのです。
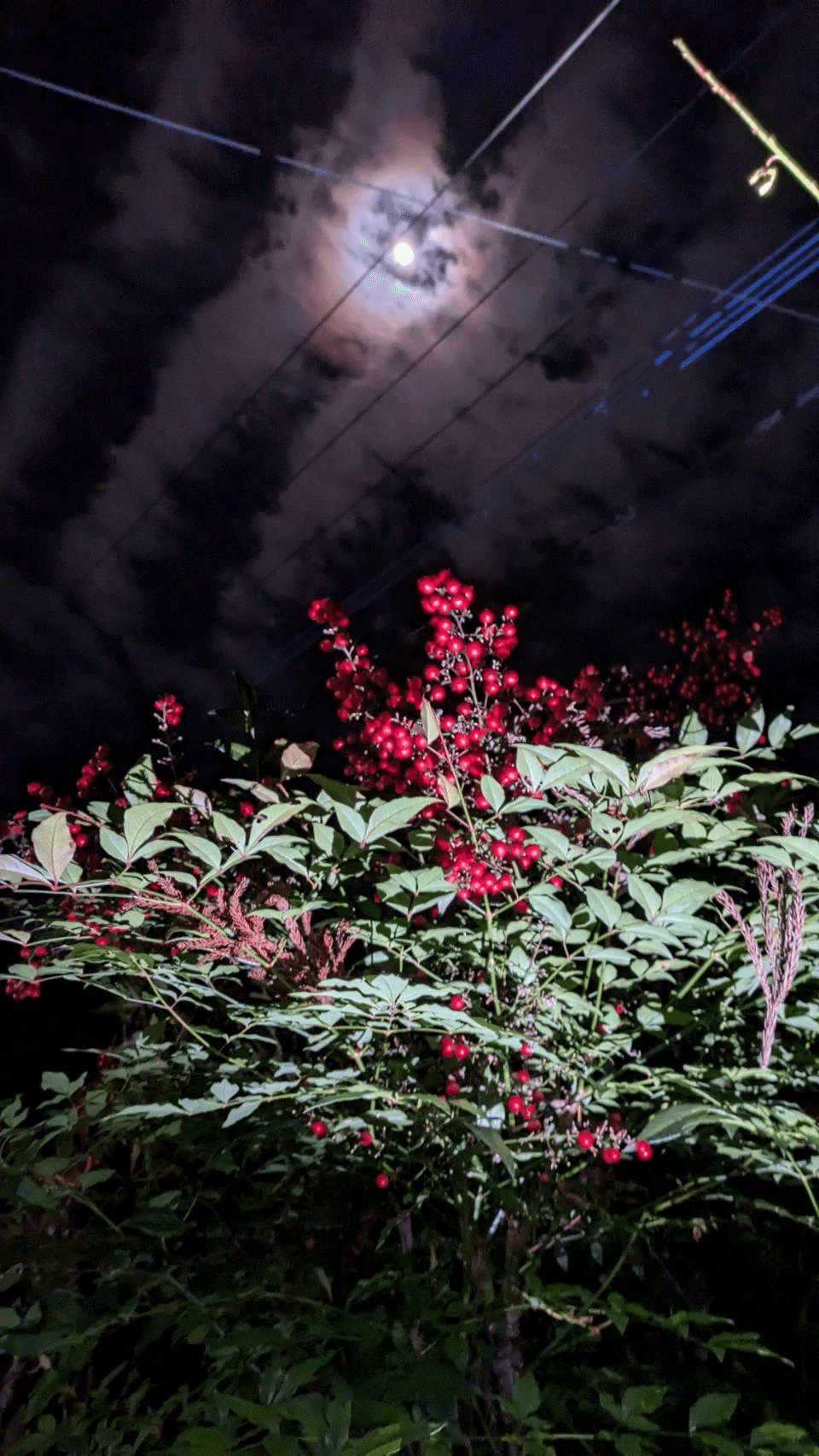
前日の副大臣へのレクチャーのときに、ネットで調べた社長の情報を伝えておりました。
副大臣は、社長の血液型や、「入社式で新入社員に一人ひとりに自分の座右の銘を書いた色紙を渡しているそうですね」と切り出して、親しみを込めて説明をされました。
社長の座右の銘は、「一隅(いちぐう)を照らす」でした。
ひとりひとりが自分のいる場所で、自らが光となり周りを照らしていくことこそ、私たちの本来の役目であり、それが積み重なることで世の中がつくられる、という意味で、天台宗の開祖の「最澄」の言葉。
富山県にいたときの知事の座右の銘と同じでした。
富山大学の医学生が卒業すると富山県に残らずに首都圏に流出するので、富山に残るよう知事の手紙を医学生に送ることを企画したことがありました。
知事に相談したところ賛同され、知事が手紙の中に自分の座右の銘を書かれたのです。
今にして思えば、「一隅を照らす」という言葉を座右の銘にしている社長さんだったのが幸運だったと思っています。
ハベレオ通信をご覧になっている皆様も、どうか一隅を照らす存在になってください。
ハゲになれという意味ではありませんので、念のため申し添えます。
