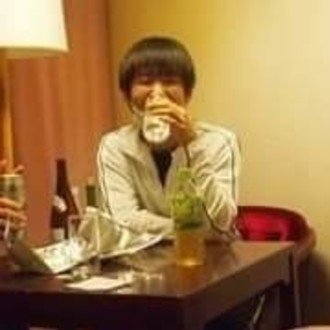「習得」と「効率化」のジレンマ
仕事も家事もそうですが、物事を手早く済ませることはとても大切です。
いつまでもダラダラ残業していてはプライベートの時間も増やせませんし、単調な仕事に手間取っていてはより高度な仕事に時間をかけることもできません。
そこで必要になるのは仕事の効率化です。特に単調なルーチンワークなどは効率化しやすいので、工夫すれば劇的に作業時間を減らすことができるでしょう。
具体的なノウハウは本屋に行けば「残業知らずの仕事術!」「無駄を捨てるライフハック!」といった書籍がズラッと並んでいるので、そちらを参考にしていただければ充分です。
効率化による弊害
しかし効率化のためのノウハウも、使い方を誤ると自分にとって大きなマイナスになってしまうので注意が必要なんですね。
例えば以下のような場合です。
Aさんは事務職員です。一か月単位のルーティンワークですが、多種多様な仕事を与えられています。
すべてを納期に間に合わせるため、各仕事に対応したマニュアルを手元に置いてそれを見ながら延々と作業を進めていきます。
本人は何をやっているか分かりませんが、マニュアル通りにやればギリギリ仕事を終わらせることができます。
しかし覚えが悪いのか、いつまでもマニュアルが手離せず、業務スピードも上がりません。
これ、何が問題か分かるでしょうか?
マニュアルを参考にすること
マニュアルを利用するのは仕事だけに限りません。新しく買った電化製品の使い方、初めて作る料理のレシピなどでもそうです。
合気道でも教本やDVD、youtubeなどを見て技を学ぶこともあるでしょう。
なぜこういったものを見るかと言えば、自分で一から模索するより正確かつ効率的で、作業時間を短縮できると思っているからです。
確かに、作業を早く終わらせることは可能です。上記のAさんもマニュアルを見ずにいちいち模索していたら確実に納期に間に合わないでしょう。
しかし、Aさんはマニュアルという効率的なツールを利用しているのに、自由な時間が増えているようには見えません。
むしろ、時間を節約するためのノウハウによって自身の成長を妨げられてしまい、いつまで経っても自由になれないというジレンマに陥っているようです。
これはAさんだけに限らず、いつも忙しい忙しいと言っている人に多い事柄です。
効率化可能なツールを多く利用しているのになぜか忙しい。その状況を打破するためには、敢えて非効率な方法を取らなければいけない、というのが今回のお話です。
もう少し詳しく見ていきましょう。
大学合気道部のコーチをやっております。頂いたサポートはコーチの活動経費(交通費)や大学合気道部の寄付に充てています。