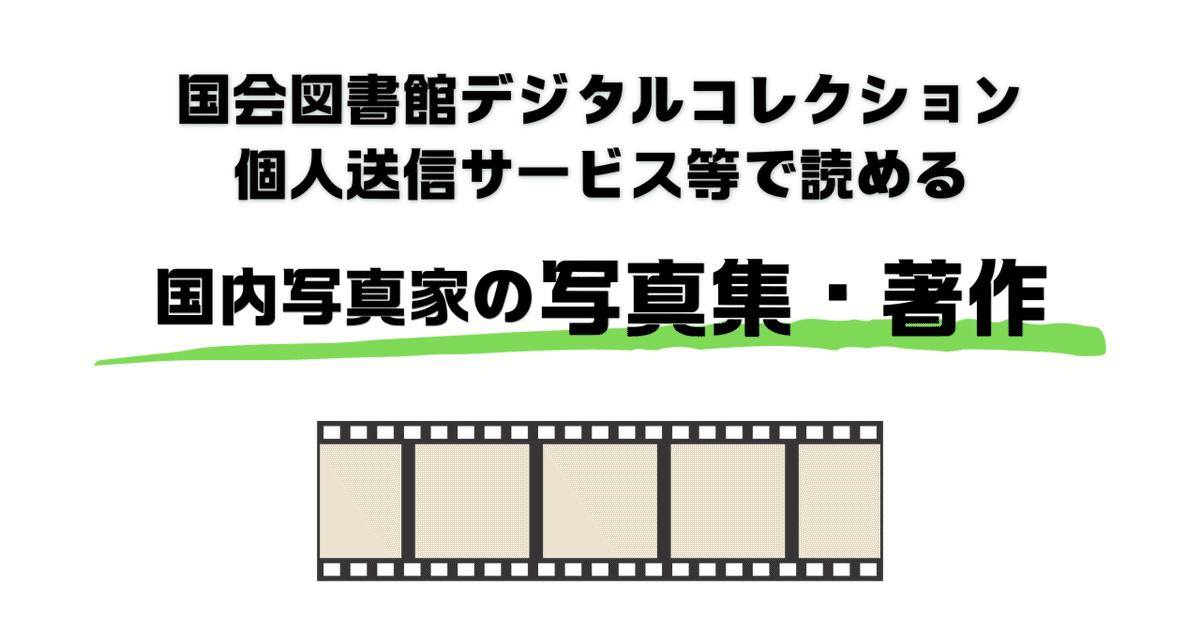
国会図書館デジタルコレクション個人送信サービス等で読める国内写真家の写真集・著作
以下の記事に触発されたので、コンセプトほか丸パクですが、表題の通りの内容を以下に記します。
とりあえずつくった暫定版です。代表的な日本の写真家(『日本の写真家101』新書館(2008)などを参考にしました)の写真集・著作のうち、主に国会図書館デジタルコレクションの個人送信サービスで読むことができるものを集めています。※ 個人送信サービスの説明や登録方法はこちら。
おもに2024年4月末の追加によって、1995年ごろまでの絶版書目を中心に、多くの文献(とくに各分野で「古典」とされているようなもの)が登録すればオンラインで読めるようになっています。
暇をみて更新するつもり…はありませんので、テーマ・地域別のリストの作成や、日本人以外の著者についてまとめたい人は好き勝手にまとめてください。また作成者は写真史の専門家ではありません。漏れがあったり、写真家の選定に論争性があるかもしれませんが、そういうのは専門家にお任せします(国会図書館デジタルで無料で読める書籍をもたない写真家は除外していますので、著名な人物であっても掲載されていない場合があります。また雑誌の口絵などを網羅すると膨大になるため、一部のみ記載しています)。
記載順は大まかには出生年をもとにしていますが、前後の関係性も加味して順序は変更しています。
一部の写真家については、解説書なども見つけるたびにリストに入れています。また、各作家の略歴と関連する出来事、肖像写真も合わせて掲載しています。
※肖像写真は、著作権が切れている、または著作権法に照らして公正な引用と著者が判断するものを掲載しています。また、前記のうえで肖像権ガイドラインに照らし合わせて公開が問題ないと判断されるものに限り掲載しています。
完璧なリストを目指したものでは決してありませんので、なにとぞご理解くださいませ。
--注意--
紹介する写真集の一部には、暴力表現、ヌード等の性的表現が含まれています。あらかじめご承知おきください。
作成:2024年5月21日 Harada Riku
公開:2025年1月6日
1. 上野 彦馬(1839~1904)
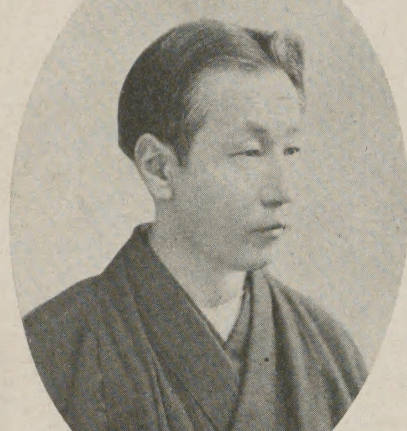
『最新写真科学大系』第10,誠文堂新光社,1935-38.
撮影者:不明
「写真の日」という記念日を知っていますか。
上野彦馬(うえの・ひこま)の父である上野俊之丞が、日本ではじめて銀板写真を撮影した1841年6月1日を記念して、その日が写真の日と定められています。
この写真の日、今から実に約200年前に日本写真の歴史はスタートしました。
___
ちなみに、写真の日は、梅本貞雄ら主導のもと日本写真協会により、1951年に制定された記念日なのですが、後に梅本の主張(6月1日説)は誤りだとわかり、現在は日本写真協会のHPで公式に否定されています(現在の説では日本初のダゲレオタイプによる写真撮影は1857年9月17日とされる)。
___
上野彦馬は長崎銀屋町で蘭学者をしていた上野俊之丞(しゅんのじょう)(1790~1851)の次男として生まれました。
父の俊之丞は長崎奉行所の御用時計師であり、塩硝(硝石:鉄砲火薬の原料)や開発やエレキテルの製作などを行うその当時一流の学者・技術者だった。彦馬はそんな父の元で育つことになります。
1858年には第二次海軍伝習所の教官として招聘されたオランダ人軍医のポンペを教官とする医学伝習所の中に新設された舎密試験所に入り、舎密[せいみ](化学)を学びます。このとき、ポンペを通じてコロジオン湿板写真を知り、同僚の堀江鍬次郎らとともに独学で技術を習得していきます。とはいえ、当時は感光剤に用いるための化学薬品(アルコールや硫酸、アンモニア等)の調達が難しく、彦馬はアンモニアの製造のために、牛の死骸を土中で腐らせたうえで鍋で煮詰める(蒸留する)というまさに苦肉の策を講じていたという。腐った牛を煮詰める姿から彼は周囲から狂人扱いされたそうです。
1859 年に日米修好通商条約に基づき長崎や横浜が開港したタイミングで日本に訪問したスイス人写真家ピエール・ロシエに写真術を学び、その後は堀江とともに江戸に出て数々の写真を撮影してまわりました。
1862年、故郷の長崎に戻り上野撮影局を開業。同撮影局では坂本龍馬や高杉晋作ら幕末に活躍した人物や当時の名士の肖像写真を数多く撮影しました。
2. 横山 松三郎(1838~1884)

写真新報社 [編]『写真新報』(152),写真新報社,1911.
撮影者:不明
天保9年に千島列島の択捉島(えとろふ)で生まれた横山松三郎(よこやま・まつさぶろう)は、函館に寄港したペリー率いる米艦隊が持ち込んだ写真(機)を通して、写真の存在をはじめて知ることになります。その後、横山は下岡蓮杖に師事することで当時最先端の科学技術であった写真術/印刷術を学んでいきます。1868年には上野池之端で写真館「通天樓」を開き、歴史に残る数多くの写真を撮影します。明治期に、現在重要文化財に指定されている『旧江戸城写真帖』や『壬申検査関係写真』を撮影したことでも著名な横山は、日本最初期の建築写真家といってもよいでしょう。
その後は、陸軍士官学校でも教鞭をとり、軽気球の飛行実験を通して日本初の空中写真を撮ったことでも知られます。
日本写真史の開祖たちのひとりである下岡蓮杖の一番弟子として名前が上がることもある横山ですが、いくつかの教科書を読む限り、彼の写真家としての功績が紹介されることは少ないようです。
3. 小川 一眞(1860~1929)

写真新報社 [編]『写真新報』(184),写真新報社,1914.
撮影者:不明
一般にはあまり知名度のない小川ですが、日本で生活している30代以降の人は確実に小川の写真を眼にしたことがあるはず(もっといえば、彼の撮った写真を今も持っている人も多いだろう)。
というのも、旧千円札の図案として採用された夏目漱石の肖像写真を撮影したのは彼だからです。
小川一眞(おがわ・かずまさ)は、現在の埼玉県行田市で、忍藩士原田庄左衛門の次男として生まれました。7歳のときを起こった戊辰戦争では父に従い初陣をしたといいます。1873年、14歳のときに上京し有馬学校に入学して英語を学び、イギリス人教師の家に書生として住み込みます。住み込み先のイギリス教師がアマチュア写真家だったことで、自身も写真に興味を持つようになり、帰郷したのちは中古のカメラを買うなどして写真の研究を続けました。その後、埼玉県初の写真館である吉原英雄写場に入門し湿板写真を学んだのち、17歳の頃に独立し群馬県富岡市で開業します。
その後、小川は写真業を一時休業し、横浜警察署で英語通訳の仕事をしながら学費を稼ぎ、1882年1月に横浜のバラ築地大学校(現在の明治学院大学)に入学しました。同年に、横浜に入港していたアメリカ海軍軍艦スワタラ号の艦長と知り合う機会を得て小川は艦長付き給仕として特別に乗艦を許可され、乗組員の一人として横浜を出発し、アメリカはボストンに留学します。
ボストンに到着した小川はRitz & Hastings photography studioで講習料を支払いながら住み込みで働くことになります。撮影だけではなく、写真製版や印刷までの大規模かつ組織的な写真/印刷業を営むアメリカの写真スタジオで修行をするなかで、当時の日本では希薄だった産業としての写真という感覚を学び取っていきます。
当時のアメリカは、1881年に創業したEastman Dry Plate Company(後のコダック社)に代表されるように、感光材が湿板から乾板へと移り変わる時代でした(「コダック」が製品化されるのは1887年)。最新の技術だった乾板写真術の熱気を浴びながら、小川は、乾板での撮影や乾板製造、コロタイプ印刷などの写真製版術も修得していきます。
1884年に帰国した後、1885年に営業写真館「玉潤館」を開設、1888年には写真製版工場と印刷工場を開業します。翌1889年には日本初のコロタイプ印刷所となる小川写真製版所を開き、美術作品のコロタイプ印刷等を手掛けるようになり。また同年には日本乾板製造会社を設立して写真乾板の製造販売も行いました(日本乾板製造会社は数年で潰れ、1907年に再設立されます)。その後、1894年には大量印刷を可能にするための写真銅版の製造を開始し、印刷事業にも力を入れます。このように、小川は手工業品としての側面の強かった写真を工業製品とするために、多くの事業を設立しており、実業家としての面も有していました。
小川が日本に導入したコロタイプ印刷は、網点がないことが特徴で、白と黒の濃淡を滑らかに仕上げること出来ます。当時の印刷水準のなかで、小川は群を抜いて優れたクオリティを実現できたわけです。この技術を用いて、小川は多くの文化財の写真をコロタイプで印刷し、その再現性の高さから高く評価されます。
1888年には宮内省、内務省、文部省が共同で実施した近畿地方の文化財調査に参加し、調査結果をまとめた美術雑誌『國華』や『真美大観』に自身の撮影した写真を掲載しました。また、日露戦争の報道や伊藤博文の国葬、明治天皇の大喪の礼の撮影など、歴史的なイベントの記録にも関わります。
19世紀の日本では、まだまだ写真は「野鄙」(下品の意味)だとみなされていました。小川は上流階級と関係を結び、当時の社交界の一流の人々の肖像写真を撮影する中で、このような風潮を打開し、写真を「高尚な技術」として公に認めさせることに成功しました。
1891年10月28日に発生した濃尾地震の調査に同行した小川による被災地写真。
『Types of Japan : celebrated geysha of Tokyo / by K. Ogawa, photographer.』[1],Kelly and Walsh,1895.
第五師団司令部 ほか『北清事変写真帖』,小川一真,1902.
写真は軍属のだれかのもので、製本と編纂について小川が実施。
小川一眞 『Yoshiwara, a nightless quarter』,小川一眞,小川一眞寫眞館 (distributor),1910.
当時の吉原を捉えた手彩色写真。
小川一眞 『[故伊藤公爵国葬写真帖]』,小川写真製版所,1909.
伊藤博文の葬儀。
明治天皇の葬儀。
佐藤鐵彌 編輯『寫真新報』(12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23),佐藤鐵彌,1890.
小川が営んでいた写真館「玉潤館」の営業用資料が掲載されている。当時の料金表も添付されている。
4. 鹿嶋 清兵衛(1866~1924)
慶応2年に大坂天満の酒問屋「鹿嶋屋」の当主鹿島清右衛門の次男として生まれた後の八代目 鹿嶋 清兵衛(かじま・せいべえ, 幼名:政之助)は、天満鹿嶋屋の没落に伴い、江戸の下り酒問屋であった江戸鹿嶋屋(江戸本店)に引き取られ、八代目清兵衛を襲名します。当時の鹿嶋屋は大豪商だったのですが、明治維新に伴って、少しずつ商いに陰りが見えはじめます。そんな時代の変革期に、清兵衛は先代が持っていた写真機を蔵で見つけ、写真をはじめることとなります。
次第に写真にのめり込んでいった清兵衛は、鹿嶋家の財産を背景に、銀座に150坪以上の写真スタジオを設け、超大型電灯による夜間撮影やイギリスから取り寄せた全紙4倍サイズの暗室カメラによる等身大撮影など、贅沢を尽くした写真撮影に取り組んでいきます(この特大暗室カメラで日本初の舞台[歌舞伎]写真を撮影します)。
金持ちの道楽という側面は強く見える清兵衛の写真との関わりですが、後の写真の歴史に貢献した部分も多くあります。清兵衛は、国産写真乾板の安定製造を目指した(が失敗した)「築地乾板製造所」(1888)の設立や、日本初の写真団体「日本寫眞会」(1889)の結成、大日本写真品評会(1893)の創立などに出資を行い、日本における写真の工業化と普及を支えました。
清兵衛は、キリンビール主催の美人写真コンテストに応募する際に、芸妓のぽん太(ゑつ)をモデルとして起用し、その縁から、後の人生を共に過ごすこととなります(妻と家業を捨て、ぽん太と再婚した後は、写真で生計を立てることになります)。晩年は舞台効果用のマグネシウムの爆発事故を起こし右の親指の切断し、写真業からは離れています。ちなみに、清兵衛は森鴎外の小説『百物語』の登場人物のモデルにもなっています。
没後、しばらく経った後、1963年に日清製油(現:日清Oillio)本社ビルの増築工事に際して、建設現場から大量の小判が発見されました。当時の時価で5~6000万円と言われる大金です。現場は鹿嶋家の屋敷跡であり、写真の現像液を入れるガラス容器に小判が入っていたため、清兵衛の埋蔵金と騒がれました。
遺失物法によって、この埋蔵金は警察の預かりとなり、半年以内に所有者が現れなければ、現在の土地の所有者と発見者に山分けされてしまいます。鹿嶋家の人々はとにかく躍起になって、所有権を実証するものを探した結果、清兵衛とその一人目の妻である乃婦(のぶ)が小判を埋めていたことを記した文献を見つけ出します。この文献が証拠となって、当時大宮に住んでいた10代目鹿嶋家当主は埋蔵金を手にしました。当時の当主は「もっと掘ればまだ埋まっているかも知れない」とホクホク顔で語っていたそうです。
小川一真の写真集だが、VとXVは清兵衛撮影のもの。
鹿嶋の伝記が掲載されている。
鹿嶋清兵衛の演劇写真については以下論文の第7章を参照。
5. 福原 信三(1883~1948)

『寫眞文化』23(5),アルス,1941.
撮影:三木淳
福原信三(ふくはら・しんぞう)は、日本の実業家、写真家であり、資生堂の初代社長としても知られています。彼は資生堂(資生堂薬局)の創業者である福原有信の三男として東京銀座に生まれ、弟に同じく写真家の福原路草がいます。
中学時代は画家を志していたが、信三は父の意向で薬学を学ぶことになり、千葉医学専門学校(現:千葉大学医学部)で薬剤師の資格を取得します。その後、1908年に渡米し、コロンビア大学薬学部で4年間の留学をします。同大を卒業後はすぐには帰国せず、1年間ヨーロッパを巡り、各地の美術館や博物館を訪れ、欧州の華やかな時代(ベル・エポック)の芸術潮流と都市景観を目の当たりにして1913年に帰国します。
1915年に資生堂を継いでからも、写真活動は継続しており、1919年には、資生堂ギャラリーを開設(現存する日本最古の画廊)し、積極的に写真の展覧会も行いました。また、信三はグラフ誌の創設に多大に貢献しており、1921年には寫眞藝術社を起こし、『寫眞藝術』を創刊。誌上で写真芸術論「光と其諧調」を展開し、当時の写真家たちに大きな影響を与えます。その後も、創刊に携わった『日本寫眞会会報』や『アサヒカメラ』などの雑誌を雑誌を通じて、信三は写真が単なる記録手段ではなく、芸術表現の一つであることを訴え続けました。
信三が誌面で展開した議論は、絵画芸術の流れを踏襲する従来の写真観に一石を投じるものでした。ピグメント印画法に代表される絵画技法の写真への転用に否定的な立場を取るなど、彼は(絵画の延長ではない)写真独自の芸術性、写真だからこそ成し得るイメージの創出にこだわりました。
また、信三のこのような立場は、手間ひま(とお金)のかかるゴム印画やブロムオイル等の技法でつくられた写真こそが「作品」だとされがちだった当時の価値観に変化を生みます。特殊な技法を使っていない、普通の印画紙に引き伸ばした写真にも「作品」としての価値を見出す考え方は、アマチュア写真界に「大衆化運動」ともいえる大きなうねりと新たな進路をあたえました。
____
「写真ではカメラを通じてそのまま自然美を捉え、表現し得る所に真の価値が存在するから一層芸術的頭脳の明晰を必要とし、人格の陶冶が必然的に要求される。価値とは人格を中心とした遠心力の総和である。一方印画が芸術品として許されるには、そこに人格が含まれ、個性が含まれて居なければならない。」
(福原信三「寫眞藝術の新使命(4)」『寫眞藝術』2 (7),1922. より抜粋)
____
現代においてもよく耳にする、「良い写真をとるためには撮り手(芸術家)の目を養い鍛える必要がある」といったモットーはまさに信三が当時の写真界に求めた「写真の新使命」といえるでしょう。
そんな信三は、1935年ごろから白内障と緑内障を併発したために視力を著しく落とすことになります。晩年は絵画鑑賞や写真撮影のすべを失った信三ですが、執筆活動は精力的に続けており、秘書の手伝いによる口述筆記によって以後も写真/芸術論を展開し続けます。
武蔵野の風景を記録したことについては、中島(2015)が詳しい。
『福原信三・福原路草写真集 : 光と其諧調』,ニッコールクラブ,1977.
グラデーションの意味の「階調」とよく間違われるが、ハーモニーの意味の「諧調」が正しい。ただし、1920~30年代当時においても、誌面ではよく「階調」と誤植されていたので、現代人からすれば一層まぎらわしい。
福原は写真芸術のことを「自然を端的に表現する俳句の境地に近い」と評している。彼は松尾芭蕉を範としており、芭蕉が自然の情景を視覚的に文章で表現したのと同じように、写真においても自然美を視覚化できないかと考えていた。福原にとって俳句は状況を視覚的/精神的に浮かび上がらせる空間芸術であり、写真の教師となる存在だったようだ。
時代背景を鑑みると「写生」を重要視する正岡子規以降のいわゆる新派の影響も大きいように思われるが、子規や高浜虚子への言及はあまり見られない。
福原信三の伝記としては、管見の限り、この著作が最も詳しい。また、伝記の冒頭に掲載されている福原の写真が、このリストに掲載している福原の写真集のなかで最もプリント(というより国会図書館での撮影)が良いようにみえる。
6. 福原 路草(1892~1946)
福原路草(ふくはら・ろそう、本名:信辰)は、資生堂の創業者である福原有信の四男として生まれます(ちなみに福原家は五男四女の9人兄弟)。兄は資生堂の初代社長であり写真家としても有名な福原信三です。
もともと路草は大学卒業後に新聞記者になりたいと思っていましたが、父の有信はそれを許しませんでした。父への反発もあってか結果として路草は生涯なんの定職にも就かないことを選択します。兄の相談相手として資生堂には常務(晩年には副社長)として席を置きましたが、甥の福原信和によれば、ただ名を連ねていただけであったといいます。パリに留学にもいきましたが、すぐに帰国してしまうなど、なにかと兄とは対照的な人物として評されることもあります。
彼の雅号である「路草」は慶応に入学した頃(1910年代前半~中頃)に参加した句会で名乗ったのがはじめで、「おれは人生のみちくさを食う男」といって「路艸」(のちに「路草」)という名前にしたそうです。会社を継ぐことの決まっている信三と9歳離れた弟の路草。彼はこの頃すでに自身の人生について達観していたのかもしれません。
路草の写真家としてのキャリアは、1920年代に本格化しました。彼は1921年に、兄の福原信三、大田黒元雄、掛札功、石田喜一郎らとともに「寫眞藝術社」を結成します。この組織は、写真技術と美学の向上を目的としており、同年6月から1923年9月まで機関紙『寫眞藝術』を発行しました。路草は兄信三と共に、この活動を通じて、写真が単なる記録手段ではなく、芸術表現の一つであることを広く訴えました。
そんな路草の作風は、ピクトリアリズムの影響を強く受けたものです。ピクトリアリズムは、写真を絵画のように扱うことを目指す運動で、柔らかいフォーカスや光と影の巧妙な操作を特徴とします。彼の作品は、このスタイルを取り入れ、詩的で夢幻的なイメージを作り出しました。特に風景写真において、その技術と美学は際立っています。
7. 高山 正隆(1895~1981)
高山正隆(たかやま・まさたか)は、科学者の高山甚太郎の子として東京市(現:東京都)で生まれます。
1920年代から1930年代にかけて活躍したアマチュア写真家で、ピクトリアリズムの代表的な作家の一人です。彼の写真家としてのキャリアは、早稲田大学在学中に始まりました。当時、音楽や油絵制作に熱中していた高山は、写真撮影にも興味を持つようになりました(あまりに熱中しすぎて、大学は中退してしまいます)。その後、写真雑誌『藝術寫眞研究』の投稿欄で選者を務めていた写真家の中島謙吉(1888~1972)に見出され活躍の幅を広げていきます。
高山が使用した主要なカメラの一つに、ヴェスト・ポケット・コダック(Vest Pocket Kodak)があります。このカメラは非常にコンパクトな折りたたみ式のモデルで、127フィルムを使用していました(ヴェストのポケットに入るくらい小さいカメラとして売り出されたのでこの名前)。当時の日本では人気のカメラで、高山をはじめとしたこのカメラの愛用者は「ベス単派」と呼び称されるようになります。
このカメラのレンズは、基本的な1群2枚構成で、開放絞りがF11に制限されていました。これは球面収差を抑えるためです。しかし、大正時代の末期につかわれていたフィルムの感度はとても低く、より高速のシャッター速度を得るためにフード様の絞りを外すことが行われました(こちらを参照)。これにより、レンズのF値はF6.8程度まで明るくなるのですが、その副作用として、大きな球面収差が発生してしまいます。しかし、怪我の功名か、この収差によって幻想的なソフトフォーカス描写が得られるようになりました。この独自の効果を狙って意図的にフードを取りはずし、絞りを開放にして撮影する技法は「ベス単フードはずし」として定着していきます。高山はこの技法を好んで実践し、幻想的かつ叙情的なピクトリアリズム作品を多数残しました。
高山の静物画が掲載されている。また、森芳太郎の論説「アマチュアリズムの勝利」は戦前のアマチュア写真文化の雰囲気を知る手がかりになる。
8. 塩谷 定好(1899~1988)
塩谷定好(しおたに・ていこう、本名:しおたに・さだよし)は鳥取県東伯郡赤崎村(現・琴浦町)の裕福な廻船問屋の家に生まれました。幼少期から芸術に興味を持ち、特に写真と絵画に関心を寄せました。実家の裕福さは、彼が小学校3年生の時からカメラを手にしていたというエピソードからも知ることが出来るでしょう。
1917年に鳥取県立農学校(現・鳥取県立倉吉農業高等学校)を卒業後、地元で「ベストクラブ」を設立し、写真活動を開始しました。ベストクラブの名前にもあるように、塩谷は「ヴェスト・ポケット・コダック」(ベス単)を愛用しており、「ベス単のフードはずし」によるソフトフォーカス描写を作品の特徴としていました。
そんな塩谷は生涯師匠と呼ぶような人を持たず、試行錯誤しながら、ほぼ独学で現像法や撮影技術を勉強します。その甲斐もあり1926年の『アサヒカメラ』創刊号の第1回月例コンテストで一等を獲得するなど、次第に頭角を現していきました。
1920年代後半には、東京の「芸術写真研究会」や京都の「日本光画協会」に参加し、全国的な写真家コミュニティと交流しました。1934年には「国際写真サロン」で連続入選し、特待員として認められるなど、その技術と芸術性は国内外で高く評価されます。
戦後、塩谷は写真教育にも力を注ぎます。専門的な写真教育機関が少なく、学ぶ機会が限られている地方都市において、多くの後進を育てた塩谷の功績は大きいものでした。1950年には「倉吉美術協会」を設立し、写真部門の審査員を務めるなど、地域の美術活動にも貢献しました。
また、2010年に塩谷定好が琴浦町から名誉町民の称号を受けたことをきっかけとして、元赤碕町長田中満雄を会長とする記念館設立準備会が発足しました(琴浦町は2004年に合併で生まれた町で、塩谷の生まれた赤崎村の地域も合併に含まれる)。2013年2月25日には「塩谷定好フォトプロジェクト」が設立され、2014年には彼の生家が「塩谷定好写真記念館」として開館しました。同記念館は現在、国の登録有形文化財に登録されています。
塩谷定好『海鳴りの風景 : 塩谷定好写真集』,ニッコールクラブ,1984.
巻末で塩屋定好・三木淳・植田正司・塩谷晋(定好の孫)での座談会がある。定好独特のセピア調での印画についても触れられている。余談だが、定好が印画紙のスポッティング作業に、近所の種畜場で採ってきた牛の精液を使用していたエピソードが紹介されている。何でも使ってみろの精神は流石です。
9. 中山 岩太(1895~1949)

『世界写真全集』第5巻 (日本),平凡社,1956.
撮影者:不明
写真が芸術の一分野として認識され始め、その技術や美学を体系的に学ぶ場が求められだしたなかで、東京美術学校(現・東京芸術大学)は、1915年に臨時写真科を開設します。この学科の第一期生の一人が中山岩太(なかやま・いわた)です。
大学卒業後の1918年に、中山は農商務省の海外実業練習生として渡米し、カリフォルニア州立大学で学びます。その後は、ニューヨークに移り、鈴木清作と共同でNY5番街に「ラカン・スタヂオ」を開設しました。そこで肖像写真師として成功した中山は、1926年にスタジオを売却し、パリへ渡ります。
パリでは、藤田嗣治やマン・レイ、エンリコ・プランポリーニなどと交流し、欧州モダニズムの最前線に触れました。この時期に彼は多くの影響を受け、その後の作品に反映されました。1927年にベルリンを経由して帰国し、しばらくは東京で写真師として働きます。
1929年、中山は兵庫県芦屋に移り、「芦屋カメラクラブ」を設立しました。このクラブは、日本の写真家たちが集まり、高度に洗練された作品を制作・発表する場として機能しました。彼はこのクラブを通じて多くの写真家を育成し、日本の写真界で指導的な役割を果たします。
芸術作品の制作の一方で、中山は商業写真家としても頭角を現しだし、1930年には、東京朝日新聞社主催の「第一回国際広告写真展」で彼の作品「福助足袋」が一等に選ばれ、広告写真の分野で先駆者としての地位を確立しました。
上記のようにマルチに活躍する中山ですが、彼の創作活動において、もっとも重要な点はいわゆる「新興写真家」という立場を取ったことでしょう。
1931年に、東京・大阪で開催された「独逸国際移動写真展」で、当時のドイツで起こった新即物主義(ノイエ・ザッハリッヒカイト)に影響を受けたドイツ新興写真が公開されます。そこで紹介されたマン・レイやアボット、モホイ=ナジ、アジェなどの作品は来場者に重大な影響を与え、浪華写真倶楽部、丹平写真倶楽部、そして中山の設立した芦屋カメラクラブなど、関西の写真家団体が一斉に芸術写真から新興写真への移行をはかるキッカケにもなりました。
新興写真家たちは、従来の絵画的な美意識(ピクトリアリズム)にとらわれず、写真ならではの表現力を追求しました。彼らは絵画的な構図や柔らかなフォーカスの代わりに、シャープでストレートな描写、抽象的な構図、大胆なアングル、フォトモンタージュなどの技法を採用しました。また、従来の芸術写真が風景やポートレートを主題としていたのに対し、新興写真は都市風景、産業、社会の変革など多様な主題を取り上げた点でも特徴的です。また、当時は小型カメラの普及とフィルム技術の向上により、写真撮影がより手軽になった時代でもありました。この変化により、それまでの大掛かりな芸術写真から、スナップショットのような機動力のある写真への移行が促進されたことも、新しい表現の隆盛に影響しています。
上記の複層的な特徴からもわかるように、新興写真は、前衛写真へと向かう潮流や、報道写真として発展していく潮流等の複数の流れを包摂していました。
なお、金丸重嶺は新興写真とは「旧芸術写真の牙城に立籠っている人達即ち、新しいこの写真に対して賛同の出来ない人達が自分たちの立場の外の存在、即ちこの新しい写真に対して便宜的につけた名称であると思う」(『新興写真の作り方』,p.70.)と述べており、新興写真はムーブメントとしての明確な輪郭を持つものではないとしています。つまり、当時の日本にはなかった新しい「写真ジャンル」を、まとめて「新興写真」(新しい写真)と称したともいえます。新興写真は、現在のように写真のジャンルが細分化し、独自の趣味・芸術性を確立する前の、未分化な源流として存在していたともいえるかもしれません。
中山は「独逸国際移動写真展」の開催後、1932年には野島康三や木村伊兵衛とともに写真誌『光画』を創刊します。この誌面上で新興写真の表現を積極的に展開していくことで、中山は「新興写真」の旗手として日本の近代的写真表現をリードする存在となります。
新興写真のブームは、多くの才能ある写真家を輩出しました。しかし、光画の創刊以降、徐々に新興写真の手法はマンネリ化し、運動は停滞していきます。
その後は、1938年に瀧口修造によって前衛写真協会が設立されるなど、一部の写真家はシュルレアリスムや抽象表現を取り入れた前衛写真へと向かいましたが、そういった動きも、太平洋戦争の勃発による厳しい社会状況のなかで大きく制限され、次第についえていきます(1941年に瀧口が特高警察に逮捕されたことで活動は終息)。
また、新興写真運動のなかで育まれた報道写真の基本枠組みは、戦時下のプロパガンダのためにグラフ雑誌の中で実践されます。こういった実践は、戦後の新しい写真の潮流(ドキュメンタリー写真やリアリズム写真など)の台頭の下敷きとなりました。
中山正子 著『ハイカラに,九十二歳 : 写真家中山岩太と生きて』,河出書房新社,1987.
妻の中山正子の自叙伝。彼女の目線から見た岩太の仕事や生活についても多くの記述がある。
10. 伊奈 信男(1898~1978)
伊奈信男(いな・のぶお)は、日本の写真評論家であり、愛媛県松山市で生まれました。1922年に東京帝国大学(現・東京大学)文学部美学美術史科を卒業し、その後は同大学の美術史研究室に勤務しました。彼の専攻は西洋美術史で、特に初期ルネサンス美術を研究していました。
1931年頃から「綜合ジャーナリズム講座」というシリーズを出版していた内外社に出入りしはじめ、大宅壮一、林達夫らの信頼を得る。その流れで1931年に設立された日本とソ連の文化交流をめざす民間組織「ソヴエート友の会」発行の月刊グラフ雑誌『ソヴエートの友』の編集長に請われて就任。その後、谷川徹三から評論家の秋葉啓を紹介されたのをきっかけに、1932年に『光画』創刊号に『写真に帰れ』を掲載します。
伊奈は『写真に帰れ』のなかで、写真が単なる絵画の模倣をするのではなく、独自の視覚表現としての価値を持つべきだと主張しました。写真本来の機械の眼としての機能を基礎として、純粋な光学現象を写真芸術とすべきだと考え。その上で、写真家が持っている社会への目線を、積極的に光学現象として切り取り、可視化(現実化)することを重要だと据えたのです。
日本の近代写真論の先駆けとなった彼の議論は、新興写真ムーブメントや後の報道写真の隆盛に大きな影響を与えます。
このような前提を理解すると、なぜフォトグラムのようなカメラを用いない(一見して純粋芸術のような)写真技法が、報道写真と同じ「新興写真」というカテゴリーで語られたのかも自ずと分かるかもしれません。モホリ=ナジは従来の写真が「光によって外部の世界を写す」ものであり、「外部に存在する事象に対応するもの」と考えていました。それに対してフォトグラムは、「完全に作家のコントロールによって生成するもの」であり、「写真家の内部の世界を写すもの」と位置付けました。光学現象によって、自身の心象や世界/社会への視座を具現化するという点で、フォトグラムと報道写真は親戚関係にあるというわけです(フォトグラムについては[港,1995.]が詳しい)。
「写真に帰れ」の発表の後、伊奈は名取洋之助、木村伊兵衛、原弘、岡田桑三らと報道写真や商業デザインの制作を主とする「日本工房」の創設に参加します。1934年には日本工房主催で「報道写真展」を開催し、そのときに出版した小冊子『報道写真に就いて』のなかで、伊奈は「ルポルターゲ・フォト」(reportage photo)を「報道写真」と訳します。
この写真展では、写真の読み方をキャプションで規定したうえで、複数のグラフィックの構成によってストーリーを展開させることで、一つのメッセージを提示するといった新しい方法(いわゆる「組写真」の方法)が示されます。こういった複数の写真構成によってストーリーを伝える方法は、今日では(報道というよりは)ドキュメンタリー写真と呼ばれるジャンルに近いものです。
現在では、複数の写真を一つのパッケージとして提示する手法はもはや当たり前のものですが、当時はまだ写真は一枚ずつ提示するものという常識とされており、こういった見せ方は斬新さを持っていました(芸術写真の時代においては、写真は絵画と同様に1つのイメージで完結させるのが普通でした)。
――――
なお、「報道写真」の用語自体は、同写真展の開催よりも古い時代から存在しており、少なくとも1918年には報道写真の用例があり、1920年代には一般的に使用されるようになっている。例えば、1922年には、東京朝日新聞が「報道写真」を一般に募集し、優れた写真は紙面に掲載するとしている。ただし、この募集情報では、「報道写真」とは各地の著名人や面白い風俗祭祀の写真のことをとりわけ指しており、現代的な報道(ジャーナリズム)とはニュアンスがやや異なる。その点では、伊奈の報道写真の用法は今までのこの用語の使用法に新しい文脈を挿入するものであったようである。
ともかく、1910年代後半~1920年代には、新聞等に掲載した写真を報道写真と呼ぶようになっている。なお、新聞に写真が使用されだした(絵画から写真に以降した)のは1890年代頃からで、新聞に写真が使用されるようになってから報道写真の用語が定着するまでには、20~30年程度のタイムラグがあるとみられる。
―――――
話を戻すと、報道写真展の直後に日本工房は分裂し、伊奈は同じく脱退した木村、原らと中央工房を設立します。1931年の満州事変から始まり1937年の日中戦争、1940年の紀元2600年祭など国威発揚の機運が高まるなかで、1941年に陸軍参謀本部および内閣情報部の後ろ盾で海外向けプロパガンダをする組織(国際報道写真協会)が設立され、この組織に合併する形で中央工房は東方社へとなります。伊奈自身は、内閣情報部の情報官としてプロパガンダ政策に関わります。
第二次世界大戦後、伊奈は写真評論家として活動を継続し、特に日本の写真史を世界写真史のなかに位置づけようとする仕事を精力的に行います。1968年からはニコンサロン名誉館長に就任するほか、日本写真協会常務理事などを務めました。彼の功績を称えて、1976年に「伊奈信男賞」が創設され、この賞は新進写真家の発掘と支援を目的としており、現在も多くの優れた写真家を輩出しています。
猿が人間を真似る時、猿は決して人間的になるのではない。反対に、猿は、人間を真似るとき、最も「猿らしく」なるのである。写真もまた「芸術」を模倣するときによっては、決して「芸術的」となることは出来ない。「芸術」の概念それ自身がまた不断の変化を受けつつある。昨日の「芸術」は、もはや今日の「芸術」ではない。写真に於て「芸術」を模倣するとき、それは常に昨日の「芸術」を模倣することになるのである。
~~
「芸術写真」と絶縁せよ。既成「芸術」のあらゆる概念を放棄せよ。偶像を破壊し去れ!そして写真の独自の「機械性」を鋭く認識せよ!
(p.3.)
―――――――――
この場合に写真芸術の内容になり得るものは、その人間の属する社会生活の断面であり、自然世界の一般事象以外にはあり得ない。そして、人間が、主体が、これらの客体をみる時、それはすでに単なる人間の眼をもって見るのではなく、「カメラの眼」をもって見るのである。カメラという表現手段と、光線単色などの表現材料――すなわち、写真芸術の形式――をもって、表現し得る範囲において見るのである。かくのごとくして内容が形象化されるためには、一定の必然的な形式を要求するのである。内容と形式は相互に必然的な関係において、互いに他を揚棄しつつ、芸術を完成するのである。写真芸術もまた、このようにして完成されるのである。
~~
写真こそは、最もこの社会生活と自然とを記録し、報導し、解釈し、批判するに適した芸術である。しかし、「カメラを持つ人」は社会的人間であることを忘れてはならない。彼が社会と游離したときこそ、写真芸術は、「現代の年代記作者」たる光輝ある視覚を棄てて更び無意味なる唯美的傾向を採り始めて、他の芸術と同様なる衰滅の道をたどるであろう。
(pp.13-14.)
「歴史に残る内外の報道写真ー戦争写真を中心としてー」『新聞写真』,日本新聞協会,1970.
同書は新聞メディアにおける写真活用の変遷についても詳しい。
絵画芸術の模倣からの独立という点で、伊奈が「写真へ帰れ」で展開する議論は、福原信三が「光と其諧調」で行った議論と類似する。しかし、伊奈と福原には、写真表現に社会批評の文脈を持ち込むか否かという点で決定的な違いがある。伊奈自身は、福原のことを「彼はこの現実の世界から遊離し、現実の社会や生活とは無関係に芸術写真に安住していたのである」と批判している(p.13.)。
11. 金丸 重嶺(1900~1977)

白川義員『山岳写真の技法』,1973.
撮影者:白川義員
金丸重嶺(かねまる・しげね)は1900年、東京市麻布区に生まれました。幼少期から写真に興味を持ち、義兄が写真家の弟子だったことも影響してアマチュアとして写真制作を始めました。その後、金丸は東京通関株式会社に入社し、都内所長を歴任しますが、写真への情熱は増すばかりで、1925年に金丸写真研究所を開業しました。1926年には、日本初の広告写真専門スタジオ「金鈴社」(金丸重嶺と共同経営していた鈴木八郎との名前を取って「金鈴」とした)を設立し、多くの企業の仕事を引き受けます。
金丸が金鈴社を立ち上げた頃、日本における広告写真はまだ初期段階にあり、あまり発展していない分野でした。当時は営利目的の撮影業というと、写真館での記念写真や肖像写真が主流であり、広告写真ビジネスに参入する写真家(撮影プロダクション)は少数でした。こういった状況のなかで、金丸は広告写真家の草分けとして活躍していきます。
さて、そんな金丸の広告制作においても、新興写真のムーブメントは重要に関わってきます。
1920年代以前の広告写真は、単純な商品の説明写真が中心であり、その多くは形式的で固定化されたものでした。これらの写真は、商品の形状や色、質感をそのまま再現することを重視して作られていて、必ずしも独創的といえるものは少なかったのです。これに対して、金丸の広告写真は、新興写真の影響を受けたアプローチを取り入れていました。
彼は、商品の外観だけでなく、その特性や機能、使用シーンを視覚的に効果的に伝えることに注力しました。例えば、「新装花王石鹸」の広告キャンペーンでは、製品の魅力を視覚的に訴求するために、石鹸を使用するシーンを想起させるような背景や小道具を配置し、写真全体で商品の価値や使い方を消費者に伝える工夫を凝らしました。これにより、単に商品を置いただけの写真ではなく、見る者の心に強く訴えかけるビジュアルを作り上げました。
こういったビジュアル作成のことを、金丸は「知的で感情的な統一」であると説明しています。金丸が挙げた実例でいうと、風邪薬の広告写真を制作する際に、小さな白い丸い錠剤をただ撮影するのではなく、体温計や水の入ったコップと一緒に撮影することで、瞬時に病気や治療を連想させる効果をつくりだすこと。これが金丸の言う「知的で感情的な統一」であり、広告写真の視覚的に訴える力を最大化するための重要な手法でした。
こうした写真にストーリーテリングの要素を取り入れる手法は、現在では広告写真制作の常識となっています。まさにこの常識を作り出した点こそ、金丸の大きな功績と言えるでしょう(なお、同時代には、映像分野でロシアのクレショフが、複数の映像[画像]の組み合わせたときに、前後の情報に直接的な繋がりがなかったとしても、無意識に関連づけをしてしまう人の心理について論じており[クレショフ効果]、1920年代はイメージと心理の関係性について多くの議論が生まれた時代でした)。
金丸が手掛けたものをはじめとして、新興写真の技法を取り入れた広告写真は、その物珍しさもあって、次第に多くの企業で採用されるようになります。そうして、徐々に広告写真は写真家の新しい職業/仕事として定着していくことになります。このように、新興写真は、単に写真芸術の幅を広げただけの新しい芸術潮流だったというわけでなく、写真家の職域や「新しい職業」を準備するまでに業界の構造を変えたムーブメントでもありました。
なお、商品広告を手掛けるほかにも、金丸は戦時下において東宝映画の作成する戦記映画の記録撮影に従事したほか、日本工房が刊行したグラフ誌『NIPPON』の契約カメラマンとして取材を行うこともありました。また、1936年には日本新聞写真連盟の特派員としてベルリンオリンピックの取材をし、1938年には日中戦争の従軍カメラマンとして内閣情報部経由で現地派遣されています。その他にも国策宣伝のための広告作成も請け負っています。太平洋戦争時の勃発後の1943年には、金丸は新興写真の技法や広告写真家として培った発揮して、巨大写真壁画「撃ちてし止まむ」を制作します。これは、勇ましい二人の兵士が戦場で戦う姿をイメージした演出写真で、縦横約13mに及ぶ巨大なものでした。東京の日本劇場外壁に掲示されたこの写真壁画は、金丸の言う「知的で感情的な統一」によって国威発揚を行った戦時プロパガンダの代表例と言えるでしょう。
日中戦争への従軍取材を終えた金丸は、同年の1938年に、その後生涯を通して教育者として関わることとなる日本大学の写真講習会で講義を行うことになります。
日本大学に写真科が設置されたのは、1939年のことで、ちょうどこの頃に、現在と同じ江古田に日芸のキャンパスが出来ます。金丸は、当時の芸術科長(現在でいう芸術学部長)に請われ、この新設の写真科の初代主任として就任することになります。
金丸の教育理念は、写真を単なる技術としてではなく、芸術としての側面を強調し、学生に対して広範な知識と高い専門性を持つ写真家の育成を目指すものでした。彼は、写真が商業や報道においてどのように利用されるかを理解し、それに必要な技術を駆使することの重要性を説きました。また、彼の教育カリキュラムはバウハウスの影響を強く受けており、写真を通じた社会的な役割や商業的な応用に重きを置いていました。当時すでに写真学校自体は日芸以外にもいくつかありましたが(東京美術学校臨時写真科や東京写真専門学校、東京高等工芸学校印刷工芸科写真部、オリエンタル写真学校など)、いずれも写真館の子弟を育てることを目的とした教育を行っており、総合的に職業としての写真家(新興写真家)を養成するものではありませんでした。そのなかにおいて、金丸の取り組んだ写真家教育は、極めて新しい態度を伴ったものでした。
戦後、日本大学専門部芸術科は再編成され、金丸は写真学科の主任として、広告写真や報道写真の分野で活躍できる人材の育成に尽力しました。その後は1970年まで教授として携わり、その間に同大学理事、常任理事、学長などを歴任します。
また、金丸は博報堂の写真部門の立ち上げに関わるなど、学生の就職先を作ったという点でも大変功績があるといえます(ちなみに、今はあるかわかりませんが、日芸写真科には金丸重嶺のことを学ぶだけの講座があるらしい)。
当時の広告写真の事例
濱田増治「広告写真の行詰りと打開」『新興写真選集』,福岡日日新聞,1937.
現代の広告写真の基本骨子が、新興写真ムーブメントが広告写真に影響する中で生まれたことは、上記の論考からもわかる。
この時代の日本における新即物主義の意味合いについて補足
Wikipediaの新即物主義(2024/06/05アクセス)の項目では「主観的ともいえる表現主義に反する態度を取り、社会の中の無名性や匿名性として存在している人間に対し冷徹な視線を注ぎ、即物的に表現する」ことを新即物主義と書いています。もちろんこの記述も正しいのですが、必ずしも「主観を排した」「(人間も含めた)物象に対するリアリズム表現」だけが新即物主義ではないということも抑えておく必要がありそうです。
例えば金丸は『新興写真の作り方』で新即物主義を以下のように紹介しています。
新即物主義は、物の直接描写にのみたよらず、又対照の形式のみを描写するに止まらず、作家の自由な心が、目的物の内容にまで喰い入った時、即ち、目的物に対して起こる物質的イメージと、精神的イメージの合致する処の、心の動きに出発して、他のイズムの様に一定の規則のもとに自然を表現しようとするのでなく、その主観が対照に如何に働きかけるかという事によって、その実態の真実を表現しようとする…(pp.63-64.)
金丸にとっては、新即物主義(New Objectiveness)は、絵画の自然主義/写実主義にみられるような事物を忠実に描写する態度のことではなく、事物に対する作家のイメージ(主観)の表出を行う態度のようです。
新即物主義は表現主義(強烈な色彩や大胆な筆致、歪んだ形態などの特徴がある:ムンクやエゴン・シーレが代表的)と対決的に紹介されることもありますが、ここでは必ずしも主観vs客観のような図式ではなく、どちらかといえば、内観vs外観(内的自己vs社会的自己;自己の情念の世界への投影vs世界に対する自己の感想の表出)といった図式が近いかもしれません。
もちろん、上記は当時の日本写真界に限定しての話であって、同時期のドイツやアメリカ等の美術界で同様の図式として受け取られていたということではありませんので、注意が必要です。
12. 瀧口 修造(1903~1979)

『日本詩人全集』第6巻,創元社,1952.
撮影者:不明
瀧口修造(たきぐち・しゅうぞう)は、1903年に富山県富山市で生まれました。幼少期から文学や美術に強い関心を持ち、1921年に上京し、慶應義塾大学英文科に入学しました。大学在学中にはウィリアム・ブレイクやアルチュール・ランボーといった詩人に影響を受け、詩作を始めました。1926年には同人誌『山繭』を創刊し、詩人としての活動を本格化させました。
瀧口はシュルレアリスム(超現実主義)の熱心な支持者であり、前衛的な詩誌『詩と詩論』『衣裳の太陽』の創刊に関わったほか、1930年にアンドレ・ブルトンの『超現実主義と絵画』の翻訳を行い、当時の欧州の芸術運動を紹介する重要な役割を果たしました。
1931年に大学卒業し、東宝の前身にあたるピー・シー・エル映画製作所に勤務した後、日本大学芸術科の教壇に立ちます。この間に美術評論や詩を発表し、1937年には詩人の山中散生とともに「海外超現実主義作品展」を企画し、銀座の日本サロンで東京展が開催します(その後、京都、大阪、名古屋、金沢を巡回)。この作品展では海外のシュルレアリスム作品や資料を多数展示され、出品作家には、マックス・エルンスト、パブロ・ピカソ、ハンス・ベルメール、ルネ・マグリット、マン・レイ等の当時すでに名声を得ていた錚々たる名前が並んでいます。この作品展は当時の写真家にも大きく影響を与え、作品展の直後はマン・レイに影響された作品が流行しました。
1938年、瀧口は永田一脩、奈良原弘らとともに「前衛写真協会」を設立し、写真の新しい表現方法を追求しました。
1930年代はじめに大きなうねりを生んだ新興写真運動も、30年代半ばには落ち着きを見せており、その技法の多くもすでに大衆化していて目新しいものではなくなっていました。そんな中で、瀧口らはより新しい写真の方向性としてシュルレアリスムの理念を取り入れた「前衛写真」を提示したのです。
とはいえ、つねに新しさを求める前衛という立場ゆえではありますが、前衛写真には最初から明確な定義や輪郭がなく、なにがこのジャンルを指し示すのかわからない、一種の流行のような混乱した概念でした。このような混乱の反動として、次第に写真家たちは前衛写真を類型的にジャンル化していくようになり、徐々に形式を取り入れただけの作品が目立つようになります。作家の創造性ではなく、模倣作品によって前衛写真が縁取られていく状況を戒めるために、瀧口は同協会の名称を「写真造形研究会」と改めます。
写真評論の他に、1938年に主著『近代芸術』を出版するなど美術界に大きな影響を与えていた瀧口ですが、これらの活動が戦時下において特高警察から危険視され、1941年に「シュルレアリスム事件」として知られる出来事で逮捕されます。この事件は、シュルレアリスムと共産主義の関係を疑われたもので、福沢一郎とともに8ヶ月間拘束されました。この逮捕を契機として、前衛表現は大きな規制を受け、前衛写真協会の活動も収束を余儀なくされました。
戦後の1950年代に、オットー・シュタイネルトが「サブジェクティブ・フォトグラフ」を提唱すると、この動向は日本でも紹介され、「主観主義写真」として知られるようになります。主観主義写真は、戦前の前衛写真の成果を引き継ぎながら、写真家の主観的視点を重視する潮流を生みます。1956年には「日本主観主義写真連盟」が創設され、瀧口修造や阿部展也、北代省三らが会員となりました。しかし、前衛写真協会が辿ったのと同様に、主観主義写真においても技法が次第に形式化していくようになり、この写真運動は1950年代末には勢いを失っていきました。瀧口が目指したシュルレアリスムと写真との接続と展開は、一部が後にコンポラ写真のムーブメントに継承されたものの、その後徐々に見られなくなっていきます。
瀧口は、晩年まで作家たちへの交流や支援を惜しまず、赤瀬川原平の「千円札裁判」では特別弁護人として立ち会ったほか、60年代に起きたアングラ文化に注目して、土方巽の暗黒舞踏や唐十郎らの状況劇場などの観劇に訪れました。国内外の芸術家と交流し、文化創生を行った彼の功績は現在にもつながっています。
瀧口修造「写真と超現実主義」『フォトタイムス』15(2),フォトタイムス社,1938.
瀧口における、シュルレアリスムと写真の関連性については以下の引用を参照。
「読者がひょっとして持たれるかも知れない誤解の一つを解いておきたいと思う。というのは、写真とは文字通り現実をうつすものであるから、写真の超現実主義というのは、故意に原画を歪曲したり、切り抜いたりすることで終止するものではないという考え方である。これはまた、写真とはかならず現実をありのままに再現するものだというふうな素朴な誤謬にも相通じるものである。この意味で超現実主義とは必ずしも実在を破壊加工するものではない。日常現実のふかい襞のかげに秘んでいる美を見出すことであり、無意識のうちに飛び去る現象を眼前にスナップすることである。一体、不思議な感動というものは、対象が、極度に非現実であり、しかも同じほど現実的であるという、一種の同時感ではないだろうか?
だから、我々にはニュース映画、科学映画の一コマに、アマチュアのスナップの中に、素晴らしい超現実的な写真を発見したとしても、それは当然である。……超現実性におけるこのような遍在性と日常性とは、写真というものによって、もっと理想的に説明されるのである。」「シュルレアリスム」という言葉は、「超現実主義」と訳されるため、しばしば「現実を超えた」世界(たとえばファンタジックなものやグロテスクなもの)を表現するのだと誤解されがちです。しかし、実際のシュルレアリスムは、現実を「超越」するという意味ではなく、現実をより深く突き詰め、その本質を凝縮した「強烈な現実」を表現することを指します。瀧口の上記の文章もそういった前提にたつと理解しやすいかも知れません。「日常現実のふかい襞のかげに秘んでいる美を見出」し、理性/意識の間隙にある「無意識のうちに飛び去る現象」を、私たちの暮らす現実世界から発見して取り出してみること。見えてはいないけれど、この世界に確かに存在するもの/存在しうるもの(超現実性における遍在性と日常性)を可視化しようとする試みが写真というわけです。
戦前の前衛写真の代表例として
13. 木村 伊兵衛(1901~1974)
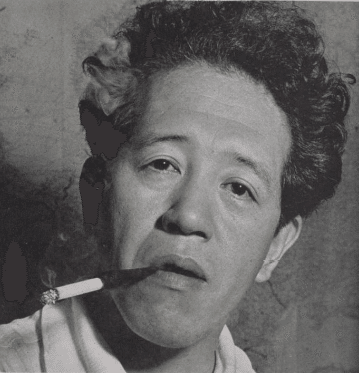
『寫眞文化』23(秋季特別増大號)(4),アルス,1941.
撮影:三木淳
木村伊兵衛(きむら・いへえ)は1901年に東京の台東区下谷に生まれた。9歳の時に荒川区東日暮里に移り住み、そこで生涯を過ごします。東日暮里の地域は職人的な雰囲気を色濃く残す場所で、木村の父親も組紐や帯締めの職人を抱えて商売を営んでいた。木村はこうした環境の中で育ち、多様な人々の日常や伝統的な江戸の気風を観察し、その影響を受けました(対談を読むと、木村は江戸っ子らしく、べらんめぇ口調で話しています)。
1920年、木村は砂糖問屋の安部幸兵衛商店に就職し、日本統治下にあって製糖事業が急拡大していた台湾の台南支店に勤めます。勤め先の台南で、木村は遠藤写真館の主人と知り合い、働きながらで営業写真の技術を学び1923年に帰国します(台湾では芸者遊びも相当だったそうです)。その後、関東大震災を経た1924年に、東日暮里で潰れた住居跡を改築し写真館を開きます。しばらくは営業写真師として働いていた木村ですが、そんな彼の本格的な転機は1929年、ライカⅠAとの出会いにあります。当時最先端のカメラであったライカは、より簡便に様々な撮影が可能とするもので、木村はこのカメラを生涯使い続け、後に「ライカの名手」と呼ばれるようになります。
1925年にドイツで発売されたライカ・カメラは、映画用の35ミリロールフィルムをスチール写真撮影に使用することで、写真機を大幅に小型化し、連続撮影を容易にしました。このカメラが1926年には日本にも輸入され、1930年代初頭には木村伊兵衛を含む若手写真家がこの機材を活用して注目を集めました。ライカを手にしてからもいくつかのカメラを試していた木村ですが、1933年に日本工房主催の個展「ライカによる文芸家肖像写真展」を開催する頃には「ライカが自分の仕事に一番しっくりきていた」(Kimura,1938.)と述べています。
ライカとの出会いの後、1930年に長瀬商会(現:花王)の広告部に入社した木村は、商品撮影のほか、工場での生産風景や労働者、一般庶民なども撮影して回ります。当時の花王は1927年に2代目に社長が代替わりするタイミングで、社風を大きく刷新しようとしていました。その一環として「花王石鹸」のリニューアル計画や、広告部の新設のほか、価格を大幅に引き下げ宣伝対象を広く庶民へ拡大しようとしていました。そんな中で、木村は大衆に訴えかける広告写真を求められます。撮影に際して、最初は大型カメラを用いていましたが、次第にライカの機動性がこのモチーフに合うとして、スナップを用いた広告撮影にスタイルを変えていくことになります。
広告の仕事をこなすなか、1931年の独逸国際移動写真展をみて大きな衝撃を受けた木村は「報道写真」の道に進むことを決意します。その勢いのままに、花王に在籍中の1932年に野島康三、中山岩太とともに『光画』を創刊し、リアリズム写真を誌面で発表していきます。
ちょうどその頃ドイツから帰国した名取洋之助と知り合い、1933年に日本工房を立ち上げ、このときに、木村は、名取からドイツ仕込みの報道写真の技法や、組写真(フォト・ストーリー)について学ぶことになります。そこでの成果は、1933年開催の文芸家肖像写真展で遺憾なく発揮されます。それまでの肖像写真は、写真館などで大型カメラを用いるもので、人物の説明のための写真という向きが一般的でした。木村はそういった旧弊な肖像写真ではない、報道写真の要素を加えた肖像の作成を目指しました。写された人の性格や感情の動きまでが分かるようなイメージを求めて、ライカを手に持ちながら、自然なポージングのポートレートを制作していきます。
その後、企業色を強めようとする名取(夫婦)と意見の合わなくなった木村や伊奈信男らは日本工房を脱退し、中央工房と国際報道写真協会を立ち上げます。国際報道写真協会では外務省の後援の下、対外宣伝のための写真制作に取り組み。特に1937年から1938年にかけては南京事件直後の南京・上海へ赴むき、「今迄外国の新聞や雑誌で支那側のひどい抗日宣伝写真ばかり出しているので本当の日本人はこういうような事で戦をしているとか、こういふ文化施設に対しては爆撃をしないとか、実際戦争をして居るけれども、戦争に無関係の支那の人とはこれだけ平和に暮しているとかそういったような事を、日本から有りの儘の写真と映画で外国に送る」ためにと述べて、プロパガンダ写真の撮影を実施しています(『カメラ』,1938.)。なお、映像班として同じく南京での撮影に赴いた白井茂によれば現地はまだ屍臭がたちこめている状況だったそうです(白井,1983.)。
1941年には国際報道写真協会は東方社に改まり、対外宣伝誌『FRONT』の発行を1945年まで行います。木村は、東方社で写真部の責任者として活動します(東方社の同僚だった濱谷浩によれば、当時、木村は周囲から腹黒いと思われて「ブラックポンポン」とあだ名されていた)。
戦後、木村は占領下の東京で再びカメラを手に取り、1946年には『東京一九四五年・秋』を刊行します。この写真集では、占領軍の様子や東京の復興の様子を写し出し、占領軍と日本人の融和を表現しています。そのすぐ後に、サン・ニュース・フォト社に入り、名取が立ち上げたグラフ誌『週刊サンニュース』の制作に携わるなどしますが、1949年には廃刊。生計を立てるために、当時活況となっていた雑誌グラビアをよく撮影するようになります。木村は美人写真を撮ることで当時から定評がありましたが、当の本人は「報道写真の方を空念仏にしてしまった」と反省しています。その後、秋田県での写真審査の依頼のために20年ぶりに農村に赴くことになり、これが転機となり、「秋田」シリーズに代表されるドキュメンタルな写真制作を行います。
後年は、ベトナム戦争の激しくなる1963年に設立された「リアリズム写真集団」に、1966年に顧問として就任。また日中友好化にも尽力しており、1956年に川端康成、谷崎潤一郎、梅原龍三郎などとともに日中文化交流協会を設立して以来、訪中撮影団の代表として1963年、1964年、1965年、1971年、1973年の計5回中国各地方を訪れ撮影しています。
木村の死後、渡部勉は木村について「社会的、政治的な問題に取り組んで告発していくという姿勢は、木村さんの中には体質的にもなかった」と評しています(『アサヒカメラ』1975年6月号)。この評価は、しばしばライバルとされた土門拳と比較すると際立ちます。土門が社会的問題に正面から取り組んだのに対し、木村は日常生活の細部を写すことに重点を置いていました。戦時中の作品でさえ、戦前・戦後と同様に「日常性」を軸に撮り続けたことは、彼のスタイルの最大の特徴と言えるでしょう。
とはいえ、「秋田」や「中国」といった題材からも分かるように、木村は社会・政治問題に取り組んでこなかったわけではありません。土門とは全く異なるアプローチで問題と関わろうとしていたのです。
Ihee Kimura『Japan through a Leica : 100 glimpses: sceneries, life and art』,The Sanseido,1938.
『木村伊兵衛写真全集昭和時代』
14. 山沢 栄子(1899~1995)
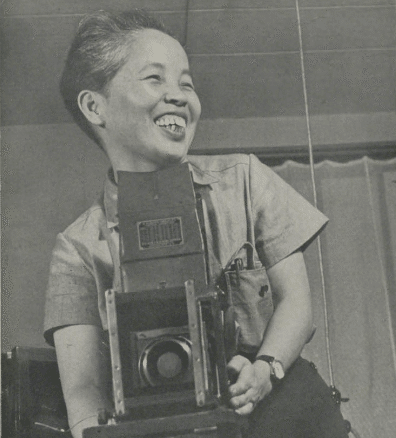
『フォトタイムス』17(10),フォトタイムス社,1940.
撮影:土門拳
山沢栄子(やまざわ・えいこ)は1899年、大阪の鉄工所の経営者の娘として生まれました。彼女は、早くからアーティストとしての道を志し、1916年に東京の女子美術学校(現:女子美術大学)の日本画科選科に入学します。在学中は日本画を学びつつ、独学で写真の勉強もはじめています。1918年に学校を卒業したのち、地元の大阪に戻り絵を描き続けていた山沢は、この頃にキリスト教会との関わりを深め、大阪YMCA(キリスト教青年会)で英語のレッスンを受けます。その後、YMCA会員たちの金銭的支援により27歳で渡米する機会を得ます。
米カリフォルニアに渡った山沢はCalifornia School of Fine Artsに入学しますが、その直後に父親が亡くなり、学費や生活費のためのアルバイトを余儀なくされます。そんな職探し折に、カメラショップの店主との偶然の出会いを通じて、ポートレート写真家として活動していたコンスエロ・カナガと出会い、彼女の助手として働くことになります。1927年12月にアートスクールでの学業を終えた後は、カナガのはからいでHarper's Bazaarのお抱え写真家であったニコラス・マレーのもとでレタッチの仕事もしています。
1929年、大阪に帰郷し、カナガから贈られたグラフレックスカメラやその他の機材を使ってプロの写真家としての仕事を始めました。絵画の道から始まった彼女の芸術活動ですが、父の死後に母を経済的に支える必要があったことや、アメリカでの経験から写真を芸術形式として捉えるようになったこともあり、「写真家」としての活動に専念することになります。
その後、1931年に大阪中之島付近にある堂ビル3F(現:堂島ビルヂング)に自身の写真スタジオを開設する機会を得た山沢は、当時の関西財界人のポートレート等を多く撮影しました。同じころ、山沢は現在の天満駅付近に構えていた個人スタジオ(山沢写真場)では写真グループ「大阪婦人写真クラブ」を立ち上げ、当時としてはまだ少なかった女性アマチュア写真家のための活動の場を主催しています(同クラブは1931年11月に中之島朝日会館で展覧会を開き、その後も活動を続けた)。また、堂ビル女学院で知られるように、堂ビルには当時の大阪で最大規模の女性教育機関が備わっており、山沢は女学校の撮影の仕事も多く行っていました。
1935年、大阪の心斎橋にある大阪十合ビル(そごう百貨店)が開店すると、当時そごうの代表を勤めていた木水氏が彼女の個展を見ていた縁もあり移転するよう招待されます。写真スタジオを移転しました頃には、彼女は著名な職業婦人として知られるようになり、雑誌『輝ク』や『婦人画報』にエッセイを執筆しています。
デパートでの撮影を続けていた彼女ですが、「デパートの写真部は撮影よりも政治的な立ち回りのほうが主要な仕事だった」とウンザリして、1938年には職を辞し。その後、新しくスタジオを立ち上げて独立をします。
あいにく戦災によってスタジオは焼けてしまい、戦後は京都で進駐軍のPX(軍営デパート)のスタジオカメラマンとして又デパートに戻ることになりますが、1952年には大阪そごう百貨店の屋上に写真スタジオを開設し、再びの独立をします。
そごう百貨店に居を構える少し前、1950年には若い女性写真家を養成するため山沢写真研究会を立ち上げています。戦前からそうであったように、彼女は自身のスタジオには積極的に女性のアシスタントを起用していました。当時(あるいは現代も)、男性の仕事として見られがちな写真業において、山沢の姿勢は特出していたと言えるでしょう。
1962年、63歳の彼女は営業写真家としての仕事を全て終わりにしスタジオを閉じます。写したいものだけを写すための生活をすると決心した山沢は、この頃に写真集『遠近』を出版します。ニューヨーク時代の写真や抽象写真など、彼女の今までとこれからをまとめたような写真集からは、彼女がつねに新しいイメージを追いかけてきた、ストイックな写真への姿勢が感じ取られます。
「カメラは何でも写してしまいますが、写らなければ良いのにと思います。本当のものしか写らなかったら、どんなにすばらしいことでしょう」と述べた彼女は、その後、抽象的な心象表現を写真で再現する前衛写真的なスタイルに大きく転向し、最晩年まで写真を取り続けます。
デートン・ミラー ほか『火花・稲妻・宇宙線 : 電気学の今昔』,三省堂,1943.
山沢が心斎橋にスタジオを構えていた時代のクライアントワーク。山沢のスタジオに所属していた中村ふじ、河野花が撮影を担当。
山沢のインタビューが掲載。
15. 安井 仲治(1903~1942)

『寫眞文化』24(5),アルス,1942.
撮影者:不明
安井仲治(やすい・なかじ)は、1903年に安井園治郎の長男として生まれます。その後、圓治郎の兄で、大阪 中之島付近で安井洋紙店を営む安井仲蔵に跡取りとして養子に迎えられ、そのまま安井洋紙店に入社します。入社後、1925年には伯父の後任を務めるかたちで監査役に就任し、1938年には取締役になっています(彼が紙商としての活動をどこまで熱心に行ったかは定かではありません)。仲治が亡くなった後、洋紙店は仲蔵から圓治郎へ継がれ、現在も屋号を変えずに大阪阿倍野で営業を続けています。
裕福な家庭で育った仲治は、10代の頃から写真に熱心に取り組んでおり、1921年に大阪明星商業高校を卒業したのちに、友人たちと回覧同人誌『AMITIE』を発行していました。
1922年の春には家族と共に東京の平和記念東京博覧会を訪れ、その際に撮影した写真《分離派の建築と其周囲》が、同時期に彼が入会した浪華写真倶楽部でのデビュー作となりました。
《分離派の建築と其周囲》がそうであるように、仲治の初期作は芸術写真の様式を踏襲しています。仲治がこの作品を公開した1922年7月の少し前、1922年4月に福原信三ら率いる写真芸術社が、大阪ではじめての展覧会を開催し、そこで提示された「光とその諧調」は関西のアマチュア写真家たちに画風に大きな影響を与えました。仲治の初期作にみられる芸術写真の様式も福原に影響を受けてのものかも知れません(仲治の死後にひらかれた座談会で、上田備山は、仲治が福原信三のことを「絶対支持」していたと語っています)。
1922年に浪華写真倶楽部に入会した後、研展などの写真展で繰り返し入選を果たし、彼は浪華写真倶楽部の代表的なメンバーとなりました。1927年秋には「銀鈴社」を結成し、1930年には「丹平写真倶楽部」に参加します。
1930年代には、新興写真が台頭し、安井もその一員として活動しました。都市を対象としたストレートな写真や報道写真、フォトモンタージュ、その場にある静物(モチーフ)に少し演出を加えた「半静物」写真、そして30年代には時代遅れになりつつあったブロムオイル印画など。この頃の彼の作風は非常に多岐にわたります。
安井の制作活動は戦時中も続き、1941年には「流氓ユダヤ」シリーズとして、リトアニアから神戸に逃れてきたユダヤ難民を撮影しました。このシリーズは、杉原千畝が発行した通過ビザにより、ポーランド系ユダヤ人難民が神戸に一時滞在していた様子を捉えたものです。安井は丹平写真倶楽部の仲間と共に、この難民たちの生活や表情を写真に収めました。このシリーズは報道写真的な側面を持ちながらも、安井の独特の美的感覚を感じさせるものであり、当時のユダヤ難民の状況をリアルに伝えています。
1941年の夏、腎臓に問題があることが判明し、その後は自宅で静養する生活を送っていましたが、無理を押して同年10月に「写真の発達とその芸術的諸相」という講演を行います。安井にとってはこれが公に出た最後の活動となりました。同年12月には神戸市の甲南病院に入院し、1942年に腎不全のため38歳の若さで亡くなりました。
亡くなる少し前、写真への統制が厳しくなる中で、安井は『写真文化』誌の編集をしていた石津良介に以下のように語ったといいます。
「これからどんな世の中になっても、写真文化の灯は、たとえどんなに小さい灯でもよいのです。この灯だけは消さないで下さいね。頼みましたよ。」
『寫眞文化』23(秋季特別増大號)(4),アルス,1941.
「彷徨よえる猶太人」1,5
16. 小石 清(1908~1957)

『報道寫眞』2(12),寫眞協會,1942.
撮影者:不明
小石清(こいし・きよし)は高級雑貨商の家系に育った影響もあり、早くからカメラに興味を持ち、彼は高等小学校を卒業後、浅沼商会大阪支店に入社し、写真技術を学びました。20歳頃には安井仲治を始め上田備山や米谷紅浪らが在籍していた浪華写真倶楽部に入会し、1931年には大阪に自身のスタジオを開設し独立しました。30年代前半の頃から浪華写真倶楽部の展示で頭角を現し、1933年には小石唯一の写真集である『初夏神経』を出版しています。
『初夏神経』では、多重露光、フォトグラム、ソラリゼーションといった技術を駆使しているほか、自作の詩と写真とのコラボレーションによって心的表象を写真に組み込むといった前衛表現を取り入れており、新興写真の一つの到達点として現在では評価されています。小石の表現は当時からすでに大きな反響を集めていましたが、一方では「表現は再び写真術の本質を離れ、独善的な主観世界に立戻ったものと見るしかない」といったややネガティブな受け止めもありました。
その後は、彼は広告写真も手掛け、クラブ石鹸の広告や鉄道省の宣伝写真などを手掛けています。1936年には自身の技術をまとめた解説書『撮影・作画の新技法』を発表しています。
1938年、小石は日本政府の情報誌『写真週報』のために、日中戦争の従軍写真家として中国に派遣されました。従軍写真家として赴いた際に撮影された写真をまとめた『半世界』(1940年)という連作を制作し、戦争のリアルな側面を前衛的な手法で表現しました。戦時中、小石の前衛的な手法は制約を受ける場面もありましたが、それでも彼は中国で多くの現地住民を撮影し、その写真を『南支人の相貌』として発表しています。
戦後、小石は福岡県門司市(現:北九州市門司区)に移り、門司駅付近で「小石カメラ」というカメラ店を開業しました。彼は門司鉄道管理局の嘱託としても活動を続けましたが、写真家としての創作活動は減少していました。
その後、1957年に小石は門司駅で転倒し頭を打ったことが原因で亡くなりました。
17. 石川 光陽(1904~1989)
石川光陽(いしかわ・こうよう)は、1904年、福井県で父竹次郎とその妻とくの間に生まれました。幼少期は国鉄に勤めていた父親の仕事の関係で福井、沼津、松本と各地を転々としました。1919年、松本駅長を最後に退職した父親が写真館を開きたいといったため、光陽はこれに付き合う形で、当時通っていた東京薬学校(現:東京薬科大学)を中退し、東京九段下の蜂谷写真館で修行を積むことになります。その後、松本で父親とともに写真館を開業しましたが、1924年に父親が亡くなり、翌年徴兵され、朝鮮の歩兵第80連隊に配属されました。
徴兵期間を終えた光陽は、東京の親戚のもとに居候していましたが、知り合いの警察官のすすめもあり、1927年に警視庁に入庁しました。警視庁では写真撮影を担当することが多く、1936年の二・二六事件では決死の思いで警視庁中庭に待機していた兵士たちを撮影しました。1942年のドーリットル空襲の際には、警視総監から空襲の記録写真を撮影するよう直々に命じられ、非常に危険な任務を遂行しました。当時は「言論出版集会結社等臨時取締法」の統制により、来襲の報道こそありましたが、被害状況の詳細は伏せられており、光陽の写真も一般に公開されることはなかったものと見られます。
石川光陽の最も知られている業績の一つは、1945年3月10日の東京大空襲の際の記録写真です。この空襲の惨状を33枚の写真に残し、その前後の空襲も含めて600枚以上の記録写真を撮影しました。当時、一般市民が空襲の被災現場を撮影することは禁じられており、光陽の写真は貴重な記録となりました。
敗戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、日本側の空襲被害の状況を精査するため、光陽に空襲被害のネガを提出するよう命じました。しかし、彼はこれを拒否し、ネガを自宅の庭に埋めて保存しました。GHQは最終的に写真のプリントの提出で妥協します。この光陽の行動によって、東京大空襲の惨状を視覚的に後世に残すことができました。
なお、空襲に関する写真は、当時東方社で『FRONT』の制作に関わっていた菊池俊吉によるものなど、複数の記録が現存しています。
光陽は戦後も警察官として活躍し、1963年に退職。1989年に85歳で亡くなりました。
雄鶏社編集部 編『東京大空襲秘録写真集』,雄鶏社,1953.
石川のほか、朝日新聞社,読売新聞社,日本観光写真映画社,影山光洋, U・S・Army photoが寫眞を提供している。
東京12チャンネル社会教養部 編 「東京大空襲・死者八万人」『新編私の昭和史』1 (暗い夜の記憶),学芸書林,1974.
18. 田淵 行男(1905~1989)

『世界写真全集』第5巻 (日本),平凡社,1956.
撮影者:不明
田淵行男(1905年-1989年)は、日本の著名な写真家であり昆虫研究者でもありました。鳥取県日野郡黒坂村(現在の日野町)で生まれた彼は、自然と山岳風景への深い愛情を抱き続けました。
田淵は、幼少期から自然に対する興味を持ち、特に蝶の観察に没頭しました。1923年頃から蝶の細密画を描き始め、1924年に東京高等師範学校博物科(現:筑波大学)に入学し、特待生として自然科学を学びました。その後、富山県や都内で教職に就きつつ、昆虫研究と山岳写真の撮影を続けました。1930年代には、北アルプスへの集団登山を生徒たちと共に行い、その美しい風景をカメラに収めることに情熱を注ぎました。
田淵の写真は、自然の美しさを捉えるだけでなく、その背後にある科学的な観察をも反映しています。特に、高山蝶の生態に関する彼の研究は、彼が「安曇野のファーブル」と称される所以でもあります。彼の研究は、北アルプスの生態系や生物多様性に関する深い洞察を提供し、多くの著作や写真集として結実しました。
1950年代には、彼の写真は『アサヒカメラ』などの主要な雑誌に掲載され、広く注目を集めました。1951年に発表された『田淵行男 山岳写真傑作集』は、彼の代表作の一つとして知られています。
1980年代に入ると、田淵はパーキンソン病と診断されましたが、それでも創作活動を続け、多くの著作をまとめ上げました。1989年に彼が亡くなるまで、彼の情熱と努力は衰えることがありませんでした。彼の遺産は、長野県安曇野市にある田淵行男記念館で保管されており、彼の作品や研究成果は次世代に受け継がれています。
田淵行男の功績は、単に写真家や研究者としての枠に収まらず、自然への深い愛情と科学的好奇心を持ち続けた一生として語り継がれています。彼の作品は、自然の美しさとその保護の重要性を訴え続けるメッセージとして、今なお多くの人々に感動を与えています。
19. 入江 泰吉(1905~1992)
入江泰吉(いりえ・たいきち)は1905年、奈良市片原町に生まれました。彼の家庭は裕福ではありませんでしたが、芸術への愛好が深く、父は古美術品の鑑定で生計を立てていました。幼少期から母に連れられて東大寺二月堂に詣で、仏教や奈良の文化に触れる機会が多く、これが後の作品に影響を与えました。入江は奈良第二尋常小学校や奈良女子高等師範学校附属小学校で学び、図画工作が得意でしたが、兄からベス単を譲り受けたことをキッカケに写真に興味を持つようになりました。
1925年、大阪の写真機器卸商に就職し、写真技術を磨きました。その後、独立して写真機材店「光芸社」を設立し、広告写真や記録写真を手がけました。この時期に文楽人形の魅力に惹かれ、文楽座に通い詰めて黄金期の文楽を撮影し、その作品は高く評価されました。
1945年の大阪大空襲で家を失った入江は奈良に戻ります。奈良で終戦を迎えた入江は、東大寺法華堂の堂守らから「アメリカが賠償金の代わりとして日本の古美術を持ち帰る」といった噂を耳にして、奈良の仏像をできるだけ記録することを決意します。闇市で揃えた機材で戒壇院の四天王像から撮りはじめた入江ですが、後にその噂は単なるデマだったと知ることになります。
戦後は、奈良の風景や仏像の写真を中心に撮影し続け、「大和路」をテーマにした作品で知られるようになりました。モノクロ写真にこだわっていましたが、1957年からカラー写真にも挑戦し、独自の色彩表現を模索しました。
入江は、浪速短期大学の教授として後進の指導にも力を注ぎました。1976年には、写真集『古色大和路』『万葉大和路』『花大和』の三部作で菊池寛賞を受賞しました。1992年に亡くなるまで、奈良の美を追求し続けました。
『入江泰吉写真全集』
20. 石津 良介(1907~1986)

『カメラ』(9),アルス,1949.
撮影者:植田正治
石津良介(いしず・りょうすけ)は1907年、岡山県岡山市に生まれました。彼は老舗紙問屋「紙石津」の長男として育ちましたが、家業を継ぐことを拒否し、映画のシナリオ作家を目指して東京へ上京します。上京後は慶応大学に入学しますが、松竹映画の蒲田撮影所に毎日のように通ってシナリオ修行をしていた彼は、大学生活を疎かにしてしまい1932年に中退することになります。
中退の後は地元岡山に帰り、父親の縁故で郵便局に就職し、翌1933年には長女をもうけます。石津の写真との出会いはこの頃です。地元の書店で見かけた写真雑誌が気になり、「これくらいなら自分だって」と思って二眼レフのローライコードを購入します。
1934年、石津は岡山在住の写真家・大森一夫、山崎治雄らと共に「光ト影の会」を結成しました。この会は、岡山県における本格的な写真クラブとしては初めてのもので、若い写真家たちに影響を与えました(後年に岡山県知事となる長野士郎も石津に憧れて参加しています)。
しかし、
石津らによる写真作品はその頃には写真雑誌の口絵に掲載されるなどしていましたが、一方では、大都市の写真家たちと自分たちとを比べたときに「一生涯その地方での有名作家で終わってしまう。そんな運命を背負っていた」と、地方写真家の苦悩も抱えていました。
「いくらわれわれが地方で頑張ってみても、所詮は犬の遠吠え、地方の土豪が田舎で暴れているようなもの。…中略…われわれ地方作家がお互いに相手をライバル視して、足の引っ張り合いをしていても始まらぬ。それより同じ悩みを抱えている同士なら、いっそこの辺で一緒に集まって、束になって花のお江戸になぐり込みをかけようではないか。」
そんな心意気に心を打たれた植田正治、緑川洋一、野村秋良、正岡国男などの写真家が参加する形で、1937年には「光ト影の会」を「中国写真家集団」に発展し、中国地方の写真家たちが参加する組織として毎年東京で展覧会を開催しました。
1938年、石津はアルス社の高桑勝雄から声をかけられ、雑誌『カメラ』の編集者に転職し、一家ともども上京して吉祥寺に居を構えます。同誌では「作家訪問記」を企画担当し、安井仲治や評論家の伊藤逸平、桑原甲子雄らと交流を深めたほか、当時まだ無名だった土門拳を紹介するなど、新進気鋭の写真家を支援しました。
その後『カメラ』は戦時下の雑誌統廃合により、1941年に『写真文化』となり、1943年には題名の"文化"という文字も許されず『写真科学』と改題されます。
日中戦争の開戦後に組織された内閣情報部主導のもと、出版業界に対する規制は徐々に強まり、1938年には婦人誌の内容を規制する「雑誌浄化運動」が、1939年からは用紙節約と警世の目的で雑誌の統廃合がはじまります。1941年には、内閣情報部や警視庁などの決定により、趣味誌は大規模に統廃合され、当時11誌あった写真雑誌は4誌にまで減ります。こういったなかで『カメラ』・『カメラクラブ』・『写真サロン』が統合され『写真文化』が創刊されました。
太平洋戦争の開戦後は、写真芸術を称揚するものは時代とそぐわなくなり、記録的なものやルポルタージュが良しとされていきます。また、隣組や警察による防諜活動が活発になり、街でスナップ撮影することや、田舎での風景の撮影が難しくなったため、写真雑誌の口絵はポートレートや子供を題材とした家庭写真が中心になりました。
戦時下において印刷用紙やフィルムが配給制となり、国策に追従しなければならなかった状況を戦後に振り返って、石津は「日本が勝つか敗けるか、ではなくて、いつ雑誌がつぶされるかの瀬戸際にたっての、苦し紛れの闘いだった」と述べています。
表現の制限された状況で、石津は伝統文化を切り取った民俗写真を大きく取り上げ、厳しい時局の中で可能な表現を模索しています。
その後、石津は『写真文化』誌が改題される1943年に編集の職を辞します。同年、石津は中国に渡り、加藤恭平、林忠彦、大竹省二らと在北京日本大使館の外郭団体として「華北弘報写真協会」を設立し、日本の宣伝写真を撮影しました。
北京で終戦を迎えた石津は翌年に復員し、岡山市内で緑川洋一と写真工房を開設しました。その後、東京で秋山庄太郎や林忠彦らと共に「銀龍社」を結成し、再び岡山での活動を中心に据えました。
1960年代には、小豆島にも足繁く通い、現地での写真展を開催します。また、岡山県高梁市での新成羽川ダムの造成に際し、高梁川流域に住む住民の暮らしぶりを後世に残すために、共同制作による記録を企画します。当時は一つの写真プロジェクトを複数人で行うような制作方式は大変珍しく、先駆的なプロジェクトでした。
晩年、石津は自ら写真撮影を行うよりも後進の育成やアマチュア写真家の指導に尽力し、地元岡山で78歳のときに亡くなります。
『風景写真の実際』(写真実技大講座 第5巻),玄光社,1937.
当時の防諜に関する撮影制限については上記が詳しい。
21. 堀野 正雄(1907~1998)
堀野正雄(ほりの・まさお)は、東京市京橋区木挽町(現東京都中央区銀座)に生まれ、幼少期から写真に興味を持ち始めました。特に、父親がアマチュア写真家であったことが、彼の写真家としての道を開く一因となりました。
1923年、堀野は東京・赤坂の演技座で行われた高田雅夫の舞踊公演を撮影し、それを高田に見せたところ写真のできを賞賛され、この縁で、同舞踊団の撮影を続けることになりました。1924年には東京高等工業学校(現東京工業大学)応用化学科に入学、卒業後の1927年、彼は築地小劇場の舞台撮影を中心にした個展を開き、以後、写真家としての活動を本格化させていきます。
堀野は1929年に村山知義らと「国際光画協会」を設立に参加し、写真を社会の生きた姿を正確かつ迅速に伝える手段として位置づけました。翌年には、新興写真研究会に参加し、板垣鷹穂の指導のもと、機械美術をテーマにした作品制作を行いました。板垣の「機械芸術論」に触発された堀野は、それまで注目されてこなかった機械的構造物(ガスタンクや鉄橋など)の美的側面を探求し、『カメラ・眼×鉄・構成』(1932年)という写真集にその成果をまとめます。
1930年代、堀野は都市光景の断片を繋ぎ合わせた、グラフ・モンタージュを試みました。「大東京の性格」や「首都貫流―隅田川アルバム」などの作品を通じて、社会派ドキュメンタリーの新たな可能性を模索します。
1933年には『婦人画報』の嘱託カメラマンとなり、以後、女性のモード写真や広告写真、報道写真を数多く手掛けます。この時期には欧米のファッション写真について堀野はよく研究しており、とくに、マーティン・ムンカッチのようなスナップ的なファッション写真を意識した写真が多く残っています。ファッションアイテムをどう引き立てるのか、服の皺はこれでいいのかなど…フ衣装のの細部に気を払って撮影をする彼のスタイルは、「女性の写真」ではなく、あくまで「ファッションの写真」を目指したもので、当時の日本においては斬新なものでした。ストレートな表現で洋裁を着こなす「モダンな女性」の表現しようとした点を踏まえて、「堀野正雄は間違いなく⽇本のファッション写真家の先駆け」であったと評されることもあります(細川,2018)。
1938年には朝鮮半島各地を取材し、1940 年には主婦の友社の特派員として南京へ派遣され、そのまま陸軍報道部嘱託となり上海で終戦を迎えました。その後は国民党系雑誌『改造畫報』写真部員として残留し活動します。帰国後の1948 年には体験的技術論と所感をまとめた『吾等の写真術』(六和商事出版部)を著していますが、戦後、堀野は徐々に写真家としての活動から距離を置き、1949年に株式会社ミニカム研究所を設立したのちは、写真用フラッシュやストロボの開発・製造に専念しました。
堀野の作品と彼の活動は、1980年代に再評価され、飯沢耕太郎や金子隆一によってその業績が再発見されましたが、それまではフラッシュメーカーのミニカムの所長が写真家の堀野正雄だとは余り知られていなかったそうです。
22. 渡辺 義雄 (1907~2000)

『世界写真全集』第5巻 (日本),平凡社,1956.
撮影者:不明
渡辺義雄(わたなべ・よしお)は1907年に新潟県南蒲原郡三条町(現・三条市)に生まれます。彼は呉服商の家庭に育ち、1920年に新潟県立三条中学校に入学すると父からコダックのポストカード判カメラを贈られ、これをきっかけに写真の道を歩み始めました。独学で現像や印画の技術を習得し、1925年に中学校を卒業後、東京の小西写真専門学校(後の東京工芸大学)に進学しました。
1928年に卒業した渡辺は、オリエンタル写真工業にエンジニアとして入社し、ここで乾板のテスト撮影などを担当しました。1930年には木村専一が結成した新興写真研究会に参加し、新しい写真表現である新即物主義に大きな影響を受けました。1931年には同社の宣伝部に異動し、『フォトタイムス』の編集や撮影に従事します。同誌では、日本におけるグラフ・ジャーナリズムの先駆けともいえる『カメラウワーク』と題する組写真のシリーズや、板垣鷹穂の示唆を受けて撮影した「御茶の水駅」を発表します。
1934年にオリエンタル写真工業を退社した後は、外務省の外郭団体である国際文化振興会や、中央工房の派生組織である国際報道写真協会に参加し、木村伊兵衛や名取洋之助と関係を深めます。
この頃は報道写真家としての活動が多くなり、鉄道省の委嘱による1937年のパリ万国博会出品の写真壁画「日本観光写真壁画」や、外務省の委嘱で木村伊兵衛らと取材した南京・上海での写真による「南京・上海報道写真展」、1942年に満州国をめぐりながら撮影した「満州国展」など、各種対外宣伝に携わります。
1940年に国際報道写真協会が解散となり、フリーになりますが、その後は出身校である東京写真専門学校の講師や日本報道写真協会の理事長などを歴任し、終戦を迎えます。
戦前は報道写真が多かった渡辺ですが、戦後は徐々に建築写真を中心に活動するようになります。代表的なものとしては、1953年に行われた伊勢神宮の第59回式年遷宮の撮影です。伊勢神宮は長らく撮影ができない神域とされており、渡辺が写真家として初めて内宮や外宮の撮影を許可されました。この後も伊勢神宮の撮影を継続し、1993年までに3回の式年遷宮を記録しています。
建築物を撮影するとき、渡辺は人と建物とのコミュニケーションの様子をおさめることが重要だと考えていました。寺社仏閣などの人の立ち入りの難しい場所、とりわけ神宮のような場所であっても、「神宮は、そこにおわします神に、人が祈り、感謝を捧げながら、神とのコミュニケーションを図ろうとするのである。その神と人との気持ちのやりとりと触れ合いの瞬間の空気を撮ることが大切だ」として、単に建物を紹介する以上のことを写真を通して行おうとしていました。
渡辺は日本写真家協会の設立に貢献し、1958年から1981年まで会長を務めました。また、金丸重嶺の誘いによって日本大学芸術学部写真学科で教鞭を執ったほか、写真の著作権保護のために日本写真著作者同盟の設立に携わるなど、後進の育成にも力を注ぎました。
また1978年発足の日本写真文化センター設立準備懇談会(のち日本写真美術館設立促進委員会と改称)の代表を務めるなど、写真の文化的価値の確立のためにも活動を続け、1990年に開館した東京都写真美術館の初代館長を務めています。
23. 影山 光洋(1907~1981)
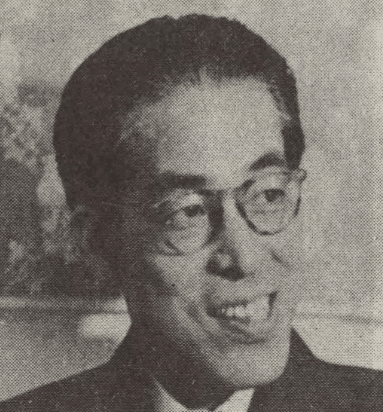
『世界写真全集』第5巻 (日本),平凡社,1956.
撮影者:不明
浜松生まれの影山光洋(かげやま・こうよう)は、戦前から戦後にかけての日本の社会情勢を鮮明に映し出しました。
影山の写真家としてキャリアは、浜松商業高校に入学した折に、母親にお祝いとして中古のベス単を買ってもらったことがキッカケといいます。浜松商業学校を卒業後は、上京して東京高等工芸学校(現・千葉大学)の写真科に進学します。田舎から上京して経済的に心もとなかった影山は、東京の日本橋でいとこが写真のレタッチ業を営んでいたので、その手伝いをして下宿代を稼ぎながら写真について学んだといいます。
1930年に卒業制作として発表した『東京百景』が朝日新聞社の当時の写真部長の目にとまり、そのまま無試験で朝日新聞社の写真部に入社します。
朝日新聞に入社後は、青森で娘を身売りした農家の取材するなど、報道写真家としてのキャリアを築いていきます。その後は、二・二六事件、南京陥落、シンガポールでの山下・パーシバル会談など、歴史的な事件を数多く記録したことで知られています。
緊迫した状況を高い正確性をもって切り取ることに長けた彼は、臨場感あふれる記録写真を多く残しており、二・二六事件の際には、建物を占拠していた部隊に一時捕縛されたものの、マフラーを巻いて隠し持っていたライカで、拳銃を構えて整列する将校たちを間近で撮影するなどしています。
戦時中、朝日新聞の従軍カメラマンや東部軍国防写真隊の班長を務め、内外地で多数の戦争写真を撮影してきた影山ですが、終戦は東京の自宅で迎えることになります。終戦間際の空襲で自宅に焼夷弾が直撃するなど、軍/民の両面で戦争を経験した彼は、有楽町の朝日新聞社屋で玉音放送を聞きます。
8月15日に写真部のデスク当番だった影山は社会部からの要請に応えて、部下のカメラマンに皇居前広場を撮影するように命じますが、部下は「ファインダーが(涙で)曇って撮れない」とすぐに帰ってきてしまいます。影山は「日本人だったらそんな写真は撮れやしない。撮れたって新聞にはのせられるものかと」思い、そのカメラマンに同情しますが、今度は二重橋前で軍人の割腹自殺騒ぎの知らせがあり、やむなく別の部下を皇居へと送ります。しかし、その部下も目を赤く腫らしてすぐに帰ってきてしまいます。仕方なく、影山自身が皇居へ向かいますが、玉砂利の前でうずくまって涙する人達をみて、結局1,2枚しか写真を撮ることはできず、すぐに会社へ引き返します。撮影した僅かな写真も現像することがどうしても躊躇われ、結果として朝日新聞は戦後初日の報道合戦で写真を掲載できず、他紙に遅れを取ることになります。影山はこのときの責任を取って辞表を提出して、朝日新聞社を退職。以後はフリーのカメラマンになります。
彼はその後、神奈川県藤沢市(鵠沼)に移り住み、急速に変わりゆく戦後日本の姿を追い続けました。
影山の作品は、戦後の日本の再建期の情景を捉えたものであり、その中でも特に評価が高いのが『芋っ子ヨッチャンの一生 五年二ヶ月涙の記録』という写真集です。この作品は、影山家の私的な日常を描いたもので、終戦後の食糧難の時代に育つ息子ヨッチャンの成長と栄養失調で亡くなるまでの短い生涯を記録しています。影山は戦前から戦後の時代を一身に受けて撮影し続けたカメラマンといえます。
24. 渡辺 勉(1908~1978)
渡辺勉(わたなべ・つとむ)は戦前は報道写真家として活動し、東方社に参加するなど、精力的に作品を発表していました。戦後は編集業や評論活動に軸足を移し、後述の『世界画報』の編集やアマチュア写真家たちに向けた啓蒙に力を注ぎます。彼の著作には『今日の写真・明日の写真』や、アサヒカメラ誌との企画によるインタビュー集の『現代の写真と写真家』などがあります。
戦中は、時局にふさわしくないとしてアマチュア写真家の活動(のとくに芸術・前衛写真)に対して否定的な意見が散見され、瀧口修造の逮捕など実力を伴った弾圧が行われました。渡辺はそういった状況において、耽美的な表現はあくまで「不健康」であって、遊戯性や贅沢性にまみれた誤った道だと前置きをしたうえで、そういった表現は「決してアマチュア写真家諸君の罪ではないと思います。それはやはり指導する側に誤った考え方があったため」であるとアマチュア写真家たちを擁護をしています。もちろん、時局に目配せするように「極めて優れた健康的慰安である写真趣味が、再検討を必要としているのは、過去の写真生活の中に、個人主義的な甘美な夢を貪り、健全な国民生活に沿はない要素があったがために、今日の時局が批判している」のだとも書き添えており。健康的な写真として、国家の思想や伝統文化の沿った内容を伝えるようなもの、とりわけ報道写真を称揚しています(ここでは、具体例として隣組での催し物等の組写真があげられています)。
こういった「写真文化を戦時統制のなかでどう残すか」という難問に対峙した渡辺は、「芸術家が国家を肯定する、ということは即ち、国民が芸術家に責任ある地位を付与しているということ」というゲッペルスの発言を引用しつつ、むしろ国家統制が写真文化を再出発させる良い機会となり、「写真文化の国民的普遍化」や「芸術的鑑賞眼の醇化」のために適切な統制は望ましいという方向性を示しました(より踏み込んで、「当局の判断に狂いがあったとしたら、カメラジャーナリズムは現状より尚文化的水準を低下してしまうであろう」と釘を刺すこともコメントしています)。
太平洋戦争の後、1946年にゾルゲ事件によって捕まった西園寺公一の執行猶予期間があけ、同氏の出資により『世界画報』が創刊されます。渡辺はこれに関わり、初代編集長を務めました。
雑誌の表紙や構成はアメリカ『ライフ』誌を意識して作られ、「戦争中は戦争や政治のことを知らされていなかった大衆に、現実のことを知らせ」ることをモットーに、戦争犯罪や民主化運動にまつわる記事を主軸に据えていました。七三一部隊を告発するために石井四郎への直撃インタビューをするなど、耳目を引く記事もありましたが、売り上げはあまり伸びず、安定した刊行をすることもついぞできませんでした。1950年5月号には「次号からは必らず定期刊行を厳守いたします」と編集室からの決意表明が掲載されましたが、資金繰りが上手くいかず同年にあえなく廃刊となっています。また、同誌には写真家の田村茂も参加しています。
その後、1975年からはじまった木村伊兵衛写真賞では第1回から選考委員を務めますが、1978年に胃がんで亡くなり、第4回までの任となりました。
晩年には、写真雑誌『アサヒカメラ』で写真批評を行い、その活動は多くの写真家や愛好者に影響を与えました。また、日本写真協会の理事としても活動し、日本の写真文化の普及と発展に寄与しました。
25. 土門 拳(1909~1990)
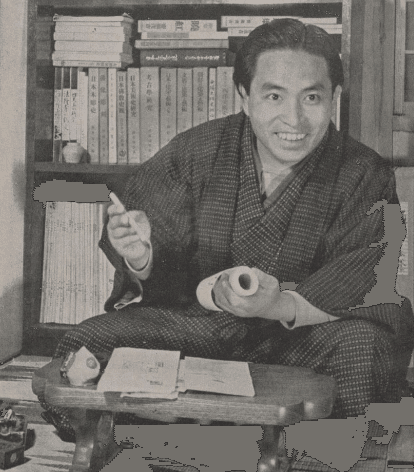
『寫眞文化』24(1),アルス,1942.
撮影:三木 淳
土門拳(どもん・けん)は1909年に山形県の酒田町(現・酒田市)で染物屋を営む家に生まれました。土門が山形で過ごしたのは6歳過ぎまでの頃で、1916年には一家ともども東京に移住し、その後は父親の仕事の都合で横浜に移り住み、1923年に旧神奈川県立第二横浜中学校(現:翠嵐高校)に入学します。
中学校では首席をとるなど秀才さを発揮した土門ですが、家が貧しかったために一時は退学しかけます。しかし、成績の良さや絵の才能を見込まれ、学費が免除となり1928年に無事卒業をすることができました。中学校時代は絵画や考古学に熱を上げていたほか、この頃に日本で盛り上がりをみせたダダ運動にも傾倒していました。
中学卒業から少し後、1931年頃からは左翼活動に接近し、共産党系の全国農民組合全国会議に所属します。彼はその積極的な活動ゆえ、この頃に複数回の逮捕をされ、拷問にかけられることもありました。
1932年、23歳のときに逮捕された折、彼は連日のように拷問を受け、ついにこれを耐えかねて「今後は共産党には近づかない」という誓約書を書くことになります。
その後、左翼活動から距離を置いた土門は、母親に「絵画好きの息子に合う仕事」として写真家になるようにすすめられます。写真家 宮内幸太郎の妻が親戚にいた縁もあり、土門は1933年に宮内の弟子となります。土門の写真家としてのキャリアはここからスタートします。
宮内の門下に入り営業写真を学ぶ土門は、レタッチ作業などを必要とする営業写真のスタイルに疑問を持ち、当時すでに定着しだしていた新興写真に惹かれるようになります。宮内写真館に収蔵されていたカメラ誌や、丸善の洋書コーナーで立ち読みした輸入写真集に刺激を受けた土門は、この頃にドイツ語の学んだり、『アサヒカメラ』に初期の作品を投稿するなどしています。
1935年、『アサヒカメラ』に掲載された「写真技師を求む」の求人を頼りに名取洋之助が率いる日本工房に応募し、100倍以上の倍率を勝ち抜き入社することになります(宮内からは転職の許しを得ることができず強引に写真館をやめています)。
名取の助手として働くことになった土門ですが、名取とは終始ソリが合わず、土門の撮影した写真を名取がビリビリに破って否定したこともありました(といっても、名取は土門だけでなく、同僚の藤本四八に対しても同じように、写真を眼の前で破ったり、顔に投げつけることがあったそうです。そうした行動が普通に行われていた会社だったのかもしれません)。
そんな職場で、土門は『NIPPON』に掲載する写真を撮影や、大学の卒業アルバム撮影、広告撮影などを担当しながら、報道写真についても学びまた実践していくことになります。
1938年、日本工房は当時外務大臣だった宇垣一成へのルポを『婦人画報』から受注します。このとき写真を担当した土門は、名取に無断で、アメリカの『ライフ』誌に宇垣を取材した写真を投稿し、これが掲載されます。工房メンバーが作成した投稿レターに記された撮影者の署名が土門の名前だったことを後に知った名取は激怒し、これが一因となり土門は日本工房を退社します(それまでにも土門の写真は『ライフ』などの海外雑誌に掲載されていましたが、それらの写真の署名は全て「名取洋之助 作」となっていました)。
1939年に日本工房を退社したばかりの時期は、生活に困りカメラを1台も持てないほどでしたが、まもなく外務省の外郭団体である国際文化振興会の嘱託カメラマンとして採用され、海外向けの写真集やポスター等を撮影するようになると、経済的にも安定しだします。またこの頃から、仏像をはじめとした伝統芸術に興味を持つようになり、仏閣や民芸品の撮影に取り組むようになります。
その後は、報道写真家の職域奉公のために組織された日本報道写真家協会に参加し、プロパガンダ写真の制作に加わります。この協会には、土門がかねてよりライバル視していた木村伊兵衛も参加しており、彼らが公に同じ組織に属する初めての機会だったとされます。
国際文化振興会での仕事を続けながら、報道写真の分野で活動を広げていた土門は、日本初の写真賞であるアルス写真文化賞を受賞します(とはいえ、戦局ゆえ第1回のみの開催となり、土門以外の受賞者はいません)。
自身のファンだった三木淳の推薦もあり、石津良介と知り合う機会を得た土門は、雑誌統廃合後の写真編成に迷っていた石津にとって渡りに船の存在でした。以前から企画していた写真賞に土門を推そうと考えた石津は、このために『写真文化』誌で複数回の土門特集を組み、マッチポンプ的に土門は受賞します。
この当時、土門の写真は、「絶対非演出」による自然な瞬間を捉えるのではなく、むしろ、その人(事物)の典型的な状態、つまりその人に身についた癖や鍛錬の結果出るてらいのない規則的なポーズをよしとしていました。その人の全人格を表現できるような瞬間が出るまで粘り強く撮影し続け、不意に現れた「その人らしさ」を撮ろうというものです。スナップとも演出とも言えないこの写真スタイルのことを土門は「最大公約数」を撮ると表現しています。
1943年には『日本評論』誌に自身の国策写真論をまとめた「対外宣伝雑誌論」を発表します。対外「宣伝」ではなく「報道」が必要であり、既存のプロパガンダ雑誌は全て廃刊統合してしまうほうがよいと、檄を飛ばす内容でしたが、軍部からの心象は悪く発禁処分となります。また土門自身は、このために国際文化振興会の嘱託を辞することになります。その後は出版社から敬遠され仕事をすることは少なくなり、代わりに奈良での仏像撮影の時間が増えるようになります。
終戦間際の1945年6月、土門のもとにも赤紙が届きますが、痔が酷かったことを理由に徴兵を逃れて、そのまま終戦を迎えます。
___
戦後の日本社会の激動期において、土門はリアリズム写真を提唱し、その写真運動を牽引しました。
1950年に編集長だった桑原甲子雄に推される形で『カメラ』誌の月例写真審査員になると、サロニズム写真からの脱却と、戦後日本の現実を捉えるような社会的リアリズムの重要性を積極的に説くようになります。このころに土門によって掲げられた「カメラとモチーフの直結」「絶対非演出の絶対スナップ」「実相観入」といったスローガンは当時のアマチュア写真家たちだけでなく、戦後の日本写真全体に深く影響を残しています。
1950年から1963年まで断続的に続けられた土門による月例審査は、写真家の登竜門としても機能しており、杵島隆や川田喜久治、東松照明、深瀬昌久など後にプロになる人物が多く参加していました。
後に「第一期リアリズム」とよばれる土門の思想的展開のもと、多くのリアリズム写真が誌面を飾りましたが、徐々に月例に応募するアマチュアたちの写真は、ホームレスなどの特定のモチーフを扱ったスナップショットへと定型化し、「乞食写真」と批判されるようになっていきます。
こういったことの背景には、土門が多くのアマチュアの共感を集めた一方で、それらを文化運動として組織化できなかったことがあるとされます。彼個人の写真家としての魅力と、彼を師と仰ぐアマチュアたちという閉じた環境の中で、「土門拳がルンペンを撮ればいっせいにアマチュアも右にならえし、『リアリズム即乞食写真』といった極端な題材主義に変調するような風潮」が生まれたと、当時を振り返って重森弘淹は述べています(重森,1967)。
また、1951年に土門と一時バトンタッチする形で月例審査を担当した濱谷浩は、土門に影響された写真が大量に応募されるのを見て、それらが形式的にリアリズムを真似ただけの「クソリアリズム」であり、流行り物に影響されて興味本位で浮浪者や傷痍軍人を盗み撮ることは写真の社会悪だと批判しています。
やがて土門は1955年に「第一期リアリズム」の終焉を宣言し、テーマ性を確立した「第二期リアリズム」へ進むべきであると主張します。
この頃から、土門は実作においても、自分なりの「リアリズム写真」を実現していかなければならないと考え始め、1955年には、東京下町の子どもたちをおさめた『江東のこども』を発表します。その後は、原爆被害を記録した『ヒロシマ』(1958)や炭鉱労働者の生活を描いた『筑豊の子どもたち』(1960)などの作品を通してリアリズムの実践へと向かうことになります。
1960年の筑豊の取材後、脳出血を発症し長期療養を余儀なくされます。リハビリを続けましたが言語・身体障害が残り、車椅子生活を送ることになります。今までのように激しいカメラワークは難しくなった土門は、その後大型カメラに主軸を切り替え、『カメラ毎日』で連載していた「古寺巡礼」シリーズに代表されるような仏閣撮影に力を入れるようになります。
土門拳「呆童漫語(三)」『フォトタイムス』17(10),フォトタイムス社,1940.
この記事で、土門は伊奈信男を批判して、伊奈の言う「報道写真家は何をなすべきか?」という問いは、「あらゆる人々のための現実の発見」といった新興芸術の理論を下敷きにして回答されるのではなく、日々の生活の根底にある倫理的かつ政治的な信条/心情と理念によって回答されるべきとします。
ニエプスがはじめて写真を撮影したときには写真理論などなかったはずだという彼の主張は戦後のリアリズム写真運動に通じるものがあります。
一方では、ここで示される生活に根ざす報道写真は、「憂国の至誠から発した世界観を基底として、この国家の立場と目的に合一する方向に、その職能を持って起き上がる」、大政翼賛の国民のひとりとして行われるべきものだと土門は述べて、伊奈の議論を「文化に対する政治の優位性を軽視して」いると看破しています。
このような発言を通して、土門は写真の社会的必要性や有用性を繰り返し発信しています。彼の真意はわかりませんが、すでに戦時統制下で写真撮影自体が難しくなってきた中で、彼なりに写真は役に立つ、必要なメディアなのだと当局にアピールするための記述だったのかも知れません。
26. 田村 茂(1909~1987)

『新日本文学』10(6)[(95)],新日本文学会,1955.
撮影:中島健蔵
北海道札幌市で生まれた田村茂(たむら・しげる)の祖父は屯田兵として札幌に入植した一団のうちのひとりでした。父も農民でしたが、田村自身は鍬を持つようなことはなかったいいます。
中学時代に写真に興味を持った田村は、札幌の三春写真館で写真技術の基礎を学びます。その後、オリエンタル写真工業の菊池東陽と知り合いだった店主の三春に、オリエンタル宛の紹介状を書いてもらい、1928年に東京へ移り、翌1929年にオリエンタル写真学校に入学しました。
3ヶ月のカリキュラムを終えて1929年秋に卒業した後、菊池東陽の紹介で銀座のアベスタジオに就職します。その後、アベスタジオは倒産し、1933年に光映社に籍を移しますが、その光映社もまもなくして潰れ、1935年にはオリエンタル時代からの知人で、光映社の頃には同僚でもあった渡辺義雄とともに、銀座にスタジオを設立します。スタジオでは渡辺に師事して建築写真を学びつつ、住宅誌の建築写真やパンフレット用のポートレートなどの宣伝写真が手掛けることが多かったようです。
後に桑沢デザイン研究所を設立する桑沢洋子とは、光映社時代に仕事の縁で知り合い、渡辺とスタジオを立ち上げる少し前(1934年)に結婚しています。桑沢はこの頃に建築写真を撮る田村の撮影助手を務めることもあったといいます。
1936年からは『婦⼈画報』の仕事を多数行い。同誌ではルポルタージュのほかムンカッチの影響を受けた屋外でのスナップ形式のモード写真が評判なり、「モード写真の⽥村」と呼ばれる、第⼀⼈者となります。また、銀座にあった桑沢と田村の住まいには、亀倉雄策や土門拳、木村伊兵衛のほか当時活躍していたクリエイターや編集者が多く出入りしていて、サロンの様子を呈していました。
婦人画報などでのルポルタージュの経験で手応えを感じていた田村は、1938年に土門拳や藤本四八らと青年報道写真研究会を結成し、報道写真へ傾倒していくことになります。婦人画報などの雑誌でポートレートや取材写真を手掛けつつ、戦争の深まる1942年~43年には陸軍の従軍カメラマンとしてビルマに派遣されています(同じビルマ行きの仲間には清水幾多郎や中央工房の沼野謙がいました)。ビルマでは戦地の惨状を巡る写真を撮影しましたが、上司だった陸軍大佐に全て却下され、結果写真は一枚も公開されていません。
日本に帰国した後は、1944年には再びの召集令状を受けてインパール作戦への参加を求められますが、徴兵忌避のために東京を離れ、北海道の親戚などを頼りながら終戦まで召集を回避しています。
戦後、渡辺勉に誘われて、1946年の創刊時から『世界画報』に参加し、メーデーなどの集会やデモの写真を多く撮影します。この頃に田村は共産党に入党し、機関誌『赤旗』の写真部で党活動の撮影もしています。
1949年に「世界画報」が廃刊になると、共産党系の雑誌『大衆クラブ』などで仕事をしつつ、フリーランスとして活動を続けていきます。彼の仕事を代表することになる『文藝春秋』での「現代日本の百人」シリーズもこの頃に引き受けたもので、1949年~1951年までの3年間を通じて、横山大観や小津安二郎など各界の著名人の肖像を百人分撮影していきました。
この時期、妻の桑沢の仕事がますます多忙になっており、夫婦で共に生活することが難しくなり、一時の別居期間をはさんで、1951年に離婚をしています(お互いの自伝で円満な離婚であったと語っています)。
戦後の彼の作品は社会問題を鋭く描写するもので、特にサリドマイド薬害事件、安保闘争、米軍基地反対運動、原水爆禁止運動などの取材で知られています。
1963年には土門拳や木村伊兵衛も参加する日本リアリズム写真集団を設立し、理事長としてアマチュア写真家の指導に尽力します。田村はリアリズム写真集団の設立背景にあった課題感を以下のように述懐しています。
「それまでもプロだけのグループはわりとあったんだけど、しばらくすると、もう使命は終わったみたいなことを宣言しちゃあ解散する。逆にアマチュアのサークルはたち消えにはならないけど、構成員や水準が幅広くて流動的だという面がある。つまり持続的な運動化しない。」
こういった課題を感じた田村は、全国の写真愛好家を永続的に牽引する運動・組織を目指してこの集団を設立し、プロ・アマを交えた研修会や親睦会を企画していきます。
とはいえ、たとえば重森弘淹が1967年に「この集団が日本共産党の文化政策の一環として組織されていることについて、疑いを挿む余地はない」と評していたように、設立にあたって共産党が全面的に関わったこの集団は、周囲からは「アカの集団」だと揶揄されたり、左翼活動のためのリクルート組織であると批判されることも多くありました(じっさい、1967年の都知事選においては、社会党・共産党が擁立した美濃部達吉を応援する活動を行っています)。
また、芸術論方面からの批判も多く、おなじく重森は「過去のプロレタリア芸術の犯したように、芸術にたんに反体制運動の思想闘争手段としてのみの役割を負わせるとき、芸術の独自性は失われるほかない。写真が政治的現象の矛盾に直接対決する芸術的に有効な手段であるとしても、そしてそれゆえときに政治的プロパガンダとなり……写真は政治に隷属する」と、リアリズム写真集団の活動を批判しています。
「一目瞭然」なものを良しとする題材主義的リアリズムと、リアリズム写真集団の政治イデオロギーを優先する態度とに一致があるという重森の指摘は、リアリズム写真集団の立場と、主観主義や映像派、後に登場するコンポラ写真のあり方との明瞭な対比を行おうとしているようにも読むことが出来ます。
1970年代以降の田村は、急速な開発に依って失われつつある日本の風土や文化遺産の記録にも力を注ぎました。その後、1987年に亡くなるまで一貫して社会の現実に向き合い、その真実を写真に収めることを使命としました。
現代日本の代表者として、共産党の野坂参三や徳田球一、宮本百合子も含まれている。
27. 名取 洋之助(1910~1962)
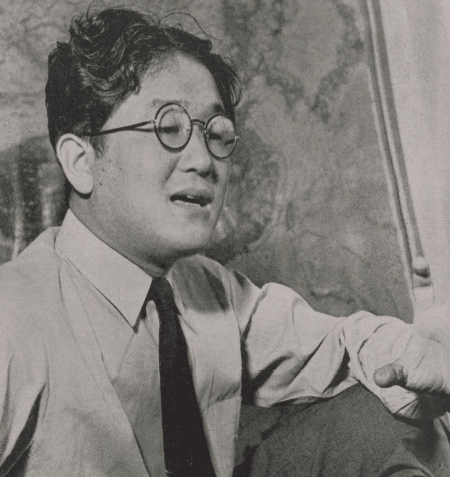
『寫眞文化』23(3),アルス,1941.
撮影:三木 淳
名取洋之助(なとり・ようのすけ)は、は東京の高輪で生まれ、富裕な家庭に育ちました。父の和作は慶應義塾大学部の経済学教授で、後に富士電機製造会社や時事新報社の社長を務めた実業家であり、母のフクは三井財閥の朝吹英二の長女、曾祖叔父には福沢諭吉がいるという名家の出身でした。この環境のおかげで、名取は芸術に触れる機会を多く得ることができました。
1926年に家族の関係もあり名取は慶應義塾普通部へ進学しましたが、成績は悪く、大学進学は難しいと言われていました。そんな名取が普通部を卒業する1928年は、父の会社に派遣されていたドイツのシーメンス社の重役が本国へ帰ることになったほか、深刻な夫婦喧嘩で傷を負った母フクが欧州への傷心旅行を計画していたタイミングでもありました(※富士電気製造社はシーメンス社と古河鉱業の合弁会社として設立)。大学に行けず、アテのない息子だった名取は、母に付き添う形でワイマール期のドイツへと渡ることになります。
ドイツに渡った彼は、前衛演劇や絵画などに興味を惹かれ、これに取り組みますが、あまり身にはつきませんでした。その後は1930年にミュンヘンの美術工芸学校に入学します。ここでは商業美術を学び、卒業後はテキスタイルデザインの仕事に就いています。またこの頃、出版社に勤めていたエルナ・フォン・メクレンブルクと結婚し、彼女と共に活動を続けました。
1931年、もともとカメラ趣味があった兄の木之助がドイツに訪れたときに、名取は兄からライカを譲り受けます。ドイツに渡る前は一切写真は撮ってこなかった名取にとって、ここでのライカ/カメラとの出会いは、今後の彼の人生において決定的な出来事となりました。
また、おなじくして、当時のドイツにおける代表的グラフ雑誌の一つで、フォトストーリーを重視した誌面づくりをしていた『ミュンヒナー・イルストリールテ・プレッセ』のレイアウト担当者と知己を得た名取は、彼から写真についての手ほどきを受けます。
1931年、妻が撮影したミュンヘン市立博物館の火事現場の写真を名取が組写真にして、これを新聞社に持ち込みます。これが、『ミュンヒナー・イルストリールテ・プレッセ』に大きく掲載され、名取は初めて写真で原稿料を得ることになります。これが彼のフォトジャーナリストとしてのキャリアの始まりとなりました。
その後は『ミュンヒナー・イルストリールテ・プレッセ』の取材カメラマンとなって欧州各地を巡ります。この頃の名取の重要な仕事として、サラエボ事件を起こしたプリンツィプの足跡をたどる取材があり、この取材の実績が認められる形で、当時の世界最大規模のグラフ誌『ベルリナー・イルストリールテ・ツァイトゥング』を発行するウルシュタイン社に引き抜かれることになります。
ウルシュタイン社の契約写真家となった名取は、1932年に同社の特派員として日本に一時帰国し、日本の文化や生活様式を撮影し、一度ドイツに戻った後すぐに満州事変への取材に派遣されます。名取は1932年の停戦まで従軍したのち日本へ戻り、原稿整理をしますが、このときにウルシュタイン社から「ドイツに帰ってきても当社で働くことはできないから、東京で日本特派員として駐在せよ」と指令を受けます。これは1933年に成立したヒトラー政権が、外国人記者のドイツ国内での報道活動を禁止したことを受けての指令でした。
ナチスな苛烈な文化統制のなかで、ドイツ関連の仕事にこだわることが難しくなり、名取は日本文化を広く国外へ伝える活動を計画します。この頃、名取は慶応の先輩である野島康三の邸宅にたびたび訪れており、野島の出資によって発行していた『光画』の同人である木村伊兵衛や伊奈信男とも交流するようになります。こういった縁もあり、名取は『光画』に関係するメンバーを誘い集めるかたちで、かねてより計画していた対外宣伝ためのプロダクションである、日本工房を設立しました。
1934年には、フォトストーリーを軸にした報道写真の先駆けとも言える「報道写真展」を企画展示しますが、あまり大きな反響は得られず、設立早々に日本工房は経営不振に陥ります。その頃に名取の妻エルナが来日し工房にも参加するのですが、これをきっかけに工房が大きく再編されることになります。
初期の日本工房は『光画』の同人・サロン的な雰囲気を受け継いでいました。ビジネスマンだったエルナからすると、そういった体制は非生産的に見受けられたようで、売上に関係ない人材をリストラしていきます。最終的には「売上に関係のあった」木村伊兵衛らも方向性の違いを感じて辞めたため、工房には名取夫婦しか残らなくなってしまいます(名取は「契約書」を作ったうえでギャラを支払うという、当時の日本では珍しかった商慣習もドイツから取り入れており、こういった点でも他のメンバーとの間に齟齬があったとされます)。
日本工房の再建にあたって、名取は慶応学閥のコネクションを最大限に活用しスタッフを集めると、鐘紡(現:カネボウ)の2代目社長である津田信吾(名取の父は一時期鐘紡の役員をしており、また津田も慶応出身という縁があった)からの金銭的支援を得ることに成功し、すぐさま対外宣伝誌『NIPPON』を創刊します(1934年)。その後、日本工房には第2期メンバーとして土門拳、藤本四八などの写真家、山名文夫、河野鷹思、亀倉雄策などのグラフィックデザイナーが結集し、当時の日本における最高水準のグラフ誌を出版していくことになります。
なお、日本工房は創刊時から日本軍部とは懇意にしており、名取は参謀本部ほかの将校とこの頃から会席をともにしています。これは、『NIPPON』誌の海外への輸出への便宜などを狙ってのことでした。こういった軍部との関わりは盧溝橋事件に端を発する1937年の日中戦争開戦を分岐点として非常に強くなっていきます。それまでは伝統文化の紹介や企業広告などに軸足のあった誌面が徐々に国策宣伝に傾斜していくようになります。
なお、この頃に土門拳が日本工房を去る事件が発生します。ふだんから、気が立つと社員の頭にビールをかけて侮辱をしたり、気に入らない写真があると撮影したカメラマンの眼の前で破り捨てるなど、横柄な態度を取っていた名取に対する精一杯の反抗として、事務所の皆が土門を応援する形で、名取に無断で土門の写真を『LIFE』誌に送ったのがきっかけです。『LIFE』に送られた土門の写真が採用されたことを知ると、名取は激昂し、土門は喧嘩別れの形で日本工房を去ることになります。
1939年、日本工房は国際報道工芸株式会社に改組されます。名取夫婦の2名からリスタートした日本工房も、この頃には本社社員50名・特派員20名を抱える大きな組織になっており、改組に当たり本社オフィスを移転するなどしています。とはいえ、相変わらず経営は苦しく、この時期にしても赤字続きでした。
この頃の名取は占領した中国と日本を行き来することが多くなり、次第に国内での『NIPPON』の編集への関わりが減ると、そのかわり中国内で立ち上げた新会社の国際報道中華総局での現地人向け雑誌制作に重きを置くようになります。
1943年頃、軍部の方針転換で中国側業者に名取が経営していた印刷所などを引き払うことになり、その後は南京の自宅で二人目の妻(アナキスト作家・宮嶋資夫の娘・玖[たま])と過ごすようになります。この頃の名取は南京での軍事教練にも参加していましたが、決まったとおりに行進ができないなど、あまり訓練成績はよくなかったといいます。
そんな名取は南京で終戦を迎えます。
敗戦が明らかになった後、軍の命令によりネガや雑誌類を焼却することになり、名取は1週間をかけて膨大な資料のすべてを灰にしました。このため、中国時代の名取の仕事はそれほど現存していません。
戦後すこしが経過した頃、1946年に名取は南京で第一子を設けます。ドイツ人の前妻と分かれた際に「日本人の子孫を残したいから」と友人に漏らしていた名取にとっては待望の子供だったといいます。新しい家族を迎え、すでに大陸で骨を埋める気持ちのあった名取は蘇州の墓地を買うなどしていましたが、その後、戦犯として告発されるおそれがあると分かると、妻子を連れて帰国をしました。
日本に戻ったあと、1947年に戦後初の仕事として『週刊サンニュース』の創刊に携わります。しかし、それまで軍関係の仕事が中心で「大衆」を意識した雑誌作りをしてこなかった名取にとって、短いサイクルで娯楽を提供しなければならない大衆向け週刊誌のスタイルは初めての経験であり、悪戦苦闘をすることになります。日本版の『LIFE』を目指してつくられた斬新な表紙や誌面構成は総じて読者からの受けが悪く、売れ行きはつねに厳しいものでした。創刊当初は欧米のグラフ誌にならって横書き左開きにしていたのを、号を重ねるなかで、一般的な文芸雑誌のスタイルにあわせて縦書き右開きに変更したり、表紙を(木村伊兵衛の撮影した)キャッチーな美女写真にしたりと、それまでの流儀を売上のために曲げざるをえなくなっていきますが、それでもなお商業主義に徹しきれず、硬派な内容の記事を堅持したこの雑誌は1949年に廃刊することになります。
その後、1950年には、岩波書店の小林勇の相談を受けて、写真を中心とするレイアウトで1冊ごとに一つのテーマを図解していくスタイルの出版物『岩波写真文庫』の制作にあたります。編集費用の使い方が荒かったために会社と軋轢が生じ、写真文庫の仕事は途中で離れることになりますが、ここでの出会いを通じて岩波書店との仕事をいくつか受け持つようになります。
____
名取のスタイルを表すうえで重要な出来事として、名取・東松論争があります。1960年に『アサヒカメラ』で渡辺勉が発表した「新しい写真表現の傾向」において、渡辺は東松照明の写真を「映像だけがあらわしうる表現」の追求をしていると高く評価します。名取はこれに対して、東松の写真は「自分の観念に合わせて選ばれたもので」「報道写真の特定の事実尊重を捨てた。時とか場所とかに制限されない方向に進もう」とする、もはや報道写真とは言えないものであり、「写真で描いた詩」のようであると反論します。名取にとってみれば、東松の写真は新興写真の時代にアマチュアによく見られたスタイル(撮影者の主観を写真へ反映するスタイル)の応用でしかなく、それは「報道」とは位相の異なる存在でした。
名取の厳しい批判に対して東松側は「写真の動脈硬化を防ぐためには『報道写真』にまつわる既成の概念を破壊する」必要があるとして応答します。
名取は組写真を通じてストーリーを伝えることを重視し、写真をあくまで事前に設定したストーリーを説明・明確化するための手段と捉えていました。一方で、東松は写真同士の組み合わせから生まれる相乗効果を重視し、写真自体に特定のストーリーを持たせず、自由な解釈が広がることを良しとしていました。「報道」を巡って、両者では根本的に考え方が異なっていました。なお、東松は自身の写真構成の考え方を従来の「組写真」と区別するために「群写真」と呼びました。
晩年、胃がんを患うなかで、名取は最後の仕事となる『ロマネスク』に取り掛かります。戦後に何度かヨーロッパを訪れたなかでロマネスク様式の寺院の美しさにとりつかれ、「芸術のための写真集」を出した彼は、1962年に戦後4度目の訪欧の旅をするさなか、かつての古巣であるミュンヘンで癌に倒れ、息を引き取ります。
木村伊兵衛, 伊奈信男 ほか『写真の常識』,慶友社,1955.
はしがきのみ記述
「日本工房の会」編集委員会 編『NIPPON先駆の青春 : 名取洋之助とそのスタッフたちの記録 1934~1945』,日本工房の会,1980.
28. 桑原 甲子雄(1913~2007)

『寫眞文化』25(5),アルス,1942.
撮影者:不明
白状すると、ずっと私は彼の名前を「こしお」だとおもっていたのだが、干支由来の読み方が正しく、きねおであった。ちなみに、桑原が生まれた1913年の干支は癸丑(きちゅう)で甲子ではない。関係ないが、甲子園は1924年の設立で、干支が甲子だったことにちなんでいる(甲子の組み合わせは干支の中でもとりわけ縁起が良いとされている)。
____
桑原甲子雄(くわばら・きねお)は東京府東京市下谷車坂町(現東京都台東区東上野)に生まれ、幼なじみの濱谷浩の影響を受け、写真に興味を持ち始めました。
1926年に東京市立第二中学校(現都立上野高校)に入学し、1931年に卒業しましたが、体調を崩して進学を断念し、家業の質屋を手伝うことになりました。しかし、商売に興味を持てなかった桑原は、濱谷の影響を受けて写真に没頭するようになります。1934年、父親に200円でライカI(C)型カメラを買ってもらい、本格的にアマチュア写真家としての活動を開始しました。同年、浅沼商会発行の写真雑誌『写真新報』が主催するライカ作品公募コンクールで特賞を受賞し、注目を集めました。主に上野や浅草など東京の下町を撮影し、『アサヒカメラ』、『フォトタイムス』、『カメラアート』などの写真雑誌で多くの入選を果たしました。1936年の成績が第1位だったため、1937年に『カメラアート』の第1回推薦作家となり、2月号で特集が組まれるほどの評価を受けました。
この時期、盲腸炎で療養していた桑原は、濱谷から金丸重嶺の『新興写真の作り方』(1931年)を贈られ、新興写真の動向に関心を持ちます。また、石津良介が組織した「中国写真家集団」のメンバーとも交流を深めました。多岐にわたる活躍にも関わらず、この頃、桑原自身は「プロになる気にはなれなかった」と振り返っています。
1940年には南満州鉄道主催の「八写真雑誌推薦満洲撮影隊」に参加し、満州を撮影しました。帰国後、「満州撮影隊現地報告展」に出展し、その成果を発表しました。1943年には在郷軍人会の依頼で出征軍人の留守家族を撮影し、1944年には外務省の外郭団体である太平洋通信社(PNP)に写真部員として勤務し、初めてプロの写真家として仕事をしました。
戦後、桑原は1947年に写真家集団銀龍社の結成に参加し、1948年にアルスに入社。『カメラ』の編集長を務め、月例写真の選者に土門拳と木村伊兵衛を起用しました。これは当時のプロとアマチュアの社会的隔たりを縮める斬新な試みでした。
『カメラ』は土門のリアリズム運動の拠点となり、東松照明、川田喜久治、福島菊次郎などが投稿する場を提供しました。
その後も『サンケイカメラ』、『カメラ芸術』、『季刊写真映像』、『写真批評』などの写真雑誌の編集長を歴任し、新人育成や写真評論に重点を置いた活動を行いました。特に『カメラ芸術』編集長時代には、荒木経惟をいち早く評価するなど、先進的な姿勢を示しました。
1965年以降、桑原は再び写真撮影に本格的に取り組み始めます。1968年の「写真100年 日本人による写真表現の歴史展」で戦前の写真が再評価され、1973年には個展「東京1930-40―失われた都市」を開催。1974年には写真集『東京昭和十一年』、『満州昭和十五年』を刊行しました。
桑原の作品は、主に東京を中心とした街中でのスナップショットが中心で、下町の風俗や生活を過度に表現的にならずに撮影したことが特徴です。特に戦前の作品は、当時としては異色であり、1970年代以降の再評価の時期には、貴重な時代の記録としてだけでなく、その現代性も注目されました。
桑原甲子雄『東京昭和十一年 : 桑原甲子雄写真集』,晶文社,1974.
1974年の2冊については、写真引伸を八重幡浩司・荒木経惟が担当している。荒木は勃起しながら桑原の写真を引伸したと冗談ぽく書いている。
29. 植田 正治(1913~2000)

『世界写真全集』第5巻 (日本),平凡社,1956.
撮影者:不明
植田正治(うえだ・しょうじ)は鳥取県西伯郡境町(現・境港市)で履物商を営む父・植田常寿郎と母・ミヤの二男として生まれました。彼の写真家としてのキャリアは、中学校時代に写真を始めたことに端を発します。画家になることを夢見ていた植田に対して家業を継がせたかった父親は、妥協案として当時アマチュア写真形の間で話題になっていたベスト判カメラ「ピコレット」を買い与えました。ところが、絵筆がカメラに変わっただけで芸術への熱意は衰えることもなく、しまいには父親は家業を継がせることを断念してしまいます。
1931年に鳥取県立米子中学校(現・米子東高等学校)を卒業後、米子写友会に入会しました。米子写友会は、淵上白陽が会長を務めた日本光画協会との太い関係を持っており、山陰地方における芸術写真との深まりを下支えします。
植田自身は、油絵的なタッチのピクトリアリズム表現を得意とした塩谷定好と中学の終わり頃から交流を持ち、芸術写真へのめり込んでいきます。
翌年、東京のオリエンタル写真学校に入学し、3ヶ月間の学びを経て帰郷し、実家の一部を改築して植田写真場を開業します。
植田が開業をした頃は新興写真ムーブメントの真っ只中であり、彼もその影響を強く受けて、今までの淡い表現の芸術写真から緻密でシャープな写真表現へと移行していきます。
1937年には中国写真家集団の創立同人となり、以後同集団の東京展に精力的に作品を発表しました。後に植田の代表作とされる「少女四態」などの群像演出写真もこの頃に発表されました。
この頃の植田の前衛的演出写真ゆえ、写壇からはシュールレアリストと評価されることもありましたが、彼自身はそれを否定して「理屈は理屈屋に任せて置いて『作家はただ作ればいい』の態度でいいぢゃないですか。難しい言葉を並べ立てて堂々と論陣を張る人の作品のみ優れた芸術作品だと、ほとんど盲目的に思い込み、理屈の一つも言えないような人間の制った画は全然問題にされないのが、タアイない現在の写壇ぢゃないでしょうか」と、むしろ自身の作品に理屈をつけたがる人々を批判して返しています。
戦時ムードが一層高まる1941年末、写真による芸術表現を良しとせず、報国のための報道写真を第一とする風潮の中で、植田は興亜写真報国会の米子支部長となります。興亜写真報国会はアマチュア写真家への防諜教育や出征者へ送る慰問写真の撮影等をする団体で、体制側から写真家を統制することを目的としていました。この頃の植田の作品は時局に合わせて報道写真の要素も取り入れますが、当時からあまり評価されませんでした。
終戦を迎えたのち、戦中に抑え込まれていたアマチュア写真家たちに再びの熱気が見え始めるなかで、植田は演出写真の制作を再開します。1947年には旧知の石津良介らによって結成された銀龍社に参加し、1949年には「綴方・私の家族」シリーズを発表。これにより、砂浜や砂丘を舞台とした幻想的な作品で高い評価を得ました。
植田が演出写真に熱を入れなおしていくのとは裏腹に、1950年代は土門拳を旗振り役としたリアリズム写真運動がブームとなります。植田はこの時期を「私の演出写真は、戦争の激化で一度、そして、このリアリズムの嵐の中で、二度目の中断をよぎなくされ」たと振り返っています。
1971年、自身初の写真集『童暦』を刊行します。1950年代からの作品を再構成したこの写真集は、今までの演出写真の手法よりも、むしろ記念写真的な手法に終止しており、植田なりのリアリズム写真への回答ともとれます。植田のこのスタイルは当時流行りを見せていたコンポラ写真とも呼応し、再注目されることとなります。
1974年からの11年間、13回にわたって「小さい伝記」が雑誌『カメラ毎日』に掲載されます。すでに還暦を迎えていた植田は自身の生活の様子や戦前のネガを掘り返して作品化するなどします。晩年となる1980年代後半~1990年代前半、外出しての撮影が難しくなっていた植田は自宅に用意したスタジオで多重露光や合成を多用した静物写真<幻視遊間>シリーズを制作しました。
____
還暦を迎えた後、植田は写真家の写真に向ける態度を「コマーシャル・フォトグラファー」と「シリアス・フォトグラファー」という2つの用語で説明しています。
食い扶持のために写真を制作するコマーシャル・フォトグラファーと、自身の美意識や内面にある何かを表現するために採算を気にしないシリアス・フォトグラファー。この2つは必ずしも矛盾するわけではありません。一人の写真家の中に両立できるものであり、対立図式をとるものではないといいます。
植田は、プロとしての活動の中で自身の美意識や独自の観念を表現できる人物、すなわち「プロ中のシリアス派」が評価されることを強く望んでいました。
30. 杵島 隆(1920~2011)
杵島隆(きじま・たかし)は1920年12月24日にアメリカ合衆国カリフォルニア州カレキシコで日本人移民の子として生まれました。1924年の排日移民法施行により、彼は母の実家である鳥取県西伯郡の杵島家に預けられ、養子として育てられました。
杵島が写真に出会ったのは中学生の頃でしたが、本格的な写真活動を始めたのは1938年に鳥取県立米子中学校を卒業した後のことです。当初、アメリカ国籍であったため進学に困難があり、電気会社に就職しましたが、1939年に養父の知人である増谷麟の推薦により東宝映画株式会社に入社し、東宝の委託学生として日本大学専門部映画科に入学しました。
1942年、日本大学を繰り上げ卒業し、東宝撮影所に勤務します。翌1943年には杵島家の籍に入り日本国籍を取得し、海軍飛行予備学生として志願しました。彼は海軍航空隊に任官し各地を転戦し、福岡の基地で沖縄での特攻の待機中に終戦を迎えました。
終戦後、杵島は郷里に戻り、知人から譲り受けたカメラで写真撮影を再開しました。現像・焼き付けや撮影の仕事を手がけながら、1948年には同郷の写真家植田正治に師事します。この頃、戦後復刊した『アサヒカメラ』や『カメラ』などの写真雑誌の月例懸賞欄に作品を投稿し、次々と入賞していきました。
杵島の写真家としての転機となったのは、1950年の『カメラ』5月号月例で特選となった「老婆像」でした。ソラリゼーションの技法を用いたこの作品は、評者を務めていた土門拳に高く評価され、杵島の名が広く知られるきっかけとなりました。同年、植田正治を中心に山陰地方の若手写真家が結成した「写真家集団エタン派」にも参加しています。
1953年、杵島は上京して、旧日本工房のメンバーによって創業されたライト・パブリシティに入社し、広告写真家としての活動を開始しました。1955年にフリーランスとなり、翌1956年にはキジマスタジオを設立しました。この頃から、彼は広告写真だけでなく、センセーショナルなヌード写真の分野でも先駆的な活動を展開していきます。
特に注目を集めたのが、1958年に制作された《桜田門》シリーズです。野外でゲリラ的に撮影されたこのヌード写真シリーズは、空間にオブジェとしてヌードを配置する芸術的な構図を持ちながら、同時に強烈な政治的な側面も有する、スキャンダラスな表現として物議を醸しました。また、無許可で皇居の桜田門前でヌード女性を撮影したということもあり、杵島は警視庁に連行され取り調べを受けています。
当時は、売春防止法の施行(1957年)や赤線廃止(1958年)が行われ、「性」に関する議論が白熱していました。また、芸術におけるわいせつ性や表現の自由を巡るチャタレイ裁判の判決が確定(1957年に出版社側が敗訴確定)し、「過激な性的表現」を芸術として捉えるべきかどうかについて、大きな議論が巻き起こっていました。
杵島の野外ヌードはこういった時代背景のなかで、とくにチャタレイ裁判の判決に対する強い反発のために撮影されたものでした。
彼の作品に対する賛否は激しく分かれ、たとえば名取洋之助は明確に反対の立場でした。また、ヌードモデルと子供が一緒に歩いたり寝転んでいる様子を撮影した《御宿でのヌードと子供》は、「子供に全裸の女性を見せるとは何ごとか」とPTAなどから強い反対を受けました。こういった論調に対して杵島は「売春防止法は全くのザル法案で全国至るところで、陰で売春は行われているのだから、健康な裸体を子供に見せるべきだ」と反論しています(じっさい、当時の御宿は海女さんが普段から全裸で歩いていたりと、子供にとって裸の女性自体は珍しいものではなかったようです)。
ヌードに注目されがちな杵島の作品ですが、それ以外にも、例えば《8月6日ピカドン広島》(1945年)や《黒い雨が降った》(1946年)といった、より明確に政治的意図を打ち出した作品も制作しています。
印刷時報社 編『月刊印刷時報』(239),印刷時報社,1964
印刷時報社で連載が掲載されている。
D.H.ロレンス 著, 羽矢謙一 訳「チャタレイ夫人の恋人」『世界文学全集』72 (ロレンス),講談社,1975.
「チャタレイ夫人の恋人」の翻訳の種類については、こちらが詳しい。チャタレイ裁判で問題となったのは、羽矢の翻訳ではなく、戦後に伊藤整が翻訳し、小山書店から出版されたバージョンです。しかし、羽矢の翻訳版も、裁判で「わいせつ」と判断された無修正版の原書を基にしている点では共通しています。
裁判で争われた1950年出版の伊藤整版の翻訳本は発禁処分のうえ絶版となっています。国会図書館でもこのバージョンを閲覧することは出来ません。なお、翻訳の違いはあれ、同じくらい「わいせつ」なはずの羽矢版の翻訳本は発禁になっていません。
梅崎進哉『チャタレー体制下のわいせつ概念とその陳腐化 -ろくでなし子事件を素材として-』西南学院大学法学論集, 50(4) 1-78, Mar, 2018.
31. 笹本 恒子(1914~2022)

『写真と技術』16(1),写真と技術編集部,1951.
撮影:吉川富三
日本ではじめて報道写真家として活動した女性である笹本恒子(ささもと・つねこ)は、1914年に現在の東京都品川区に生まれます。
笹本の写真家としてのキャリアは、1939年に東京日日新聞(現在の毎日新聞)で挿絵のアルバイトとして始まりました。その後、1940年4月に財団法人・写真協会に入り、日本初の女性報道写真家となりました。この時期、笹本は海外使節団の動向や著名人の活動など、国内の出来事を世界に向けて発信する重要な役割を担いました。
太平洋戦争中、笹本は「日独伊三国同盟婦人祝賀会」や「ヒットラーユーゲント(ヒットラー青年団)来日」など、歴史的に重要な場面を撮影しました。これらの写真は、戦時下の日本の社会状況を生々しく伝える貴重な記録となっています。
戦後、笹本は1945年に千葉新聞に勤務し、1946年にはフェミニズム団体の婦人民主クラブの機関誌「婦人民主新聞」の嘱託カメラマンとなりました。1947年にはフリーのフォトジャーナリストとして活動を開始し、1950年には日本写真家協会の創立会員となりました。この時期、笹本は「マッカーサー元帥夫妻」や「三井三池争議」、「安保闘争」など、戦後日本の復興と社会変動を象徴する場面を撮影しました。笹本の写真は、単なる記録を超えて、その時代を生きた人々の表情や雰囲気を鮮明に捉えています。
1985年、71歳で開催した写真展「昭和を彩った人たち」により、笹本は写真家としての活動を再開しました。この展示会は大きな反響を呼び、笹本の名前を再び世に知らしめることとなりました。笹本の後年の活動は、特に「明治の女たち」をテーマにした作品群で知られています。『輝く明治の女たち』などの著作では、画家の三岸節子、女優の杉村春子、作家の佐多稲子など、明治生まれの著名な女性たちの肖像を収めています。
笹本の功績は国内外で高く評価され、2011年には吉川英治文化賞と日本写真協会賞功労賞を受賞しました。さらに2016年には、写真界の最高栄誉の一つである「ルーシー賞」を受賞し、国際的にもその功績が認められました。
また、女性として初めて報道写真の分野に進出した先駆者として、後続の女性写真家たちに大きな影響を与えました。笹本の業績を称えて、2016年には「笹本恒子写真賞」が創設されました。この賞は、実績ある写真家の活動を支援し、笹本の精神を引き継ぐ次世代の写真家の育成を目的としています。
戦前、戦中、戦後の激動の時代を生き抜き、100歳を超えてなお現役として活動を続けた笹本は、2022年8月15日に107歳で逝去します。
32. 濱谷 浩(1915~1999)

『世界写真全集』第5巻 (日本),平凡社,1956.
撮影者:不明
濱谷浩(はまや・ひろし)は、1915年に東京の上野で生まれます。関東商業学校(現・関東第一高等学校)在学中に父の友人の写真家からハンドカメラをもらい、写真の手ほどきを受けます。
1933年に卒業後は、学校の推薦で二水実用航空研究所に航空写真家として就職しますが、すぐに会社が倒産したため一銭も給金を受け取れないまま失業します。
失業後、商業学校でお世話になった教師に再就職先を相談した濱谷は、オリエンタル写真工業への入社を世話され、銀座の東京出張所に勤めることになります。オリエンタル写真工業では渡辺義雄の助手などをするかたわら、1930年代は東京の市井を対象にした作品を制作しました。1936年には、菊池寛ら府中競馬場にいるのを撮影した組写真が『ホームライフ』誌に掲載されています。
1937年、父親の方針で一家で上野から大森へと引っ越すことになり、同じくしてオリエンタルを退社します。以後はフリーのカメラマンとして独立し、兄の田中雅夫とともに「銀スタジオ」を名乗って開業します。翌年には瀧口修造、田中雅夫らと前衛写真協会を、また土門拳、林忠彦らとともに青年報道写真研究会を結成しました。
1939年、西園寺公一が主催していたグラフ誌『グラフィック』の取材で新潟県高田市(現・上越市)を訪れ、このときに地元の青年の紹介で民俗学者の市川信次と交流を持ちます(のちに市川が渋沢敬三に引き合わせ、これもまた大きく影響します)。このときの経験が濱谷の写真家としての方向性を大きく変え、民俗写真へと誘うるきっかけとなりました。1940年から10年間にわたり、新潟県中頸城郡谷浜村(現・上越市桑取谷)の小正月の民俗行事を記録するなど、民俗学的な視点から日本の風土や人々の営みを捉える撮影を続けます。この時期の作品は後に自身初の写真集『雪国』として結実します。
太平洋戦争直前、濱谷は1941年に陸軍より従軍召集を受けるも、軍隊の上下関係を嫌いこれを拒否します。同年に、木村伊兵衛から入社すれば軍に徴用もされないと誘われ、東方社に参加します。東方社では対外宣伝誌『FRONT』のため、軍事演習や満州の都市などを撮影しました。
1943年、濱谷は東方社を辞職しました。きっかけは、撮影のために飛行機に同乗した写真部員が墜落事故に遭い負傷した際の出来事です。この時、東方社は治療費の支払いを渋り、濱谷は写真部員を代表して東方社理事の岡田桑三に抗議しましたが、取り合ってもらえませんでした。同じ頃、濱谷は陸軍報道部からラバウル戦線への従軍を命じられましたが、これを断りました。岡田は濱谷が召集を断ったことに激怒し、濱谷を問い詰めました。この出来事が決定打となり、両者の溝は深まり、濱谷は最終的に辞職することになりました。
その後、外務省外郭団体の太平洋通信社(PNP)に所属し、学者や文化人らの肖像撮影を手がけます。
1944年、ネガフィルムを疎開させるために新潟県高田市(現・上越市)を訪れたタイミングで徴兵の電報を受け取ります。東京に戻ると横須賀海兵団に入隊することに決まりますが、入隊時の身体検査の際に心臓弁膜症だと軍医に言われ召集解除となります。
濱谷は、ここで経験した数日ばかりの軍隊生活を振り返って、それまでのカメラ越しに外側から見ていた軍隊と、内側から見た軍隊とでは全く別世界で「憎悪感と嫌悪感で心身が充満した」と述べています。
1945年、恒例となっていた桑取谷での雪中撮影をこなした濱谷は新潟から東京に戻ると一転して空襲の火の海を経験します。自宅の大森付近も焼け野原になり、できる限り機材やネガを疎開させたかった濱谷は新潟高田と東京都をしきりに往復して運搬をします。そんななか、濱谷は高田の善導寺で8月15日を迎えます。このときに撮影した《終戦の日の太陽》をは後に濱谷の代表作の一つとなっています。
戦後、高田での暮らしを続けることを決めた濱谷は、地方文化をもり立てることを目的にした雑誌『文藝冊子』の創刊に携わります(『文藝冊子』は『文芸たかだ』と改名して現在も高田文化協会からの刊行が続いています)。この頃は、高田周辺で交流を持った多くの芸術家や文化人の肖像を撮影していたほか、食い扶持のために、妙高高原のPXで売る絵葉書用の写真を撮影するなどしていました。
戦後すぐから『世界画報』などの雑誌に写真や原稿を提供をしていた縁もあり、1951年から『文藝春秋』で「日本を創る百人」シリーズを担当することになります。これは田村茂の撮影した「現代日本の百人」の続編で、当時大きく部数を伸ばしていた『文藝春秋』の誌面を飾る花形企画でした。長期連載を抱えた濱谷は東京での仕事のやりやすくするために、1952年に神奈川県大磯町に転居します。その後はシリーズの64人目までを撮影しますが、徐々に編集部による人選が難航していき、結局100人目を待たずに企画は中断することになります。企画は打ち切りとなったものの東京のメジャー文芸誌との縁を得たことで、『文藝春秋』のほかに『中央公論』や『小説新潮』などとも仕事をするようになっていきました。
彼の代表作「裏日本」シリーズの撮影は1954年からはじまり、3年間に渡ります。和辻哲郎の『風土:人間学的考察』をバイブルとしていた彼は、日本海側の12府県を訪ね、各地の風土を取材しながら、戦後日本に残る土着性と周辺化された地域社会ついて記録していきました。濱谷の写真は戦後の復興の中で置き去りにされてきた地方都市の姿を切り取り、1955年に発表した「アワラの田植え」(富山県)の写真は、胸まで泥につかる過酷な労働の実態を示したことで、現地の農村生活改善のきっかけにもなりました。これらの写真は1955年にニューヨーク近代美術館で開催された《ザ・ファミリー・オブ・マン(人間家族)》展にも出品しています。
その後も、1957年に飢餓寸前の生活を送る北海道の開拓民を取材したのを中央公論に掲載し、この報道がきっかけとなり、北海道庁を巻き込んだ生活改善運動がはじまるなど、濱谷のジャーナリストとしての活動はこの頃に一層の熱を帯びていきます。
こういった濱谷の思想は、「人間が人間を理解するために 日本人が日本人を理解するために」という『裏日本』の巻頭文に集約されているといえます。日本の風土と人間をめぐる探究が、彼の生涯の主題となりました。
1960年、「裏日本」シリーズで彼を知ったマグナム・フォト所属のマルク・リブーに推薦された濱谷は、アジア人では初のマグナムの寄稿写真家となります。ちょうど同じ頃に60年安保闘争が起こります。それまで直接的な政治取材とは関わりがなかった濱谷でしたが、「民主主義を崩壊に導く暴力」を感じ取り、徹底的にこの問題を取材しようと決意します。この成果は、マグナム・フォトを通してヨーロッパ各国に報道されるとともに、『怒りと悲しみの記録』として出版されました。しかし、安保闘争や学生運動をめぐる取材を続けたことで「アカ」だとみなされた濱谷は仕事を干されてしまいます。
仕事のなくなった後は、改めて日本の自然を捉えたいと考え『日本列島」シリーズの制作に当たります。その後は日本や世界各地の自然を撮影することに力を注いでいくようになります。
濱谷の自然写真の特出するところは、元来「ピクチャレスクな対象」として描かれてきた風景を、科学的な観察対象として写し出そうとした点にあります。「自然科学を裏付けとして撮影すること」を重視し、「光と其の諧調を美的に再現」しようとする俳諧の延長としての風景写真を乗り越ようと主張しました。
1960年代後半から世界の自然を撮影し、約8年間で六大陸を踏破します。1965年、ニューヨーク近代美術館の「12人の写真家たち―現代写真国際展」に出品。1969年にはニューヨークのアジアハウスで個展「HAMAYA'S JAPAN」開催、全米を巡回するなど国内外を問わず評価され、1987年に日本人写真家として初めてハッセルブラッド国際写真賞を受賞しました。
濱谷浩『スナップの撮り方 アルス写真文庫』第10,アルス,1939.
「カメラマンは頑強でなくてはならない。スナップ寫眞術の一つの條件としては肉體的の勞苦に良く耐へることが必要だ。」p.47.
33. 林 忠彦(1918~1990)

『世界写真全集』第5巻 (日本),平凡社,1956.
撮影者:不明
林忠彦(はやし・ただひこ)は、1918年に山口県徳山市(現在の周南市)に生まれ、祖父の代から続く写真館の長男として育ちました。幼少期から写真に親しんだ林は、1935年に徳山商業学校を卒業すると、家業を継ぐべく大阪の中山正一写真館に修業に出されます。
1936年に肺結核を患い一時帰郷しましたが、退院後は磯部潤一郎が主催する地元のアマチュア写真クラブ「猫之眼会」に参加し、活動を再開しました。 1938年、林は東京のオリエンタル写真学校で学びを深め、翌1939年には銀座の東京光芸社に入社しました。ここでプロの写真家としてのキャリアをスタートさせ、内閣情報部の宣伝誌『写真週報』にルポを寄稿するなど報道写真家として活動を始めます。その後1942年に林は石津良介、大竹省らとともに華北弘報写真協会を設立して中国にわたります。できるだけ戦場に行きたくなかった林は中国の産業現場の写真をメインにしていました。
その後、玉音放送を北京の大使館で迎えた林は、国民政府や八路軍からも残留の誘いを受けて、翌年春まで中国に残ります。
1946年、地元山口県に帰郷するとすぐに上京し、東京での撮影活動を開始します。焼け野原になった廃墟をさまよう林は、なんとかこの東京を撮りたいと思って借金をして小型カメラを用意したといいます。『婦人公論』で上野の撮影をしたことを端緒として、徐々に復興しだした雑誌業界で林は頭角を現します。
当時は「カストリ雑誌」と呼ばれるエログロをネタにした安価な大衆娯楽誌がブームとなっており、林は多いときには25誌もの雑誌のしごとを受け持ちました。とにかく忙しいのでヒロポンを打って徹夜で写真を焼くこともあったそうです。
カストリ雑誌の名前の由来は、当時出回っていた粗悪な密造酒「カストリ焼酎」に由来します。3合呑むと潰れるカストリ焼酎のように、たった3号で休廃刊するカストリ雑誌というわけです。すぐに潰れてしまうので、仕事を引き受けても原稿料をもらえないことも少なくなかったといいます。
1946年に銀座のバー「ルパン」で知り合った織田作之助を撮影したことを皮切りに、この頃の林は、太宰治や坂口安吾といった作家たちの写真を数多く撮影します。1948年には「小説新潮」に連載した文士写真のシリーズで人気を博しました。また、林の撮影した太宰治のポートレートは、彼の劇的な自殺(1948年没)の直前に撮影されたとあって、使用注文が相次ぎます。
「シャッター以前」という彼のスタイルを代表する言葉はこの頃に語られたものです。「私は、どんな場合でも、カメラポジションを決定してから、ワンカット、10分以上かかった事は、先ずありません、すべて写真はシャッター以前の問題と思って居ります」という林は、ロケハンや人物へのインタビューといった事前構想と準備こそが撮影の秘訣であると指摘しています。
1947年、石津良介の呼びかけで決済された写真グループ「銀竜社」に参加します。1950年には木村伊兵衛を初代会長として日本写真家協会が設立されると、これに参加します。また、1953年には秋山庄太郎・大竹省二・早田雄二と二科会に写真部を創設するなど、後進の指導にも尽力しました。1961年に、日本写真家協会副会長に就任しています(1971年には理事に就任する)。
『日本の画家』『日本の経営者』『日本の家元』など、文士シリーズに続く肖像写真と、『カストリ時代』などの社会に鋭い目を注いだ写真が長らく林の仕事の中心でしたが、晩年は風景写真に向かい東海道を撮影し続けました。
67歳で癌に冒され、さらに脳内出血のため半身不随となりながらも、東海道を中心とした写真を撮り続け、亡くなる数ヶ月前の1990年9月に『林忠彦写真集 東海道』を刊行しています。
撮影には四男の林義勝(父と同じく写真家)がサポートにあたり、忠彦の死後、義勝も同じく東海道を巡る写真集を制作しています。
林の死後、1991年に周南市と周南市文化振興財団によって「林忠彦賞」が創設されました。この賞は、「社会は心を撃つ写真をさがしています」というキャッチフレーズのもと、その時代を最も象徴する写真を選出することをコンセプトとしています。
「作家の立場を語る」『フォトグラフィ』2(7)(14),フォトグラフィ,1950.
眞継不二夫・松島進・大竹省二・林忠彦の座談会
34. 佐々木 崑(1918~2009)
佐々木崑(ささき・こん)は、1918年に中国の青島で生まれました。幼少期に神戸に移住し、1937年に神戸村野工業学校を卒業しました。その後、彼は日本理化工業(現:大陽日酸株式会社)に就職し、1939年から1942年まで従軍しました。中学時代から写真への興味が強くあった彼は、戦後に写真への情熱を高めてアマチュア写真家として活動し始めます。1951年に撮影のために神戸を訪れた際、木村伊兵衛と出会い、彼に師事するようになります。1955年には神戸でカメラ機材店を開業し、1957年に大阪へ移り商業写真スタジオを経営します。
佐々木の初期の作品には、神戸の麻薬地帯や遊郭、未就学児童などの社会問題がテーマとなっており、これらは『アサヒグラフ』誌などで発表されました。彼の作品は、その鋭い視点と社会への深い洞察を反映しており、写真を通じて社会の不正を告発する役割を果たしました。
その後、木村の勧めもあり、1960年に再び上京し、フリーランスの写真家としての活動を始めました。この間、木村の撮影助手や、1962年に来日したユージン・スミスの暗室助手を務めました。
1960年代には、佐々木は科学写真の分野に進出しました。特に、東京シネマでの科学映画のスチル写真担当として、顕微鏡写真などの特殊な技法を用いた作品を数多く制作しました。1966年からは『アサヒカメラ』誌で「小さい生命」という連載を開始し、昆虫や小動物の脱皮や羽化、誕生などの瞬間を捉えた写真を発表しました。この連載は、彼を自然科学写真の先駆者として評価させるものであり、1972年には日本写真協会賞年度賞を受賞しました。
その後も、佐々木は「続・小さい生命」として連載を続け、日本国内外で個展を開催し、彼の作品は広く認知されました。「小さい生命」と「続・小さい生命」のシリーズは同誌上で256回の連載を続ける長期シリーズとなっています。
彼はまた、撮影に必要な機材を自作するなど、技術的な側面にも精通しており、カメラ雑誌での機材テストや技法書の執筆なども手がけました。1978年には竹村嘉夫らとともに日本自然科学写真協会(SSP)を設立し、副会長、後には会長を務めました。
35. 三木 淳(1919~1992)

『世界写真全集』第5巻 (日本),平凡社,1956.
撮影者:不明
※三木についてはウィキペディアがとても詳しいので、詳細はそちらをご覧下さい。
三木淳(みき・じゅん)は1919年、岡山県児島郡藤戸町(現在の倉敷市)に生まれました。彼の父親は綿織物卸商を営む豪商で、三木は裕福な家庭に育ちました。幼少期から写真に興味を持ち、10歳ごろにはすでに写真撮影に親しんでいました。彼の写真家としてのキャリアは、慶應義塾大学経済学部在学中から始まります。1941年、国際報道工芸(名取洋之助が創設)の美術部長だった亀倉雄策の指導を受け、土門拳の助手も務めました。 1943年に大学を卒業後、貿易会社に入社しましたが、直後に陸軍に入隊し、第二次世界大戦を経験しました。
戦後、1947年に名取洋之助の誘いを受けてサンニュースフォトス社に入社し、極東軍事裁判の撮影を担当します。この時期、彼の写真は『週刊サンニュース』に多く掲載され、東京の停電の様子や銀座、職業安定所、常磐炭鉱などのドキュメントを発表しています。
1948年にはINP通信社に移籍し、翌年にはタイムライフ社東京支局の依頼でシベリア抑留からの引き揚げ再開で帰国した元陸軍兵たちを撮影しました。このルポルタージュが『ライフ』誌に掲載されたことをきっかけに、1949年にタイムライフ社に正式に入社を果たします。彼は1957年まで同誌で数々のルポルタージュを発表し、特に1951年のサンフランシスコ講和条約調印時に撮影した吉田茂首相の写真は広く知られています。
1950年には「集団フォト」という写真家グループを提唱し、土門拳や木村伊兵衛を顧問に迎えました。このグループは、翌年に第1回展を開催し、フランス人写真家アンリ・カルチエ=ブレッソンの作品を初めて日本に紹介しました。これにより、海外のフォトジャーナリストたちと日本の写真界の交流を推進する役割を果たしました。また、ライフ所属の写真家デビッド・ダグラス・ダンカンが、この頃に、三木が愛用していたニコンレンズの性能のよさを知り朝鮮戦争の取材で使用したことをキッカケに、ニコン(日本光学)の名前は世界的な知名度を得ていくことになります。
1951年には、ニコンの長岡正男から、ニコン製品の愛用者のためにどう支援をしたらよいかと相談を受けて、愛好家のための親善団体の設立と「会社は金は出すけれども口は出さない」といった方針を提案します。その後、1952年に「ニッコールクラブ」が設立されます。
1953年、三木は朝鮮戦争の従軍カメラマンを務めます。彼にとってはじめての戦場であった朝鮮半島で、過酷な状況をフィルムに収めました。ときには塹壕で撮影している彼のもつクロームメッキで光るカメラを標的にして銃撃されることもあり、この経験を元にカメラボディを黒くするようにニコンに求めたといいます。
1956年、ベトナム戦争に対する取材方針の違いからタイムライフ社を退社します(タイムはあくまでアメリカの雑誌であり、北ベトナムに同情的な内容を掲載することができなかったことが主因となっています)。その後はフリーランスの写真家として活動を続け、1958年から翌年にかけて中南米各国を取材撮影しました。1960年には雑誌『日本』に発表したルポルタージュ「麻薬を捜せ」で講談社写真賞を受賞し、1962年の個展「メキシコ写真展――新興国の表情」では日本写真協会年度賞を受賞しました。
1972年、三木は脳腫瘍で倒れると大きな手術を実施し、九死に一生を得ます。その時の経験から、徐々に後進育成に重きを置くようになります。
1977年には日本大学芸術学部教授に就任し、学生たちへの指導に力を注ぎました。三木は亡くなる1992年まで日芸で教鞭をとっています。
また、1981年には日本写真家協会の会長に就任すると、国際交流の拡大や国公立の写真美術館の建設の重要性を積極的に訴えました。それまで日本国内には写真専門の美術館がなく、これを後進育成の大きな課題だと捉えていた三木は、1983年に日本初の写真美術館として開館される土門拳記念館の整備にあたっては、積極的に旗振り役を務め、開館後は初代館長を務めました。
36. 岩宮 武二(1920~1989)

『世界写真全集』第5巻 (日本),平凡社,1956.
撮影者:不明
岩宮武二(いわみや・たけじ)は、鳥取県米子市で生まれました。1938年に鳥取県立米子商蚕学校商業科(現・鳥取県立米子南商業高等学校)を卒業後、彼は阪急百貨店に入社し、その後プロ野球チーム南海(現・福岡ソフトバンクホークス)の二軍投手として活動します。しかし、体調を崩し退団を余儀なくされます。 1940年、岩宮はサラリーマンをしながら丹平写真倶楽部に入会し、写真の世界への第一歩を踏み出した。しかし、その翌年の1941年、彼は応召され満州に赴くこととなります。
戦後1945年、復員した岩宮は大阪でフリーランスの写真家としてキャリアをスタートさせます。岩宮の写真家としての活動が本格化したのは1955年からで、この年に岩宮フォトスを設立します。関西を拠点に広告写真家として活躍する一方で、自身の芸術作品の制作にも精力的に取り組みました。
岩宮の思想は、日本の美や風土への深い洞察と探求に根ざしていました。彼の作品は、日本の伝統的な形態や空間、そして文化的な要素を独自の視点で捉え、写真を通じて表現したものが多く。特に「佐渡」「京都」「日本海」「日本のかたち」「宮廷の庭」などのシリーズは、日本の美的感覚と自然環境の融合を見事に捉えた作品として高く評価されています。
1962年に発表した『かたち 日本の伝承I・II』は日本写真協会賞年度賞を受賞し、1965年の『京 kyoto in KYOTO』は毎日芸術賞を獲得。さらに、1968年の『宮廷の庭Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』では芸術選奨文部大臣賞を受賞するなど、その芸術性は高く評価されました。
1966年には大阪芸術大学教授の写真学科長に就任し、後進の育成にも尽力しました。晩年になっても岩宮の創造性は衰えることなく、1989年に発表した『アジアの仏像』で再び日本写真協会賞年度賞を受賞しています。この作品は、日本の伝統美への探求から、より広くアジアの文化遺産へと視野を広げたものとして注目されました。
37. 石元 泰博(1921~2012)

『世界写真全集』第5巻 (日本),平凡社,1956.
撮影者:不明
石元泰博(いしもと・やすひろ)は、1921年にアメリカのサンフランシスコで生まれ、3歳の時に両親の故郷である高知県高岡町(現・土佐市)に移り住みます。1939年に高知県立農業学校(現・高知県立高知農業高等学校)を卒業すると、再びアメリカへ渡り、ジュニアカレッジを経て、1941年にカリフォルニア大学農業スクールに入学します。満州での農地改良に必要な技術を習得するために、米式の近代的な農法を学びはじめた石元ですが、まもなくして真珠湾攻撃が起こったことをキッカケに彼の人生は大きく軌道修正をすることになります。
第二次世界大戦の発生に伴う日系人の強制収容により、石元は1942年から1944年までコロラド州南東部のアマチ収容所に収容されます。収容所では、消防団とシルクスクリーン工房で働きました。当初は厳しい制限があったものの、徐々に収容所内でのカメラに関する制限がゆるくなっていき、個人のカメラ所有も許されるようになります。石元は、知人に預けていたコダックのカメラを取り寄せ、キャンプ生活の合間に写真仲間と共にキャンプ内の様子を撮影して回りました。
1944年、日本の敗色が濃厚と判断され、終戦を待たずして解放されたものの、沿岸地方に行くことは政府によって禁じられていたために生まれ育ったサンフランシスコなどにはいけず、内陸のシカゴに移住します。それからはキャンプ時代に培ったシルクスクリーンの技術で糊口をしのいでいましたが、終戦後は、荒廃した日本の復興のためを思ってシカゴのノースウェスタン大学に入学し、建築を学びはじめます。
石元はこの頃には、地元で有名だったフォトクラブ「フォト・ディアボーン」に入会するほど写真沼につかっていました。そんな彼は、ある日書店で1冊の本と出会います。ニュー・バウハウスの設立者の一人ジョージ・ケペッシュ著『視覚言語』です。この本に触発されて以後は一層写真に熱をいれるようになり、ノースウェスタン大学は1年で退学します。
フォトクラブの知り合いの日系人写真家ハリー・シゲタ(重田 欣二)の勧めもあり、1948年にシカゴ・インスティテュート・オブ・デザイン(通称、ニュー・バウハウス)に入学しました。ここで石元は、写真技法だけでなく、後の作品の基礎となる造形感覚の訓練を積みます。その後、1950年にはライフ誌で受賞したほかモホイ=ナジ賞(ニュー・バウハウスの学内賞)を受賞するなどしています。
1953年、前年に学校を卒業した石元は、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の写真部長エドワード・スタイケン企画のグループ展「Always the Young Strangers」に出展し、同年に病気の父親を見舞うために久しぶりに日本の地を踏みます。地元高知に滞在した後は、東京の幡ヶ谷に移り住み、以後6年間日本に滞在します。
この頃、MoMAの建築デザイン部門でキュレーターを務めるアーサー・ドレイクラーが「Japanese Exhibition House」展の準備のために来日していました。石元はスタイケンの紹介を受けて、ドレイクラーに同行することになり、建築家の吉村順三らといっしょに京都・奈良などを視察し、日本の伝統建築を調査します。この調査の際に桂離宮にも訪れており、その後1954年には1ヶ月にわたって桂離宮の撮影しています。
のちに発表された桂離宮の作品で、石元は高い評価を受けることになります。石元の撮影した桂離宮は、日本的情緒を排除したリアルな表現と、徹底した造形の強調が特徴的です。17世紀の日本の美意識をもと建てられた桂離宮を、20世紀のモダンな視点で再解釈し、西洋と日本の美学を調和させた新しい解釈を提案しました。伝統建築を土着的な文脈から見るだけではない、彼の視点は当時の日本では新鮮な驚きをもって受け入れられました。
1953年に日本の雑誌に初めて写真を寄稿したのを皮切りに(『アサヒカメラ』8月号)、石元は日本の写真界に徐々に知られるようになります。1954年にはタケミヤ画廊にて国内初の個展を開催。1955年には、開校したばかりの桑沢デザイン研究所で講師に就任し1971年まで写真を教えることになります。
またこの頃に、シカゴ時代からの知人の浜田隆一の紹介で丹下健三と知り合います。丹下は、石元の結婚式の仲人を務めており、その交流の深さが伺えます。
1957年には「日本のかたち」「桂離宮」で第1回日本写真批評家協会作家賞を受賞しますが、翌1958年に日本国籍を離脱すると、千代田光学精工(現:コニカミノルタ)の支援を得て妻とともに渡米し、シカゴに戻ります。シカゴでの制作活動やMoMAでの展示などを続けますが、1961年末に再来日すると、縁あって影山光洋の自宅離れに住むことになります。日本での仕事をリスタートさせた石元は東京綜合写真専門学校の教授に就任、1966年には東京造形大学の教授に就任しました。
その後、1969年に日本国籍を取得し、同年に代表作『シカゴ , シカゴ』を出版します。また、影山邸に長く居候をしていた石元ですが、1971年に品川に居を移すと、翌年には教職をすべて辞めて、自身の写真活動に集中するようになります。
以後は日本の寺社仏閣や街並みの撮影を主軸にして活動を続けます。
2012年2月6日、石元泰博は東京都の病院で肺炎と脳梗塞のため90歳で逝去しました。死後、正四位、旭日重光章が追贈されました。 石元の遺志により、2014年6月に地元高知の県立美術館に石元泰博フォトセンターが開設されています。
個人的にこの写真集はとってもオススメだ。
石元泰博, 富山治夫『人間革命の記録』,写真評論社,1973.
日蓮正宗総本山大石寺の正本堂の写真。正本堂は池田大作の時代に、おもに創価学会員の寄付金によって建設費が賄われたもの。
阪神・淡路大震災のあとの耐震調査で分かった強度不足が判明したが、その少し前に日蓮正宗が創価学会を破門したために、学会経由の寄進を集められず、耐震補強のための費用捻出が難しいと判断され、1998年に解体された。現在は跡地に日本寺院建築の奉安堂がある。
石元泰博『シカゴ,シカゴ : 石元泰博写真集 その2』,リブロポート,1983.
リブロポート版はハードカバー仕様、キャノン版はソフトカバー仕様と装丁が異なる。ただし、掲載写真は同一。印刷についてはどちらも光村原色版印刷所(現:光村印刷)が担当。
38. 芳賀 日出男(1921~2022)
芳賀日出男(はが・ひでお)は、1921年に満州の大連(現・中国大連市)で生まれました。彼の父は満鉄の社員であり、芳賀は幼少期から写真に興味を持ち、その情熱は大学時代に一層深まりました。芳賀は、大学受験の際に初めて日本の地を踏み、その後は慶應義塾大学に入学し中国文学を学びます。在学中はカメラクラブに所属して写真への関心を高めました。
大学で受けた折口信夫の講義は、彼の人生に大きな影響を与えました。特に「村の祭りの日に神の姿の者が訪れる」という言葉に感銘を受け、これを写真に収めたいという願望が芽生えます。これが、彼が民俗写真家としての道を歩む契機となりました。
1943年、在学中に学徒出陣し、海軍に入隊しましたが、終戦後に東京に戻り、フリーランスの写真家として活動を開始しました。1950年代のリアリズム写真運動のなか、都市のスナップなどをする人たちを脇目に見ながら、芳賀は民俗行事や祭りの写真を撮り続けました。彼は、単なる記録写真にとどまらない「民俗写真」という新たなジャンルを切り開き、作品は徐々に認知され始めます。
1958年には初の個展「田の神」を開催し、翌年には写真集『田の神 日本の稲作儀礼』を刊行しました。芳賀の写真は、民俗に対する深い理解と哲学に基づいており、彼は日本や世界各地の祭礼や芸能をテーマにした作品を数多く残しました。その作品は、時代と共に失われつつある日本人の宗教的風土や先達の日々の営みを伝えるものです。
1960年代に結婚した妻の杏子は、彼の写真活動を支える重要な存在となりました。彼は日本国内だけでなく、ヨーロッパの民俗行事にも撮影の幅を広げ、1970年には大阪万国博覧会の「お祭り広場」のプロデューサーを務め、世界各国の祭りを紹介する企画を成功させました。また、1973年には全日本郷土芸能協会を設立し、後に理事長に就任しました。
芳賀は生涯を通じて、民俗写真を「人々の人生の記録」と位置づけ、消えゆく祭りや風習を記録することの重要性を強調しました。彼の作品は40万点にも及び、その多くは芳賀ライブラリーで整理され、民俗学的な資料として提供されています。
1995年には旭日小綬章を受章し、日本写真家協会の名誉会員としても知られています。
芳賀日出男は、2022年11月12日に101歳で亡くなりました。晩年には、健康に気を使いながらも、写真撮影を続けることをライフワークとしました。彼の功績は、民俗写真というジャンルの確立にとどまらず、日本文化の豊かさを後世に伝える重要な役割を果たしました。
39. 福田 勝治(1899~1991)

『フォトタイムス』6(4),フォトタイムス社,1929.
撮影者:不明
福田勝治(ふくだ・かつじ)は、1899年1月17日に山口県佐波郡三田尻中之関村(現在の防府市)に生まれました。中学を卒業後、1920年に上京し、高千穂製作所(現:オリンパス)に入社しました。そこで同僚から入手したベスト・ポケット・コダックカメラで写真撮影を始めたことが、彼の写真家としてのキャリアの出発点となりました。 1923年の関東大震災を機に高千穂製作所を退社し、大阪へ移り、淵上白陽が主宰する写真雑誌『白陽』の編集助手を務めました。
1925年には、モホリ=ナジやマン・レイに影響を受けた《静物》を第1回日本写真美術展に出品し、イルフォード・ダイヤモンド賞を受賞しました。その後、堺で営業写真館を経営し、広告会社青雲社で広告写真を手がけるなど、様々な経験を積みました。 福田の写真家としての本格的なデビューは、1936年に『アサヒカメラ』誌で連載した「カメラ診断」でした。この連載では、女優の原節子や入江たか子らをモデルに作例写真を撮影し、クローズ・アップを多用した明るく洗練された作風が人気を呼びました。翌1937年には、この連載をまとめた写真集『女の写し方』を刊行し、ベストセラーとなりました。 第二次世界大戦前後の時期には、『出発』(1940)、『牛飼ふ小学校』(1941)、『神宮外苑』(1942)などの写真集を出版し、農村生活や日本の風景を題材とした作品を発表しました。1944年には大政翼賛会の委嘱で朝鮮半島各地を撮影するなど、時代の要請に応じた活動も行いました。
戦後、福田は女性写真や静物写真の撮影を再開し、光の演出に巧みで大らかなエロティシズムにあふれた独自の美学を追求しました。『裸婦五態』(1946)、『花と裸婦と』(1947)をはじめ多数の写真集を出版し、ジャーナリズムから脚光を浴びました。
1955年には、キヤノン・コンテストで推選を受け、イタリアを撮影旅行しました。この旅行で撮影された作品は、翌年の「イタリア写真展」で発表され、大好評を博しました。同年、日本写真協会年度賞を受賞し、後年の1986年には日本写真協会功労賞も受賞しています。
福田の写真への思想は、美しさと芸術性を追求する「耽美的な作風」として特徴づけられます。彼は静物、女性、風景などを主題とし、光と影の巧みな操作によって独自の美的世界を創造しました。戦後、土門拳らが提唱したリアリズム写真主義の批判の標的となることもありましたが、自らの美学を貫き、「孤高のモダニスト」として自身の求める写真を撮り続けました。
福田は、アマチュア写真家向けの手引書も多数執筆し、『現像の実際』『春の写真術』『花の写し方』などがベストセラーとなりました。これらの著作を通じて、写真技術の普及にも貢献しました。 晩年には、〈京都〉〈銀座〉〈隅田川〉といった日本の風景を見つめ直した連作を発表し、また実験的なカラー写真〈花の裸婦〉のシリーズでは、ユーモア溢れる自由な創造力を示しました。
福田の自叙伝
40. 中村 立行(1912~1995)
大正元年7月31日、ちょうど明治天皇が亡くなった翌日に生まれた中村立行(なかむら・りっこう[本名:たつゆき])は、次の天皇が決まるまでの臨時の呼称であった「立行天皇」(のちの大正天皇)にちなんで名付けられたと言われています。
※「立行(立皇?)天皇」に関する習俗・典礼を発見できなかったので、その名付けの詳細は不明でした。
神戸で新聞卸しを営む家に生まれた中村は、1930年に神戸県立第三中学校(現:兵庫県立長田高校)を卒業後、上京して東京美術学校(現:東京芸術大学)油絵科に入学します。1936年に美術学校を卒業したのちは、丹波篠山の陸軍歩兵第70連隊に入隊します。多紀連山を舞台とした山岳訓練などのきわめて厳しい訓練で知られ、「丹波の鬼連隊」と称されるほどの過酷な部隊に配された中村ですが、入隊一ヶ月目に胸部疾患のために兵役免除になり、早々に軍隊生活を終えることになります。以降は、終戦まで
品川区立宮前小学校の美術教員として勤務しました。
この教員時代に写真に興味を持ち始め、1943年末にミノルタ製の二眼レフカメラを購入したことが、本格的な写真活動の始まりとなりました。1944年5月に撮影した『小使いさん』という作品は1947年にアルスカメラの月例コンテストに初入選し、写真への情熱もますます高まっていきました。 第二次世界大戦末期には、学童疎開の引率教員として児童たちの生活を記録撮影しました。これらの写真は、戦時下の子どもたちの姿を捉えた貴重な歴史資料となっています。
終戦後、中村は写真家としての活動を本格化させます。1947年に教員を辞め、GHQ(連合国最高司令官総司令部)エデュケーション・センターの写真担当となり、1948年には美容雑誌『百日草』の写真部に勤務し、以降3年間はモード写真に専念します。なお、この間は江藤方斗(えとう・ほうと=絵とフォト)のペンネームで活動しています。
この頃、日本では新しい憲法が施行され、表現の自由と検閲の禁止が定められました。戦前にあった内務省へのよる検閲(出版法による事前納本制度)がなくなり、性的表現について、かなり自由に行えるようになります。こういったなかで、戦前の「エロ・グロ・ナンセンス」の系譜を引き継ぐかたちで、カストリ雑誌とよばれる数多くの雑誌が登場します。こういった雑誌では、芸術写真と称してヌード写真も多く掲載されていました。
また、1947年から始まった新宿帝都座の「額縁ショウ」を端緒として、ストリップブームが起こり、各地でストリップ劇場が設置されていきます。その後、1950年代後半には「全スト」と呼ばれる全裸でのストリップショーも現れるようになっていきます。
こういった、「エロ」を求める大衆のニーズも受けつつ、ヌード写真を撮影するカメラマンのニーズも高まっていきます。
また、プロに続く形でアマチュアカメラマンもヌード写真を撮るようになると、各所にヌードスタジオが乱立し、ヌード撮影会ビジネスも活況となります(「ストリップを観に行くよりも安い」とストリップ/覗き感覚で撮影会に参加する人も多かったと言います)。
写真家たちは、ヌード写真の撮影・公開の自由を得て、「『兎に角ヌードを移さなきゃ話にならない』という考え、バスに乗り遅れまいとすためあせった気持、そういうものが写真家達の心の底にひそみ、無暗にヌードを撮りまくった」と伊藤逸平(1959)は戦後すぐの頃を振り返っています。このような戦後~1950年代はじめ頃までの”無闇矢鱈に撮られたヌード写真”は、グラフ誌の読者からさえ、ストリップの延長として見られる向きも強く、芸術としての側面が強調されることはあまりない状況でした。中村の作品は、こうした状況の中で、それまでのヌード写真のイメージを大きく刷新していきます。
1950年にアルス写真年鑑に掲載された《裸婦》を皮切りとして、中村は猥雑ではない"清潔なヌード"を提示したことで、戦後のヌード写真界をリードする存在となりました(とはいえ、実際にはいきなり芸術扱いされたわけではありません)。
それまでのヌード写真とは異なり、裸体をオブジェクトとして扱い、「お色気」を冷徹に排除した作品は、明らかに新しいヌードのあり方でした。林忠彦はこういった中村の作風がモディリアーニに影響を受けているとして、彼を”モジグリの立行さん”と称していました。
1952年に『ヌードフォトの研究』を刊行し、1954年には複数のモデルを使ったフォルムの組み合わせによるヌード撮影に取り組みました。1955年からは自然光を用いた屋外でのヌード撮影も手がけ、表現の幅を広げていきました。
1956年には、美術雑誌『アトリエ』別冊「画家とモデル」特集で浜村美智子をモデルに撮影し、大きな反響を呼びます。
同年、秋山庄太郎らと女性を主題とする写真家の集団「ギネ・グルッペ」を結成し、写真界での活動をさらに活発化させました。
1960年代以降、中村はカラーフィルムによるヌード表現にも挑戦し、エロティックな感覚を追求した作品を制作しました。1970年には新書判写真集『裸 NUDE』を出版しています。
一方で、中村は日常的な風景や路上の光景にも目を向けていました。1973年にはキヤノンサロンで個展「路傍」を開催し、品川区大井町近辺を中心とした街のスナップ写真を発表しました。この「路傍」シリーズは、中村自身が「モク拾い写真術」と呼んだもので、特定の主題にこだわらず、路上で心に響く情景を切り取っていく独自のスタイルを確立しました。 晩年、中村は自身の写真人生を振り返り、戦前からの未発表作品を含む多数の写真を再検討しました。その成果は1991年に写真集『昭和・裸婦・残景』としてまとめられ、ヌード写真だけでなく、戦中戦後の庶民生活や品川の街の変遷を捉えた貴重な記録としても高く評価されています。
中村は同時代のヌード写真家たちと異なり、コマーシャルフォトを嫌い、あまり積極的に仕事を引き受けない主義でした。「女性や子供に見せても恥ずかしくない写真」を第一とし、「商品」として女性の裸体を撮影するのを避けて、自身の制作に打ち込んだ彼は、金銭面では比較的余裕のない生活を送っていたと言います。
中村立行『おんな : 中村立行作品集』,浪速書房,1965.
戦後ヌードにおける金字塔的な作品。
41. 秋山 庄太郎(1920~2003)

『世界写真全集』第5巻 (日本),平凡社,1956.
撮影者:不明
1920年、東京の神田の青果仲買業を営む家に生まれた秋山庄太郎(あきやま・しょうたろう)は、妾の子だったこともあり、生まれてすぐに伯母の養子となります。3歳までは横浜で育ち、関東大震災の後は都内を転々とします。
彼が初めて写真を撮影したのは13歳の頃、愛犬を写したのが最初の写真で、これが楽しくて次第に写真が彼の趣味となります。
1933年に旧制東京府立第八中学校(現:東京都立小山台高等学校)に入学すると、原節子のデビュー作「ためらふ勿れ若人よ」を観たことをきっかけに学内に非公認の写真部を設立し、勝手に学内展覧会を開くなどします。
1938年に中学を卒業すると、早稲田大学商学部に入学します。この頃にようやく実父が秋山のことを認知するのですが、ギクシャクとした家族関係のために秋山は泥酔して潰れることが多く、親族から一時勘当されることもありました。
大学では写真部で活動を続け、福原信三の主宰する「日本写真会」に作品を投稿して、福原からも評価されたほか、グラフ誌に作品が掲載されることも何度かありました。
大学在学中に学生結婚をした秋山は、この頃に妻のポートレートなどを集めたアルバムを作成していますが、この頃のポートレートを振り返って秋山は「レンブラントの影響がいちばん強かった。僕の女性写真に関していえば、西洋絵画の影響を受けている」と述べています。
1943年に大学を卒業すると、東京田辺製薬(現:田辺三菱製薬)に入社します。このときに、自費出版にて処女作品集『翳』を制作します。戦時下の物資不足の中であったものの、出征目前のなかでどうにか自身の作品を残したいと思い、愛用のローライコードを売り払うなどして資金を作り、150部を製本しました。「翳」というテーマは谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』からとったもので、写真の大半はソフトトーンの女性ポートレートでした。若い女性や芸妓などの写真は、その後の秋山の写真家としての活動ともリンクする写真集です。
この作品集の制作の後、まもなくして召集状を受け取った秋山はカバンにできたての作品集を一冊詰めて、中国に通信兵として渡ります。秋山は終戦までこの一冊を守り抜き、中国大陸で戦いました。
1945年5月、陸軍少尉に昇進した秋山は内地への転属となり、長野県で終戦を迎えます。
___
終戦後は、父親のつてで東京生鮮食料品荷受組合に就職しますが、父親と衝突して間もなく退職。その後は早大写真部の後輩の稲村正隆・土方健一らと「秋山写真工房」を銀座の千疋屋前に構えます。これが本格的に職業写真家として活動を始めるキッカケになりましたが、客はあまり来ず、1947年には借金が膨らみ秋山写真工房は解散します。
その後、林忠彦・石津良介らと写真集団「銀龍社」の結成に参加。同じ頃に、林忠彦の推薦で近代映画社に入社すると映画雑誌『近代映画』のカメラマンとなります。入社後、まもなくして大船撮影所で知り合った原節子と知己を得て、「原節子番のカメラマン」となります。以降、原は秋山の娘の名付け親になるなど、公私ともに深い交流を続ける関係を築きました。
1947年~1951年までの映画雑誌でのカメラマン時代に多くの映画スターと知り合ったほか、ライティングなどの技法を深めます。
1951年、編集方針を巡って編集長と対立が深まり、実質的にクビといえる状況で、勢いのままに近代映画社を退社し、以降はフリーカメラマンとなります。近代映画時代の写真は写真集『美貌と裸婦』に収録されています。
その後は、個展や林忠彦との共同展を開催するほか、グラフ誌での掲載を続けます。
3年間のフリー生活である程度の下地ができたこともあり、1955年に東京の麻布今井町(現:六本木)にスタジオを構えます。当時は、1953年にパリから「クリスチャン ディオール」のコレクションが来日し、「ニュー・ルック」スタイルが大流行したほか、1954年にはオードリー・ヘップバーン主演の『ローマの休日』『麗しのサブリナ』の影響でサブリナパンツやヘップバーンカットが流行するなど新しいモードが隆盛した時代でした。ファッション文化が華やいでいくなかで、女性専科だった秋山はモード写真家として重宝されます。
その後、1960年代には服は「作る」ものから「選ぶ」ものに移行しますが、これもファッション写真の需要を拡大させました。合繊メーカーによる技術発展や品質の規格化、百貨店によるサイズの統一化などが進むなか、高級既製服を手掛けるアパレルメーカーが増えていき、必然的にデザイナーと写真家の連携が密に生まれていくことになります。
1958年に金丸重嶺を初代会長に迎えて日本広告写真家協会が創立されると、秋山も創立会員として参加します(秋山は1971年に第ニ代会長となります)。
その後は雑誌の表紙連載を数多く務めるほか、1950年代の仕事を総括をする作品集『おんな。おとこ・ヨーロッパ』を上梓します。
1966年に日本写真専門学院(現・日本写真芸術専門学校)の講師となり、この頃から花の写真を撮影するようになります。以降、花の写真は秋山のライフワークとなりました。1982年に日本写真専門学院が日本写真芸術専門学校となると、初代校長に就任します。その後、1986年には紫綬褒章を受章、1993年には勲四等旭日小綬章を受章しています。
秋山は晩年、山形県米沢市に「山粧亭」というアトリエをかまえます。「山粧というのは紅葉のことをいうのだが、字解きをしていくと、山形の米沢の庄太郎の家ということになる」というのが名前の由来。この縁により、秋山庄太郎記念米沢市写真文化賞という写真賞が米沢市により主催されています。
そんな秋山は女性の美しさを撮影することの難しさをこう語っています。
「そっくりに撮ると”変な顔”、倍くらい綺麗に撮って“少し満足”、ウソみたいに綺麗に撮るとやっと“ニッコリ”、なかなか感謝してもらえませんよ。」
42. 大竹 省二(1920~2015)

『世界写真全集』第5巻 (日本),平凡社,1956.
撮影者:不明
1920年、静岡県小笠郡(現:掛川市)の運送業を営む家に長男として生まれた大竹省二(おおたけ・しょうじ)は、幼くして母親を亡くし、小学校にあがるまでは親戚の家に預けられるなど転々とした生活で肩身の狭い思いをしていました。1928年、父に連れられ上京し、日暮里で継母と暮らすことになります。大竹のカメラとの出会いはこの頃で、トイカメラをよくいじって一人で遊んでいたといいます。
1933年、京北実業学校に入学すると、父親にトーゴーカメラを買ってもらい、ますます写真に熱を上げるようになります。
トーゴーカメラとは、東郷堂カメラという会社が製造・販売していた、安価でシンプルな作りのカメラです。当時はカメラと現像セットが一緒に販売されており、押入れなどの暗い場所で手軽に現像ができました。価格も1円と比較的安く、特に子供たちの間で人気があったようです(当時の1円は現在の千円程度に相当します)。同じく1円で購入できる簡単なカメラ(「円カメ」と呼ばれた)が他にも多く販売されたため、当時は「円カメブーム」が巻き起こっていました。大竹はそのときのカメラとの出会いが「青天の霹靂」であり「この一個のカメラがよもや私の運命を今日あらしめようとは思わなかった」と回顧しています。
徐々に写真にのめり込んでいった大竹は、父にねだって14歳の頃に初めて本格的なカメラを手にします。この頃から、アサヒカメラの月例に応募するなど、アマチュア写真家としての第一歩を踏み出し始めます。その後、中学5年生の頃には、アサヒカメラの月例コンテストに入選するなど頭角を現していきます。
1940年、父親の命令で、上海にある東亜同文書院に入学しますが、在学中に学徒応召をうけ、ほどなくして内地に帰国します。日本に戻った後、プロの写真家になるチャンスをうかがっていたところ、タイミングよく体外宣伝誌『コマース・ジャパン』の撮影担当として仕事を得ます。雑誌カメラマンとして短い期間を活動していましたが、すぐに陸軍に応召され24歳のときに北京大使館報道部に配属されます。北京では、林忠彦らがやっていた大使館の外郭団体「華北広報写真協会」をサポートする仕事をしていました。
____
北京で終戦を迎えた大竹は、1945年10月に東京へと引き上げますが、以前に暮らしていた家は空襲のために焼け跡となっていました。ただ、幸いにも栃木に疎開していた父は無事で、このときに父から6x6判カメラをもらうこともできました。
家もなく金もなかった大竹は、防空壕を改造して住居にしたり、病院から拾ってきた薬用アルコールで密造酒を作って売ってみたり、とにかく何でも出来ることをしながらその日その日をやり過ごす生活を続けることになります。
そんな生活のなか、たまたま知り合った米軍通信隊員のツテで、ライフ誌東京支局のカメラマンだったジョニー・フローリアの私設助手を務めることになります。
その後、1947年にはGHQの広報部宣伝中隊に嘱託カメラマンとして雇われ、この時期、米軍専用で使われていたアーニー・パイル劇場(現:東京宝塚劇場)で来日した歌手や女優を撮影し、写真家としての技術を磨きます。また、米軍の仕事ということもあり、国内では滅多に入手できなかったカラーフィルムを贅沢に使うこともできました。大竹は、邦人カメラマンとしてはいち早くカラーの衝撃を体験したといえます。
アーニー・パイル劇場での仕事は1年余りで終わり、その後はまた苦しい生活に逆戻りしますが、徐々に雑誌での仕事なども得るようになります。
1950年には三木淳がライフ社に移った後の後任としてINP社東京支局に採用されます。INP社のカメラマンだったグローズ・クラウンの助手を務めますが、すぐ後にクラウンが急逝したため、会社の人員整理によって大竹は退社することになります。
その後は、フリーランス1951年からアサヒカメラ誌で来日する世界の著名な音楽家たちの肖像を撮る連載写真を5年間担当しました。このときの連載は『世界の音楽家』として出版されています。また、1954年には『サンケイカメラ』誌で依田義賢の脚本によるフォトストーリー『白い夢』の写真を担当し、好評を博しています。
1956年、女性を撮る写真家たちのグループ「ギネ・グルッペ」が結成され、この創立メンバーとなります。会員には秋山庄太郎、杵島隆、中村正也らがいました。このころからヌードや女優などを撮ることが仕事の大半になっていき、秋山と並んで「婦人科」「女性専科」と称されるようになります。雑誌文化の復興のなかで表紙写真やグラビアを撮影する仕事などもますます増えていました。
1960年代に入ると、大竹は徐々に映画の仕事も手掛けるようになります。1961年には外務省委託映画「シンフォニー・ジャパン」の演出・監督を務め、ローマの短編映画祭でグランプリを受賞。1963年には石原慎太郎や若槻繁らと映画輸出を目指して「百世紀プロ」を結成しています。60年代後半からはエッセイなどの執筆依頼が激増し、写真以外の仕事もさらに増えていきます。
1971年には日本テレビ「お昼のワイドショー」で、大竹が主婦やOLのヌードを撮る「美しき裸像の思い出」が企画され、数千人の主婦がこぞって応募したことで話題となりました。母と子の「ファミリーヌード」を撮るなど、企画は5年間続くことになり、この頃に大竹の知名度は一段とあがることになります。1970年代には、テレビで乳首を映すことが許されるようになり、バラエティ番組やドラマで特に必要がなくても乳房が映し出されることが増えた時代でした。大竹はこうした時代の流れにうまく乗り、人気を高めました。
1974年には松本清張原作の映画『砂の器』に教授役で特別出演したほか、同じく松本清張原作の映画『わるいやつら』でも部長刑事役として特別出演します。また、有名人の手相や人相による運勢判断を行い、その関連でテレビ出演や一般向けの著書も数多く手掛けています。
ちなみに、沼田早苗やミス・ユニバース日本代表だった織作峰子は、大竹の写真モデルを務めた後、彼に師事し、のちに写真家として独立しています。
大竹はテレビ番組を通して素人ヌードのきっかけを作った立役者といえますが、彼自身は「露骨で興味本位な写真は僕自身好みません。清潔なのがいいですね」というように、扇状的なヌクためのヌード写真とは距離を起きたかったようです。「エロくないヌード」という態度があったからこそ、大竹は多くの主婦の人気を得られたのですが、とはいえこれは、「ぼくは、女性は花と同じじゃないか、という見方」「恥じらいのない女性は少しも美しくない」という彼の発言からもわかるように、女性(のヌード)に対する保守性の裏返しとも言えます。
ちなみに、大竹は当時の女性についてこんな感想を述べています。
「写真とってて思うのは、非常にご都合主義で、保守になったり、えらい進歩的になったり、ケース・バイ・ケースで自分に都合のいいように使い分けするのが今の女性じゃないかと思うな。ズルさといえばズルさ。自分の経験をハッキリ持ってないんじゃないかと思う。ウーマンリブとか何とかヘンに風潮に酔ってしまってね」(1975年産経新聞での発言)
43. 中村 正也(1926~2001)
中村正也(なかむら・まさや)は1926年に横浜で生まれ、戦後のヌード写真ブームの日本の写真界に大きな足跡を残した写真家です。
父親は火災報知器などの製造会社を経営しており、電車の踏切がおりるときの警報音がカンカンと鳴る装置のパテントをもっていたそうです(現在は一連の装置は開放特許です)。父親自身が熱心なアマチュア写真家で自宅に暗室もあるような環境でした。中村は、7歳頃に父親の愛機だったライカで初めての写真を撮っています。写真趣味を子供に伝染させたい父からカメラを買い与えられ、撮影しては父の暗室で現像するという生活だったという。
1938年に川崎市立川崎工業学校の電気科に入学。この頃に父にせがんで鳩舎をつくってもらい伝書鳩を8羽飼いはじめます。中村の後の作品のキーポイントになっている「鳥」との積極的な関わりはここから始まったようです。また、死んだ鳩は解剖して死因を特定しようとしたり、解剖写真を撮影したりと、当時はとにかく熱心で一時は獣医になろうとも思っていました。
1943年、戦争がいよいよ深まっていくと、勤労動員のために大森にあった田中航空計器科学研究室で働きだし、終戦間際の1945年2月には海軍電探学校に入隊します。その後は、戦場には行くことなく終戦となります。
終戦後まもなくして、東京高等工芸学校の写真科(現:千葉大学工学部)に入学し、写真家としての道のりが本格的に始まります。1948年に同校を卒業後は、東洋現像所に務めて映画フィルムの現像を担当しますが、すぐに仕事に飽きてしまってわずか3日で退社します。その後すぐに、読売新聞写真部に入社しますが、新人に任せられる暗室仕事や小間使いの作業に耐えられず、また報道現場での仕事もうまく行かずで、半年あまりで退社します。その後は映画世界社に入社して写真部長の早田雄二の下で『映画世界』『映画ファン』などに掲載する女優のポートレートや映画のスチルを担当しました。映画世界社の後は映画スター社に務め、新劇俳優など舞台演劇のスチルを手掛け、1951年にフリーになります。
フリーになってからは『中央公論』『婦人画報』などで報道写真を掲載するほか、戦後~50年代前半を代表するファッション雑誌『ロマンス』『スタイル』でファッション写真も撮り始めます。
この時期、婦人誌は徐々にファッションページに力を入れだしていましたが、当時はまだプロのファッションモデルがおらず、女優を使ってのファッション写真が多くありました。そういったなかで、中村をはじめとする映画雑誌で経験のあるカメラマンがファッション写真の現場でも多く採用されていました(当時の女性写真を撮る写真家の多くは、このように映画雑誌のカメラマンからの出発でした)。
また。この頃に結婚して、麻布材木町(現:六本木のけやき坂付近)に家を買い、また歌舞伎座前に個人プロダクションの桂写真工房を設立します。
1954年、早田雄二が開設したスタジオに協力参加して、映画雑誌の仕事や着物などの広告写真を引き受けます。この時期の仕事を通じて「グラマーフォトのマサヤ」として形容されることの多い女性写真の撮影技術を磨いていきました。
「グラマーフォト」とは、被写体(女性)のもつ「女性特有の魅力」を引き出すことを最大の目的とするアプローチのことを指します。中村のグラマーフォトの特徴は、彼が被写体となる個人の「人間的魅力」を描くポートレートと、女性全般の魅力を客観的に捉えるグラマーフォトを明確に区別していた点にあります。彼が焦点を当てたかったのは、その人個人の魅力や人間一般がもつ魅力ではなく、あくまで「女性特有の魅力」についてであり、こういった視点を通じてそれまでのポートレートの潮流とは異なる新しいアプローチを打ち出しました(詳しくは中村の著書『グラマア・フォトの写し方』(1957年)を参照ください)。
とりわけ中村立行の写真に見られるように、中村正也以前の女性写真、特にヌード写真では、被写体の女性をオブジェとして扱い、人間のフォルムそれ自体を美的または神秘的な象徴として表現することが重視されていました。中村正也の写真は、このような形式を打破し、女性の魅力/色気を新たな視点で捉えた点で斬新だったわけです。
当時はポートレート、ファッション、ヌードといった分野が未分化で、女性写真はそれらをひとまとめにしたものとして理解されていました。そういったなかで、中村は、女性を美しく魅力的(グラマー)に見せるための写真と、単なるポートレートやファッション写真、ヌード写真とに明確な違いがあるのだと強く主張しました。
1955年に彼の代表作の一つで、坂口安吾との取材旅行の記録を、安吾の言葉と中村の写真で綴った「新日本風土記 坂口安吾」の連載を始めます。なお、連載を開始してまもなく安吾が脳出血のために亡くなったために、連載は一時ストップし、翌年の再開の折には安吾に代わって大井廣介が担当を務めました。
ちょうどこの頃に、妻と離婚したこともあり、中村はつらい日々を酒浸りとなって過ごします。カメラと車それぞれ一台以外すべて酒代に消えてしまっといいます。また、早田のスタジオも退社して、再び完全なフリーランスに戻ります。
1956年、『写真サロン』などで発表した石田正子をモデルとした一連のグラマーフォトが大きな話題を呼び、中村の知名度は一気に引き上がります。翌年には批評家の福島辰夫が主催して開かれた写真展の「10人の眼」展に誘われ。石元泰博、川田喜久治、川原舜、佐藤明、丹野章、東松照明、常盤とよ子、奈良原一高、細江英公と肩を並べて展示を行います。「10人の眼」展は若手写真家たちによる新しい表現を集めての展示会で、木村伊兵衛と土門拳が顧問をつとめた「集団フォト」を乗り越える、次世代の交流場として企画されたものでした。ここでの交流がもととなって、写真家集団「VIVO」が結成され、私的な情感を前面に出した報道写真やいわゆる「映像主義」といった新しい潮流がうみだされることとなります。ただし、中村はVIVOには参加せず、創設まもなくから参加している写真家集団「ギネ・グルッペ」での活動に力を入れていきます。ギネ・グルッペは「婦人科(Gynecology:ギネコロジー)をもじったもので、女性を専門にした写真制作を行うグループです。グループには中村のほか秋山庄太郎や早田雄二、大竹省二らが参加していました。
1958年、新宿でマサヤスタジオを開設します。またこの頃に日本広告写真協会の創設すると同時に入会し、ヌードフォトをグラフ誌に寄稿するほかに『装苑』などのファッション誌でファッショングラビアを担当していきます。その後は、ベネチア・ビエンナーレに出展し、フランス・プリズマ社から写真集『NUES JAPONAISES』を出版し、国外でも徐々に紹介されていきました。
1960年代に入ると、中村の活動はさらに広がりを見せます。
1961年にはマサヤスタジオにコピーライターやグラフィックデザイナーを新規に迎え、広告制作会社として本格的に始動させます。電通・博報堂などの大手広告代理店の依頼を受けて、幅広い広告制作を手掛けていきます。
以降は、一層知名度を上げて、広告制作とヌードフォトの2軸を往復しながら多くの展示会や広告制作に携わります。代表的なものとしては、旭化成の依頼で制作して大阪国際空港ロビーに展示されたジャンボカラーパノラマ「世界の風景と人間」や、日本航空のポスター・カレンダー制作などがあります。
1966年には「ライフ30周年記念号」に委嘱されたヌード作品が日本で最も新しい広告写真と賞賛され、ニューヨーク・アートディレクターズ・クラブ写真賞を受賞するなど、国際的にも高い評価を得ました。 1969年には「野分け」シリーズで、秋の草むらの中にヌードを配置し、日本文学的・叙情的な雰囲気を醸し出す作品を発表。1971年には当時の人気モデル 杉本エマを起用した「エマ ヌード イン アフリカ」で、アフリカの大自然の中に現代的な女性ヌードを解き放つという斬新な試みを行いました。
44. 増山 たづ子(1917~2006)
増山たづ子(ますやま・たづこ)は1917年、岐阜県の山奥にある徳山村で生まれました。
叔父の川口半平は後に岐阜県教育長も務めた教育者で、児童文学者としても著名です。川口夫婦には子供がなかったので、たづ子を養女として迎えられる予定でした。そのため、幼少期は岐阜市の叔父の家で過ごし、教養や和裁を身につけました。
1936年、19歳のたづ子は同じ徳山村出身で名古屋で大工をしていた増山徳治郎と結婚します。婚約が決まったとき、たづ子は徳治郎と面識がありませんでした。知らぬ間に進んでいた結婚の手続きに抵抗するため、彼女は兄のいた中国の旅順へ一時逃避していましたが、徳治郎から毎週のように届く手紙にほだされ、帰国し結婚することになります。
結婚から間もなく、日中戦争が始まり、やがて日本は太平洋戦争に突入していきます。徳治郎は召集を受けて、インパール作戦のために出兵します。もともと名古屋の現場と徳山村を往復する生活だったこともあり、たづ子と徳治郎がともに暮らした期間は1年半程度だっといいます。
終戦後、徳治郎はインパールから帰らず、行方不明扱いとなり、たづ子は何も入っていない白木の箱を"遺骨"の代わりに受け取ります。夫だけでなく弟も戦死した彼女は、この頃はよく自殺することを考えて、太宰治やトルストイなどの著作を読みながら死に方を探していたと言います。じっさい、岐阜市にある金華山の裏から飛び降りて死のうとしたこともありましたが、叔父の説得もあり、たづ子は自殺をとどまり、「死んだつもりで生きとれば、わけない」と思い直します。このとき叔父は、たづ子の手を煮えたぎる鉄瓶に突っ込みながら「体の不自由な人たちも、今は一生懸命生きている。五体満足なお前が、人間としての務めさえ出来ないのか」と説教をしたといいます。
戦後、たづ子は農業をするかたわらで、民宿「増山屋」を営んでいました。そんな折に、1957年に持ち上がった徳山ダム建設計画に直面します。
計画の起こった当初を振り返ってたづ子は以下のよう述べています。
「ダムになっちゃかなわんてな、初めは村一丸となって反対したんだけど、途中から割れたな。若いもんがどんどん町へ出ていくという過疎の問題があってな、この際ダムになったほうがいいという促進派とな、大事なふるさとを水底に沈めてまったら、ご先祖様に申し訳がないという反対派に分かれたな」
「国がやろうと思うことは戦争もダムも必ずやるから、反対するのは大河に蟻がさからうようなもの」
戦争を経験したたづ子にとってダム事業は、心情とは裏腹に受け入れざるを得ないものでした。
その後、2008年にダムが完成するまでの51年間におよぶ徳山村とダムとの歴史は、村内外の政治を巻き込んで、多くの争いを経ながら展開をしていきます。
_____
1957年の当初は建設反対でまとまっていた村民ですが、徐々に意見が分かれだします。「貧しい山村が、立ち上がるためには、ダムをテコに、その補償金で村の中に産業を興す以外に、考えられなかった」と、計画開示時に村長だった江口政之は振り返っています。最終的には、江口の後任として、1968年に村長に就任した根尾定雄が「全村の水没と離村」という方針を固めます。
根尾定雄は1969年に、県当局に改めて「けっきょくダムは造るのか造らないのか」を早く決めるように要望を出したほか、村長や村議会議員がダムにまつわる補償等の問題を話し合う協議会を組織するなど、離村の成功を目指して動きを進めます。
1957年にダム計画が明らかになってから、この時点ですでに12年が経過しており、調査ばかりで一向に建設される気配がない「幻のダム」のせいで、村全体の行政が停滞していました。いつダムになるのか分からない状況で新規事業を始めることも出来ず、かといってダムが建つ具体的な計画も見えてこない。どうせ沈んでしまうのだからと、山や田畑の管理を怠る村民も多くなりだし、村に並んでいた茅葺屋根も、手間がかかるからとトタン屋根に徐々に姿を変えていく。こういった状況に、しびれを切らしてのことでした。
その後、1974年には正式に河川予定地となり、ダム建設工事は決定的なものとなります。とはいえ、こういった動きはほとんどの村民に知らされていませんでした。
これが村民の知るところになるのは、3年後の1977年。根尾と水資源開発公団が交わしていた事務処理のための協定書が明らかになったためでした。ただ、この頃には建設反対の声は小さくなっており、むしろ、補償金の基準をどうするかという金額を争う問題が大きな話題となっていきます。
ダムの現地立ち入り調査がはじまった1972年頃には、ダムの補償金を狙って、旅人を泊めない民宿や客を入れないパチンコ店、バーや喫茶店など、形だけの施設が建ちはじめたほか、実際には暮らしていないのに補償金目当てで住民登録のみを村に残す者も現れはじめ、補償金の魅力に後押しされる形で、ダムが建つのを待望する声が高まっていました。
しかし、補償金を巡る争いはなかなか決着しません。公団側の提示する補償基準を金額が安すぎると、粘り強く交渉を続けたい村民と、早く補償金を得て村を離れたい村民。両者の溝は深まります。村民から自殺者を出すなど、交渉は紆余曲折を経ますが、最後は早期の補償基準策定を求める声が多数となり、計画開始から26年経った1983年に補償基準が調印されます。翌年からは住民の移転がはじまりました。
また、1983年頃に新聞などでダム補償交渉の妥結が近いことが報道されると、村外から金融業者や建築業者が多く訪れるようになります。合計400億円ほどにもなる巨額の補償金を目当てにしてのことでした(補償金は一世帯あたり1千万円から1億円超でした)。県内の建築業者や銀行や信用金庫、村民の移転先にある農協などが、補償金を得た村民を得意先にしようと訪問してきたわけです。農協の貯金口座を作る説明会やモデルハウスの見学会、建築業者による連日の戸別訪問なども増えていきました。
1984年以降、村外へ移住する人々が増えていきますが、移住後もダム工事の影響は続きました。補償交渉の際、移住後の生活には問題が生じないと住民に説明されていたものの、実際には転居先で補償金に対する多額の税金を支払うことになりました。税金のことを全く考慮せず、補償金を注ぎ込んで家や土地を購入する人が多かったため、後に請求された税金に対応できず困窮するケースが相次ぎました。村外での生活経験が乏しく、さらに山間部では税務に関する専門知識にアクセスするのが物理的にも困難だったために起きた出来事でした。
_____
たづ子が村の記録を残そうと思い立ったのは、ダム建設のための本格的な調査がはじまっていた1973年頃のことです。テープレコーダーを買い、村人の歌や民話を録音して歩きました。1977年、たづ子は60歳でカメラを手にし、故郷の記録を始めました。使用したのは「ピッカリコニカ」というストロボを内蔵したコンパクトカメラ。初めてカメラを触った人が暗い場所でも失敗しないで写真が撮れるので人気を得たカメラです。彼女は村の日常や行事、人々の表情を熱心に撮影し、約10万点のプリント写真とネガフィルム約3900本、アルバム約600冊を残します(現像代は一ヶ月に10万円以上、ときには26万円以上にもなりました)。
「夫がいつ帰ってきても、楽しかった村を見せてやれる」。帰らない夫を思いながら撮影したといいます。
たづ子の写真は、1978年に名古屋のカメラ店の2階にあるギャラリーで初めて個展が開かれ、好評を博しました。いつも現像を依頼していた業者が彼女の写真を気に入り、企画したもので、こじんまりとした展示でしたが、大きな話題を呼びます。その展示が注目を集めた結果、デパートや地下鉄の通路など、さまざまな場所で写真が展示されるようになります。
その後、写真集『故郷 私の徳山村写真日記』が出版され、東京でも写真展が開催されました。彼女の活動は各種メディアでも注目を集め、1982年には映画『ふるさと』にも出演しています。
活躍の幅を広げるたづ子の傍ら、この頃、彼女の兄は補償問題に悩み、その苦しみを紛らわすために大量の酒を飲むようになり、アルコール中毒に陥っていました。そして、彼は酩酊状態でいろりに頭を突っ込んでしまい、そのまま亡くなっています(1981年)。
1983年の補償基準の調印後、工事のために村の家々は次々に取り壊され、その残骸はすべて焼かれていきました。一軒一軒、燃える家を撮影していったたづ子は当時を振り返って「燃える家は、村のお葬式だで」と述べています。彼女が村の記録を残す活動を続ける中、たづ子の民宿は、徳山村の記憶を残そうとする村内外の人々が集まる場所となりました。
そして、村で青果商を営む根尾弥七や、徳山小学校の教師を務めていた篠田通弘を中心に、徳山村で出土した土器や独自の方言、俳句、短歌、昔話や説話など、徳山の文化と歴史を記録した『ゆるえ』という冊子が発行されます。「ゆるえ」とは村の方言で「いろり端」を意味します。たづ子の家のゆるえに集まった村民たちが、村の記録を残そうと始めたこの雑誌は、1982年から1984年の間に第6号まで刊行されました。
1984年に「エイボン功績賞」を受賞し、たづ子は社会的にも高く評価されました。しかし、彼女の真の目的は、ダムに沈む故郷の姿を記録し、人々の生きた証を残すことにありました。故郷の記憶を後世に伝えるために全力を注いでいたのです。1985年7月、たづ子は岐阜市郊外に転居しましたが、徳山村との繋がりを絶つことはありませんでした。新居の近くに畑を作り、徳山の草花を植えて、孫たちに自然を大切にする心を教え続けました。
増山たづ子の写真は、失われゆく山村の暮らしや文化、そしてそこで生きる人々の表情を生き生きと捉えています。彼女の取り組みは単なる記録を超え、人々の記憶や感情、そして生活の歴史を未来に伝える貴重な遺産となりました。彼女の遺志は「増山たづ子の遺志を継ぐ館」によって引き継がれ、写真展や講演会を通じて、徳山村の記憶が今も語り継がれています。
2006年3月、88歳で彼女が亡くなってから半年後、徳山ダムの試験湛水が始まり、旧徳山村の跡地は水没します。たづ子は、村が沈むその瞬間をシャッターに収めることなく、この世を去りました。
朝日新聞社岐阜支局 編『浮いてまう徳山村 : わが国最大の「ダムに沈む村」からの報告』,ブックショップ「マイタウン」,1986.
ダム事業に伴う自治体内部での争いや、開発業者を含む村外企業が利権目当てに参入していた様子が記載されている。
徳山村は250k㎡以上の広大な面積を持つ自治体で、最盛期には約2300名(1960年)の住民が暮らしていました。「村」という言葉からは小さな集落を連想しがちですが、人口密度こそ低いものの、決して少ない人数がそこで生活していました。また、面積だけで比較すると大阪市よりも広く、この広大な地域の大部分がダムに姿を変えたことを考えれば、この事業がいかに大規模であったかが想像しやすいでしょう。
ダム技術センター 編『ダム技術』(165),ダム技術センター,2000.
ダム開発事業者の側からみた増山さんの印象が記載されている。
45. 清岡 純子(1921~1991)
清岡純子(きよおか・すみこ)は1921年に京都御所の近くで生まれました。父親は貴族院議員で子爵の清岡長言。母も同じ子爵の位を持つ唐橋家の出身で、生え抜きの「貴族」でした。5人きょうだいの末っ子だった彼女は小さいことからオテンバで、父の長言からは「おとなしくしないと尼寺にやるぞ!」と叱られてばかりだったそうです。
京都府女子師範附属小学校を卒業後は、父親が校長を務めていた菊花高等女学校へ入学。その後は、東山京都女子専門学校(現:京都女子大学)へ進学するも身体が弱かったために中退します。
純子の写真家としての第一歩は1948年。新日本新聞社とキネマ画報社の写真部に所属したことに始まります。報道カメラマンとしてのキャリアを重ねたのち、1957年に大阪の新歌舞伎座の写真部に転職しブロマイドなどを撮影にいそしみますが、芸能界の雰囲気に馴染めず、1960年に退社します。
写真家としての仕事を失った純子は、退社後にチャームスクール(=フィニッシングスクール:女性の礼儀作法を教える学校。日本では80年代以降に花嫁修業の学校としてとくに広がった)を開校します。欧米流の新しい美容や女性美の流行の中で、1957年に大関早苗が日本初のチャームスクールを開校し、メディアの注目を集めていました。純子は、華族出身の経験を活かして、この潮流に乗ろうとしたわけです。
1965年、純子は東京に拠点を移し、フリーのカメラマンとして活動しだします。フリーになった純子は、1967年に『尼寺』を出版。中宮寺の住職である日野西 光尊の叔母であるほか、華族出身のコネで門跡寺院の住職とは深い交流のあった純子は、一般の人が垣間見ることのできない尼寺の生活を撮影することが出来ました。出版後には東急百貨店で展示会が開かれるなど好評だったといいます。
その後も、『門跡尼寺秘蔵人形』(1973年)を出版するなど、尼寺との関わりは深く、尼門跡人形使節として訪米もしています。
1974年には小田急百貨店で「門跡尼寺秘蔵御所人形と清岡純子写真展」が開催され、会場には華族出身者として縁のある三笠宮妃百合子や島津久子も訪れました。また、この年に彼女はポーランド国際芸術写真協会主催による「ビーナス'74展」に裸婦作品を出展し、日本人として初の受賞をしています。
報道出身の純子は社会派カメラマンとしての活動も続け、この頃はベトナムや沖縄などを取材してまわり、新聞などに報道写真を寄稿しました。
寺院との関わりや報道に基づいた仕事を続けながらも、1960年代から1970年代以降の純子の活動は大きく2つに分かれていきます。一つは、1970年代前半まで積極的に取り組んでいた「レズビアン写真家」としての活動。もう一つは、1970年代後半から晩年まで続いた、少女や少年を被写体とする活動です。
_________
終戦後、新体制の中でさまざまなセクシュアリティが広がっていきました。特に、男性同性愛(ゲイ)の表面化は顕著であり、1950年代後半には「シスターボーイ」や「ゲイバー」が注目され、「第1次ゲイブーム」ともいえる現象が起こりました。しかし、その時代でも、女の人同士が恋愛する「レズビアン」についてはあまり表に出ることがありませんでした。
雑誌にレズビアンについての記事が載ることもありましたが、それはほとんど男性が面白がって書いたものばかりで、実際にレズビアンの人たちがどんな気持ちでいるのかはあまり語られませんでした。むしろ、レズビアンに対して、男性の性的な欲望の視線が向けるような、男性目線の語りのほうが多くありました。これは、レズビアンが「性的な快楽を求める」「自由奔放な性を持つ」女性として誤解されていたからです。女性が性欲を持ったり、それを楽しもうとすることは「色情狂」とされ、異常な性欲を持つ変態と見なされていました。このような間違った考えから、「自由に性を楽しむ女性なら、男の人の欲望にも応じるだろう」「レズビアンなんて俺が治してやる」といった見当違いな言説が広まってもいました。このようにして、1950年代から60年代にかけて、レズビアンは次第に「ポルノ」の一部として扱われるようになっていったのです。こういったなか、1969年6月に純子は雑誌『現代』に「倒錯したわが愛の告白」と題する回想記を寄稿して、自身がレズビアンになった経緯を公にしました。同誌では赤裸々に女性同士のセックスの方法について記載されており、1960年代においてはかなり異質な語りでした(純子がレズビアンであることを明らかにしたのがどのタイミングだったのかは調べられませんでしたが、遅くとも1968年には公にカミングアウトしていました)。
その後、1971年に日本初のレズビアンサークル「若草の会」が登場し、徐々にレズビアンの社会運動は拡大していきますが、純子の活動はそういった動きの先駆けだったといえます。
純子は日本におけるレズビアン活動の先駆者として『女と女 レスビアンの世界』(1968)、『告白ー女と女の悦楽 濃密なる愛撫の応酬〈ほんとのレズ〉』(1969)『レスビアンラブ入門 心に愛を唇に乳房を』(1971)、『How to Les / 女の聖書』(1972)、『禁断の魔女 清岡純子のラブ・フォト』(1973)をたてつづけに出版し、いずれも大きな反響を得ます。「性の解放」が謳われる一方で、ヌード写真として流通しているのはあくまで男性目線の女性ヌードであり、女性の目線で女性の性的欲望や衝動について描写するものは皆無でした。そんな状況で、純子は新しいイメージを作り出していきました。
______
「尼寺」「御所人形」「裸婦」「レズビアニズム」と、女性的美を題材にした作品を生み出してきた純子は、1977年に初めて少女をテーマとしたヌード写真集を出版します。「聖少女」と題されたその作品は好評を博し、翌年から1980年にかけて新聞社主催による「清岡純子写真展」が全国各地のデパート(とくに三越)で毎年開催されました。
当時、少女のヌード写真はポルノというよりも(少なくとも体裁上は)芸術写真を志向したものでした。たとえば、1971年には、「彼女はまだ11才。どう育つでしょう、セックスセックスセックスの世の中で」というコメントを添えて、長友健二の撮影した11歳の女性のヌード写真が毎日新聞に意見広告として掲載されています。これは「性の解放」に対するカウンターとして”無垢”で非性的な少女を演出したものでした。
また、沢渡朔が8歳のモデルを撮影し、1973年に出版した写真集『少女アリス』には、著名な文芸家である瀧口修造と谷川俊太郎が詩を提供しています。このことからも、この作品がポルノではなく芸術写真の文脈に位置づけようとして制作されたことがわかります(もちろん、読者がそういった文脈を適切に受け取っていたかはわかりません)。純子のヌード作品がデパートで展示されていたのも、こういった背景を受けてのことでした。
純子は1977年『聖少女』を皮切りに、その後1983年まで毎年「聖少女」シリーズを出し続けました。特に1983年に出した『私は「まゆ」13歳』が大ヒットし、少女写真の分野で確固たる地位を築きました。この成功を受けて、1981年には季刊誌『白薔薇園』、1982年には月刊誌『プチ・トマト』を発刊することになります。しかし、本人も振り返るように、この頃から「粗製濫造と言うか儲け主義と言うか、ええかげんな事になってしもて。あと…中略…露出度やらなんやらがだんだんエスカレートしたり」していき、当初の芸術としての方向性は影を潜めて、ロリコンブームを背景にした商業的な側面が露骨になっていきます。結局、『プチ・トマト』42号が1987年に摘発を受け、43号の発売前に廃刊されます。以降は性的描写を抑えるという約束のもと、雑誌『フレッシュ・プチトマト』を創刊しリスタートします。
当時の性描写規制を理解するうえで重要な点として「陰毛」(ヘアヌード)の扱いが挙げられます。
1960年代以降、写真誌やピンク映画(成人向けの映画)を中心に、ヌードの表現が徐々に増えてきました。特に1960年代後半になると、日本テレビの深夜番組『11PM』や、映画監督・若松孝二のピンク映画、さらに寺山修司のアングラ演劇(地下演劇)などが、積極的にヌードを扱い始めます。このような時代背景の中で、警察によるわいせつ物の取り締まり(刑法第175条)に関して、暗黙のルールが次第に形成されていきました。そのルールとは、「乳房は映してもよいが、陰毛や性器は映してはならない」というものです。これは明文化された法律ではなく、自然と出来上がった不文律であり、表現者やメディアはこのルールに従いながら、創作や表現を行うことを余儀なくされました。この規制の中で、映画や雑誌は様々な工夫を凝らしながら、ぎりぎりの表現を模索していったのです。
あたらしい脱法な性表現を模索する中で、現れたのがビニ本(ビニール本)です。
ビニ本ブームが始まった場所は、神保町にある芳賀書店とされています。この書店では成人向け雑誌の売り上げがとても良かったため、コーナーを拡大することになります。その際に、立ち読みを防ぐため、雑誌を中が見えないようビニール袋に包んで販売したところ、購入する人がむしろ増えて、店の売り上げがさらに伸びました。その結果、1979年にはビニ本に特化した支店、「芳賀書店 神田古書センター店」をオープンします。この新店舗はニュースや雑誌でも取り上げられ、一躍有名になり、ビニ本ブームが広がるきっかけとなりました。こういったビニ本では、薄い肌着が濡れて透ける「透けパン」と呼ばれるスタイルが流行しました。建前上は下着を履いているものの実際には陰毛が透けて見える「透けパン」という工夫により、規制の隙間をすり抜けながら扇状的な商品を提供しようとしたわけです。また、こうしたポルノ雑誌を販売する自動販売機が各地に設置され(自販機本)、1978年から数年間、このジャンルは大きな盛り上がりを見せました。しかし、1980年に芳賀書店の当時の取締役が猥褻物の販売を理由に逮捕されるなど、警察の摘発や行政からの指導は次第に強まっていき、陰毛が透けるような写真表現は一時的に流通から姿を消すことになります(こういった表現は90年代以降のヘアヌード解禁にともなって再登場します)。
そういったなかで、新たに注目されたのが「少女の裸」だったのです。1980年代の日本では、「陰毛」の有無が猥褻かどうかを判断する基準とされていました。そのため、陰毛が透けて見えるビニ本は規制されましたが、陰毛が生えていない少女の裸(より露骨に当時の表現を引用するなら「少女のワレメ」)については、猥褻とは見なされていませんでした。その結果、ビニ本規制の後は、18歳未満の子どもの裸(少女ヌードがおもであったが、少年ヌードもあった)が紙面の多くを占めていくことになります。また、これらのヌード写真を扱った本は、成人向け書籍のコーナーではなく一般的な「写真集」のコーナーに配されることも珍しくなく、そういった点も流通を助長していました。
このように、芸術性を追求したいカメラマン、商魂たくましい出版社、ビニ本の代わりが欲しい読者の思惑が重なりあい、この三者の欲望の帰結として少女ヌードは市場を席巻していきました。ただし、このブームの寿命は短く、1985年を境に終息していきます。
1985年4月、練馬区の職員が少女に対して暴力行為を行い、その様子をロリコン雑誌の『ヘイ!バディー』に投稿していたことが発覚し、大きな社会問題になりました。また、アメリカのヌーディスト村を撮影した写真集『モペット』の輸入にあたって、写真集に掲載されていた女児の陰部が猥褻図画にあたるかどうかを争って1980年から続いていた裁判が決着し、1984年に「猥褻図画にあたる」として判決が確定したこともあり、子どもの陰部露出を法的に規制することが可能になっていきました。
そういった流れを受けて、1985年10月に『ヘイ!バディー』の特別号『ロリコンランド8』を含む3つの雑誌が、猥褻図画頒布の容疑で摘発されます。加えて、1989年に連続幼女誘拐事件(M君事件)が発生するとロリコンに対する世間からのバッシングは一層強くなっていきました。純子の『プチトマト』もこういった動きの中で発禁となります。
______
性描写が問題とされ、発禁となった『プチトマト』ですが、陸上自衛隊が撮影協力のため戦車を貸し出したり、フジテレビが撮影に同行して取材をするなど、当時はそれほどアングラな存在ではありませんでした。
また、季刊誌『白薔薇園』が創刊された際には、0歳から100歳までの女性ヌードをテーマにした「清岡賞」という賞金100万円のコンテストが企画されましたが、この企画には、中尾ミエや菅原文太、村上龍、横尾忠則、渡辺貞夫、石坂浩二、桜田淳子、ジョーン・シェパードらといったさまざまな分野の著名人が審査員として参加しており、一部の審査員は自ら少女のヌード撮影に挑戦することもありました。
少女を巡るポルノ的な需要/受容が徐々に強まっていく時勢においても、このように純子の写真は依然として「芸術」としての位置づけを保とうとして(ないし、保って)いました。ファインアートの体裁を取りつつ、著名人を巻き込んだことで、一連の写真集を芸術作品として評価させようとしていたわけです。
彼女はそういった自らの立ち位置を、「私個人としては少女は好きな事、ないんです。ただ写真の素材として美しいと思うから撮ってるんでね」と述べています。
一連の発禁騒動の少しあと、1991年に純子は亡くなります。葬儀には彼女の被写体を務めた女性も数名参加したといいます。
没後、功績をまとめた遺作集が数社から刊行されましたが、1999年の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の施行に併せて、これらの書籍を絶版となりました。また、2005年には国立国会図書館蔵書の「清岡純子写真集 Best Selection!」が児童ポルノの認定を受け、同館では閲覧不可となっています。
______
「女性とは何か?」という問いを追い続けることが、純子の一貫したテーマでした。彼女は、美しさや悲しさ、そして醜さといった、女性が持つあらゆる面を探し求めていました。これが、彼女の作品に共通する課題であり、レズビアン写真や少女写真は、そういった女性の身体が見せるさまざまな姿や感情を見つけ出すための手段だったといえるかもしれません。
城市郎「好色本のヘンな描写」『新評』17(2),新評社,1970.
清岡の『告白』(1969)の書評が載っている。
上野昂志「大流りの『少女ヌード』の階層化」『マネジメント』40(12),日本能率協会,1981.
賞金100万円を掲げて清岡が設立した、少女ヌードを対象とした写真賞の「清岡純子賞」に1592点の応募作品があったことが紹介されている。
なお、上野のいう少女ヌードの階層性とは、被写体の階層性のことを指している。清岡などの"予算のあるカメラマン"は、ヨーロッパに出向きそれなりの金額を支払って白人少女のヌードを撮影するが、ビニール本に載せる写真を撮影しているような予算の少ないカメラマンは、「東南アジアで間に合わせ」たという。
佐藤眞一 「『児童ポルノ』制限に思う」 日本図書館協会図書館雑誌編集委員会 編『図書館雑誌』99(9)(982),日本図書館協会,2005.
梅崎進哉『チャタレー体制下のわいせつ概念とその陳腐化 -ろくでなし子事件を素材として-』西南学院大学法学論集, 50(4) 1-78, Mar, 2018.
46. 田中 光常(1924~2016)
田中光常(たなか・こうじょう)は、1924年5月11日に静岡県の蒲原町で生まれました。彼の家系は明治時代の政治家である田中光顕を祖父に持ち、その影響から若くして様々な知識を吸収する環境にありました。彼は東京の第一市立中学校(現・九段中等教育学校)を経て、1944年に函館高等水産学校(現在の北海道大学水産学部)を卒業後、海軍に任官しました。終戦後は一時的に漁業に従事しますが、肺を病んだことをきっかけに療養中に写真に興味を持つようになりました。
田中が写真に対して抱いた最初の関心は、当時としては珍しい「動物写真」という分野でした。写真家松島進が主宰する研究会に参加し、技術を磨いていく中で、1950年代初期にはフリーランスとして活動を開始します。当初は科学雑誌や園芸雑誌向けの撮影を行っていましたが、次第に野生動物の写真へと専念するようになります。
1963年から1965年にかけて、彼の代表作である「日本野生動物記」が『アサヒカメラ』誌に連載され、国内外で動物写真家としての名声を確立しました。この作品により1964年には日本写真協会賞新人賞、さらに日本写真批評家協会賞特別賞を受賞します。これを機に、田中は動物写真家としての道をより深く探究することになります。1966年には続編「続・日本野生動物記」を発表し、その集大成として1968年に『日本野生動物記』として出版されました。
1965年にはアフリカへ取材旅行に出かけ、これ以降、田中の活動は日本国内にとどまらず、世界各地の動物を撮影することに専念しました。彼の作品は単に動物の姿を捉えるだけでなく、動物たちの自然な姿や生態を写真に記録することを重要視していました。このアプローチは、当時の技術や情報が限られた時代にあって、先駆的なものでした。
田中の仕事は、数多くの著書にまとめられています。たとえば、1968年に出版された『カラー 日本の野生動物』や、1970年から1972年にかけて出版された『世界動物記』(全5巻)などがその代表例です。また、彼の写真に対する思考をまとめたエッセイとして、『世界の動物を追う:動物撮影ノート三十年』や『動物への愛限りなく:世界の野生動物紀行』なども発表されました。これらの作品は、彼が動物写真家としてどのような哲学を持っていたかを示しています。
田中の写真思想は、動物に対する敬意と愛情を基盤にしています。彼は、動物の生態を単に観察するだけでなく、その感情や行動を写真を通して表現することを目指していました。また、田中の写真は、動物たちが生きる自然環境の美しさと儚さをも映し出しており、これにより自然保護の重要性を訴え続けました。
「いい写真を撮ろうと鳥の巣を動かし枝を折る。そのことによって確かに素晴らしい写真はものにできるが、折角、天敵から守るために作った巣がむき出しになり、雛はカラスの餌食になる。そうでなくとも無理矢理細工をして残した人間のニオイは、結局、動物達の生態系を破壊してしまうことになるんです」
彼の活動は、写真業界だけでなく、自然保護運動にも大きな影響を与えました。田中は日本パンダ保護協会の会長を務めたり、世界自然保護基金(WWF)の日本委員会評議員としても活動し、環境保護に尽力しました。これらの功績により、1989年には紫綬褒章を、2000年には旭日小綬章を受章しています。
世界野生動物記シリーズ
田中光常『野生の家族 (教養カラー文庫. 田中光常の野生の世界 5』,社会思想社,1976.
47. 長野 重一(1925~2019)
長野重一(ながの・しげいち)は、1925年に大分県で生まれ、7歳の時に東京に移り住み、以後亡くなるまでを東京で過ごしました。
中学生の頃から写真部で活動し、写真に興味を持ち始めます。その後は慶應義塾大学に進学し、在学中に写真サークル「フォトフレンズ」に参加。そこで、写真家の野島康三から指導を受けます。
1947年に慶應義塾大学経済学部を卒業した長野は、当初商社に就職しましたが、すぐに別の道へ進むことになります。慶應の先輩である写真家の三木淳の紹介で、名取洋之助が創刊準備を進めていた『週刊サンニュース』に編集部員として採用され、商社はわずかひと月で退職。その後、サンニュースフォトスに入社し、編集の仕事を担当するとともに、木村伊兵衛の撮影助手としても活動しました。
そんな中、ある日取材で訪れた養老院で、カメラマンが用意できなかったため、代わりに長野が撮影を担当することになります。このときに撮影した写真《養老院の老婆》をコンテストに応募したところ、特選に選ばれました。これをきっかけに、長野は写真家としての道を歩み始めます。
長野が初めて大きな注目を集めたのは、1949年から岩波書店の『岩波写真文庫』の制作に携わった時期です。この文庫は、戦後の日本の風景や文化を写真とテキストで伝える大規模なプロジェクトでした。『週刊サンニュース』は1949年3月に廃刊となりましたが、長野はその少しあとに名取の誘いを受け、岩波映画製作所に入社。彼はそこで、岩波写真文庫の撮影を担当するようになります。長野は約60ものタイトルで撮影を担当しましたが、次第に説明的な写真を撮ることに物足りなさを感じるようになり、1954年にフリーランスの写真家として独立します。
フリーランスになった長野は、ドキュメンタリー写真の世界に足を踏み入れ、客観的な報道写真ではなく、彼自身の視点から日本を切り取る写真を撮り始めます。1956年には、木村伊兵衛と土門拳が顧問を務める若手写真家グループ「集団フォト」に参加し、1959年まで「集団フォト展」に出品しました。1958年には、初の海外取材で香港に渡り、その年の東京での初個展「香港」を開催しました。
1960年には、東ベルリンで開催された国際報道写真家会議に日本代表として出席し、東西ベルリンを取材。その成果をもとに、個展「ベルリン-東と西と」を発表し、雑誌にも掲載されました。また、この年に『アサヒカメラ』で連載された「話題のフォト・ルポ」では、安保闘争における警視庁機動隊や、高度経済成長期のサラリーマンの日常を写した作品が注目を集め、日本写真批評家協会賞作家賞を受賞しました。
長野は、社会の出来事を写真家自身の問題意識から捉える撮影手法を「フォトエッセイ」と位置づけ、客観性を重視する従来の報道写真とは異なる手法を追求しました。彼のドキュメンタリー写真への姿勢や考え方は著書『ドキュメンタリー写真』(1977年)でまとめられています。
また、フリーランスになった後は、カメラ雑誌に技法に関する記事を寄稿し、次第に週刊誌や総合誌の仕事も手がけるようになります。その後、1967年から1970年まで『朝日ジャーナル』のグラビアページの企画・編集を担当し、森山大道や深瀬昌久といった当時の若手写真家たちを積極的に起用しました。このように写真界とのつながりを保ちながらも、次第に自ら作品を発表する機会は少なくなっていきます。
1960年代に入ると、長野は写真よりも映画やテレビCMの撮影に力を入れるようになります。1959年に岩波映画製作所のテレビ記録映画「年輪の秘密」シリーズの一つである『出雲かぐら』の撮影を担当。これは、映画監督の羽仁進からの誘いによるもので、以降は多くの映画で撮影を担当するようになりました。
彼が手がけた映画には、市川崑監督の『東京オリンピック』(1965年、一部撮影と編集を担当)、羽仁進監督の『アンデスの花嫁』(1966年)、市川崑監督の人形劇映画『トッポ・ジージョのボタン戦争』(1967年)などがあります。
また、1960年代末から1970年代にかけては、テレビCMの撮影にも多く携わり、1973年にはレナウンの「イエイエ」CMでADC賞を受賞しました。この時期、映画監督の大林宜彦とともに多くのコマーシャルフィルムを制作し、後に大林監督の『日本殉情伝 おかしなふたり』(1988年)、『北京的西瓜』(1989年)、『ふたり』(1991年)などの作品で撮影を担当しました。こうして長野は、映画やCMの世界で映像作家としての存在感を高めていきます。
再び写真に専念し始めたのは1980年代になってからです。バブル景気に沸く少し前、徐々に自身の記憶の中にある東京の風景から遠のいていく街の様子を、「遠い視線」というテーマで見つめようとする試みをはじめました。違和感を抱かせるような風景を、やや距離を置いた視点で冷淡に捉えた一連の写真は、写真集『遠い視線』(1989年)や『東京好日』(1995年)にまとめられています。
長野は、街を歩きながら撮影することについて「日頃見慣れた街がその日だけ見せる表情が面白い」と語っています。また、「28ミリというカメラのレンズは人間の目に一番近いと思う。できるだけ人が街を見る視線、同じ高さ、同じ角度で街を写す。それが街を歩く写真の一番の楽しみです」と、好んで28ミリのレンズを用いていました。
1990年代以降になると、長野の半世紀にわたる軌跡を振り返る写真展が多く開催されました。代表的なものに「私の出逢った半世紀」(1994年)や「この国の記憶 長野重一・写真の仕事」(2000年)などがあります。こうした展覧会を通じて、長野の長いキャリアとその中で培われた独自の視点が広く評価されるようになりました。
48. 大辻 清司(1923~2001)

『世界写真全集』第5巻 (日本),平凡社,1956.
撮影者:不明
大辻清司(おおつじ・きよじ)は、多くの美術家や音楽家と交流しながら試みた実験的な写真作品や、写真とデザインの融合を推し進めた活動などで知られる写真家で、桑沢デザイン研究所や東京造形大学、筑波大学、九州産業大学等で教鞭をとり、教育者として多くの優れた写真表現者を輩出したことでも知られます。
1923年に東京市城東区大島(現:江東区大島)に生まれた大辻は、機械技師の家庭で育ちました。小学校の修学旅行で叔父からカメラを借りたことをきっかけに写真を撮るようになり、中学時代に写真雑誌『フォトタイムス』のバックナンバーをまとめて入手したことから、最新の海外の前衛的な写真の動向や、美術評論家の瀧口修造の評論などに触れ、シュルレアリスムや前衛写真に強く惹かれるようになります。
1942年、大辻は東京写真専門学校(現在の東京工芸大学)に入学しましたが、1943年からはじまった文系学生に対する学徒出陣のために陸軍に召集され大学を離れます。千葉県柏の航空教育隊に入隊した後、全国を転々としたのち、福生の航空整備学校で少年兵への航空整備の教育等を担当していたおりに終戦を迎えます。
戦後に復員すると、写真スタジオに勤務して経験を積み、その後は美術家の斎藤義重の誘いで、斎藤が当時勤務していた雑誌『家庭文化』の編集部で編集と写真撮影の仕事に携わります。ここでの斎藤やその他のアーティストとの出会いが、彼のその後のキャリアに大きな影響を与えました。
1947年には新宿で自身の写真スタジオを開業し、商業写真家として活動を始めました(とはいえ、経営はまったく上手くいかず、一時はスタジオに製麺機を持ち込んでうどん製造をして日銭を稼ぐなどもしていました)。
1949年には、上野の東京都美術館で開催された美術文化協会の「第9回 美術文化展」に作品《いたましき物体》を出品し、美術文化協会に新設された写真部の会員となり、この頃から、オブジェなどを用いた前衛的な写真表現に取り組むようになり、前衛写真家としてのスタートを切ります。また、同年に、東京写真専門学校の同窓たちと写真同人誌『ほとがらひい』を創刊し、写真に関する論考を執筆するようになっています。
1953年、大辻は瀧口修造を指導者とする前衛芸術グループ「実験工房」に参加します。このグループには、北代省三、福島秀子、駒井哲郎、山口勝弘といった美術家たちや、園田高弘、武満徹、湯浅譲二などの音楽家たちが名を連ねており、ジャンルを超えた総合的な芸術表現に取り組んでいきました。
また同年に、大辻はデザイナーの伊藤幸作や浜田浜雄、写真家の樋口忠男、土方健一らと共に「グラフィック集団」を結成します。写真とデザインの新たな融合を目指し、戦後日本の商業美術に「グラフィック・デザイン」という概念を浸透させる活動にも取り組みました。
この時期の大辻の作品は、構成主義やシュルレアリスムの影響が強く感じられ、物体や空間に対する鋭い洞察力を持った作品が多く制作されました。『アサヒグラフ』誌のコラム「ΑPN」のカット写真を担当したほか、日本初の実験映画ともされる《キネカリグラフ》(石元泰博・辻彩子と共作でタイトルは瀧口修造の命名)もこの頃に作成しています。《キリカネグラフ》はカナダの実験映像作家ノーマン・マクラレンに触発されて製作されたもので、16ミリフィルムに染料やマジックインキで直接絵を描いたり、黒く現像したフィルムを針や金鋸の歯で削って模様をつけるなどの実験的な技法を用いて製作されました。
大辻は1950年代初頭より『美術手帖』、『みづゑ』、『リビングデザイン』、『新建築』など出版メディアでの撮影仕事を手掛けるようになり、1956年には新潮社と『芸術新潮』の嘱託カメラマンの契約を結びます。1970年代まで美術雑誌、建築雑誌や企業PR誌などさまざまな出版物のための写真撮影を担当していました。
1950年代後半からは、徐々に教育者としての側面が目立つようになります。1958年に創設されたばかりの桑沢デザイン研究所で講師に就任したのを皮切りに、東京綜合写真専門学校、東京造形大学、筑波大学、九州産業大学などで教鞭を執り、高梨豊や牛腸茂雄、畠山直哉などの多くの後進を育てました。
1960年代以降、大辻は「実験工房」や「グラフィック集団」での活動を通じて、美術、デザイン、映像、音楽、建築など、同時代のさまざまな表現者と密接に関わりながら、多岐にわたる実験的な写真表現に取り組んでいきました。また、1975年には写真雑誌『アサヒカメラ』にて「大辻清司実験室」を通年で連載し、1989年には『写真ノート』をまとめ上げるなど、写真の特性に対する深い考察を綴った多くの著述を残し、写真の理論的な側面において、後続の写真家たちに広く影響を与えました。
大辻清司を語るうえで重要なテーマとして「コンポラ写真」があります。
1960年代末頃、日本の若い写真家たちによる日常的光景に淡々とアプローチする新しい写真の傾向を敏感に察知した大辻は、そういったスタイルの写真に「コンポラ写真」という名前を与えます。
この「コンポラ写真」という名称は、「コンテンポラリー(同時代の)写真」を略したものです。日本で現れた新しい写真の傾向と、1966年にアメリカ・ニューヨーク州のジョージ・イーストマン・ハウスで開催されたグループ展「Contemporary Photographers: Toward a Social Landscape」で紹介された作品との間に共通する特徴があったため、この名が生まれました。このアメリカでの展示会は、ネーサン・ライアンズがディレクションを務め、ブルース・デイヴィッドソン、リー・フリードランダー、ゲイリー・ウィノグランド、ダニー・ライアン、デュアン・マイケルズの5人の写真家が参加しました。
「コンポラ写真」という呼称がメディアで初めて使われたのは、1968年6月号の月刊写真雑誌『カメラ毎日』の特集「シンポジウム/現代の写真:『日常の情景』について」でした。この特集は、若い世代を中心に自然発生的に流行の兆しを見せ始めた新しい写真の傾向を取り上げたもので、そういった新しい写真の総体を大辻がコンポラ写真と呼んだことがこの用語の始まりです。座談会の内容は広く反響を呼び、やがてここで紹介された作品の新傾向は、『カメラ毎日』以外の写真雑誌や、写真以外のメディアでも取り上げられるようになります。
この特集のなかで、大辻はコンポラ写真のいくつかの共通した特徴を整理しています。まず、これらの写真は、素人のようにシンプルにカメラを使い、横位置で撮影されたものが多く、技巧や構図に過度な工夫を凝らしていません。被写体には、日常のありふれた風景や事象が多く選ばれています。また、変わった対象を撮影する際でも、それを強調せず、日常の風景に溶け込むように引き気味に撮るのが特徴です。これらの写真は、身近な事物を軸にプライベートな心境を表現するようでもありました。要するに、これらの写真はそっけなく、「日常ありふれた何げない事象」を捉えたものといえます。
こういったコンポラ写真に対する反応はさまざまで、一歩引いた表現がノンポリ的にみえる点に時代性を見出し、共感を示す意見もあれば、逆に、激動する時代に背を向けて内向的な態度をとる表現だとして否定的に評価する声も少なくありませんでした(00年代批評的に翻訳をするなら、コンポラ写真はセカイ系への批判とだいたい同じような意見を受けていました)。
大辻自身は、コンポラ写真について「外へ働きかける力がどんなに無力であるかを思い知らされた諦観の現われ」や、「目をつぶっていれば平和で安穏であるかに思えてくる世情とも関係しているかもしれない」と指摘しており、必ずしもその新しい表現を肯定的に捉えていたわけではありません。
加えて大辻は、「表現を仕事とする人たちには、うつり変わる事態にもはや論理をうちたてる暇がないし、ぐらついた価値観の上にどんな論理も立てようがない。…中略…一人一人がお互いに、自分の論理をもつほかはないのである。それが相互に通じ合うものであるかどうか、一つの方法として表現をとおしてぶつけ合い確かめ合うほかはない。こうして主義の時代は、今や遠ざかりつつある。通じ合うのは、現状一般の認識である」というように、諦観や瞑目が時勢の産物であると捉えていました。
富山由紀子(2022)は、こういったコンポラ写真の隆盛の背景には、カメラ雑誌に掲載される写真が、報道や広告分野のプロフェッショナルワークに占領されていき、雑誌を購買するアマチュア読者との間に亀裂が生じていたことがあるといいます。そういった亀裂の修復のために、日常性を軸とした技巧を凝らしていない写真の評価する向きがあったというわけです。とはいえ、伊奈信男は「かつて戦後の日本でリアリズムが盛んに騒がれたことがある。そして、だれもかれもが非常に安易にスナップして、それがいわゆるチョロスナといわれた。それで、コンポラが盛んになってくると、今度はコンポラにもチョロスナが始った。(笑い)」と、うわべだけを真似て「コンポラ風」な写真を撮るエピゴーネンが生まれていることに、釘を刺してもいます。
『カメラ毎日』での大辻の寄稿以降、コンポラ写真の概念は徐々に広まり、論じる人が増えていく中で、この概念を論じる側の認識も拡散していきました。次第に、大辻の定義に収まらない写真までもがコンポラ写真として扱われるようになり、その意味はさまざまな立場や議論、作品によって広がり、複雑化していきます。
1968年に創刊された同人誌『provoke』で旗手を務めた中平卓馬や、同誌第二号から参加した森山大道は、粒子の荒さやピントのぶれを特徴とする「アレ・ブレ・ボケ」の表現で注目を集めました。こうした彼らの写真表現は、しばしばコンポラ写真の一部と見なされることもありました。また、『provoke』には「日常の情景」特集に参加していた高梨豊や岡田隆彦も同人として参加しており、このことがコンポラ写真と『provoke』、さらには「アレ・ブレ・ボケ」写真との境界線を曖昧にし、混乱を生む一因となりました。
一方で、「アレ・ブレ・ボケ」とコンポラを、時代を象徴する表裏一体の表現として捉える見解も生まれました。東松照明は「現代写真をどうする:起て!アレ・ブレ、コンポラの患者どもよ」という寄稿の中で、両者の同時代性について論じています。彼はコンポラ写真を「意識があいまい」で、「一人一人がばらばらな存在」であり、自分たちがコンポラであるという自覚さえも持たない表現と見なしました。それに対し、アレ・ブレはより意識的で、「相互に連帯感を持ち、患者としての自覚を強めている」と指摘します。さらに、東松は、コンポラ写真は「存在自体が希薄で人に不快感を与えない。体制にとって無毒無害」なものとする一方、アレ・ブレは「メカニズムの破壊を企てるゆえに、有毒有害なものとして体制からしめ出される」と論じ、両者の性質の違いを明確に対比しました。
中平や森山自身は、はじめはコンポラの流行に対して一定の距離を置いていましたが、徐々に明確に否定的な立場を取るようになり、東松と類似したロジックでコンポラのスタイルを批判するようになります。
1970年代も半ばに差しかかる頃、流行としてのコンポラ写真は勢いを失っていきました。大辻は1970年の論考で「コンポラ写真はこのわずかな年月のうちに、写真一般のなかに吸収され」、「発展的に解体しつつある。近いうちに特にコンポラ写真と呼ぶ必要もなくなるだろう」と指摘しています。
まさにこの予見の通り、次第に「コンポラ」という呼称は使われなくなり、その精神は「私写真」や「コンセプト・フォト」といった新たな表現へと受け継がれていきました。コンポラ写真が持っていた、作家個人の私的な視点や日常へのまなざし、そして近代的な進歩主義の価値観を避けようとする姿勢は、こうした新しい潮流の中で形を変えながら息づいていったのです。
また現代においては、どこにでもある日常が、その人を包み込む社会との関係性を象徴しているといった理路が見出されて、コンポラ写真は「社会的なもの」を「個人的なもの」から析出させようとした潮流だったと評価される向きもあります。
大辻のコンポラ写真との関わりは、名付け親であり、また牛腸茂雄らのコンポラ写真を代表する作家の教師であったことが目立ちますが、彼の前衛への視座とコンポラ写真との関係を見出すことも出来ます。
1968年の「日常の情景」特集の参加者の中で最年長だった石元泰博について、彼の1962年の個展に触れた評論家の渡辺勉は次のように評しています。「素材としては、日常の断片をかすめとったものにすぎないが、ひとたびこの作者の鋭い観察と巧緻な技術のなかでにつめられると、日常的な属性のなかに秘められた内面的なリアリティーが浮き彫りにされてくるのは驚くほかはない」。
彼(ないし他の特集参加者)の作品は日常のありふれた風景を切り取ることで、隠れた真実を浮き彫りにしていきました。渡辺は直接述べていませんが、こういった日常から別様な現実を取得する営為はシュルレアリスムと連続するものといえます。
大辻自身もコンポラ写真に触発され、それまでの大判写真の手法から一転して、若手が用いたスナップショットの技法を積極的に取り入れ、新たな表現の可能性を模索する実験的なアプローチを展開しました。彼は(無)意識的に日常風景のスナップショットを撮影し始め、シュルレアリスムの自動筆記と結びつけてこれを分析しています。こうした試みは、写真を通じて自己の主観や意識の立脚点≒無意識を問い直す探究の起点となり、大辻の作品世界に一層の奥行きをもたらしました。
自身の撮影行為を客観的に分析し、写真を介して自身がどのように世界と関わっているのか。写真はどこまでが主観で、どこまでが客観か。カメラの眼と人間の眼はどのように相補的なのか。スナップ写真を巡る議論の多くについて、大辻は影響を残しています。
49. 重森 弘淹(1926~1992)
重森弘淹(しげもり・こうえん)は、1926年に生まれ、1992年に没した日本の写真評論家、教育者として知られています。
作庭家でいけばなの研究でも著名な重森三玲の次男として生まれ、兄には作庭家の重森完途がいます。弘淹の名前はドイツの哲学者ヘルマン・コーエンに由来するもので、兄の完途はイマヌエル・カントをちなんで名付けられました。父親の三玲自身はジャン=フランソワ・ミレーへの尊敬の念から、自身の名前を出生名の計夫から三玲へと改名しています。
いまでは写真評論家として知られるところの多い弘淹ですが、彼がはじめに世間で注目をあつめたのは、いけばなの世界でのことでした。
1930年代初頭に父の三玲が中心となって「新興いけばな」運動を始めます。弘淹はこの父の活動に影響を受け、いけばなの世界に入りました。
三玲らの始めた新興いけばな運動は、伝統的ないけばなの型や、花器による制限、華"道"のもつ道徳性を否定し、「植物は最も重要なる素材である」として、いけばなを植物を用いた純粋な芸術として捉え直そうとする革新的な試みでした。
1927年に草月流を創始した勅使河原蒼風ら実践者と三玲らの研究者が共同で1930年に「新興いけばな宣言」が発表し、その後1936年には新興いけばな協会を結成します。しかし、戦時体制の強化により、この動きはまとまった実績を得ないまま中断を余儀なくされました。 第二次世界大戦後、新興いけばなは「前衛いけばな」と名前を新たにして息を吹き返します。
前衛いけばなの名称は、新興いけばな宣言にも参加していた中山文甫が1948年に大阪大丸で「前衛挿花個展」を開いたことが端緒とされます。これ以降、特に関西地域では諸派がこの傾向に歩調を合わせるかたちで新しい表現を展開していきます。一見して前衛芸術としての生け花というスタンスが伝播したようにもみえますが、弘淹によれば、これは家元の表現をよしとして弟子が模倣するといった、伝統的な封建制度によって伝播・流行したのであって、社会運動としての機運や「前衛」に関する思想的方向性のないものであったといいます。
美術評論家の三頭谷鷹史によれば、この時期、いけばな界には主に三つの潮流が生まれました(三頭谷 2023)。ひとつは、勅使河原蒼風や中山文甫らによる造形的な革新とそれに追随する門弟による「造形いけばな」の動きです。新興いけばなでもあった素材の拡大(例えば、くず鉄やビニールをもちいるなど)に加えて、ファッションショーや歌舞伎などに活動範囲を広げながら、いけばなの芸術化を進めました。ふたつ目は重森三玲を中心として設立された私塾「白東塾」での独自の生け花研究と流派制度の解体を目指す動きです。家元と門弟という、家族的な関係性の中で行われる生け花を「個人の芸術」にしようとする動きでした。そして最後が若手作家らによる「新世代集団」の活動です。
弘淹は、この第三の潮流である「新世代集団」の中心的メンバーとして頭角を現しました。1951年、彼は工藤昌伸、勅使河原宏、下田尚利とともにこの集団を結成し、当時のいけばな界で最も若い世代を代表する前衛的なグループとして注目を集めます(弘淹自身は批評を主としており、実作はしませんでした)。
新世代集団の活動は、重森三玲が1949年に創刊し、弘淹が編集を務めた『いけばな芸術』の誌面を活動の基盤として、「テーマ性いけばな」の主張を展開します。テーマ性いけばなは社会主義リアリズムの影響を受けたもので、いけばなによって社会問題を表現するといった左派的な意識に基づくものでした。弘淹はこの活動の中において現代いけばなを巡る批評活動を精力的に行います。
その後、前衛芸術自体が退行していくなかで活動は徐々についえていき、『いけばな芸術』は1955年に廃刊し、新世代集団も事実上の解散となります。
『いけばな芸術』の廃刊後、重森は生まれ育った京都から東京へと拠点を移し、写真批評家の道へと転進します。新世代集団でともに活動した下田尚利が「重森は、食わなきゃならないから、写真批評に力を入れ、数年後には写真専門学校をつくる。宏(引用注:勅使河原宏)は映画にのめり込む」と述べていたように、いけばなで食っていけない中で、新しい食い扶持として「写真」を見出した形とも言えるかもしれません(ちなみに、こう述べる下田自身も写真の仕事をしたのち広告制作会社を立ち上げています)。
重森と写真との初期の関係はそれほど多くの記録は残っていませんが、ひとつは、『いけばな芸術』誌での土門拳をはじめとする写真家との交流、もう一つは花田清輝氏らが1948年に結成した「夜の会」への参加があげられます。資本主義批判やシュルレアリスムや社会リアリズムについての関心と写真メディアとの接合はこの頃にあったと見られます。
また、この頃の重森の活動として重要なものに、写真技能師法への反対運動があげられます。
1955年に営業写真家の団体の日本写真文化協会が中心となって写真技術師法案という法案を国会に提出して通過させようと働きかけをしました。これは国家試験かそれに準ずる方法で写真家を審査して、合格したものに写真技術師の資格を与え、無資格者による無断の写真営業を禁じようというもので、例えば、観光地での記念撮影や結婚式の撮影において、資格を持たない人による営業活動を制限する規制を設けようとしたものでした(厳密には、無資格者が営業を行う際は必ず「無資格者です」と顧客に通知すること、おこたった場合は罰金を科すといった制限でした)。
体裁としては、写真文化の発展と写真館を営む写真家の社会的地位の向上を目的としていましたが、既得権益を作るものとして多くの批判が集まります。
この法案に反対するために日本写真家協会がまず声明文を発し、写真批評家たちも集まって相談して、批評家有志で反対声明を出しました。このときに写真批評家クラブを作ろうという話がおこり、重森弘淹はこれに参加します。重森のほかは、渡辺勉、田中雅夫、渡辺好章、桑原甲子雄らが名を連ねました。
この集いは、1958年には日本写真批評家協会と正式に名乗るようになり、書記長には渡辺好章が就任します。
活動の一環として批評家協会では「夏期総合写真大学」という写真セミナーが開催されており、これは撮影技術よりも芸術理論や作家論を主軸にしたもので、当時としては珍しい内容でした。
重森はこの夏期大学の企画に講師として参加し、このときから彼の教育者の仕事が本格的にはじまります。
ここでの経験をもとに、重森は従来の写真学校で主軸とされてきた撮影技術の習得だけでなく、写真理論や批評の方法論の教育を重視した新たな教育機関を構想しました。そして、その年の9月に東中野に東京フォトスクールを開校します。
講師陣には福田勝治や石元泰博、東松照明といった写真家のほか、渡辺勉や伊藤知巳らの批評家が集まり授業が始まります。このフォトスクールからは英伸三や桑原史成が輩出されています。
東京フォトスクールは設立から1年余り経った頃に下落合に拠点を移し東京綜合写真専門学校へと改称され、1963年には横浜市日吉に新校舎を建設して再移転し、現在に至ります。下落合時代の卒業生には篠山紀信や操上和美、須田一政ら、その後の写真界を代表する写真家が連なります。
なお、批評家協会の活動の源泉となっていた写真技術師法案はその後廃案となりましたが、こういった営業写真師を保護しようとする運動はその後も続き、その成果は、写真技能士資格として結実します。この資格は、営業写真(たとえば七五三や振り袖写真)の撮影技能について熟達度を測るもので、1978年の第1回資格試験以降、現在まで続いています。日本写真文化協会のほか、日本写真専門学校(現:日本写真映像専門学校)などの強い政治的働きかけによって、写真家に関する唯一の国家資格(職業能力開発促進法に基づく技能士資格)として制定されました。
1957年、重森は「10人の眼展」を企画します(結果としてプロデュースは福島辰夫が行うことになりますが、田中雅夫によれば”言い出しっぺ”は重森とのこと)。木村伊兵衛と土門拳を代表とする旧来の報道/リアリズムを乗り越える、新たなリアリズム表現を生み出す場所として期待され、のちには出展作家だった東松照明や奈良原一高らによって写真家集団「VIVO」が創設されます。
この時代を象徴する出来事として60年安保闘争があります。重森も左派知識人の一人として、1960年頃からデモ集会に参加するようになり、国会前のデモに多くの写真家やジャーナリストとともに集うようになります。この頃のデモには、日本写真家協会の会長を務めていた渡辺義雄や木村伊兵衛といった著名な写真家のほか、写真雑誌の編集委員や写真学校の学生など、写真関係者が数多く参加していました(闘争には東京綜合写真専門学校の学生も多く参加しました)。
重森は、1950年代に隆盛を極めていたリアリズム写真運動に対して、批判的かつ建設的な姿勢を取りました。彼は、単純な現実の模写や記録としての写真の役割を超えて、写真家の主観を通じた現実の解釈や表現の重要性を強調しました。
重森の基本的な思想は、「表現とは作者による批評的な行為であり、批評性なくして表現は成り立たない」というものでした。この考えに基づき、彼は土門拳の「絶対非演出」に代表される、現実をそのまま写し取ろうとする反映論的リアリズムや、劇的な瞬間に遭遇する「目撃者」としての写真家像を批判します。
たとえば、ウィリアム・クラインのノーファインダー手法を参考にし、「見えるものをそのまま描く」という方法から脱却する必要性を説きます。また、現実の中に作者の意図したようなの「決定的瞬間」が存在するという前提自体が幻想であると重森は考えます。決定的瞬間とは、無数にある現実のあり方の中から、作者が自身の観念によって「唯一無二」として恣意的に順位付けしたものに過ぎないと主張するのです。
さらに、ロバート・フランクの『アメリカ人』を例に、重森は写真家を「目撃者」ではなく「傍観者」として捉える立場を提示します。現実(撮影対象)に対して撮影者は、自身を超越的な立場に置くのではなく、その場にたまたま居合わせた相対的な存在として位置づけるべきだと考え、撮影対象のことは自己と現実との関係性の中で、「ただ見る」ことしかできないと述べています。
重森はこうした写真観を代表する日本の新時代の作家として、東松照明や奈良原一高といった新しい世代の写真家たちを積極的に支持しました。必ずしも劇的な場面でなくとも、というよりも、むしろ劇的でないことによって、より一層社会的情景や現実感を想起しうる表現があり、それらは、従来のリアリズム写真のもつドラマチズムな虚飾性を超えうると考えたのです。重森は、彼らの作品に見られる独自の視点や表現方法を高く評価し、その意義を論じることで、日本の写真表現の新たな可能性を開拓しようとしました。
____
重森の死後、彼の功績を称える「重森弘淹写真評論賞」が設立され、2000年には第6回、2003年には第9回の授賞が行われるなど、その影響力は現在も続いています。
50. 多木 浩二(1928~2011)
多木浩二(たき・こうじ)は、戦後日本の美学、美術史、写真評論、建築論など多岐にわたる分野で活躍した評論家であり、彼の活動はそれぞれの領域を越えて思想の幅と深さを伴っていました。
神戸に生まれた多木は、太平洋戦争の開戦後、16歳の頃(1944年)に広島の江田島にある海軍兵学校に入ります。江田島から広島市内までは直線距離で20km程と近く、多木は江田島から広島に落とされた原爆を目撃したといいます。
その後、京都の旧制第三高等学校を経て東京大学文学部美学美術史学科を卒業します。大学を出たあとは名取洋之助が率いる第3次日本工房のスタッフとして参加し『岩波写真文庫』の制作に関わります。その後、博報堂に入社し、広告や編集に携わります。
1961年には、編集デザイン事務所ARBO(アルボ)を設立し、旭硝子(現AGC)の広報誌『ガラス』の編集、執筆、撮影に取り組みます。この頃、多木はヨーロッパを訪れ、そこでの建築体験が後の建築論の基盤となります。彼の建築に対する洞察は、物質と空間の関係、またそれが社会とどう結びつくかという点に深く根ざしており、篠原一男や坂本一成といった建築家たちとの対話を通じて、より重層的な理解へと発展していきました。
多木は1950年代中頃から美術評論を始め、美術雑誌『みづゑ』に寄稿した「井上長三郎論」で佳作に選ばれると、その後も『美術手帖』や『デザイン』といった媒体に寄稿し続けます。
1968年の「写真100年―日本人による写真表現の歴史」展は、多木浩二の写真論、ひいては彼の思想形成に多大な影響を与えました。日本の写真史を編纂し直す経験は、多木の写真へのアプローチ、そして後の『PROVOKE』のような実践へと繋がっていきました。
まず、多木は同展の編纂委員として深く関与しました。これは、単なる資料収集や展示作業ではなく、日本の写真史を改めて批評的に見直す機会となりました。委員長は濱谷浩で、実行委員には東松照明、内藤正敏、中平卓馬といった戦後に活躍を始めた写真家が多く名を連ねていました。これは、戦時中の国家宣伝に多くの写真家が加担した事実を、戦後の写真家たちが客観的に見つめ直そうという意図の表れだったと言えるでしょう。多木自身も、この展示を通じて、戦前・戦中写真のイデオロギー性と、写真の「記録性」と「表現」の関係性を深く認識することになりました。
写真100年展で扱われた写真は、技術史や社会状況を反映したものでしたが、多木はそれらを単に事実として記録するのではなく、それぞれの時代の社会構造やイデオロギーが写真にどのように反映されているかを分析しました。特に、戦時下のプロパガンダ写真や、それとは対照的な「アノニマスなドキュメント」としての記録写真(例えば、山端庸介の原爆後の長崎の写真、田本研造による北海道開拓の写真)を比較検討することで、写真の持つ二重性、そして写真の「表現」とは何かという問いを深めました。 「表現」を個人の主観的な行為として捉えるのではなく、社会状況や歴史的文脈の中に位置づけることで、写真の持つ社会的な意味や影響を改めて考え直す契機となりました。
「写真100年展」で、多木は戦前・戦中写真のイデオロギー性を明確に認識しました。 それは、写真が単なる「記録」としてではなく、政治やイデオロギーを伝える強力な「装置」として機能してきたことを示していました。この認識は、多木が『PROVOKE』において、既存の秩序や権威に挑戦し、写真の新たな可能性を探求しようとした原動力の一つとなったと言えるでしょう。
1968年、中平卓馬や高梨豊とともに、写真とテキストが融合した実験的な同人誌『PROVOKE』を創刊します。多木は、中平卓馬と共に編集の中心人物として、写真とテキストの新たな関係性を模索し、単なる写真集ではなく、「思想のための挑発的資料」としての位置づけを意図し、既存の秩序や常識を揺るがすことを目指しました。そのなかで、従来のリアリズム写真を批判する「ブレボケ」と呼ばれるスタイルを通じて、写真における新たな表現を提示していきます(多木自身は、「アレブレボケ」の表現方法が、背景になった思想を置き去りにするかたちで1990年代以降に再評価されたことに対して、晩年に至るまで懐疑的な態度を示し、やや距離を置いていました)。
彼の関心は写真のみならず、建築やデザインの領域に広がっていき、特に記号論や社会的文脈における写真・建築の位置付けを探求するようになります。
多木が写真と建築の両方に共通して関心を抱いていたのは、「空間」という概念でした。彼は、写真と建築の双方を通して、「空間」を様々な角度から考察しました。写真においては、写真家が「見る」ことによって生み出される空間、また写真によって提示される空間。建築においては、建築家が設計した物理的な空間、そこに住まう人々の生活によって形成される空間、そして歴史的・社会的な文脈によって作られる空間などを分析し、それらの空間がどのように形成され、どのように意味を持つのかを考察しました。
『生きられた家』(1976年)は、この建築と空間に対する多木の考え方が明確に示された著作です。この本では、建築を単なる建造物としてではなく、そこに住まう人々の生活や歴史、文化が積み重なって形成される空間として捉えています。篠山紀信の写真集のために書かれたテキストを再構成して作られたこの本は、建築と人間の生活との密接な関係性を示しており、多木の建築と写真への思想を象徴する作品と言えます。
多木にとって、建築と写真は、世界を理解し表現するための相互に関連した「装置」でした。建築は、写真を通して分析・解釈される対象であり、同時に写真撮影の重要な被写体でもありました。
1980年代には、『現代思想』誌への連載をまとめた『眼の隠喩―視線の現象学』(1982年)を発表し、社会的・文化的影響を受けた視線と、それが世界をどのように形作ってきたかを芸術史・思想史の視点から分析し、写真論に新たな地平を開きました。
また、『天皇の肖像』(1988年)では、明治天皇の肖像写真を通して、写真による権力の視覚化と政治的利用の歴史を考察しています。『写真の誘惑』(1990年)では、ロバート・メープルソープのセルフポートレートを手がかりに、写真の解釈と時間の関係、そして「隠喩としての死」をテーマにしています。
これらの80年代以降の著作では、写真を芸術的視点ではなく社会的視座から捉えることにより、写真が単なる視覚表現にとどまらず、いかに社会(をどう捉えるか)に影響を及ぼすかという議論に軸足を写していきます。
『絵で見るフランス革命』(1989年)ではフランス革命の歴史を視覚的に捉えることで、単なる歴史的事象の記述にとどまらず、視覚表現が歴史的記憶にどのように関与するかについて新たな問いを提示しています。この作品について多木は「やっとここまできた」と述懐し、それまでの蓄積された思想が具体的な形となったことに対する達成感を感じていたようです。
1994年からは、建築家の八束はじめとともに『10+1』誌の編集に携わり、建築や都市についての幅広い論考を発表する場を設けました。この雑誌は、建築を単なる空間の設計としてではなく、社会構造や人間の営みと結びついたものとして捉え直す試みであり、多木の思想が反映されている重要な活動のひとつといえます。
多木の晩年は、写真への関与は直接的には減少したものの、彼の思想はますます深化し、建築、美術、歴史、哲学など、より広範な領域へと広がりを見せました。 「写真」というメディアへの関心は薄れたわけではなく、むしろ、写真を通して得た知見や方法論を、他の分野の研究・批評に活かしていく段階に移行したと言えるかもしれません。
W.ベンヤミン 著 ほか『複製技術時代の芸術』,紀伊国屋書店,1965.
関連図書として
針生一郎 編『われわれにとって万博とはなにか』,田畑書店,1969.
多木の大阪万博への反対論を収録
田中雄一郎 『都市を読む装置としての写真-多木浩二の写真論と未整理ネガに基く考察・研究』, 九州産業大学 博士論文,2015.
51. 常盤 とよ子(1928~2019)

『新婦人』12(4)(121),文化実業社,1957-04.
撮影者:自写像
常盤とよ子(ときわ・とよこ)は、日本の戦後写真史において重要な役割を果たした女性写真家です。特に1950年代後半に発表した写真集『危険な毒花』で注目を集めました。この作品は、1956年の売春防止法施行以前の横浜の娼婦街(いわゆる赤線)で撮影された売春婦たちの生態を記録したもので、当時としてはセンセーショナルな内容でした。
神奈川の鶴見に生まれた常磐は、1950年にいわゆる花嫁学校とされた東京家政学院、ついで伊東茂平が開いていた洋裁学校を卒業して、花嫁準備をしていた折に、兄の友人に勧められてカメラを手にします。常磐の兄も写真趣味をもっており、その兄の友人も写真青年でした。
「人類の発生依頼、無限に連続している、一秒一秒。この一秒一秒の現実こそ、われわれの生命の燃焼によって成立しているので、その瞬間を捉えることは、こいつはたしかに貴重なことなのだ」
「戦後は、女の人があらゆる職業面に目ざましい進出を見せてきたが、まだ写真界には、これぞという女流写真家が出ていないね。~~ひょっとすると一流カメラウーマンになれるとも限らないね」
兄の友人の話すそんな口ぶりに感化された彼女は、「平凡な社会人/家庭人」になるよりも、カメラマンの道を目指すほうが良いと決心します。この頃には、結納まで済ませた学生時代からの婚約者もいましたが、写真の志のために縁組を破談となりました。
その後、1951年に創設して間もない頃の白百合カメラクラブに参加します。これは、小説家の吉屋信子、画家の三岸節子、三笠宮妃百合子らが中心となって設立された女性限定のカメラサークルで、1950年代半ばには500名以上の会員がおり、当時として日本最大の女性カメラサークルでした。常磐によれば、写真創作に熱心に取り組むというよりは、社交クラブとしての側面が強く。彼女の他にはプロを目指すような人はほとんど見当たらなかったといいます。
クラブでの活動に熱を入れていた常磐ですが、次第に土門拳らによるリアリズム写真運動の影響を強く受けるようになり、被写体を社会の底辺の労働者や、横浜の駐留米兵などに絞っていきます。家の近くの横浜港に出かけては米兵を撮影していた彼女ですが、やがて興味の矛先が「洋パン」と呼ばれる「駐留軍に媚びを売る女たち(娼婦)」へと移って行きます。
父親を1945年5月の横浜大空襲で亡くした常磐からすれば、米兵は親の仇であり、そんな彼らを相手に働く娼婦に対しても怒りと憎しみを抱いていました。そのため、初期の撮影では、娼婦たちの「生態の醜悪さ」や「嫌らしさ」を表現しようとしてシャッターを切っていました。
赤線での撮影は、当初は隠し撮りで撮影していましたが、次第に娼婦たちと打ち解け、「写真を撮ってくれるお姉ちゃん」として警戒されずに撮影できるようになります。また、この頃には、女たちが性病の検診を受けにくる病院の医師らの協力で、病院や遊郭の室内での撮影も可能になっていきます。本牧のチャブ屋にも医師のツテで訪れることができました。通常はカメラを向けられたがらない娼婦や斡旋業者たちも、「先生」の検診に随伴する常磐には強く出れず撮影を許容したようです。
撮影を続ける中で、常盤の視点は変化していきます。
最初は娼婦の醜悪さを描こうとしていたのが、やがては売春制度の持つ負の面を訴えるようなルポルタージュの目線へと移行していきます。
常磐はさらに、娼婦たちの間にあるヒエラルキーや、生活環境、人間関係にも注目するようになります。特に、外国人相手の娼婦である「洋パン」と、日本人相手の娼婦の違いを認識し、それぞれの生活や状況を深く掘り下げて撮影をしていきました。
____
赤線での撮影を続けるなか、常磐のもとに川崎の学生が訪問します。「写真クラブをつくったんですが・・・みんな初心者ばかりなものですから、常磐さんにおしえていただきたいと思いまして」と学生に請われた彼女は快くその依頼を引き受けます。
「どんぐりクラブ」と銘打たれたクラブで講師する常磐は、学生に向けた教材を作る過程で、自身の創作に中核的なテーマ性が欠けていることを悟り、次第に「女の職業」をテーマとして定めていきます。デパートの店員やファッションモデルといった職業を被写体にテーマを磨いていく中で、次第に「赤線地帯の女たち」も働く女性なのだと、常磐の中で明確なモチーフが立ち上がります。
このモチーフは、1956年4月に銀座の小西六フォトギャラリーで開かれた個展「働く女性」で結実します。この個展では、海女やモデル、看護師などの「善いとされる職業」写真と、女子プロレスラーやヌードモデル、赤線地帯の女たち等を「悪いとされる職業」を2つに分けて対照的に発表しました。
この個展は大きな反響を呼び、翌年には赤線地帯での写真をまとめた写真集『危険は毒花』を出版します。写真集は瞬く間に重版となり、常磐はジャーナリストとして脚光を浴びます。
『危険な毒花』では、常盤は単に娼婦たちの姿を記録しただけでなく、その生活空間や心理状態までも写し出しました。例えば、娼婦の部屋に置かれた家具や調度品を、彼女たちの置かれた状況や、自己肯定感の表れとして捉え、独特の視点で撮影しています。また、病院で治療を受ける娼婦の姿や、検診を受ける娼婦たちの行列なども捉え、彼女たちの現実をありのままに表現しました。
彼女は女性写真家としての立場を強く意識し、男性写真家とは異なる視点で女性を撮影しました。特に、女子プロレスラーを撮影した際、彼女たちが「ストリップ・ショウ的な見世物」ではなく、現実を鋭くえぐるような作品にしたいという強い思いがあったと語っています。
また『危険な毒花』を出版した1957年には、福島辰夫の企画による「10人の眼」展の第1回展(小西六ギャラリー)に参加した他、今井壽惠との二人展を開催します。翌1958年には田中雅夫の呼びかけによって、常盤や今井、赤堀益子など14人の女性写真家による「女流写真家協会」を結成し、第1回展を開催します。
1962年から1965年にかけて、常盤はテレビ映画「働く女性たち」シリーズを制作し、多くの女性たちの姿を映し出した。また、1974年には横浜市使節団の一員としてソビエト連邦を取材するなど、国際的な視野を持って活動した。1980年代からは海外での取材活動も積極的に行い、台湾やマレーシアなどで写真を撮影した。
1985年以降、常盤は高齢者問題に焦点を当てた作品を発表するなど、社会的なテーマを一貫して追求する姿勢を貫き、1995年に夫の奥村泰宏が亡くなった後は、神奈川県写真作家協会会長として地域の写真文化に貢献し続けました。
2018年には、常盤とよ子の写真群が姪の栗林阿裕子によって横浜都市発展記念館に寄贈され、整理と公開が進められています。
「『男ではなく、女だからということで、写真をとるのになにかプラスになることがある?』 よくわたしはこんな質問をうけることがある。その人の心にはじめから、女性だから、と決めてかかるような調子が感じられる。むろん、その人の考えに誤りはないと思う。でもプラス、マイナスすれば芸術や仕事の上で男女の区別などあろうとは信じられない。もちろん、それは撮影時の対象によつていろいろと違いはあるにしても、わたしの場合、男の人を撮影するときほど気が楽なことはない。というのは、男性というのは総じて、女性に対してはやさしく振る舞つてくれるらしいからである。」
常盤とよ子 「スカートをはいたカメラマン」『危険な毒花』1957, p.12.
梶原洋生『「売いん」等に係る条例の制定 -1946年から1957年までの整理-』,新潟医療福祉会誌18(2) 44-5, 2018.
中川紗智『娼婦の移動実態からみた盛り場の性格── 1950 年代の横浜を事例として──』,地理学評論 92‒5,2019.
52. 矢頭 保(1928?~1973)
矢頭保(やとう・たもつ)は、1925年頃に兵庫県西宮市で生まれたとされる日本の写真家です。なお、彼の生年月日について定かな情報はなく、1928年の出生というのも確かではありません。その生い立ちについては不明な点が多いものの、1952年に宝塚歌劇団の男子研究生(第4期生)として入団したことが最も古い確かな経歴として知られています。
宝塚歌劇団の男子部は、1945~1954年までの間に存在した組織で、戦後復興を目指して宝塚歌劇団の創始者・小林一三の発案により、「男女共演の劇団」を目指して発足しました。1952年までに4回の募集が行われ、矢頭を含めて、最終的に25人が合格しました。男子部の生徒たちは女性団員と共に舞台出演を目指してレッスンに励みましたが、在団生やファンからの強い反発を受け、宝塚大劇場のメインステージに立つことは叶いませんでした。1951年の大劇場公演「虞美人草」ではカゲコーラスに参加するなど一部の出演はありましたが、最終的に1954年3月に解散しました。
矢頭はこの解散のタイミングで歌劇団を離れ、1950年に小林一三が設立した軽演劇集団の宝塚新芸座に移籍します(軽演劇とは例えば吉本新喜劇のようなコミカル演劇のこと)。
この劇団は小林が関西漫才界の重鎮であった秋田實に、「漫才師による劇団の結成」をもちかけて発足したもので、当時人気だった漫才師たちを軸にした漫才中心の劇団でした。
もともとダンスの得意だった矢頭は、宝塚新芸座への移籍のすぐ後に、大阪梅田にあった東宝北野劇場(現:TOHOシネマズ梅田)の北野劇場ダンシングチームに再度籍を移しています。
1956年頃からは東京に活動の場を移し、ダンサーを目指しましたが、この頃に大きな交通事故に遭い、両足を骨折してしまいます。ダンサーの道を諦めざるを得なくなった矢頭は、日雇いの仕事などをして厳しい時期を過ごしていたといいます。
そんな矢頭に人生の大きな転機が訪れます。
新宿のゲイ・バーでメレディス・ウェザビーと出会ったのです。ウェザビーは三島由紀夫の「仮面の告白」の翻訳者であり、後に美術系出版社ウェザヒル社を立ち上げた人物です。この出会いをきっかけに、矢頭はウェザビーの庇護を受け、麻布竜土町(現在の六本木7丁目)にあるウェザビー邸で同棲生活を始めました。
ウェザビー邸に住みだした後、矢頭は日活に所属し、俳優としてデビューします。1958年からは「高田保」、1961年からは「矢頭健男」という芸名を使用し、主にアクション映画の端役として出演しています。具体的には、小林旭主演の『銀座旋風児・黒幕は誰だ』や赤木圭一郎主演の『霧笛が俺を呼んでいる』などにわずかに出演しています。
ただ、演劇人としての芽はあまり育たず、大きな役を得ることはないまま1962年に日活を辞めます。
ウェザビー邸ではゲイ・パーティもよく開催され、文化人や芸術家、外国人などが出入りしていました。このときに矢頭は三島とも面識を深めていったとみられます。
その後、ウェザビーとの出会いを通じて、矢頭は写真やアートの世界に触れ、写真撮影を始めるようになります。ウェザビーからカメラを買ってもらい、簡単にカメラの使い方を教えてもらっただけで、特に学校で写真の教育を受けたわけでも、写真家に弟子入りしたわけでもありませんでした。
徐々に写真にのめり込んでいった矢頭は、1966年に『体道~日本のボディビルダーたち』を出版します。この写真集は同タイトルの日本語版と、"Young Samurai"と題する英語版が出版されました。前者には美術出版社版とウェザヒル出版社版があり、後者はウェザヒル出版社のみが出版しています。
この写真集には三島由紀夫が序文を寄せており、自身も褌姿でモデルを務めています。『体道』はパブリックに出版されたメールヌード写真集としては日本では最初期のものです。とはいえ、同性愛的な文脈を前面に出すことは難しかったため、体裁としてはボディビルの魅力をアピールするための写真集となっており、当時日本ボディビル協会理事長だった玉利齊や、同協会顧問の平松俊男が寄稿をしています。
日本でボディビルが知名度を得たのは、1955年夏に、日本テレビで全4回のボディビルの特集番組『男性美を創る―ボディ・ビルディング―』が放送されたことがきっかけです。この番組には1954年に創設された日本初のボディビルクラブ「早稲田大学バーベルクラブ」の主将でもあった玉利や同クラブでコーチだった平松、プロレス雑誌を出版する会社の社長だった田鶴浜弘らが関わっており、彼らの人脈を活かして、番組にはボディビルの実演者や豪華なゲストが集まりました。当時の力道山によるプロレスブームも影響し、マッチョな男性像への憧れの声が集まるなど、番組は大きな反響を得ます。
また、放送の少し後の1955年10月には日本初のボディビルジム「日本ボディビルセンター」が渋谷に開設され、開設1ヶ月あまりで1000名ほどの入会希望者があったといいます。
三島由紀夫が肉体改造を始めたのもこの頃です。自身の貧弱な肉体にコンプレックスのあった三島は、雑誌で早大バーベルクラブのことを知ると、これなら自分にもできるかもしれないと思い。その後すぐに玉利に連絡を取って、1955年9月頃から玉利との個人レッスンを開始します。三島はトレーニングの様子をしきりに撮影しており、ジムでの様子の一部は矢頭が撮影していたと考えられます。『体道』のなかで三島がポージングをしているのはそういった関連もあってのことでしょう。
この頃の矢頭は三島の要望で、プライベートな写真撮影をこなすことも多く、チョコレートを体に塗りつけて血が飛び出たように見せた「切腹写真」なども撮影しています。
三島は、雑誌などで公開するパブリックな写真については、篠山紀信(「聖セバスチャンの殉教」など)や細江英公(『薔薇刑』)に依頼していましたが、自身の嗜好を満たすための私的な写真は六本木のスタジオで矢頭に撮らせていたようです。
三島と交流があった堂本正樹は、澁澤龍彦が編集を務めた雑誌『血と薔薇』に三島のグラビア写真を載せる際、上記のような公私の使い分けがあったために、矢頭が撮影に呼ばれなかったと述べています。
なお、ボディビルブームがおきた1950年代は、同性愛的行為は異常性欲として捉えられ、”治療”の対象でもありました。この時期は日本でフロイト心理学が注目を浴びた時期でもあり、フロイト理論の通俗的理解をもとにして、自己陶酔的でナルシシスティックな行為を精神分裂病の症状の一つとして認識する向きもありました。こういった考えをベースにして、オナニーなどのマスターベーションにふける男性は異性愛に向かいことができず同性愛などの異常性欲者に陥るとみなされる傾向がありました。自己の肉体への耽溺と自己陶酔的な活動であると認識されていたボディビルにおいても同様で、ボディビルをするひとは、マスターベーション的に肉体改造をしていて同性愛的だとみなす言説があったのです。こういったホモフォビアを背景にした当時のボディビル批判に対して、三島は、知的な活動のためにはむしろ肉体が重要であり、ボディビルはエリート男性にとって重要な行為なのだと、ボディビルと階級的魅力を結びつけるロジックで批判に応えています。
その後、矢頭は1969年には『裸祭り』という写真集を出版し、こちらにも三島が序文を寄せています。また、巻末には、民俗学者の萩原竜夫や山路興造による裸祭りに関する文章が収録されています。矢頭と学者らとの関係は不明ですが、これらの文章を収録した背景には、写真集を学術的な体裁を整えたものとする意図があったと考えられます。このことは、単なる「男性の裸を撮る口実」としてではなく、写真集を真正なものとして位置付けようとする矢頭さんの姿勢を示しているといえるでしょう。
この写真集が発表される頃、矢頭は映画用スチル写真や写真雑誌の取材などの仕事を手掛けていました。ただし、写真ギャラリーとの関わりや他の写真家との交友はなく、その方面で広く知られることはありませんでした。なお、ウエザビーからの経済的援助はこの頃も続いていました。
1970年11月25日、三島由紀夫は盾の会のメンバーであった森田必勝と共に割腹自殺をしました。
1972年に出版された『OTOKO』は矢頭の最後の写真集となります。出版元は"Rho-Delta Press"と記載されていますが、これはウエザヒル社の別名であり、猥褻物として処分されるリスクを回避するためにこの名を用いたとされています。この写真集は一般の流通ルートには乗らなかったようで、前の2作とは異なり国会図書館にも収蔵されていません。日本国内での販売元として記載されているのは、現在は存在しない西新宿のゲイショップで、矢頭自身がこの写真集をゲイバーに置いて販売していたとも言われています。
この写真集の特徴は、これまでの作品と異なり、社会の規範内で認められたテーマ(ボディビルや裸祭り)を借用するのではなく、純粋な男性ヌードを扱っている点にあります。また、男性同士の絡みを含む写真も挿入されており、矢頭は初めて隠れ蓑なしにエロスを主題とする表現に挑んだと言えるでしょう。
『OTOKO』は、モデルのアンニュイな表情をよく捉え、性的興奮を直接煽る表現を慎重に避けるように構成されています。「下品」な読者の期待に応えるものではありません。これは、同じ年に出版された波賀九郎の「梵」に収められた扇情的な写真と対照的です。
なお、この3作目を制作していた1970~1971年頃、ウェザビーが新しい恋人を作ったことで、矢頭との蜜月関係は終わりを迎えたようです。矢頭は3作目出版の前後にウェザビーの家を出て、高田馬場で暮らし始めました。
3作目の出版後、ウェザビーから離れて暮らしていた折の1973年5月、矢頭保は就寝中に亡くなります。心臓発作のための突然の死でした。矢頭保の葬儀は、ウィザビー邸の隣の法庵寺で友人たちの手で行なわれました。
53. 田沼 武能(1929~2022)

『世界写真全集』第5巻 (日本),平凡社,1956.
撮影者:不明
田沼武能(たぬま・たけよし)は東京浅草で生まれ、実家は営業写真館「田沼写真館」でした。6人兄弟の次男で、写真に触れたのは小学校2年生の時。校外授業で国立病院へと傷病兵慰問に行く際に、父から写真を撮ることを勧められ、米コダック製のベスト判カメラを渡されたのが最初です。
東京府立第十一中学校(現:都立江北高等学校)に入学すると、親からドイツ製カメラのスーパー・セミ・イコンタを譲られ、学校生活を撮影するようになりましたが、当時は写真にはそれほど強い関心を持っておらず、彫刻家や建築家を志した時期もありました。
1945年3月10日の東京大空襲で、田沼の実家である写真館は焼失します。
爆撃により上野・浅草近辺を焼き尽くされ、10万名を超えるともされる死者・行方不明者がでます。空襲後には、町の至るところに死体が横たわっており、仮埋葬をするために上野公園には埋葬待ちの死者が長い列を作るように並べられていました。
爆撃の猛火から命からがら避難した翌日、焼け跡に戻った田沼が目にしたのは、忘れられない悲劇的な光景でした。
焼け落ちた実家の前にあった防火水槽の中で、3歳ほどの子どもが焼死していたのです。炎から逃れる母親がわが子を助けようと水槽に入れたものの、水は蒸発し、男の子は立ったまま命を落としていました。その姿は地蔵のようで、16歳だった田沼に「お地蔵さまは子どもの化身」という思いを抱かせたといいます。
実家の焼失後、中学校を繰り上げ卒業し、疎開先の長野県で代用教員として終戦を迎えると、戦後は栃木県足利市を経て、1946年に一家で浅草に戻ります。
その後、以前から目指していた建築家となるために、早稲田第一高等学院を受験するも入試で不合格となり、実家が写真館であったことや友人の勧めから、仕方なく東京写真工業専門学校(現・東京工芸大学)へ進学します。
田沼が入学した当時、東京写真工業専門学校は空襲で校舎を失い、小西六写真工業株式会社(現:コニカミノルタ)の淀橋工場内の青年学校を仮校舎としていました。戦後のインフレで学生も教員も生活費を稼ぐためアルバイトに追われる日々でしたが、写真技術を活かした仕事は多く、田沼は極東軍事裁判所で裁判資料を写真で複製するアルバイトに従事しました。その他には進駐軍向けのクラブでウェイターもしていたといいます。
実家の写真館で学んでいたため、学校の授業のほうは退屈であまり身が入らずにいました。そんな日々を送っていると、「このままでは人間が駄目になってしまう」という気持ちが強まっていきます。生家の田沼写真館では、戦前からアメリカのグラフ誌『ライフ』を定期購読していたのもあり、「どうせ写真をやるなら、『ライフ』のようなグラフ・ジャーナリズムの世界に入りたい」と強く思うようになりました。
学内で報道写真部をつくると、新聞社のカメラマンたちに交じってメーデーやデモの様子を撮影するなど積極的に取り組みます。
1949年、田沼は3年制だった東京写真工業専門学校を卒業します。卒業した年、各新聞社でカメラマンの公募はなく、NHK写真部を受験しましたが入社は叶わず、就職先に困っていました。そんな中、学校の先輩で兄の友人だった三堀家義から、サン・ニュース・フォトスが人を探していると聞き、二人で面接を受けに行くと、二人ともすぐに採用が決まります。この会社は名取洋之助が編集主幹として『週刊サンニュース』を発行しており、写真スタッフには木村伊兵衛や藤本四八など、戦前から活躍する写真家たちが揃っていました。しかし、サンニュースの業績は当時すでに厳しいもので、田沼が入社したときにはすでに雑誌は休刊していました。編集主幹の名取も岩波写真文庫に移ってしまいます。
入社半年後、田沼は希望して木村伊兵衛と同じ部門に異動し、木村の助手となることができました。当初、田沼の申し出に「助手はいらねえ」と一喝されましたが、諦めずに行動を共にするうちに徐々に師弟関係を築きました。共に下町出身という共通点もあり、次第に親しみを感じる関係へと発展したといいます。
木村伊兵衛は休みの日に下町でスナップ撮影をしており、田沼は同行しながら写真家に必要な技術や被写体との接し方を目で盗みながら学びました。
木村の影響を受けた田沼は、当時高価だったライカを1年間節約して購入し、浅草などの下町でスナップ撮影を開始。これらの写真は、雑誌掲載の予定はなかったものの、「良い写真を撮りたい」という熱意で撮り続け、その後1980年に『下町、ひと昔』として写真集にまとめられました。
ジャーナリズムを志してサン・ニュース・フォトスに入社した田沼でしたが、業績不振のため、会社からはほとんど給料を受け取れませんでした。あげくには、会社のほうがアルバイトを奨励するほどでした。他の社員と同様に、田沼も昼間に会社で働くかたわらで、夜はアルバイトをして生活を支えました。他社の暗室作業の手伝いや、ブロマイド用に松竹少女歌劇団の舞台稽古を撮影するなど、忙しくしていたようです。
サン・ニュース・フォトスでの給料が支払われない状況を案じた木村伊兵衛の紹介により、田沼はサン・ニュース・フォトスの社員のまま、1950年1月創刊の月刊誌『藝術新潮』の嘱託写真家となります。この仕事では、舞台撮影や絵画の複写、画家や文士、音楽家のポートレートなど、雑誌に掲載される写真の多くを田沼が一手に引き受けました。
1950年6月に始まった朝鮮戦争による特需景気は、日本国内の企業や工場に活気をもたらし、サン・ニュース・フォトスにも広告や宣伝用の写真撮影の注文が次々と舞い込むようになりました。しかし、業績回復の兆しも束の間で、同社は1953年に倒産し、田沼は新たに設立されたサン通信に移籍し、嘱託写真家として活動を続けることになります。
その後、田沼のもとには『藝術新潮』をはじめとする多くの雑誌からの撮影依頼が舞い込み、多忙を極める日々を送っていました。しかし、ある日、師匠の木村伊兵衛に呼び出されると、「いつまでもそんなことをしていたら、マスコミに潰されてしまうぞ。お前は頼まれ仕事をこなしているだけで、自分の作品がないじゃないか。」と叱咤されます。自身でも、独自の作品を残さなければ写真家としての未来がないという危機感は抱いていたものの、仕事を断ることで次の依頼が途絶えるのではないかという恐れから、その一歩を踏み出すことができずにいました。
そんな田沼に転機が訪れたのは、1964年の東京オリンピックでした。この大会で撮影した写真が高く評価され、米国のタイム・ライフ社から契約写真家としてのオファーが舞い込んだのです。この契約は、同社が発行する『LIFE』『FORTUNE』『Sports Illustrated』といった雑誌の取材撮影を担当するもので、年間の仕事日数は全体の3分の1程度、報酬は田沼の当時の年収に匹敵する額でした。この契約によって、田沼はタイム社の仕事以外の時間を、自身の作品制作に充てることができると考え、二つ返事で引き受けました。
1965年、ニューヨークのタイム・ライフ本社で1週間の研修を受けた後、田沼はフランス・パリを訪れます。日曜日の朝、ブローニュの森を散策していると、ピクニックに来ていた子どもたちの一団に出会いました。遊びに熱中する子どもたちの姿に魅せられ、田沼は、夢中でシャッターを切ります。この経験を通じて、彼は自身も出展した写真展「人間家族」(The Family of Man)の子ども版ともいえる作品を撮影したいという新たな目標を抱くようになりました。
人間家族展では、結婚や誕生、家族、労働、遊び、飢餓、戦争、死といった人間社会の営みが、ひとつの家族のように描かれていました。田沼はこの展示に深い感銘を受けて、1956年の日本での会期中には、何度も会場を訪れては作品に見入る日々を過ごしたそうです。
とはいえ、当時は子どもの写真は「プロの写真家が撮るものではない」と軽んじられる風潮がありました。しかし田沼は、子どもたちが「社会を映し出す鏡」であると確信していました。子どもの姿を通して、その国の環境や文化が見え、さらには時代の変化をも伝えられると考えたのです。世間の評価を気にすることなく、自分が信じたテーマに全精力を注ぐ決意をした田沼は、足かけ10年にわたり世界各地で撮影を続けました。
ライフ誌との契約が1972年に終了した後、その成果として、1975年に『すばらしい子供たち』と題した個展を開催し、同名の写真集を刊行しました。この個展と写真集は大きな反響を呼び、その結果、田沼は日本写真協会年度賞を受賞し、写真家としての地位を確立しました。
1984年、仕事の撮影などで以前から交流のあった黒柳徹子がユニセフ(UNICEF)の親善大使に任命されます。田沼はそのことを耳にすると、すぐに黒柳に電話をして、彼女の途上国訪問に随伴することの許可を取ります。その後は、自費で黒柳のアフリカやアジアなど途上国への訪問に同行するようになりました。この名コンビはその後37年間にわたり約40カ国を訪れ、飢餓や戦争で苦しむ子どもたちの現状を世界に伝え、多くの支援を呼び込む活動を続けました。
____
田沼は、写真家としての活動に留まらず、「日本写真家協会」「日本写真著作権協会」「全日本写真連盟」の会長を歴任し、写真文化の発展と権利の保護に多大な貢献を果たしました。特に、写真の著作権保護期間を他の著作物と同様に延長する法改正を実現するための活動や、写真のネガフィルムや原板を文化財として保存し、後世に伝える活動に尽力しました。
写真は、カメラという装置を用いて「機械が実在するものを記録する」特性を持つ技術です。このため、「人が多くの労力をもって手作業で生み出す絵画」などとは異なる表現とされてきました。こうした特徴から、著作権法の歴史において、写真は絵画や彫刻など他の創作物とは異なる扱いを受けてきました。たとえば、1899年に制定された日本最初の著作権法(旧著作権法)では、一般的な著作物の著作権が著作者の生存中および死後に30年間保護されるのに対し、写真の保護期間は発行または公表の翌年からわずか10年間と、はるかに短かく設定されていました。
戦後、旧著作権法が全面改正され、1970年に制定された現行著作権法では、写真の著作権保護期間が大幅に延長され、写真の保護期間は公表後50年間とされました。しかし、一般的な著作物の保護期間(著作者の生存中および死後50年間)と比較すると、依然として短いものでした。
こういった”不平等”を打破するために、田沼をはじめとした多くの写真家がロビイングを続け、その結果、1997年に法改正があり「著作者の没後50年間保護」が実現しました。また、2018年以降はTPP整備法による著作権法の再改正で没後70年間の保護にまで期間が延長されています。この成果は、写真家の権利を守る大きな一歩となりました。
以下では、おもに田沼をはじめとする写真家が、現行著作権法の制定やその後の改定に際してどのように関わったのかを更に見ていきます。
1950(昭和25)年5月、「写真家集団」「青年写真協会」「日本青年報道写真協会」という3つの団体が統合され、プロ写真家の地位と権利を守り、写真を社会に普及させる目的で「日本写真家協会」(JPS)が設立されました。初代会長には木村伊兵衛が選出されましたが、生来面倒事を嫌う木村は、助手であった田沼に多くの実務を任せました。その結果、設立メンバーの中で最年少の田沼は次第に写真界で注目を集めるようになりました。
JPSは1953年には日本著作権協議会に加入し、1955年からは本格的に著作権協議会内で写真著作権にかかわる議論を深めていきます。とはいえ、この頃、写真家たちに写真にコピーライトを表記したり、著作権契約書を交わすように啓発をする程度で、本格的に法律問題に乗り出すのは更に後のことです。
その後、1957年には木村から引き継いで渡辺義雄が2代目JPS会長になります。渡辺はJPS発足時に会則に「著作権の確立、擁護」を盛り込むように意見するなど、会の創設時から写真家の著作権擁護に強い熱意をもっていました。戦前から戦後にかけては、使用料を支払わずに無断で写真が使用されてしまうことも珍しくなく、写真家が生計を維持するためにも、これまで以上に強力な著作権の確立が必要不可欠だったからです。
1962年4月、文部省は文部省設置法を一部改正し、新たに著作権制度審議会が設置されます。著作権法の全面改正に向けた本格的な作業の一歩目の出来事でした。なお、この審議会には劇作家や評論家、法学者、出版業界、電機メーカーなど、多くの識者が集いましたが、残念ながら写真関係者が構成メンバーに入ることはなく、あくまで意見参考人として会に呼ばれるのみでした。
審議会では、主に保護すべき写真を「芸術写真等、美術的価値を有するもの」に限定するか、報道写真、記録写真、学術写真、肖像写真を含めた広範囲の写真を保護対象とするかといった保護範囲について。そして、写真一般を保護するときに、芸術写真とそれ以外の写真とで保護期間に差異を設けるべきかについても議論がなされました。
丹野章や渡辺義雄ら参考人は、ここでの議論に際して、芸術写真とそれ以外を明瞭に区分けしたり定義することは困難として、保護範囲を広く捉えるべきであること。そして、同様に保護期間に優劣をつけることは困難だと意見しています。また、渡辺らはこのときに、保護期間の起算点を発行時とする考え方に対する質問に対し、写真以外の著作物が著作者の死後を起算点としているのに対し、写真のみ発行の翌年から起算するのは不公平であるとの指摘しています。
最終的には、1965年の審議会で、写真の保護範囲に制限を設けないこと、写真著作物の保護期間は一律で発表後50年という方針が固まります。当時の参議院委員会での質疑では、写真はただシャッターを押すだけで「一般の著作物に比して精神的な創作性の程度が低い」と一般に認識されている。だから、写真記録は保護するよりも公共のために早く自由にすべきだ…といった意見もでており、こういったことが影響しての結論でした。
この方案について、JPSら写真家団体は、写真の保護期間について、他の著作物と同様に「著作者の生存中および死後50年」に改正すべきとの見解が一貫して主張し、複数回にわたり意見書や要望書を提出して抗議します。また、このタイミングでJPSを含めた6団体が合同で全日本写真著作権同盟を組織します。
一方で、写真をできるだけ安く使いたい出版業界や放送業界の団体からは、むしろ写真の保護期間は短い方が良いという意見が出されます。具体的には、写真の保護期間は公表後50年ではなく20年程度にすべきといった主張が強く押し出されていました。
その後も写真家たちの活動の熱は冷めず、1966年10月には第1回写真著作権を守る全国集会が実施され、プロアマ問わず600名以上の参加者がありました。
1970年、著作権法の改正直前の衆参議院委員会では、写真団体と出版団体の意見の食い違いは平行線をたどり、結果としては、先述の1965年審議会での案の通りに著作権法は改正されます(1970年公布,翌年施行)。著作権法の施行の少し後、1971年に写真著作権の管理機構として日本写真著作権協会が設立されます。著作者に代わって著作物から利益を得て分配するというJASRACに似た仕組みを運用する協会です。同協会は2000年に全日本写真著作者同盟と合併し、その後は2009年には一般社団法人となり、現在も活動を続けています。田沼は2000年の合併時から会長となり、以後亡くなるまで会長職を続けます。
1970年の著作権法改正の後、長らく写真著作権は「公表後50年」ルールで運用されていましたが、その間も写真家団体は活動を続けていました。1995年にJPSの5代目会長に就任した田沼は、渡辺義雄ら先人たちの夢であった「没後50年」を達成するために、著作権法の改正に向けた動きを加速させます。
90年代の著作権法の改正はインターネット時代に対応することが主眼でしたが、このタイミングで田沼はロビイングを強め、1996年の改正時に「著作者の没後50年間保護」を実現しました(現在は没後70年間に延長されています)。この成果は、写真家の権利を守る大きな一歩となりました。
また、写真原版の歴史的・文化的価値を強調してきた田沼は、2007年に文化庁委託事業として設立された「日本写真保存センター」の設立に尽力しました。これは、自分の先輩世代の戦中や戦後に活躍した写真家たちの貴重なフィルムが適切に保存されず、劣化や破損が進んでいく現状に危機感を抱いてのことでした。フィルムは保存環境が悪いと、湿気に反応して加水分解を起こして、徐々に表面がベタつきはじめ、最終的には粉々になってしまいます。かといって、写真家の遺族に適切なフィルムの保存を依頼することは、保管のための費用やスペースの問題を考えれば現実的ではありません。田沼はそういった課題を解決するために写真保存のための公共事業の必要性を訴えました。
2003年には文化功労者に選出され、2019年には写真家として初めて文化勲章を受章しました。2022年、黒柳徹子との次の渡航を約束していたなか、田沼は93歳で亡くなります。奇しくも「写真の日」である6月1日のことでした。
粟生田弓,酒井麻千子『写真の著作権保護期間をめぐる議論
-戦後の著作権法全面改正と写真家の活動』,東京大学大学院
情報学環紀要 情報学研究(106),2024.数藤雅彦『写真資料のデジタル保存とインターネット公開に関する 著作権・肖像権等の留意点』,日本写真学会誌 87-2,2024.
54. 白川 義員(1935~2022)

白川義員 著『旧約聖書の世界 : 白川義員作品集』,小学館,1980.
撮影者:不明
白川義員(しらかわ・よしかず)は1935年、愛媛県宇摩郡金生村(現:四国中央市)に生まれました。彼は中学生の頃、親戚から譲り受けたカメラをきっかけに写真の世界に触れ、写真コンテストで入賞を果たします。その後、高校では写真部を創設し、日本大学芸術学部写真学科に進学しました。卒業後はニッポン放送やフジテレビで勤務したのち、1962年に中日新聞社の特派員として世界35か国を取材し、フリーランスの写真家として独立しました。
白川の作品は「地球再発見による人間性回復へ」をテーマに掲げ、原始的な自然や聖地を撮影することに特徴があります。彼は特に山岳写真や大自然の荘厳さを捉えることに情熱を注ぎました。代表作には『世界百名山』や『永遠の日本』があり、これらのプロジェクトでは数年をかけて世界各地を巡り、日の出や日没といった瞬間的な美しさを追求しました。
ウユニ塩湖やザ・ウェーブなど、観光地として知られる以前の未踏地を訪れ、その風景美を初めて世界に紹介する役割も果たしました。
1996年以降は「世界百名山」の撮影プロジェクトに着手し、さまざまな大陸の山岳を取材しながら写真展を開催しています。27か国127座もの山々を空撮し、その中から100座を選定して作品集として発表しました。このプロジェクトはNHKスペシャルでも取り上げられ、多くの人々に自然への畏敬と保護意識を喚起しました。
白川を語るうえで外せないことの一つに、パロディー・モンタージュ写真事件があります。事件の経緯は以下のとおりです。
白川は、オーストリアのチロル州にあるサンクト・クリストフという雪山で、1966年にスキーヤーたちが描いた美しいシュプール(スキー板の跡)を撮影しました。この写真は「雪山の波」とも言える独特の光景をカラーで捉えたもので、白川のこだわりと努力が詰まった作品です。撮影許可を得るためには約2か月もの交渉が必要で、ヘリコプターを使ったりするなど、費用も1,000万円に及びました。この写真は、翌1967年に『SKI '67第四集』という写真集や、1968年の米資本保険会社AIU’(現:AIG)のカレンダーにも使用されました。
この写真を巡って問題が起きたのは、1970年のことです。グラフィックデザイナーのマッド・アマノが、この雪山写真を無断で改変し、自身の写真集『SOS』や雑誌『週刊現代』に掲載したのです。アマノは、雪山のシュプールがタイヤのわだちに似ていることに着目し、この写真を加工して、巨大なタイヤを雪山に合成しました。巨大タイヤを背にしたスキーヤーたちが雪山を滑りながら必死に逃げているような構図に仕立てることで、自動車公害に追われる人々の悲しさを表現した風刺的なパロディにしたとアマノは説明しています。元の写真が使われたAIUが自動車保険も扱っていることから、自動車関連企業の姿勢に対して疑問を投げかける意図も込められていたようです。
アマノの作品は白黒に加工されており、元のカラー写真の雰囲気を大きく変えていました。また、この作品には白川の名前が表示されることなく、アマノさん自身の名前が著作権マークとともに記載されていました。
これを知った白川は、自身の氏名表示を省かれただけでなく、著作物の内容を大きく変更されたとして提訴し、著作権法上の財産権侵害と著作者人格権の侵害を強く訴えました。一方アマノは、社会風刺としてのパロディ作品であり、世界的にも認められた芸術手法であるモンタージュの一環なのだから正当化されると主張しました。最高裁まで争った裁判でしたが、最終的には天野の作品は引用やパロディと認められる範囲を逸脱していると判断されました。 この訴訟で特に注目を集めたのは、最高裁が示した「明瞭区別性」と「主従関係」の二要件と呼ばれる基準です。この判例によって、他人の著作物の引用に際しては引用箇所がどこからどこまでか明確に分かるようにしなければならないこと、またその引用部分が被引用者側であり、自らの創作部分が主でなければならないという考え方が確立されました。
この事件は、パロディや風刺といった創作の自由と、原著作者の権利のバランスをいかに保つかを探る過程で大きな反響を呼び、最終的には16年にわたる長期係争の末、疲弊した当事者同士は和解の道を選ぶこととなりました。その後もこの判例は、社会問題を風刺するためのパロディ表現がどこまで許容されるのか、あるいは原著作物の保護がどの程度まで及ぶのかの論点に光を当てる重要な先例として位置づけられます。
また、判例上定義された「引用」の二要件が後の裁判例や著作権法改正に少なからぬ影響を及ぼしました。
55. 岡村 昭彦(1929~1985)
岡村昭彦(おかむら・あきひこ)は、1929年に東京の原宿で生まれました。父方の曽祖父には宮内官僚で男爵の堤正誼、母方の曾祖父には、佐賀の七賢人の一人に数えられる伯爵の佐野常民と華やかな家系にあり、いわゆる御曹司でした。
岡村は学習院初等科、中等科を経て東京中学校に転校。
転校と同時に他家へ預けられ、そこから通学していました。しかし戦況の悪化に伴い蒲田の軍需工場へ勤労動員され、ほとんど学校へ行かなかったようです。1945年3月に中学を卒業した後は、伯父の緒方知三郎が学長を務める東京医学専門学校(現在の東京医科大学)へ進学します。空襲で原宿の邸宅が焼け落ちてしまったので、別荘の鎌倉に一家で移り住み、そこから学校へは通っていました。
岡村が専門学校に進学した少し後、戦争が終結。敗戦後の公職追放のために海軍参謀を務めていた父親は失職し、生活が困窮します。岡村は東京医専に通いながら、とにかく働いて病弱な母や親戚らを必死に支えました。
働きながら医師を目指して勉強をしていた岡村ですが、1947年、学費値上げに反対して演説を行い、東京医学専門学校から退学処分を受けます。
その後は方々を渡り歩き、ほどなくして、日本共産党に入党します。入党後は弟が札幌にいたつてで1950年に北海道に渡り、共産党の山村工作に従事していたこともあったようです。
1951年の初冬、岡村は釧路へと移り住みます。同年10月に開催された日本共産党の第5回全国協議会(五全協)の決定に基づくものでした。五全協では、中国の毛沢東戦略に倣い、農村部への非公然の武装宣伝隊「山村工作隊」を組織することが決まり、農村部で党の拠点(解放区)を築く目的で多数の人員が配置されました。岡村もこの一員だったわけです。
ここで岡村は「岡村照彦」の偽名を用い、医師免許を持たぬまま東京大学医学士と称しながら医院を開業しました。無資格の女子高生を看護婦に仕立てて同居し、薬局から医薬品を詐取しながら偉業を行っていたのですが、すぐにそのことが発覚し、1951年12月16日に釧路市警に詐欺容疑で逮捕されます。さらに、医師法違反、医療法違反、堕胎罪といった複数の容疑が追及され、岡村の非合法な医療行為による被害を訴える女性たちの証言も相次ぎました。釧路地裁は1952年1月26日に懲役4月の実刑判決を下し、岡村は釧路刑務所に収監されました。既に1949年には医師政令違反で執行猶予付きの懲役刑を受けており、さらに1950年には横浜地裁で米国ドル不法所持の罪で有罪判決を受けていたため、執行猶予が取り消されて服役を余儀なくされました。
出所後の岡村は、修道院の客室係や書店員として働いた後、九州三井三池炭鉱でおこった三池闘争に参加します。炭鉱労働者たちの中で生活するうちに、部落解放運動家で社会党の重鎮だった松本治一郎と出会い、部落問題への関心を深めていきました。1959年頃には部落解放同盟に参加し、オルグ活動をしながら東京荒川の皮革工場で働き、安保闘争にも参加しています。1961年からは千葉県に拠点を移し現地で部落解放運動を続けます。岡村は行政に働きかけ、生活改善に取り組むとともに、子どもたちの教育にも力を入れ、この過程で出会った部落出身労働者とともに生活し、冤罪事件や下水問題など地域の諸問題に取り組むなどしました。
しかし、新参者の岡村が瞬く間にムラでリーダー的存在になったことに、一部のムラ人は反発しました。岡村は子供たちの教育、排水溝の建設、養豚事業など、次々と新しい取り組みを始め、人々を巻き込んでいきました。その行動力から、世話になった人々からは「英雄」として尊敬されましたが、ムラの秩序を乱し、既得権益に触れられることを嫌う一部の人々は、「うまいところを取られる」として反感を抱いたようです。
養豚事業で成長した豚を売却する際に、その売買代金をめぐるトラブルが発生すると、その問題の責任を、岡村さんが背負うことになったほか、その地域の若者たちによる輪姦事件が『週刊実話』に詳細に報じられた際、情報提供者とみなされて彼らから激しい糾弾を受けることとなります。こういった、事情が重なり、岡村は1961年にその場を去らざるを得なくなりました。
そんな折に、労働組合の全国組織・総評(日本労働組合総評議会)が1961年に創刊した週刊誌『新週刊』の編集部からスカウトされます。新週刊では上野英信、土門挙、三木淳らといった作家やジャーナリストと交流を深める機会を得て、これが後の岡村の活動にもつながっていきます。
その後、『新週刊』が廃刊となったため、1962年からはPANA通信(Pan-Asia Newspaper Alliance)の契約特派員に転職し、同年末に初の海外取材でバンコクへと向かいます。これ以降、岡村は南ヴェトナムの戦場を駆け回り、「報道写真家」としての活動をはじめることになります。
このように、岡村の写真家としてのキャリアは比較的遅くに始まりました。1962年、33歳でPANA通信社に入社し、特派員となって初めてカメラを購入しました。カメラについては全くの素人で、バンコクに行く途中、香港でM型ライカ(M3)を購入したものの、フィルムの詰め方もわからなかったそうです。
1963年から、岡村はラオスやベトナムでの戦争取材を開始し、その後も世界各地の紛争地域で精力的に活動しました。彼の写真は『毎日グラフ』『朝日ジャーナル』『世界』『ライフ』などの雑誌に掲載され、1964年には講談社写真賞を受賞しました。
1965年、岡村は『ライフ』誌と契約を結び、PANA通信社を退社します。同年、彼の著書『南ベトナム戦争従軍記』が出版され、ベストセラーとなりました。この年、岡村は芸術選奨文部大臣賞、アメリカ海外記者クラブ最優秀報道写真年度賞、日本写真協会年度賞を受賞し、その功績が広く認められました。
岡村の写真に対する思想は、従来の報道写真の手法とは一線を画すものでした。彼はマグナム的な主流の報道写真の特徴であるモノクローム、決定的瞬間、ヒューマニズムの表現に対して、カラー写真の使用、アンチクライマックスの瞬間の捉え方、人間の感情ではなく行動を撮ることを重視しました。当時の報道やアートの世界では、「モノクロこそがプロの仕事であり、カラーはアマチュア」という棲み分けが一般的でした。そのような状況下で、岡村がカラーで撮影した米兵の死体の写真は非常にセンセーショナルでした。このアプローチは、正統な写真教育の枠を外れた道から写真の世界に入った岡村ならではのものと言えます。
岡村は「証拠力のある写真」という概念を提唱しましたが、これは一般的に理解されているような衝撃的な瞬間を捉えた写真ではありませんでした。むしろ、日常と戦場の連続性を示すような、より静的で象徴的な場面を捉えることを重視しました。
彼のカラー写真の使用は、日常の色彩を戦場に持ち込むことで、視聴者により身近な感覚で戦争の現実を伝えようとする試みでした。また、異常なアングルを避け、できるだけ自然な視点で撮影することも彼の方針でした。
1972年の『ライフ』誌休刊後も、岡村は世界各地での取材活動を続けました。しかし、1980年代に入ると、彼の関心は次第にバイオエシックス(生命倫理)へと移っていきました。1982年頃からは、看護師、医師、母親らを対象にバイオエシックスやホスピスについての講演を行い、これらのテーマに関する著作活動も活発に行いました。
岡村昭彦の人生は、写真家としての15年余りの活動期間に集中的に行われた撮影活動と、その前後の多様な経験によって形作られました。彼は5万点の写真と2万点以上の蔵書を残し、1985年に56歳で亡くなりました。
56. 藤井 秀樹(1934~2010)
藤井秀樹(ふじい・ひでき)は、1952年に東京都立白鷗高等学校を卒業後、日本大学芸術学部写真学科に進学し、写真家の秋山庄太郎に師事しました。
藤井の職業キャリアは1957年、株式会社婦人生活社への入社から始まりました。その後、1960年に日本デザインセンターの設立と同時に入社し、広告写真の分野で活動を開始しました。1963年にはフリーランスの写真家として独立し、1965年にスタジオ・エフを設立しました。この時期、藤井はマックスファクターの国内キャンペーンを担当し、朝日新聞広告賞を受賞するなど、広告写真界で注目を集めました。
1970年代から1980年代にかけて、藤井は国内外で多数の個展を開催し、その作品は世界的に高い評価を受けました。特筆すべきは、1976年にロンドンのフォトグラファーズギャラリーで開催された「ヘルムート・ニュートンとの二人展」です。1977年には、スティーリー・ダンの6作目のアルバム『彩(エイジャ)』のジャケットに、藤井が撮影した山口小夜子の写真が起用されました。このジャケット写真は、赤と黒と白のみの色使いと山口小夜子の圧倒的な存在感で、アルバムのイメージを見事に表現し、高い評価を得ました。
2002年には学校法人呉学園日本写真芸術専門学校の校長に就任し、同年、日本広告写真家協会の会長にも就任しました。2007年には同協会の顧問となり、さらにNPO法人全日本福祉写真協会の顧問にも就任しました。
57. 東松 照明(1930~2012)
東松照明(とうまつ・しょうめい)の写真家としてのキャリアは、愛知大学法経学部経済学科在学中の1954年に始まりました。土門拳・木村伊兵衛が審査員を務める「カメラ(CAMERA)」の月例コンテストに応募し、学内新聞に発表した「皮肉な誕生」が反響を呼びました。卒業後、『岩波写真文庫』のスタッフとなりましたが、1956年にフリーランスとなります。
1958年、東松は「地方政治家」を題材にした作品群で日本写真批評家協会新人賞を受賞しました。翌1959年には、奈良原一高や細江英公らと共に写真家集団「VIVO」を設立します。この結成には、1957年に東京の小西六フォトギャラリーで開催された写真評論家・福島辰夫企画の第1回『10人の眼』展が大きな契機となりました。
当時の日本写真界では、土門拳を中心とする「リアリズム写真運動」が強い影響力を持っていましたが、VIVOはそれに対抗し、新しい日本の現代写真表現を模索しました。彼らは「私的」あるいは「主観的」な写真表現、そして写真家の個性が反映された作品を目指しました。さらに、VIVOの設立には、写真家自身が作品の使用をコントロールしたいという意図もありました。マグナム・フォトをモデルにしたセルフ・エージェンシーを目指し、単なる写真家の集団ではなく、写真家の権利を守る組織としての性格も持っていました。VIVOは1961年6月までの約2年間と短い活動期間でしたが、後の写真界に大きな影響をもたらしました。「映像派」と呼ばれた彼らの極端なクローズアップやハイコントラストな画調などの技法的な実験性は、現代の写真表現にも受け継がれているといえます。
1961年には土門拳らと広島、長崎の被爆者、被爆遺構などを取材し、『hiroshima-nagasaki document 1961』を刊行しました。この作品で第5回日本写真批評家協会作家賞を受賞しています。
1960年代、東松は都市や社会問題に焦点を当てた作品を多く制作しました。石油コンビナート、住宅群の空撮、無表情なビルや人物のスナップ、学園紛争、新宿周辺のアングラ文化などを撮影し、戦後日本の社会情勢を凝縮したような多様な視点を示しました。
1969年、東松は「アサヒカメラ」の特派として初めて沖縄を2カ月間取材しました。東松は沖縄への取材をまとめて、写真集『沖縄に基地があるのではなく基地の中に沖縄がある』を出版しました。その後、1972年に東松は沖縄の「日本復帰」を那覇で迎え、1年間滞在しました。翌1973年には宮古島に移住し、7カ月間滞在しています。この頃は基地問題だけでなく豊かな自然や琉球文化にも関心を深めていきました。その成果は1975年の写真集『太陽の鉛筆』に結実し、日本写真協会年度賞、芸術選奨文部大臣賞、毎日芸術賞を受賞しています。
沖縄から帰った東松は、1974年にWORKSHOP写真学校を設立します。荒木経惟、深瀬昌久、細江英公、森山大道、横須賀功光といった当時第一線で活躍していた写真家たちが講師を務め、それぞれが週1回、寺子屋形式で写真教室を開講しました。この学校は機関誌『季刊WORKSHOP』を刊行し、独自の情報発信も行っていました。WORKSHOP写真学校は、1970年代後半の自主ギャラリーの設立ブームを担ったことでも知られます。
1970年代、特に東京を中心に、若手写真家たちが自主運営するギャラリーが次々と誕生しました。例えば、綜合写真専門学校の学生を中心に始まった「プリズム」(1976-77)、WORKSHOP写真学校・森山大道教室の卒業生たちによる「CAMP」(1976-84)、そして同じくWORKSHOP写真学校・東松照明教室の出身者たちによる「PUT」(1976-79)などが活発に活動を展開しました。
この自主ギャラリー・ブームの背景には、それまでの写真展の多くが、カメラ関連企業(ニコンや小西六など)のギャラリーを主な発表の場としてきたという状況がありました。こうした既存の場に依存せず、新しい発表の場を求めた若者たちは、自分たちのスペースを確保し、展覧会の開催だけでなく、印刷物の発行や自主ギャラリー同士の交流を通じて、新たな写真表現の可能性を探求していきました。
展示される写真作品は多岐にわたりましたが、特にコンセプチュアルな方法論に挑戦する若い写真家たちの活動を支える場として、自主ギャラリーは重要な役割を果たしました。
東松の写真を語る際にとりわけ話題にされるのは、「群写真」という概念でしょう。これは、名取洋之助の「組写真」(ストーリーを主張するための素材、道具として写真を挿絵のように使う手法)に対する反発から生まれたもので、複数枚の写真により映像自体を語らせ、作家の思想を語らせる手法です。
1984年には「SHOMEI TOMATSU Japan 1952-1981」展がウィーン近代美術館などで開催され、1992年にはメトロポリタン美術館で「SAKURA +PLASTICS」展が開かれるなど、国際的な評価も高まりました。
1998年に長崎に移住した東松は、1999年に「日本列島クロニクル―東松照明の50年」展(東京都写真美術館)を開催し、日本芸術大賞を受賞しました。2000年代に入っても精力的に活動を続け、晩年まで精力的に作品を発表し続けました。
58. 奈良原 一高(1931~2020)
1931年に福岡県で生まれた奈良原一高(ならはら・いっこう)は、検事であった父親の転勤に伴い、国内各地で青春期を過ごしました。
奈良原の写真への興味は早くから芽生え、1946年に写真の撮影を始めています。1954年に中央大学法学部を卒業後、さらに学びを深めるため早稲田大学大学院芸術(美術史)専攻修士課程に進学しました。
1955年には、新進気鋭の芸術家たちが集まる「実在者」というグループに参加し、池田満寿夫や靉嘔らと交流を持ちました。さらに、池田龍雄や河原温といった芸術家、そして美術評論家の瀧口修造らとも親交を深めていきました。この時期、同じく写真家として活動を始めていた東松照明や細江英公とも知り合うことになります。
1956年、奈良原は松島ギャラリーで「人間の土地」と題した個展を開催します。これが彼のデビュー作となり、写真家としての道を本格的に歩み始めるきっかけとなりました。
1959年、奈良原は東松照明や細江英公らとともにセルフ・エージェンシー「VIVO」を設立しました。この団体は、戦後の日本写真の独立性を高めるために活動し、商業写真から距離を置きつつ、アートとしての写真の可能性を追求しました。しかし、1961年に解散しています。
その後、奈良原はヨーロッパやアメリカを活動の拠点としました。1962年から1965年にかけてパリに滞在し、1970年から1974年にはニューヨークで活動しました。この期間中、彼は「人間の土地」や「消滅した時間」など、歴史や文化、社会的なテーマを掘り下げたシリーズを発表しました。これらの作品は、彼が一貫して抱き続けた「人間と空間の関係性」というテーマを深めたものであり、独自の視点で世界を捉えています。
彼の作品は、単なる瞬間の記録ではなく、時間の流れや人間の営みを深く見つめるものでした。特に初期の代表作『王国』は、北海道の男子修道院と和歌山県の女子刑務所という、外界から隔絶された場所を撮影したシリーズで、強烈な印象を与えました。
奈良原の写真は、強い構成力と抽象性を持ち、観る者に深い感覚的体験を与えます。その芸術観は、単なるリアリズムを超え、写真を詩的かつ哲学的なものとして再解釈しました。彼は「写真は単なる記録ではなく、人間が自然や社会に向き合うための手段である」といった信念を持って創作を続けました。
晩年には、九州産業大学大学院で教授を務め、後進の育成にも力を入れました。
59. 細江 英公(1933~2024)
細江英公(ほそえ・えいこう)は、1933年に山形県米沢市で生まれ、東京で育った写真家です。戦時中は米沢市に疎開しましたが、神主だった父親は東京に残って仕事を続けました。
細江の写真への興味は幼少期から始まり、父親のカメラを借りて撮影を始めました。15歳で初めて自分のカメラを購入し、18歳だった1951年に「富士フォトコンテスト」の学生の部で《ポーディちゃん》が最高賞を受賞します。1952年、東京写真短期大学(現・東京工芸大学)の写真技術科に入学すると、デモクラート美術家協会の中心人物だった瑛九と出会い、強い影響を受けます。1954年に卒業後、フリーランスの写真家としてキャリアをスタートさせ、写真雑誌や女性雑誌などの仕事を始めました。
1956年に初個展「細江英公写真展 フォトストーリー『東京のアメリカ娘』」を銀座の小西六フォトギャラリーで開催しました。1959年には、東松照明、奈良原一高、川田喜久治らとともに写真家によるセルフエージェンシー「VIVO」を結成しました。VIVOは、当時主流だったドキュメンタリー写真の客観的な現実描写に対し、より個人的な視点を追求しました。
1960年に『おとこと女』で日本写真批評家協会新人賞を受賞し、生と死というテーマや人間の肉体にアプローチした独自の耽美な世界観で高い評価を獲得しました。同年には映像作品《へそと原爆》も制作しています。
細江の代表作の一つとして、1963年に発表された三島由紀夫の裸体をとらえた『薔薇刑』があります。この作品は細江の名を世界に轟かせ、特にバラを口に咥えた三島の顔をアップで撮った一枚は彼を代表する作品になりました。
暗黒舞踏家との交流でも知られる細江は、1969年に秋田の農村を舞台に舞踊家の土方巽を写した『鎌鼬』で芸術選奨文部大臣賞を受賞しました。また、2006年には大野一雄を46年間撮り続けた写真集『胡蝶の夢 舞踏家・大野一雄 細江英公人間写真集』を刊行しています。
細江は写真文化の発展や後進の育成にも尽力し、1974年には若手写真家による寺子屋形式の学校「WORKSHOP写真学校」の設立に参加しました。1975年に東京写真大学短期大学部教授となり、1994年には東京工芸大学芸術学部教授に就任しました。1995年には清里フォトアートミュージアムの初代館長に就任し、亡くなるまで館長職を勤めました。
細江の功績は国内外で高く評価され、1998年に紫綬褒章を受章、2003年には世界を代表する写真家7人の1人として英王立写真協会創立150周年特別記念メダルを受章しました。2006年には写真界の世界的業績を顕彰するアメリカのルーシー賞の「先見的業績部門」を日本人として初めて受賞しました。
細江英公は2024年9月16日、91歳で左副腎腫瘍のために東京都杉並区の病院で死去しました。
細江英公 『新版 薔薇刑 : 細江英公写真集』,集英社,1984.
『薔薇刑』は同タイトルで今までに6度にわたって出版されている。63年の初版と84年版とではデザインが大きく異なる。
60. 深瀬 昌久(1934~2012)
深瀬昌久(ふかせ・まさひさ)は、北海道中川郡美深町で生まれ、1908年に祖父が創設した深瀬写真館の3代目跡継ぎとして期待されて育ちました。幼少期から写真に触れる機会が多く、6歳の頃からプリント水洗の仕事を手伝っていたといいます。
深瀬は日本大学芸術学部写真学科に進学し、1956年に卒業後、第一宣伝社に入社して商業写真を中心とする仕事に就きました。1960年には初の個展「製油所の空」を小西六ギャラリーで開催しましたが、これは会社の仕事として撮った写真を構成したものでした。
本格的なアーティストとしてのデビューは、1961年の写真展「豚を殺せ」(銀座画廊)で、これをきっかけに専業写真家としての道を歩むこととなり、深瀬写真館は後に弟の了暉が継ぐことになります。この時のことを深瀬は「写真師と写真家の岐路になった」と振り返っています。
1964年には日本デザインセンターに移り、同年鰐部洋子と結婚しました。1967年には河出書房新社に入社して写真部長となりましたが、翌1968年に退社してフリーランスの写真家となります。
深瀬の代表作《洋子》は、彼の妻・洋子を被写体に10年以上にわたり撮影された写真シリーズです。結婚後も撮影を続けた深瀬は、1960年代には夫婦で暮らしていた草加松原団地を舞台に、1970年代には北海道や金沢、伊豆などの旅行先で洋子を撮影しました。特に印象的なのは、1973年の秋、深瀬が毎朝洋子が勤め先の画廊へ出勤する姿を四階の自宅窓から望遠レンズで撮影し続けたことです。この写真群は「洋子」と題され、誌上で発表されました。翌1974年には、ニューヨーク近代美術館で開催された写真展「New Japanese Photography」にも《洋子》が出品され、国際的な評価を得ています。
しかし、長年の撮影を続ける中で、二人の間に「写真を撮るために一緒にいる」という矛盾が生じるようになり、1976年に深瀬と洋子は別れることとなりました。このシリーズは、深瀬と洋子の関係性の変化や複雑さをも浮かび上がらせる作品群として、深瀬の代表作に位置づけられています。
1976年の春、深瀬は妻・洋子との離婚をきっかけに旅に出ます。幼少期の記憶が残る北海道を訪れ、函館から故郷の美深町まで北上。さらに根室の納沙布岬、釧路、標茶、トドワラ、美幌、網走、襟裳岬など各地を巡りながら撮影をしました。東京に戻り、写真家の山岸章二にその写真を見せた際、カラスが印象的に写っていたことから「鴉(カラス)」というタイトルを勧められます。同年、15年ぶりとなる写真展「鴉」を開催し、この作品は深瀬の代表作の一つとなりました。また、この展示は高く評価され、翌1977年には第2回伊奈信男賞を受賞しています。
深瀬は生涯にわたり多くの猫と暮らし、その姿を写真に残しました。特に印象深い存在が、サスケとモモエです。1977年の初夏、洋子との離別から半年ほどが経った頃、深瀬は友人で写真家の高梨豊の紹介で子猫を譲り受けます。その活発な動きが忍者の猿飛佐助を思わせたため、「サスケ」と名付けました。しかし、譲り受けて間もなくサスケは行方不明になり、再会を果たせないまま、深瀬はよく似た別の子猫を引き取ります。この新たな子猫も「二代目サスケ」と名付けられ、深瀬はどこへ行くにも連れ歩くほど可愛がりました。
翌年、成猫となり動きが緩慢になったサスケに刺激を与えるため、深瀬は再び子猫を引き取り、「モモエ」と名付けて飼い始めます。二匹との日々を振り返り、深瀬は「私はみめうるわしい可愛い猫でなく、猫の瞳に私を映しながら、その愛しさを撮りたかった」と記しています。猫たちとの生活は「サスケ!! いとしき猫よ」(1978)や「猫の麦わら帽子」(1979)にまとめられています。
1970年代は核家族化と一億総中流ともいわれた所得水準の向上によりペット需要が拡大した時代でした。また、1972年に日本で初めての商業猫雑誌である『キャットライフ』が創刊されます(なお、同人猫雑誌の歴史はさらに古く、1950年代からありました)。その後も猫専門誌が次々に創刊され、「サスケ」が出版された1978年はまさに猫ブーム真っ只中でした。深瀬の猫写真は当時の猫ブーム乗るかたちで出版されたものでした。
深瀬の語りをみると、妻・鴉・猫、いずれのモチーフにおいても、深瀬は被写体を通して自分自身を撮影していたとも言えるかもしれません。
1985年頃から、深瀬は中断していた家族写真の撮影を再開しました。1987年には父の死までを撮った写真をまとめて写真展「父の記憶」を開催し、1991年には『家族』を出版しています。
しかし、1992年に新宿ゴールデン街の行きつけの店で階段から転落し脳障害を負い、20年間の闘病の末、2012年6月9日に78歳で亡くなりました。この事故以降、深瀬の作家活動は途絶え、一切作品制作はしませんでした。
61. 高梨 豊(1935~)
高梨豊(たかなし・ゆたか)は1957年に日本大学芸術学部を卒業後、八木治のスタジオに就職しました。その後、桑沢デザイン研究所に入学し、大辻清司に師事します。
1961年に桑沢デザイン研究所を卒業し、日本デザインセンターに入社。この時期から広告写真の分野で活躍し始め、その才能を発揮します。
1964年に「オツカレサマ」で第8回日本写真批評家協会新人賞を受賞し、1967年には第5回パリ青年ビエンナーレ写真部門大賞を獲得しました。
1968年、高梨は中平卓馬、多木浩二、岡田隆彦らと共に写真同人誌『PROVOKE』を創刊します。この雑誌は戦後日本の写真表現に革命をもたらし、高梨の写真家としての立場を確立する重要な出来事となりました。『PROVOKE』は1970年に活動を休止しましたが、その影響力は日本の写真界に長く残りました。
1970年代、高梨は日本デザインセンターを退社しフリーランスとなり、都市と人間の関係を探求する作品を多く発表しました。代表作『都市へ』(1974)や『町』(1977)は、この時期の成果です。
1980年代に入ると、高梨は東京造形大学で教鞭を執り始めました。1980年に助教授、1983年に教授となり、2000年には客員教授を務めました。この間も精力的に作品を発表し続け、1983年に『東京人 1978〜1983』で第34回日本写真協会賞年度賞を受賞しました[1]。
1990年代には、高梨の作品がさらに評価され、多くの賞を受賞しました。1991年に第3回「写真の会」賞、1993年に第9回東川賞国内作家賞、1994年に第43回日本写真協会賞年度賞を受賞しています[1]。また、1993年には赤瀬川原平、秋山祐徳太子と「ライカ同盟」を結成し、ライカカメラを使用した独自の写真活動を展開しました。
2000年代に入っても、高梨の創作活動は衰えを見せませんでした。『地名論』(2000年)、『ノスタルジア』(2004年)、『囲市』(2007年)などの写真集を発表し、都市や場所の持つ意味を探求し続けました。
2009年には東京国立近代美術館で個展「高梨豊 光のフィールドノート」が開催されました。この展覧会は高梨の最初期の作品から最新作までを紹介する過去最大規模の個展となり、日本人写真家の個展としても同美術館最大規模のものでした。
2012年には写真集『IN'』で第31回土門拳賞を受賞し、同年にはパリのアンリ・カルティエ=ブレッソン財団で個展「Yutaka Takanashi」を開催しました。
高梨豊の写真に対する考えは、都市という主題を通じて一貫して表現されています。彼は半世紀以上にわたるキャリアを通じて、さまざまな方法論を駆使し、変化し続ける都市の姿を捉え続けてきました。高梨の作品は、単なる都市の記録にとどまらず、都市と人間の関係性、そして時間の流れの中で変化する都市の姿を深く探求しています。
62. 石黒 健治(1935~)
石黒健治(いしぐろ・けんじ)は福井県生の写真家。1959年に桑沢デザイン研究所を修了し、同年に写真協会新人奨励賞を受賞しました。
石黒の写真作品は、1950年代後半から1960年代にかけての東京の前衛的な芸術シーンと密接に関連しています。この時期は日本の急速な経済成長の始まりであり、石黒の作品はこの不安定で変化の激しい時代を反映していました。
アーティスト、建設労働者、学生運動家、街路など、幅広い主題を扱い、ファインアート的な構図、フォトジャーナリズム的なアプローチ、あるいはスナップショット的な手法で撮影していて、ひとつのテーマに固執しないこと時代がテーマとなりました。この多様性は、石黒が「不連続性を通じた連続性」と呼ぶ実践の一部でした。
彼の代表的な写真展には「不幸な若者たち」「ナチュラル」「シアター」「夫婦の肖像」などがあります。また、写真集としては「健さん」「広島HIROSHIMA NOW」「ナチュラル」などを出版しています。
石黒の作品は、戦後の都市の解体と戦前の芸術の解体を記録し、それに参加する行為でもありました。彼のカメラは、変化する日本社会を捉える道具であり、同時に芸術表現の手段でもありました。
石黒の活動は写真だけにとどまりませんでした。ミステリードキュメント「サキエル氏のパスポート」を出版するなど、文筆活動も行っています。さらに、映画製作にも携わり、今村昌平監督の『人間蒸発』では撮影を担当し、『無力の王』(東映セントラル)では監督を務めるなど、多方面で才能を発揮しました。
2016年には、写真集『不思議の国 FAIRYLAND』(彩流社)を刊行しました。この作品は、石黒の長年にわたる写真家としての経験と視点を集大成したものと言えるでしょう。
石黒の写真は、一見すると様式や主題に断絶があるように見えますが、全体としては一貫した作品群として統一性を持っています。この「不連続性を通じた連続性」という概念は、石黒の芸術哲学の核心を表しています。彼は、多様な被写体や撮影技法を用いることで、変化する社会の複雑さを表現しようとしました。
63. 今井 壽惠(1931~2009)
今井壽惠(いまい・ひさえ)は、1931年、東京・東中野にある「今井写真館」の長女として誕生しました。父の康道は銀座松屋写真部長を務めており、写真との深い縁が彼女の生い立ちから築かれていました。
今井一家は敬虔なキリスト教徒でもあり、戦時中は、家族は疎開先の静岡県三島で「神国日本を滅ぼそうとしている異教徒」とされ、理不尽な迫害を受けました。特に父・康道はスパイ容疑をかけられ、特高警察に拘束されるという過酷な状況に置かれました。彼は拘束中に拷問を受け、その苦しみを家族で耐え抜いた経験は、今井の人生観にも深い影響を与えたと考えられます。
1950年頃、今井は文化学院の芸術科に入学。学院では柳宗理などからのレッスンを受けて、一連の勉強の中でマン・レイの作品などに影響を受けました。1952年に文化学院美術科を卒業、その後に本格的に写真の世界に足を踏み入れました。
学生生活を終えた彼女は、結婚を考えながらも、その前に何か形に残せるものを作りたいという強い思いを抱いていました。そんな折、父の友人である富士フィルム宣伝部長・平松太郎氏から写真展の開催を勧められたことが、彼女の新たな一歩を後押しします。
須賀の海辺や御宿海岸を訪れ、打ち上げられた魚の死体、捨てられた冷蔵庫、海草や貝殻といった、彼女だけの視点で捉えた光景を写真に収めます。こうして撮影された作品は1956年、彼女の初めての個展「白昼夢」で展示されました。ジャン・コクトーの影響を受けた彼女の作品は、心象風景を写し出し、文学的かつ自由な表現を写真という媒体で繊細に描き出しました。当時、リアリズム写真が主流であった中、彼女の前衛的な作品は一躍話題となり、新人女性写真家として大きな注目を集めることになります。
同世代の写真家集団「VIVO」らの活動とともに、写真界に新しい風を吹き込みました。
1959年には「ロバと王様とわたし」で日本写真批評家協会新人賞を受賞し、1960年には「オフェリアその後」でカメラ芸術・芸術賞を受賞するなど、詩的な写真作品で高い評価を得ました。コマーシャルの仕事でも多忙を極めていた今井でしたが、1962年にタクシーに乗っていたときに交通事故に遭遇し、一命は取り留めたものの、療養生活は三年にも及び、そのうち一年半もの間視力を失うという試練に直面します。乗ったタクシーが対向車線のタクシーと正面衝突する大事故でした。
今井は当時30歳。高円寺にスタジオを構え、『装苑』や『婦人画報』などの雑誌で月に数百ページに及ぶ撮影を手がける、飛ぶ鳥を落とす勢いの売れっ子写真家でした。助手を務めていた写真家・浜野祐子によれば、今井は「ひと月働けば家が一軒建つ」ほどの稼ぎがあったといいます。しかし、その輝かしい成功は一瞬にして失われてしまいました。さらに追い打ちをかけるように、婚約者からは病室で「なかったことにしてほしい」と告げられ、婚約破棄を言い渡されます。身心ともに傷つき、事故後の1年半は文字通り暗闇の中で過ごす日々となりました。
視力を回復した後、今井の人生に大きな転機が訪れます。映画「アラビアのロレンス」に登場する生命力溢れる馬の姿に深く感動したことをきっかけに、馬への関心を持ち始めたのです。親交のあった寺山修司に競馬の世界へ導かれ、1970年にイギリスで名馬「ニジンスキー」と出会います。人間以上の気品と細やかな情感を持つ馬の精神性の高さに衝撃を受けた今井は、以降、世界中の牧場や競馬場でシャッターを切り、競走馬の血統を追究していきました。
今井は馬に深い愛情を傾け、心を通わせることで、単なる生態記録を超えた、馬の個性や特徴を引き出した写真を撮影しました。その独特の視点と技術により、馬写真の第一人者として国内外で認められるようになりました。
「情感を馬の写真に持ち込んだのは、私が最初かもしれません」と語っているように、今井は馬を単なる被写体としてではなく、感情を持つ存在として捉え、その瞬間の最高の表現を追求し続けました。
また、「馬の写真はその馬を最高に表現したものが一枚あればいい」という信念を持ち、撮影の前から、どの馬をどこでどのように撮りたいかをはっきりと決めていたといいます。そのために、馬を追いかけ、最高の瞬間を待ち、撮り続けるという姿勢を貫きました。
2009年に逝去した今井ですが、その功績は2010年に2009年度JRA賞馬事文化賞功労賞を受賞するなど、死後も高く評価され続けています。我々が普段見かける競馬写真の多くは今井の写真の影響を受けています。今井の撮影した競走馬のポートレートは、競走馬を単なる賭けの対象としてではなく、愛好すべき対象としてアイドル視するような現代的態度の下地のひとつと言えるでしょう。
64. 沢田 教一(1936~1970)
沢田教一(さわだ・きょういち)の写真への興味は、1955年に青森市の小島写真店でアルバイトとして働き始めたことがきっかけでした。ここで彼は写真技術を習得し、店主の小島一郎から影響を受けました。また、この時期にロバート・キャパの『イメージズ・オブ・ウォー』やアンリ・カルティエ=ブレッソンの『決定的瞬間』に触れ、報道写真家としての道を志すようになります。
1961年、上京した沢田はUPI通信社東京支局に入社し、プロの写真家としてのキャリアをスタートさせました。しかし、彼の真価が発揮されたのは1965年2月、自費でベトナムに渡り取材を始めてからでした。この時期はベトナム戦争が全面戦争に発展した時期と重なり、沢田の写真は世界的な注目を集めることになります。
1965年9月6日、沢田はクイニョン北方のロクチュアン村で、銃弾を避けながら川を渡る母子の姿を捉えた『安全への逃避』(Flee to Safety)を撮影しました。この写真は世界中に配信され、翌年のピューリッツァー賞写真部門を受賞するなど、沢田の名を世界に知らしめる代表作となりました。
沢田の写真は、戦争の残酷さと人間の尊厳を同時に捉えた点で高く評価されました。彼は常に最前線で取材を行い、ジャングルでの過酷な環境下でもライカを片手に写真を撮り続けました。
しかし、沢田の輝かしいキャリアは1970年10月28日、カンボジアでの取材中に突如として終わりを迎えます。プノンペンの南約34キロ地点で何者かに銃撃され、34歳の若さで命を落としました。その死の詳細は今なお謎に包まれています。
65. 操上 和美(1936~)
操上和美(くりがみ・かずみ)は、1936年に北海道富良野で生まれました。24歳で上京し、1961年に東京綜合写真専門学校を卒業します。卒業時には学校からの推薦を受けてライトパブリシティを受験しますが、友人でもあった篠山紀信に面接で競り負け、家庭総合雑誌『住まいと暮らしの画報』のカメラマンに落ち着きます。その後、写真家の杉本直也が新規に設立したセントラルスタジオにアシスタントとして参加しました。操上は杉本に師事しながら、広告制作について学んでいきます。
1965年、操上はフリーランスの写真家として活動を開始します。操上が初めて手がけた映像作品は、ミツワ石鹸のCMでした。当時はまだモノクロ映像の時代であったため、白い泡は映像で綺麗に映らないとして不適切とされており、加えて女性の裸も当然ながらNGとされていました。しかし、操上はあえてこのテーマに挑みました。内容は、泡風呂から女性が立ち上がる瞬間にバスタオルで身体を包み込むというもので、裸が映ることはありませんでしたが、これが大変な話題を呼び、大ヒットを記録しました。
この成功を機に、「操上ならすべてを任せられる」と評価されるようになり、一気にプロダクション業務が増加。多忙な日々が始まりました。
操上はそれ以来60年近くにわたってファッション、雑誌、広告写真の第一線で活躍してきました。彼の作品は、著名人の印象的なポートレートから、サントリー「オールド」や木村拓哉出演のJRA、コメ兵のモデル絶叫シリーズなど、記憶に残るCMの数々まで多岐にわたります。70~80年代にはパルコの広告を数多く手掛けました。
操上の写真に対する姿勢は、常に新しい表現を追求し、被写体との真摯な対話を重視するものでした。彼は、「写真は相手を利用して実は自分を写している」という考えを持ち、被写体との対話を通じて自身の美意識を高めていきました。また、「道端に咲く花を美しいと思えないとダメだよ」というグラフィックデザイナー田中一光の言葉を心に留め、日常の中に美を見出す姿勢を大切にしてきました。
現在88歳を迎えた操上は、今なお現役の写真家として活躍し続けています。
操上和美『Alternates : 操上和美写真集』,誠文堂新光社,1983.
前記の82年発刊のものは雑誌『ブレーン』の別冊として出版されたもので種別が雑誌となっている。83年発刊のものは、それを書籍として装丁を改めて再出版したもの。2つは一部構成が異なる。
66. 江成 常夫(1936~)
江成常夫(えなり・つねお)は、1936年に神奈川県相模原市で生まれました。
1962年、江成は毎日新聞社に入社し、報道カメラマンとしてのキャリアをスタートさせます。航空機事故や学生運動、沖縄返還前夜の現場など、数々の歴史的瞬間を記録し、報道写真家としての基盤を築きました。1974年に同社を退社し、フリーランスの写真家として独立した後は、より個人的で深いテーマに取り組むようになります。報道写真の枠を超え、自身の視点や思想を写真を通じて表現することを志したゆえのことでした。
江成の作品の中心には、戦争とその影響を受けた人々の姿があります。彼は、アメリカに移住した日本人女性、いわゆる「戦争花嫁」をテーマにした写真集『花嫁のアメリカ』で注目を集めた。この作品では、戦後の混乱期に米兵と結婚し、異国の地で新たな生活を築いた女性たちの姿を記録しました。
当時、戦争花嫁は「従順な女性」や「異国で苦労する犠牲者」といった固定観念で語られることが多かったのですが、江成の作品は、彼女たちがいかに主体的に新しい人生を切り開いていったかを示しました。戦争が個人の人生に与えた影響を浮き彫りにしたこの作品は、1981年に木村伊兵衛賞を受賞するなど高い評価を得ています。
その後、江成は中国東北部、旧満洲を訪れ、日本の敗戦後に取り残された戦争孤児や、かつての日本統治時代の遺構を撮影した。『シャオハイの満洲』や『まぼろし国・満洲』といった写真集では、戦争が生んだ悲劇や、歴史の中で忘れ去られた人々の存在を記録している。これらの作品は、戦争の記憶を風化させないための重要な試みでした。
さらに、江成は広島と長崎の被爆地を訪れ、被爆者の遺品や遺構を撮影するプロジェクトにも取り組んだ。『被爆 ヒロシマ・ナガサキ いのちの証』では、原爆の恐怖とその影響を後世に伝えるため、10年以上にわたり被爆者の証言や遺品を記録した。彼は、原爆ドームや被爆者の遺品を通じて、戦争の悲惨さと核兵器の非人道性を訴え、核廃絶への思いを強く表現している。この作品群は、広島平和記念資料館や長崎原爆資料館の協力を得て制作され、国内外で高い評価を受けた。
彼は、戦争の記憶を記録することが、未来への教訓となると考え、写真を通じて「負の昭和」と向き合い続けました。彼の作品は、戦争の悲劇を直視することで、現代社会が抱える課題や人間の本質を問いかけるものでした。
岩佐将志『戦争がうみだす「異邦人としての他者」ー日本人「戦争花嫁」を事例としてー』,関西学院大学先端社会研究所紀要 1,2009.
嘉本伊都子『なぜ花嫁は海を渡るのか? : 〈モダニティ〉のスピンオフ』,京都女子大学大学院現代社会研究科紀要 15,2021.
67. 英 伸三(1936~)
千葉県千葉市で生まれた英伸三(はなぶさ・しんぞう)は小学校6年生のときに東京品川へと移住。中学卒業後は東京通信工業(現:ソニー株式会社)に勤務しながら、東京都立港工業高校の定時制コースに通い、高校卒業後は東京フォト・スクール(現:東京綜合写真専門学校)の夜間部で学びます。1960年に綜合写専を卒業後、ソニーを退社し、フリーランスの報道カメラマンとして活動を開始しました。1960年代から日本の高度経済成長期における社会の変化をテーマに、特に農村や農業問題に焦点を当てたドキュメンタリー写真を数多く発表しました。とりわけ、農村の過疎化や出稼ぎ労働、女性労働者の現状、子どもの教育問題など、経済成長の裏側に潜む社会問題を熱心に扱いました。
1965年には「農村電子工業」という作品で日本写真批評家協会新人賞を受賞し、注目を集めました。この作品では、農家の女性が抵抗器やコンデンサーの組み立てを内職として行う姿を捉え、農村の現金収入の実態を浮き彫りにしました。また、視覚障害者をテーマにした作品も評価され、社会的弱者に対する深い洞察力が高く評価されました。1971年には写真集『農村からの証言』で日本ジャーナリスト会議奨励賞を受賞し、農村の現実を記録する写真家としての地位を確立しました。
1980年代に入ると、英氏は活動の幅をさらに広げ、教育現場や都市部の町工場など、農村以外のテーマにも取り組むようになります。1983年には、写真絵本『みず』でボローニャ国際児童図書展グラフィック賞を受賞し、子ども向けの作品でも国際的な評価を得ました。
1990年代には、鹿児島県土地改良事業団体連合会の依頼を受け、鹿児島県内を取材し『鹿児島発農れんれん』を刊行しました。この作品では、地域の農業や土地改良の現場を記録し、地方の農村社会が抱える課題を再び取り上げました。また、1992年には日中国交正常化20周年を記念して中国の写真家との交流を企画し、上海や江南地方を取材しています。
68. 浅井 慎平(1937~)
浅井慎平(あさい・しんぺい)は1937年、愛知県瀬戸市に生まれました。幼少期を名古屋市中区大須で過ごし、愛知県立旭丘高等学校を経て早稲田大学政治経済学部に進学しますが、中退という道を選びます。その後、写真と出会うことがきっかけとなり、自身の創作活動を広げていきました。
1966年にビートルズが来日した際には、彼らの行動に密着して撮影を敢行し、写真集『ビートルズ東京 100時間のロマン』を発表しました。これが商業ベースでの大きなデビュー作となり、広告や雑誌の仕事へとつながっていきます。その後、麦焼酎「いいちこ」の広告写真や「VAN JACKET」「JANTZEN」などファッション関連の広告を手がけ、1981年には「PARCO」の広告一式で東京アートディレクターズクラブ最高賞を受賞しました。
さらに1977年6月には、音のみで構成されたアルバム『波〜サーフ・ブレイク・フロム・ジャマイカ』をCBSソニーから発売し、オリコンチャートで19位に入る記録を残しました。このアルバムは彼がジャマイカで録音した波の音をもとに制作されており、多数の枚数が売れ、風景音だけの作品としては異例のヒットとなりました。その影響を受けて別の環境音楽アルバムが企画されたともいわれています。
写真家としての活動にとどまらず、1982年にはタモリ主演の映画『キッドナップ・ブルース』において、脚本、監督、撮影、照明の四役を一人でこなします。また1984年から1994年にかけては、クイズ番組『象印クイズ ヒントでピント』(テレビ朝日)に出演し、男性軍キャプテンとして長年親しまれました。
1991年になると、千葉県南房総市千倉町に「海岸美術館」を設立し、自身の作品やガラス工芸なども展示しました。この美術館では、美術館の内部と自然環境が一体化したような快適で開放的な空間づくりを目指していて、訪れる人に四季折々の風を感じさせる演出がなされていました(現在は閉館)。
69. 立木 義浩(1937~)
立木義浩(たつき・よしひろ)は1937年に徳島県で生まれ、写真館を営む家系のもとで育ちました。ちなみに、立木の母親の立木香都子はNHK連続テレビ小説『なっちゃんの写真館』(1980)の主人公のモデルとなっています。
1958年に東京写真短期大学を卒業すると同時に、堀内誠一らが設立に関わった広告制作会社アドセンターに参加し、本格的にカメラマンとしての道を歩み始めます。当時の日本は雑誌創刊や広告需要が急増し、メディアの力が花開く時代を迎えていました。その流れに強く乗りながら、立木はファッション写真やドキュメンタリー要素を織りまぜた作品を量産し、注目を集めていきました。
1965年には写真雑誌『カメラ毎日』4月号において、56ページという異例のボリュームで「舌出し天使」を発表し、大きな話題を呼びます。明るい作風に隠された独特の視点と構成は新しさを感じさせ、とりわけモダンな感覚に敏感だった若い世代へ強い印象を残しました。この作品が評価されて、第9回日本写真批評家協会新人賞を受賞し、立木の名は一躍広く知られるようになります。 その後1969年にはアドセンターを退社し、フリーランスに転身します。芸能人や文化人を含む多くの著名人を撮影し、とりわけ女性ポートレートやヌード写真の分野で話題を集めました。一方で世界各国を訪れてはスナップ写真を日常的に撮り続け、「マイ・アメリカ」(1980年)や「東寺」(1998年)など、多数の写真集を次々と刊行していきます。
さらに2012年の「Tōkyōtō」や2016年の「動機なき写真 just because」、2018年に改めて出版された「舌出し天使」など、新旧の作品を再編する形でもコンスタントに発表し続けています。
立木が写真業界に残した大きな功績の一つは、広告や雑誌を通じて芸術性と商業性を融合させる道筋に貢献したことです。高度経済成長期のメディア拡大とともに、人々はより洗練されたビジュアルを求めるようになりました。そうした中、立木が広告制作会社の現場で身につけたクリエイティブの感覚は、ファッション写真や著名人のポートレートにおいて斬新な表現を可能にし、多くの新規読者層を開拓したといわれます。それは同時に、戦後日本の自由闊達な文化風土を象徴する社会的現象と呼応していました。 写真への姿勢としては「瞬間」に反応しながらも、どこか躍動感のあるドラマを添えるという点が特徴だとされています。立木自身は被写体が誰であれ、一歩踏み込むことで人間性をとらえつつ、そこにある生活の匂いや独自の世界観を写し取りたいという思いを持っているとたびたび述べています。撮影技術よりも、まずは被写体に寄り添う発想の重要性を説いており、この姿勢が若手写真家や広告制作者たちに対しても豊かな刺激を与えました。
70. 大倉 舜二(1937~2015)
大倉舜二(おおくら・しゅんじ)は1937年に東京で生まれ、日本画家の川合玉堂の孫にあたると伝えられています。獨協高等学校を卒業後、植物写真家の富成忠夫氏から写真の基礎を学び、続いて三木淳氏に三日間だけ師事したのち、佐藤明氏からファッション写真について指導を受けました。
1959年には22歳の若さで独立し、ファッションだけでなく料理や昆虫、生け花など幅広い被写体を手がけるようになりました。1960年代から1970年代は雑誌や広告の需要拡大にともないファッション写真などの分野が活況を呈しており、大倉もその流れの中で独自の感覚を発揮しました。ファッション撮影には明確な構成や演出が求められる一方で、昆虫や舞台といった分野では瞬間の表情や動きを逃さない観察力が要求されます。大倉はこれらの異なる要素をバランスよく習得し、対象をどのように提示するかを常に検討していたと考えられます。
彼が「できるだけ被写体そのものを引き立てる」という姿勢を保とうとしたことは、ファッション写真や静物/生物写真の分野でも共通して感じられるところです。
1971年、大倉は写真集『EMMA』を刊行し、同年に第3回講談社出版文化賞を受賞しました。本作は『カメラ毎日』の別冊「PRIVATE」シリーズ第二弾として位置づけられ、フィクションと現実を交錯させる独特の構成が話題を呼びました。当時、日本では高度経済成長や若者文化の台頭など社会が大きく変貌を遂げていましたが、大倉の作品には、モデル像や舞台裏の空気感をどこか虚実のはざまに据えながらも生身の存在を見つめる視点が表れているように見えます。
こうした表現には、写真の持つ記録性と演出性が同居するという、当時の新しい写真文化の潮流の一端も感じられます。
独立した当初からファッション分野だけにとどまらず、昆虫写真や生け花の写真、舞台俳優のポスター、さらにはドキュメンタリー的な要素を含む作品などを撮り続けてきたことは、刊行作品の多様さからもうかがえます。作品ごとに求められる技術と視点は異なりますが、大倉は対象を取り巻く空気感や動きを写真という二次元の中でどう表現するかを常に模索していたとみられます。その姿勢は見る者に対し、写真が単なるイメージの記録ではなく、状況やコンセプトを深く映し込む表現手段でもあることを示唆するものです。
2000年には写真集『Tokyo X』を講談社インターナショナルから刊行し、都会の断片を独自の視点で切り取る試みを重ねました。戦後からバブル崩壊後までに至る東京の変容はしばしば社会現象として語られますが、その過程を近距離から見つめることは、写真家にとっては時代と対峙する作業ともいえます。大倉の活動時期は、敗戦後のアメリカ文化の流入や高度経済成長、若者によるカウンターカルチャーの躍進など、多くの変化が折り重なる時代と重なります。彼の作品の中にはその「都市の空気」や変貌する社会の閃光を感じ取れるものがあり、それらはスポンサーという商業的要請と写真家自身の視点との間をどう折り合わせるかという問いかけをも含んでいたのではないかと思われます。
2015年に大倉は悪性リンパ腫のため77歳で亡くなりました。最後までさまざまなジャンルの撮影に携わり、広告、出版、芸術といった領域を横断する活動を続けたことは、戦後の日本で写真が大きく展開していく一過程を具現化した例として興味深いです。大倉自身は作品のために緻密な準備や構成をおこないながらも、被写体への真摯な視線を保とうとしたという評価があります。一方で、それを過度にドラマチックには語らず、あくまで写真家の仕事として淡々とこなし続けた姿勢は、華やかなファッションや芸能の表舞台を題材としながらも、写真行為そのものを常に落ち着いた位置においていたことをうかがわせます。
71. 横須賀 功光(1937~2003)
横須賀功光(よこすか・のりあき)は1937年に神奈川県横浜市で生まれ、1956年に日本大学芸術学部写真学科に入学しました。在学中から資生堂の社内報にて表紙写真を撮る機会を得て、卒業後の1960年にはフリーカメラマンとして資生堂宣伝部の広告キャンペーンに参加し、本格的に活動を始めました。1963年に『カメラ毎日』誌上で発表した作品「モード・イン」などが高く評価され、日本写真協会新人賞や日本写真批評家協会新人賞を受賞しました。同時期には資生堂広告でもアート・ディレクターズ・クラブ(ADC)賞特別賞を獲得するなど、多数の賞に立て続けに選ばれ、新世代の才能として注目されるようになりました。
1960年代後半、彼は広告写真とファッション写真の両方で先鋭的な造形表現を展開し、1966年には日本の広告界初といわれる本格的海外ロケをハワイで敢行しました。この撮影では前田美波里をモデルとした「太陽に愛されよう」というキャンペーンビジュアルを制作し、当時の広告文化を象徴する印象的なイメージの一つとして語られています。さらに1969年の個展で発表したヌード作品「亜」では、空間と身体を鋭く捉える作風が大きな話題となりました
1970年代に入るとパルコや角川書店などの広告キャンペーンで活躍を続けます。その一方で、1974年に東松照明や深瀬昌久、荒木経惟らとWORKSHOP写真学校を設立に携わり、新しい写真表現を模索する場にも積極的に参加していました。
1983年にはイタリアンヴォーグ、ドイツヴォーグ、フレンチヴォーグのフリーランススタッフカメラマンとなり、日本人としては初の活動例とされています。このように国内外で多彩に活躍し、1989年には個展「光銀事件」で伊奈信男賞を受賞しました。1993年の個展「エロスの部屋」ではプラチナ・プリントを用いた作品を披露し、古典技法を生かした写真制作の可能性を探求する姿勢を示しました。晩年は母校の日本大学芸術学部写真学科で教え、後進を育成しながら意欲的な作品発表も続けました。
横須賀の作品は、鋭い造形感覚と光を読み解く視点が特徴で、撮影の対象や空間との緊張感を強く意識した構成が多いといわれます。広告写真の分野では、企業イメージを単に宣伝するだけでなく、ビジュアルそのものが時代の象徴となるようなインパクトを追求しました。その背景には高度経済成長期以降、広告とメディアが人々の価値観に与える影響が急速に広がった社会現象があり、若い世代の感覚をとらえた先鋭的なビジュアル表現が求められる風潮があったと考えられます。横須賀の写真は、まさにその流れを先取りする形で、多様な表現が容認され始めた当時の広告業界を活性化させた一因になったといわれています。
72. 内藤 正敏(1938~)
内藤正敏(ないとう・まさとし)は早稲田大学理工学部で応用化学を専攻した後、化学製品会社に短期間勤務しましたが、高校時代から続けていた写真への情熱が転機となり、1962年にフリーの写真家として活動を開始しました。
内藤は初期に「SF写真」と呼ばれる独自の作風を確立しました。これは化学反応を接写し、生命の起源や宇宙の生成と消滅をテーマにしたもので、早川書房の『ハヤカワ・SF・シリーズ』の表紙を飾るなど注目を集めました。しかし、25歳の時に山形県湯殿山麓で即身仏に出会った経験が彼の創作活動に大きな影響を与え、修験道への興味を深めることとなりました。この体験を経て、「婆バクハツ!」シリーズをはじめとする東北地方の民間信仰を主題とした写真作品を多数制作しました。
内藤は写真家であると同時に民俗学者としても活躍し、東北芸術工科大学の教授を務めるなど、学術的な研究にも力を注ぎました。彼の写真作品は、見えない世界を視覚化する試みとして評価されており、民俗学の視点を取り入れることで、自然と都市、科学と宗教といった異質のテーマを多角的に表現しました。また、彼は「モノの本質を幻視できる呪具」としての写真と「もう一つのカメラ」としての民俗学を融合させることで、独自の世界観を築き上げました。
73. 中平 卓馬(1938~2015)
中平卓馬(なかひら・たくま)は、日本の戦後写真史において重要な足跡を残した写真家であり批評家です。彼の活動は、写真表現の革新とその思想的背景を深く掘り下げるもので、同時代の写真家や後世の表現者たちに大きな影響を与えました。
中平は東京都に生まれ、東京外国語大学スペイン語学科を卒業しました。卒業後は雑誌『現代の眼』の編集者としてキャリアをスタートさせます。この時期に写真家・東松照明との出会いを通じて写真に興味を持ち、1965年頃から独学で写真を学び始めました。
1968年、中平は多木浩二、高梨豊、岡田隆彦、森山大道らとともに写真同人誌『Provoke(プロヴォーク)』を創刊します。この雑誌は「思想のための挑発的資料」という副題が示すように、それまでの写真表現を根本から見直し、新たな思想を提起することを目的としていました。中平らは、「アレ・ブレ・ボケ」と呼ばれる荒々しい粒子感や焦点の定まらない構図など、従来の技術的洗練とは一線を画す実験的な手法を採用しました。当時、日本国内外で高まっていた学生運動や社会改革への関心が、この挑発的な表現活動にも影響を与えており、『Provoke』は単なる芸術運動ではなく、社会的・政治的文脈とも密接につながっていました。
1970年には写真集『来たるべき言葉のために』を出版し、その中で都市風景や日常の断片を捉えたスナップショットが注目されました。しかし、中平はその後、自らの作風に対して批判的になり、1973年には評論集『なぜ、植物図鑑か』を発表します。
中平は、この著作で従来の写真表現、とりわけ自身が関与した『Provoke(プロヴォーク)』時代の「アレ・ブレ・ボケ」スタイルを否定しました。『Provoke』で展開された荒々しい粒子感や不安定な構図は、社会や人間の内面を挑発的に表現するものでしたが、中平はこれを「情緒的で詩的な世界観の押し付け」として批判します。彼は、このような表現が写真家自身の主観や感情を過剰に投影し、「世界そのもの」を見つめることを妨げていると考えました。「写真は記録である」がしかし、それは撮影者の想念の記録でもあるという、東松照明らの考えに真っ向対峙するような主張を展開しました。
ここでの核心的なテーマは、「事物が事物であること」を明確に捉えるという姿勢です。中平は、写真が「世界はこうあるべきだ」という人間中心的な視点やイメージによって歪められるべきではないと主張しました。代わりに、彼は写真を通じて「あるがままの世界」を記録することを目指しました。この考え方を象徴するのが「植物図鑑」という比喩です。
植物図鑑とは、対象を客観的かつ正確に記録するものであり、そこには感情や主観的解釈が入り込む余地がありません。中平はこの図鑑的視点を写真にも適用しようとしました。
写真が従来の意味での「芸術」であること、つまり、作家の想念の発露となることを否定し、あくまで記録のための道具であることを強調したのです。
「図鑑は直接的に当の対象を明快に指示することをその最大の機能とする。あらゆる陰影、またそこに忍び込む情緒を斥けて成り立つのが図鑑である。“悲しそうな”猫の図鑑というものは存在しない。もし図鑑に少しでもあいまいなる部分があるとすれば、それは図鑑の機能を果たしていない。あらゆるものの羅列、並置が図鑑の性格である。」
中平が上記に述べるように、例えば、猫をただ猫として撮影すること(「事物そのもの」を撮影すること)で、写真が純粋な記録として成立すると考えました。
中平はこの新たな方向性を通じて、人間中心主義や福原信三以来の芸術写真の概念にも挑戦しました。彼は、芸術家が特権的な存在として世界を解釈し、それを作品として外化する時代は終わったと述べています。そして、人間が世界に対して敗北を認め、その上で「此岸(現実)」と「彼岸(理想)」の分離を受け入れることこそ、新しい表現の出発点になると考えました。
撮影を通して生じる、「私」による世界への加害を怖れ、中平は自身の強烈な視線を写真に投影することを拒絶しました。その結果、彼は自己を「空っぽ」にするという方法を選び、カメラの受動性を極限まで追求する道へと進んでいきます。
しかし、その矢先、中平は1977年に急性アルコール中毒による昏倒で記憶喪失という大きな試練に直面します。この出来事は彼の人生と創作活動に劇的な転換点をもたらしましたが、その後も沖縄や横浜などで撮影活動を再開し、記憶障害と向き合いながら新たな作品群を生み出していきました。
2003年には横浜美術館で大規模な回顧展「原点復帰-横浜」が開催され、それまでのキャリア全体が再評価される契機となりました。さらに2011年には大阪で新作展「キリカエ」を開催するなど、晩年まで精力的に活動しました。彼の作品は国内外で展示され続けており、その思想と表現は今なお議論されています。
中平卓馬が日本写真界にもたらした最大の貢献は、その思想性と批評性です。彼は写真が単なる記録媒体ではなく、「現実の断片」として新たな思想や言葉を呼び起こす力を持つと考えました。この視点は『Provoke』時代から一貫しており、写真と現実、言葉との関係性について深い洞察を示しています。また、「アレ・ブレ・ボケ」の実験的手法やその後の客観主義への転向は、多くの同時代作家や後進に影響を与えました。
中平が『植物図鑑』で実施した「雑駁な被写体を徹底して提示する」という実験は、作家の主観やドラマを強調しがちな写真表現への批判的視点を提供しました。写真行為を「対象の多様性を捉えるための継続的な探求」として捉える姿勢は、現代の写真家による日常への再注目や、膨大な記録を積み上げるアーカイブ的な試み(例:SNSを通じた日常的写真の集積など)にも影響を与えています。
田尻歩『「存在の闘い」としての写真理論 : 中平卓馬の写真理論再読』,一橋大学大学院言語社会研究科,2019.
中平卓馬をシュルレアリストとして再定置しようとする論説です。個人的にはこのように中平を捉えるのが最も簡潔におもえます。
74. 森山 大道(1938~)
森山大道(もりやま・だいどう)は1938年、大阪府池田市に生まれました。幼少期は父の転勤に伴い各地を転々とし、孤独な少年時代を過ごしました。この経験が後のストリートスナップへの情熱に繋がったと言われています。高校時代にはデザインを学び、卒業後はフリーのグラフィックデザイナーとして活動を開始しましたが、写真家との出会いをきっかけに写真の世界へ進むことを決意します。
1960年、岩宮武二のスタジオでアシスタントとなり、写真家としての第一歩を踏み出しました。この時期、ウィリアム・クラインの写真集『ニューヨーク』に衝撃を受け、都市の混沌としたエネルギーを写真で表現することに強い関心を抱きます。
1961年に上京すると、解散直後の写真家集団「VIVO」のメンバーであった細江英公に師事し、暗室作業や撮影技術を学びました。1964年には独立し、フリーランスの写真家として活動を開始します。当初は仕事が少なく苦労しましたが、神奈川県横須賀で撮影した作品が『カメラ毎日』誌に掲載され注目を集めました。この頃から彼の作風は「アレ・ブレ・ボケ」と呼ばれる特徴的なものとなり、フィルム粒子の粗さやピントの甘さ、手ぶれなどを意図的に活用することで、既存の美的価値観に挑戦する姿勢を示しました。
1968年には写真集『にっぽん劇場写真帖』を発表し、一躍注目を浴びます。同年、中平卓馬らと共に写真同人誌『Provoke』に参加し、「言葉よりも先に視覚的な衝撃」を追求する前衛的な活動を展開しました。この動きは当時の日本社会の政治的・文化的混乱とも共鳴し、多くの若者やアーティストたちに影響を与えました。また、この時期の日米安保条約改定反対運動や高度経済成長による都市化といった社会現象も、森山の作品テーマと深く結びついています。
1970年代には『狩人』や『写真よさようなら』など実験的な作品集を発表し、その中でアンディ・ウォーホルから影響を受けた大胆なトリミングや抽象的な構図が見られます。しかし、この時期にはスランプにも陥り、一時的に制作活動から離れることもありました。それでも1980年代になると再び創作意欲を取り戻し、『光と影』という連載や同名の写真集で新たな表現領域を切り開きました。この作品は「写真とは何か」という問いへの答えとして位置づけられ、多くの批評家から高い評価を受けました。
森山はその後も国内外で活躍し続け、日本のみならず世界中で個展を開催しました。2012年にはニューヨーク国際写真センター(ICP)からインフィニティ賞生涯功績部門賞を受賞し、日本人として初めてこの栄誉に輝きました。また、2019年には「写真界のノーベル賞」とも呼ばれるハッセルブラッド賞も受賞しています。彼の作品は単なる記録写真ではなく、「光と影」のコントラストや都市風景の断片から人間存在そのものへの問いかけを感じさせるものです。
森山が写真業界にもたらした最大の功績は、既存の美学や技術的制約への挑戦です。「アレ・ブレ・ボケ」というスタイルは当初批判も受けましたが、その後、多くのフォロワーや新世代の写真家たちに影響を与えました。また、彼自身が「ストリート・カメラマン」と称するように、街路という日常空間から普遍的なテーマや感情を引き出す手法は、新しい視覚言語として確立されました。
75.井上 青龍(1931~1988)
井上青龍(いのうえ・せいりゅう)は、高知県土佐市に生まれ、1950年代から関西を中心に活動を開始しました。井上は、巨匠岩宮武二に師事し、写真表現の技術と哲学を学びました。その後、大阪の釜ヶ崎という地域を舞台に、社会的弱者や労働者の日常を記録するドキュメンタリー写真で注目を集めました。
釜ヶ崎は日本有数のドヤ街として知られ、戦後の高度経済成長期においても貧困や労働問題が深刻な地域でした。井上はこの地に住み込み、住民たちとの信頼関係を築きながら撮影を進めました。彼が釜ヶ崎をテーマとした最初の個展「人間百景—釜ヶ崎」(1960年)は、現地の過酷な日常と人間ドラマを描写し、多くの反響を呼びました。この作品で井上は、第5回日本写真批評家協会新人賞とカメラ芸術新人賞を受賞し、一躍脚光を浴びます。
井上の写真には、生半可なヒューマニズムではなく、被写体への深い共感と鋭い観察眼が込められていました。彼はシャッターを切ること自体が「きつい行為」であると語り、とりわけ釜ヶ崎のような社会的弱者が集う場所では、その行為が持つ倫理的な重みを強く意識していました。このため、撮影当初の1年間はカメラを持ちながらもシャッターを切らず、住民たちとの距離感や信頼関係の構築に努めたとされています。
しかし、釜ヶ崎での活動は井上にとって精神的にも大きな負担となりました。「結局、釜ヶ崎を変えることはできなかった」と語った彼は、その後テーマ選びに苦悩し、一時的に創作活動から遠ざかります。それでも彼は写真家として生き続け、旧式のカメラを手に広告撮影や競馬場通いなど無頼派的な生活スタイルを貫きました。
1980年代になると、井上は新たなテーマとして南島・奄美大島や徳之島など日本の離島文化に目を向けました。この時期には「道祖神」など日本文化や信仰に根ざした作品も手掛けています。また、大阪芸術大学で教鞭を執り、多くの学生たちに影響を与えました。井上のゼミ生たちは後にドキュメンタリー写真やジャーナリズムの分野で活躍し、その精神を受け継いでいます。
井上が活動した時代背景には、高度経済成長期特有の都市化や貧困問題がありました。釜ヶ崎では暴動が繰り返されるなど社会的緊張が高まっており、その記録は単なる芸術作品以上に重要な歴史資料ともなっています。また、「北帰行」と題した在日朝鮮人の祖国帰還運動なども撮影しており、日本社会が抱える民族問題にも鋭い視線を向けています。
1988年、井上青龍は鹿児島県徳之島で撮影中に水難事故で亡くなりました。
晩年、井上は大阪芸大の教員をしていました。机に一升瓶をどんと置き、講義が済むと学生を引き連れ、釜ケ崎のホルモン屋へと向かう。無頼の写真家でした。
76. 嬉野 京子(1940~)
嬉野京子(うれしの・きょうこ)は1940年に東京都で生まれ、1960年代からフリーの報道写真家として活動を始めました。彼女は日本リアリズム写真集団の創設メンバーの一人であり、戦後の日本社会や沖縄の現実を鋭く捉えた作品で知られています。
嬉野が写真家として注目されるきっかけとなったのは、1960年代の沖縄取材です。当時、沖縄はアメリカ軍の統治下にあり、住民たちは土地の強制収用や軍事支配に苦しんでいました。嬉野は本土で行われた安保闘争を通じて沖縄問題に関心を抱き、1965年と1967年に現地を訪れます。特に1965年には、祖国復帰運動の行進中に米軍トラックが6歳の少女を轢き殺すという悲劇的な事件に遭遇しました。この場面を撮影した彼女の写真は、米軍支配下での日常的な暴力と不条理を象徴するものとして広く知られるようになりました。
この撮影には命の危険が伴いました。米軍統治下では報道活動が厳しく制限されており、特に「写真家」という肩書きでは沖縄への渡航許可が下りない状況でした。それでも彼女は現地へ赴き、行進団の協力を得て撮影を敢行します。この際、一人の行進者が米兵の注意を逸らすために話しかけるなど、周囲の協力も重要な役割を果たしました。この写真が本土で発表されると、日本社会に大きな衝撃を与え、沖縄返還運動への関心を高める契機となりました。
嬉野京子は報道写真家として、日本リアリズム写真集団に所属し、戦後の社会問題や沖縄問題をテーマにしたいわば「説明的報道写真」を手がけました。彼女の作品は、社会的不条理を告発し、視覚的記録を通じて社会変革を促すことを目指していたものですが、ときに、その活動が「政治性に偏りすぎている」といった批判にも直面しました。
例えば、1969年に『アサヒカメラ』で行われた座談会「コンポラかリアリズムか」では、座談会に参加した中平卓馬は、日本リアリズム写真集団が「安易な政治性」に支配されていると批判し、同集団の写真について「中小企業の倒産か、ハチマキして手を挙げている写真しかない」と揶揄しました。これに対し、嬉野は被写体の多様性を根拠に反論し、自身の作品が家族や教育問題、民族芸能など多面的なテーマを扱っていることを強調しました。この議論は平行線をたどり、新旧のリアリズム表現における両者の立場の違いが浮き彫りとなった事例と見ることもできます。
77. 広田 尚敬(1935~)
広田尚敬(ひろた・なおたか)は、日本の鉄道写真界を代表する写真家であり、彼の鉄道写真のスタイルと視点が後の撮り鉄たちの与えた影響は計り知れません(もちろん、いい影響です)。
彼の人生と業績は、鉄道写真というジャンルにおける新たな表現方法の確立と、社会的な影響をもたらしました。
広田は東京で生まれ、幼少期から鉄道に強い興味を抱いていました。彼の鉄道への情熱は、模型作りから始まりました。駅で列車の寸法を測り、それを基に精巧な模型を制作していたことが、後に写真撮影へとつながります。初めてカメラを手にしたのは中学3年生の修学旅行時で、関西方面の電車を撮影したことがきっかけでした。この経験が彼を写真の世界に引き込み、高校時代には鉄道友の会に所属し、本格的に鉄道写真を撮り始めました。
中央大学経済学部卒業後、兄との約束で一度商社に就職しますが、1年後にはフリーランスの写真家として独立します。その後、1968年に初個展「蒸気機関車たち」を開催し、その独自の表現手法が高く評価されました。この展示では、日本の豊かな自然と蒸気機関車を組み合わせた大胆な構図やデフォルメされたイメージが注目され、「広田調」と称されるスタイルを確立しました。
広田の作品は、単なる編成写真にとどまらず、革新的な技術や自作機材を用いた表現が特徴です。特に有名なのが「動止フォトグラフ」と呼ばれる撮影手法です。この技法では、自作のスリットカメラを使い、走行中の列車側面を真横から流し撮りすることで、列車が静止しているかのように見せつつ背景だけを流動的に描写します。この手法は鉄道写真における新しい視覚的体験を提供し、多くのファンや後進の写真家たちに影響を与えました。
また、広田は子供向け写真絵本にも力を入れました。当時、絵本市場ではリアリティが欠けていると感じた彼は、本物志向の子供たちに向けて鉄道写真絵本を制作しました。この試みは大成功し、多くの子供たちに愛される作品となりました。
1960~70年代、日本各地で蒸気機関車が引退する際、多くの鉄道ファンが「最後の雄姿」を記録しようと集まりました。この時期に「三脚林」と呼ばれるほど多くの人々が名所に集結し、現在の撮り鉄文化の基盤が形成されました。
広田は、そういった撮り鉄たちの”先生”として、1970年代から1980年代初頭にかけて、日本で最も著名な鉄道写真家として活躍しました。その活動範囲は日本国内だけでなく、アメリカ合衆国など海外にも及び、「Trains」誌などでも作品が掲載されました。また、1988年には日本鉄道写真家協会を設立し、その初代会長として鉄道写真界全体の発展にも寄与しました。
78. 二村 保(1941~2011)
二村保(ふたむら たもつ)は、モータースポーツ写真の第一人者として知られ、特にラリーやカーレースを題材にした作品で国際的な評価を得た写真家です。現代にも通じるモータースポーツの写真表現の基盤を作り上げた一人とも言えます。
二村は東京写真短期大学(現:東京工芸大学)を卒業後、日本テレビで報道カメラマンとして働きました。その後、1967年にフリーランスとなり、オーストラリアで行われた「サザンクロス・ラリー」を取材したことが転機となりました。翌1968年にはメキシコへ渡り、メキシコオリンピックの公式フォトグラファーを務めています。
二村は特に1960年代後半から1970年代にかけて、世界中で開催されるモータースポーツイベントを精力的に取材しました。1968年から1970年にかけて撮影したCan-Amシリーズや日本グランプリなどの写真を収めた『レーシング』という写真集を1970年に発表し、その後も『THE RALLY』(1979年)や『RALLYE』(1985年)、『FINISH』(1993年)など数々の写真集を出版しました。これらの作品は、モータースポーツの躍動感や緊張感を巧みに捉えたものであり、彼の卓越した技術と芸術的感性が高く評価されています。
日本でモータースポーツが流行しだしたのは1960年代のことです。1962年にはホンダが三重県に鈴鹿サーキットを建設し、これを皮切りに富士スピードウェイ(1966)などのサーキットが続々と誕生しました。特に鈴鹿サーキットでは1963年に第1回日本グランプリ自動車レースが開催され、20万人以上の観客を集めたことで、一般大衆へのモータースポーツ認知度向上に大きく寄与しました。また、この時期は国内メーカーによる積極的な参入も見られました。トヨタや日産などは、自社の技術力を示す場としてレース活動を活用し、特に日本グランプリでは激しい競争を繰り広げました。このような競争は一般消費者にも注目され、自動車販売促進にもつながりました。二村はこういった当時のブームと自動車業界という強力なスポンサーのもと、拡大していくレース業界を記録し続けました。
また二村は、単なる静止画撮影に留まらず、自ら録音したラリーカーのエンジン音や走行音を収録したLPレコードもリリースするなど、多角的な表現活動を展開しました。このような取り組みは、音と視覚を組み合わせることでモータースポーツの臨場感をより深く伝える試みでした。
1972年には活動拠点をヨーロッパへ移し、本場であるモータースポーツ文化と密接に関わりながら撮影活動を続けました。特にラリー・モンテカルロや世界各地で開催されるラリーイベントを取材し、その成果として発表された『THE RALLY』では、8年間にわたり15カ国以上で撮影された膨大な量の写真が収録されています。このような長期的かつ国際的な視点からの作品制作は、当時としては非常に先進的でした。
さらに二村は、日本レース写真家協会(JRPA)の初代会長も務め、日本国内でモータースポーツ写真家としての地位向上にも寄与しました。彼の活動は、単なる個人としての成功だけでなく、日本全体の写真文化やモータースポーツ文化にも大きな影響を与えています。
二村保が残した作品群は、美術館やギャラリーでも展示されることがあり、レース写真を芸術として認知させたという点で大きな功績があります。
79. 土田 ヒロミ(1939~)
土田ヒロミ(つちだ・ひろみ)は1940年、福井県に生まれ。大学を出た後、ポーラ化粧品本舗(現:ポーラ)の開発部に勤務しながら東京綜合写真専門学校に通い、1971年に「自閉空間」で第8回太陽賞を受賞したことで注目を集めると、退職してフリーの者しなになります。この作品は、当時の日本社会の変化や都市化の進展に伴う孤独や疎外感を鋭く捉えたものであり、彼の写真家としてのキャリアの重要な出発点となりました。
土田の作品は、日本の土俗的な文化や高度経済成長期における社会変化、さらには広島や福島といった歴史的・社会的なテーマを扱うことで知られています。特に彼の代表作である『俗神』では、日本各地の民間信仰や祭りなどを通じて、伝統文化が持つ象徴性とそれが近代化によって変容する様子を描き出しました。この作品は、単なる記録写真にとどまらず、被写体との関係性や視覚的な構成力を重視した芸術的なアプローチが特徴です。
また、彼の写真集『ヒロシマ』では、広島という都市が持つ戦争の記憶とその後の復興過程をテーマにしています。この作品は、戦後日本が直面した課題やトラウマを視覚的に表現する試みであり、多くの批評家から高い評価を受けました。同様に、『フクシマ』では東日本大震災後の福島を題材にし、自然災害と原発事故が地域社会にもたらした影響を記録しています。これらの作品群は、日本社会が抱える「負の昭和」や「負の平成」とも言える側面を浮き彫りにしつつ、その中で生きる人々の日常や風景に焦点を当てています。
土田ヒロミの写真表現には、実験的で独自の視点が反映されています。例えば、『砂を数える』では、一見すると無機質で抽象的な風景写真が並びますが、それらは人間活動と自然環境との相互作用を考察する試みとして捉えることができます。このようなアプローチは、アメリカ発祥の「ニュー・トポグラフィックス」と呼ばれる写真運動との関連性も指摘されています。
80. 栗林 慧(1939~)
栗林慧(くりばやし・さとし)は、1939年に中国の瀋陽で生まれ、戦後は長崎県北松浦郡田平町(現:平戸市)で育ちました。彼は昆虫や生物の生態を専門とする写真家であり、独自の技術と視点で自然界の瞬間を切り取る作品を数多く発表してきました。
栗林の写真家としてのキャリアは異色の経歴から始まりました。中学卒業後、酒店勤務や陸上自衛隊員、保険会社社員などを経験した後、1969年にフリーランスの生物生態写真家として独立しました。彼は東京綜合写真専門学校で写真の基礎を学びましたが中退し、その後は独学で撮影技術を磨きました。この過程で、昆虫撮影に特化した機材を自作するなど、技術革新への情熱を見せています。
栗林が注目を集めた理由の一つは、「虫の目レンズ」と呼ばれる独自開発のカメラシステムです。この技術は極端に深い被写界深度を実現し、昆虫など小さな生物を背景まで鮮明に捉えることが可能です。また、1/50000秒という超高速シャッター速度を備えた撮影装置も開発し、花粉が飛び散る瞬間や昆虫の飛翔を捉えることに成功しました。これらの技術は単なるスチル写真だけでなく動画撮影にも応用され、NHKなどの番組制作にも活用されています。
1978年には日本写真協会新人賞を受賞し、その後も伊奈信男賞や日本写真協会年度賞など数々の栄誉に輝きました。特に2006年には科学写真分野で権威ある「レナート・ニルソン賞」を日本人として初めて受賞し、その功績が国際的にも認められています。
栗林の作品には、生物や自然への深い洞察と愛情が込められています。彼は昆虫たちの多様性と美しさに魅了され、それらを記録することに生涯を捧げてきました。その結果、生物写真というジャンルにおいて新たな表現方法を切り開き、多くの人々に自然界への興味と感動を与えています。また彼の活動は、科学教育や環境保護意識の向上にも寄与しており、社会的な意義も大きいと言えます。
彼が設立した「栗林自然科学写真研究所」は、次世代への教育活動にも力を入れており、特に子どもたちに対して自然への関心を育む取り組みを行っています。また、彼が住む長崎県平戸市では1992年に「たびら昆虫自然園」がオープンし、この地域で撮影された昆虫写真が展示されています。この施設は地域活性化にも貢献しており、栗林氏の活動が地方文化振興にも寄与しています。
81. 沢渡 朔(1940~)
沢渡朔(さわたり・はじめ、1940年1月1日生まれ)は、女性ポートレートやファッション写真の分野で独自の地位を築きました。
沢渡は東京で生まれ、中学時代に中古のリコーフレックスを手にしたことをきっかけに写真に興味を持ちました。高校では写真部に所属し、『サンケイカメラ』誌の月例コンテストで複数回入賞するなど、早くからその才能を発揮しました。その後、日本大学芸術学部写真学科に進学し、在学中から『カメラ毎日』や『女性自身』などの雑誌で作品を発表するようになります。この時期には、詩人の白石かずことともに米軍横田基地を訪れ、黒人女性や子供たちを撮影するなど、社会的・文化的背景を反映した作品も制作しました。
大学卒業後、日本デザインセンターに入社し、高梨豊のアシスタントとして広告写真の技術を学びましたが、その後フリーランスとして独立します。フリー転向後はファッション写真に興味を持ち始め、立木義浩の紹介で雑誌や広告の仕事を手掛けるようになりました。この頃から、彼の作品にはジャズやヌーヴェルヴァーグ映画など、学生時代に傾倒したカルチャーの影響が色濃く表れるようになります。
1970年代初頭には、編集者の桑原茂夫や谷川俊太郎らと共同制作した『少女アリス』(1973年)という写真集が大きな注目を集めました。この作品は、不思議の国のアリスをモチーフとし、イギリス人少女モデル・サマンサを被写体に幻想的な世界観を描き出しています。また同時期には、イタリア人モデル・ナディアとのコラボレーションによる連作「ナディア」も高い評価を受けました。これらの作品は、女性や少女というテーマに対する新しい視点と表現方法を提示し、日本写真協会年度賞や講談社出版文化賞写真賞など、多くの賞を受賞しました。
なお、「少女アリス」には当時8歳だったモデルのヌード写真が含まれており、これが児童ポルノに該当するのか、またこれを再販すべきなのか(2014年再販)は度々議論にあがっています。
1970年代後半以降、沢渡は一つのテーマが「完結してしまった」と感じたと言われており、その後40代に入るとスランプに陥ります。それでも50代になると再び創作意欲が湧き上がり、多くの女性グラビアや写真集制作に取り組むようになります。彼は常に被写体との適度な距離感を保ちながら、その自然な魅力と艶やかさを引き出すことに長けていました。
また、「少女」や「女性」というテーマに対する独自の視点は、多くのフォトグラファーやアーティストにも影響を与えています。特に1970年代には篠山紀信や立木義浩らとともに「カメラマンブーム」を牽引し、日本国内外で注目される存在となりました。
82. 須田 一政(1940~2019)
須田一政(すだ・いっせい)の作品は、日常的な風景や何気ない瞬間を捉えながらも、その中に潜む異質さや緊張感を映し出す独特のスタイルで知られています。
須田は東京神田で生まれ、1962年に東京綜合写真専門学校を卒業しました。その後、1967年から1970年まで寺山修司が主宰する演劇実験室「天井桟敷」で専属カメラマンとして活動し、この経験が彼の創作活動に大きな影響を与えました。この時期に培われた舞台的な視点や非日常への感受性は、後の作品にも色濃く反映されています。
1971年にフリーランスとなった須田は、1976年に発表した写真集『風姿花伝』で日本写真協会新人賞を受賞しました。この作品は、能楽の大成者である世阿弥の芸論からタイトルを借りたもので、関東から東北地方にかけて撮影された祭礼や人々の姿が中心となっています。しかし、須田が注目したのは祭りそのものではなく、それが生み出す日常と非日常の「あわい」に存在する独特な雰囲気でした。彼の写真には、人間だけでなく動物や無機物までもがアニミズム的な生命感を帯びて写されており、その表現力は高く評価されました。
須田の代表的なスタイルは、6×6判カメラによる正方形フォーマットを用いた作品群です。この形式は被写体との距離感や構図の自由度を高め、須田独自の浮遊感や即物的な視点を可能にしました。彼が捉えた風景や物体には、一見平凡でありながらも不穏さや緊張感が漂い、それが「須田調」と呼ばれる独特のスタイルとして確立されました。このスタイルは多くの写真家に影響を与え、一時期は正方形フォーマット自体が須田作品と結びつけられるほどでした。
また、須田はテーマを決めずに旅先や日常生活で出会った風景を撮影することが多く、その自由奔放なアプローチも特徴的です。例えば、『物草拾遺』では無名の風景や物体が題材となり、それらが持つ「目に見えないもの」を記録しようとする試みが見られます。こうした作品には、被写体そのものよりも、それに触れた際の須田自身の感情や視線が色濃く反映されています。
1997年には写真集『人間の記憶』で第16回土門拳賞を受賞し、その後も国内外で高い評価を得続けました。晩年には人工透析を受けながらも創作活動を続け、2019年に78歳で逝去しました。その生涯にわたる活動は、日本写真界のみならず国際的にも大きな影響を与えています。
須田一政の写真には、「何気ないもの」を通じて深い人間性や社会性を浮かび上がらせる力があります。それは単なる記録ではなく、一種の詩的な表現とも言えるでしょう。
83. 本橋 成一(1940~)
本橋成一(もとはし・せいいち)は1940年に東京・東中野で生まれ、1960年代から写真家としての活動を始めました。若い頃に写真専門学校を卒業する際、卒業制作のテーマとして炭鉱を選んだことをきっかけに、作家・上野英信と出会い、筑豊の炭鉱住宅やそこで暮らす人々を撮影しました。この作品群は1968年に「炭鉱〈ヤマ〉」としてまとめられ、第5回太陽賞を受賞しています。当時、土門拳による「筑豊のこどもたち」の影響で、多くの写真家が炭鉱地帯を撮影していましたが、本橋は地域に頻繁に足を運び、被写体と同じ地平に立とうとする姿勢を貫きました。この意識は、その後の作品においても一貫しており、人々と生活を共にしながら、現場で時間をかけて写真を撮るという流儀を築き上げたといえます。
1960年代後半から本橋は、大衆芸能やサーカス、魚河岸や上野駅など、多様な場所で働く人々の姿を継続的に撮影しました。そこには、日常を営む人々の生命力や、世間の中心からはあまり映されない労働の実態がありました。本橋は決して対象を過度に美化することなく、その生の豊かさを撮影し続けました。
1980年代には、食肉処理場の作業工程に踏み込み、血を浴びながら黙々と働く人々や、家畜の命と向き合う姿を撮影しています。大量生産や消費を支える社会の底流にある現場の姿を正面から捉えたという点で、社会ドキュメンタリーとしての意味も見いだせるといわれています。
1980年代後半になると、本橋はチェルノブイリ原子力発電所事故の取材に関心をもち、その被災地で暮らし続ける人々を長期にわたって撮影し始めました。当初は写真集としてまとめられましたが、1998年に『ナージャの村』というタイトルで映画監督としてのキャリアをスタートさせ、以降も『アレクセイと泉』(2002年)や『ナミイと唄えば』(2006年)、『バオバブの記憶』(2009年)など、原発事故あるいは環境問題下での人々の暮らしに着目したドキュメンタリー映画を続けて発表します。本橋はこうした活動を通じ、3.11以降の日本における原子力や環境への見方にも示唆を与えました。撮影後に被写体との対話を重ね、その共同体との関係性を深めるという独特の手法は、写真や映画が持つドキュメンタリーとしての特質を社会に問いかける姿勢とも重なります。
チェルノブイリ原子力発電所事故後の被災地の描き方をめぐって、1998年の『技術と人間』誌で本橋と広河隆一の論争ともいえる意見交換が行われました。
当時、広河はフォトジャーナリストとして1989年頃からチェルノブイリを取材し、被災村の実態を悲惨かつ荒涼とした光景として伝えていました。一方、本橋の作品は、事故後も故郷に留まって暮らす人々の姿や日常の営みに焦点を当てて、彼らの生命力や豊かな表情を写真や映像作品(『ナージャの村』など)で描いていました。 広河は本橋の作品が「高濃度汚染の危険性を軽視しすぎではないか」と疑問を呈し、特に事故の悲惨さや汚染による被害が深刻化する実態を覆い隠してしまうおそれがあると指摘しました。広河は「放射線による影響を過小評価することは、次の犠牲者を生む危険性につながる」と強調しています。一方で本橋は、「この事故は人類全体による責任であり、個人に帰せられるものではない」という主張を述べ、自らは村に残る人々の生き方を描くことによって、ありのままの現実を提示して問題提起しているのだと反論しました。 議論のもう一つの焦点は、本橋の作品が「村を離れた人たちの視点を十分に取り上げていないのではないか」という広河の批判でした。村に残る道を選んだ人と、やむを得ず村から離れることを選んだ人との間に生まれる分断や価値観の相違に光が当てられていないのでは、という指摘です。これに対して本橋は、撮影者として被写体の暮らしを丹念に追うというスタンスを続け、それを通して「人が生きる現実」を色濃く描こうとしたと述べています。
放射能災害によって住民が置かれた過酷な状況をどう捉え、社会に伝えるかという点で、本橋と広河はそれぞれ異なる立場を主張しました。両者の論争は、報道や記録映像がおのずと内包する「どこに焦点を当てるのか」「どの部分を切り取るのか」という写真家のスタンスの違いを浮き彫りにしています。
批評の中には、本橋の撮影スタイルを「鋭く切り取るのではなく、時間をかけて懐に入る」と評する声もあり、まなざしの温度感が作品全体に通底していると指摘されています。また被写体となる人々が背負う現実を安易にドラマ化するのではなく、営みをそのまま尊重しようとする姿勢が作風の特徴となっています。
チェルノブイリ原発事故、そして後年の福島第一原発事故など、人々が生活基盤を揺るがされた状況下で、本橋の写真や映画は「一見忘れがちな場所に根づく命」を記録する役割を担いました。
84. 稲越 功一(1941~2009)
稲越功一(いなこし・こういち)の多彩なキャリアは、広告写真から始まり、風景や人物の撮影、さらには日常の何気ない瞬間を切り取るスナップショットに至るまで、多岐にわたります。
岐阜県高山市に生まれた稲越は、武蔵野美術大学を中退後、モス・アドバタイジング株式会社でグラフィックデザイナーとしてキャリアをスタートさせました。1970年には有限会社イエローを設立し、フリーランスの写真家として独立しました。
稲越の初期の作品として注目されるのが、1971年に発表された写真集『Maybe, Maybe』です。この作品では、日常生活の中で見過ごされがちな光景をモノクロームで捉え、その詩的な美しさと深い洞察力が評価されました。この写真集は、日本におけるスナップショット写真の新たな潮流を切り開いたとも、コンポラ写真の代名詞とも言われることがあります。その後も『Meet Again』(1973年)や『記憶都市』(1987年)など、彼の作品は一貫して日常性とその中に潜む普遍的な美を追求し続けました。
コマーシャルの領域では、稲越は多くの著名人や文化人の肖像写真も手掛けています。例えば、市川猿之助や中村吉右衛門といった伝統芸能界の人物から、ミュージシャンや俳優まで幅広いジャンルで活躍する人々を撮影しています。
また、彼が特筆されるもう一つの側面は、その文筆活動です。稲越は自らエッセイや詩を書くことでも知られ、その文章と写真が融合した作品集も多く出版されました。例えば、『使いみちのない風景』(村上春樹との共作)では、文章と写真が相互に補完し合いながら、一つの芸術作品として完成されています。
ファッションや広告産業の隆盛、あるいは多メディア化が進んでいく背景のなかで、稲越のように現場を横断しつつ自分の作家性を追究する写真家が目立ちはじめたことは、一種の社会現象といえます。アマチュア的なコンポラ写真の表現に取り組んでいた彼は、むしろコマーシャルの分野でその名を広めました。その活動は、日本における写真集ブームや出版文化の変遷と密接に結びついており、1980年代以降の写真界が生み出した多様な潮流を象徴する存在の一つと位置づけられます。
85. 荒木 経惟(1940~)
荒木経惟(あらき・のぶよし)は、1940年に東京で生まれ、日本を代表する写真家として知られています。その作品は、生(エロス)と死(タナトス)、そして無常観を主題とし、彼の独特な視点と表現力によって写真界に多大な影響を与えました。荒木のキャリアの始まりは、1963年に広告代理店・電通で商業写真家として働き始めたことに遡ります。在職中から個展を開催し、私家版写真集も刊行するなど、早くから自身の芸術的探求を進めていました。
彼の転機となったのは、1971年に発表した写真集『センチメンタルな旅』です。この作品は、新婚旅行を記録したものでありながら、単なる記録写真を超えた個人的な視点と感情が込められています。これは「私写真」と呼ばれるジャンルの先駆けとされ、文学の「私小説」に倣った個人的な表現スタイルを写真に持ち込む試みでした。この作品は既存の写真表現への挑戦であり、彼自身の写真家としての決意表明でもありました。
以降、荒木は東京の日常や私生活、セクシャルな情景、一連の組み写真からなる「物語写真」など、多様なテーマで作品を発表しました。特に江戸時代の春画を彷彿とさせるセンセーショナルな人物描写や花々、食事、空景など、日常的な被写体に美しさを見出す作品群が特徴的です。彼のヌード写真やエロティックな作品は、その過激さゆえに議論を呼びましたが、それらは単なる挑発ではなく、人間存在そのものへの深い洞察が込められています。
芸術寄りのヌード写真を撮る「ギネ・グルッペ」の影で、カストリ雑誌の紙面を埋めていたような、わいせつ性の限界に挑戦するようなエロ写真は市場に数多く並んでおり、これらは写真家の食い扶持のひとつとして確立していっていきました。しかし、そういった仕事はいわゆる「美人写真」を扱うのと比べて一段低い地位の仕事とされ、バイネームで写真が発表されることも少なかったのです。そののなかで、荒木は、裏のエロ写真のスタイルや掲載媒体自体を「作品」化し、表との垣根を飛び越えた存在と言えます。ヌード写真が芸術という鎧で武装することで、写真家の勃起したペニスや濡れたヴァギナを隠すのを笑い飛ばすように、どれほどわいせつであろうとも、被写体と写真家との関係を虚飾なく表現する写真こそが、人間の美しさを真に体現すると捉える。女性に対する荒木の思想の前衛性はこのような点にこそあるといえます。
また、1980年代以降には妻・陽子との生活やその死後の喪失感をテーマにした作品も多く発表されました。特に『冬へ』や『センチメンタルな旅・冬の旅』などは、愛する人との別れという普遍的なテーマを扱い、多くの人々に深い感動を与えました。これらの作品は、生と死という対極的なテーマを同時に描き出すことで、人間存在そのものへの問いかけとなっています。
しかしながら、彼の性的表現は賛否両論を巻き起こしました。荒木のヌード写真は一部では「搾取的」だと批判される一方で、「解放的」だと評価されることもありました。特に1990年代以降、西洋でも注目されるようになり、多文化主義的な視点から非西洋作家への関心が高まった中で、荒木の作品はその独自性ゆえに国際的なアートシーンでも地位を確立しました。さらに、荒木が市場にもたらした影響には、「企業体アラキ」と呼ばれるような彼自身とその周囲による戦略的なブランド化があります。膨大な数の出版物や展覧会によって彼の作品が広く流通し、その結果としてアート市場での商品価値が高まりました。このような流通戦略は、荒木個人だけではなく、日本全体の写真文化やアート市場にも影響を及ぼしました。一方で、近年ではモデルとの関係性や契約問題が取り沙汰され、「#MeToo」運動とも関連して批判が高まりました。モデルを務めた女性による告発は、荒木作品における被写体との権力関係や倫理性について再考させる契機となりました。この問題は、彼の作品が持つ芸術的価値とは別に、社会的・倫理的側面からも議論されています。
総じて言えば、荒木経惟のヌード写真は、その独創性と挑発性によって写真表現や市場に革新をもたらしました。しかし同時に、その表現手法やモデルとの関係性については批判も多く、芸術と倫理の境界について議論が続いています。この二面性こそが荒木作品の特異性であり、それゆえに彼の作品は今なお注目され続けていると言えるでしょう。
菱沼良樹 ほか『百花百蝶 : Yoshiki Hishinuma by Nobuyoshi Araki』,講談社インターナショナル,2000.
荒木経惟「脱いでもヌードとは限らない」『広告批評』(176),マドラ出版,1994.
1990年代にみられる「ヘアヌード」ブームにおける、業界内部の目線や距離感については、同誌の「『ヘア・ヌード』の見方 」( 飯沢耕太郎)が参考になる。
また、同時代においてヌード写真集を、対決的にあるいは協働的に出版しあっていた、篠山紀信と荒木経惟の表現における対比については「虞美人草の太陽 篠山紀信「激写」論 」(草森紳一)の指摘が示唆的である。
婦人画報社 編『夫婦春秋 : 女房が笛吹きゃ亭主が踊る』,婦人画報社,1987.
妻の荒木陽子さんと経惟の夫婦観について、それぞれがコメントを寄せている。
結婚式はその翌年の夏、青学会館でごく普通に上げたのだが、披露宴がぶっ飛んでいた。ご主人が勝手に、新婦陽子さんのヌードのスライドを、出席者一同の前で大映しにしてみせたのである。
「それには私も驚いちゃって。それまでヌードは限りなく取られていたからだったんですけどね。周りを見ると一同シーン、親戚のおばあちゃんなんか、ショックで二、三日寝込んだそうです」
陽子さんは?
「私は、それで、逆に度胸をつけてしまいました」
ここ数年、気になることが一つ。もう二年前になるが、夫婦で手相を見てもらったときのこと、「今は家庭運が非常にうまくいっていますが、あと五年ぐらいになにか起こるかもしれません」と言われたこと――。
「信じてはいないんですけれど、暗示にかかりやすいほうなので……。それに、有名な占い師のかただったので、わりと気にしてるんです。どうなるのかわからないんですけれど」
そうなったらそうなったでいい、いろいろ楽しめば――と思う一方で、陽子さんは、老後は夫婦で仲良く、根津あたりでモンジャ焼きの店をやりたいと、本気で考えたりしている。
(一九八六年二月号)
____
※引用者注
「なにか起こるかもしれない」と占われたちょうど5年後の1989年に、陽子さんは子宮肉腫のために東京女子医大病院に入院し、翌年1990年1月に永眠した。
86. 篠山 紀信(1940~2024)
篠山紀信(しのやま・きしん)は、1940年に東京都新宿区北新宿で生まれました。幼い頃に戦争で父親を亡くし、仏教寺院で育てられるという特別な環境の中で成長しました。高校卒業後、一般大学の受験に失敗した篠山は、日本大学芸術学部写真学科に進学します。写真には特に興味がなかったものの、在学中からその才能を発揮し、1961年には「日本広告写真家協会展公募部門」でAPA賞を受賞しました。
この受賞をきっかけに、篠山は広告制作会社「ライトパブリシティ」に入社し、本格的にプロの写真家としてのキャリアをスタートさせます。1968年にはフリーランスとなり、その後、さまざまなジャンルで活躍しました。特に注目を集めたのが、芸能人や一般の人々を撮影したポートレートやヌード写真です。篠山の作品は単なる記録写真にとどまらず、被写体の個性やその時代の空気を鮮やかに浮かび上がらせるものでした。
彼の代表作には、作家の三島由紀夫や、ジョン・レノンとオノ・ヨーコのポートレートがあります。特に後者は、アルバム『ダブル・ファンタジー』のジャケット写真として世界的に有名です。1975年には雑誌『GORO』で山口百恵さんを撮影したことから始まったシリーズ「激写」が話題を呼びました。このシリーズでは無名のモデルから人気芸能人までを撮影し、篠山の名声を一層高めました。そして、1979年には「激写」の被写体の一人であった元歌手の南沙織さんと結婚したことも大きな注目を集めました。
篠山紀信のキャリアにおいて特筆すべき点は、常に新しい表現技法や技術に挑戦し続けた姿勢です。
「激写」のほか、複数のカメラで同時にシャッターを切る「シノラマ」や、デジタル技術を駆使した「digi+KISHIN」など、最先端の技術と独創的な表現を融合させ、新たな写真の可能性を切り開いてきました。
篠山紀信を語る上で外せない要素の一つに、1990年代初頭の「ヘアヌードブーム」との関わりがあります。その象徴的な出来事が、1991年に発表された宮沢りえの写真集『Santa Fe』です。この作品は日本初のヘアヌード写真集として社会現象を巻き起こし、155万部を売り上げる驚異的なベストセラーとなりました。小室哲哉プロデュースの楽曲がオリコン1位を記録し、前年には紅白歌合戦にも出演するなど、当時絶頂の人気を誇った宮沢りえがヌードに挑戦したことで、書店には男性客が殺到しました。
『Santa Fe』は、篠山が手がけた樋口可南子の写真集『Water Fruit 不測の事態』とともに、ヘアヌードブームの火付け役となりました。しかし、このブームの裏では「猥褻か芸術か」を巡る激しい議論が巻き起こりました。特に宮沢りえのヌード写真が一般紙の全面広告に掲載されるという大胆な展開は、雑誌や新聞におけるヌード表現の規制の境界を越え、日本社会に大きな衝撃を与えました。この出来事は「ヘアヌード」という言葉を日本中に浸透させるきっかけとなり、社会的インパクトは計り知れないものでした。
ただし篠山紀信氏自身は、「ヘアヌードブームの立役者」とみられることについて否定的でした。
実際、篠山氏は「ヘアヌード」という呼び方そのものを嫌っており、「ヌードって隠れて見るものだったのにね。ヌードの偏見を国民的に覆した本かもしれない。僕は自分ではヘアヌードなんて1度も言ってない。ヘアヌードて言われるから写ってるのかと、見たら1枚なんだよね。よくこれでヘアヌードって言うなって。世の中がジャンルを作っちゃったんだよね。」と語っています。また、当時あまりにも篠山にヘアヌードの依頼が来るので、「気に食わないな」と思ってヘアだけの写真集『ヘア / Hair』(1994)を出版するなど、皮肉交じりにこのブームに応答しています。
篠山は表現の限界に挑む中で、社会的に物議を醸すこともありました。その代表的な出来事が、2009年に発売された写真集『20XX TOKYO』に関連する問題です。この写真集では、東京都内の目に触れる野外でモデル女優の裸を撮影したとして、公然わいせつ罪の疑いで篠山の事務所が警視庁から家宅捜索を受けました。問題とされたのは写真集自体のわいせつ性ではなく、撮影場所が東京都立青山霊園を含む公衆の目に触れる12カ所であった点です。特に、1874年に開設された青山霊園での撮影は、史上初のヌード撮影だったため批判が集中しました。
とはいえ写真家の仲間からは同情の声も少なくなく、加納典明はテレビ番組で「こんな程度で罪になるんだったら、写真は撮れない」と彼は自身の作品を「芸術」として位置づけ、その表現の自由を訴えています。
なお、篠山は捜査当初、警視庁に「水着で撮影していた」という虚偽の内容を記した始末書を提出してが、後に違法性を認めて、篠山本人とモデル2人は警視庁生活安全部保安課に書類送検されています。その後、篠山は東京簡易裁判所から公然わいせつ罪と礼拝所不敬罪で罰金30万円の略式命令を受けました。
また、篠山は荒木経惟との論争も彼の人となりを知るうえでは重要なポイントでしょう。1991年、新潮社のPR誌『波』で行われた荒木経惟との対談を行いました。この対談では、荒木が妻・陽子さんの死後、その棺の中で眠る姿を撮影した写真集『センチメンタルな旅・冬の旅』について激しい意見交換が行われました。篠山はこの作品について、「荒木ほどの写真家がこれをやってしまったことに失望した」と述べ、荒木がこれまで築いてきた「多義性」や「リアリティ」を裏切るものだと批判しました。一方で荒木は、「これは自分自身のための作品であり、第一の読者は自分だ」と反論し、自らの哲学を貫きました。
篠山はまた、美術館やギャラリーでの展示活動にも力を入れました。2012年から全国巡回展として開催された「篠山紀信展 写真力 THE PEOPLE by KISHIN」は、多くの観客を動員し、彼の作品が単なる写真ではなく「時代」を記録するイコンとして評価されていることを示しています。この展覧会では坂東玉三郎や被災地の人々など、多様な被写体が取り上げられました。
晩年まで活躍し続けた篠山紀信は2024年1月4日、83歳でその生涯を閉じました。その足跡は日本写真界のみならず、大衆文化全体にも深い影響を与え続けています。
87. 渡辺 克巳(1941~2006)
渡辺克巳(わたなべ・かつみ)は、岩手県盛岡市出身の写真家であり、主に新宿を舞台に活動しました。
渡辺は盛岡第一高等学校の定時制に通いながら、毎日新聞社盛岡支局で補助員として働き、写真の面白さを知りました。その後、高校卒業後に国鉄に就職しますが、写真への情熱を捨てきれず、1961年に上京します。翌年から5年間、東條会館でスタジオ撮影を学びました。この期間に培った技術が、後の彼の独自性ある写真表現に繋がります。
1965年からは「流しの写真屋」として新宿で活動を開始しました。「1ポーズ3枚1組200円」という手軽な価格設定でポートレート撮影を行い、新宿の街角で多くの人々と接触しました。この活動は単なる商業的な仕事に留まらず、彼が新宿という地域社会やそこに生きる人々と深く関わる契機となりました。特に歌舞伎町など当時の新宿の裏社会や夜の顔を捉えた写真は、その時代の雰囲気や社会的な背景を感じさせるものとして注目されます。
1973年には、「カメラ毎日」6月号で新人写真家紹介ページ「アルバム」に「新宿・歌舞伎町」を発表し、大きな話題を呼びました。この作品は同年、「カメラ毎日」アルバム賞を受賞し、渡辺の名を広く知らしめるきっかけとなりました。同年には写真集『新宿群盗伝』も刊行され、その独特な視点とリアルな描写が評価されました。
その後も渡辺は新宿を拠点に活動を続けながら、多様な職業にも挑戦しました。焼き芋屋や写真館経営なども経験しつつ、「フォーカス」や「週刊文春」などで週刊誌カメラマンとしても活躍しました。これらの経験は彼の視点をさらに広げ、多様な人間模様を捉える力となりました。
1998年には、1960~90年代の新宿の景色をまとめた写真集『新宿』で日本写真協会年度賞を受賞しました。新宿は戦後の闇市から発展した地域で、歌舞伎町やゴールデン街といった歓楽街は、かつて非合法な売春や風俗産業が盛んだった場所でもあります。渡辺の写真は、そうした場所で働く娼婦や労働者、外国人労働者など、社会的に弱い立場の人々を記録し、彼らの生活や感情をリアルに伝えました。
1980年代以降、新宿では性風俗産業が急速に拡大し、売春や違法な商売が広がる一方で、都市の繁栄の裏に貧困や社会的排除といった問題が浮き彫りになりました。また、新宿駅周辺では1990年代半ばから「排除アート」と呼ばれるホームレス対策が進められ、物理的な障害物を設置してホームレスを追い出す取り組みが議論を呼びました。これらの対策は治安や美化を目的としていましたが、結果的に社会的弱者をさらに孤立させもしました。
新宿はまた、1980年代以降、多くの外国人労働者が生活の拠点とした場所でもあります。彼らは不安定な雇用や差別に直面することが多く、渡辺の写真はその日常や苦悩も記録しています。
88. 鈴木 清(1943~2000)
鈴木清(すずき・きよし)は、福島県いわき市出身の写真家です。彼の作品は、炭鉱の町や路上生活者、旅役者、アジア各地の風景や人々をテーマに、独自の視点で社会や人間を深く見つめたものとして知られています。また、自費出版やユニークな展示方法が特徴です。
高校卒業後、鈴木は漫画家を目指して上京しますが、土門拳の写真集『筑豊のこどもたち』に感銘を受け、写真家を志します。1969年に東京綜合写真専門学校を卒業し、『カメラ毎日』誌で「シリーズ・炭鉱の町」を連載しました。彼の生まれ故郷である炭鉱の町での人々の暮らしや社会問題を写し出し、写真家としての第一歩となりました。
1972年、自費出版による最初の写真集『流れの歌』を発表。続く1976年には、インド取材をもとにした『ブラーマンの光』を発表し、宗教や精神世界への関心を示しました。さらに1982年には、路上生活者をテーマにした写真集『天幕の街』で日本写真協会新人賞を受賞。社会的に弱い立場の人々に寄り添いながら、人間そのものへの深い問いを投げかけました。
1980年代後半から1990年代にかけて、鈴木はバブル期の日本社会や昭和という時代全体を見つめた作品を制作しました。『夢の走り』(1988年)は港町を舞台に夢や潜在意識を描き、『愚者の船』(1991年)では都市空間とそこに生きる人々を写しました。『修羅の圏』(1994年)では、自身の故郷いわき市を舞台に、自伝的な視点で記憶や歴史を掘り下げ、この作品で土門拳賞を受賞しました。
鈴木は写真集の制作にも独自のこだわりを持ち、撮影だけでなく編集やレイアウトにも深く関わりました。彼の写真集は引用文や詩的な文章が挿入され、単なる写真の集まりではなく、読む人に深い考えを促す作品として仕上げられています。また、自費出版という形式にこだわり、芸術表現の自由を守り抜きました。
展示方法にも革新性がありました。鈴木は壁だけでなく、床や天井も使った立体的な展示空間を作り出し、観客がその場全体と対話できるような体験型展示を実現しました。このような新しい展示スタイルは、後の写真家やデザイナーにも影響を与えました。
教育分野でも、鈴木は母校の東京綜合写真専門学校で講師を務め、多くの若い写真家に影響を与えました。その教え子の中には、金村修など後に著名になった写真家も含まれています。
89. 竹内 敏信(1943~2022)
竹内敏信(たけうち・としのぶ)は1943年に愛知県で生まれ、名城大学理工学部在学中から写真に関心を寄せていました。卒業後は愛知県庁に勤めましたが、社会問題への強い興味をきっかけに、公害や環境汚染の実態を追うドキュメンタリー写真を自主的に撮りはじめます。1972年には四日市をはじめとする伊勢湾の公害実態を約2年かけて取材し、埋め立て予定の塩田や汚れた海面、打ち上げられたプラスチックごみ、生活に影響を受けながらも懸命に生きる人々の日常をモノクロ写真で克明に捉えました。このシリーズは「汚染海域―伊勢湾からの報告―」と題され、銀座ニコンサロンで個展を開いて強い反響を呼びます。県庁勤務と並行してこうした報道的写真を撮り続けていた竹内は、同年にフリーランスの写真家として本格的に独立を果たしました。
その後、竹内の関心は次第に「破壊された後の姿を撮るより、自然の美しさを伝えることのほうが、保護を訴える力になるのではないか」という発想へと変化していきます。そこで1980年代頃から、日本の原風景を撮り続けることを主軸に据え、活動の場を東京へ移しました。
風景写真といえば当時は大判や中判カメラもしくは慎重な構図決めが主流でしたが、竹内は機動力やレンズワークの柔軟性を重視し、35mm一眼レフカメラを用いた撮影を積極的に取り入れていきます。これは当時の風景写真界では異例とされ、「描写力に劣る」とも言われていた小型カメラで、波しぶきや雷光、あるいは滴に濡れる小さな綿毛まで、多様な自然の表情をダイナミックかつ機敏に捉える撮影方法を確立しました。
1985年に出版された写真集『天地聲聞』は、竹内の名を大きく知らしめる契機となりました。仏教用語からとられたこの題名は「自然を師とし、天地の摂理を悟る」という意味を含み、日本人が遠い昔から見つめてきた風景に今一度目を向け、その尊さを共有したいという意図が込められています。この写真集は、多様な気象や季節の一瞬を捉え、当時は大胆とされていたズームレンズの使用も相まって、多くの読者から注目を集めました。それとともに「風景写真ブーム」が加速し、写真雑誌やカレンダー、紀行雑誌などで風景を特集する機会が増えたとされています。
その流れの中で竹内に作品依頼が相次ぎ、若年層も含め幅広い層が風景写真に熱中していく現象が生まれました。
やがて桜を主題にしたシリーズ『櫻』や『櫻暦』、再び大型カメラによる作品集『天地風韻』などを通じて、「日本人の心と結びつく情景を表現する写真」に力を注ぎました。とりわけ桜の撮影には並々ならぬ情熱を注ぎ、「毎年、体が桜を求めるかのように旅をしてきた」と自著のあとがきなどで言及しており、日本各地を巡っては名木や老木にレンズを向け続けました。
竹内は後年も、写真誌や書籍を通じて撮影手法や使用機材のデータを惜しみなく公開し、アマチュア写真家や学生への指導にも熱心に取り組みました。また日本写真芸術専門学校校長の校長に就任し、講演や写真展において、自らの経験を後進に伝える活動を続けました。一方で、日本各地の自然環境を守るためには、破壊される前段階で美の意義を強調しておく方が有効である、という一貫した考えを持ち続けています。そして、花や山河の微妙な移り変わりを撮りためた多数の作品を発表し、旅情や情緒だけではない「自然に対する畏敬」の感覚も示そうと試みてきました。
90. 広河 隆一(1943~)
広河隆一(ひろかわ・りゅういち)は1943年に中華民国天津市で生まれ、幼少期に日本へ引き揚げました。大阪府で育ち、早稲田大学教育学部を卒業後、1967年にイスラエルへ渡航し、農業ボランティアを通じて現地文化やヘブライ語を学びました。この経験が彼のフォトジャーナリストとしての基盤を築き、特に中東問題への関心を深める契機となりました。
彼は1970年代からパレスチナ問題やレバノン内戦など中東地域の紛争を取材し、その写真と報道で国際的な評価を得ました。1982年のサブラ・シャティーラ難民キャンプ虐殺事件では、その惨状を記録した写真が「よみうり写真大賞」や「IOJ国際報道写真展大賞・金賞」を受賞するなど、大きな注目を集めます。また、1998年には自身の取材活動を振り返る著書『パレスチナ難民キャンプの瓦礫の中で』を発表し、中東問題における30年の歴史を記録しました。
2004年にはフォトジャーナリズム月刊誌「DAYS JAPAN」を再創刊し、編集長として10年間その指揮を執りました。この雑誌は戦争や環境問題、人権侵害など世界各地で起きている社会的課題に焦点を当て、多くの読者に支持されました。また、広河はチェルノブイリ原発事故後に設立された「チェルノブイリ子ども基金」の代表としても活動し、被災地支援や医療支援に尽力しました。
しかしながら、彼のキャリアは2018年12月以降、大きな転機を迎えます。週刊文春による報道で、『DAYS JAPAN』の編集部や関連する女性スタッフへの性暴力やセクシャルハラスメントが明るみに出ました。この報道後、設立された検証委員会は、広河が長期間にわたり少なくとも17人の女性に対して性暴力やパワーハラスメントを行ったことを認定しました。これらの行為は彼が持つ権力や地位を利用したものであり、多くの被害者が声を上げられない状況が長く続いていました。
この問題は#MeToo運動ともあいまって、社会的にも大きな波紋を呼び起こし、「性暴力」や「労働環境」に関する議論が活発化しました。広河自身は一部謝罪コメントを公表しましたが、その後も「実際は合意があった」と主張するなど、一貫した反省の姿勢には欠ける態度が見られました。これにより、彼のこれまでの人権活動や社会的貢献にも影響が及び、多くのイベントや写真展が中止される事態となりました。また、『DAYS JAPAN』もこのタイミングで経営難となり破産しています。
広河隆一の写真に対する考え方は、被写体となる人々との信頼関係を重視し、その生活や苦悩に寄り添う姿勢が特徴でした。しかし、その裏で明らかになった権力乱用と倫理観の欠如は、彼が掲げていた理念との矛盾として批判されています。このような経緯から、広河隆一という人物像は功績と問題行動が複雑に絡み合うものとなっています。彼の活動はフォトジャーナリズム界に多大な影響を与えた一方で、その影響力が負の側面でも行使されたことへの反省と再評価が求められています。
91. 北井 一夫(1944~)
北井一夫は1944年、中国の鞍山で生まれ、戦後日本に引き揚げました。彼は日本大学芸術学部写真学科に入学しますが、わずか半年の在学で中退します。その理由について、北井自身は「教授たちの言うことを一切聞かなかった」と述べており、既存の教育体制や権威への反発がうかがえます。この頃から、彼の写真家としての独自性が形作られていきました。
北井が最初に注目を集めたのは、1965年に自費出版した写真集『抵抗』です。この作品は、神奈川県横須賀港へのアメリカ原子力潜水艦寄港に反対するデモを記録したものでした。当時の日本は安保闘争やベトナム反戦運動など社会的混乱が続いており、北井はその渦中で学生運動や労働者運動を撮影しました。
その後、北井はさらなる挑戦として写真集『過激派』の出版を試みますが、自費出版の経済的ハードルに直面し計画は頓挫します。この挫折を経て神戸に戻った彼は、港湾労働者の日常を撮影し始めました。この時期の作品には、労働者たちの素朴な生活や労働環境が映し出されており、北井の視点が社会的弱者や現場に寄り添うものであったことが感じられます。
1969年には成田空港建設反対運動(三里塚闘争)を取材し、その成果として写真集『三里塚』を発表しました。北井はこの取材を通じて、自身の写真観を大きく変化させました。それまで学生運動など「主張する」写真を撮っていた彼ですが、この時期から「主張しない」写真へと移行します。三里塚で出会った農民たちの生活に根ざした闘争に触れることで、人間の日常や生活そのものを写し取ることの重要性を認識したのです。この視点は後年の作品『村へ』にも引き継がれ、日本全国の農村風景と人々の日常を記録するシリーズとなりました。
92. 大石 芳野(1944~)
大石芳野(おおいし・よしの)は日本大学藝術学部写真学科を卒業した報道写真家です。
大石が写真家として注目されるきっかけとなったのは、1970年代にパプアニューギニアで行った取材でした。彼女は現地で300日以上滞在し、石器時代さながらの生活を送る人々と共に過ごします。以降、大石はベトナム戦争やカンボジア内戦、広島・長崎の原爆被害者、さらにはコソボやダルフールなど、世界各地の戦禍を取材し続けています。
彼女が特に重視しているテーマは、「戦争が終わってもその傷跡は消えない」ということです。例えば、ベトナム戦争では枯葉剤による健康被害が世代を超えて続いており、大石はその影響を受けた人々の姿を記録しました。また、カンボジアではポル・ポト政権下で虐殺や強制労働を強いられた人々の心の傷に迫り、その現実を世界に伝えました。
大石自身が語るように、彼女は戦争を知らない世代として「自分が無知であること」を自覚し、それを埋めるために現地で直接見聞きすることにこだわります。この姿勢が、被写体との信頼関係を築き、その結果として深い人間性が映し出された写真へと繋がっています。
2004年からは世界平和アピール七人委員会の委員として活動し、多くの講演や出版活動を通じて、戦争や平和について考えるきっかけを提供しています。
93. 藤原 新也(1944~)
藤原新也(ふじわら・しんや)は1944年、福岡県北九州市に生まれました。東京藝術大学美術学部油画科に進学するも中退し、その後アジア各地を旅する中で写真と文章を組み合わせた表現を確立しました。彼の初出版である『印度放浪』(1972)は、インドを旅した経験をもとにした写真とエッセイの融合作品であり、当時の日本の若者に大きな影響を与えました。この作品は、高度経済成長期の日本社会における精神的な空虚感や自己探求の欲求を背景に、多くの読者に支持されました。
藤原の作品には一貫して「生と死」というテーマが流れています。インドやチベットなどで撮影された写真には、人間の死とその周囲に存在する宗教的儀式や自然が映し出されており、それらは日本とは異なる死生観を鮮烈に伝えています。特に『メメント・モリ』(1983年)では、「死を思え」というラテン語のタイトル通り、死を直視することで生の本質を浮き彫りにするという彼独自の哲学が表現されています。この作品は、写真だけでなくキャプションによる文章表現でも注目され、「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ」といった挑発的な言葉が社会的な議論を呼びました。1970年代後半から1980年代は、スピリチュアルな体験を求めるバックパッカーや、一部のカウンタカルチャーに親和的な層のインド旅行が増えていった時期でもあります。藤原の著作もインドを「神秘の国」としてまなざし、イメージを形作る一助になったといえます。
藤原は写真家としてだけでなく、文筆家や画家としても活動しています。東京藝術大学で培った絵画技術はその後も活かされ、個展では写真だけでなく絵画や書道作品も展示されています。2023年には世田谷美術館で大規模な回顧展「祈り・藤原新也」が開催され、生涯を通じた彼の創作活動が「祈り」というテーマのもと再解釈されました。この展覧会では、インドやチベットで撮影された初期作から東日本大震災後の被災地やコロナ禍の無人都市まで、多岐にわたる作品が展示されました。
94. 丹野 清志(1944~)
丹野清志(たんの・きよし)は1944年、福島県福島市に生まれました。彼は1964年に東京写真短期大学(現・東京工芸大学)を卒業後、農村雑誌『家の光』のスタッフカメラマンとして勤務しました。その後1970年にフリーランスとなり、日本列島各地を巡りながら都市や農村、漁村の風景や人々の暮らしを記録し続けます。
丹野の写真家としての活動は、社会的背景や時代の空気感を捉えることに重きを置いていました。彼の初期の作品では、炭鉱住宅や地方都市など、当時の日本が抱えていた社会問題や生活環境がテーマとなることが多く、例えば「1963炭鉱住宅」や「死に絶える都市」などの写真展でその視点を示しています。これらは、高度経済成長期における都市化や公害問題、地方の過疎化といった社会現象を背景に、人々の日常生活を記録したものです。
丹野はまた、農村や漁村での生活をテーマにした作品も多く発表しました。写真集『村の記憶』や『路地の向こうに』では、農村の日常風景や人々との交流を通じて、従来の「貧しい農村」という固定観念を覆すような明るさと希望を描き出しています。彼自身が語るところによれば、「農民が苦労しているだけ」というステレオタイプなイメージではなく、「実際には希望を持って日々生きている姿」を伝えたかったといいます。
また、1970年代には多摩川をテーマにした作品も注目されました。当時、多摩川は公害問題が深刻化しており、「死の川」とまで呼ばれていましたが、その中でも人々の日常生活や川辺での楽しみ方を丹野はカメラに収めています。メディア上で公害問題ばかりが注目される中、その裏で営まれるが日常生活に焦点を当ててのことでした。
丹野は写真家としてだけでなく、エッセイストとしても活躍しました。彼の著書『なぜ上手い写真が撮れないのか』では、「上手い写真」ではなく「良い写真」を目指すための考え方を提案しています。この中で彼は、テクニックだけではなく、自分自身が何を表現したいかという内面的な問いかけが重要だと述べています。また、「写真クラブ」などで見られる形式的な写真文化に対しても批判的であり、「個としての写真」を追求する姿勢を持つことを訴えます。
丹野清志は、そのキャリア全体を通じて、日本各地を旅しながら「普通」の人々の日常生活や風景を記録し続けました。彼の作品は、人々の日常に潜む美しさを強く映し出しています。
95. 中村 征夫(1945~)
中村征夫(なかむら・いくお)は秋田県潟上市に生まれ、少年時代を八郎潟で過ごし、自然と親しむ中で育ちましたが、高校卒業後に上京し、秋葉原の家電店に就職します。しかし職場環境になじめず、休日には海へ出かけ、素潜りを楽しむようになります。この頃、神奈川県真鶴岬で水中カメラを手にしたダイバーと出会ったことが、彼の人生を大きく変える契機となりました。独学で水中写真を学び始めた中村は、やがて撮影プロダクションに入社し、水中カメラマンとしてのキャリアをスタートさせます。
31歳でフリーランスとなった中村は、1977年に初めて東京湾に潜り、その環境に衝撃を受けます。ヘドロに覆われた「死の海」とも言える状況下で、小さなカニや魚が懸命に生きる姿を目の当たりにし、「東京湾の撮影をライフワークとする」と決意しました。この経験は彼の写真家としての方向性を決定づけるものであり、単なる美しい風景写真ではなく、海洋環境や生態系の現状を伝えるジャーナリスティックな視点を持つ写真家としての道を歩むきっかけとなりました。
1993年には取材先の奥尻島で北海道南西沖地震に遭遇し、津波によって機材のほとんどを失いながらも、唯一残ったカメラで被災地の惨状を撮影しました。その写真は共同通信社を通じて世界中に配信され、多くの新聞に掲載されました。この出来事は、中村が報道写真家としても評価される契機となります。また、中村は石垣島白保地区でアオサンゴ大群落をモノクロ写真で撮影し、その作品が環境保護活動にもつながりました。この写真集が後押しとなり、白保地区で計画されていた空港建設が白紙撤回されたというエピソードは特筆すべきものです。
中村の作品は単なる記録ではなく、人々に深い感動や問題意識を喚起する力があります。例えば、東京湾では汚染された環境下でも力強く生きる生物たちの姿を捉え、その生命力や環境問題への警鐘を発信してきました。また、サンゴ礁や干潟など、日本各地や世界中の海洋環境問題にも取り組み、その現状を写真や講演会など多様なメディアで伝えています。
1988年には『全・東京湾』と『海中顔面博覧会』で木村伊兵衛写真賞を受賞。2007年には『海中2万7000時間の旅』で土門拳賞も受賞しています。また、2009年には故郷秋田県潟上市に「ブルーホール」という自身の写真ギャラリーを開設し、多くの人々に海洋環境への関心を呼びかけています。
96. 鬼海 弘雄(1945~2020)
鬼海弘雄(きかい・ひろお)は1945年、山形県寒河江市(旧醍醐村)に生まれました。高校卒業後は山形県職員として働きましたが、将来の自分の姿が見えてしまうような感覚に陥り、哲学を学ぶために法政大学文学部哲学科へ進学します。そこで哲学者・福田定良の教えを受け、自分で考えることの面白さに目覚めたといいます。
大学卒業後、鬼海はトラック運転手や造船所工員、遠洋マグロ漁船乗組員など、さまざまな職業を経験しました。これらの仕事を通じて得た「肉体労働」の実感や人間の原点への洞察が、彼の写真表現に深く刻まれることになります。その一方で、彼はダイアン・アーバスの写真集に触れ、「見ても見ても見飽きない写真がある」という衝撃を受け、それが写真家としての道を選ぶきっかけとなりました。
1973年から始まった浅草寺での人物撮影は、彼のライフワークとなります。このシリーズは45年もの長きにわたり続けられ、「PERSONA(ペルソナ)」というタイトルで発表しました。彼は被写体を探し回ることなく、浅草寺境内で「やって来る」人々を待ち続け、その中から撮りたい人物を選び出しました。このアプローチには、「人間そのもの」を等価に捉えたいという彼独自の哲学的視点が反映されています。
鬼海の写真制作には一貫したスタイルがあります。例えば、30年以上使い続けたハッセルブラッド製カメラと標準レンズのみを用い、露出や光などの条件も一定に保つことで、一人ひとりの被写体に差異をつけないよう心掛けました。
2004年には浅草寺で撮りためた肖像写真集『PERSONA』で第23回土門拳賞を受賞しました。この作品は国内外で高く評価され、鬼海が日本写真界だけでなく国際的にも注目される契機となりました。
97. 牛腸 茂雄(1946~1983)
牛腸茂雄(ごちょう・しげお)は、新潟県加茂市出身の写真家であり、短い生涯でしたが、そのなかで独自の視点と表現を追求しました。日常の風景や人々の表情を繊細に捉え、コンポラ写真の旗手のひとりとして現代では知られます。
幼少期、牛腸は胸椎カリエスという病気を患い、成長が止まるという身体的なハンディキャップを抱えました。この経験は彼の人生観や創作活動に大きな影響を与えたと考えられています。彼は新潟県立三条実業高等学校商業科(現・新潟県立三条商業高等学校)を卒業後、デザインを学ぶために上京し、桑沢デザイン研究所に入学しました。そこで写真家・大辻清司との出会いがあり、大辻の勧めで写真専攻に進むことになります。
1968年に桑沢デザイン研究所を卒業後、牛腸はデザインの仕事と並行して写真撮影を続けました。1971年には初めての写真集『日々』を発表し、1977年には代表作『SELF AND OTHERS』を自費出版します。
牛腸の作品には、「コンポラ写真」と呼ばれるスタイルが反映されています。これは、当時の日本写真界で議論されていた「アレ・ブレ・ボケ」のような激しい表現とは対照的に、穏やかで静謐な日常風景や人物像を描き出すものでした。彼は特別な演出や加工を排し、被写体そのものが持つ自然な存在感や時間の流れに焦点を当てました。このアプローチは、同時代の写真家たちから批判されることもありましたが、一方で多くの共感と支持も得ました。
また、牛腸は写真以外にも創作意欲を示し、心理学的手法であるロールシャッハテストやマーブリング技法を応用した作品も制作しました。さらに8ミリや16ミリフィルムによる映画制作にも挑戦するなど、多岐にわたる活動を展開しました。
牛腸茂雄は1983年に36歳という若さで亡くなり、その後しばらくは彼の作品が広く注目されることはありませんでした。しかし、1990年代に入ると飯沢耕太郎が編集長を務めた写真雑誌『deja-vu』第8号(1992年)で牛腸の特集が組まれたことを契機に、彼の作品が再び脚光を浴びるようになります。 飯沢は牛腸の作品に深い関心を持ち、特に写真集『SELF AND OTHERS』の持つ独自性や普遍性を高く評価しました。この写真集は、被写体との親密な関係性や静謐な日常風景を捉えたものであり、飯沢はその作品が持つ「見ること」と「見られること」の関係性や、人間存在への洞察に注目しました。さらに、飯沢は牛腸の作品について講演会やエッセイなどで積極的に言及し、その魅力を多くの人々に伝える役割を果たしました。 なお、飯沢自身も語っているように、生前の牛腸とは直接の接点がなく、展覧会や個展で名前を見かける程度だったとされています。
98. 潮田 登久子(1940~)
潮田登久子(うしおだ・とくこ)は1940年に東京都で生まれ、静物を中心としたモノクロ写真で知られる日本の写真家です。
1960年、潮田は桑沢デザイン研究所に入学し、石元泰博や大辻清司から指導を受けました。それまでカメラに触れたことがなかった彼女ですが、石元の授業で「渋谷の街で見知らぬ人に声をかけて写真を撮る」という課題をきっかけに、一眼レフカメラを購入し、写真撮影を始めました。1963年に同研究所を卒業後、新宿や上野など東京の街頭で道行く人々を撮影するシリーズ作品を制作し、1976年には初個展「微笑みの手錠」を開催しました。
1966年から1978年まで、潮田は桑沢デザイン研究所および東京造形大学で講師として教鞭を執り、多くの後進を育てました。この時期には、自身もフリーランスとして活動を開始し、家庭や日常生活に目を向けた作品制作へとシフトしていきます。1978年には夫となる島尾伸三との間に長女が誕生し、その後一家は世田谷区豪徳寺の旧尾崎邸に移り住みました。この洋館での生活が、彼女の代表作「冷蔵庫/ICE BOX」シリーズ誕生の契機となります。
1981年から彼女は冷蔵庫の内外を撮影するというユニークなテーマに取り組み始めました。このシリーズでは、冷蔵庫という身近な存在が家庭や時代背景を象徴するものとして描かれています。6×6フォーマットのカメラで冷蔵庫正面から扉を閉じた状態と開けた状態を撮影するスタイルは、一見シンプルながらも生活の美しさや不思議さを追体験させる作品です。1996年には写真集『冷蔵庫/ICE BOX』として出版されました。
潮田はこの作品について以下のように話しています。
「貧しいけれど、実に平和なこの毎日が不思議に思えてなりませんでした。そして、思いもつかなかった今の自分の生活を冷蔵庫を定点観測することで記録に留めておこうと思いました。」
1995年には「本とその置かれている環境」をテーマとした「本の景色/BIBLIOTHECA」シリーズに着手します。解体前のみすず書房旧社屋で見つけた一冊の本からインスピレーションを得たこのシリーズでは、本という物体が持つ時間的・物理的な存在感が強調されています。図書館や古書店などで自然光のみを用いて撮影されたこれらのモノクロ作品は、2003年に初めて発表され、その後三部作として出版されました。
2022年には40年前の未発表作品をまとめた写真集『マイハズバンド』が出版されました。この作品は家族との日々や生活空間をテーマとし、彼女自身が過去と向き合う試みでもありました。同年、この写真集は「Paris Photo–Aperture PhotoBook Awards」で審査員特別賞を受賞しました。
99. 島尾 伸三(1948~)
島尾伸三は1948年、神戸市に生まれ、奄美大島で育ちました。父は小説家の島尾敏雄、母は同じく小説家の島尾ミホです。彼の家庭環境は文学と芸術に深く根ざしており、これが後の創作活動に影響を与えました。1974年に東京造形大学造形学部映像学科に入学し、写真を専攻します。この頃、父から譲り受けたリコーワイドというカメラを用いて写真撮影を始めました。
1975年には初の個展「China Town」を開催し、フリーランスの写真家として活動を開始します。その後、同じく写真家である潮田登久子と結婚し、一人娘で後に漫画家になる しまおまほが誕生しました。
100. 渡辺兼人(1947~)
渡辺兼人(わたなべ・かねんど)は、1966年に東京綜合写真専門学校に入学し、卒業後、1973年に初の個展「暗黒の夢想」(ニコンサロン)を開催します。この展示では、切り裂きジャックをテーマにした作品を公開しました。
渡辺が広く知られるようになったのは1980年に刊行された写真集『既視の街』によるものです。この作品は小説家・金井美恵子との共同制作で、文章とモノクローム写真が織り成す独特の世界観が高い評価を受けました。翌1981年には、この写真集および同名の個展で第7回木村伊兵衛写真賞を受賞します。
『既視の街』では「既視感」というテーマが中心に据えられ、都市風景や日常的な場面が一見平凡ながらもどこか不穏さや詩情を感じさせる構図で捉えられています。この作品は写真と言葉が互いに解釈を補完しないという独自のアプローチで制作されており、写真と文学の新しい融合形態として注目されました。
渡辺の作品は一貫して「静寂」と「余白」を重視する美学が特徴です。彼自身が語るように、写真とは対象物そのものではなく、それを取り巻く空間や時間、そして観る者との関係性を捉えるものです。
彼の作品は2003年に京都現代美術館・何必館に永久収蔵され、国内外で高い評価を受け続けています。その中でもストリートスナップや都市風景へのアプローチはアンリ・カルティエ=ブレッソンや木村伊兵衛といった巨匠たちとの系譜につながるものとされています。
101. 十文字 美信(1947~)
十文字美信(じゅうもんじ・びしん)は、篠山紀信の助手を経て1971年に写真家として独立。その後、資生堂や松下電器産業(現パナソニック)からの依頼を受け、広告写真やコマーシャルフィルム(CF)の撮影を手がけるようになります。
一方で、十文字は広告写真だけに留まらず、自身の独自のテーマに基づく作品制作にも力を注ぎました。1974年には、デビュー作「UNTITLED(首なし)」シリーズがニューヨーク近代美術館(MoMA)の「New Japanese Photography」展に出品され、国際的な評価を得ました。。
1970年代から1980年代にかけて、十文字は自身の体験や日本人としてのアイデンティティに焦点を当てた作品を発表しました。その中でも特筆すべきは、ハワイの日系移民一世を撮影した『蘭の舟』(1981年)や、インドシナ半島北部のヤオ族を取材した『澄み透った闇』(1987年)です。
1980年代以降、彼の関心は日本的な美意識へと向かいました。特に「黄金」と「侘び」という対照的な美学を探求し、それらを写真表現に昇華させました。『黄金風天人』(1990年)や『わび』(2002年)といった作品集では、日本文化が持つ繊細で複雑な美意識が色濃く反映されています。また、この時期には3D写真技法を考案し特許を取得しています。
さらに2000年代には、多摩美術大学教授として後進の育成にも携わりながら、新たな挑戦を続けました。一眼レフカメラの動画機能に着目し、それを活用した映像作品「さくら」や「おわら風の盆」を発表するなど、デジタル技術への適応も見せています。また、自作アタッチメントによる多重露光作品「FACES」や、日本仏像文化への深い洞察が込められた「残欠」など、多様なテーマで意欲的な活動を展開しました。
102. 石内 都(1947~)
石内都(いしうち・みやこ)は群馬県桐生市に生まれ、6歳から神奈川県横須賀市で育ちました。多摩美術大学で染織を学んだ後、写真の道に進む決定的な契機はありませんでしたが、友人から譲り受けた暗室道具をきっかけに写真を始めました。彼女の初期作品は、青春時代を過ごした横須賀の街を撮影した「絶唱、横須賀ストーリー」や、住人のいなくなったアパートを題材とした「APARTMENT」などで、これらは日本の高度経済成長期の影響を受けた街や建物の記憶を捉えたものです。これらの作品が評価され、1979年には女性写真家として初めて木村伊兵衛賞を受賞しました。
石内の写真には一貫して「時間」と「身体」がテーマとして流れています。1980年代以降、彼女は目に見えない時間の痕跡を身体に求め、「1・9・4・7」では自身と同じ1947年生まれの女性たちの手足を撮影し、「Scars」では身体に残る傷跡を題材としました。これらの作品は、個人の身体が持つ記憶や歴史を掘り起こし、それが社会的な文脈とどう結びつくかを問いかけていま。
2000年代になると、「Mother’s」というシリーズで彼女自身の母親が遺した遺品(下着や口紅など)を撮影し、その作品で2005年ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表作家に選ばれました。
また、「ひろしま」シリーズでは広島平和記念資料館に寄贈された被爆者の遺品(衣服や靴など)を撮影しました。被爆者の日常生活や個々人の存在感が強調し、戦争の「悲惨さ」だけでなく、被爆者が持っていた日常的な美しさや個性にも目を向けており、「広島」というテーマに新しい視点から切り取りました。
さらに近年では、メキシコの画家フリーダ・カーロの遺品を撮影するプロジェクトにも取り組みました。ここでも石内は遺品という物質的な存在から、その所有者の人生や時間の痕跡を浮かび上がらせる手法を展開しています。
103. 橋口 譲二(1949~)
橋口譲二は1949年、鹿児島県に生まれた日本の写真家で、彼のキャリアは1968年に上京し、写真専門学校に進学したことから始まりましたが、途中で中退しました。その後、全国を放浪しながら写真家としての道を模索しました。1981年には、新宿や原宿で若者たちの姿を捉えた作品「視線」が、第18回太陽賞を受賞し、一躍注目を集めます。
ちなみに、写真集『視線』はメディアファクトリーから出版予定でしたが、出版直前で肖像権の問題から発売中止となり、1997年に自費出版という形で世に送り出されました。
1980年代後半から1990年代にかけて、橋口は「日本と日本人」をテーマに全国各地で撮影を行い、数多くの写真集を発表しました。特に、17歳の少年少女たちのポートレートとインタビューを収めた『十七歳の地図』(1988年)は、同世代の若者たちから大きな共感と支持を得ました。また、『Father』(1990年)では父親像、『職 1991~1995 WORK』(1996年)では様々な職業人、『夢 Dream』(1997年)では高齢者をテーマに、それぞれ異なる世代や職業層の日本人を記録しました。
橋口はまた、ベルリンとの深い関わりでも知られています。1981年以降何度もベルリンを訪れ、ベルリンの壁崩壊前後の様子を記録しました。特に中古のローライフレックスで撮影した『BERLIN』(1992年)は、そのドキュメンタリー性と芸術性が注目され、日本写真協会賞年度賞や東川賞国内作家賞などを受賞しています。
104. ハービー・山口(1950~)
ハービー・山口(はーび・やまぐち)は1950年、東京都に生まれました。幼少期には腰椎カリエスという病を患い、長期間の療養生活を余儀なくされましたが、この経験が彼の人間観や写真家としての視点に大きな影響を与えました。中学時代に写真部に所属したことがきっかけで写真に出会い、友達や人々との交流を夢見てカメラを手にするようになります。高校時代にはアルバイトで貯めた資金を使い、当時の高級一眼レフカメラであるニコンFを購入し、本格的な写真家への道を志しました。
大学では経済学を専攻し、卒業後の1973年にロンドンに渡ります。当初はツトム・ヤマシタ主宰の劇団「レッド・ブッダ・シアター」で役者として活動しましたが、その後写真家としてのキャリアを本格化させました。当時のロンドンはパンクムーブメントが最高潮に達しており、ハービーはその熱気あふれる時代の中心で活動しました。彼はザ・クラッシュやボーイ・ジョージといったミュージシャンたちと交流し、彼らの日常やライブパフォーマンスを撮影することで注目を集めます。特にザ・クラッシュのジョー・ストラマーから「撮りたいものは撮れ、それがパンクだろ」という言葉を受けたエピソードは有名で、この言葉が以後の彼の写真家人生の指針となりました。
約10年間のロンドン生活を経て帰国した後も、ハービーはモノクローム写真を中心とした作品制作を続け、市井の人々やアーティストたちの日常を優しい視点で切り取るスタイルを確立しました。彼の写真には「人間が輝く瞬間」や「希望」がテーマとして一貫しており、その清楚で温かみのある作風は多くのファンから支持されています。また、福山雅治や布袋寅泰など日本国内外の著名なアーティストとのコラボレーションも行い、CDジャケットや雑誌撮影など幅広い分野で活躍しました。
105. 松本 路子(1950~)
松本路子(まつもと・みちこ)は1950年、静岡県に生まれ、法政大学文学部日本文学科を卒業後、写真家としての道を歩み始めました。人物写真や海外レポートを中心に展開され、訪れた国は60か国以上に及びます。特に1970年代から1980年代にかけて、女性アーティストや女性運動をテーマにした作品で注目されました。1978年には、女性運動を記録した写真集『のびやかな女たち』を発表。70年代のフェミニズムカルチャーを知るうえで重要な記録となっています。
1980年代以降は、アーティストの肖像写真を中心とした活動が顕著となり、『肖像 ニューヨークの女たち』や『ニキ・ド・サンファール』など、多くの写真集を出版しました。これらの作品では、ニューヨークやヨーロッパで活躍する女性アーティストたちの個性や生き方が鮮明に描かれています。特にフランスの造形作家ニキ・ド・サンファールとの交流は深く、彼女の自由な発想と遊び心に触発され、その後も長期間にわたりニキを撮影し続けました。2024年には松本が監督するかたちでニキを扱った映画『Viva Niki タロット・ガーデンへの道』を制作しています。
1970年代から1980年代にかけて松本はフェミニズム運動の記録を盛んに行い、当時の女性運動の様子を示す貴重な資料となっています。
106. 岩合 光昭(1950~)
岩合光昭(いわごう・みつあき)は、1950年に東京都で生まれた動物写真家です。彼の父であり、同じく動物写真家であった岩合徳光の影響を受け、幼少期から自然と動物に親しみました。19歳のとき、父の助手として訪れたガラパゴス諸島での経験が、彼の写真家としての道を決定づけるきっかけとなりました。
大学在学中から写真家として活動を始めた岩合は、1979年にアサヒグラフ誌で連載した『海からの手紙』で第5回木村伊兵衛写真賞を受賞します。この作品では、海洋生物学者レイチェル・カーソンの著作『われらをめぐる海』に触発され、自然の壮大さとその繊細な営みを写真で表現しました。その後、1982年から1984年にかけてアフリカ・タンザニアのセレンゲティ国立公園に滞在し、野生動物を撮影した写真集『おきて』を発表。この作品は英語版が世界中で15万部以上売れるベストセラーとなり、日本人として初めて『ナショナルジオグラフィック』誌の表紙を2度飾るという快挙も達成しました。
岩合の写真における独自性は、「ありのまま」を捉える姿勢にあります。人間中心の視点ではなく、動物や自然そのものの視点から世界を見ることを重視しており、この哲学は彼の全ての作品に一貫しています。特にセレンゲティでの経験から、人間が自然や動物を理解するには、その場に深く溶け込む必要があると考えるようになり、この姿勢が後年の活動にも影響を与えています。
2012年にはNHK BSプレミアムで『岩合光昭の世界ネコ歩き』が放送開始されました。この番組では猫という身近な存在を通じて、世界各地の文化や生活環境を映し出す試みがなされています。番組は猫目線で進行し、人間社会と猫との関係性や共生の形を描き、多くの視聴者から支持を得ました。この番組は猫ブームとも相まって「ネコノミクス」と呼ばれる経済効果にも寄与し、関連する写真展や書籍も人気を博しています。
また、2019年には映画『ねことじいちゃん』で監督デビューし、猫との共生や地域社会とのつながりを描きました。この作品でも彼独自の視点が活かされ、人間と猫との関係性が温かく描かれています。
107. 武田花(1951~2024)
武田花(たけだ・はな)は1951年、作家・武田泰淳と随筆家・武田百合子の長女として東京都に生まれました。幼少期から高校卒業まで立教女学院に通い、寄宿舎生活を経験しましたが、父の書斎への立ち入りが禁じられていたため、父親の職業を友人から教えられるまで知らなかったというエピソードが残っています。高校卒業後、父から贈られたカメラ(ペンタックスSV)をきっかけに写真の道へ進むことを決意します。一時は写真学校に通いましたがすぐに退学。その後、東洋大学に進学し、多様なアルバイトをしながら生活を支えました。
大学卒業後、野良猫や古い町並みを主な被写体とするモノクロ写真を撮り続け、1980年に初の写真集『猫町横丁』を刊行しました。その後も猫や町並みをテーマにした作品を発表し続け、1986年には初の写真展「猫のいた場所」を開催。翌年には写真集『猫・陽あたる場所』が出版され、広く注目されるようになります。1990年には『眠そうな町』で第15回木村伊兵衛賞を受賞します。
武田花の活動は、日本社会における「猫ブーム」の一端を担ったとも言われます。
108. 石川 真生(1953~)
石川真生(いしかわ・まお)は1953年、米軍統治下の沖縄県大宜味村に生まれました。幼少期から沖縄の複雑な社会状況に触れ、写真家としての道を歩むきっかけとなったのは、地元でのデモや衝突を目撃した高校時代の経験でした。1970年代に写真を始め、1974年にはWORKSHOP写真学校東松照明教室で学び、写真家としての基盤を築きました。
石川の作品は、沖縄という地理的・歴史的背景を軸に、人々の生活や感情を深く掘り下げるものです。特に1970年代から1980年代にかけては、米軍基地周辺で働く女性や黒人兵士との交流を通じて、沖縄が抱える社会問題を写真で記録しました。この時期の代表作としては『熱き日々 in キャンプハンセン!!』が挙げられます。石川は単なる観察者ではなく、自らもその環境に身を置き、被写体と密接な関係を築くことで、写真にリアリティと親密さを持たせています。
2011年には『FENCES, OKINAWA』でさがみはら写真賞を受賞し、その後も国内外で高い評価を受け続けています。特に2014年から取り組んでいる「大琉球写真絵巻」シリーズでは、沖縄の歴史や文化を地元住民が演じる形で再現し、それを撮影しています。
石川の作品には、常に沖縄特有の地政学的課題が影響しています。米軍基地問題や戦後復帰後も続く経済的・社会的格差など、沖縄が抱える現実を背景に、人間の尊厳やアイデンティティへの問いかけが込められています。しかし彼女自身は、自作が政治的なメッセージだけではなく、「愛」をテーマとしていると語っています。この姿勢は、「暴力では敵わないから、写真でコラーっと可愛く抗議する」という彼女独特のユーモアとも結びついています。
2021年には沖縄県立博物館・美術館で回顧展「醜くも美しい人の一生、私は人間が好きだ。」が開催されました。この展覧会では彼女の初期作品から最新作までが紹介され、多くの観客に彼女の活動が再評価される機会となりました。
109. 飯沢耕太郎(1954~)
飯沢耕太郎(いいざわ・こうたろう)は1954年、宮城県仙台市に生まれました。日本大学芸術学部写真学科を卒業後、筑波大学大学院で芸術学を研究し、博士課程を修了しました。1980年代に写真評論の活動を開始し、特に20世紀前半の日本写真史の研究で知られるようになります。その中でも『「芸術写真」とその時代』(1986年)、『写真に帰れ 光画の時代』(1988年)、『都市の視線 日本の写真 1920〜30年代』(1989年)という三部作は、日本写真史における重要な時代を深く掘り下げた作品として評価されています。
彼の活動は学術研究にとどまらず、雑誌『déjà-vu』の編集長として新進気鋭の写真家を紹介するなど、写真界に新たな流れを作り出しました。また、キヤノン主催の「写真新世紀」など、多くの公募展や写真賞の審査員としても活躍し、若手写真家の発掘と育成にも力を注いでいます。
飯沢が特に注目したのは、日本写真文化の多様性とその国際的な位置づけです。彼は東京を中心とした写真文化の発展に深く関わり、東京都写真美術館や川崎市市民ミュージアムなど、日本における写真美術館設立の流れにも影響を与えました。また、自身が運営する「めぐたま食堂」では5000冊以上の写真集を公開し、写真を身近なものにする活動にも力を入れています。
これは余談ですが、飯沢史観ともいわれますが、90年代以降の飯沢耕太郎の活躍の結果、飯沢の整理した写真史観がメディアで目立つようになり、これが批判の対象になることもあります。
ちなみに、飯沢は「きのこ文学研究家」としても知られ、『きのこ文学大全』などユニークな著書を執筆しています。
博論を書籍化したものです。
110. 上田 義彦(1957~)
上田義彦(うえだ・よしひこ)は1957年、兵庫県に生まれた写真家であり、多摩美術大学の教授としても活動しています。彼は福田匡伸氏や有田泰而氏に師事した後、1982年に独立し、広告写真やアート写真の両分野で高い評価を得てきました。東京ADC賞最高賞やニューヨークADC賞、日本写真協会作家賞など、国内外で数々の受賞歴を持ち、特にサントリーや無印良品といった企業の広告写真を通じて広く知られています。また、2011年から2018年まで自身のギャラリー「Gallery 916」を主宰し、写真展や写真集のプロデュースなどを手掛けました。
上田の作品は、自然や人間の日常に深く根ざしたテーマが特徴です。代表作には、ネイティブアメリカンの聖なる森を撮影した『QUINAULT』、舞踏家天児牛大を捉えた『AMAGATSU』、家族の日常を記録した『at Home』などがあります。『at Home』では、自身の家族を13年間撮り続けることで、「この瞬間は二度と訪れない」という切実な気づきを表現しました。このような視点は、「日常こそが奇跡である」という彼の哲学にも通じています。
写真に対する上田のアプローチは、衝動的かつ直感的な撮影スタイルに基づいています。「あっ」と思った瞬間にシャッターを切る彼の姿勢を、彼自身は、西部劇でガンマンが素早く銃を撃つ動作になぞらえ「シュート・フロム・ザ・ヒップ」と表現しています。「良い写真を撮ろう」という意識がのぼる前に撮影するそんな彼のスタイルを象徴する表現にも見えます。
また、彼は「写真は鏡」であり、撮影者自身の感情や迷いが被写体に反映されると語っています。
上田義彦はまた、映画監督としても活動しており、2021年には初監督作品『椿の庭』を発表しました。この映画では、一軒家とその庭を舞台に、人々の日常と喪失感が描かれています。
111. 三好 和義(1958~)
三好和義(みよし・よしかず)は1958年、徳島県徳島市に生まれました。幼少期、実家が営むバナナの輸入業を通じて南国の雰囲気に親しみ、これが彼の写真家としての「楽園」への関心の原点となります。小学生時代には大阪万博を訪れ、写真撮影の魅力に目覚め、中学2年生のときには沖縄を一人旅し、その景色や文化に感銘を受けたことで写真家を志すようになります。14歳で地元紙「徳島新聞」に作品が掲載され、弱冠17歳で二科展に最年少入選、翌年には銀座ニコンサロンで個展を開催し、一躍注目を集めました。
大学進学後は広告写真や雑誌撮影など幅広い分野で活躍しましたが、次第に指示通りに撮影する仕事に違和感を覚え、自らの表現を追求するため独立します。そして南国の島々を巡る旅を経て、1985年に初写真集『RAKUEN』を出版。この作品は異例のベストセラーとなり、木村伊兵衛賞を当時最年少で受賞しました。この成功が「楽園写真家」としての地位を確立する契機となります。
三好が『RAKUEN』を発表した1980年代は、海外の南国への観光は日本人にとって特別な憧れの対象であり、観光業界では急速に成長する分野の一つでした。この時期の観光事情を振り返ると、国内外での南国リゾート地への注目が高まり、観光スタイルや目的にも変化が見られました。
まず、1970年代から1980年代初頭にかけて、日本国内では宮崎県が「新婚旅行のメッカ」として人気を博し、「南国宮崎」というブランドイメージが形成されていました。これは、青島や日南海岸といった温暖な気候や美しい自然を活用した観光戦略によるもので、新婚旅行客や家族旅行客を中心に多くの人々を引きつけました。一方で、沖縄も1970年代後半から観光地としての地位を確立し始め、1980年代には航空会社による積極的なプロモーションが展開され、「リゾート」「マリン・レジャー」「青い空とビーチ」といったイメージが広く浸透しました。
国内での南国旅行が定番化していく一方で、海外旅行市場は1980年代に大きく拡大しました。1978年の成田空港開港や1985年のプラザ合意による円高進行を背景に、日本人の海外渡航者数は急増し、南国リゾート地への旅行が一般化しました。グアムやハワイ、モルディブなどが人気の渡航先となり、日本航空やデベロッパーによるリゾート施設の建設が活発化するなど、これら地域は観光業の中心地として発展していきました。
このような背景の中で発表された『RAKUEN』は、三好自身が訪れたタヒチやモルディブといった南国リゾート地を舞台に、その美しい自然を鮮やかな色彩と独自の視点で切り取った作品でした。この写真集は単なる風景写真集というよりは、「楽園」という理想郷を視覚的に表現したもので、多くの人々に強い印象を与えました。『RAKUEN』は異例のベストセラーとなり、その成功は日本国内外で南国リゾートへの関心をさらに高める契機となりました。
当時、日本人旅行者の間では「卒業旅行」や「ショッピング・ツーリスト」など多様な旅行スタイルが広がりつつありましたが、『RAKUEN』はこれらのトレンドにも影響を与えたと考えられます。三好の作品は単なる観光ガイドとしてではなく、観光地そのものへの新たな視点や価値観を提供し、人々に未知なる場所への憧れを作り出したとも言えます。
112. 長島有里枝(1973~)
長島有里枝(ながしま・ゆりえ)は、1990年代初頭に写真家としてデビューし、特に「セルフポートレイト」シリーズで注目を集めました。この作品は、長島自身とその家族が全裸で撮影されたもので、家庭内の日常を演じる一方で、裸体という極めて個人的な状態を通じて家族の役割や社会の視線を批評的に問い直すものでした。当時、女性写真家たちが「女の子写真」と呼ばれる潮流の中で語られたことに対し、長島はその枠組みに疑問を抱き続けました。
彼女の初期作品は、男性中心的な視線や価値観への挑戦として位置づけられます。例えば、当時流行していたヘアヌード写真集が女性を性的対象として消費する文脈に対し、長島の作品は「裸はただの裸」という視点を提示し、鑑賞者の固定観念を揺さぶるものでした。しかし、その意図が十分に理解されず、「若い女性のナルシシズム」といった偏見にさらされることも多くありました。
その後、長島は母親となり、子育てや家事といった現実的な課題と向き合う中で、自身の経験を通じて女性の社会的役割や不平等について考察を深めていきます。2011年には武蔵大学大学院人文科学研究科に入学し、千田有紀に師事しながらフェミニズムを学びました。この学びは彼女の作品や執筆活動にも反映され、ジェンダーや家族といったテーマをより深く掘り下げる契機となりました。
近年では、視覚障害者とのコラボレーションや祖母が遺した押し花や写真素材を用いた作品など、新たな表現方法にも挑戦しています。これらの取り組みは、「見る」という行為そのものや身体性について再考する試みでもあります。また、フェミニズム的視点から社会構造への問いかけを続ける中で、彼女自身の身体や経験が創作の重要な出発点となっています。
長島有里枝と深く関わる社会現象として、「ガーリーフォト」や第三波フェミニズムがあります。1990年代、日本では若い女性写真家たちは新たな表現を模索しながら、男性中心的な写真業界に、にわかに対抗していました。この動きは英米で広まった「ガーリーカルチャー」とも共鳴し、自分自身の視点から「女らしさ」や「若さ」を再定義する試みとして評価されています。長島はこうした潮流の中で、自身の作品が単なる「女の子写真」として消費されることへの異議申し立てを続け、その語り直しにも力を注いできました。
長島は、写真評論家の飯沢耕太郎が提唱した「女の子写真」という概念に対して、ジェンダーの視点から鋭い批判を展開しました。「女の子写真」という呼称は、1990年代に台頭した若い女性写真家たちの作品を指すものとして広まりましたが、長島はこのカテゴリー化が性差別的であり、女性写真家の表現を矮小化するものだと指摘しています。
飯沢は「女の子写真」を、「軽やかさ」「技術的未熟さ」「感覚的」といった特徴で語り、それを「男性写真家にはない魅力」として評価しましたが、長島はこれがジェンダーバイアスに基づく偏見であると批判しました。彼女は、こうした言説が若い女性写真家を「未熟で傷つきやすい存在」として男性の庇護下に置く構造を強化し、結果として女性表現者の主体性を奪うものだと論じています。
さらに、飯沢が「女の子写真」の背景として挙げた技術的要因――例えば「コンパクトカメラや携帯電話カメラの普及」が女性写真家の参入障壁を下げたという主張――についても、長島は事実誤認だと反論しました。彼女自身や多くの同世代の女性写真家が、一眼レフカメラなど高度な機材を使用していたことや、「携帯電話カメラの普及率が高まったのは1990年代後半以降」であることをデータで示し、この理論が現実に即していないことを明らかにしました。
また、飯沢が「女の子写真」を語る際に用いた「女性原理」や「男性原理」といった性二元論的な枠組みについても批判しています。このようなステレオタイプなジェンダー観は既に時代遅れであり、当時のジェンダー研究でも否定されていたものです。長島はジュディス・バトラーなどフェミニズム理論を参照し、「性差」そのものが社会的構築物であることを示しながら、「女の子写真」というカテゴリー化自体が性差別的な言説に基づいていると指摘しました。なお、こういった長島の社会構築主義的な論述のスタイルは、指導教官だった千田の影響も多分にあるように思われます。
さらに、「女の子写真」という呼称には、「僕ら」という異性愛男性視点から若い女性を消費する欲望が内包されているとし、この言説がホモソーシャルな連帯やミソジニー(女性嫌悪)を助長している点も問題視しました。特に、『スタジオ・ボイス』誌における「僕らはヒロミックスが好きだ。」というマニフェストは、その象徴的な例として挙げられています。女性写真家は、写真家である前に「女の子」として見られており、彼らの作品よりも彼ら自身が消費の対象だったというのです。
長島はこうした批判を通じて、「女の子写真」という枠組みではなく、「ガーリーフォト」という新たな概念を提唱しました。この用語には、男性中心的な視線から解放された自己規定的な「ガール」性という意味合いが込められており、第3波フェミニズムとの接続も意識されています。彼女はこの新しい視点から、自身や同時代の女性写真家たちの表現を再評価しようと試みています。
長島有里枝によるこれらの批判は、単なる写真界への異議申し立てに留まらず、日本社会全体における男性中心主義やジェンダー不平等への挑戦でもあります。「女の子写真」という言説が持つ問題点を冷静かつ徹底的に検証した彼女の取り組みは、表現者としてだけでなく、社会学的視点からも重要な意義を持っています。
113.国立国会図書館
写真は、意思や観念を表現するメディアとして、あるいは芸術としてその地位を拡大してきました。しかし、写真が持つ「記録」としての価値は揺らぐことはありません。特に、デジタルアーカイブの時代において、その記録としての機能はますます重要になっていきます。私たちが日常的にスマートフォンで撮影する何気ない風景も、加工されようとされまいと、歴史を振り返り未来を築くための重要なアーカイブとなり得るのです。
図書館、特に国会図書館で行われる写真の「アーカイブ化」の作業は、過去と未来を繋ぐ極めて写真的な行為と言えるでしょう。新しい書籍が日々納入され、その記録がデジタル化されていく中で、写真の機能が再び注目されます。これらのアーカイブは単なる記録にとどまらず、後の時代にとって重要な資料となるのです。まさに、写真が「記録」を表示することの価値が高まる時代において、写真というメディアの本来の役割が再確認されるのです。
増田彰久が語ったように、良い写真とは、まず写真の中に映る建築を魅せたあとに、写真を魅力に気づかせるような写真だとするならば、国会図書館で行われる写真行為もまた、表示される内容の素晴らしさを伝えたうえで、写真という媒体そのものの良さを際立たせる仕事をしていると言えるでしょう。
中平卓馬は、「最終的にはだれが撮ったかわからなくてもいい」(『アサヒカメラ』1969年4月号、p.231)と語り、写真が持つ匿名性と記録性について触れました。彼の言葉からも、写真が本来持つ「資料」としての価値が強調されていることがわかります。写真とは、ただの瞬間を切り取るものではなく、その瞬間を記録し、後の時代に意味を持つ資料として残るべきものだという思いが込められているのです。
ここまでに紹介した書誌はすべて写真の形式でアーカイブとして保存されています。国会図書館では日々新しい書籍が納入され、アーカイブ化する作業が続けられています。こういった過去と未来とをリレーする(記録する)という、極めて写真的な行為が日本で最も行われているのは、スタジオや路上、デモ隊の眼前などではなく、図書館の中かもしれません。
・国立国会図書館ビジョン2021-2025 -国立国会図書館のデジタルシフト-
・アーカイブ撮影の様子
🖼️
いいなと思ったら応援しよう!

