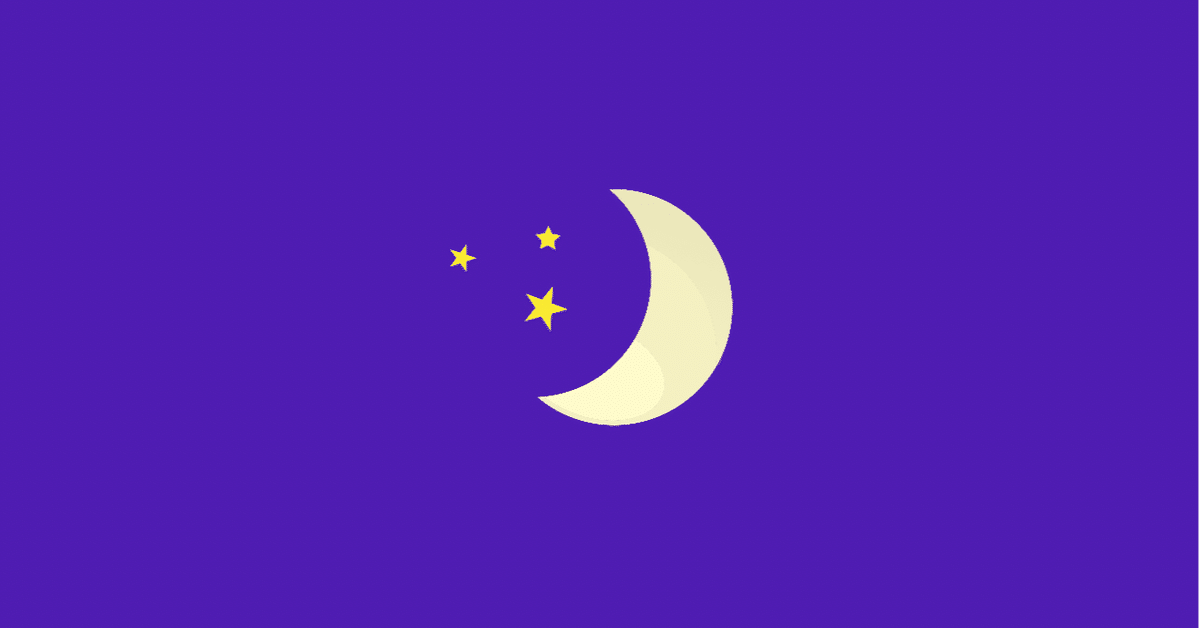
⑥まとめ 「YOASOBI」の魅力は「スキマ」にあり !| 令和の歌物語の担い手・YOASOBIの魅力 〜YOASOBI×古典文学〜
「小説を音楽にするユニット」YOASOBI
代表曲「夜に駆ける」は、ストリーミング再生回数4億回を突破。一世を風靡するアーティストだ。
そんなYOASOBIが繰り出す「小説×歌」。
古典文学でいうところの「物語×和歌」=「歌物語」というジャンルに当て嵌めて考えることができるのでは……?
1000年前から続くヒットの法則の上にいるのが
YOASOBIなんじゃないか?!
そんな仮説のもと、「古典文学と比較したYOASOBIの新しさ、面白さについて考えてみよう!」という自己満足で構成された記事を、ここにしたためていこうと思う。
1.はじめに
2.YOASOBIにおける「歌物語」性
3.平安古典文学『伊勢物語』における、歌×物語、そして「映像」への展開
4.YOASOBIがもつ「小説×音楽×映像」の奥行き
5.サブスク音楽配信サービスの時代だからこその「YOASOBI」
6.まとめ 「YOASOBI」の魅力は「スキマ」にあり !←いまここ
前回の記事はこちら💁🏻♀️
これまでの記事はこちらのマガジンから💁🏻♀️
🌙YOASOBIの魅力、解釈のスキマ🏃♀️
文学作品において「をかし」であることの条件の一つは「解釈の余地」「スキマ」がある作品である、ということだと思う。
一つの読み方しかできない、のではなく、幾つもの捉え方ができること。考える隙間があること。
「サブスクウケする」今時の音楽のカタチを踏襲したYOASOBI。
ヒットした反面、ただ音楽の表面を聴いて止まってしまう人があまりにも多いという現状があった。
古典文学作品における「歌物語」ジャンルの系譜に寄り添いながらも「映像」という第三の軸をもつ"新しさ"ーー
YOASOBIの真骨頂は、「小説×音楽×映像」。
その立体性。解釈と想起の奥行きだ。
「サブスクで手軽に聞けるから、一曲を腰を据えて聞く機会が減った」
※前記事参照
これを逆手にとれば、何度でも聞いて、何度でもそれぞれを行き来して、考察して、読みを深めることができる。読解の海を楽しむことができる。
今この時代だからこそ、私たちはYOASOBIの「隙間」に、じっくりと想いを馳せることができるのだ。
平安時代に生まれた「歌物語」の系譜にあるYOASOBIの「小説×音楽」というジャンル。
そしてそこに加わる、3つ目の軸「映像」。
意図されていないところからめちゃくちゃに行間を読んで「自分にとってのオイシイストーリー」を作り上げるのは、ヲタクの二次創作の得意技。
それは、ここまで見てきたように、1000年以上前からの得意技でもあるわけで。
ありとあらゆる想像をいろんな方向に、いろんな切り口から、広げていける素材は今、私たちの目の前にある!
サブスクの、ザッピングの時代だからこそ、立ち止まれる音楽はウケる。YOASOBIは、ここからさらに可能性を伸ばしていけることだろう。
🌙YOASOBI×古典文学 マガジン🏃♀️
---🌙🏃♀️---
春からずーーーーーーっと私の下書きにあった「YOASOBI×古典文学」、やっとまとめまで投稿し終わりました!!!
本当は「おまけ」もあるんですが、そちらは完全に腐ってしまったので、またフレッシュな記事が書けたら追加いたします🥺🙏
最近のYOASOBIだと、郵便局とコラボしてるのが激アツですよね。郵便局の前を通りかかってポスター見るたびソワソワしています。💌
UNIQLOコラボTですか?買いました。
買ったら前日譚がついてきたので読みました。
ほんとYOASOBIって最高ですね(真顔)
まぁそんな感じのテンションなので、またなにかしら書く予感。
ここまで読んでくださったかた、ありがとうございました!また古典の記事でお会いしましょう!
「さよなら」
---☕️🕊---
猪狩はな 💙@hana_so14
https://twitter.com/hana_so14

いいなと思ったら応援しよう!

