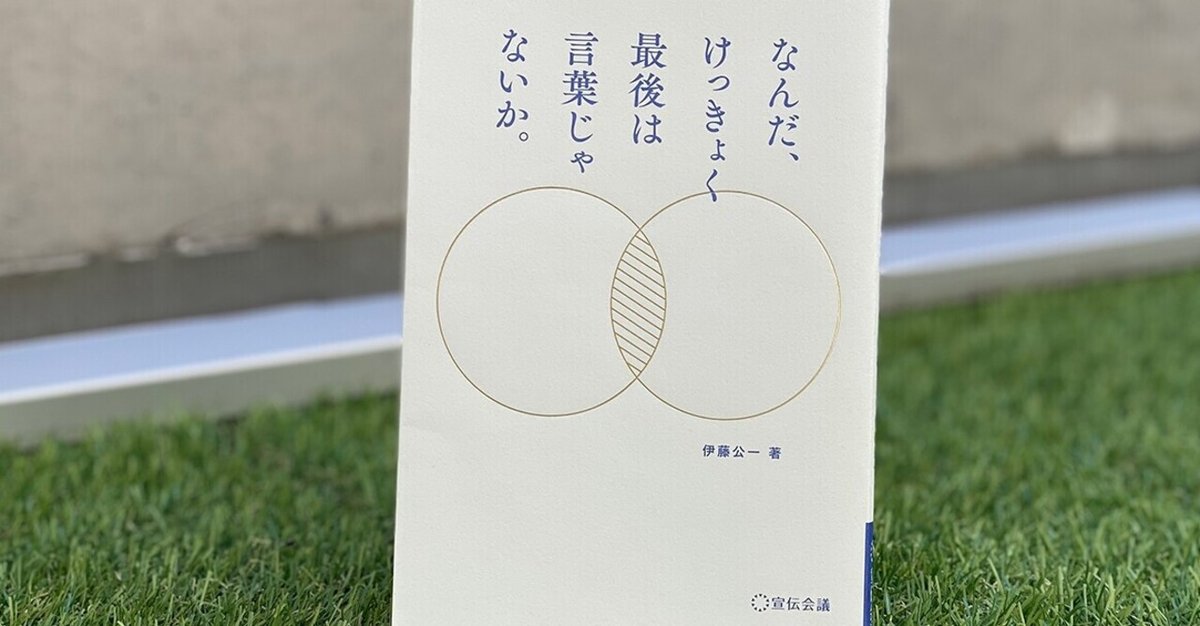
【広告本読書録:099】なんだ、けっきょく最後は言葉じゃないか。
伊藤公一 著 宣伝会議 発行
ギャップって、魅力ですよね。
あ、いや『GAP』ではなく、文字通り言葉どおりのギャップ。ほら、いかつい本職の方が雨の日に捨てられた子ネコを拾って飼いはじめる、とか。東大理3を首席で卒業した漁師、とか。銀座のママが作家として文壇デビューするとか。
語弊を恐れず言えば、すんごい高いところから低いところへ、あるいは底辺から天上界へ、みたいなジェットコースター的なストーリーに人は惹かれるんですかね。なんか、バイアスがかかるんですよね。
そして、いまここに一冊の本があります。
『なんだ、けっきょく最後は言葉じゃないか。』
品のいい色の紙に、やわらかな青の文字。高級感が嫌味なく伝わってくる特色で箔押しされたベン図。装丁全体から漂う、やさしい春風。おまけに帯には「人の心を動かすには、言葉を磨くしかないんだ。」とある。
ぼくは書店ではじめてこの本を手にしたとき(ああ、今度の広告本読書録はこれで決まりだ。きっととてもやさしい本だから、スムーズに書けそう。よかった…)とおもったのです。
しかし。
しかしであります。
この本、早くも本年度ナンバーワンの『羊の皮を被った狼本』あるいは『ツンデレブック』であることに疑いの余地なし、間違いなし。
やさしそうな顔をして、その中身。
ガチのコピーテクニック伝授本だった!
超高度、超難易度高い。いやもちろんさらっと上っ面だけなぞるように眺めれば、書いてある内容を理解することはできますよ。だけど書かれていることを実践しよう、自分のものにしよう、把握し咀嚼しようとすると話は別。生半可な気持ちで向き合うとあっという間に消化不良を起こす。
そんな問題作なのです。
え?お前の理解力、読解力が低いからだ?
それはそうかもしれませんね。まあ、でも、そうだとしてもですよ。ここに至るまで結構な冊数の広告本を読んできたわけですよ、ぼくも。
そのぼくがこれはむずかしい、かわいい顔してヤルな!とふんどしを締めなおした。なんでもかんでもやさしく、わかりやすければいいってもんじゃないのでは、とおもっていたところだったのでどストライクだった。
ぜひ、みなさんにもぜひお手にとっていただきたい。どぞ!
筆者の伊藤公一さんは電通出身のクリーティブディレクター。独立されたのは昨年ですからずいぶんと長い間、電通で活躍されていたことになります。受賞歴が多数にわたるのはもちろんのこと、Hondaの「負けるもんか」や三井ホームの「帰りたい家であること」などみんなの記憶に残るキャンペーンをたくさん手掛けておられます。
そんな重鎮が静かに、丁寧に、そして美しく語る言葉を起点とするコミュニケーションの思考法。この読書録ではぼくが特に惹かれたいくつかのテーマを紹介しつつ、全体像をなんとかつかんでお伝えしたいとおもいます。
…できるかな。難しいんだよ、ホント。
デジタル領域の言葉づくり
伊藤さんは「今、言葉はちょっと元気がない」とした上で、広告業界の大きな変化について「デジタル領域の言葉づくり」を解説しています。
テストを繰り返し最適な言葉を探していく、生まれては消えていく言葉の判断基準は、あくまで即効性、つまり短期的な売り上げです。効率的であるといえば確かにそうですが、言葉選びが即物的になってきている気がするのも事実です。
これは本当に、共感しますし、実感してもいます。いまぼくの仕事の主戦場はブランディングやインタビューなのですが、20%ぐらいはWeb広告の依頼があります。バナーやランディングページといった仕事で求められるのはまさにここに書かれている通り、即効性。すぐ売れる、すごく売れるコピーが正解という世界です。
そこには、一切の考える、あるいは感じる間を認めない息苦しさがある。ぼくはそういう仕事を広告だとおもっていません。あれは販促です。販促のコピーなら、過去に東○ストアのチラシを作っていた経験で作れる。販促のコピーならハードセルだからわかりやすさ、インパクトのみ。
広告のコピーは、そうじゃないとおもうんです。では、どういうものが広告のコピーか。伊藤さんがひとつの答えを出してくれています。デジタル広告のコピーと普通のコピーを例に出して。
売れるのはもしかすると前者かもしれませんが、どちらが発展性があるかといえば、やはり後者でしょう。その違いは、私は言葉の「余白」にあると思います。余白を持つということは、読み手に考える余地をあえて残すということです。書き手がわざと余白を作り、読み手がそれを解き明かす。この応酬が、上質なコミュニケーションのひとつの形なのではないかと思います。
ぼくは、この一文を読んで「おお、まさにそのとおりだ…」と深く納得しました。余白。けっきょく、余白。なんてタイトルのデザイン本もありますが余白を楽しむことがコミュニケーションの質を高めるという発想。非常にハラオチしたところです。
伊藤さんは「わかりやすい、ということは必ずしも褒め言葉ではないかもしれませんね」とおっしゃいます。ここのところ、ぼくが読む本の筆者はみんな口を揃えて、わかりやすいことはいいことばかりではない、と説きます。このあたり、デジタル広告=販促一本やりの広告トレンドに対する危機感から来ているものだとしたら…。
絞ることで狭くなる?
ぼくは以前、求人広告を主に手掛けていました。その前には商品広告を作っていたことがあり、その経験から「ターゲットを一人に絞り込むこと」の有効性を肌で感じていました。
しかし、求人広告の世界はターゲットは広ければ広いほどいい、と考えられていた。クライアントも、営業も、できるだけ広く、どんな人からも応募がくるように、絞り込むようなフレーズはことごとく却下され続けました。ぼくからすると、まるで地獄です。
伊藤さんはこの本で、この点について議論すべきポイントを整理しています。まず、いろいろな業種でコモディティ化が進む中、広いけど浅いコミュニケーションではモノは売れないのではないか、と。
1000人がその商品を「知っている」状況と、200人がその商品の「ファン」という状況ではどちらが売れるか。どちらがその商品にとって好ましい状況なのか。
そしてもうひとつ。一人に絞って書いたとしても、結局はかなりの人に届くはずだと考えている。その人の背後には同じ価値観の人間がたくさんいるから、たとえ一人に向けて書いてもその後ろにいる人たちにも届く、というのです。
人間は自分に向かって話しかけられないと、耳を貸さない生き物です。まして、忙しくてイライラしている現代の人たちに、浅く広い問いかけは、ほぼ届かないと考えるべきでしょう。
基本的に無関心な人たちの顔をこちらに向けるためには、まず自分に向けてメッセージが発信されているんだな、と認識させることからはじめないと、と伊藤さん。ああ、ぼくも求人広告時代にこうやって理路整然と説得することができたら…。
コピーを書くプロセス
さらに伊藤さんは「言葉を磨くなら、コピーの勉強をするといい」と、より具体的なコピー作法について踏み込んで解説してくれます。
それは①設定⇒②発見⇒③定着というもの。
まず①設定のところでは「イメージの到達点」を設定せよ、と説きます。情報が正確につたわればいいインフォメーションと違い、広告が人の心を動かすコミュニケーションである以上、企業や商品にどんなイメージを持ってもらうことがゴールなのか、をあらかじめきちんとセットしておこう、というのです。
伊藤さんはここで、イメージの重要性をあらためて語ります。イメージの反対語は(正確ではありませんが意味合いとして)ファクト。そしてビジネスパーソンの大好物もまた、ファクトです。その傾向はここ数年でマシマシになってきているとぼくはかんじています。
しかし、考えてみると、どんなに事実をベースにした広告を作っても生活者に伝わるのは、この広告は事実を伝えようとしている感じがするなというイメージでしかありません。たとえば、企業の実際の研究者が出てきて、その会社の最新の研究の成果をアピールする広告があったとしても、伝わるのはどこまでいっても「ああ、この会社は進んだ技術があるんだな」というイメージです。
ぼくはこのくだりを読んだとき、目から火花が飛び出るかってぐらいガーン!と衝撃をくらいました。と、いうのも過去の仕事でいつも喧嘩になっていたのはファクト対イメージだったからです。
そしていつもイメージ派のぼくは負けを喫していました。ファクト勢に押し切られていたんです。でも伊藤さんのこの解説があれば、ファクト派がいかに結局イメージしか伝えられないかをわからせることができた。
そんなイメージしか伝わらないなら、こっちのイメージのほうがよりグッドじゃないですか?と説得できたと思うと。ああ、惜しい。
続いて②発見です。設定したイメージをどうやって獲得するか、そのための道筋を見つけることを説明しています。伊藤さんいわく文脈の発見です。ここちょっと難しいです。
ターゲットをこんな気持ちにさせようとイメージの到達点を設定したら、その目標に向かってコピーを書いていけばいいのですが、いったい何を書いたらそれが実現できるのか、その文脈を発見するプロセスが必要です。
ぼくは自分の頭の悪さを呪います。いったい何が書いてあるのか、さっぱり理解できないんですから。どういうことなんだ?とおもいながら読み進めていくと、なんとなく、おぼろげながら、わかったような気がします。
ぼくなりの解釈ですが、おそらく最初に設定したイメージを獲得するためにはどういうことをするのがベターなのかを考えることなのでは?
それはビジュアルトーンやタイポグラフィ、映像の雰囲気、言葉の強弱といったことから、もしかしたらイベントや社会活動といったアクティベーションまで含まれるかもしれません。
しかしそうした一切合財を設計することが、最初に設定したイメージを獲得するために不可欠である、ということなんじゃないだろうか。あってるかどうかはなはだ自信がありませんが、一応そういうことだと結論づけました。
ほら。難しいでしょ?
そして最後は③定着です。伊藤さんは言葉にするとき、レトリックよりも単語の精度をあげよう、と教えてくれます。たとえば「旅と旅行」「父と父親」「生活」と「暮らす」の違いにこだわり、適切に使い分けられるか。
ここがアバウトだとイメージの到達点にきっちりたどり着くことが難しくなる、と伊藤さんは語ります。
ここまで来て、ようやくコピーを書くことになります。このプロセスをきちんと踏めば、おそらくコピーは書けるようになるでしょう。しかし、言うは易し。会得するのは簡単ではありません。
さらに最後の最後にチェックすべきこととして
それはプロセス①で設定したイメージに、ちゃんとこのコピーは読み手を連れていってくれるものになっているかどうかのチェックです。到達できていれば、あとは自信を持ってプレゼンするばかりです。
さらっと書かれていますが、いやいや、そのチェックもできるようになるまでは修業が必要です。なぜなら、判断するためにはそれを支える知識と経験が必要だからです。ね、難しいでしょう?
イメージの設定とコピーの人格
そんな落ち込むぼくをはげますかのように、伊藤さんはイメージの到達点にたどり着くための近道として「コピーに人格を持たせる」ことを推奨します。いくつかご紹介します。
【知的で大人なコピー】
例:恋は、遠い日の花火ではない。
感情⇒納得と憧憬
【胸ぐらをつかむコピー】
例:拳骨で読め。乳房で読め。
感情⇒覚醒と成長
【威風堂々としたコピー】
例:地図に残る仕事。
感情⇒賛同と尊敬
他にも「優しいコピー」「いいやつなコピー」などいくつかのコピーの人格を紹介。同時にそのコピーにふれることで湧き上がる感情がどんなものかについても解説してくれています。
そして、いよいよコピーライティングの技術へ、となるのですが、名作コピーを取り上げて、そのメソッドを簡潔にひもといています。いわく「異物との結合」いわく「元素分解してみる」いわく「誰かになって書いてみる」いわく「逆を言う」などなど…。
いずれもかなり具体的にコピーメソッドが書かれているのですが、総じて言っていることのレベルが高いです。即戦力になる。おそらくですが、若き頃にこの本を手にしたならば、まずまちがいなくこの『コピーライティングの技術』の章から読み始めたことでしょう。
だから、だめだったんだ、といまになってわかります。
やっぱり、それじゃだめで、技術に至るまでの考え方、プロセス、視点、思いといったものがしっかりと根を張っていないと、どれだけ技術をまとったとしてもパンチが軽い、あるいは真芯を捉えられない。
この本は、その難しさゆえに、コピー技術の前の段階が何より大切なのだ。コピー上達に近道はない(あれ?渡辺潤平さんと同じ?)ということを身を以て知ることのできる一冊なのです。
