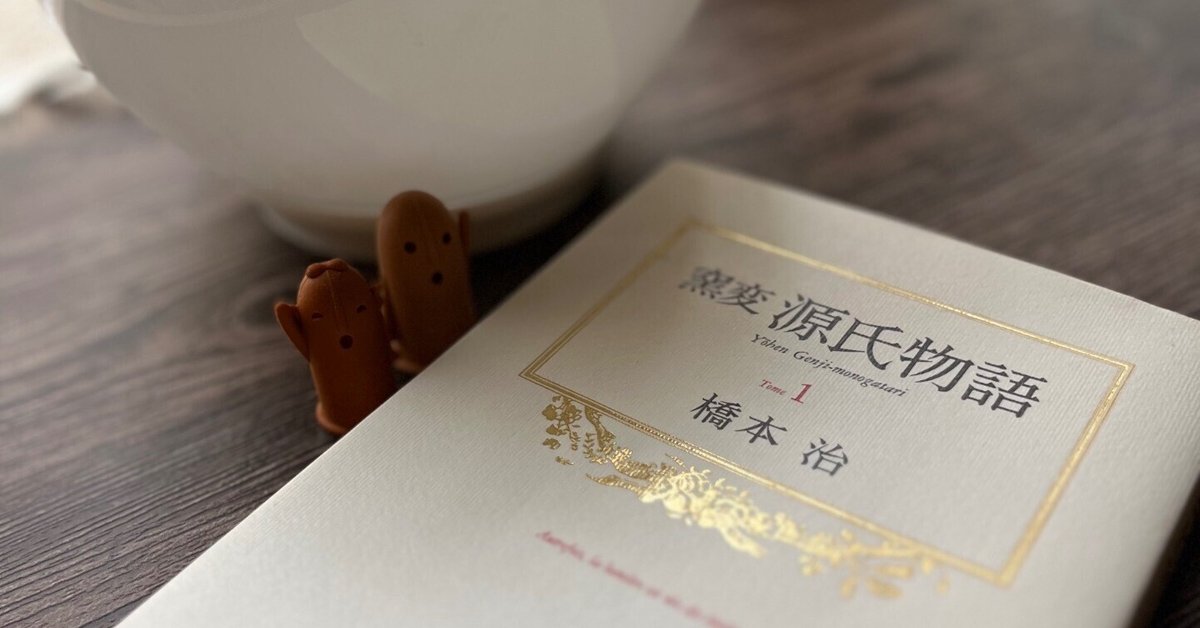
橋本治「窯変源氏物語」と「おおくぼ源氏」① 桐壺 帚木 空蝉
「窯変源氏物語」の中に挿入される、おおくぼひさこの写真を語ります
私の初めての源氏物語は田辺聖子の「新源氏物語」だった。
田辺聖子の書く光源氏は心優しく、ひたむきで若々しい青年だったように思う。
私はまだ十代だったけど、田辺聖子は女の子の望む光源氏を見せてくれた。
その後は円地文子、瀬戸内寂聴、大和和紀の源氏物語を薄目でつまみ読みしたくらいだったが、光源氏に本気で恋をしてしまったのは何といっても橋本治の「窯変源氏物語」だった。
私はもうその頃は大人になっていて子供もいるような歳になっていたが、図書館で初めてこの本を見つけて読んだ時、本当に音がしたのだ。
ドキューン!って。
血まみれになって図書館の床の上に倒れ込んだ私は(ウソです)、薄れゆく意識の中で
「これ何巻あんの?14巻?
マジか。全巻揃えたら一体いくらかかるねん…。」
そんなことを思いながらこと切れた。(だからウソですってば)
「窯変源氏物語」は後半の宇治十帖を除いて全て光源氏のモノローグで語られる。
自身の美しさを隠そうともしない傲慢な若い源氏も、辺境の地で落ちぶれた失意の源氏も、重い身分となり分別盛りの源氏も、若い妻の不義に怒り狂うほぼ老害の源氏も、みんな魅力的ではあるが、それと同じくらいヤなヤツなのだ。
天皇の息子という高貴な生まれを鼻にかけるようなお人好しでは決してない。
それに、全巻を通して溢れ漂うそこはかとないミソジニーのかほり。
光源氏の死後、作者紫式部のモノローグに代わった宇治十帖においてもそれは変わらない。
歌舞伎の「色悪」にキャーッってなるマダムの気持ちって、こんなんなんかなって思う。
窯変源氏と色悪はちょっと違うだろうけど。
「窯変源氏物語」の中でもうひとつ私をシビれさせたのは一帖ごとに挿入される、おおくぼひさこの写真だった。
これがもう素晴らしくて、「窯変源氏物語写真集」としても出版されたが、どの写真にもいちいち身悶えしながら見入ったものだった。
ぜひこれらの写真も一緒に投稿したかったが、なんだかヤバそうなので文章で紹介いたします。
怒られるのイヤだもん。
「桐壺(きりつぼ)」
「いずれのおん時にか、女御更衣あまたさぶらいたまひける中に…」と始まる源氏物語の第一章。
光源氏の母である桐壺の更衣は、「更衣」というさほど高くもない身分でありながら帝の寵を得、
そのことで後宮の女達に妬まれて虐め抜かれたあげく、光源氏を産み落としこの世を去る。
ここに挿入される写真がスゴい。
二歳ぐらいの幼児を中央に座らせてその背後には、成熟した女の裸のマネキンが5体ずらりと並ぶ。このマネキンは多分後宮の女達なのだろう。
彼女たちはウィッグもつけない丸坊主で、全員頭から黒いベールを被らされており、ベール越しのその顔はどれも無表情という、何とも寒々とした写真なのだ。
後宮にいる女達というのは当時の貴族階級の男達にとって、朝廷での立身のために使われる大事なコマだった。
男達は野心をもって帝に娘を献上し、帝の胤を産ませ次の帝の外祖父となって朝廷に君臨するために自分の娘にかしずき、美しく飾り立て華々しく入内させる。
写真の中のマネキンたちのうつろな表情は、そうしてされるがままに後宮に連れてこられた女達の、豪華な衣装の中身なのかも知れない。
しかもそこには妬み嫉みといった黒いベールが降り注がれ、マネキンたち全員の足元に澱となってわだかまり、光源氏と思しき幼児までも飲み込もうとしている。
「窯変源氏物語」に挿入される、おおくぼひさこの写真はすべてこんなふうに、一帖一帖の物語の中にあるテーマを意味深に、時には残酷に、しかも美しく描き出す。
十二単の写真なんて一枚もないのに、平安時代とはどういう時代だったのか、源氏物語とは本当はどういう物語なのか。
それを問う場所へ否応なく引き摺り込まれてしまう仕掛けがそこにはある。
「帚木(ははきぎ)」
有名な「雨夜の品定め」と呼ばれる章だ。
登場人物は光源氏と頭の中将、それに左馬頭と藤式部丞。
宮中の宿直所(とのいどころ)で、雨に降りこまれヒマを持て余した男達が源氏の部屋へやって来て長々と女性談義を始める。
高貴の女ってのは気位ばっかり高くってめんどくせえんスよねー、とか
受領階級の「中の品」くらいの女ってのも捨てたもんじゃありませんぜー、とか
案外ああいう所に掘り出し物ってあるんスよねー、とか源氏を囲んで好き勝手な女性観を、自分の体験を交えて熱心に語り合う。
源氏は基本的にムッツリスケベさんだから、いかにも興味なさげに三人の話しを聞いている。
紫式部って、当時のこういう男達の話しを実際に聞いていたんだろうか。
妙に現実味があるのだ。
宮中で立ち働く紫式部のような女房たちは、当時の貴族の男達にとって物の数には入っていない。
男達のそばに侍りながら、そこにはいないものとして扱われ勝手な女性談義を聞かされて、紫式部は、きっとすごい冷たい目で彼らを見ていたんだろうな。
「源氏物語」や「枕草子」といった女房文学は今で言えば少女まんがだ。
かな文字で書かれた文章など大の男が読むものではなかった。
だからこそ紫式部はこういうこともへーきで物語にも書いたのだろうけど、こういうものをこっそり読む男だってきっといただろう。
絶対、「紫式部怖ぇ〜っ」ってなったと思う。
この章に挿入される写真も面白い。
大きな机を囲んで五人の男性が向かい合って座っている。
中央奥にひとり、両脇に二人ずつ四人。
手前には誰もいないので、そこに座を占めて自分もそのグループの一員になろうと思えばなれる構図だ。
全員、偉そうに組んだ足を机の上にいっせいに投げ出している。
ただ両脇四人の体は写真から見切れていて、投げ出した足の先しか写っていない。
どの足も高そうな靴を履き、お洒落な靴下を覗かせている。
中央の人物だけがこちらと向かい合っているので体は見えるが、なぜか帽子を深く被り、さらに煙草を挟んだ指で強くそれを押さえているのでその顔はわからない。
男達の密談といった雰囲気がないでもないが不思議な写真だ。
中央で顔を隠している男が多分光源氏だろう。
机の上にはタイプライター、本や手帳、裏面を見せて立つフォトスタンド、数枚の書類が適度に散乱している。
背後には大きなキャビネット、ポールハンガーに架けられた帽子、コート。
これらひとつひとつに「雨夜の品定め」のメタファーを感じさせる。
「帚木」には、頭の中将が面白半分で源氏の厨子を漁り女との書簡を探す場面があるが、背後の大きなキャビネットはもちろんこの厨子なのだろう。
「空蝉(うつせみ)」
雨夜の品定めで、受領階級の女ってわりといいっスよーと好きものの男達に教えられた光源氏は、そういう「中の品」に出会える機会を伺っていた。
そんな折、「かた塞がり」で妻のいる左大臣邸から追い出されるハメになった光源氏は、紀伊の守の屋敷に「かたたがえ」することになる。
瀟洒な邸宅に賓客として迎え入れられた源氏は、なんとそこで紀伊の守の父、伊予の介の若い後妻をてごめにする。
「ご存知ないかも知れませんが、ずっとあなたの事をお慕い申していたのでございますよ。」
とかなんとか言ってるけど、レイプですからね、それ。
この後妻を気に入った源氏はその後も何度も彼女に手紙を送るが、いくら待っても返事は来ない。
剛を煮やした源氏は、彼女の幼い弟をたぶらかし手引きをさせて紀伊の守の屋敷に忍びこむ。
そこで物陰から、取り繕わない素の女達の実態を興味深々で覗き見する。
まったく、何やってんだかこの人は。
夜更けて女の寝所へ潜り込み、思いを遂げようとするも気取られて夏物の薄衣一枚を残して逃げられる。
取り残された源氏は、事の成り行きで伊予の介の娘のほうと契ってしまう。
「ご存じなかったかも知れませんが…」の例のアレだ。
自分を拒む女がこの世にはいるのだという事を生まれて初めて知った源氏は、彼女が源氏から逃げるために脱ぎ捨てていった薄衣を持ち帰り、悔しいやら切ないやら。
この章に挿入される写真はステキだ。
豪華にラッピングされリボンで飾られた花束が、寝乱れた後のようなサテンの上にそっと横たえられている。
ただし、この花束には花だけが無い。
ラッピングとリボンだけ。
「空蝉」。
セミの抜け殻なのだ。
「窯変源氏物語」の中には、こういったビジュアルだけでそれがどの章であるのかを、凄い審美眼で示す写真が一帖ごとに収められている。
他にもすごい写真がたくさんあるが、今回はとりあえずこれにて。
ここまで読んでくださって本当にありがとうございます。
