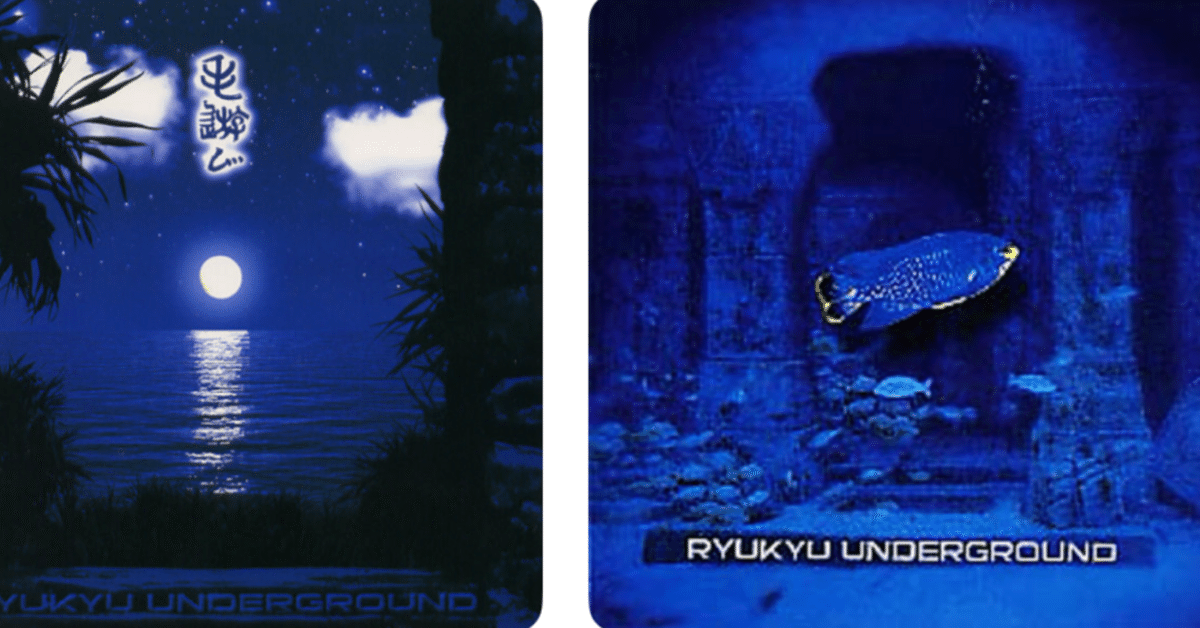
沖縄民謡とブレイクビーツの融合が織りなす魅惑の「沖縄バレアリック」。琉球アンダーグラウンドの知名度の低さに一石を投じたい。
琉球アンダーグラウンドについてまず思うのは、ほんのちょっだけ後のタイミングでデビューしたRYUKYUDISKOに座席を奪い取られてしまったなぁ、という印象である。
RYUKYUDISKOの音楽性がよりキャッチーだったのでしょうがなかったと理解できる反面、琉球アンダーグラウンドの知名度がその魅力に反してあまりに低い現状に一石を投じるべく、ぜひここで紹介しておきたい。
琉球アンダーグラウンドは、イギリス出身のキース・ゴードンとカリフォルニア出身のジョン・テイラーによって、沖縄にて結成された二人組のエレクトロユニットである。「琉球」と冠したユニット名のとおり「沖縄民謡 meets クラブミュージック」がコンセプトである。
イギリスのニューカッスルで生まれたキース・ゴードンは、マンチェスターでDJとして過ごした後、デンマークに移住しリミキサーとしても活動。アジア・オセアニア各国を放浪し、オーストラリア在住時にりんけんバンドの音楽と出会い沖縄民謡に魅了される。その後大阪に移住し、喜納昌吉やネーネーズのライブに足繁く通うようになる。
片やジョン・テイラーは、レコードショップのワールドミュージック担当バイヤーとして働いていた時に沖縄民謡と出会う。と同時にジョンはU-Royの全米ツアーに同行した経歴を持つギタリストでもあった。
1998年、沖縄に旅行中だったキースと、大学の博士課程のフィールドワークで沖縄に来ていたジョンが出会い「沖縄民謡ガチ勢の西洋人同士」として意気投合。二人でエレクトロユニット「琉球アンダーグラウンド」を結成し、楽曲制作をはじめる。
3年という長い制作期間を経て発表されたセルフタイトルのデビューアルバム『琉球アンダーグラウンド(2002)』ではサンプリングベースで、続く2ndアルバム『毛遊び(2003)』では金城実、よなは徹、内里美香といった現役の唄い手をゲストに迎え、沖縄民謡とクラブサウンドを見事に融合させたサウンドを世にドロップ。「レコード番長」こと須永辰緒にも絶賛される完成度で話題となる。その後もキッド・ロコ、ジャンキーXL、ビル・ラズウェルといった錚々たるクリエイターが参加したリミックスアルバム『Ryukyu Remixed(2004)』など話題作を挟みながら、2000年代は精力的なリリースを続けた。
Soi Soi(2002)/ 琉球アンダーグラウンド
Tinsagu nu Hana Dub(2002)/ 琉球アンダーグラウンド
Kokusai dori Dub(2002)/ 琉球アンダーグラウンド
花 extended mix(2003)/ 琉球アンダーグラウンド
毛遊び(2003)/ 琉球アンダーグラウンド
恋尽ぬ花(2003)/ 琉球アンダーグラウンド
琉球アンダーグラウンドの音楽は、クラブミュージックに三線の音色を申し訳程度にまぶしてみました、みたいな薄っぺらいミクスチャーではなく、元ネタおよびゲスト奏者や唄い手へのリスペクトに溢れる、唯一無二の「沖縄バレアリックサウンド」に仕上がっている。沖縄民謡をクラブミュージックの引き立て役として扱っているのではなく、引き立て役の側になっているのはむしろキースとジョン両名の十八番であるブレイクビーツやダブの方である。音楽だけでなく沖縄の歴史や人々、文化に対する両名の深い洞察と理解をひしひしと感じる。事実、キースは今も沖縄に住んでいる(はず)。
反面、実際のビートの音自体はぶっとくて聴き応えがある。とりわけダブと沖縄民謡との相性は抜群で、ディレイとリバーブが効いた三線の音色や高音域の歌声は、陽炎で揺らめく沖縄の原風景を映像喚起させてくれる。目を閉じながらのリラックスタイムにも、身体を揺らしながのパーティタイムにも、双方にお誂え向きの申し分ないバランスで、あらゆる意味で上辺じゃ出せない深度のサウンドスケープである。
しかしながら、2009年に4thアルバム『ウムイ』を発表後、2025年現在まで新作の発表を含む目立った活動が無くなっているのが寂しい。
ジョンがロサンゼルスで地理学教授の職を得ており、メンバー二人の間に物理的な距離がある、という本人達側の事情も大いにあるっぽいのだが、確かに当時、私自身が「俺しか聴いてない」感を如実に感じるほど、セールスや話題性と言う意味で琉球アンダーグラウンドが好事家向けのニッチなフィールドに甘んじていた印象は強い。
RYUKYUDISKOのアルバムが石野卓球主宰のPlatikおよびキューンレコードからのリリースだったのに対して、琉球アンダーグラウンドのアルバムはハワイアンや純邦楽などワールドミュージックを専門に扱うリスペクトレコードからのリリースだったために、レコード屋の多くが琉球アンダーグラウンドのCDを「ワールドミュージックの棚に」置いていたことも、多くの人が彼らの音楽にアクセスしづらかった大きな一因だと思う。ワールドミュージックコーナーは大半のレコード屋で陸の孤島のような辺境に追いやられているのでけっこう敷居が高いのである。
ケルト音楽のCDを物色していた上品な老紳士の横で、場違いな気持ちでソワソワしながら琉球アンダーグラウンドのCDを探していた19歳の私。そんな思いをしなくても、配信サービス上でアーティスト名を打ち込めば目の前にアルバムが出てくるようになった2020年代のまさに今こそ、あらゆる音楽サブスクで「琉球アンダーグラウンド」と検索してみてほしい。
窓の外は雪が降り積もっていますが、琉球アンダーグラウンドの音楽で一足先の夏を、沖縄を感じてみてください。
またやーさい。
