
ル・クレジオ『ブルターニュの歌』
存命のフランス人作家では世界的に最も高名な作家のひとり、ル・クレジオ。1963年の『調書』で華々しいデビューを飾り、硬質な詩的散文で一世を風靡しましたが、やがて父祖の地モーリシャスやアフリカ、世界各地を舞台にした文化人類学の視点を持つ作風に移ります。2008年ノーベル文学賞受賞。

Wikipediaより
世界各地を放浪するように書き続けてきた彼も80代に。2020年、ついに自分の幼少期をテーマにした作品が出たということで邦訳を読んでみました。結局歳をとると幼少期の事を回想したくなるのでしょうか。
内容
フランスにも各地に豊かな個性と文化がありますが、北西部のブルターニュ地方はケルト人たちの領域で、ブルトン語というフランス語とは全く異なる言語を話す民族がずっと住んでいます。
ル・クレジオは先祖がブルトン人で、夏のたびに家族でブルターニュに訪れていました。その回顧と現代の対比がメインです。ブルターニュ文化については下記に↓
現代のブルターニュ地方はブルトン語などどこからも聞こえてこない、栄えていた漁村もただの倉庫街に変わり、詩情も文化もあったものではないという論調で綴られており、2017年の『アルマ』などでも書かれてきた、故郷喪失者を超えて「故郷滅亡者」となった人の唸りがあります。
昔と今では変わってしまった、ではなく、本質から全て絶えてしまった文化への悲壮です。
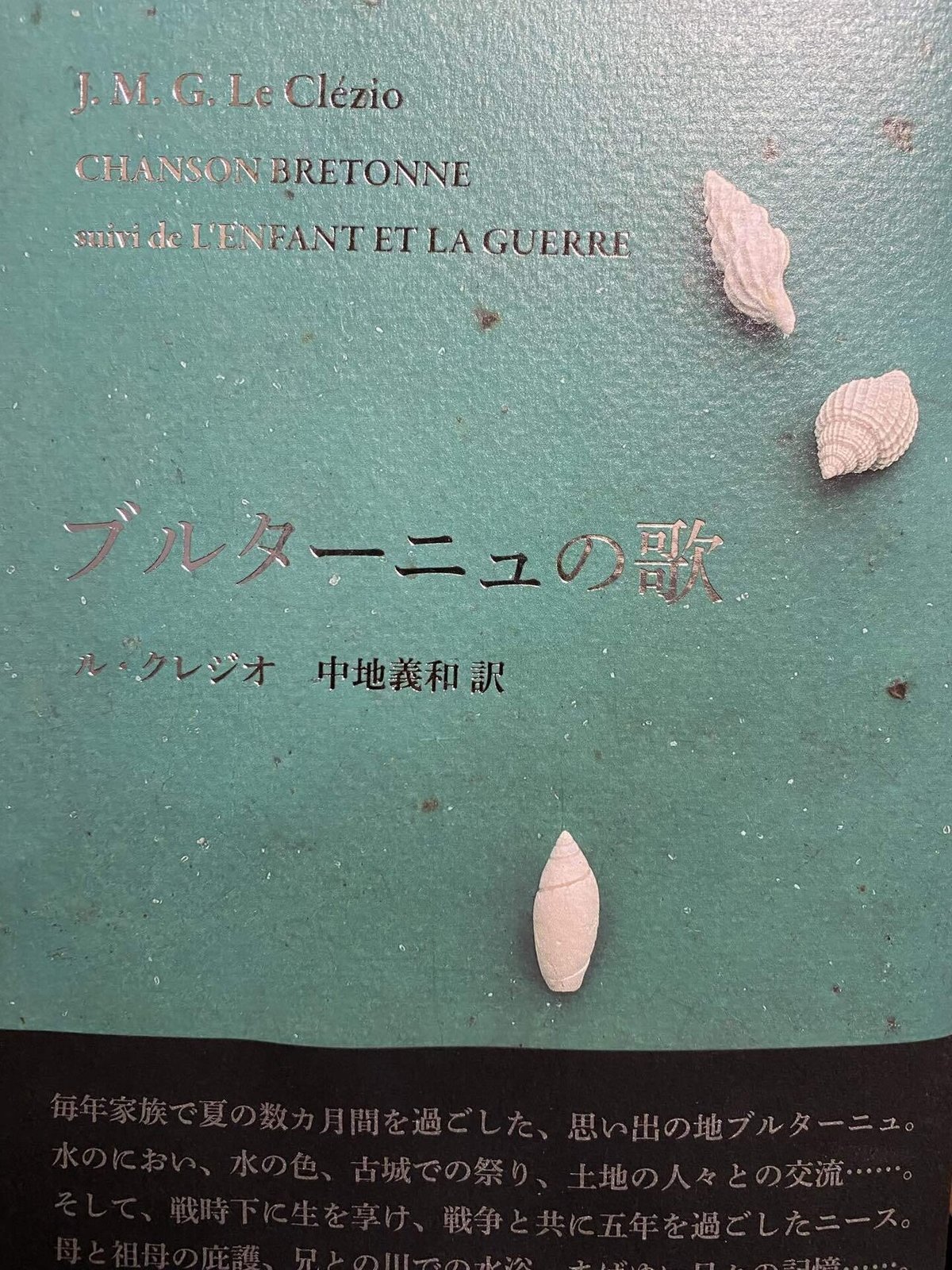
とはいえ著者は、郷愁に浸るということを断固拒否しています。長年の文明評論家としての立場がそうさせるのでしょうが、ありきたりな回想録に堕ちることを断固拒否しています。
郷愁は名誉ある感情ではない。一つの弱さ、苦渋を分泌する痙攣にすぎない。この不能は現に在るものを見えなくする。現在こそが唯一の真実なのに、過去へと意識を向けるのだ。
この強靭な態度を貫くためか、何度も上の引用のようなニュアンスの言葉を書き連ねています。具体的な地理や植生、風習などを精密に書き込むことで郷愁のポエジーから離れようとしているのは明らかですし、批判精神はストレートに伝わってきます。全体において冷静という言葉が適切なように思います。
また『ル・クレジオ 文学と映画を語る』という作家の講演録も近年出版されていますが、そこでも郷愁(ノスタルジー)に頼ることを批難していて、現代の作家はどこまでも現代を主に置くべきと主張しています。
しかし、その宣言や態度が本作ではどこかぶれています。徹底されていません。現代のブルターニュの清潔さや便利さを褒めるくらいが現代についての描写で、概ね昔はよかったという話です。
ル・クレジオの作品をあまり知らない読者が素朴に読めば、明らかに老作家の回想録と受け取るしかないものです。私も氏の思いとは裏腹に、ジャンルとしての回想録になってしまっていると思いました。
文章と内容から郷愁を排除し、過去の美化を避けたからといって、主題そのものがノスタルジーであることの限界が漂っています。
もし郷愁を避け、単なる回想録になってしまうのを拒むなら、例えばサルトルの『言葉』のように、自分の幼少期を基にしたフィクションとして提示することもできたのですが。
いずれにせよ氏が断固拒否しようとした郷愁の文学になっていたのは否めませんし、反-自伝とは呼べない、もしくは失敗しています。
そのあたりを無視すれば、幼少期をたどる作家の回想録としては最高峰のものだと私は思いました。
附属の『子供と戦争』が傑作
第二次世界大戦中フランスは降伏し、ニースはイタリア軍が占領することになりました。ニースに疎開していた幼いル・クレジオ少年とその一家はイタリアの緩い占領政策の中で生きていたのですが、ナチス・ドイツの占領に変わり、英国籍でもあった一家は敵性国民として、強制収容所に入れられる危機に一変します。その時の苦難からアフリカにいる父の元へ逃げるまでの日々の回想です
戦時中に生まれた者は真に子どもでいることができません。「子どもと戦争」という無数に著されてきたテーマにおいて、抑圧の悲劇が醸す悲しみやカタルシスを排し、分析に徹する眼差しと文章は、郷愁を排そうとしたものの成功しているとは言えない『ブルターニュの歌』よりもこちらで発揮されています。
戦争の終わり、それは子供には何の意味もない。子供は〈歴史〉の中で生きているわけではない。子供はいろいろなできごと、作り話、すばやく捉えた他人の言葉、目覚めたまま見た夢しか知らない。
事実→それに対する内省という構図できっちり進んでいく安定感に支えられた、空爆や逮捕への恐怖の表現は、昔の回想ということで距離ができたことによる鎮静の賜物、沈殿の成熟であるように思います。
本作の魅力
フランス文学といえばどうしてもパリとその周辺のお話ですが、こちらは北西部ブルターニュと南仏ニースです。幼少期の思い出とともにフランスの地方性を強烈に閉じ込めた小品になっており、多くの日本人にとっては未知の世界が提示されています。そこには植民地主義の態度は外国だけでなく国内にも向かうという、大きな主題が背景にあるように思いました。
ただそのエキゾティズムこそが本書の特別な魅力になっています。ブルトン語のルビなどが出てきますし、意識にあまり上らないフランスの地方を取り上げた時点で醸し出される強烈な個性が、非フランス人読者を驚かせます。
また表現が端正です。訳者の中地氏の才も大きく寄与していますが、文字通り味読できる文学作品となっています。わら束を使った古民家の表現として、
ここブルターニュでは、ドレが挿絵を添えたペローの童話から出てきたように、古い時代のほとんど魔法のような魅力を醸し出していた。「貧しさ」という語は当たるまい、時間の流れから取り残され、現代世界から忘れられた場所という感じがした。そう、一枚のデッサンのなかに入ったような。
回想などいくらでも誇張したり飛躍しがちなジャンルですが、終始この調子で書かれており端正です。抑制され引き締まっています。そしてこのほどよい緊張の中にル・クレジオの本分である文明批評のまなざしが多分に潜んでおり、凝縮度が極めて高いものでした。長編のフィクションではこうはいきません。
そして『ブルターニュの歌』と『子どもと戦争』の二作は片方が欠けると前者は回想録、後者は批評というそれだけのものになってしまったでしょう。二作が支え合い、反響しあい、文学としてより豊かになっています。見事としかいえません。
本人が力説する「郷愁の排除」は達成されているかと言えば首を傾げます。ただその枠組みを外して読めば、豊かな文化や多くの箴言と巡り合える傑作であると思います。
ル・クレジオの愛読者なら好き嫌いは分かれても、長旅の終わりのような芳醇な余韻を感じることでしょう。
・
ここから先は
¥ 300
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
