
真釈 般若心経/宮坂宥洪【読書ノート】
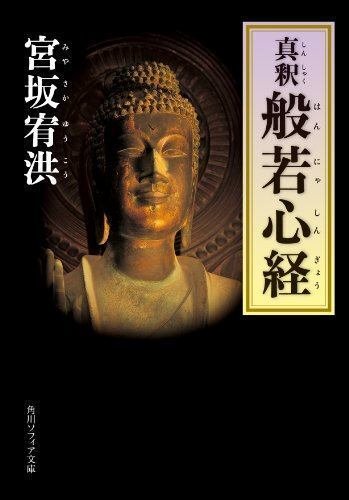
『般若心経』とは、心の内面の問題を解いたものではなく、具体的な修行方法が説かれたものだった!経典成立当時の古代インドの言語、サンスクリット語研究が導き出した新解釈で、経典の真実を明らかにする。
【漢訳本文】
【読み下し】
【原典和訳】
第一章:マントラを説いた経典
マントラという祈りの言葉
真実 の 言葉、 真言
マントラを説いた『般若心経』
『般若心経』の生い立ち
『般若心経』の伝来と漢訳
『般若心経』の説明に入る前に、この経典の生い立ちをふり返ってみますと、この経典は中国の明代の小説 『西遊記』で有名な唐の三蔵法師玄奘 (602~664)がインドからサンスクリット原典を持ち帰って漢訳したものです。
訳出したのは唐の貞観二十三年(六四九)五月と伝えられていますから、今から千三百五十年以上も昔のことです。
玄奘より二百五十年近く前に、 姚秦の鳩摩羅什 (三五〇~四〇九頃、以下「羅什」と略称)が別の題名 (『摩訶般若波羅蜜大明呪経』)で訳出し、それよりさらに二百年前に三国呉の訳経家の支謙が訳し、これは題名(『摩訶般若波羅蜜呪経』)だけが伝えられています。
こうした点から、『般若心経』の原型はインドにおいて三世紀頃には成立していたであろうと推測されます。
玄奘以降にも漢訳されたものが五本残っていますが、一般に『般若心経』といえば玄奘訳をさします。中国でも古くから 『般若心経』の注釈がたびたびなされてきましたが、どれも玄奘訳に対するものばかりです。それほど玄奘の漢訳は権威あるものとして重んじられ、現代に到るまで親しまれてきました。
わが国に伝わった時期は定かではありませんが、入唐して玄奘に師事し、六六〇年(斉明天皇六年)に帰国した道昭(六二九〜七○○)が持ち帰った可能性が高いと思います。天平年間(七二九〜七四九)から研究や写経が非常に盛んに行われるようになりました。
日本仏教の全宗派に共通する経典というのは実は存在しません。 それでも、一応すべての僧侶が知っている経典というと、たぶん『般若心経』しかないでしょう。 『般若心経』ほど僧俗を問わず広範囲にわたって尊ばれてきた経典はありません。
『般若心経』のタイトルは原典になかった?
「般若波羅蜜多心」とはどんな意味か
『般若心経』の「小本」と「大本」
『般若心経』は一幕もののドラマ
観自在菩薩の登場と全体の構成
観自在菩薩が行った深遠な般若波羅蜜多の修行とは、一体どんな修行だったのか。これを明確にしておきましょう。それは「掲諦、掲諦……」のマントラを誦えることなのです。
マントラを静かに、あるいは心の中で何度も繰り返して誦える修行を念誦法(サンスクリットで「ジャパ」)といいます。その結果が、「五蘊は皆空なりと照見して、一切の苦厄を度せり」ということなのです。
このあと観自在菩薩が舎利子の質問に答えるかたちで、「舎利子よ」と語りかけ、「五蘊皆空」の説明が始まります。「色不異空」に始まり、「無智、亦無得」までの段落が、その具体的な内容です。 なぜそのような素晴らしい成果が得られるかというと、これが「般若波羅蜜多」と称するマントラを念誦する修行だというのです。三世の諸仏も同じようにして最高のさとりを得ているのだとして、「故知(ゆえに知るべし!)」と続きます。
「心」とは「マントラ」のこと
では、そのマントラはどういうものか、お教えいたしましょうと観自在菩薩が言い、最後に「掲諦、掲諦……」の句が示されるのです。
その直後に尾題が添えられています。玄奘訳では、「般若波羅蜜多心経」となっていますが、原典では「以上で、プラジュニャー・パーラミター・フリダヤ(般若波羅蜜多のマントラ)、提示し終わる」となっていて、先に述べたように「経」にあたる語はありません。ですから、これを「尾題(びだい)」と言っていますが、それはしいてタイトルを探せばこれが相当するということでして、私はこれも本文の一部と考えてよいのではないかと思っています。
つまり、この「尾題」は『般若心経』全体のタイトルなのではなく、「掲諦、掲諦……」の句をうけて「これが般若波羅蜜多のマントラである」と訳すべき文なのです。この最終句までが、観自在菩薩の台詞と解すべきでしょう。先に私が、果たしてこの尾題が経典全体のタイトルにあたるかどうかということについては、実は問題があると述べたのは、こういうことなのです。
これが『般若心経』の全体の構成です。
正しい理解のために
「フリダヤ」の正しい解釈
タイトルの「般若波羅蜜多心」とは「般若波羅蜜多のマントラ」のことでした。
『般若心経』の本文にそってタイトルの意味を考えれば、明白この上ないことであるにもかかわらず、なぜこれまでそのように理解されてこなかったのでしょう。
多くの解説者が漢字の「心」を現代流に勝手に解釈している原因の一つは、「心」という漢字に「真言」という意味があるとは思いもよらないからでしょう。
では、「フリダヤ」にマントラの意味があるかといいますと、そのような意味は一般のサンスクリットの辞書には載っていません。
ですから、サンスクリットを読める現代の学者も誤解してしまうのです。しかし、インドの文献ではフリダヤ・マントラという言い方は珍しいことではなく、フリダヤがマントラの別称として用いられることはよくあることなのです。
現代の『般若心経』の解説書の中では最も評価の高い中村元・紀野一義訳註『般若心経 金剛般若経』(岩波文庫)では、漢訳の経題についての註で、「梵文原典に最初からこの経名が附いていたのではない。原文の最後に『智慧の完成の心(真言)を終る』とあったのを、漢訳者が冒頭に持ってきて題名としたのである」と記し、「心」の後に括弧で「真言」と言い換えているのは、まったく正しい理解にもとづいています。
以上のことを繰り返してまとめますと、「般若波羅蜜多心」とは、経典の最後の「掲諦、掲諦、波羅掲諦、波羅僧掲諦、菩提、娑婆賀」のマントラをさします。したがって、『般若心経』の経題は「般若波羅蜜多のマントラを説いた経」というのが正解です
多くの解説者の方々には失礼な言い方になるかもしれませんが、タイトルの意味すら分からないようでは、この尊い経典を解説する資格がありません。「心」の一字を取り上げても、この経典は一筋縄ではいかない奥深さをそなえているのです。
第二章:自己の探求瞑想主義と観自在菩薩という意味
マントラを念誦する修行法
インド仏教史の中の『般若心経』
新しい仏教運動の合い言葉
さて、大乗仏教の先駆をなした経典が、般若波羅蜜多経です。
般若経、と略して呼ばれますが、この名称の経典は実にたくさんあって、なんと紀元前後から六百年の長きにわたって延々と生み出されてきました。その集大成が、玄奘の漢訳した『大般若波羅蜜多経』六百巻です。総字数五百万余字の最大の経典です。
般若経は、その名の通り、般若波羅蜜多を主題とし、もっぱらその称揚に徹した経典です。般若波羅蜜多を保持し、心にとどめ、読誦し、供養し、あるいは書写することがいかに大切か、いかに功徳があるかということが繰り返し説かれています。大乗仏教徒にとって、般若波羅蜜多は、新しい仏教運動のスローガンであり、いわば合い言葉でした。彼らはこの言葉のもとに集い、この言葉に依り、この言葉のもとで修行に励んだのです。
仏母(ぶつも)という女尊それだけではありません。諸仏がさとりを得るのは般若(智慧)の力に依るのであるということから、般若波羅蜜多そのものが神格化されるようになりました。大乗仏教徒は、般若波羅蜜多を、諸仏を生む母、すなわち「仏母」として尊び崇め、その絶大な功徳を宣揚したのです。般若波羅蜜多が仏母という女尊だというと奇異に感じられるかもしれませんが、インドでは古い時代から、風雨や雷などの自然現象のみならず言葉や時間や法則といった抽象的なものに至るまで、何であれ尊ぶべきものを容易に神格化する傾向がありました。例えば阿弥陀如来は光を神格化した仏ですし、文殊菩薩は智慧を、弥勒菩薩は友情を神格化した菩薩だといっても差し支えなく、これと同じことなのです。般若波羅蜜多が女尊とされたのは、原語「プラジュニャー・パーラミター」が女性名詞だったからです。『般若心経』も、般若経の一つであることは言うまでもありません。般若波羅蜜多を主題とする経典です。『般若心経』は般若波羅蜜多のマントラを説いた経であると先に申し上げましたが、その「掲諦、掲諦……」のマントラは、仏母としての般若波羅蜜多に対する祈りの言葉だったのです。玄奘訳の『般若心経』には「仏母」という言葉は用いられていませんので、読者の中にはまだ首をかしげる方もいるかもしれませんが、後代の施護訳の経題は「仏説聖仏母般若波羅蜜多経」となっていて、「聖仏母」という言葉を冠して般若波羅蜜多が仏母であることを明確に示しています。チベット版の『般若心経』でも、「バガヴァティー(女尊 =仏母)たるプラジュニャー・パーラミターのフリダヤ」とサンスクリットの経題が明記されていて、そのことが確認できます。それは後代の解釈ではないかと思われる方もいるかもしれませんが、「般若波羅蜜多はこれ諸仏の母」ということは他の般若経では夙(つと)に頻繁に述べられていたことなのです(玄奘訳『大般若波羅蜜多経』第三〇五 ~三〇八巻「初分仏母品」、羅什訳『大品般若経』第十四巻「仏母品」・第二十七巻「法尚品」参照)。読者の皆さんには意外でしょうが、『般若心経』は、仏母たる般若波羅蜜多を本尊とする経典なのです。『般若心経』は小品ながらも、般若経の中でも特異な地位を占め、独立した一巻の経典として重んじられてきました。実は、『般若心経』は般若経の集大成である『大般若波羅蜜多経』六百巻の中に含まれていません。『般若心経』だけがいわば除外された格好になっていて、その理由は今ひとつ定かではありませんが、それほど特別な経典とみなされていたということなのでしょう。
『般若心経』が重んじられてきたわけ
六つの実践徳目よりさらに上の徳目
ところで、なぜ「深(深遠な)般若波羅蜜多」というのでしょうか。つい見過ごしてしまいがちですが、この「深」の一語は何を意味しているのでしょう。単に深浅の度合いのことであるならば、これに対して「浅い般若波羅蜜多」というのがあるのか、それは何かということになってしまいます。もちろんそうではありません。この「深」にあたるサンスクリットの「ガンビーラ」は「甚だ深い」とか「尋常ではない」を意味します。深般若波羅蜜多とは、要するに普通の般若波羅蜜多ではないということです。
では、普通の般若波羅蜜多、すなわち大乗仏教において特に何の形容もなく、ただ般若波羅蜜多というと、これは菩薩の実践徳目のことをさします。つまり、大乗の菩薩が当初よりみずからに課した六つの実践徳目(六波羅蜜)というものがあるのですが、それは、(一)布施(ほどこすこと)(二)持戒(いましめを守ること)(三)忍辱(苦難に耐えしのぶこと)(四)精進(怠らず励むこと)(五)禅定(心を静めること)(六)智慧(正しい智慧を持つこと)以上の六つです。この六番目の徳目のことをいうのです。『般若心経』が提示している般若波羅蜜多は、この実践徳目としての般若波羅蜜多とまったく無関係というわけではありません。無関係どころか、『般若心経』においても、般若波羅蜜多が菩薩の実践徳目であるということじたいは踏まえられています。しかし、ここでは普通に考えられているような六徳目の中の一つという意味合いではないということを強調するために「深」と形容されているのです。まさしく『般若心経』の般若波羅蜜多は特別な念誦法であり、偉大なマントラであり、尊ぶべき仏母のことですから、明らかに普通に考えられている般若波羅蜜多とは一線を画した「尋常ではない」ものです。そのために「深般若波羅蜜多」と言っているのですから、ほとんどの解説書がこの字義を無視して菩薩の六つの実践徳目の説明に終始しているのは見当違いと言わざるをえません。
インド哲学で異彩を放つ「空観」
自分という存在を見極める
自己を観察する瞑想
観ることが般若に立脚した修行
「一切の苦厄を度す」という一挿句
仏伝レリーフでわかった『般若心経』のメッセージ
第三章:空の瞑想
五蘊皆空の伝授
また、「色不異空、空不異色」と「色即是空、空即是色」は同じことを言っているのか、それとも何か違った意味合いのことを伝えようとしているのか。さらにまた、「色不異空」と「空不異色」、「色即是空」と「空即是色」とは、それぞれ主語が入れ替わっているが、このように主語が交代することによってやはり何か別のことを伝えようとしているのだろうか。だれしもこうした疑問を抱かれることでしょう。
的はずれな解釈
漢訳本文の「色不異空、空不異色」「色即是空、空即是色」は、原典では、「色は空性であり、空性は色である」「色とは別に空性はなく、空性とは別に色はない」「色なるものこそが空性であり、空性なるものこそが色である」となっています。漢訳は二段に分かれているのに対して、原典では三段に分かれています。
漢訳本文の第一段の「色不異空、空不異色」が、原典の第二段の「色とは別に空性はなく、空性とは別に色はない」に相当するのはまちがいないでしょう。
では、漢訳本文の第二段の「色即是空、空即是色」が、原典の第一段の「色は空性であり、空性は色である」を訳出したものなのか、それとも第三段の「色なるものこそが空性であり、空性なるものこそが色である」を訳出したものなのか、これは判別できません。 中村元博士は次のように解釈しています。
「玄奘は原文に三段に分けてあったものを故意に二段に省略したということになる。この三段はいずれも同じことを言っているにすぎないという考え方もある。しかし短い心経の中で無意味に同じことを三度繰り返す必要はあるまい。三段それぞれに意味があったと見るべきであろう」
「色とは別に空性はなく、空性とは別に色はない」も「色なるものこそが空性であり、空性なるものこそが色である」も同じです。これらはすべて「五蘊皆空」とまったく同じことを、ただ「色」について述べた文であると断定せざるを得ないのです。ではなぜ、同じことをそんなに何度も繰り返して述べる必要があったのでしょう。これは単なる修辞上の言い換えではなく、また言い換えることによって何か違った含意を伝えようとしているのでもなく、『般若心経』が瞑想の指南書なるがゆえの、これは瞑想のプロセスにおける、いわば念押しだと思うのです。このように観よ、このように観よ、と親切に言ってくれているのです。律蔵大品という初期の仏典(後述、本書「大乗仏教成立以前に編纂された聖典」)には、釈尊が法を説く場合、「私は三度この義を説く」という表現がよく出てきます。また、成道後の釈尊に梵天が説法を三度懇請し、それで釈尊は説法を決意したという話も伝わっています。仏法僧の三宝に帰依するという「三帰依文」は今でも三度誦えることになっています。インドでは古くから重要なことを三度繰り返して言うという習慣があったのです。でも、インド人でない玄奘は、二度繰り返せば十分だと思ったのでしょう。それだけのことです。
色即是空の意味
色即是空という二つの段階
註:色(物質的現象)=空(自性:実体)
見極めた上でレベルを超えて見極める本段は「五蘊皆空」(自性空)を言い換えたものですから、「色即是空」(空性)は、「五蘊皆空」とまったく同じことを「色」について述べているのです。「空なること」か、「空なるもの」かしかし、サンスクリットに精通したインド人ならば、「色は空性である」という、このサンスクリットの原文を見たら、これは文法的に成立しない文だと必ず言うでしょう。どういうことかと言いますと、「空」という漢字をみる限り、これは「空なるもの」なのか「空なること」なのか判別できませんが、原語の「シューニャター」は抽象名詞でして、「空なること」を意味し、「空なるもの」を意味する「シューニャ」ではないのです。原文を「色は空性(空なること)である」と和訳しても、日本人ならこれは文法的に成立しない文だとまでは思わないかもしれません。
でも、例えば、「この本は重要です」と言うことはできますが、「この本は重要性です」と言ったら、日本語としても意味をなしませんね。それと同じことなのです。なぜこんな破格の構文が用いられているかということです。少なくとも、現存するサンスクリット写本のすべては、「シューニャター(空性)」の語を用いているのです。やはりこの語でなければならなかったのでしょう。一見破格の構文に思われますが、「シューニャター(空性)」という言葉を用いることによって、レベルの差異を明らかにする仕組みが設けられていたのです。サンスクリットの名詞はすべて何らかの動詞(正確には、動詞の語根)から派生しているのですが、この「シューニャ(空なるもの)」という語は「膨らむ」という意味の動詞から派生した名詞で、「膨らんだ状態」というのが原義です。
ちょうどシャボン玉が膨らんだような状態をさします。それが転じて、「からっぽ」という意味になるのですが、これを瞑想の中で観る、すなわち「空観」とは、どのようなものだと考えればよいでしょうか。私たちは、日常生活を営む上で、自分自身に対してさまざまな枠付けをしています。親であり、子であり、社会人であると自覚し、たえず自分とはこういうものであり、こうあらねばならないと考え、行動しています。しっかりとした自己の確立とか自己形成はとても大切なことです。それは言うまでもないことです。しかし、その自己の確立なり自己形成が、一方で実は自己の執着であり、我欲の巣であり、あらゆる苦しみの原因でもあることを見抜くことの出来る「観点」があり、それは世間レベルを超えたところにあるということを、四層の建物の比喩でみてきました。
世間レベルを超えた観点とはどのようなものでしょう。少なくとも、それは世間レベルにおける自分を頭から否定するものではなく、世間レベルにおける自分自身を冷静に観察できるようになることでしょう。そこに至れば、なるほど自分という存在はこういうものか、実にさまざまな枠付けを自分でしていて、実に窮屈なものだな、そもそも、それがなければ自分という存在はどこにもないということではないか、ということが分かるでしょう。すなわち、「無我」ということを了解するのです。しかし、そこではまだ枠付けがあるということが分かるだけです。
さらに観察を深めると、膨らんだシャボン玉がはじけて消えてしまうように、あらゆる枠付けが消えてしまい、まったく開放された広がりが現出するでしょう。視野を妨げる何物もなく、開放的な広がりがどこまでも続く、見晴らしの良い見地に立つといったらよいでしょうか。実は「空」の最も本質的な意味は、こうした状態、つまりまったくの開放的な広がりです。そうした空を「観る」ということは、観る対象と観る自分とがもはや別ではなく、自分自身が空の「成る」ことを意味します。すなわち、完全に開放された境地に至るということです。
瞑想修行の階段を昇る
四階のフロア、観自在菩薩の境地
「自己」の正体を見極めて「無我」へ
第四章:不生不滅の諸法
原意から探る法(ダルマ)の意味
ダルマはどこに保持されるのか
釈尊の成道と諸法の顕現
五蘊と十二因縁
律蔵大品「大犍度(だいけんど)」におさめられている『五比丘篇(ごびくへん)』は、釈尊がサールナートで五人の比丘に対して行った最初の説法(初転法輪)の様子を伝えていますが、そこでは十二縁起にはまったくふれず、五蘊について次に引用するように述べている箇所があります。
「比丘らよ。このことを考えてみよ。色は恒常であろうか、それとも無常であろうか」
「無常です」
「では、無常なるものは苦であろうか、それとも楽であろうか」
「苦です」
「無常にして苦、そして変容するもの(ダンマ)を、これは私のものである、これは私である、これは私の自我である、とみなすことは妥当であろうか」
「いえ、違います。」(以下、受・想・行・識についても同じ説諭が繰り返される)
「比丘らよ。(五蘊は、私のものではない、私ではない、私の自我ではないと)このように正しく観察するならば、高貴なる弟子は、色を厭い、受を厭い、想を厭い、行を厭い、識を厭う。厭えば、離貪し、欲を離れて解脱する」
〔『五比丘篇』〕ここで最も重要なことは、釈尊の瞑想において顕現した諸法は、瞑想の中で滅尽されるべきものであったということです。『般若心経』においても、五蘊は皆空であるとして、その存在が否定されています。諸法は瞑想の中において初めて顕現するものですが、最終的に否定されなければならないものだったのです。漢訳で省略された「ここにおいて」『般若心経』の前の段と本段で観自在菩薩が舎利子に語りかける際に、原典では「ここにおいて、シャーリプトラよ」といい、「ここにおいて(イハ)」という言葉を添えています。この言葉は漢訳本文では省略されています。玄奘訳だけでなく、他のどの漢訳でも省かれています。
岩波文庫本は、これを「この世においては」と訳しています。しかし、そのように訳してしまうと、「あの世」においては違うのかといった余計な問題が出てきそうです。そんな問題は『般若心経』では言うまでもなく論外です。だから、漢訳者も無視してもかまわないと判断したのかもしれませんし、そうであるならば、特に重要な言葉ではなかったと言えるかもしれません。しかし、これを私なりに解釈するならば、サンスクリットの「イハ」は、この世とかあの世とかは無関係に、単純に「ここ」「この場所」を意味する語です。観自在菩薩が語る「ここ」とはどこをさすのでしょうか。むろん「この世」には違いありませんが、観自在菩薩は四階のフロアにいるのです。四階の大乗レベルのフロアにおいて観るならば、ということが「ここにおいて」という言葉で表現されているとみるべきではないかと思うのです。
前の段落では「色即是空」、本段では「諸法空相」が舎利子に伝授されました。それは四階の大乗レベルのフロアにおいて初めて観ることのできるものです。漢訳では無視されている「ここにおいて」という一見何の変哲もない言葉は、実は『般若心経』が説きあかす高次の「観点」そのものを示す、とても重要な言葉だったと言えるのではないでしょうか。
諸法は空を特徴としている
舎利子の入門
ダルマ研究(アビダルマ)の活発化
アビダルマへの批判が生んだ大乗仏教
なぜ観自在菩薩と舎利子なのか
六つの「不」の真意
「ここ」とはどこか
第五章:空の中には何もない
ないものとはダルマ
本段の趣旨は煎じ詰めれば、「空の中には何もない」ということですが、空の普通の意味は「からっぽ」ですから、からっぽの中に何もないのは当たり前のことです。ここではそんな当たり前すぎることを述べているのではもちろんありません。第一と第二の伝授を承けて「この故に」といい、ダルマにかんするさらなる伝授が行われるのです。
問題は何がないかということです。ないものが列挙されている点が重要です。言うまでもなく、ここに列挙されているのはすべて「自己という経験主体を構成する要素として瞑想の中に顕現して存在するもの」としてのダルマ(諸法)です。
単に何もない、ではなく、いかなるダルマもない、と言っているのです。
『般若心経』にみるダルマの分類法
十二縁起のダルマをどう観るか
因果系列は無明に始まる
十二縁起という瞑想のプロセス
四諦説は「真理」とは無関係
「智もなく、得もなし」瞑想指南の完了
第六章:涅槃の境地
【漢訳本文】以無所得故、菩提薩埵、依般若波羅蜜多故、心無罣礙、無罣礙故、無有恐怖、*遠離一切顚倒夢想、究竟涅槃。
【読み下し】得る所なきをもっての故に、菩提薩埵は般若波羅蜜多によるが故に、心に罣礙なし。罣礙なきが故に、恐怖あることなし。*一切の顚倒夢想を遠離して涅槃を究竟せり。
【原典和訳】この故に、ここにはいかなるものもないから、菩薩は般若波羅蜜多を拠り所として、心の妨げなく安住している。心の妨げがないので、恐れがなく、*ないものをあると考えるような見方を超越していて、まったく開放された境地でいる。
*註:『自性(svabhava)が存在しない』と考えるような誤った見方を離れて、全く開放された境地でいる。
本段の主語は菩提薩埵
誤解を招く「無所得」
本段冒頭の「得る所なきをもっての故に(以無所得故)」の一句についてですが、わが国の伝統的な訓読の仕方では、この一句はこの段の一部とせず、前の段落の文章に含ませて、「智もなく、得もなし、得る所なきをもっての故に」と読ませています。 しかし、原典には、この一句の前に「この故に」という接続詞がありますから、やはり本段の一部と考えるべきでしょう。
般若波羅蜜多によって
プラジュニャー」は「知る」を意味する動詞語根「ジュニャー」に「プラ」という接頭辞がついた語の名詞形です。この接頭辞は「前に」という意味があることから、ほとんどの学者はプラジュニャーを、知識以前の知、すなわち「無分別知」のことだと説明するのですが、そうではなく、この接頭辞「プラ」は、「前方に進める」という意味にとらなくてはなりません。つまり、通常の知を一歩進めた高度な知、または高度な知をもたらす知がプラジュニャーなのです。
決して通常の意識以前の、たとえば動物的あるいは幼児的な、分別のない状態に戻ることではありません。
その境地は、私たちの視界をはるかに超えてはいたけれども、すべてを包含していたのです。
心を妨げるものもない
「心に罣礙なし」について説明します。
この「心」の原語は「チッタ」です。経題の「心」(フリダヤ)とは別で、これこそ私たち人間の内面の心をさす言葉です。アビダルマ論師たちはダルマを分類して最終的に「五位七十五法」という体系にまとめあげたのですが、実に心そのものも一つのダルマにほかなりませんから、心を妨げるものもなければ、妨げられるもの(心)もないということになるのです。
いかなる恐怖も、その原因が何であれ、心から生じるといえるでしょう。
「般若心経」は「心の大切さ」を説く経などでは全然なくて、むしろその反対に、心というようなものはないのだ、ないということが観察できるレベルがあるのだ、ということを説いている、それこそ恐るべき経典なのです。
「超越」とは階段を昇り切っていること
「涅槃」の原意は覆いのない状態
次の一文、一切の「顛倒夢想を遠離して」は、「ない」と観察されるダルマを「ある」と錯誤しているレベルに対して、きっぱりと「ない」といっているのです。
最後の句、「究竟涅槃」は、伝統的には「涅槃を究竟せり」と訓読します。
「涅槃」という言葉は、普通は次のように説明されています。
「もとは吹き消すこと、吹き消した状態を意味するが、佛教では燃え盛る煩悩の火を吹き消して、悟りの智慧を獲得した境地をいう」(『佛教大事典』小学館)
なぜ上記の事典ないし辞典のような説明がなされているかというと、「ニルヴァーナ」の語源が、「(風などが)吹く」という意味の動詞語根「ヴァー」から派生した名詞だと考えられているからです。
外国のバーリ語研究者の間では、「ニルヴァーナ」の語は「ヴァー」ではなく、「ヴリ(覆う)」であろうと考えられています(バーリ聖典協会篇「バーリ語(一英語)辞典」参照)空海は「般若心経秘鍵」の中で、「妨げのない自由な境地が涅槃に入るということである」(無礙離障は入涅槃の義)と解説しています。空海は明らかに原語「ニルヴァーナ」の語根は「ヴリ」と考えていたと思われます。空海の解釈によりますと、「心に罣礙なし」という前の文と脈絡がぴたっと合う、ということにお気づきでしょうか。「覆いのない、妨げのない状態」が涅槃なのです。そのような状態まで「ない」としてしまえば、「般若心経」はまるで意味不明の経典になってしまうでしょう。本段で提案はしっかりと肯定されています。このことからも「般若心経」は何でもかんでも、「空」といって否定しているのではないことがお分かりいただけるでしょう。
第七章:般若のさとり
般若波羅蜜多に立脚して「さとる」
本段の趣旨は、「さとれるものは般若波羅蜜多による」ということにあります。
いったい釈尊をはじめとする諸仏がさとりを開いたのは般若波羅蜜多によるなどということは、初期のいかなる仏典にも記されていないことでした。
しかし、大乗の菩薩たちは、従来の伝承を見直し、釈尊の教えの真意は何であったかと追究し、自己自身の内なる探究を通じて、ついにこれにこそ立脚すべきという確かなものとして、般若波羅蜜多に辿り着いたのでした。彼らは大胆にも、仏の崇高なさとりの境地さえも、実は般若波羅蜜多によるのであると確信し、ここに般若波羅蜜多を高々と賞揚する一巻の経典が誕生したのです。
編纂された『般若心経』
『大品般若経』から抽出された部分
今さらこんなことを言うと驚かれるかもしれませんが、『般若心経』は経典としてはごく短いものながら、実は出所の異なるいくつかの文が巧みに編纂されて一巻の経典として成立したものなのです。
最初期の般若経として、八千頌からなる『小品般若経』があり、次いで、より大部の二万五千頌からなる『大品般若経』が誕生しました。
いずれも羅什による漢訳(前者は十巻二十九品、後者は四十巻九十品)が現存しています。実は、『般若心経』の大部分は、この『大品般若経』の中から抽出された文で構成されているのです。本文の最初の部分の
「観自在菩薩、行深般若波羅蜜多時、照見五蘊皆空、度一切苦厄」と、最終の部分の「故、説般若波羅蜜多咒。即説咒曰。掲諦、掲諦、波羅掲諦、波羅僧掲諦、菩提、娑婆賀、般若心経」を除く全文が、『大品般若経』から抽出されたかたちで構成されているということになります。
羅什訳と玄奘訳
前世紀の初頭、敦煌より出土した経典の中に、全文が音写語で書かれた『般若心経』がありました。玄奘の弟子の慈恩大師基による序文が添えられていて、その中に次のような逸話が記されています。
三蔵法師玄奘がインドに向う途上、空慧寺の道場で病に苦しむ僧がいて看病をしたところ、『般若心経』を授かり、この経を誦してゆけば災難から逃れられると教えられた。果たして無事にインドに到着した玄奘が目的地であるナーランダー寺に赴くと、そこになんと、かの病僧がいた。驚く玄奘に、私は観自在菩薩であると告げて姿を消したというのです。
この『梵本般若心経』の冒頭には「この経は玄奘が観自在菩薩から親授された梵本(サンスクリット本)なので潤色しない」と記されています。大切な原典であるから、いかなる手も加えず、漢訳もせず、原音に忠実に音写しておく、という意味です。
この逸話が物語っているのは、玄奘にとって、『般若心経』は格別尊重すべき経典であったということでしょう。玄奘がインドへの旅路において『般若心経』を誦えていったという伝承は古くからありました。玄奘の弟子慧立が書き、さらに同じ弟子の彦悰が、書き加えた『大慈恩寺三蔵法師伝』にも、そのことが記されています。
玄奘が観自在菩薩から『般若心経』を親授されたという逸話も、現代人の観点から実際にはありえないと言うのは簡単ですが、果たしてそれも荒唐無稽な話と断定してしまってよいものでしょうか。この尊い経の原典を入手しえたのも、決してたやすく単に人から人へと手渡されたというようなことではなく、そこに人知を超えた大きな力の存在を思わざるを得ない、そのような敬虔な気持ちが根底にあって、この信念を後世に伝えようとした決意の表明のようにも思えるのです。
三世の諸仏
仏説の真意
第八章:祈りのマントラ
【漢訳本文】故知、般若波羅蜜多、是大神咒、是大明咒、是無上咒、是無等等咒、能除一切苦、真実不虚故、説般若波羅蜜多咒。即説咒曰。掲諦、掲諦、波羅掲諦、波羅僧掲諦、菩提、娑婆賀。般若心経。
【原典和訳】それ故に知るべきである。般若波羅蜜多の大いなるマントラ、大いなる明知のマントラ、この上ないマントラ、比類なきマントラは、すべての苦を鎮めるものであり、偽りがないから、真実である。般若波羅蜜多の修行で誦えるマントラは、次の通りである。 ガテー、ガテー、パーラガテー、パーラサンガテー、ボーディ、スヴァーハー。 以上で、般若波羅蜜多のマントラ、提示し終わる。
四種の賛辞
本段は「故に知るべし」という言葉で始まります。「般若心経」全段の中で、ここだけが強い命令口調になっています。観自在菩薩が舎利子に最終的な伝授を行う最も重要な場面です。
大神咒=マハー・マントラ(偉大なる真言)
大明咒=マハー・ヴィディヤーマントラ(偉大なる明知の真言)
無上呪=アヌッタラ・マントラ(この上ない真言)
無等等咒=アサマサマ・マントラ(比類なき真言)
漢訳本文は、「能除一切苦真実不虚故、説般若波羅蜜多咒」と続きます。この箇所は伝統的には、「よく一切の苦を除き、真実にして虚しからず。故に般若波羅蜜多の咒を説く」と読み下します。現代の解説書でもこちらの読み方をするほうが多いようです。
「故に」という語を次の「般若波羅蜜多の咒を説く」にかけて読んでしまうのだと思われますが、原典では、「偽りがないから、真実である」という文構成になっています。故に般若波羅蜜多の咒を説く」という読み方はただしくありません。「真実」にあたるサンスクリットは「サトヤ」ですが、ここでも「サトヤ」は、真理といった抽象的なものではなく、「確実な、信頼の置ける、効き目のあるもの」を意味しています。
むろんこれは般若波羅蜜多のマントラのことをさしています。次の「不虚」にあたるサンスクリットの「アミティヤー」は、「予言していない」「嘘偽りでない」を意味します。かくして、この本文全体は、「般若波羅蜜多のマントラは、すべての苦を鎮める、確実な、信頼の置ける、効き目のある言葉である。なぜならば、矛盾なく、嘘偽りのないものだから」ということを述べていると、ご理解いただけるでしょう。
四つの修行階梯効き目のある言葉マントラについて用いられるべき場面でのみ効力発揮マントラに関して最も重要なことは、マントラは特定の儀礼や瞑想修行において師より弟子に伝授される言葉で、そこで用いられて(誦えられて)、はじめてマントラの名にあたいするものになるということです。つまり、例えば本に印刷されている「掲諦、掲諦……」の文字は、それだけではマントラでも何でもないのです。
たとえマントラの字句の意味を理解したとしても、それだけではマントラを会得したことにはならず、また当然、その字句と意味をいくら公開しても、マントラの秘密性または神秘性をそこなうことにはならないのです。経典の作者がいないように、マントラの作者もいません。よって、「作者の意図」は探りようもありません。ひとつとして起源の分かるマントラもありません。
*註
羯諦咒の意図⇒自性に合一すること
マントラは有資格者から伝授されたものしか効果をもたない
羯諦咒の伝授と効果⇒全知性と悟り(プルシャ)が得られる
「掲諦、掲諦」にこめられた賛美
現行の三つの訳し方
一つは「ガテー」(掲諦)を、「往く」を意味する動詞の過去完了形の男性名詞「ガタ」の単数於格とみて、「往けるとき」と解釈する仕方です。
「往けるときに、往けるときに、彼岸に往けるときに、彼岸に完全に往けるときに、さとりあり、スヴァーハー」
もう一つは、「ガテー」(掲諦)をやはり「往く」を意味する動詞から派生した、女性名詞の「ガター」または「ガティ」の単数呼格とみて、「往ける者よ」と解釈する仕方です。
「往ける者よ、往ける者よ、彼岸に往ける者よ、彼岸に全く往ける者よ、さとりよ、幸あれ。」
実はもう一つ、代表的な訳し方があります。それは渡邊照宏博士の訳です。
「到れり、到れり、彼岸に到れり、彼岸に到着せり、悟りに。めでたし」
これは、「ガテー」(掲諦)を、「往く」を意味する動詞の過去完了形の男性名詞「ガタ」の単数主格と解釈したものだと思われます。正規のサンスクリット文法では、こうした解釈はできません。これは原文を、古代東部インド語(釈尊の時代に用いられていたと推定される古語)とみて、その文法を適用して解読した結果です。
結論を言いますと、これはだれかがどこかへ往くとか往かないとかいうことではなく、このマントラは最後の「娑婆賀」を除いて、一言一句、すべて「般若波羅密多」を言い換えたものです。あくまでも般若波羅蜜多を称えた、「般若波羅蜜多のマントラ」なのです。
ただ、最後の「娑婆賀」(スヴァーハー)だけは別で、これは供物を捧げる際に誦える定型の終句として用いられてきたもので、「成就あれ!」というほどの意味の言葉です。
諸仏がさとりを得るのは般若の力に依るのであるということから、大乗仏教徒は般若波羅蜜多を、仏母として尊び崇め、その絶大な功徳を宣揚したのです。このことは玄奘訳「大般若波羅蜜多経」六百巻はもとより、羅什訳『大品般若経」によっても確認できることです。ならば、般若波羅蜜多を仏母として称えるマントラが「般若心経」に掲げられていても何らふしぎなことではありません。そうであるなら、
「母よ、母よ、般若波羅蜜多なる母よ、どうかさとりをもたらしたまえー。」
マントラの全文の意味はおよそこのようなものでしょう。釈尊ご生誕の聖地ルンビニーの守護神は、生母マーヤー(摩耶)夫人です。
今はネパール領のその現地名「ルンミンデーイ」の原意は、「失われた女神」です。数百年の時を経て、仏陀の母は「般若波羅密多」として蘇り、大乗仏教の原動力となったのでした。
「般若心経』は「仏母」たる般若波羅蜜多を本尊とする経典だと申しあげました。ならば、般若波羅蜜多を仏母として称えるマントラが「般若心経』に掲げられていても何らふしぎなことではありません。そうであるなら、
『母よ、母よ、般若波羅蜜多なる母よ、どうかさとりをもたらしたまえー。』
マントラの全文の意味はおよそこのようなものでしょう。
釈尊ご生誕の聖地ルンビニーの守護神は、生母マーヤー(摩耶)夫人です。釈尊をこの世に産んでわずか七日で没した母マーヤーの名は「幻影」を意味します。今はネバール領のその現地名「ルンミンデーイ」の原意は、「失われた女神」です。
数百年の時を経て、仏陀の母は「般若波羅蜜多」として蘇り、大乗仏教の原動力となったのでした。
