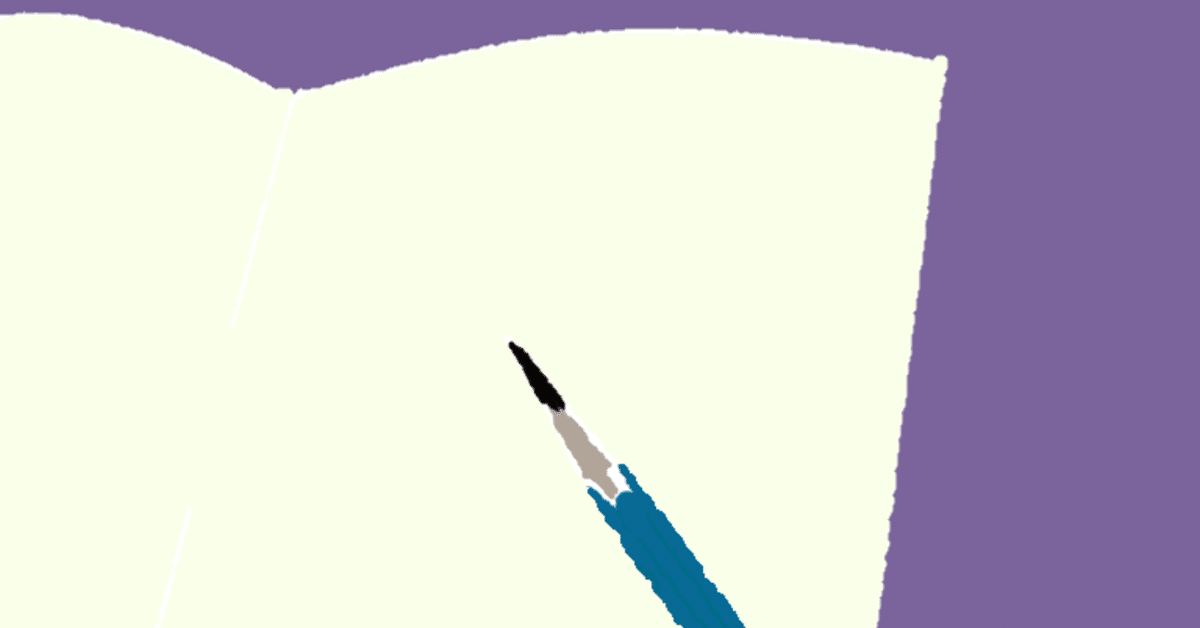
想いを書く
誰が言ったのか。そのひとはどういう雰囲気なのか。好きか嫌いか。
そういうごく付随的な要素で変わるものだと思う。その科目を得意になるかどうかは。
高校一年生のとき、私は古文が苦手だった。
古文の教師が、苦手だったから。
妙に張りのある体躯も、粘着質な声も、ねっとり進む授業も、好きじゃない。それらの印象ひとつひとつが私のなかで「古文」という科目の形をつくる。
古文はもちろん、赤点をとった。
高校二年生になると、古文の担任は変わった。
30代前半くらいの愛想のない男の先生だった。いつもこめかみに筋が立っていて気難しい顔をしている。あんまり笑わない。
先生はその年の授業のはじめに言った。
「古文は、ものがたりを楽しんでほしい」
それまで古文の授業とは文字を写す作業だった。
A4のノートを横にして本文を写す。その横に文法の解き方を書いていき、さらにその横に先生が黒板に書いた現代語訳を板書する。とにかくたくさんの文字を写す作業。
先生はそれをやめた。
本文と現代語訳が印字されたプリントが配られ、授業では肝となる文法と解釈の流れを教えてくれる。そしてものがたりを読む。
もともと古文の写す作業の多さにうんざりしていた私は、この授業がすぐに気に入った。
この授業の良さは、ものがたりと文法の主従関係を入れ替えられたことだと思う。「文法を得るためのテキスト」から「ものがたりを楽しむための文法」に。
ものがたりを楽しむ気持ちは、いつも私の中心にいて支えてくれた。たとえそれが限られた試験時間のなかでも。
私はぐいぐいと国語の成績を伸ばし、半年後の模試でついにクラスで一番の点数を取った。
答案が返されるとき、先生が驚きながらも喜びの浮かんだ顔で褒めてくれた。私は本当に嬉しかった。
それからはいつも国語だけは一番の点数を取れた。
私は古文が好きになった。
先生と、先生の授業が、好きだった。
解答用紙の定められたマス目にただしく過不足なく文字を置くこと。先生の授業が好きだと伝えるのにこれ以上の方法はないと思う。
だから心をこめて答案を書く。先生の手から返される答案がいつも一番いい点数であることを祈っていた。大学受験のためというよりも、先生の気難しい顔にすこし赤みがさしてほころぶのを見たいために。
二年生の終わり、先生が退職すると知った。
退職して整体師を目指すのだという。
私は驚いた。先生というのはずっと先生なのだと思っていた。
退職の日が近づくと各クラスごとに寄せ書きが回され、私の手元にきたときにはもうほとんど埋まっていた。
残されたごくちいさいスペース。
そこに、先生が見る最後の、私の文字を綴る。
私は一年生の時は古文は赤点でしたが、
先生の「物語を楽しむ」という授業が大好きで、
二年生では古文が一番の得意科目になりました。
先生でよかったです。
ありがとうございます。
問われもせず、ただしさも必要なく、先生に届けるためだけの、はじめての自分の言葉。
これまでの、どの答案よりも心をこめて書いた。
退職の日、体育館で行われた送別会には全校生徒が集まった。花束を抱えた先生はたくさんの生徒に囲まれてもみくちゃにされていた。先生の新しい門出に相応しい、賑やかさと明るさがあった。
私もなにか声を掛けたり手を差し出したりしたかったけど、あまりの人の波と熱気に阻まれる。これが最後なのに。
なんとかつま先立ちをしてようやく人の頭の合間から顔を出すと、先生が一瞬、私のほうを見た。目が合った。
先生はハッとした顔をして、にっこり笑って、うなずいた。
あぁ寄せ書き、読んでくれたんだな、と思う。
私はやっぱり声は掛けれなくて、でもきちんと、うなずき返すことだけはできた。
先生への想いは、いつも文字にして届けていた。
あの古文の授業の楽しさを、先生の最後の笑顔を、忘れずにいること。
この想いと文章が、いつかまた、先生に届きますように。
