
改善を成功に導くカギ その弐の二
前回の記事『改善を成功に導くカギ その弐の一』で予告したとおり、今回は複雑さに対する恐れを克服する方法についてお伝えします。
この複雑さに対する恐れというのは、色々な現れ方をしますが、最も多いのは「面倒くさい」と途中で投げ出すことです。
手放すと言い換えても良いでしょう。
ですので『複雑さに対する恐れ』を克服する方法は、あなたの『継続力』を上げる一歩になるのです。
どっちが複雑?

まずはこちらの画像(↓)からご覧ください。

こちらのAとBの画像、どちらが複雑に見えるでしょうか。
この2つの画像を見た大半の方が、Aと答えられるでしょう。
でもこの画像を、科学者と呼ばれる方に見せると全員が間違いなくBを選ばれるのです。
なぜなら、Bには因果関係(矢印)が書かれており、それぞれの○に関連性があることが分かります。
対して、Aにはそれが書かれていません。
つまり、Aの4つの○には関連性があるのか、それともないのかすら分からない状況なのです。
物事はそもそもシンプルである

エリヤフ・ゴールドラット博士の著書の中でも、博士自身が「この一冊を読んでもらえれば良い」といった本があります。
それがこの【ザ・チョイス】(副題:複雑さに惑わされるな!)です。
私自身も最初に『物事はそもそもシンプルである』という博士の言葉を教わった時、それがどういうことかよく分かりませんでした。
そして今も、その答えを追求し続けている途中です。
この本の中で博士はこのように語られています。
「『ものごとは、そもそもシンプルである』というのは、まあ簡単に言えば、近代科学すべての基本だな。ニュートンも『自然は極めてシンプルで、自らと調和している』と言っている」
つまり『物事は、そもそもシンプルである』という博士の言葉は、ニュートンの言葉『自然は極めてシンプルで、自らと調和している』を受け継いだものなのです。
そして、どうして私たちが感じていることと、ニュートンが言っていることが違うのかを説明してくれています。
「しかし、ニュートンが言っているのは、その反対だ。物事は収束していくと言うんだ。深く掘り下げれば掘り下げるほど、共通の原因が現れてくる。十分深く掘り下げると、根底にはすべてに共通した少数の原因、根本的な原因しか存在していない。原因と結果の関係を通して、これらの根本的な原因がシステム全体を支配しているというんだ」
【ザ・チョイス】を読み進める中で、この部分(結構最初に来ます)を読んだ時は、正直かなり混乱しました。
ただそれが頭の中にあって、様々な取り組みの度に「本当にそうなのか?」を繰り返していたのです。
その中で何度か『えっ、コレなの?』という体験をしたことがあります。
ある部署の在庫の問題に取り組んでいた時のことです。
どこでも同じでしょうが、その部署も必要なものが品切れを起こし、必要でないものが溢れている状況でした。
どうしてこんなことになるのだろうと色々原因を追及していった時、あることに気がつきました。
「もしかして、在庫の数の決め方を知らないんじゃないのか?」
知っていて当然だと思っていたのですが、メンバーに尋ねたところ返ってきた答えは「知らない」「考えたこともない」「あるなら教えて欲しい」というものだったのです。
問題の根本原因が『在庫の数の決め方を知らない』という、そんな単純なものだったとは思いもよらず、あっけにとられたのを覚えています。
実際その部署では、在庫数の決め方を教えることで、在庫切れの回数を減らすことには成功しましたが、根本解決には至っておらず、追求がまだまだ足りないようです。(全く別方向からヒントはいただいたので、現在はそちらを確認中です)
ですが、根本原因に近いモノの一つにたどり着けたのは間違いない事実です。
それ以降は、より『物事はそもそもシンプルである』と自分に言い聞かせながら、原因追及をしています。
因果関係から根本原因を探す

今更言うまでもないことですが、原因と結果の関係は以下のように図式化できます。
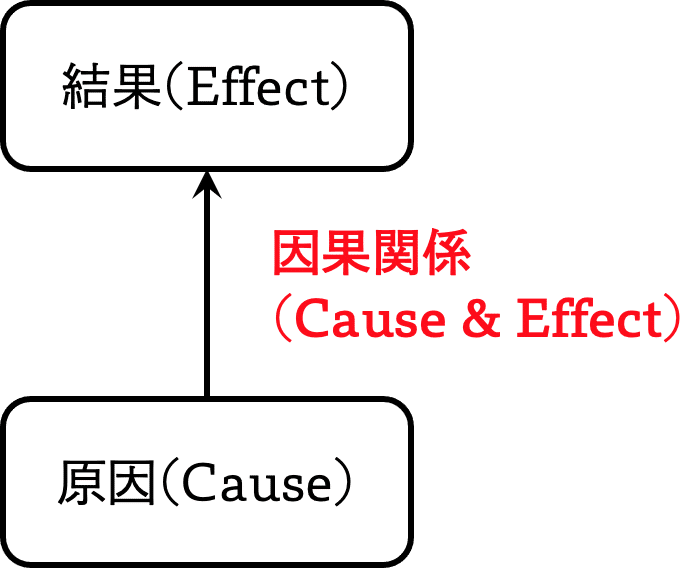
結果には必ず、それを生み出した原因があります。
この前提で一番最初のこちらの画像をもう一度見てください。

Aの方は4つの○があるだけです。
この4つの○を結果だと仮定した場合、この4つの結果に関連性があるのか無いのかも分かりません。
もしこの4つの結果が問題で、それぞれ独立したモノだとしたら、4つの問題に対してそれぞれの解決策を見つけ出さなければなりません。
だとすれば、4つも解決策を見つけ出すためには、それぞれの問題の関係性を説き明かさなければなりません。
それはとても面倒で、複雑なことではないでしょうか。

対してBの方は、すべての○が矢印でつながっています。
すべての○が問題だとしても、その根本原因を見つけ出し、そこを解決することで、他の○の問題も連鎖的に解決できることになります。
そしてBの図の中の根本原因を探っていくと、左下の○が最初のスタートになっています。
だとしたらこの左下の○(根本原因:上のB図の赤丸)を解決すれば良いのです。
私たちが恐れる複雑さとは、Bの図のように矢印による関係性が示されていない、Aの図ではないでしょうか?
複雑さに対する恐れを克服する方法とは、因果関係に目を向け、起こっている事象を矢印でつなげる、至ってシンプルな方法なのです。
シンプル = 簡単・単純ではない!

ただ一つ注意していただきたいことがあります。
『シンプル(Simple)』を日本語訳すると、『簡単』とか『単純』などの日本語訳になりますが、どうもコレは正しくないと私は思っています。
ある時ネットで『シンプル(Simple)』をネットで翻訳してみたのですが、その時はシンプルはシンプルとしか出ませんでした。
確かに「簡単」とか「単純」という意味で使われることもありますが、「簡単」は “Easy” が、「単純」は “Simplicity” の方が正しいようです。
特に、博士の言葉である『物事はそもそもシンプルである』のシンプルを、『簡単』や『単純』と訳してしまうと、間違ったイメージを与えてしまうのではないかと思うのです。
なのであえて日本語に訳すとしたら、私は「わかりやすい」にしたいと思います。
日々の仕事や生活の中では自覚しにくいですが、複雑さに対する恐れというのは、常に私たちに襲いかかってきます。
特に情報が溢れている現代社会においては、複雑でないものを探す方が難しいのではないでしょうか。
だからこそ、この『複雑さに対する恐れを克服する方法』である、原因と結果の法則(因果関係)に目を向け、そのつながりを明らかにしていくことこそ、現代社会に対抗する手段の一つだと思うのです。
さて、本日は『複雑さに対する恐れ』に的を絞ってお伝えしましたが、本来の題材である『全社的な取り組み』に対する答えからは、少しずれてしまったかも知れません。
ですので次回は、全社的取り組みを成功に導いたMAZDAの事例を元に、そこから成功の法則を探っていきたいと思います。
