
鴨南蛮と鴨なんばと鴨そば

元旦の有料版ではご挨拶しましたが、定期版は今年初なので改めまして、明けましておめでとうございます。私事ですが、NOTEも2年目に突入致しました。これも読んでくださる皆さまのおかげです。誠ににありがとさんでございます。
さて、新年最初の定期版は、Eijyoさんにお誘い頂いた「さざれ石」に投稿するために書きたいと思います。

筆者は蕎麦の専門家ではございません。そこらへんにゴロゴロしている程度の蕎麦好きでございます。しかしながら、他の皆さんのような蕎麦の食レポやお店紹介は苦手でございます。そこで、お酒を飲みながら読んでいただける、蕎麦好きのための軽いお話を、「鴨南蛮と鴨なんばと鴨そば」と題して、少しばかり妄想してみようという趣向でございます。 どうぞ呑みながら、ごゆるりと、適当にお読み下さい。

鴨南蛮
鴨南蛮の元祖は、日本橋の蕎麦屋「笹屋」と伝えられています。笹屋の店主治兵衛さんが長崎の「南蛮煮」をもとに考案した蕎麦を「鴨南ばん」と命名しました。その内容は、鴨肉三枚とたたき骨(叩いて亀裂を入れた骨)二本に短冊に切った長ねぎを入れた温かい蕎麦です。

南蛮煮
鴨南ばんのもとになった南蛮煮とは、味醂・砂糖と醤油、唐辛子で魚・肉と野菜を煮たものです。同じ材料を焼く、あるいは揚げて、南蛮酢(唐辛子入り三杯酢)に漬けたものが南蛮漬けです。この調理方法は長崎から広まったようで、全国的に唐辛子が入った料理を「南蛮」と名付けました。
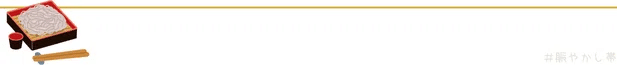
南蛮とは
南蛮とは、中国の中華思想に基づく呼び名です。古来、中国の漢民族は自国が世界の中心に位置すると考え、自国民こそが世界を支配すべき最高の民族で、他の国・異民族は劣等だと見なしていました。これが中華思想で、劣等民族の中でも、現在の雲南省やその周辺の東南アジア諸国は野蛮な国・民族だと考え、南蛮族と呼んで特に軽蔑していました。この南蛮族について、三国志演技に興味深い一文があります。

諸葛孔明
西暦225年、孔明は南蛮(現・雲南省)を平定し、成都へ引きあげる途中、荒れ狂う濾水という河にさしかかります。 河を渡れず困り果てる孔明に、「この河の荒神を鎮めるには49人分の頭を捧げる風習がある」と土地の長が言いました。
孔明は「みだりに人を犠牲にしてはならない」といい、料理人を呼んで小麦粉をこねさせ、中に牛や羊の肉を詰めた球体を作らせます。これを蛮族の兵士の頭に見立てて「蛮頭」と名付けました。その夜、儀式を行い、供物として蛮頭49個を河に投げ込むと、たちまち氾濫は鎮まり、孔明軍は無事に河を渡れたのです。
こんな逸話が『三国志演義』にあるのですが、この「蛮頭」が後に「饅頭」になったというのです。現在、私達が大好きな肉まん・豚まんのことです。ということは、肉まん・豚まんの中身は脳みそですね…。 駄菓子菓子、この一節には注釈が付いていて、「この話は『事物紀原(中国の書物)』を出典とする」とあるのです。
そこで、事物紀原を調べてみると、孔明が孟獲(三国志演義に蛮族の王として登場する武将)を征伐した際、こう進言する者があった。
「蛮地には邪術が多いゆえ、神に祈り、神兵の助力を受けるべきです。蛮人の習俗では、人を殺し、その首を祭ります。すると、神がこの生贄を享け、兵を出してくれるのです」
孔明はこの進言には従わず、羊と豚の肉を混ぜ、小麦を練って作った皮で包み、これを人頭に似せて供物としました。果たして神はこの供物を享け、兵を出してくれそうです。「後人はこれこそ饅頭の起源であるとする」(『事物紀原』巻9/酒醴飲食部第46)とあります。ただ、この逸話も信憑性には疑問符が付きます。筆者は、中国語の「蛮頭」と「饅頭」の発音が同じで、そこから逆算で作り上げた物語ではないかと思います。まあ、三国志演技は小説なので、史実とは限らないと承知の上なのですが。

唐辛子
南蛮と言えば唐辛子ですが、唐辛子は熱帯アメリカが原産で、中南米で古くから栽培されていました。考古学的な調査により、紀元前8000~7000年にはペルーの中部山岳地帯で、紀元前7000年頃にはメキシコで栽培されていたことがわかっています。この歴史から言えば、唐辛子が東南アジアに伝わるのはもっと後なのですが、分かっている限りでは15世紀にコロンブスによってヨーロッパに持ち込まれ、そこからインドに伝えられたようです。
インドから唐にシルクロード経由で持ち込まれた唐辛子は、唐から日本に伝えられたので唐辛子です。

鴨南蛮には七味唐辛子
現在の鴨南蛮には唐辛子は入っていません。それは七味唐辛子があったからです。七味は江戸・薬研堀で考案され、蕎麦・うどんには早くから使われていました。ですから、わざわざ唐辛子を入れなくても、客が好みで七味を振り入れることを考慮して省かれたのだと思います。

南蛮は葱ではない
南蛮料理については、葱が入っているから「南蛮料理」だという説もありますが、葱の伝来は奈良時代以前なので葱=南蛮なら、日本料理にもっとたくさんの「南蛮」があるはずです。例えば、葱入り味噌汁が南蛮汁とか。そんなことはないので、筆者は、葱が入るから「鴨南蛮」だという説を支持しません。鴨南蛮に葱が入っているのは、鴨と葱が出会い物だからです。

根深葱
葱は中央アジア原産で、中国では紀元前200年ごろから栽培されていました。日本には奈良時代より前に、朝鮮半島経由で持ち込まれたと思われます。
元々耐寒性の強い野菜なので、日本では寒い地域から温かい地域まで、広く栽培されていました。旬はどの地域でも冬です。
関東では寒さが厳しいので、緑色の葉部分が肉厚で固くなります。その固い葉の部分をできるだけ少なくするために、関東ローム層の柔らかい土を寄せて伸びた部分を埋めました。これを繰り返して、育てるうちに白い部分が長くなり、関東では根深葱が主流になりました。

鴨葱
「鴨が葱を背負って来る」ということわざがあります。このことわざがいつ誕生したのかは定かではありません。ただ、鴨が一般的に食用にされるのは江戸時代からで、おそらく「鴨葱」も江戸時代以降の作だろうと思います。その意味は、鴨が葱を背負って来ると料理するのに好都合だということです。現在の鴨南蛮には合鴨が使われていますが、元々は野生の真鴨で作る料理でした。真鴨が日本に渡ってくるのは冬。根深葱の旬も冬。ということで、鴨と葱は出会い物なのです。

出会い物
「出会い物」とは同じ季節が旬の美味しい物同志の組み合わせです。日本料理は旬を大切にするので、筍と若芽の「若竹煮」、真鯛とかぶらで「鯛かぶら」、鱧と松茸なら「土瓶蒸し」、そして鴨と葱は「鴨鍋」です。鴨は海の物ではないので、出会い物としては異例ですが、海を越えて渡ってくるのですからいいでしょう。鴨南蛮は蕎麦屋発祥の出会い物料理なのです。

再び鴨南蛮
ずいぶん寄り道をしてしまいました。以上のような理由から、鴨南蛮は鴨と根深葱が入った、江戸蕎麦です。江戸蕎麦ですから、色黒の出汁に白い根深が映えて、とても見栄えがします。

難波葱
「なにわの伝統野菜」のひとつに難波葱があります。難波葱は葉葱なので、白い部分は根元の少しだけですが、昔の葉葱はもっと白い部分が長く、緑色の部分も今よりは固かったようです。それでも葉先の部分を早取りすると、柔らかい葱がほんの少しだけ取れます。それが宮中で喜ばれました。
そのほんの少しのために、飛鳥京や藤原京に近い大和や大坂で、葉葱を栽培するようになりました。この葉葱が和銅4年(711年)には京に持ち込まれ、後に品種改良の末に、葉の大部分が柔らかい九条葱になります。
江戸時代になると、大坂・難波で葉葱の大規模栽培が始まります。現在の大阪市中央区で、観光地であるミナミのど真ん中です。その頃には、緑色の葉の部分が長く、白い部分が短い姿に改良されており、大坂名産の「難波葱」として認知されます。蕎麦にもうどんにも重宝された難波葱ですが、難波葱よりもさらに柔らかい九条葱が量産されるようになると姿を消しました。現在は「なにわの伝統野菜」として細々と守り続けられています。

鴨なんば
一般的には「鴨なんば」は「鴨南蛮」と同じものだと言われていますが、それは間違いです。鴨なんばは、鴨肉と難波葱が入った「鴨難波」なのです。もちろん大坂の蕎麦なので出汁の色は薄く、1~2cmほどの斜め切りにした難波葱(現在はほとんど九条葱)の緑色がよく映えます。

鴨そば
江戸の鴨南蛮は登場してすぐに大人気になりました。その評判はすぐに上方に届き、鴨難波が登場します。
大坂で鴨難波が人気になったころ、京でも鴨肉が入った蕎麦が登場していました。当然ですが、鴨南蛮でも鴨難波でもありません。茶屋の女性達(後に舞妓さんと呼ばれるようになる)が大きな口を開けなくても食べられるように、鴨肉に九条葱の小口切りをあしらった、その名も「鴨そば」です。

食は文化
今となっては、「鴨なんば」は鴨南蛮のことだと言われ、京都で九条葱が入った「鴨南蛮」や「鴨なんば」が売られています。もはや鴨入り蕎麦の文化は無茶苦茶になっているのです。嘆かわしいことではありますが、料理とはそういうものです。
料理は文化です。文化は時とともに、土地とともに常に変化しているのです。鴨難波が鴨なんばになり、鴨南蛮のことだと言われるのは、難波葱を見なくなったからです。その裏には九条葱が難波葱を駆逐した事実があります。
いづれ、鴨入り蕎麦は葱の種類に関係なく「鴨南蛮」の名称で統一されるでしょう。それは、ここに書いたような歴史を誰も知らなくなった時で、文化とはそういうものです。

そろそろお蕎麦に…
いかがでございましたか? 蕎麦前代わりになりましたでしょうか? ええ心もちで、 十分におあがりになられたら、そろそろお蕎麦にしまひょか。
#蕎麦食推進クラブさざれ石


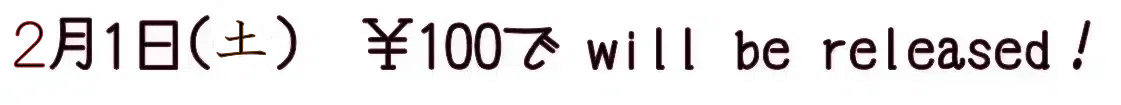
上方落語のお料理 ①≪鴻池の犬≫

▶演じるは昭和の爆笑王 二代目 桂枝雀 !
▶お料理は「鯛の浜焼き」と「う巻き」
▶上方落語のおいしいもんを、どうぞおあがり。
上方落語のお料理① ≪鴻池の犬≫

