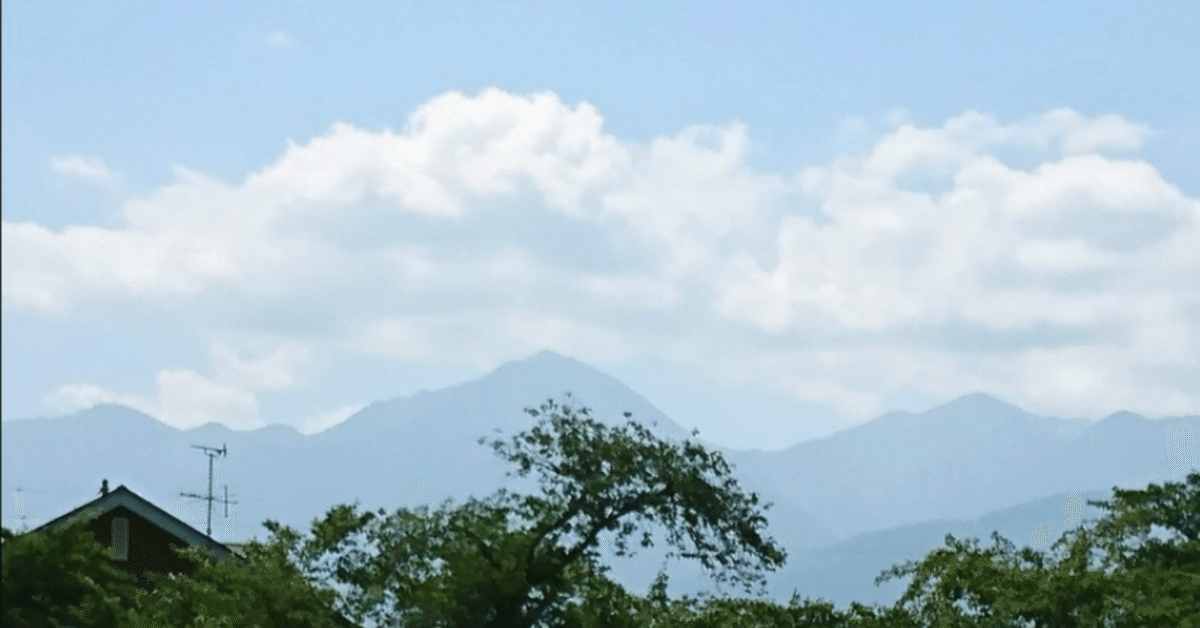
「しあわせ」の在りか〜カアル・ブッセによせて
『 山のあなた 』
カアル・ブッセ 上田敏訳
山のあなたの空遠く
「幸」住むと人のいふ
噫、われひとゝ尋めゆきて、
涙さしぐみ、かへりきぬ。
山のあなたになほ遠く
「幸」住むと人のいふ。
ー「海潮音」上田敏訳詩集ー
(新潮文庫)
※ ※ ※ ※ ※ ※
わたしは、
「自分は不遇の人生を送って来た。」
と、ずうっと、思っていた。。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
幼い頃から、わたしは「負けず嫌い」で、将来は、人から尊敬されるべき「何者か」になろうと考えていた。
野心家だったのだ。
だから、そのために、わたしは、「男の子になんか負けない!」という気概を持って、ずっと頑張って勉強してきた。
まだまだ、「女の子」は、「料理」や「家事全般」をこなせるようになって、「早く嫁に行け」という時代だったけれど、わたしは「男に従うような人生はまっぴらだ!」と考えていた。
大学を卒業して、東京の郊外の、某市の公務員に採用されたあたりまで、わたしは、結構「上手くやっている」つもりでいた。
でも、働き始めてみたら、わたしは、「公務員」には全く向いていなかったのだ。何もかもが慣例通りの「事務仕事」は、わたしの神経を、ただただすり減らすだけだった。浮いていたのか、その人間関係にもなじめなかった。
結局、わたしは「適応障害」を起こし、二年くらいしか、働くことが出来なかった。
その後は、結婚して、「専業主婦」になり、普通に、「家事全般と子育ての日々」をこなす生活が続いていった。
結局、尊敬されるべき「何者か」に、わたしはなれなかったのだ。。
いったい、なんのために、ずっと、あんなに勉強して来たんだろう。。
優等生だったわたしは、その一件で、初めて「挫折」を味わった。「自分の人生を切り拓く」という、大切だったはずのテーマも、「病んだこと」で、わたしのなかから、いつのまにかすうっと消えて行ってしまっていた。。
その後は、「家族のために生きること」が、あたかも「自分の人生」であるかのように思い込んで、暮らしていたのだ。
家族には、いろいろな「不運」が、次々と襲って来た。
子どもたちは「不登校」になった。それに、家庭がガタガタしたことや、様々な不運が重なって、「夫」は完全に「出世コース」から外されてしまった。
わたしたち夫婦の「理想」は、どんどんしぼんで行った。
それでも「夫」は、生活のために、辞めることも出来ずに、定年まで頑張って働いてくれたけれど、四十代の前半で、わたしは、既に息切れしていて、もう、「人生に疲れきって」いたように思う。
「いつの日かなんとかなる。」
と、とりあえず固く信じているだけで、「未来」は全く見えなかった。ただただ必死に、日々をこなしていたのだ。
「こんなことに、負けるもんか!」という、「負けず嫌いな気持ち」だけが、わたしを支えていた。
その気持ちだけが、「切り拓く人生のために培ったもの」の「かけら」として、わたしに残されていたのだ。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
そんなとき、わたしの前に、「再びの下北沢」は現れた。
あの夜、渋谷の大きなライブハウスで行われたコンサートで、最後に出演したバンドのボーカルの「彼」が、
「下北沢に来て下さい。」
と、壇上からかけた言葉は、今となっては、わたしにかけられた「呪文」だったように思われる。
その「言葉」を聞いた瞬間から、もう、おそらく、わたしの「人生の再検証」と、「自分探し」は、始まっていたのだろうと思われるからだ。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
「下北沢」で遭遇した、さまざまな出来事については、これまで、もう、いろいろに書いた。だから、もう、ここには書かない。
最近のわたしは、もう一歩進んで、「しあわせ」ついて考えるようになったので、そのことについて書いてみようと思う。
大病して余命宣告まで受けたのに、死ななかったわたしは、生きている「自分」に、まずは「安堵」した。
だから、まず、「死なずに」「生きている」ことは、「しあわせ」なのだということに、間違いはない。
でも、それは、最低線であって、それだけで充分ではないはずだ。
では、人は、「何」によって、より、高次元の「しあわせ」を感じることが出来るんだろうか。。
それは、自分が、自分にとって「大好きなもの」と「譲れないもの」とに囲まれた暮らしをしている、ということ、ではないだろうか、と、わたしは感じている。
「大好きなもの」や「譲れないもの」は、「かけがえのない仲間」の人もいるだろうし、「集めたフィギュア」の人もいるだろう。
また、「押しのサインや写メ」だったり、「家族」や「恋人」、さらには「子どもや孫」の「存在」という人もいるだろう。
自分が精力を傾けて築いて来た「仕事」という人もいるかもしれない。
何でも良い。
自分が「大好きなもの」、「譲れないもの」、それだけが、自分に、「しあわせ」をくれる、とわたしは、気付いたのだ。
余命宣告を受けて、「死」を隣りに感じたとき、一番先に思ったこと、それは、
「わたしはもう、大好きな人たちや、大好きなものたちを、見ることも聴くことも出来ない。」
という事実であった。お金とか、社会的な地位とか、そんなものは、とるに足りないものなのだ、と、こころの底から感じたのだった。
「共に在ること」から、自分だけが切り離されてゆくのだ、と感じたとき、「死の残酷さ」を、恐ろしくも、身近に感じた。
「大好きなもの」や「譲れないもの」で、自分のまわりを取り囲んで生きるとき、「しあわせ」は、もう、すぐそばに居て、わたしを見て微笑んでいる。
では、「大好きなもの」や「譲れないもの」は、どうやったら、間違いなく、認識出来るのだろうか。
それは、「自分に嘘をつかないこと」である。
「本当の自分」だけが、自分にとっての、「大切なもの」や「譲れないもの」を知っているからだ。
「本当の自分」が、どんなに、世間とズレていて、「変なやつ」だったとしても、「本当の自分」を、「世間」の「定式通り」の方式に当てはめようとしてはいけない。
「本当の自分」を嫌い、ないがしろにして、「世間」の「定式通り」に合わせようとした瞬間に、「しあわせ」は逃げてゆく。
わたしは、「突拍子もない」発想をするし、同世代の人たちとは気が合わないからお友達もいないし、大好きなものは、「矛盾」や「孤独」で、「声」や「音」に、やたらに拘っている「変な人」だけれども、そんな自分を許したところから、少しずつ、「しあわせ」はやって来た。
だから、わたしは、「変な自分」を「好きになる」ことにした。
「世間」に合わせた「自分」を「演出」しようとしていた時期には、いつだって、「不幸」が隣リに居たように思う。
そして、「本当の自分」をないがしろにしていたから、「しあわせ」は、わたしにそっぽを向いていた。
「本当の、変な自分」を好きになって、「世間の定式のしあわせ」に合わせることなど、きっぱりとやめてしまった今のわたしに、「しあわせ」は、優しく微笑んでくれている。
わたしの部屋には、聴き続けて来た二千枚以上のCDと、大好きな文学書がぎっしり詰め込まれた書棚もある。
わたしは、「大好きなもの」に囲まれて暮らしている。
そして、わたしを放っておいてくれる「優しい夫」も居る。
わたしにとって、譲れないほどに大切な、「矛盾」も「孤独」も、「こころの自由」も、全てわたしのまわりに揃っている。
「しあわせ」は、「山のあなた」に住んでいたりはしない。だから、「しあわせ」を見つけられなかったからといって、泣く必要はない。
「しあわせの在りか」について、「世間の人たち」の「言葉」に惑わされたり、無理に合わせたりしてはいけないのだ。
なぜなら、
「しあわせ」は、あなたが気付きさえすれば、いつだって、あなたのなかに、ちゃんと、存在していて、あなたに向かって微笑んでいるのだから。
