
奥が深い摩擦の世界
みなさんは摩擦という言葉を聞いたことがあると思います。しかし、その詳細を説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか。
いやいや、摩擦熱とかの摩擦でしょ、ものをつかむときに必要な現象でしょ!と言われるかもしれませんね。
それぐらい私たちの身近なところにあふれている摩擦ですが、摩擦が起きている表面で何が起きているか説明できますか?
少なくとも勉強する前の私は、あれどういうことだっけ?となりました。当たり前すぎて、実はあんまり理解していない摩擦の世界を一緒に見ていきましょう。
摩擦とは
そもそも摩擦とは何でしょうか。
摩擦(まさつ、英: friction)とは、固体表面が互いに接しているとき、それらの間に相対運動を妨げる力(摩擦力)がはたらく現象をいう。by wikipedia
なんだかわかったようなわからないような表現ですよね。
一番気になるのは、この運動を妨げる力(摩擦力)がどこからやってくるのか?というところです。今回は、高校では学ばない摩擦のミクロな世界を少しだけ紹介します。そこには、高校生の頃は考えなかった興味深い物質の関係性が見えてきます。
まず、高校で習う摩擦力では、摩擦係数というものが出てきます。この摩擦係数っていうのがいったい何なのかわからないまま、高校物理は終わってしまいます。
テストでは計算などもしましたが、摩擦係数が大きいと、摩擦力が強くなるってことぐらいしかわかりませんね。
また、摩擦には見かけの表面積が影響しないというも有名な話です。でも、面積が広い方が摩擦がたくさん働くようにも感じますよね。これが直感とは異なるところです。そんな感覚とはずれる、ちょっと良くわからない点を、少しずつ紐解いていきましょう。
摩擦をミクロの世界で見てみると
私が10年ぶりぐらいに改めて考え直して、疑問に思ってしまったのは面積の問題です。昔習ったことと感覚が合わないんですね。
しかし、これは調べてみると非常にわかりやすく説明することができることがわかりました。ここではわかりやすいように机の上にブロックが置いてある状態を考えてみましょう。

そもそも私たちが見ている面積というのはブロックと床の接する面積のことです。しかし、ミクロな世界で見てみると実はブロックは床に全部接しているわけではないんです。

なぜなら、ブロックも床もミクロに見てみると凸凹しているんです。私たちの目で見てもわからないぐらいの小さな隙間があるわけですね。つまり、見た目の面積と実際に触れている(摩擦が働く)面積とは異なるということです。
この本当に接触している面積を真実接触面積といいます。重要なのは、この真実接触面積の方だったのです。
そして、真実接触面積はブロックの重さによって変わります。ブロックが重いほど、ブロックは凸凹の表面を押して実際に接触する面積(真実接触面積)が大きくなります。
実際に、摩擦が働く面積が増えるというわけです。
そうです。摩擦力が物質の重さ(垂直抗力[N])と摩擦係数で表されるというのはまさに真実接触面積が変わるからだったということです。
摩擦にもいろいろ種類がある
ここまでは床にブロックが置いてあるのを想定しましたが、その床が水や油で濡れていたらどうでしょうか?
ツルツルして摩擦が小さくなる気がしませんか?
まさに摩擦には大きく分けていくつかの種類があります。
乾燥摩擦
その名の通り、乾燥した表面に生じる摩擦です。最初に考えていた、床とブロックの間に水や油がない状態ですね。これは凸凹の空間に空気が挟まった状態になります。

境界潤滑
床とブロックの間に若干の流体(水や油)が挟まった状態です。ただ、この状態ではまだ摩擦力が高いままです。さらに流体の量が増えて真実接触面積が減っていくと、混合潤滑、流体潤滑へと推移します。

混合潤滑
床とブロックの間の流体が増えてきて、真実接触面積が減ってきた状態です。この状態では、乾燥摩擦や境界潤滑よりも低い摩擦力を示し、ツルツル感を増していますね。ただし、まだ床とブロックが直接接するところがわずかに残っています。
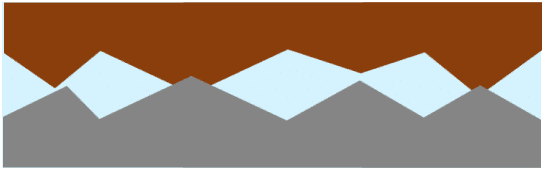
流体潤滑
最後に、床とブロックの間が完全に流体で満たされている状態です。もはや床とブロックが直接接する箇所がなくなっています。この状態になると、摩擦力は床とブロックの関係ではなく、間に挟まっている流体の特徴が重要になるんですね。
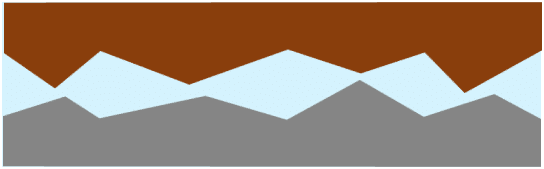
そして、実際に接触する面積(真実接触面積)と物質固有のせん断応力の組み合わせで、摩擦力が決定されるということのようです。
今回は、非常にざっくりと紹介しましたが、摩擦を1つとってもかなり複雑であることがわかります。このような摩擦の世界というのは学問ではトライボロジーという名前がついています。
あまり聞きなれないかもしれませんが、あらゆる摩擦に関することにつながるので私たちの生活に大きな影響を及ぼすといえるでしょう。
最後に
今回は、摩擦について簡単に紹介してみました。私自身あまり深く考えたことがなかった物理の世界ですが、非常に面白いなと感じました。
