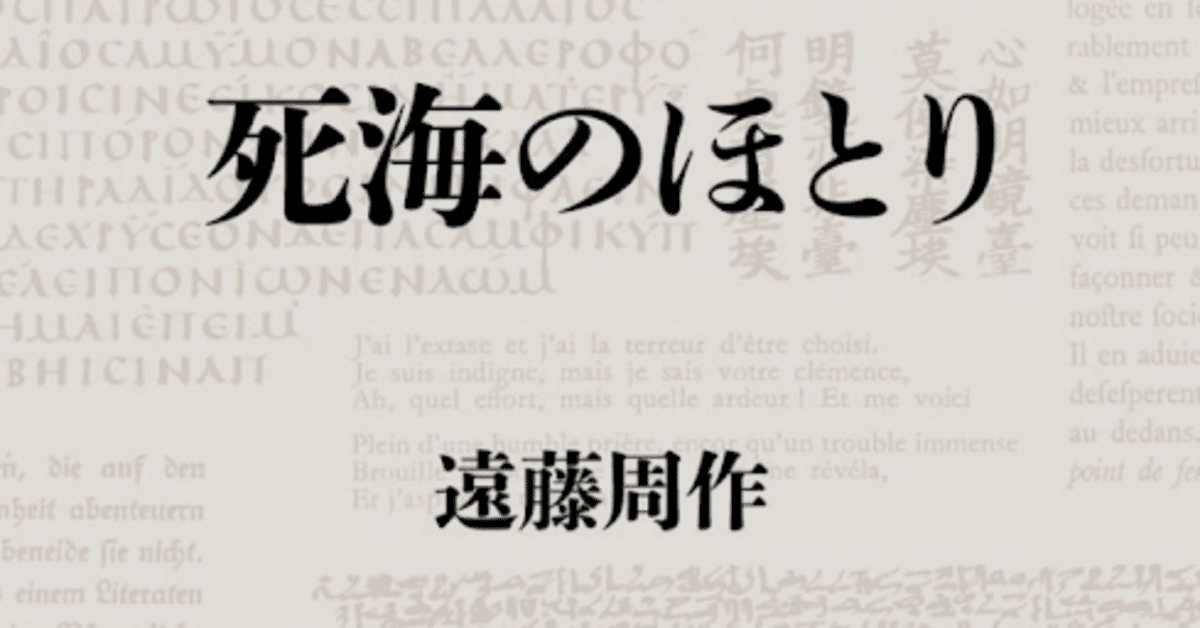
遠藤周作「死海のほとり」
本書を読むのは、3回目になります。
1回目は30代前半、2回目はそれから5,6年経ってからでしょうか。
もともと遠藤周作は、ユーモア小説ともいえる「狐狸庵閑話」などを読んではいました。
30歳のころに聖書を読むキッカケがあり、それ以後キリスト教関連の小説や解説書などを読み始めました。
そのキッカケは、以下のnote記事として書きましたので、興味のある方は覗いてみてください。
本書は、ヨーロッパを旅行していた筆者が足を延ばしてイスラエルにきたところから始まります。
目的は、イエスの足跡を辿ることによって自身の信仰に対する葛藤への区切りをつけるためです。
20数年前にキリスト教系の学校の寮生活をともにしていた戸田を訪ねて案内をしてもらいます。
戸田は、当時(第2次世界大戦の戦時中)、信仰の熱い寮生でしたが、5,6年前に聖書学を研究のためにイスラエルに来ており、現在は国連機関の事務所で働いています。
筆者自身と戸田が、イエスの足跡を訪ね歩きながら二人がイエスに対する思いを語る章とイエスの教えとその弟子たち、イエスの十字架による死刑までを綴る章とを交互に対比しながら話が進められます。
そのなかで、筆者が寮生の頃に関心を持っていた神父の助手、ポーランド人のコバルスキ
「ねずみ」と呼ばれていた弱い男のことが、本書の核心となっていきます。
コバルスキは、狡く立ち回る男で寮生からは軽蔑されていました。
コバルスキは、収容所に入れられたということを聞きますがその後の消息は不明でした。
同じ収容所にいた人を尋ね探し当てて、最後は収容所のガス室に送られ死んだことを知りました。
筆者の心中には、十字架のイエスの死とガス室の「ねずみ」の死が重なり合います。
本書から以下を引用します。
(遠藤周作. 死海のほとり(新潮文庫)新潮社. Kindle 版 )
(イスラエルにきた思い)
自分 の 意志 で なく 親 から 一つ の 宗教 を 選ば さ れ た という こと は 後に 私 の 心 に 重荷 となり、 幾度 も 棄てよ う と し た もの だ。 その くせ 棄て た あと、 自分 が どう なる のか、 何 を する のか 自信 も なく、 心 の 奥 で この 矛盾 に 決着 を つけ ね ば なら ぬ と 何時も 言い きかせ て き た ので ある。 ローマ で 急 に エルサレム に 行こ う という 気 に なっ た のは、 あるいは この 決着 を 今度 は つけ て みよ う という 心 が 働い て い た の かも しれ ぬ。
(ガス室送りとなったねずみのを見ていた人の証言)
うし ろ で 私 は じっと それ を 見送っ て い まし た。 コバルスキ は よろめきよろめき ながら 温和 し くつ い て いき まし た。 その 時、 私 は 一瞬―― 一瞬 です が、 彼 の 右側 に もう 一人 の 誰か が、 彼 と 同じ よう に よろめき、 足 を 曳き ずっ て いる のを この 眼 で 見 た の です。 その 人 は コバルスキ と 同じ よう に みじめ な 囚人 の 服装 を し て、 コバルスキ と 同じ よう に 尿 を 地面 に たれ ながら 歩い て い まし た……
(イエスの死とねずみの死)
その こと を 考え た 時、 私 は 泣き だし たかっ た。 そんな 気 に なっ た のは、 私 の ねずみ が こんな 惨め な 石 鹼 に 変っ て しまっ た のに、 イエス だけが 栄光 ある 死 を とげ た と 思え なかっ た から だ。 (そう です) もし イエス が そば に い たら、 私 は こう 言い たかっ た。( あなた も 石 鹼 に なっ た。 それ は 知っ て い ます。 だから あなた は、 私 の ねずみ も 石 鹼 にさ れ た のか)
(結末)
この旅 で 私 に 付きまとっ て き た のは、 イエス だっ た か、 ねずみ だっ た のか。 もう よく わから ない。 だが、 その ねずみ の 蔭 に あなた は 隠れ て い た のは 確か だ し、 ひょっと する と、 あなた は 私 の 人生 にも ねずみ や その ほか の 人間 と 一緒 に 従い て こ られ た かも しれ ぬ。 ~ 中略 ~ 私 の 書い た ほか の 弱虫 たち。 私 が 創り だし た 人間 たち の その なか に、 あなた は おら れ、 私 の 人生 を 摑 まえよ う 摑 まえよ う とさ れ て いる。 私 が あなた を 棄てよ う と し た 時 でさえ、 あなた は 私 を 生涯、 棄てよ う とさ れ ぬ。
わたしはクリスチャンではありませんが、主人公の心中、葛藤に感銘を受けます。
きっと結論など出せないことでしょうが、主人公の精神性に崇高なものさえ感じてしまいます。
いったいなぜなのでしょうか。
わたしには理解することはできないのですが、必死にイエスに向き合っている主人公の姿勢に、わたし自身が浄化されるような心持ちになるのかもしれません。
本書は私小説ではないと思いますが、精神的な意味では私小説ではないでしょうか。
わたしは本書を純粋な意味で、小説として読んでいないかもしれません。
イエスに対する主人公=筆者の思いを顕わに表現したものとして受け取っています。
もちろん物語性がないわけではありません。
たぶん戸田もコバルスキも筆者の分身であり、筆者の創作なのでしょう。
遠藤周作は生前にはテレビにもよく出演するユーモアのあるジョークが好きな人だった、と記憶しています。
そのような氏を懐かしく思い出します。
それとともに今回再々読した「死海のほとり」での主人公(それは遠藤周作自身なのでしょう)の人生に対する真摯な態度に心うたれる思いです。
