
正しくて 楽しい人。
これまでで、いちばんやったこと。
あるく、食べるといった、生活に必要な行為のほかのことで、いちばんやったことはなに?
ときかれたら、多分、本を読むこと、と答える。
ひとりで本を読むのが好きなのは子どもの頃からで、今もそうだけど、あまり明るい性格ではなかったので、
誰かと何かをするとなったときに、人に気をつかったり、よくわからないルールの遊びに負けて罰ゲームを受けたりするのが嫌だったのもあり、
(自分にとって不利な)つまらない遊びをするくらいなら、「早く帰って本の続きを読みたいなぁ」とおもっていた。
大人になった今も、聞きたいとおもえない話を延々と聞かされる場面があると同じように苦痛で、「早く帰ってあの本の続き読みたいなぁ」って考えている。
それと関係があるのかどうかはわからないけど、最近たてつづけに、おすすめの本をたずねられたり、どんな本を読んでいるか訊かれる機会があった。
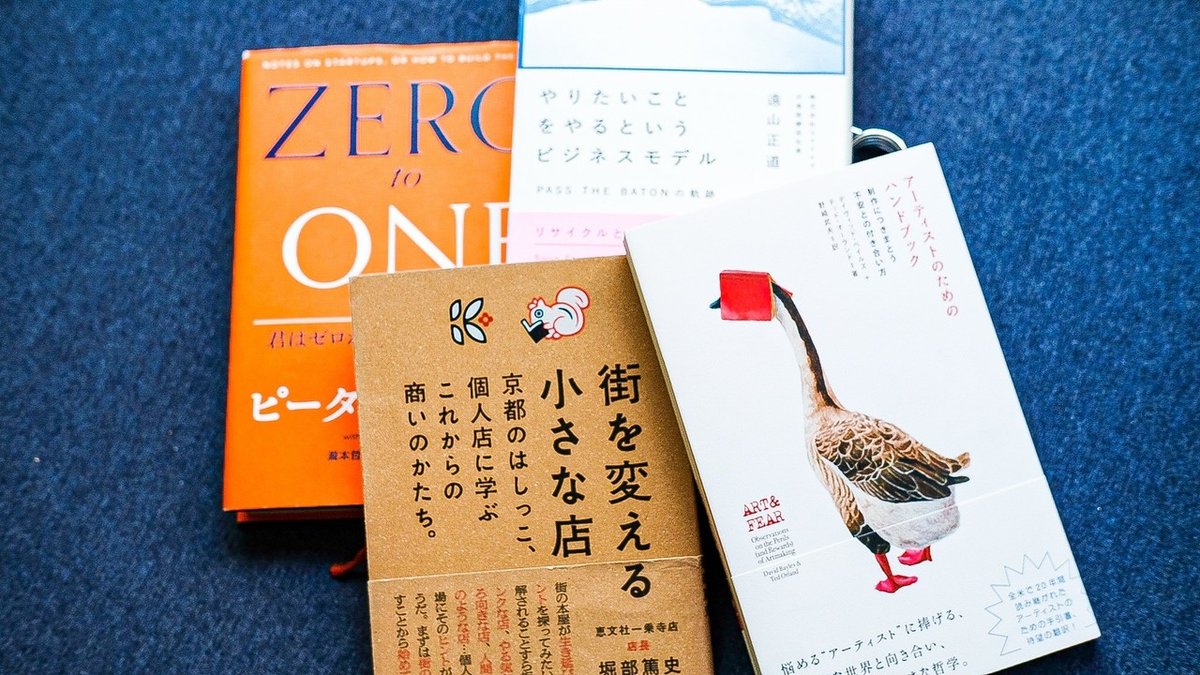
このところ、数年前に読んだものを思い出してもう一度読みたいと感じたり、あらためて2020年の、今の自分に ”必要” と感じて買いなおした本も数冊あって、読むとやっぱりおもしろい。
読んだ数は数えないし、読書目標もない。
読まないといけない本もないし、読まないと決めているジャンルもない。
決めごとを持ち込まないのは純粋に読むのが好きで、たのしいからなのかもしれない。
読み終えたらすぐに手放す。
otherwise 増えすぎて大変なことになるから、手持ちの本はワイン箱2つ分と決めている。読みたくなったらまた買ったり借りたりすればいい。
テンポラリーな滞在をベースにいろんな場所で暮らしていた頃から、ずっとそんなふうに、本を読んできた。

今日はこの本の話を。

《アップルを創った怪物--もうひとりの創業者、ウォズニアック自伝--》
彼が本を出すことを決めた理由はこちら。
(帯文抜粋)
僕はアップルを退社したことになっているし、不満があったから退社したことになっている。どっちも違うんだよ。
でもさ、これは二つとも、事実として歴史に残ってしまった。アップルの歴史について書いた本、どれでもいいから読んでごらんよ。まず間違いなく、間違ってるほうの話が載っているから
えっ、と思う方もいるかもしれない。
2020年2月の時点では、彼はアップルから週給を得ている唯一の社員だと言い、その額も明かしている。
本書は、いたずら好きの機械オタク少年時代から(膨大なインタビューを経てライティングされたことに由来する)ウォズ自身の語りで進んでいく。
《まず間違いなく、間違ってるほうの話が載っている》本が多くあるなかで、これは貴重だとおもう。

スティーブ・ジョブズの話をするひとは多いけど、スティーブ・ウォズニアック(ウォズ)の話をするひとはそれほど多くない。
アップルというブランドそのものに興味がなければ、iPhoneやMacBookを使っていても、《こっちのスティーブ》の存在を知らない人も多いとおもう。
でも、私にはウォズの視点、ウォズの経験から紡ぎ出されるストーリーがおもしろかった。
素直で、【自分が正しいと思うこと】を口にしているひとの言うことはいつもおもしろい。
実際に正しいかはわからない。
でも、おもしろい、と人に感じさせる何かがある。
たとえば、
アップルの草創期、ふたりのスティーブがやり遂げた仕事のエピソード。
報酬はジョブズが受け取り、「700ドルもらった」とウォズに伝えてその半分をウォズは受け取った。
しかし実際には2000ドルから3000ドルが支払われていたことをあとで知る。(ジョブズがピンハネしていた?)
ウォズはそれについてこう述べている。
ウソをつかれたんだから、そりゃ傷ついたよ。
でも、だからといってどうこうしようとは思わなかった。
これは有名な話のようで、ウィキペディアにも記載がある。
ジョブズがアタリの技師になったころ、ブロック崩しゲームである「ブレイクアウト」の設計を命じられた。
ジョブズは自身の手に余る仕事であることを認識。
すぐにウォズニアックに助けを頼んで、2人は4日間の徹夜でブレイクアウトを完成させた。
ジョブズは報酬の山分けをウォズニアックに提案し、アタリから受け取ったとする700ドルのうち350ドルを小切手にしてウォズニアックに渡した。
しかし、実際にはジョブズはアタリから5000ドルを受け取っていた。
後にウォズニアックの知るところになるが、彼はたとえ25セントしかもらえなくても引き受けただろう、と語った。
(スティーブ・ゲイリー・ウォズニアックのWikipediaより)
お金にならないことでも、やったほうがいい場合は確かにある。
お金にならないことをやる価値とは。

これは実感から言えることでもある。
何もできなかった頃、何をしていいかわからなかった頃に、とにかくいろんなところにいろんな経験をしに行った。
その頃のメモにはこんな記載が。
「お金にならない経験には、お金にはならないが《何か》がある、
大事なのはその《何か》のほうだ。」
これもその頃読んだ何かに書いてあったことだ。
当時は、何もない自分が嫌でたまらなかったし、その中身のなさ、からっぽさに耐えられなかった。
海外で時間を過ごして、いかに自分の人生について考えてこなかったか、流されて決めてきたかということを見せつけられたとき、
何とかしないといけない、とわかったことは救いだったけど、
やってみたいとおもうことは、お金にならないことが大半で、行ってみたいとおもう場所に行くには、お金が必要だった。
でも、「お金にはならないが《何か》がある経験」を得るために、必要なぶんだけを逆算して稼ぎ、それ以外の時間は《経験すること》に費やした。
自分でやってみることができる経験、いいこともそうでないことも、ともかく自分で引き受けてみることのできる時間がほしかった。
「知っていることの少なさ」「やったことがあることの少なさ」を痛感していたからだとおもう。
これかな、ちがうかも、やっぱこれかな、あー、やっぱちがうわ、
っていうことを繰り返してきて、今はなんとか、これかも、とおもえることをできてはいる、というより、やっと始めることができたくらい。
選択に迷うとき、最後に強めのヒントになるのは、お金にはならなかったけど、なぜあれをやったのだったか、という経験の動機の部分にあった。
お金が得られないのはいったん不利益でもあるが、それ以上に、
《それでも》やりたいとおもったのは何故だったのか、という自分自身の《譲れなさ》がわかることには価値がある。
今につながる大きなヒントはいつもそこにあったような気がする。

同じ日に死ぬ二人の男
ウォズはアタリ社の報酬の件に、自身の倫理感や考え、ジョブズとの関係について触れたあと、
ちょっと変な話なんだけど、と続ける。
(最終的にアップル i ボードになるものを作り始めたころ)同じ日に死ぬ二人の男のことが頭に浮かんだ。
片方は成功者。
会社を経営し、いつも目標の売上げを達成し、利益を出し続けるんだ。
もう一人はのらりくらりとしてて、お金もあんまり持ってない。
ジョークが好きで、世の中でおもしろいと思うこと、変わった装置とかテクノロジーとか、なんかかんかを追っかけ、ただただ笑って人生を過ごすんだ
具体的な人物は書かれていない。そしてこう続く。
【物事をコントロールする人より、笑って過ごす人のほうが幸せだって、僕は思う。それが僕の考え方なんだ。】
この2行が、自分にはもはや結論だった。
いちばんピンときたし、グッときた。
自分自身が何より楽しさを大事にしているのに、長くその理由をスパッと答えられずにきたからかもしれない。
言葉にできずにいたことを、言い当てられたような気がするとき、それは自分の言葉に変換しやすくなり、同時に理解のレベルがグッと上がる。
本の力はすごくて、
どんなに親しい誰かの、自分だけに向けられた励ましよりも、会ったこともないひとの、大勢に向けられた言葉のほうが響くことはあって、
ひとは、言葉以上に、共通の体験をとおして語りかけることができる。
これまでそういうヒントをたくさんの本から、たくさんの著者からもらってきた。



「そんなに楽しさって大事?」
自分でそうおもったことはない。大事にきまってるし、疑ったことはない。
でも、面と向かって言われたことはある。そして答えられなかったことがあった。
言ったって伝わらない。また否定されるだけ。
そういう思いこみがあったのだとおもう。
それでも、言い続けないとなかったことになってしまうし、伝わる相手に向ければいいのだと今はわかるのだけど。
ウォズは続ける。
だから、ブレイクアウトで起こったこと(先の報酬の額でウソをつかれたこと)なんかも気にせずにきた。
もちろん違う考え方もありうるし、あのとき、関係を絶ってしまうという考え方だってある。
でも、だからといって相手を批難しなくてもいいと思う。みんな違うんだ。そう思って暮らすのが一番いいし、幸せになれる方法だと僕は思う。
日本語版訳者の井口さんによる訳者あとがきには。
仕事を楽しみ、ジョークを楽しみ、いたずらを楽しむ。
人生、とにかく楽しまなきゃ損だとばかりに楽しみまくっている人物である。
本人も語っているが、アップルという企業の特色にいろいろな意味で「楽しい」が入る理由は、創業者の片割れであるウォズのこの性格があるのかもしれない
信念は意図せず滲み出る。
自ずと反映されるものなんだよね。
大事にしていることだから、そうなるんだよね。
なんとなく難しい顔をして否定的な意見を言ってみるのが、重要そうに聞こえたり、黙って決められたことをやることが真面目みたいにされてしまっていたり、
楽しむことを認めようとしない雰囲気がある場面は多いのに、
楽しんじゃいけない理由を答えられるひとは少ない。
というか、それはたぶん、ないのだとおもう。
楽しんじゃいけない理由はない。
成果と楽しさはトレードオフじゃない。

正しくて 楽しいひと。
真面目さという正しさも持ちながら、楽しく行える人が求められているとおもう。
楽しく行えるひとは、楽しく行おうとする人、だ。
the person who is trying to make it fun.
それを楽しいものにしようとする人。
it は仕事かもしれないし、生活かもしれないし、挑戦かもしれないし、後片付けかもしれない。
この【 trying to 】の部分に姿勢や人柄が表れるという話は以前も書いたけれど、trying to という《進行形》からもわかるように、これはその時点での、できる、できないを問うものではない。
何をしようとしているか、どうあろうとしているか、どこに向いているかの部分だから、全部に影響するからこそ、滲み出るのだし、違う言いかたをすれば、絶対にバレるとおもう。
正しくあろうとすることで得た信用を頼りに、楽しくしようとする姿勢でいい時間をつくりだす。
そんなことを求められている気がする。

《正しくて楽しい人。》
自分はそうありたいし、そういう人が大好きだし、周りにいてほしいとおもう。
どちらかだけではなくて。
正しさとたのしさは矛盾するものではないし、相反もしない。
バランスをとればいいだけだ。
言うほど簡単ではないこともわかる。だからこそ、そういう人が好きなのだ。
彼らは負の連鎖を断ち切っている。ものすごくかっこいい。
何もわからなかった頃に、そういう大人が周りにいてくれたことで、自分の中に勇気の種のようなものが蒔かれたのかな、と今は感じている。
そういうことを大事にしていっていいんだ、堂々とそれを言っていこう。
そんな気にさせられた本。
いい本は、自分の答えを強化してくれる。
正解をくれるのではなく、結論を見つける助けをしてくれる。
(グッときたエピソードは198、199ページにあります。)

今日は本の話をしました。
読んでいただきありがとうございます。
好きな本を好きなように、好きなだけ読むのが好きです。
お仕事のご相談、お問い合わせはこちらに。
chieoikawa5@gmail.com
からも受け付けています。
よろしくお願いいたします☺︎
いいなと思ったら応援しよう!

