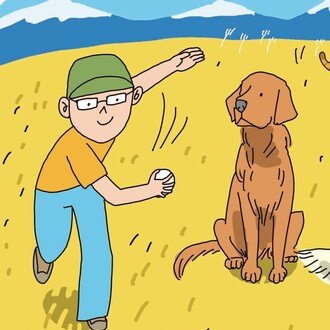ここまでわかった犬たちの内なる世界 #13 思いやり〜イヌが”最良の友”になるとき
イヌの「親切心」や「思いやり」を示す行動が、ニュースやSNSで話題になることがあります。
中でも筆者にインパクトを与えたのが、イヌが交通事故に遭いそうになっている仲間のイヌを助け出す動画です。 一時期、その動画やそれと似たような動画が拡散されてネット上を賑わしていたので、ご覧になった方も多いことでしょう。
今回は、「思いやり」をテーマに犬たちの内なる世界を探っていきたいと思います。そこで、まず最初に、1つの仮説を立ててみたいと思います。
イヌの「思いやり」は、《 》、仲間への共感、 友情、 一緒に行動することで生まれる連帯感など様々なポジティブな感情と結びついている
上記太字の2行が仮説です。あえて空欄をつくりました。 仮にあなたがこの仮説をある程度支持するとすれば、《 》 にどんな言葉を入れますか?
筆者が空欄に何を書き込んだかについては、最後に明かしますね。種明かしをしておくと、ポジティブな感情の1つで、単語(名詞)です。
イヌは孤独を嫌う
犬がなにより望むことは何だろう? それは集団に帰属すること、仲間を持つことであるーー と、エリザベス・M・トーマスは『犬たちの隠された生活』の中で綴っています。
八ヶ岳山麓の牧草地を拠点に “半放し飼い”のイヌたちを観察していた頃の筆者は、 先入観なしにイヌを観ることに徹しようと考えていたので、 イヌ関係の本をいくつか揃えたものの、ほとんどは “積ん読 “にしていました。
八ヶ岳のフィールドワークを終えてから『 犬たちの隠された生活』を熟読すると、 イヌたちの社会生活についての精緻な描写に惹かれたのは言うに及ばず、同書の中で語られる世界観にインスパイアされ、自分のフィールドでの体験がより鮮明に印象づけられました。
また、「あの時のあのイヌの行動、あの出来事は、なるほどそういう意味だったのかもしれない」といった自身の観察に意味付けを可能にするような描写も発見することができました。 その内の1つが、この項の冒頭に引用した「集団に帰属すること、仲間を持つこと」です。
実際に、筆者の体験的実感として、イヌは仲間を持つことに幸福感を抱くことは疑いようのないことだと思います(その仲間がイヌではなく人間であっても)。
そして、集団への帰属というと少し堅苦しく感じるかもしれませんが、イヌたちは連帯感(のようなもの)に心地よさを感じているのではないかと思います。
言い換えれば孤独を嫌うということです。
というわけで、 八ヶ岳山麓の牧草地での”イヌの集団”をめぐる話から始めましょう。
例年以上に積雪が多かったその冬は、 散歩するイヌたちは自力でラッセルして歩かなければなりませんでした。

この写真の場面の後、まもなく何が起こったかと言えば、改めて⏫見出し画像をご覧ください。

状況説明をすると、1歳半の雌のゴールデンレトリバー(奥)が少し遅れをとった4歳の雄(手前)を気遣って振り向いています。「 思いやり」を示しているのです。
父子の絆に “イヌの不思議 “を垣間見る
同じ年の夏、筆者の記憶に残る印象的なシーンに遭遇しました。
#04「イヌは仮説を組み立てる?」で筆者とふざけ合いの遊びをするイヌとして紹介した「トロフィーの息子」が、けがを負った「アビー」という名のわが子を慰めている場面なのですが、そのタイミングが絶妙だったのです。そのわずか5分前にアビーは同年代の2歳の雄に挑発されフェンス越しに近づいたところ、 鼻面に牙を当てられてしまいました(フェンス越しに激しく吠え合うということはイヌの世界では珍しくないことなのです。 ほとんどが同性間で行なわれます)。
トロフィーの息子は、その様子を目撃していませんでしたが、 アビーの異変を察知したらしく、 まもなく姿を現しました。 物理的に目に見えない位置にトロフィーの息子がいたにもかかわらずアビー のもとへ駆けつけたのです。
父イヌがわが子に対して、はっきりと思いやりを示したのです。

それにしても絶妙のタイミングでした。
たまたまそこに来たら、わが子が傷ついていたので慰めたということに過ぎないのかもしれません。 しかし、その時の筆者は別の解釈をしました。 言葉ではうまく説明ができない何か特別な力が働いたのではないか、 あえて言うなら、イヌが独自に持つ超感覚的知覚のようなものが働いたのかもしれない。一連の流れを目の当たりにした筆者には、 実感としてそう思えたのです。
超感覚的知覚というのは、過剰な言い回しというべきでしょうか。イヌはその鋭い嗅覚によって、現実には目で見てない世界を「見る」ことができるのです。 この点については、コラムの終盤で直近の研究成果なども紹介しつつ、ご説明します。
産後のキャロンを気遣った”迷い犬”
牧草地には、常時少なくとも30頭のゴールデンレトリバーを始めとする大型犬が 自由に行動しています。 いつでも仲睦まじくというわけにはいかず、 前述したアビーのように、けんかを仕掛けたり、けんかに巻き込まれたりをすることもあります。 感心したのは、けんかを未然に防ぐために間に割って入るイヌがいることです。
こんな場面がありました。
8月も終わりを迎える頃のことです。産後間もない ゴールデンレトリバーのキャロンが独立棟の個室で子イヌたちに授乳していました。 キャロンは子育て上手の立派な母イヌでした。
八ヶ岳の高原地帯です。夏場でもクーラーは必要ありません。風通しを配慮して部屋のドアは開放されており、外から中の様子がうかがえる状態でした。

キャロンを目がけて、盛んに吠え続け、挑発を始めている ゴールデンレトリバーがいます。キャロンと同年代のアンジェロです。 気性の激しいところのあるアンジェロには、相性の良くない同性のイヌが何頭かいました。そのうちの1頭がキャロンです。
普段は温厚なキャロンですが、この時は苛立ちもピークに達したのか、 その場は一触即発の不穏な空気に包まれました。 無理もありません。 子育ての最中に、 部屋の出入り口に立ちふさがれてワンワンやられるわけですから。
キャロンは牙をむいて応酬しました。この厄介者を何とかして早く追い払いたいのです。
(これはワンワンやってる方を厳重注意だな)
こういう非常時は、写真を撮るより、イヌたちの安全が優先です。筆者は20メートル先にあるキャロンの部屋に向かって一歩踏み出そうとしました。
その時です。 アンジェロの背後からするりと手が伸びました(つい「手」と書きましたが、実際には前脚です)。彼女を抱え込んだ”第3のイヌ”が現れたのです。
するり。抱え込んだ前脚はすぐに相手の身体から離れ、その前脚の持ち主とともにその場を通り抜けました。
瞬間。不意をつかれた形になったアンジェロはもう吠えていません。
やれやれ。おかげで事なきを得ました。
そのときの筆者には、この第3のイヌが平和の使徒の如くに映りました。
第3のイヌは「サクラ」という雌のゴールデンレトリバー(純潔種ではないかもしれない)で、 やはりキャロンと年齢は近いと推定されます。なぜ「推定」なのかというと、 元は"迷い犬"だったからです。

サクラは「社会化」が不足しているように見受けられ、 普段は落ち着きがなく、矢鱈と「 要求吠え」 が多く、 人への飛びつき癖もあるという次第で、筆者の頭を悩ますことも多々ありました。しかしこのときばかりは、サクラに救われたような気分になったのです。
以上、 八ヶ岳山麓の牧草地という空間でイヌたちが垣間見せた「思いやり」行動についてのちょっとしたエピソードをお話ししました。
オオカミの騎士道
皆さんの中には、 少年少女時代に『シートン動物記』を読んで育った方がいらっしゃるのではないか、と推断します(筆者もその1人です)。
「シートン」の名を聞くと、物語作家のイメージを思い浮かべる人が多いと思いますが、実は優れたナチュラリストであり、 膨大な量のノンフィクションを残しています。
物心両面の応援は、いつでも歓迎しています。 皆様からのチップは、より良い作品づくりのために自由に使わせていただきます。