
友達に教えたいリスクとお金の話(9-3)
引き続き債券のリスクを考えます。今回は「信用リスク」です。
3)信用リスク(発行体のリスク)
信用リスクとは、国や企業などが債券の元本や利金の支払いができなくなる「債務不履行(デフォルト)」のリスクをいいます。「デフォルトリスク」と呼ぶこともあります。
コラム6「債券の信用リスクと格付け」で見たように、信用リスクが低い発行体とその発行体が発行する債券は、より高い利回りを提供し、投資家を引き付けようとします。しかし高い利回りは、債券の償還期限が来るまでの数年間(長期債の場合は10年かそれ以上)、利払いが予定通りにされない、償還日が来ても元本が返ってこない、という「デフォルト(債務不履行)」のリスクをとった代償なのです。
デフォルトリスクがリスクのまま顕在化せず、無事利息も元本も予定通り払われる場合もありますが、実際にデフォルトが起きると、数年単位で元利払いが遅れ、最悪の場合は部分的にしか(あるいはまったく)支払われないケースもあります。
このデフォルトリスクがどの程度かを示す指標が「信用格付け」です。ムーディズやスタンダード&プアーズなど第三者機関である格付機関が公開された情報をもとに分析して出す指標です。信用格付けが高いほどデフォルトリスクは低く、低いほどデフォルトリスクが高いとされます。一つの目安としてBBBマイナス相当までの格付けを「投資適格債」と呼び、それ未満の債券を「投機的格付債」または「ハイ・イールド債」と呼んでいます。
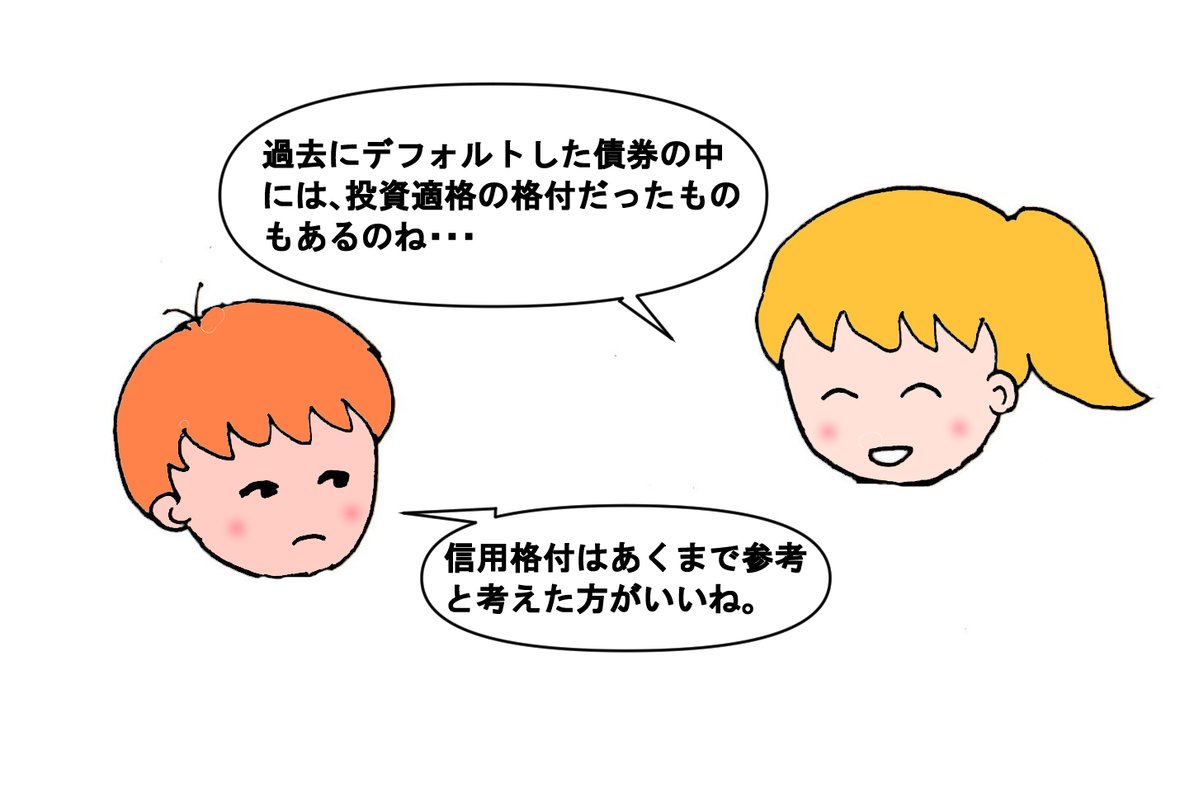
信用格付は万能でないことを念頭に置きましょう。
生命保険会社や公的年金などが債券に投資する時、ポートフォリオの中心に据えているのは投資適格債です。特に、1)金利リスクで学んだ「マッチング運用」をする場合は、途中でデフォルトすればマッチングどころではないので、投資適格債の、比較的高い格付けの債券や自国通貨の国債を選んで行います。
こうした機関投資家は、ハイ・イールド債にも一部投資を行いますが、その場合は非常に多くの銘柄に分散投資をして、仮にデフォルトがあっても影響が最小限になるようリスクを抑えています。

信用格付は万能ではないことを念頭に置きましょう。
ここで気をつけたいのは、外国の国債の扱いです。国債であれば安心だと思いがちですが、投機的格付けの国債もあります。投機的格付けの国債は「新興国国債」として市場で扱われます。
国債であっても投機的格付けの債券には、個人投資家は手を出さない方が無難でしょう。それでも、投機的格付け債券の高利回りを享受したいと思う場合は、投資信託を通じて、多数の銘柄に分散投資をすることです。またハイ・イールド債や新興国国債の投資信託に投資する割合は、株式ほどではないものの、一般的な債券よりリスクが大きいという認識を持っておくことが重要です。(次項に続く)
