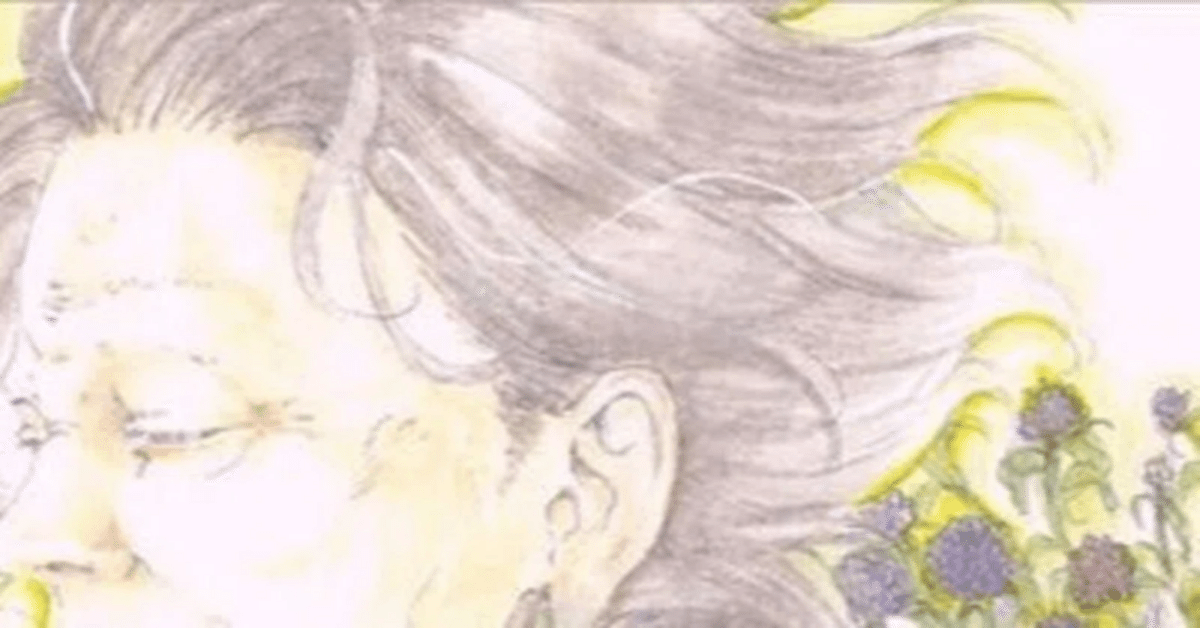
【知られざるアーティストの記憶】第84話 S医院のバイ・ディジタル O-リングテスト
Illustration by 宮﨑英麻
*彼は何も遺さずにひっそりとこの世を去った。
知られざるアーティストが最後の1年2ヶ月で
マリに遺した記憶の物語*
第12章 S医院に通う日々
第84話 S医院のバイ・ディジタル O-リングテスト
「今度は、ワダさんだけお入りください。」
扉の向こうからT先生の声がした。
「ワダさんだけだって。」
彼はマリと目を見合わせてから、診察室に入って行った。S医院の施術に好奇心を持つのはむしろマリのほうなのに、マリにはその見学が決して許されなかった。扉の向こうを覗き見たい衝動を抱えながら、時々かすかに漏れ聞こえる話し声に耳を凝らすしかなかった。
やがて診察室から出てきた彼は、先ほどは土気色だった頬を真っピンクに紅潮させていた。どんなことをされたのかを一通り話した後に、
「けっこう痛いんだよ。」
と言った。先生の著書には、施術に伴う苦痛は耐えられる程度だと書かれていたが、普段痛みや苦痛をあまり口にしない彼が「けっこう痛い」と口にするほどなのであった。
注目の「バイ・ディジタル O-リングテスト」による測定結果がB5を半分にした用紙に記入され渡された。測定項目およびこの日の治療前の数値はこのようであった。
今日の最終測定値
(令和4年1月27日)
反応 4+ / 3+ / 2+ / 1+ / ー
水銀 1.5g( 0 )
遺伝子抗体 81ng( 0 )
テロメア 195ng( 0 )
アセチルコリン 113㎍(1500以上)
テロメア 11ng(100以上)
インターフェロンγ 11ng(70以上)
(カッコ内 基準値)
マリにも彼にもこの数値の意味はさっぱり分からなかった。マリがこの日の帰りに買い求めたT先生の著書には、それぞれの数値に関する説明がごく簡単に書かれていた。「テロメア」には「癌テロメア」ともう一つは失念してしまったが、二種類あった。それぞれの数値がカッコ内の基準値であることが望ましく、すべての結果を総合して一番上の「反応」が「4+」から「-」までの中から判定される。これは、体がどれだけ癌体質に傾いているかを表すもので、「4+」が最も悪く、「-」が健康な状態である。1月27日の治療前には、「4+」に丸が付けられていた。
治療後の測定結果には、下の3つの数値しか記入されていなかった。それは、その後もずっと同じであった。アセチルコリン、テロメア、インターフェロンγの3つが、S医院の癌判定の要となる数値のようであった。治療後にはアセチルコリンが113から200へ、テロメアが11から76へ、インターフェロンγが11から46へ、それぞれ急上昇していた。たった一回の治療でここまで改善するというのは逆にいぶかしくもあったが、これらを信じるのであればS医院の治療効果のすばらしさを物語っていた。むろん、抗がん剤を拒否してS医院の門をくぐったからには、この馴染みのない数値を信じるように努めた。

この日の会計で彼は、初診料、薬代その他を合計してかなりの金額を支払った。両親が遺してくれた預金をS医院の治療費に当てることを決意したのである。処方された薬および食品は、乳酸菌の粉末、オリーブリーフの粉末、霊芝(サルノコシカケ)のお茶、漢方の補中益気湯であった。おばちゃんはそれぞれの飲み方と飲むタイミングを丁寧に紙に書いてくれた。
その他に、電磁波をカットするためのシリコン製のブレスレットを勧められ、購入した。5000円もするブレスレットを普段の彼なら絶対に買わない。大きな治療費を支払った後であっては「ついで」のようにしか感じられなかったのもあろうが、それほどに彼がS医院の療法に賭けようとしていることがうかがえた。
この日の待合室では、何人かの患者さんと居合わせた。互いに深刻な病気を治療しに来ている者同士、安易に目を合わせたり話しかけるようなことはせず、ただ心の中でその人の境遇を慮った。その中で、マリと同世代くらいの、非常に痩せた神経質そうな男性の姿が妙にマリの心に引っ掛かった。その人が醸し出している、不器用で滑らかさのない神経質さは、イクミの持つ、粒子の細かい妖精のような神経質さとはまた種類が違っていた。S医院の向かいのバス停で帰りのバスを待つ間もその人と一緒になったが、やはり話しかけることはしなかった。
マリはこのあと、彼とどのように家に帰ったのか、または途中で別れたのかについては、なぜか記憶が抜け落ちている。

それ以来、毎週決まった曜日の決まった時間に予約を取り、マリの運転する車で二人でS医院に通う日々が始まった。それは少なくともマリにとっては、抗がん剤から自由になり、彼自らが選び取った療法に二人で一歩を踏み出すことへの期待に溢れ、まるで生まれたばかりの恋の時代のような、ふわふわとした不確かな明るさと喜びに彩られていた。それは、彼のように現実的なリスクや不安と常に隣り合わせでいたわけではなかったからだ。
★この物語は著者の体験したノンフィクションですが、登場人物の名前はすべて仮名です。
