
【白鹿記念酒造博物館 酒ミュージアム】「伝統的酒造りの近現代」をもっと楽しめる! おすすめ本5選
注目の特別展にあわせて、CUMAGUSおすすめの5冊を紹介するマガジン「特別展・企画展をもっと楽しめる!おすすめ本5選」
今週は、白鹿記念酒造博物館(酒ミュージアム)で開催されている「伝統的酒造りの近現代」(2024.12/4~25.3/3)をピックアップ!
本日のブックリストはこちらです!
ユネスコ無形文化遺産に登録!日本の「伝統的酒造り」
江戸時代以降、清酒造りは全国的に行われていきました。とりわけ灘五郷を擁する兵庫県は、主産地として現在でも盛んに酒造りが行われています。
灘五郷の酒造りを担ってきたのは、丹波杜氏と呼ばれる技術者集団です。明治維新以降は、丹波杜氏の卓越した技術が全国各地に移転し、国内の清酒造りの基盤が調えられました。
一方地方では、その土地に根差した軟水醸造法が開発されたた他、比較的容易に酒造りが可能な、山廃酛・速醸酛が普及していきます。
当展示では、伝統的酒造りが歩んだ近現代の軌跡をご紹介します。
兵庫の「灘五郷」といえば、日本を代表する酒どころ。
江戸の吞兵衛たちに珍重された「下り酒(上方から船で運ばれてくるお酒)」の中でも、灘五郷の酒は「灘の生一本」として、特別な地位を築いていたほどです。
現在でも、この灘エリアでは多くの酒蔵が軒を連ねています。
今回取り上げる白鹿記念酒造博物館のほかにも
・沢の鶴資料館
・白鶴酒造資料館
・菊正宗酒造記念館
などなど、酒造りに関する博物館も多数!
……ここはもう、酒飲み文系の聖地では?
そんな灘五郷の博物館と、展示「伝統的酒造りの近現代」をもっと楽しめる、5冊のご紹介です!
オススメ本① ゼロから分かる! 図解日本酒入門(世界文化社)山本 洋子 (著)
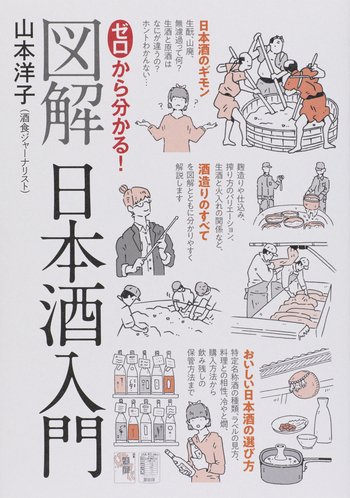
https://books.sekaibunka.com/book/b10102671.html
著者名:山本 洋子 (著)
出版社名:世界文化社
定価:1,650円 (本体1,500円+税)
A5判:192頁
【初心者必携!日本酒のあらゆるギモンをイラストで分かりやすく解説】
お店ではどんな順番で飲むのが良い?」「特定名称酒ってどう違うの?」「ラベルの用語が難しい」「日本酒と料理の合わせ方は?」「このお酒は、冷やと燗どっちで味わうのがいい?」「飲み切れなかった日本酒の保存方法は?」 ……あらゆる日本酒のギモンを図解でわかりやすく解説します。
まずは純米とか吟醸とかよく聞くけど、なんのこと? という初心者さんにもやさしい解説本です。
味はわかってるつもりでも、
「生酛」ってなに? 「山廃」ってなに? 「麹」と「酵母」って違うの?
なんて聞かれると、意外と説明がむずかしいもの。(飲んでると特に)
飲みなれている人も、持っておくと安心!
オススメ本② 日本の酒 (岩波文庫 青 945-1)坂口 謹一郎 (著)

https://www.iwanami.co.jp/book/b247068.html
著者名:坂口 謹一郎 (著)
出版社名:岩波書店(岩波文庫)
定価:935円 (本体850円+税)
文庫判:260ページ
【文化史・社会史を渉猟した醗酵学者による決定版・日本酒読本】
古い文明は必ず美酒を持つ.醸造酒でありながら世界的に見ても珍しい蒸留酒並のアルコール度を誇る日本酒.麴カビから育てた酒の文化史・社会史を古今の書に探り,科学の眼で語る.「火入」「生酛」「山廃造り」等,日本の酒造りの方法はどこが興味深くまた優れているか.醱酵学者・坂口博士(1897―1994)の決定版・日本酒読本.
日本酒の解説本はたくさん出版されていますが、その中でも古典的名著といえばこの「日本の酒」。
日本酒ができるまでの発酵のしくみ、日本酒の歴史、日本酒の味や香りを表現することばまで、広く紹介した決定版です。
「日本酒」と「伝統的酒造り」の成立まで、数々の創意工夫があったことがよくわかる1冊。小泉武夫氏による解説も必読です。
オススメ本③ 日本酒の世界 (講談社学術文庫)小泉武夫 (著)

https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000358922
著者名:小泉武夫 (著)
出版社名:講談社(講談社学術文庫)
定価:1,100円 (本体1,000円+税)
文庫判:256頁
【日本酒の誕生から、その愉しみまで】
縄文時代中期のデンプン酒に始まり、農耕の神に捧げた弥生時代、
平安時代から熱燗を嗜み、戦国の世では酒で契りを交わし、江戸時代には新酒を求めて番船競争まで繰り広げる――。
古来、誕生から葬式まで、一生の儀礼にも欠かせないほど愛されてきた日本酒は、いかに発生、発達してきたのか。
日本書紀や古事記など豊富な史料をもとに、時代ごとの「味」を調べあげ、日々の暮らしと酒嗜みの変遷も考察。造り酒屋に生まれた発酵学の第一人者だからこそ書けた、日本酒大全!
オススメ本②「日本の酒」の解説者、小泉武夫氏による1冊。
縄文から現代まで、時代ごとの酒の味、たしなみ方の変遷を様々な角度から追っていきます。
日本人と日本酒の長く、深いおつきあいを知ると、我々は昔っから酒好きだったんだなぁ、と腑に落ちること間違いなし。
オススメ本④ 酒造りの歴史 第五版(雄山閣)柚木 学 (著)

https://www.yuzankaku.co.jp/products/detail.php?product_id=8994
著者名:柚木 学 (著)
出版社名:雄山閣
定価:4,620円 (本体4,200円+税)
A5判:344頁
【江戸時代、酒造りの経済史】
日本の「伝統的酒造り」ユネスコ無形文化遺産登録決定!!
近世酒造業の発展を研究の中心にすえて、その社会経済史的側面と醸造技術史的側面を通して、日本の伝統文化を醸成してきたといっても過言ではない「日本酒」の歴史と推移を追求した記念碑的名著の復刊。
江戸時代の灘を中心に、酒造業の発展と統制の歴史を追った1冊。
「近世酒造業の発展を研究の中心にすえて、その社会経済史的側面と醸造技術史的側面とを考察した(はしがき)」とある通り、酒造りの技術の発達だけでなく、経済史・法制史的な観点を用いて、江戸~明治の酒造業の発展を紐解きます。
オススメ本⑤ 灘の蔵元三百年 国酒・日本酒の謎に迫る(径書房)西村 隆治 (著)

http://site.komichi.co.jp/books/2016/10/10/248/
著者名:西村 隆治 (著)
出版社名:径書房
定価:1,870円 (本体1,700円+税)
四六判:256頁
【灘の老舗「沢の鶴」当主が語る、日本酒のいまむかし】
日本酒は近年、輸出の増加、女性や若者の間での人気回復から、復権の兆しが明らかになってきた。そうした時期に出版されたのが本書である。灘の大手蔵元、沢の鶴14代目当主が歴史文化、行政、醸造法、味や香りなど日本酒概論の趣を醸しつつ、主題に迫る。
灘の老舗「沢の鶴」の14代目当主として、現在の酒造界に向き合い続けてきた著者による1冊。
伝統を受け継ぐ当事者として、現代の日本酒のありかたを深く考察します。
歴史だけでなく、日本酒のいま、灘の酒蔵のいまを知りたい人におすすめです。
あとがき
白鹿記念酒造博物館(酒ミュージアム)「伝統的酒造りの近現代」(2024.12/4~25.3/3)をもっと楽しめる!
今週の5冊はいかがでしたか?
酒蔵めぐりに、酒造博物館めぐりに、晩酌のおともにもぜひどうぞ。
マガジン「特別展・企画展をもっと楽しめる!おすすめ本5選」は毎週水曜日更新です。
今後も注目の特別展・企画展を取り上げていきます。お楽しみに!
