
戦中「日本的キリスト教を読む」を読む
タモリの、「2023年は新しい戦前になるんじゃないでしょうか」との発言が大きな波紋を呼んでいる。
時あたかも、キリスト教的なルーツを離れて日本の風物詩として浸透したクリスマスを越えてすぐ、寺で鐘かれる除夜の鐘で年を越し、多くの人が神社へと初詣する正月。そして厳寒のさなか、2月11日「建国記念の日」と、クリスチャンにとっては殊に、日本の宗教風土について考えさせられることの多いこの時期だ。そんななか、東京基督教大学長・山口陽一氏渾身の作「日本的キリスト教を読む」を読んだ。
これは、月刊『福音と世界』(新教出版社)に1年以上にわたって連載中(2022年2月号〜2023年連載中)のものである。
今回は「日本的キリスト教を読む」の緒論に当たる「第1回」「第2回」を読む。
戦争の狂気に突き進んだ時代のキリスト教プロテスタント界の言論を描く
これは一言で言えば、戦争の狂気に突き進んだ時代の日本の、その狂気ぶりをかいま見、その中で生きた、キリスト教プロテスタントの、その言論リーダーたる人々の、狂気に立ち向かう奮闘と、それより多くの体たらく(いや、無力という方が適切だろう。クリスチャン少数の状況にあって)ぶりを描くことになろう。
酷いかたちの「新しい戦前」を迎えることのないように、また、世界の中にあって日本が、より良い自分たちの未来を構想していけるよう、歴史のかがみとしたい。
山口氏の論では「狭義の日本的キリスト教」を扱う
第1回で山口氏はこれからの連載において扱う内容について、「狭義の日本的キリスト教」が中心と定義する。いわば良い意味ではない方で「特殊な」キリスト教なのである。

「広義の日本的キリスト教」とはキリスト教を日本に適用させる試み全て
そのためにまず、狭義ではない「広義」の「日本的キリスト教」について定義している。それは、「キリスト教を日本に適応させようとする試みすべて」である。
脱線 広義の日本的キリスト教の文化形成に成功したゴスペルin文楽
早速の脱線で申し訳ないが、「ゴスペルin文楽」のような取り組みはこの「広義の日本的キリスト教」に当たるだろう。
ゴスペルin文楽は1993年ごろ創始された。これは、古典芸能・文楽の、プロの太夫(たゆう。ストーリーテラー)である豊竹呂太夫(とよたけ・ろだゆう)がまだ英太夫(はなふさだゆう)という名前であった時に創始した。聖書の、キリストの物語を、古典の文楽の節回しで、古典同様に太棹三味線の伴奏に乗って語るのだ。西暦2000年以降は、人形付き(イエス・キリストの役の人形は、古典では「俊寛」の役のもの)の上演も年何回か興行されている。その際、古典の文楽の舞台で共演するプロの三味線弾きや人形遣いたちが、喜んで「新作文楽」に取り組んでくれるわけだ。
ちなみに呂太夫は「切場語り」(クライマックスの部分を正式に語ることが許された者)に2022年昇格し、現在4人しかいない切場語りの一人となった。それはゴスペルin文楽への取り組みも含めて、芸の成熟が認められてのことだから、ゴスペルin文楽は日本の文化の一部として認められたとも解釈できるだろう。

JEA、近放伝などプロテスタント福音派系超教派の協力団体肝いりで
行われたチャリティ公演。より本格的な興行は西暦2000年を俟つ。
人形はイエスの母、マリア。大夫は豊竹英大夫(現・呂太夫)
私自身、広義の日本的キリスト教に取り組んできた
そのことについては私自身、1994年、まだ始まったばかりで無名のゴスペルin文楽を、週刊『クリスチャン新聞』紙上に記事として載せ(当時は、人形付きで行うことなど考えられなかったので「賛美義太夫」と呼ばれた。その命名者は私である)、今日のゴスペルin文楽隆盛の発端をひらくこととなった。また1999年より、呂太夫師匠(旧・英太夫師匠)の公式WEBサイトを運営してきただけに思いは深い。
それはすなわち私自身、広義の意味での日本的キリスト教に高い関心を有し、そこに参画してきた人間であるわけだ。
今や、「忠臣蔵よりゴスペルin文楽の方が、古典芸能である文楽の格好の入門である」とまで評してくれる人がいるほどに、広義の日本的キリスト教の、文化面での取り組みとして成功したと言えるのではないだろうか。
平和の時代、健全な市民社会の庇護に下にゴスペルin文楽の興隆を見たのは幸いなことであった。そんな時代が末永く続くように願う。
内村鑑三の目指したのも広義の日本的キリスト教
さて、山口氏の連載内容に戻ろう。同氏は、内村鑑三が目指したのも広義の日本的キリスト教であったとする。この点も、戦前からの無教会派クリスチャンであった母方の大伯母を身近に知る者としては、深く頷かれるところである。大伯母は戦前から、矢内原忠雄の末席の弟子であった。矢内原が、軍国主義路線批判の故に1937年、東京帝国大教授職を追われ、山中湖畔の別荘に「蟄居」していた際、終戦に至るまで看護師の立場でお近くに仕えていた。
軍国主義的路線を批判したための言論弾圧で社会的立場を剥奪された師のため、同じクリスチャンとしてその復帰を執り成し祈り続け、日本の厳寒の時代が過ぎて、新生日本のリーダーシップを執る立場(東大総長)に矢内原が返り咲いたのを大伯母は目撃したわけだ。

毅然として、日本のあるべき姿は軍国主義、自国中心主義などではないと、堂々と主張を貫いた内村の弟子、矢内原こそ真の愛国者であり、そこに良い意味での日本的キリスト教の証しを見せてくれたというべきであろう。
アジア太平洋戦争期における日本の狂気的思想統制に対応する狭義の日本的キリスト教
さて、山口氏が連載で扱うのは「狭義」の日本的キリスト教である。
「大東亜戦争」での桁外れの民間人、兵員の死
その定義を山口氏は、「アジア太平洋戦争の時代に登場したもの」とする。
アジア太平洋戦争はまず、開戦中当時「大東亜戦争」と呼ばれたもの(1941年12月8日~45年9月7日)を指す。
それは、真珠湾攻撃を端緒にアメリカ等連合国と全面的に交戦し、当初(42年始め)は、西はミャンマー(旧ビルマ)から東はギルバート諸島に至る広大な地域の制空権、制陸権を得て“占領”するも、42年6月ミッドウェー海戦の後8月、ガダルカナル戦から始まる連合軍の本格的反撃により消耗戦に入り、多数の餓死、特攻作戦などを含む多くの兵員の死者を出し、また44年末から本格化した本土空襲、45年3月からの沖縄戦、45年8月の、広島・長崎への原爆投下を経て、大日本帝国の全面降伏に至ったもの。

多くの兵員と、幾多の民間人も、戦争による直接被害を被ったことを下記の統計で示しておく。
*太平洋戦争によるわが国の被害総合報告書
(1949、経済安定本部=当時「省」と同格)
兵員死者 約156万人
兵員行方不明 約 31万人
一般市民 約 67万人
*本土への空襲 44年6月以降
110箇所以上へ850回以上
罹災 約910万人
死者 約17万6000人(沖縄戦及び原爆被害を除く)
*沖縄地上戦 45年3月から
(下記統計は、<沖縄県の福祉>=1976年=から)
日本側死者 約18万8000人
内、日本兵 約6万6千人
沖縄県出身軍人・軍属 約2万8千人
戦闘参加者 約5万5千人
一般住民(推定) 約3万9千人
米国側死者 約1万3千人
*原爆被害
広島8月6日 罹災約42万人、死者約26万人
長崎8月9日 罹災約12万人、死者約7万5000人
1931年「満州事変」以降の国論統制からの継続
この大東亜戦争は、東條英機首相の下、「アジアを白人の手からアジア人自らの手に奪い返す」「アジア人のアジアを創りあげる」ことを大義名分として開戦された。
それは、それ以前からの、中国方面への軍事力による侵攻、それを可能とする国論の統制としての大政翼賛体制の構築・完成の連続としての展開であった。
そのことを踏まえて、アジア太平洋戦争のことを、1931年「満州事変」に始まる「15年戦争」の別称とする人も多い。
1931年からの15年戦争の異称としてアジア太平洋戦争を採用している山口
山口陽一の論「日本的キリスト教を読む」では、「15年戦争の別称としてのアジア太平洋戦争」下における狭義の日本的キリスト教について論じている。
そういう狭義の日本的キリスト教について特に取り上げる理由を説明するのに山口は、土肥昭夫(同志社大学名誉教授)による次のような「日本的キリスト教」とは何か、の解説を引用する。
1930年代に現れた、キリスト教の教説を日本的伝統と様々な方法で関連づけて理解しようとする試み。当時日本の支配層は国内の経済危機を乗越えるために中国侵略に乗出し、更に日中戦争、太平洋戦争へと突入、国民の精神的統合を図るために、非常時、国体明徴、皇道精神の振興を唱えた。多数の日本共産党転向が伝えられ、近代の終末や超克、日本への回帰が論じられ、日本の古典、神道、その他の歴史的伝統を再評価し、そこに自己の精神的根拠を見出す傾向も見られた。
(太字三浦)
すなわち、上掲した統計でも分かるように、桁外れの戦争被害を被り、明らかに政府のミスリードによる負け戦だと分かっていても負けを認めて終戦に向かうことができず、かえって更に大きな痛みを被る路線に突き進むことを許す世論が醸造されるほど、「国民の精神」が「統合」され、国民は「そこに自己の精神的根拠を見出す」ほどまでにマインドコントロールと紛うほど、常軌を逸して「統御」されていた1941年以降。そして、否応なくそんな大政翼賛体制に向かって突き進んでいた1930年代以降。

戦争遂行中心の異常な時代の、キリスト教界の言説を追う山口の論文
そんな当時の日本の「異常」な状況下にあって、キリスト教界の側からも「対応」せざるを得ないものとして発生した(あるいは心から進んで国策に協賛した者も多くある)、「狭義の日本的キリスト教」というものがあることを山口は述べているわけである。
小学校すら国民学校となり皇国民錬成を目指した異常
1941年以降の時代の異常さは、例えば、義務教育である小学校さえ「国民学校」という名の元に改編され、太平洋戦争への総力戦体制に対応して、常に軍人の監視の下に、言行一致・心身一体の皇国民錬成の教育を目ざし、学校行事や団体訓練が重視され、剣術訓練、薙刀体操などが必須の授業として行われた。正に狂気の時代だったのである。

司馬遼太郎もその国民学校のありさまを、『この国のかたち』「無題」に書いている。その中で、当時国民学校の生徒で戦後40年経ってその記憶を話してくれた仙台の法律学者が、「小学校まで軍隊組織になったんです。校長が連隊長で、クラスの級長は小隊長というあんばいでした。冬でもハダシで登下校させられました」と語るのを聞いて「どこの国の話かとはじめは信じがたく、ついには耳をおおいたくなった。鍛錬などというようなものではなく、加虐ではないか」と記している。
奴隷として若者を育てる「教育」
また、国民学校ではないが同時代に、島根県浜田の名門(旧制)中学の生徒であった友人の、戦後20年の談として、「中学生というより奴隷だった。それ以降、奴隷として支配された人間がどんなものかがわかるようになった。極端にいえば、いったん奴隷的に支配された人間は信ずべきではないといまでも思っている」という証言を紹介し、多数の取材の裏付けをもって、「このような事例を挙げれば、きりもない」と司馬は書いている。
キリスト教(プロテスタント)への弾圧
特高や憲兵による国民の思想の監視、弾圧
さらにその時代、思想監視機関「特別高等警察」(特高。1928年、全国一律設置に至った)や「憲兵」(明治時代から存在し、時代の趨勢と共に「治安維持」の機能を強化してきた)による苛烈な、「国民の思想の監視」と弾圧は、「敵性宗教」(キリスト教は敵国である欧米の宗教と理解された)であるキリスト教に対して強かったことを指摘しなければならない。
あらゆる教派の教会に対して、礼拝説教などの内容の、臨場監視が行われ圧力が掛けられた。
ホーリネス教会(第6部、9部)教職らの逮捕、獄死者も出す
その中で甚だしくは1941年1月、靖国神社参拝を拒んだために小山宗祐牧師補(旧・日本ホーリネス教会、当時・日本聖教会)が、函館の地域社会による密告を受け、憲兵隊に検挙されて、獄中死(過酷な拷問の結果)に至ったことを前触れに、1942年6月、ホーリネス教会系(当時、日本基督教団第6部、第9部)の教職者69人が逮捕され(第1次検挙。43年3月には第2次検挙28人)、134人の検挙者のうち75人が「治安維持法」違反の容疑で起訴され、うち7人が獄死に至った、日本におけるプロテスタントへの最大の迫害事件が起こったことを忘れることはできない。

疎開先から大阪に帰ったら「教会がなくなっていた」
個人的な話になるが、筆者の母方の祖父母は、戦前きよめ教会(第9部)の教会員であり、大阪在住から空襲を避けて岡山に疎開。戦後大阪に戻った際、所属していた「都島きよめ教会」が「なくなっていた」。そのように学生時代、ちらりと聞いたことは忘れられない。
それは、第3回大阪大空襲などで建物が焼失したということか、第6部、第9部の解散により、法的な教会存立の根拠を失い、教職は離職、信徒は離散した事態の両方を意味しているのであろうか。

戦後すぐ祖父は、神戸の湊川伝道館を訪ねたが通うには距離が遠かったのか、姉(矢内原の末弟子だった私の大伯母)のアドバイスを入れ、無教会「的」信仰を個人的に守っていたが(私は祖父の生前、その口からキリスト教について聞いたことは一度もない。そして祖父の葬式を大祖母の仕切りで、長屋の自宅においてキリスト教式に行った際、小学校3年生の私が口語訳聖書で詩篇90篇10節=「われわれのよわいは…健やかであっても80年…その一生はただ、ほねおりと悩みであって…われらは飛び去るのです」=を読ませられたのが、人生最初のキリスト教との接点だった)、祖父の逝去後祖母は、クリスチャンになっていた長女(私の母)のアドバイスを容れて、大衆伝道者・正木茂が開拓していた福音派の、北大阪ルーテル教会で信仰生活を送ることになった。
日本全国でこのように、戦前熱心な教会生活を送っていたものの、戦争で大きな紆余曲折を経て、何とか信仰の命脈を保ったり、なかには棄教した人々も多いのではないだろうかということを、痛みを込めて推測せざるを得ない。
日本基督教団の成立と惨憺たる状況の問題点
ここで、日本のプロテスタントの最大教派である日本基督教団が、それまで別々であった諸教団の合同によって1941年6月に創立し、その創立総会は「君が代斉唱」「宮城遥拝」「皇軍兵士のための黙祷」「皇国臣民の誓い」の国民儀礼を以って開始され、総会中、「われら基督教信者であると同時に日本臣民であり、皇国に忠誠を尽くすを以って第一とす」との宣誓が行われたといったことは忘れてはならない歴史的事実である。
当初「部会制」をとった日基教団
この日本基督教団は創立時、旧教派に基づいて「部会制」をとっていた。部会と旧諸教団の対応は次の通りである。
第一部…日本基督教会
第二部…日本メソヂスト教会、日本美普教会、日本聖園教会
第三部…日本組合基督教会、日本基督同胞教会、日本福音教会、基督友会、基督教会
第四部…日本バプテスト基督教団
第五部…日本福音ルーテル教会
第六部…日本聖教会(ホーリネス系)
第七部…日本伝道基督教団(日本イエス・キリスト教会、日本協同基督教会、基督伝道教会(現シオン・キリスト教団)、基督伝道隊、基督復興教会、日本伝道基督教団、日本ペンテコステ教会、日本聖潔基督教会)
第八部…日本聖化基督教団(日本同盟基督協会、日本自由メソヂスト教会、日本ナザレン教会(東部・西部)、世界宣教団)
第九部…きよめ教会(ホーリネス系)、日本自由基督教会
第十部…日本独立教会同盟(ウェスレアン・メソヂスト教会、普及福音教会、日本一致基督教団、東京基督教会、日本神の教会、日本聖書教会(現日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団)、聖霊教会、活水教会
第十一部…救世団(旧救世軍)
伊勢参拝を当然のように行った初代日基教団統理・富田満牧師
部会のうち最大で、神学的に最も正統であることを自認し、また教会員の社会的立場などから、「主流派」は第一部(旧・日本基督教会)であった。
旧・日本基督教会は1872年、ジェームス・バラらの設立による日本初のプロテスタント教会「日本基督公会」にまで歴史がさかのぼる。

ここを舞台に、日本基督公会の横浜海岸教会が設立され、それが旧・日本基督教会にとして発展した。左は1922年に同じ場所に建て替えられた教会堂
1941年、日本基督教団創立時の統理は、旧・日本基督教会議長であった富田満が就任した。
その富田は1942年1月、伊勢神宮に参拝し、「天照大神に教団の設立を報告」。そして、「我が国における新教団の発足を報告し、その今後における発展を希願せられた」という惨憺たるありさまであった。


大正時点では神社参拝強要は憲法違反と表明していた主流派の旧・日基教会
しかし、旧・日本基督教会は、1917年(大正6年)段階の大会(第31回)の時点ではまだ、神社非宗教論を否定し、学生が神社参拝を強制されることは大日本帝国憲法の信教の自由に抵触するという明確な意思表明を、「神社に関する決議」として行っていた。

そこから25年を経て、日本基督教会の代表(議長)であった富田自身が、日本基督教団初代統理となり、伊勢神宮に参拝するという事態に立ち至っていたのであった。そして、キリスト教プロテスタントの合同最大教派の代表者が、当たり前のように伊勢参拝を行うに至った時代の流れに「すっかり飲まれたものとしてのキリスト教」や、あるいは少数ながらも「その状況下でも世界に普遍的なキリスト教の本質を何とか保とうとしつつ、同時代の同胞への弁証的な営みとして論を述べる」ものとして「狭義の日本的キリスト教」があったわけである。
その流れは1930年(昭和5年)代以降の15年戦争期を通して加速し、41年からの「大東亜戦争」の大政翼賛体制下に至っては極限に達していたことはすでに述べた通りである。
ホーリネス系弾圧を当局に“感謝”した日基教団の姿勢
またホーリネス系教職一斉検挙の際、日本基督教団の公式見解は、「軽々しき行動を慎み、暫く成行きを静観すること」「皇国民たるの自覚に立ち、臣道の実践を志すことを求めた」(『日本基督教団史資料集第二巻』)というものだった。
同教団幹部らで「彼らの熱狂的信仰は我々教団では手の下しようもないくらい気違いじみているため、これを御当局において処断して下さったことは、教団にとり幸い」「こうした不純なものを除去することによって日基教団のいかなるものかが一段に認められて、今後の運営上かえって好結果がえられるのではないかと考え、当局の措置に感謝」などと述べる者すらあり、当局のホーリネス検挙を歓迎した(『ホーリネス・バンドの軌跡』)ありさまであったことには慄然とする。
旧ホーリネス教会(第6部、第9部)解散への日基教団の姿勢
さらに1943年4月、当時の日本基督教団(富田統理)は、文部省から宗教団体法に基づいて、第6部と第9部の教会設立認可の取り消し処分と教師辞任を指示されてそれを実行し、日基教団内のホーリネス系の教会は強制的に解散させられた(戦後もようやく1984年に日本基督教団は、当時の誤りを認め、旧ホーリネス教会関係者と家族を教団総会に招いて公式に謝罪した)。
このホーリネス系教会解散につき当時の日本基督教団財務局長は、「結社禁止は当然の処置であるとおもう。日本においてキリスト者が再臨問題をとりあげて説くことがそもそもの間違いである」と述べ、富田統理も、ホーリネスの学的程度が低いからだと弁明したという。
戦後77年の今、福音派から当時の教界への視線
その辺りの消息を、山口陽一は非常に遠回しな言い方で、「土肥昭夫が言うように、日本基督教団が日本的キリスト教に陥っていたのならば、主流の教会は 日本的キリスト教に影響を受けることはなかったとは言えない」と指摘する。
考えてみれば山口自身、戦後の生まれ(1958)であり福音派の人物である。日本の福音派は戦後、アメリカから多くの「新しい」宣教師がやって来ての伝道と、戦前からの、主にホーリネス系の、多くの筋金入りの教界指導者たちが協力して、教派横断的に発展してきたものと言える。アメリカの福音派の影響を濃厚に受けていることも言うまでもない。
そして福音派は、日本のプロテスタントでは主流派ではない。
山口が学長を務める東京基督教大学は、福音派勢力によって設立された。

世界の福音派の「中心」にいるアメリカのキリスト教と
日本で戦前から苦難の中でリーダーシップを執ってきた
ホーリネス系などの教界指導者が牽引して実現した
『福音と世界』での連載の意味するところ
その山口が、現在の日本基督教団系、主流派の主要メディアと目される『福音と世界』に連載を依頼されることは、20世紀においては考えられなかったかもしれない。
彼が1995年、日本福音主義神学会という福音派だけの神学会に参加したのみならず、キリスト教史学会(2001年参加)、日基督教学会(2010年参加)と、福音派ならぬプロテスタント主流派も多く含む、より幅広いキリスト教(特にその歴史)についての学的な交流に入り、そこにおいてその論述が認められるようになったことの反映として『福音と世界』への連載執筆は捉えられるべきだろう。

戦後発の福音派の神学界への貢献の高まり
それはまた、日本のプロテスタントにおける福音派の存在感、貢献度が高まったことの中にある出来事と考えて良いと思う。
福音派神学から、戦時体制にまつわる主流派神学の自己認識の甘さを指摘
さて山口は土肥昭夫を引用して、「日本基督教団が日本的キリスト教に陥っていた」ということはすなわち、主流派の教会が、日本的キリスト教にどっぷりと影響を受けたということに他ならないと指摘したのだった。
創設以来、戦時中の日本基督教団の惨憺たるありさまに、山口自身は連載「第1回」「第2回」には触れていないが、私が既に述べた日本基督教団の状況が当然の前提として読者に把握されていることを踏まえての土肥の引用なのである。
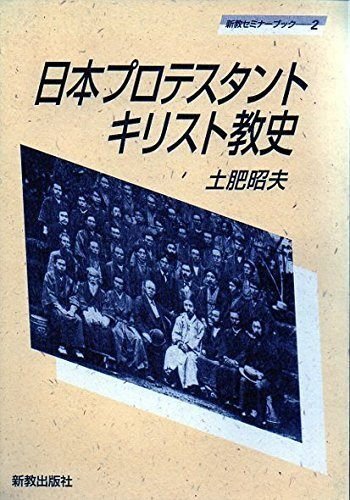
土肥昭夫の著。同志社大学の彼は戦後において、
主流派からも、日本のキリスト教史の泰斗と言われた
それを山口が述べる背景は、教界主流派を代表する教界史家の一人・佐藤敏夫(2006年にキリスト教文化功労賞受賞)が1992年に著した『日本神学史』において、狭義の日本的キリスト教に関して記した著述に異論を申し立ててのことである。
佐藤は記す。
日本では、日本的キリスト教はそもそもマイノリティ・グループであったキリスト教界の中の、更にマイノリティ・グループのものであり、主流(main stream)の教会は、とくにそれによって影響を受けることはいう程のことはなかった 。
(太字三浦)

主流派の、「自由主義」(同志社系)と「敬虔主義」(ホーリネス系)が日本的キリスト教に陥ったと他人事の姿勢を批判
山口はこの佐藤の論を解説して、「極端な日本的キリスト教を念頭において、自由主義と敬虔主義の人々が日本的キリスト教に走りやすかった」と佐藤は言っているのだと言う。そして、それに該当する歴史上の中心人物として海老名弾正(自由主義)、中田重治(敬虔主義)を念頭に置いていると解説する。
三浦注 ここで出てきた「自由主義」というのは、「神学的な意味でリベラル」という意味である。既述の、戦時下の日本基督教団においては第三部となった「日本組合基督教会」などがとった路線で海老名はその代表格に当たるし、その神学的な流れは、今日も同志社大学に至るものと目される(ちなみに土肥昭夫は、同志社の名誉教授になった人物で、日本プロテスタント・キリスト教史家の第一人者と目されている。彼が、日基教団の主流派の歴史的経緯を、より批判的に見ることができたのは当然であろう)。
一方敬虔主義は、四捨五入して、第6部、第9部のことを指していると考えて差し支えない。中田重治は、第6部、第9部の共通の強固な母体を据えた人物として今日まで覚えられているのである。
だから、戦時下の、直接的な弾圧の中をくぐってきた、筋金入りのホーリネス系教職の指導者たちから多くの薫陶を受けて育った福音派の山口としては、黙って見過ごせず、指摘せずにはおけないない記述であるわけだろう。
日本基督教団が日本的キリスト教に陥ったのはすなわち、主流派の教会がどっぷりだったいうことに他ならない
そして山口は、上述の土肥の記述に引き続く論述を引用する。
日本基督教団はこのような(極端な日本的キリスト教)研究を奨励する一方、これを巧みに受け入れ、その極端な部分は切捨てて、これを生活綱領、戦時布教方針、『日本基督教団より大東亜共栄圏に在る基督教徒に送る書簡』といった実施的目的に反映させていった。
そして、この土肥の記述は、「佐藤によれば日本的キリスト教に走りやすくないはずの、正統教理を重視する主流の教会の日本的キリスト教をこそ問題にしているのである」と解説する。
土肥とはまた別の「主流派ではない」プロテスタントの目から見れば、土肥の言うことはよく分かるよ、といったところであろうか。
『福音と世界』のどの読者にも「自分ごと」として考えて欲しい
このように山口は読者に対し、「日本的キリスト教」の問題という場合、「自由主義や敬虔主義者による、極端に走った日本的キリスト教」だけでなく、日本のプロテスタントのメインライン(主流)が「無自覚的に」自らを染めていた狭義の日本的キリスト教についてまで、長い連載の中で掘り起こしたいという志を示し、「どの読者にあっても、“自らのこと”として受け止めて欲しい」という表明を行ったものであろう。
日本的キリスト教のカテゴライズと、それらへの評価
箸にも棒にもかからぬものと今日的に学ぶべき点のあるもの
さて、山口は<「日本的キリスト教」を読む>の第1回で、狭義の日本的キリスト教について①「箸にも棒にもかからないどうしようもないもの」と、②「今日から見ても十分考慮すべきものを含んだもの」がある旨を解説した。
問題にすらならない神道との習合・混淆路線
①については、久山康(関西学院大学教授)の『近代日本とキリスト教――大正・昭和篇――』をひいて、「日本の神道とキリスト教を安易に習合し、皇道的キリスト教を樹立しようとしたもの」で、それは「単なる時代への迎合で問題に(すら)ならない、とし、その具体的人物として「佐藤定吉や渡瀬常吉」を挙げる。
この①の路線を鈴木範久は、「キリスト教を国家神道という宗教の内に全く従属的に解消させる」もので「従属」路線とでもいうべきものだと言ったと山口は解説する。
また笠原芳光はこの同じ路線を「混淆」という類型に分類し、そうではない「両立」「触発」という類型と区別した。
脱線 大平正芳は神道との混淆路線を忌避し、矢内原に真のキリスト教を求めた
さてここでまた脱線するのだが、先日、戦後クリスチャン宰相として知られた大平正芳の信仰について調べ書いた際、1920年代後半、大平が一番最初に郷里の香川で、旧・高松商業高等学校の学生としてキリスト教の求道に導かれたのは、全国巡回していた佐藤定吉を通してであったことを興味深く思うものである。
大平は佐藤の教えについて「神が愛であるということが分からなかった」ということと、もっと「聖書そのものからの教えを求める」方向に向かい、それは内村鑑三とその弟子たちの著作に親しむことであったと、日本経済新聞「私の履歴書」に自ら記している。
そして、旧・東京商科大学(現・一橋大学)に進学後は、矢内原忠雄が自由が丘の自宅で開いていた聖書研究会で親しく教えを受けた、ということは感慨深い。
その大学卒業後の履歴として、若き大蔵省官僚として1939年から40年まで「興亜院」蒙疆連絡部や経済部で行政官の経験をしながらも、「現地の軍部の独善的なやり方」を大胆に批判していたこと(伊藤正義)と、矢内原の教えを受けたことは平仄が合っているように感じられる。
国家神道にキリスト教を全く従属させてしまう姿勢を持つ佐藤の言説に若き日の大平は得心いかず、より世界に普遍的な聖書的なキリスト教を求め、その日本的表現である無教会派の内村や矢内原の教えを受けて満足したということが、戦後、政治家になってからのものの考え方、歩みに大きな影響を与えていると改めて感じられてならない。
「日本の精神風土に真のキリスト教を根付かせよう」との努力は今日学び得るもの
さて、狭義の日本的キリスト教の大きな流れの②について、久山康は次のように記していると山口は引用する。
第二の流れは民族主義の勃興に促されて、いままでの植民地的キリスト教の在り方を反省し、日本の精神風土の中に真のキリスト教を定着させようとした努力として、今日でも十分考慮すべき点を含んだものだと思うのです。
「植民地的キリスト教」脱却指向に学び得る
すなわち久山は、狭義のキリスト教の中にも、現代の視点から見て積極的に学ぶべきを含むものがあり、それは「植民地的キリスト教」を脱そうと志し、「日本の精神風土に“真のキリスト教”を定着させよう」という努力の部分であることを指摘し、山口もその説に同意している。
そして久山は②の類型の人々として「無教会の人々」や魚木忠一、藤原藤男、村松克己などを挙げている。
日本人としての主体性において正統なキリスト教をつかんだ内村鑑三への評価
私は大平正芳の関連で内村鑑三のキリスト教受容について改めて内村の自伝『余は如何にしてキリスト信徒となりし乎』を読み返したが、ウィリアム・クラークはじめ欧米人による教説だけでは納得せず、あくまでも日本人として、自分が正しい人間として生きていける道としてのキリスト教を追求し、アメリカに私費留学の際、「キリスト教」の浸透したアメリカ社会の良い点も暗黒の点も直接見聞きしたうえで、アマースト大学のジュリアス・シーリー学長からの人格的な薫陶を受ける諸経験の末、アメリカに引き継がれていた正統なキリスト教を日本人の側から、その感性、理解をもって心底受け入れた、その内容を記していた。
無教会派の路線が、日本の軍国主義を批判をもせざるを得なくなった必然
それは「無教会運動」という「かたち」をとるものとなったが、その信仰に根ざす信念は、内村本人にあっては非戦論となり、矢内原にあっても軍国主義への忌憚なき批判となったことは興味深い。
日本を愛する愛国者たることは、場合によっては国家の姿勢に対する批判とならざるを得ないことがあることを彼らの存在は示しているのであるし、その点に世界に普遍的なものとしての正統なキリスト教(現在のロシアのプーチンの奉じる自国の身勝手な戦争に裏付けを与える「キリスト教」のようなものでなく)のしるしを見る思いがする。
国家神道とキリスト教の「共存」路線には今日も見解が分かれる
さて、②と①のいわば間に「共存」(国家神道を宗教とは見ず、キリスト教と共存させる)という類型があると鈴木は分類する。また、笠原もその路線を「両立」という類型に分類した。そして山口は「共存」や「両立」の路線への評価について今日、「見解が分かれている」と記す。
その「見解の分かれ」は私の観るところ、現在の「反靖国運動」を巡っての、憲法に基づく政教分離原則に照らして、「目的効果論」をどう考えるかの議論にも関連するものと思われる。
今日十分評価に耐えるものとして無教会派や魚木の、神道との「対立」や日本文化を「触発」路線
さて明確に②である路線として鈴木は「対立」(キリスト教と国家神道を対立的にとらえる)という類型に分類した。そして、無教会人士はこの「対立」に当たるものであると評価した。
笠原は明確な②の路線を「触発」と分類した。
これは日本人の宗教的精神がキリスト教に「触発」されて、日本人の持ち味の良きものがさらに開発されるという考え方だと解説する。
*ここで、これまで出た分類について図表で整理しておきたい
久山靖1956 鈴木範久1962 笠原芳光1974
①神道と安易な習合 神道に「従属」 神道と「混淆」
(皇道的キリスト教)
神道と「共存」 神道と「両立」
②日本の精神風土に根付く 神道と「対立」 日本風土を「触発」
(今日も学ぶ点多い)
今日積極的に学ぶべき点の多い「触発」路線の魚木忠一を熊野義孝を通して論じる
そして「触発」の路線として、久山、鈴木などの「諸氏が、今日的意義のある「日本的キリスト教」として評する魚木忠一の論の概説を山口は、熊野義孝の『日本キリスト教倫理思想史』「日本的キリスト教」(1972)に沿って紹介するのである。
熊野義孝は戦前から主流派として神学界をリードした人物
熊野は1899年の生まれ。主流派の日本基督教会の福音理解に本格的な神学的表現を与えた人物といわれる。戦後も、東京神学大学教授として教義学(組織神学)の第一人者の一人。
熊野は、上述の富田満の15歳後輩で、狭義の日本的キリスト教の盛んだった時代の空気のなかに自らも浸って生きた人物である。

熊野義孝は、後列左に写っている。左から3人目が富田満
熊野は日本的キリスト教を、社会的キリスト教の次に流行ったものと把握
熊野は狭義の日本的キリスト教について、それ以前の「社会的キリスト教」の流行に取って代わったものだと評する。そして、前者と後者について共通するのは、リアルな歴史認識ができていない(イデオロギー先行ということか)論考であると考察する。
さらに海外宣教団体からの決別について、それは不幸なことではあったが、明治以来の「植民地主義的教会」と見た場合、そのこと自体は福音の「変曲」ではないと評する。
そして、「日本的キリスト教は戦争後半には「甚だ低声になった」と、同時代人としての印象を述べている」というのは興味深い。「第2回」に山口が、今回連載において取り上げる書物60数冊のリストを挙げているが、1930年から1941年大東亜戦争開戦(12月)までのものが50数冊(年平均5冊)、一方1942年以降45年まで約10冊(年平均2冊、しかも1945年発行は0冊)と確かに、熊野の印象は事実をうがったものであることを発行冊数によって裏付けられる。
これは書籍作成用の紙の不足ということもあろうし、全般に書物など書いているほどの余裕もないとか、負けが見えている戦争の中で弁明的にものを言う気力さえ失せていた、ということを意味するのであろうか?
主流派神学は日本的キリスト教に影響されず正統性を保持したとの熊野の見解――土肥昭夫と山口の反論
そして熊野は、同じ東京神学大学教授である佐藤と同様(記述の佐藤の『日本神学史』は1992年)、自分たち主流の教会は日本的キリスト教に影響を受けることなく、神学の正統性を保持したとの自負を記す。この熊野の1972年の論述、また佐藤が同趣旨を92年に展開したことへの鋭い批判として、同志社大学の土肥を援用しつつ「日本基督教団が日本的キリスト教に陥っていたならば、主流の教会は、日本的キリスト教に影響を受けることはなたったとは言えない」と述べ、「極端な日本的キリスト教に比べ、それを批判する見識を持っていた分、その無自覚さはより厄介である」とまで、痛切な批判を述べているのである。
日本的キリスト教の論も絶え絶えの戦争末期に「日本基督教」論を公にした魚木
そういうことの上で山口は、熊野が取り上げる魚木について記すのである。
魚木は同志社大学教授である。すなわち佐藤が、極端な日本的キリスト教に陥りがちだった「自由主義」の人々の一人である。
ところが戦後、既述しただけでも久山、笠原、熊野といった人々から、戦後の今日でも通用するキリスト教の日本への土着を論じた優れた論であることを評価されている。ネットで調べてみると、他にも同様の、戦時下の魚崎の言論に対する今日の観点から見た高い評価を述べる人々がいる。
魚崎が、日本のアジア太平洋戦争という15年の間のどのタイミングで論を述べたかを考えると大変興味深い。彼の「日本基督教」論を記した『日本基督教の精神的的伝統は』1941年、『日本基督教の性格』は43年に至ってなのである。
これから述べるように、戦時中の、軍国主義的体制への付和雷同的な言動と一線を画した、学問的に本格的な「日本基督教」(魚木自身、他と同類のものと見られることを避けるべく「日本的キリスト教」という用語を「避け」てこの語を自らの論について使っているのである)の論を、この期に及んで出してきたことは大変に興味深いことに感じられる。
同志社の後輩が述べる魚木の人物像
同大学の『同志社時報』(年2回発行)第56号(1975年11月)に「同志社人物誌」第39回として魚木が特集されている(執筆・山崎亨)。

山崎の紹介によると魚木は、自分が卒業論文や修士論文の指導を行う学生に対して「平均以上の、あるいは他の学生の二倍ぐらいの参考書を読ませ」た。それほどまでに学問のことに関して「厳格で、融通のきかない教師」であった。その姿勢は、自分自身に対しても同様で、1922年(大正11年)同志社大学卒業後、直ちにユニオン神学校修士課程で学び、4年後にマスター・オブ・セークレッドセオロジーの学位(神学修士と博士の中問)を最優秀の称号と共に受けた。この時期の魚木を知る人は、彼を修道僧になぞらえたという。
さらにドイツ・マールブルグ大学の後1927年(昭和2年)、同志社大学神学部で教員となり、27年間終始一貫して同志社大学における教育に身を献げた。魚木は学内行政に腕を振るうというタイプではなく、自らの学術的研究と学生の指導に注力したことを山崎は特筆している。
時流におもねる姿勢ではなく厳密な歴史研究に立脚して学問しようとの姿勢の魚木
そのような魚木が書いた「日本基督教」論は、時流に流されるという動機のものではなく、また論の中身としても安易に時のイデオロギーに沿ったものを書くというこでとなく、厳密に、実際の歴史の研究を踏まえた学問的に厳密な姿勢のものであろうとしたわけだろう。
そして、その論は、戦後全般には「日本的キリスト教」の一つと忌避されたが、見る目のある神学者やキリスト教歴史家の多くで、「今日にも通用するものを多く含むキリスト教の日本への土着化」論であると評価する者たちもいるわけだ。
それらのことを踏まえて、山口が、熊野の取り上げた魚崎を紹介していることを考えると興味深い。
なぜなら山口は熊野の、「神学的にも主流である自分たちが、戦時中に日本的キリスト教に影響されることはなかった」旨、言明することへの鋭い批判を加えているからだ。そして、そうでありならがら熊野も魚木に高い評価を与えざるを得なかったことを記して描いているからだ。
組織的に正統な筋目だから正統な中身というわけではない――山口の警句?
山口は、「組織的に正統な筋目の人間が論じることだから直ちに正統な中身であるわけではない」ということを言いたいのかもしれない。また、「“自らが正統である”という自認が仇となって、無自覚的のうちに正統の道から外れているという、より深刻な事態があるのだ」とさえ指摘している。
加えて、「正しい(正統な)ことをどんな時代にあっても言い続けるために、“正統なラインに立場を持っている”ということとは異なる、もっと本質的な理由があるのではないかと言いたいようである。
さて、熊野の理解によると、魚木は「日本基督教」論のなかで、国家神道と安易に「混淆」し「従属」するキリスト教まがいではなく、逆に、日本の宗教的文化に対して「触発」を与え、新しい発展を起こさせるものとしての「日本基督教」を表明している。
日本のキリスト教プロテスタント神学の最正統派の人々から見て、正統派ではない「自由主義」的傾向の同志社に属する魚木から、まさに時代におもねらず、世界や歴史の中における普遍性を帯びた日本における基督教のあるべき姿についての論を、狂い果てた日本の戦争の狂気のきわまった時期に上梓し得たことが示しているのは、「神学者、キリスト教歴史家にとって大切なのは、世渡りや行政手腕ではなく、学問に対する誠実な姿勢と学問の手腕である」ということではないだろうか。そのようなものとして書かれたものこそ、それがどんな時代に書かれたものであってすら、後世の歴史の評価に足る論をなす根本であることが言外に語られているように感じる。
さて、熊野による魚崎の紹介を述べて、私のこの文を閉じたい。
繰り返すが、熊野の評によると魚木の「日本基督教」論は「戦後の「福音の土着化」論として通用する」部分を多く含んだものである。
世界の中で日本を俯瞰し、類型づけようとした魚木
魚木は、日本精神と福音信仰の両方について考察を加え(ということは両者は「別物」であるという基本認識が根本にあるということだろう)、その上で、すでに日本の「土壌」を成しているものの要素の中で、儒教は「礼教的」(倫理)の要素を与え、仏教は「哲学的教理的」(知的な悟り)の要素を与えていると分析した上で、キリスト教はそういう土壌に対し「体得される他力の贖い」を与えることができるし、そうすべきであると主張している。
魚木は、文化的雰囲気や表現形態が日本的であるあるというよりも、日本精神を地盤として生い立つキリスト教を「日本基督教」として主張しているのである。
歴史神学を専門とする魚木は、そのことをするにおいて、世界史全体を俯瞰するものとして、キリスト教思想の起源及びその発達を歴史的事実の根拠に基づいて分析し類型づけして記述した。
熊野や山口の論述からはみ出すが、『同志社人物誌』「魚木忠一」(山崎亨)によると魚木は、「救贖的歴史観に立って基督教精神史を見」、その歴史は「究極点に向かって進展しながらもその途上において類型的段階」があると考える説をその学業の中で常にとっていた。
その類型的段階というのは「ある民族が、その文化(発展)の段階において独特の福音体得や、救済把握」をしているということである。
さらにその類型をつかむための方法論として、「時代的、社会的環境の中に傑出した人物たち」について、それぞれの類型における「数人の思想に焦点を当てる」ことでそれぞれの類型の在り方を浮かび上がらせることができ(彼はルターやカルヴァンもそのような対象として扱った)、そうやって浮かび上がった各類型は「他の類型と対照されながら、相補いつつ福音理解を深めていく」と考えていた(その説は、ゼーベルグが『教義史 第二、第三版』(1920)に提示したものを魚木は受け継いでいるというのが山崎の解説である)。
そのようにして類型として分類されるのは魚木によれば、「原始基督教」型、「ギリシャ」型、「ラテン」型、「ローマ」型、「ゲルマン」型、「アングロサクソン」型、そして「日本」型であると結論づけられる。
熊野の解釈によれば、その「日本型」類型の特色(日本の文化独特に,その土壌に生い立つもの)の現れは、まず「聖書の理解」ということで、「儒教(仏教、神道)を霊的意味での「旧約」とし、キリスト教をその完成と観る」ものと熊野は言う。そして熊野は更に、この魚木の論について。時流に合わせた「弁疎的護教論」というより「固陋な聖書神言論者」に対する啓蒙であるとしている。
また「霊魂論」について、「日本型」においてはラテン語における「アニマ(anima)」(普通、霊魂と訳される)は「精神」と解すべきだと言う。そしてこれは、「武士道からキリスト教の「精神主義」に「触発」したとする。
「摂理信仰の体得」については、元来「ほがらか」な「神道が人生の深刻さを仏教に学」んでいたところ、その土壌がキリスト教の摂理信仰に触発されて、「苦難に克ち、生死を超え、宿命を打ち破る「ほがらかさ」になった」のだとする。
魚木が戦時下の時流に合わせて脱線していると熊野が批判する部分
「臣民の道」「報国」が明白な召命という論
そのような魚木の「日本基督教」論に熊野は理解を示しながら、その論のある部分は、「時代色すこぶる濃厚」(戦争の狂気に突き進んでいった時流に合わせすぎている、ということ)と批判するのは、日本型類型におけるキリスト教が「「臣民の道、孝道、国土愛、職域奉公」にその性格を持ち、特に「臣民の道」に「明かである」と言うところである。
キリスト論の追求を深掘りしなかったのが当時の傾向であり魚木の脱線の理由
魚木はその「「忠孝信一如」を特徴とする日本基督教の根底」にあるのは「「僕神」としてのキリスト」であると「ピリピ2章1節から11節を引用しながら、己を卑しくして死にまで従う「臣民の道」を説」き、「報国」ということが日本的類型のキリスト教においては「召命」ということなのだ、と論をまとめている。
そのことに対し熊野は「キリスト論に進むことを避ける当時の神学の傾向を指摘」し「なぜキリスト論に進むことを避ける傾向が生じたかの究明は課題である」としている。
だから熊野は、世界に普遍のキリスト教のキリスト論をしっかりやれば「報国が召命」などという脱線には陥らない、ということをしっかり弁証したいと言っているわけであろうと私は思う。
魚木は「日本基督教」論では汎神論的世界観に接近してしまっている
また熊野は魚木が「類型論」を採ったことについて、大正末から哲学界に強い感化を与えたディルタイの影響を推測し、その結果「歴史的相対主義ないしは汎神論的な世界観に接近」してしまっていると指摘する。
その説の裏付けとして熊野は魚木自身の「(日本)基督教の特色は習合宗教を案出すること」ではないと言いつつ、「神道は神道、仏教は仏教、基督教は基督教として存続しつつ、最も密接なる相互関係に立つことを信じるところにある」、「真の意味における(日本基督教の)福音伝道」は「他を深めつつ自らを深めること」であるとし、熊野は総括して、魚木は歴史神学者であるが「歴史的実証主義に立つ」よりも「観念的な歴史意識に導かれて」しまっていると批判するが、同時に魚木に対して「きわめて同情的」とまとめている。
魚木にして乗り越えられなかった限界――観念論への逃避
私はがそれを読んで思うことは、魚木が体制翼賛的な時流を根拠にすることなく、自らの独立したあくまで学的な取り組みとして、世界のキリスト教に「日本型」という類型を加えたのは評価できるにしても、やはり歴史をあくまで事実の実証として明らかにするのでなく、観念的に処理しなければこの時における論を成し得なかった、という、魚木にして乗り越えられなかった限界を熊野は、また山口も指摘しているのであろう。
魚木と同論の比屋根安定の方が「習合的解釈」を克服しようとした
さらに山口は熊野が、魚木と「論旨の進行」を「同じ軌道に沿っている」比屋根安定の論の方を高く評していることを紹介する。
それは比屋根は魚木とほぼ同じ方向性の論を張ったが、魚木がそれを「在るべき日本キリスト教」として描き出そうとしていることに対し、比屋根は、「いまの現状としてはこうだ」という叙景または、それを知りたい人への日本的キリスト教の「道案内」に留めていることが良いとしている。
さらに比屋根が、日本的キリスト教における習合的宗教解釈を批判した『所謂日本的基督教を批判する』を熊野は高く評価している。
熊野は比屋根が魚木と同じ方向性をとりながら、その路線が「習合的宗教解釈」になってしまう点をさらに克服しようと努めた点にアドバンテージを与え、それを合わせて魚木の「日本基督教」論を読めば、なお普遍的な、今日にも通用する論になるであろうと惜しんでいるわけであろう。そのような論は、今日の我々が取り上げてさらに精巧に発展させていく意味があるものと熊野も山口も考えているのであろう。
これで、山口の連載の諸論であろう「第1回」「第2回」についての私の文を結びとしたい。
第3回以降の山口の連載
第3回以降、山口が1月に1人ずつ取り上げているのは、曽我部四郎『皇室と基督教』(2022年3月号)、對野福平『我國体と基督教』(5月)、黒崎幸吉『我が國体と基督教』など(6月)、中田重治『聖書より見たる日本』(7月)、内村鑑三著を海軍少将太田十三男編の『愛国心と基督教』(8月)、山口鹿三『日本精神とカトリック教』(9月)、海老名弾正『日本国民と基督教』(10月)、谷口茂壽『日本人に与へられし基督教』(11月)・・・となっている。
私も、個人的に関心の高い内村鑑三の流れの黒崎や、太田による内村の扱い方、「敬虔主義」のビッグネーム・中田重治、「自由主義」(同志社)のビッグネーム海老名などを中心に、また読み解きたいと思う。
魚木や比屋根が今後取り上げられるのか興味深いところである。
完
いいなと思ったら応援しよう!

