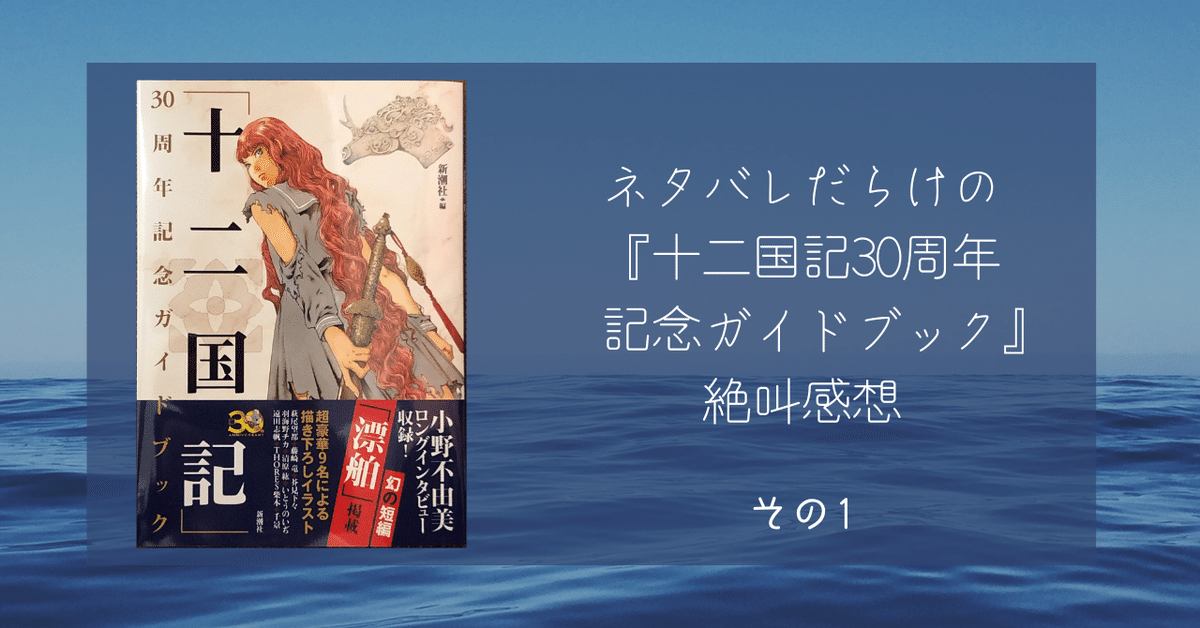
【ネタバレしかない】『十二国記30周年記念ガイドブック』絶叫感想 その1
2022年8月25日、事前情報の時点でファンを阿鼻叫喚へと叩き落としていた、『十二国記30周年記念ガイドブック』が発売された。
事前予約をしていたものの、当日朝になっても書店から発送完了メールが来ないことに業を煮やしたわたしは、予約をキャンセルして書店へ向かった。
1店目は「予約分で完売」、2店目は「こちらが最後の1冊です」だった。
セーフセーフ。
しかして、25日からこれまでわたしはどうにも体調が優れなかった。
『十二国記30周年記念ガイドブック』という衝撃を、受け止めるだけの体力が心身ともにないことがよくわかっていた。
だから我慢した。
全力で本に向き合える、この時を。
アートギャラリー
実を言うと、この記事はまだ読み終わらない途中で書いている。
今まさに、「記念アートギャラリー」を見終えたところだ。
前情報の時点で絶叫していた。
あの「フジリュー」、我が青春の『封神演技』の作者が寄稿しているではないか!!
フジリューの十二国記だあああああああああああああああ!!!!!
情報が出た時から狂喜乱舞していた。
ほかの方々も、お名前は拝見したことのある著名な漫画家、イラストレーターばかりなのだが、やはりフジリューである。
フジリューは誰を描くのだろうか。
ページをめくる前に、目をつぶって深呼吸をした。
いよいよだ。
あああああああああああああああああああああああああ!!!!!!!!!
珠晶ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!
星彩に乗ってるーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!
かーーーーわーーーーいーーーーいーーーー!!!!!!!!!!!
ぜぇぜぇ。はぁはぁ。
この手袋と靴の大きさよ。
あまりにもフジリューよ。
珠昌の可愛さよ。
喜媚ちゃんかな?
この珠昌は語尾に「☆」がついても許せる。
かわいい。
そして星彩の美しさよ。
これが騶虞の美しさか…… そして改めて、古代中国風の背景大得意ですね、フジリュー。
ああ、すばらしい。
ちょっとほかの先生方のイラストについてはもうご勘弁いただきたい。
わたしの全てはフジリューに持っていかれた。
でもどのイラストもすんばらしかった。
陽子も泰麒も最高じゃあないですか。
好き。
各巻紹介
話は戻って、ガイドブックは各物語の紹介から始まるのだが、もうあらすじ・紹介文だけで泣きそうになった。
特に最近、『魔性の子』から泰麒の物語を読み直している最中なので。
そうか、『魔性の子』の2年後に『風の海 迷宮の岸』が出たのか。
『ゴースト・ハント』シリーズあたりから小野先生を追いかけていた若き読者は、度肝を抜かれたであろうな……
わたしは『魔性の子』は当時のホワイトハート版の『華胥の夢』を読み終えた後に読んだため、もともと「空白の時間の物語」として読んだわけだけれど、紹介文にあったように「先に読むか、後に読むか。どちらか一つしか選べない、そしてどちらも読後感が違うはずの物語」というのに深くうなづいてしまった。
できることなら、記憶を消して両方を堪能したい。
『月の影 影の海』、紹介文で「前半はちょっと辛いが」と書かれていたが、ちょっとどころではない。
誰もが布教をする際に、「下巻になったらネズミが出てくるから。ネズミが出てくるまで耐えて」と言って布教をするのだ。
ネズミが出るまで耐えなければ、十二国記の素晴らしい世界に触れることができない。
あの辛さは「ちょっと」どころではない。
『丕緒の鳥』
エピソード5に『丕緒の鳥』が来ていたのは、意外といえば意外だった。
そうか、新潮文庫に映った時点で、5巻目として刊行されていたのか。
わたしとしては、というか、多くのファンにとっては、『華胥の夢』の次の2冊目の短編集、という位置付けなのだろうと思うけれど。
実はこの短編集に入っている「落照の獄」ー 柳の刑吏の物語 ー は、2009年だかの「yomyom」に掲載されているのを読んでいた。
当時、日本ではなんらかの事件の犯人の「死刑執行」について、議論が大いに交わされていたことを覚えている。
だから「落照の獄」を読んだとき、これまでの主要人物が誰一人登場せず、「帰山」で朝の終わりを示唆されていただけの柳で、官吏たちが「死刑執行の是非」について議論するだけの、ある意味で主人公不在のこの物語に、「十二国記でこれをするのか……」と感嘆した。
いや、ある意味で落胆はした。
なにしろ、大好きなキャラクターたちが、一ミリも出てこないのだから。
そして『丕緒の鳥』に収録されている作品はいずれも、「十二国記の主人公ではない人々」を主人公に据えた物語だった。
王が変わろうと、国が傾こうと、そんなことは関係なく、あるいはそれに振り回されて生きている人々がいる、という、その淡々とした事実。
慶の物語であったり、柳の物語であったりと、舞台となる国と時代は大体わかるようにはなっていたけれど、初読のとき一番叫んだのは「青条の蘭」だった。
いくら読み進めても、どの国の話かわからない。
どの時代の話かわからない。
最後の最後になって、主人公が植物に蔓延る疫病の情報を届けた時にかけられた、「今の地官遂人は話のわかる人だから」という一言で、
「帷湍じゃないかーーーーーーーーーーー!!!!!!
延王の!!!
この匂わせっぷり!!!!!
これもう絶対大丈夫なやつーーーーー!!!」
と絶叫したのは、今でもいい思い出です。
まったく、延主従はこれだから好きなんだよ。
出てくるだけで「あ、もうこれ大丈夫なやつ」てなるやつ。
ちなみに「あ、これもう大丈夫なやつ」のTOP2は「延主従」と「楽俊」です。
異論はあるまい。
『図南の翼』
これはもう大好きなやつ。
みんな大好きでしょ、珠昌。
紹介文にもある通り、一番爽快で、一番「冒険活劇」という言葉が似合うのが、この『図南の翼』。
あらためて、ありがとうフジリュー。
十二国記の推しキャラはみなさんそれぞれいると思いますが、わたしは断固として利広です。
いや、「もっと好きなキャラ」とか「もっと好きなエピソード」とかはたくさんあるんですが、わたしの性癖に一番ぶっ刺さるのが利広なのでね。
なのでエピローグは大好きです。そして「帰山」も。
珠昌がさ、世間知らずのお嬢様かつ敏腕の商人であり、「あたしが王になるのよ」と豪快に言ってのけるその裏で、「あたしに王なんて務まるわけないじゃない。でもこれが民の義務だからよ」と弱音を抱えているところ。
そんなところに読者はグッとくるのでしょうねぇ。
『図南の翼』の前に『風の万里 黎明の空』でドS女王様として登場した彼女が、こんな思いを抱えて登極したなんて。
そりゃあ祥瓊のことだってぶん殴りたくもなりますよね。
わかります。
『白銀の墟 玄の月』の思い出
忘れもしない、2019年9月12日。
18年ぶりの長編新刊、ということで、十二国記の民は湧きに湧いていた。
紹介文にもあるとおり、発売日に合わせて有給をとるものあり、関東を直撃した大型台風に対して「王がお戻りになるのだから仕方がない」と言い合った、あの伝説の発売日である。
わたしはその日、出勤予定日だった。
朝イチで通る乗り換え駅の書店の開店は8時。仕方がない、帰りに買うしかないか。
そう考えていたのだが、仕事の行きと帰りの電車の時間、我慢してやる義理などないと心に誓い、早朝から売り出している書店の情報を探し始めた。
都内に1件、24時間営業=9月12日0時に本を手にできる書店を見つけた。
すぐに電話して予約をした。
そしてその日が近づくにつれ、超大型台風が東京を直撃する、というニュースが溢れかえった。
ベランダのものはしまえ。
窓には目張りをしろ。
水と非常食、懐中電灯の用意を忘れるな。
ガスコンロを買え。
外が気になっても、絶対に窓を開けるな。
インフラ関係者以外は出勤をするな、外出をするな。
JRも早々に日中の運休、本数の削減を発表した。
東京ではあり得ない、未曾有の大災害が予想された。
さすがに職場からも、「この日は臨時休暇とします」との通達が出た。
東京直撃は午前から午後にかけて。
大丈夫、9月12日0時には、まだ警報圏には入らない。
わたしは夜10時、つまり発売の2時間前に書店に行った。
レインスーツとレインコートという、完全防備だ。
店内には、王の帰還を待ち望む民の姿がちらほらといるようだった。
だれも本を立ち読みすることなく、そわそわと店内をうろついているので、目立つことこの上ない。
10時半ごろ、アルバイトの店員が流石にまずいと思ったのか、どこかに電話をかけ始めた。
店長にでも対応を確認しようと思ったのだろう。
すぐさま、「十二国記の新刊を予約されている方は、こちらからお並びください」と声がかかった。
わたしは気がついたら、前から10番目以内に並べていた。
ラッキーである。
待機列は店内の外周のうち半分を、あっという間に埋め尽くした。
列の最前にいた数名の猛者が、「”最後尾”と書いた紙を後ろの方に持ってもらったらどうですか」と店員に進言し、即座に受け入れられた。
どう見てもその道の者である。
店員が札を持って列の最後に行くと、最後尾の方が「わたしが持ちますよ、順番に回していくんで」といって店員を解放した。
どう見てもその道の者である。
11時過ぎ、新潮社の担当の方が様子を見にこられた。
その時には、列は店内の外周を一周していた。
担当の方も驚かれたことだろう。
超大型台風の警報がこれだけ出ていて、終電がなくなる危険のある中、これだけの人が最速購入を求めて列を成しているのである。
11時が過ぎると、流石に雨も強くなっていった。
列の前後の方々と、「王がお戻りになるから仕方がありませんねえ」「今回の蝕は被害がどのくらいになることやら」と不謹慎極まりない話をしつつ待っていた。
だが待機列は店の外周にまで及んでいる。
そして山手線の終電は0時台だか1時台である。
0時に会計を始めたら、これだけの人数を捌けるのだろうか。
危機感を覚えたのは、やはり「その道」の最前列の人々だったようで、店長と思しき人に「先にお会計をして、0時になったら商品を渡す、というのは可能でしょうか」と交渉を始めた。
さすが猛者は発想が違う。
この提案もすぐに受け入れられた。
なにせ、予約の方法が「書店で直接(控えあり)」「電話で(控えなし)」の2種類であり、支払い方法は現金、クレジットカード、交通系ICの3種類あったのだ。
予約者名を付き合わせるだけでも大変な作業である。
予約者はどうせ、その日発売の1・2巻両方を買っているのである。
問題は、1組なのか2組なのか、あるいは3組なのか、その程度だ。
誰にどの包みを渡しても問題ない。
かくして、店員の手動による「ご予約方法は…お名前は…セット数は…お支払い方法は…」が始まった。
レジは2台の町の本屋である。
名前と控えを確認し、現金なりカードなりを預かりレジに戻る、お釣りとレシートを持って戻る。
はい次の人。
おかげで、0時を回る頃には、店内の半分以上の人の会計が済む状態になっていた。
11時50分
11時55分
11時58分
11時59分
カウントダウン
9月12日0時ちょうど。
「只今より、十二国記新刊をお渡しいたします」
万雷の拍手。
お会計が終わっている列はあまりにもスムーズに、「こちらです」「ありがとうございます」と袋に入った新刊を受け取って書店を出ていく。
見ると、店外の外周の見えないところまで、待機列は伸びていた。
事情を全く知らない一般のお客さんが目を丸くして、「今日何かあるんですか」と呟くのに、「新刊の発売日で」と返し、同志は互いに「道中ご無事で」と声を掛け合って帰っていく。
ある人は目の前の山手線の駅に、ある人は24時間営業のファミレスに向かって。
0時の発売から、0時5分の山手線乗車まで、一瞬の出来事だった。
泰王帰還による(1・2巻では帰還はならなかったが)蝕は、丸1日続いた。
わたしは帰宅後、あまりの眠さに即座にベッドに入り、新刊を開いたのは昼を過ぎてからだった。
3・4巻の発売日は、今度こそ王のご帰還であるにもかかわらず、晴天であった。
わたしは今度こそ有給をとり、しかして0時前に並ぶのはもう懲り懲りだったので、7時から十二国記だけを販売開始する三省堂書店で予約をすることにした。
5時過ぎに着いたら、3番目だった。
購入してそのまま店の向かいのスタバに入る。
どの席の人も一様に同じ本を読んでいる光景は、圧巻というよりも異様だった。
誰もが息をのみ、緊張した面持ちで一心にページを捲る姿に、うっかり朝活だかで入店してしまった人はどう思っただろうか。
隣の人も、後ろの人も、目の前の人も、向こうの人も、全員が同じ本を読んでいる。
全員が、泰王のご無事と泰麒の行く末を祈り続けている。
こんな読書体験は、後にも先にもこの時だけだろう。
わたしは最後の、驍宗様と泰麒の対面シーンが、あまりに美しくて泣けてくる。
泰麒には、幼い頃に中庭に立たされていたときの、雪の冷たさと鋭利さがまとわりついている。
圧倒的な静寂、美しさ、時の流れが止まったような厳かなあのシーンほど、胸を抉るものはない。
幼くいとけない、可愛らしくて優しい泰麒は、永遠に失われてしまった。
そこにいるのは、何があっても驍宗様のお側にいるという鋼の意志をもった、儚くも美しい泰麒だ。
そんな感慨をもって、美しい哀しさに浸りながら読んでいたのに、それを軽々とぶち壊してくれるんだよな、延主従。
延が出てきた瞬間の安心安定感といったら、どんな保険よりも心強いですわ。
特別エッセイ
何人もの作家が新刊への想いを綴っている特別エッセイ。
わたしの愛する「八咫烏」シリーズの阿部智里さん、『鏡の孤城』の辻村深月さんをはじめ、読んではいないが名前を聞いたことのある方々が、万感の想いを綴っている。
ちょっと笑ってしまったけど、作家さんでも「小野主上」って呼ぶんですね。
一般人ファンだけじゃなかった。そりゃそうか。
一旦休憩
あまりにも長くなってしまったので、とりあえずここまで。
後半の小野主上のロングインタビューと、待望の幻の短編「漂舶」を読んだらまた叫びにきます。
ところで、『白銀の墟 玄の月』ってみなさんどうやって入力してます?
わたしは怠惰な民で単語登録していないため、毎回
「はくぎん の はいきょ(廃を消す)、くろうと(人を消す)の月」って入力しています。
もっと楽な入力方法があったら教えてください。
いいなと思ったら応援しよう!

