
ホタル狩りへ行った夏
Miiさんの記事を読んで、思い出したことを書かせていたただこうと思います。
記事を書くヒントをいただき感謝いたします。
私は息子たちが3歳違いだったので、地元の小学校には9年間お世話になりました。
そのうち3年間はPTA本部役員として充実した体験をさせていただいた事があります。
そのうちのひとつ、校庭での「デイキャンプ」は今でも忘れられない思い出なのです。
校内デイキャンプの恒例イベント
地域のボランティアグループ「おやじの会」が主催し、PTA役員や教員の方々の協力による恒例行事で、毎年6月のいずれかの土曜に実施していました。
午後から集合して、少しゲームなどを楽しみながらのオリエンテーションでコミュニケーションを深め、その後は小グループに分かれて、夕食用にカレーライスを作ります。
なるべく大人が手を貸さず、子供たちにさせるのが主旨なのですが、これがまた、包丁の扱いなどは怖くて見ていられず、特に低学年グループについた時には、思わず口と手が出てしまいます。
基本的に我が子のグループにはつかないので、私がつくのはよその子なので、余計に責任を感じてしまうのです。
ヒヤヒヤしながら見守るのですが、それがなかなか度胸の要る事でした。
6月は梅雨とはいえ晴れれば非常に日差しも強く、大汗をかきながらの調理で、なかなか体力を使うハードな事でした。
その分、出来上がったカレーライスは家で食べるよりずっと美味しく、何杯もおかわりする子供たちも大勢いました。
「ホタルを放つ」人気イベント
現在は捕獲禁止か?
さて、本題ですが、夕食を食べ終えてみんなで片付けをした後、19時ぐらいになるとやっと暗くなり始めます。
ここで毎年子供たちが楽しみにしているのが、
ホタルを校庭に放つ事でした。
今現在、当小学校のホームページを見ても、「校内キャンプ」は6年生のみになっており、ましてや「夜のホタル」などどこにも載っていません。
きっと絶滅危惧となる蛍の捕獲は厳しくなって、完全に禁止されてしまったのかもしれません。
当時18年ほど前は、詳細はわかりませんが、教育の一環であればOKだという許容範囲があったのだと思われます。
校内の電灯を全て消し、真っ暗にした状態でのホタルの光は、とても幻想的で、みんな目を輝かせて、黄帽子を網変わりにして捕まえて、間近で観察していました。
中にはホタルを見るのは初めての子も多く、それぞれにとっては大変貴重な体験だったのです。
蛍の捕獲は本部役員の仕事
それらの蛍はどのようにして用意したかというと、
これもまたありがたいことに、地元の年配の方々の中でボランティア協力して下さる方が、ホタルの生息するところまで案内してくださり、本部役員が捕獲するのです。
本部役員とはいえ、決して強制ではなく、希望者のみなのですが、我が家は毎年、二人の息子たちと共に参加させていただきました。
ですから、参加の各役員にはそれぞれの子供たちも、もれなく付いてきますので、総勢約12,3人になり、2台に分乗して向かいました。
ホタルの生態上、捕獲できる気候は限られています。
無風で気温が高い日が望ましく、
雨が降っていたり風が強い日は中止となるため、2日ほどの候補日を予定して実行していました。
ですから、当日に中止となる時もあったのです。
蛍の生育条件
ボランティアの方の案内のもと、車で高速を使い1時間以上かけて山を越えた田舎まで行きました。
蛍はそもそも何をエサとしているのか?
幼虫時代に水中でカワニナという貝を食べて成虫になります。成虫となったホタルはエサを食べません。管になっている口から、水分を吸って生きてます。
カワニナとは細長い淡水巻貝で、それらが生育するところしかいませんし、また、タニシもエサとするため、それらが生育するような澄んだ美しい川が流れている所しかいないそうなのです。
川を覗いて、タニシやカワニナがいるようであれば、まず蛍の生育地域だと言えそうです。
ホタルは、卵から成虫になるまでに1年もかかり、しかも成虫となる前まで生涯のほとんどを水中で過ごし、やっと成虫になっと思ったら、たったの2週間で寿命となります。
いくら2週間の寿命とはいえ、捕まえた時点で蛍がどれぐらいの日数を生きているかわからないし、エサが水だけでいいからといっても、そんなにも長く保管できません。
せいぜい捕獲するのは2,3日前ぐらいにでないといけません。
全ての条件は一か八かの自然任せでした。
突然降って湧くホタルたち
私たちは全員、蒸し暑いにもかかわらず、長袖長ズボン、首にはタオルを巻きつけたスタイルで、暮れてゆく田舎の小川を散策していると、突然、蛍は現れます。
だいたい19時30分頃でしょうか?
一つ二つと蛍のか弱い光が見えたかと思って、見渡してみると、嘘のようにたくさんの黄緑色の光の玉があります。
街灯もない真っ暗な田舎の夜に、川のせせらぎの音と、フワフワと浮遊するたくさんの幻想的な黄緑の光。
この世のものとは思えないような優しい光景があたりに広がっていました。
「うわ!ホタルや!」
子供たちの驚きと好奇心に満ちた声が闇に響き、どの子も夢中で獲っています。
蛍は、フワフワ、ユラユラといった感じで飛び、シャープな動き方はしないので、面白いように捕まえる事ができます。
そして不思議な事に、ちょうど1時間ほどで、蛍は嘘のようにいなくなります。
正確にいうとその場に蛍はいるのですが、
お尻を光らせるという”求愛行動”を止めただけなのです。
私は3年間、3回とも参加しましたが、ホタルが光るのはちょうど1時間だったので、その正確な自然の営みには感心するばかりでした。
ゲンジボタルとヘイケボタル
日本に生息しいている蛍には主に、
・ゲンジボタル
・ヘイケボタル
があります。
文字通り、源氏蛍と平家蛍と書きます。
・ゲンジボタルー体長は約15mm。直線的に飛ぶ。頭部模様は十字。
・ヘイケボタルー体長約9mm。曲線的に飛ぶ。頭部模様は太線一本。

出典:大江町山里交流館
これらがなぜゲンジとヘイケという名がついたのか?
まずはゲンジボタルが先に名付けられて、そのあとに発見されたヘイケボタルの方が、小さくて光も弱々しいからとのことらなのです。
なんか、それでは平家に対して失礼なことだなと思えてしまいす。
では元々のゲンジボタルの由来はというと、
・「光る」と『源氏物語』の光源氏をかけたとする説
・光ることに一種の力を感じたことから、山伏を意味する験師(げんじ)に由来する説(柳田国男)
・戦に敗れた源頼政の亡霊がホタルとなり、合戦を行った伝説に由来する説
・光るので暗くてもよく見えることから、顕示(けんじ)に由来する説
・戦国時代、ホタルが乱れ飛ぶ様子を螢合戦と呼んでおり、源平合戦になぞらえたという説
ゲンジの名の由来は歴史上の源氏だけの説ではないようです。
なんか強くて大きいから源氏だとか、
弱くて小さいから平家だとか、
それはあまりにも極端な平家に対しての一歩的な中傷だと思えるので、
源平には関係のない由来説の方が有力だと、私は思いたいです。
*****
その当時は、ゲンジだとか、ヘイケだとか、なにも気にも留めていなかったのですが、確か直線飛びと曲線飛びの両方のホタルが飛んでいて、捕まえたのを観察すると、大きいのと小さいのとが混じっていたので、単にオスとメスだと勝手に思い込んでいました。
種類がまったく違うものだったとは、後になって知りました。
それにしても、数組の親子で、汗だくになりながらホタルを獲ったあの蒸し暑い初夏の事を思い出すと、川辺の独特の臭いと、草を踏む感覚とともに、この目で見た美しい光景は忘れられず、なんと貴重な体験だったことかと思い至ります。
そしてそれを地元の小学校の校庭に放った時の、子供たちの生き生きした好奇心あふれる表情を見て、大きなやりがいを感じた幸せな気持が、今さらながらに蘇るのです。
トップ画像:photoAC写真のフリー素材サイト
参考文献:ことくらべ

皆さんのスキのおかげです!
いつもありがとうございます。

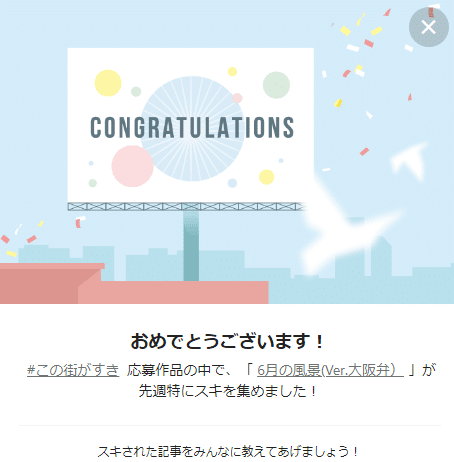
いいなと思ったら応援しよう!

