
千葉とうしろう・プロフィール
論理的な作文教師。
主に中学生を対象に、論理的な作文講座を開いています。「自分の意見を言えない」を「言える」に、或いは「自分の意見が無い」を「有る」に変えます。
1.自分の意見を言えない悩みは論理が解決する
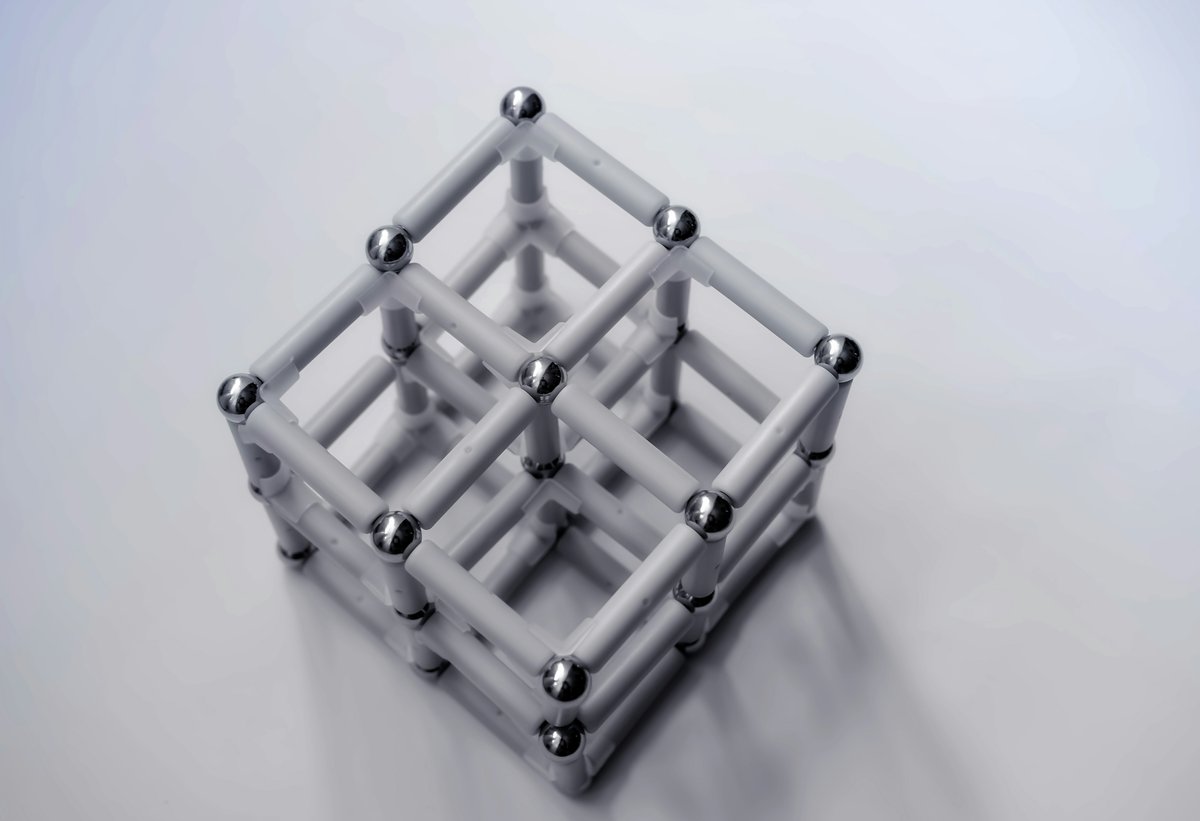
「自分の意見を言えない」ことの解決方法は2つ考えられます。1つは論理的な意見をもつこと、2つ目は「意見を言うべきかどうか」を論理的に判断すること。いずれにしろ論理を身につけることです。
(1)論理的な意見をもつこと
自分の意見を言うために必要なのは論理。論理によって意見に説得力が宿り、それによって自分の意見に自信をもてるからです。非論理的な文章と論理的な文章を比べて、説得力の違いを見てみましょう。まずは非論理的な文章から。
(ア)昼はマックにしよう。
(イ)私の経験からすると、中学の友だち付き合いは大切にした方がいい。これは間違いない。
(ウ)今日の夜は音楽を聞こう。なぜなら、明日は雨が降るだろうから。
まず(ア)。これは主張のみで、「どうして昼はマックなのか」の理由がありません。「昼はマックにしよう」と言われて、もしも相手が別の場所、例えばコンビニで昼を済ませたいと考えていたら、すんなりと「わかった。よしマックに行こう」とはならないでしょう。説得する材料がないのです。
次に(イ)。これにも理由がありません。どうして「中学の友だち付き合いは大切にした方がいい」と言えるのか。「私の経験だ」とか「間違いない」と言われても説得力はありません。百歩譲って、お互いが知り合いどうしなら説得力が出る余地があるのかもしれませんが、見知らぬ人から「私の経験」だの「間違いない」だの言われても、「なるほど、確かに大切にした方がいいね」とはなりません。
それから(ウ)。2つの文章の繋がりがわからないので意味不明です。確かに「なぜなら」は論理性を示す接続詞ですが、接続される2つの文章がここまで繋がりがないと、これは「非論理的」と言わざる得ないでしょう。
これらの文章を論理的に書き直すとこうなります。
(ア)昼はマックにしよう。ここからマックは近いから。あまり昼時間がないし、すぐに戻って来られる所がいいよ。
(イ)中学の友だち付き合いは大切にした方がいい。中学の友だち付き合いが、その後の人生の基礎になるから。ニュースキャスターがそう言ってたよ。
(ウ)今日の夜は音楽を聞こう。なぜなら、明日は雨が降るだろうから。雨が降ると気分が重くなるし、雨が降る前に気分を盛り上げておきたい。気分を盛り上げるには音楽だ。
論理は、主張を理由や根拠が支えることで現れます。
(ア)は主張「昼はマックにしよう」を理由「ここからマックは近いからね」が支え、さらに理由を根拠「あまり昼時間がないし、すぐに戻って来られる所がいいよ」で支えています。意見に説得力があり、「なるほど」と思いますね。
(イ)は主張「中学の友だち付き合いは大切にした方がいい」を理由「中学の友だち付き合いが、その後の人生の基礎になるから」が支え、その理由を根拠「ニュースキャスターがそう言ってた」が支えています。厳密な説得力があるわけではありませんが、「ニュースキャスターが言っていた」と言われると、「ならそうなのかも」と思います。
(ウ)は無理矢理ですが、なんとか理屈が通る文章になりました。主張「今日の夜は音楽を聞こう」を理由「明日は雨が降るだろうから」が支え、理由を根拠「雨が降ると気分が重くなるし、雨が降る前に気分を盛り上げておきたい。気分を盛り上げるには音楽だ」が支えています。
上記論理的な文章の例には説得力があります。論理が説得力をもたらすのです。意見に説得力があれば、自分の意見を言うことに自信をもてますよね。論理的な意見をもつことが、自分の意見を言えないことの1つ目の解消方法です。
(2)「意見を言うべきかどうか」を論理的に判断する
自分の意見を言えないことの2つ目の解決方法は、「意見を言うべきかどうか」を論理的に判断すること。自分の意見が言えなくて悩むのは大抵、思考が非論理的だからです。論理的に判断していれば「自分の意見を言えない」などと悩むことはありません。例えば、友人たちと何気ない会話をしていたとしましょう。「数学のテストが難しかったね」と誰かが言ったとして、アナタは「いいや、数学は簡単だった。勉強たところが出たし」という意見をもったとします。この意見を発言した場合に予想されるメリットとデメリットを比較して、どちらを取るかです。
予想されるメリット
・自分の考えを表明できる
・会話に参加できる
・話に進展が見込める
・「すごい」と称賛される
予想されるデメリット
・自慢として非難される
・「難しかったね」と言った友人が落ち込む
もしもアナタが「友人からどう思われるか」に特に関心があって、「自慢として非難される」ことのリスクが大きいと判断すれば「言わない」という選択肢を取れば良いのです。理由や根拠から判断を導けば、それはただ考えなしに「言えなかった」こととは違います。他の選択肢を比較考慮して判断した結果ですから。他の選択肢(意見を言う)は「メリットがない・少ない」として、頭から削除されます。悩むことはありません。もしも後から「やっぱり会話に参加すればよかったかな」などと悩むのだとすれば、それは論理以外のこと(感情)を選択肢に持ち込んで、判断のロジックをわざわざ難しくしているのでしょう。「〜するのがい良い」「〜するべし」と考えたらそうするのです。「〜するのがい良い」と考えたのにそうしないのでは非論理的です。
「意見を言うべきかどうか」を論理的に判断することで、自分の意見を言えないことの悩みは解決し得るのです。
(3)まとめ
このように、自分の意見を言えない悩みの解決方法は2つ考えられます。まず論理的な意見をもつことで説得力が宿り、自分の意見を言うことに自信をもてます。それから「意見を言うべきかどうか」を論理的に判断することでも、悩むことがなくなります。いずれにしても論理を身につけることで、自分の意見を言えないことの悩みは解決できます。
2.論理は警察官の経験から

私は元々は警察官をしており、警察の仕事の中で論理に目覚めました。説得の必要性を感じ、いざ勉強して論理が好きになり、仕事の中で論理を磨いたのです。
警察官は言い合いの仕事です。警察の責務は犯罪者や交通違反者などを見つけ、彼らにペナルティーを与えること。けれど誰もペナルティーを受けたくない。犯罪者として捕まったり、交通切符を切られるのは御免こうむりたい。ここから言い合いが始まり、相手を説得する必要が生じます。犯罪者であったり、交通違反者であることを相手に認めさせる。強制的に応じること(逮捕)もありますが、それは最終的な手段です。自由が認められている社会で個人の自由を制限しようとすると、それに付随する書類や手続きが多くなります。できればそんな面倒はかけたくないので、穏便に済ませるべく、説得が最善なのです。相手に犯罪者なり交通違反者であることを認めさせるため、説得の技術を養いました。説得の思考・技術が論理です。
(1)止まれなかったということは…。後件否定式
論理を使った説得の例です。例えば交通違反の取締りで、相手に速度が出ていたことを認めさせたい時に、私はこんな決まり文句を使っていました。
いつでも止まれる速度で走っていたなら、止まれたんです。(前提1)
運転手さんは止まれなかった。(前提2)
止まれなかったってことは、いつでも止まれる速度で走っていなかったってことです。(結論)
「AならB」が成り立つ時、「Bでない なら Aでない」が成り立ちます。例えば
横浜市民なら神奈川県民。(前提1)
あなたは神奈川県民ではない。(前提2)
ということは、横浜市民でもない。(結論)
犬なら哺乳類。(前提1)
この動物は哺乳類ではない。(前提2)
ということは、この動物は哺乳類でもない。(結論)
上記例2と例3ならば納得する人が多いと思います。これは人間の頭で考える限り、どう考えても否定できないもの。同じように例1も「止まれなかった」という事実から「いつでも止まれる速度で走っていなかった(速度が出ていた)」ことが導けます。
このように
「AならB」が成り立つ時、「Bでない なら Aでない」が成り立つ
というのは実はメジャーな思考方法であり、後件否定式という名前がついています。
前提を認めたら結論も認めざるを得なくなってしまう。前提と結論の間にある目に見えない効力が論理です。論理とはこのような、まこと不思議なものなのです。
(2)警察だって…。人と論は別
万引き犯人を捕まえたところ、犯人からこんなことを言われたことがあります。
警察だって悪いことしてるじゃないか
つまりこの犯人が言いたいのはこういうことです。
警察だって悪いことをしているじゃないか。いくら万引きが悪いからといって、悪いことをしてる警察が捕まえられるのか。
もしも論理を知らなければ、「警察だって悪いことをしてるじゃないか」と言われて縮まった態度になるのでしょう。
実際「お前だって●●じゃないか」と言われると、その後も強い態度を取ることが難しくなります。早く走るためのアドバイスをするのは足の速い人でなければならないように思いますし、テスト勉強についてアドバイスできるのはテストで高得点をとっている人でなければならないように思います。そうでなければ「お前が言うな」と言われるでしょうから。
けれどそれは間違いです。「お前だって●●じゃないか」と、あ「お前が言うな」と言われて恐れ入る必要はありません。足が遅くても早く走るためのアドバイスを堂々とするべきだし、テストで高得点でなくともテスト勉強についてのアドバイスを胸を張ってするべきです。というのも「人と論は別」ですから。
「人と論は別」とは、「その人の言っていることと、その人の人柄は別にして考えなければならない」ということです。例えば、ドロボーが「万引きなんかするな。犯罪だぞ」と言ったところで、確かに「お前が言うな」とは思いますが、万引きが犯罪であり、するべきで無いことに変わりありません。痴漢犯人が「盗撮なんかするな。みっともない」と言ってところで、確かに「お前が言うな」とは思いますが、盗撮がみっともない行為であり、するべきで無いことに変わりありません。発言内容「その人が言っていること」と、人柄「その人がどういう人なのか」を混同してはならず、分けて考えることが論理的な態度なのです。
同じように、万引き犯人から「警察だって悪いことしてるじゃないか」と言われて怯むことはありません。淡々と万引き犯人として処理すればいいのです。
「お前だって●●じゃないか」と言われても堂々としていられるのは、論理を知っているからです。論理が身につけることで、相手の発言が論理的かどうかを判断できるようになります。
このように、後件否定式で速度が出ていたことを認めさせたり、「警察だって悪いことしてるじゃないか」と言われても、人と論は別であることから怯まなかったり。私は警察の仕事の中で論理を身につけ、そして磨いてきたのです。
3.趣味の話

(1)反論しますが悪気はありません
反論が趣味です。あまり良い趣味ではないですよね。「良い趣味ではない」というのは「反感を買いやすい」という意味です。私たちの社会では、「理由を聞くこと」と「言いがかりをつけること」が混同されます。主張された意見に対して「それはどうしてですか?」と理由を聞き返すと、「言いがかりをつけている」と思われる。例えば「募金しましょう」という主張に対して「どうして募金するんですか?」と聞き返すと、募金反対派だと思われる。私たちが住んでいるのは、論理を全面に出すと相手の反感を買うことが多い、非論理的であることを前提にしたことを求められる社会なのです。
同じように、相手の論理の揚げ足をとる反論は、反感を買います。確かに、「正しい」と思って書いた記事や発言に「それは違う」と言われると気持ちに波が立つのはわかります。けれど論理的な行為としてみた場合、反論は論理に対する純粋な追求です。例えば反論は相手の論理を認めるからこそできます。反論相手の文章に論理がまったく無かったら、反論などできません。主張を支える理由や根拠があるから、その間違いを指摘できます。非論理的な文章には反論すらできない。だから反論できるということは、相手の記事や発言の論理性を認めていることでもあるんです。
(2)アニメと読書のファンです
読書をするし、アニメをよく鑑賞します。ハイカルチャーとサブカルチャーをうまく融合させた記事を書きたいと思いまして。読書(ハイカルチャー)で培った知識で、アニメ(サブカルチャー)を紹介・評論する記事です。
以上、千葉とうしろうのプロフィールでした。
自分の意見を言えるようになる論理的な作文講座はこちらのストアカサイトからお申し込みください。また質問等ありましたら、以下のフォームからお問い合わせください。
仕事依頼の記事はこちら。
