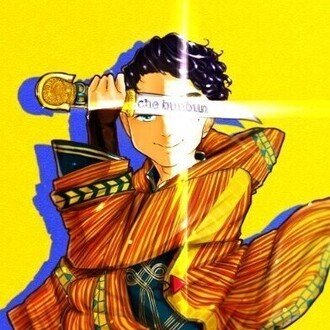映画と美術#13『写楽』蔦屋重三郎のビジネス的側面にも注目
▷キーワード:浮世絵、東洲斎写楽、蔦屋重三郎
17世紀後半、江戸芸術の代表ともいえる「浮世絵」は、国内の大衆文化を盛り上げるだけではなく印象派画家に多大なる影響を与えた。菱川師宣は木版と絵の部分を独立させ、風俗の様子を描き出す領域を開拓した。墨一色だった浮世絵も、鈴木春信を始めとし錦絵などといった技法を編み出すことにより、独特な色彩が生まれることとなる。

そんな浮世絵の代名詞のひとつといえば東洲斎写楽「三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛」だろう。大胆にデフォルメされた歌舞伎役者の姿は、大谷鬼次の奴江戸兵衛の個性や演技を現代にまで伝えるほどの躍動感がある。しかし、写楽は疾風怒濤のように現れて消えた浮世絵師でもある。1794年に歌舞伎役者などの上半身を収めた大首絵を発表し注目を集め、150もの作品を生み出したが、10ヶ月後には姿を消した。
彼の正体については、国内外で議論されている。中野三敏「写楽 江戸人としての実像」に詳細が書かれており、江戸時代には1,000近い浮世絵師がいたが、素性が明瞭な者はほとんどいなかった。写楽に関しては、浮世絵研究の中で最重要文献、斎藤月岑「増補・浮世絵類考」にて「俗称斎藤十郎兵衛。江戸八丁堀に住む。阿波候の能役者。」と記載されていた。その後、独人ユリウス・クルト「写楽」により国内外で写楽研究が進む中で、「写楽は誰なのか?」といった疑惑が巻き起こり論争が発生、写楽=斎藤十郎兵衛説を再検討する事態にまで発展した。
さて、写楽=斎藤十郎兵衛説をベースとした映画があるそれは篠田正浩監督の『写楽』である。『心中天網島』で見事に人形浄瑠璃や歌舞伎の世界を映画へ昇華させた彼が、写楽研究科でもあるフランキー堺とタッグを組んだ。また、製作にTSUTAYAが関わっている。TSUTAYAは創業者である増田宗昭の祖父がかつて営んでいた店の屋号「ツタヤ」が由来となっている。NHKのインタビューによれば、
映画ブログ『チェ・ブンブンのティーマ』の管理人です。よろしければサポートよろしくお願いします。謎の映画探しの資金として活用させていただきます。