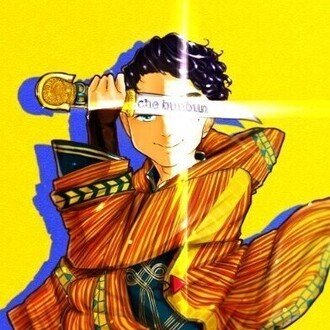映画と美術#2『わたしたちの国立西洋美術館 奇跡のコレクションの舞台裏』1年半の休館、その裏で行われたものとは?
※この記事は無料で最後まで読めます。
▷キーワード:ル・コルビュジエ、美術館経営、世界遺産
2016年に世界遺産登録された上野の国立西洋美術館を行ってきた。これは、ル・コルビュジエが1955年に設計図を作り、弟子の前川國男、板倉準三、吉阪隆正がプロジェクトの中心となり1959年に建設された美術館である。ル・コルビュジエが打ち立てた近代建築の五原則のひとつであるピロティが特徴的な建物は、実業家である松方幸次郎の「松方コレクション」を所蔵する美術館として機能している。先日、初めて訪れたのだが、そのラインナップの充実度は凄まじく、モネ「睡蓮」に始まりシニャック「サン=トロぺの港」、ロダン「考える人」と美術に関心がある人なら一度は本で目にしたことのある作品がずらりと並んでいたのだ。そんな国立西洋美術館は2020/10/19から2022/4/8までの間、館内施設整備のため長期休館となった。休館中、国立西洋美術館ではどのような取り組みが行われてきたのだろうか?
『わたしたちの国立西洋美術館 奇跡のコレクションの舞台裏』は、その全貌を明らかにすると共に美術館が抱える問題が見えてくる一作となっている。
今回の館内施設整備の中心となったのは「前庭」の作り直しであった。国立西洋美術館の前庭の下には特別展の会場がある。天井部分は防水加工がされているが25年ぐらい経っているため、改修する必要があった。また、世界遺産に登録された際の努力目標として「前庭」をル・コルビュジエが考える本来のものに戻す必要があった。世界遺産登録には真正性が重要視されている。これは文化遺産が持つ、伝統や建築技法、思想が正しく継承されているかを表す概念だが、国立西洋美術館の「前庭」は真正性の観点で問題があったのだ。映画はそんな大規模な工事の現場を追う。
外の彫刻ひとつとっても、複雑に絡み合う土台を分析し、パズルを解くようにパーツの外し方を吟味する。また、館内の所蔵品をどのように魅せるのかを学芸員同士がディスカッションしながら決めていく。さらに、長期休館中であることを活かして国内外に作品を貸し出す取り組みも行う。膨大な作業を20名程度の学芸員や研究者で行う。
取材の中で、日本の美術界の予算不足問題も浮き彫りになる。昔から新聞社とコラボを組み、展覧会を行なってきた。税金で運用されているので、購入、レンタルする美術品が適切であるか緊張が走る。特にコロナ禍では現地に行って確認することができなかったため、写真で判断しないといけず、学芸員の緊張感は非常に高いものとなっていたそうだ。確かに、美術品をどのように魅せるかは重要だ。映画のサブスクリプションサービスもそうだが、そこにあるだけでは機能しない。届くべき人に、どのような作品があるかが伝わってこそ見てもらえる。正直、国立西洋美術館に行って初めてモネ「睡蓮」やシニャック「サン=トロぺの港」、ロダン「考える人」が所蔵されていることを知った。特にシニャックの絵は好みだったため、もう少し早く知りたかったと思ってしまった。『わたしたちの国立西洋美術館 奇跡のコレクションの舞台裏』は、美術を届ける活動の一環として機能する作品といえるであろう。
『わたしたちの国立西洋美術館 奇跡のコレクションの舞台裏』(2023)
製作国:日本
上映時間:105分
監督:大墻敦

映画ブログ『チェ・ブンブンのティーマ』の管理人です。よろしければサポートよろしくお願いします。謎の映画探しの資金として活用させていただきます。