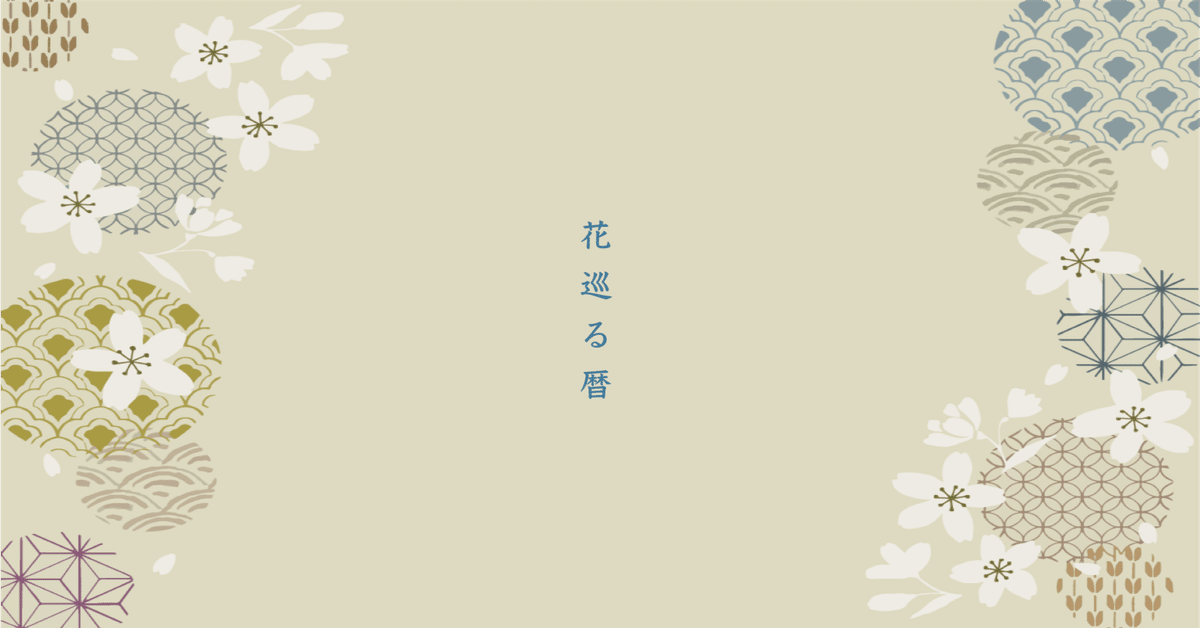
第四話 朔風花払 ―きたかぜはながはらう― (七)
<全十九話> <一> <二> <三> <四> <五> <六> <七> <八> <九> <十>
<十一> <十二> <十三> <十四> <十五> <十六> <十七> <十八> <十九>
<七>
咲保は、わっ、と泣き伏したくなった。だが、できなかった。気を緩めれば、二度と立ち上がれなくなる。彼女が取り乱せば、弟や妹も混乱させる。だが、この嵐の中にいるような、荒れ狂う気持ちをどうすればいいのかもわからない。
(足が冷たい……寒い。ああ、竈に火を入れなきゃ。お部屋にも炭を……)
どうしよう。どうしよう……?
桐眞が、兄がいなくなってしまう。いなくなってしまった。もう、二度と会えないかもしれない。桐眞は善良な人間だ。少しは悪いところもあるかもしれないが、良い事もたくさんしている。こんな風に生を終えていい人間ではない。家には必要な人間だ。いなくなっては、困る人や悲しむ人が大勢いる。なのに、なぜこんなことになるのか?
「……さん」
どうしよう――こんな時にこそ兄が必要なのに、どうしていないのだろう? 目頭が熱くて痛い。
(どうしよう、どうしたらいいの……?)
「さ……さん、さくほさん!」
どうしよう……
「咲保さん!」
肩にかかる手の重さに、あ、と気づけば、目の前に浜路がいた。
「落ち着いてください。大丈夫です」
「浜路……お兄さまが……」
「はい、わかっています」
「これからどうすればいいの? お兄さまがいなくて、私はなにも出来なくて……」
「いいえ、なにも出来ないわけではありません。若さまも頑張ってくださるはずです。だから、取り戻しましょう」
「……取り戻す……?」
「はい、無事に。なに一つ損なわず」
「そんなこと……出来るの?」
「やります。難しいですが、こちからかも手を伸ばせば、若さまならば。だから、手を貸してください。私も、このままではすませられません」
いつもどこか自信なさげな浜路が、やけに頼もしく見えた。
「でも……どこにいるのかもわからない。『あわい』は広すぎるわ」
「大丈夫です。みぃさんがついていますから」
「あ、みぃ……」
そう言えば、そうだった。桐眞に追い縋った飼い猫のことが、すっかり頭から抜け落ちていた。みぃも大事な家族の一員だというのに、なんということだろう。
「私は、みぃさんならどこにいても見つけられます。少しの被毛さえあれば、広い『あわい』のどこにいるかがわかります」
「そうなの……?」
「迷子の猫を探すのも、私どもの務めですから。みぃさんのいるところに若さまもいらっしゃるでしょう。迎えに行くまでの間、きっとあの賢い子が若さまをお守りするでしょう」
任せろ、と言わんばかりに浜路は自分の胸を軽く叩いた。
「モノにはモノのやり方があります。非は向こうにあります。一緒に目にものを見せてやりましょう!」
力強く笑みを浮かべる浜路に、咲保はしっかりと頷いた。
「お医者さまを呼んできました!」
磐雄の声が廊下に響き渡った。
◇◇◇
ちくしょう、やられた――!!
不覚としか言いようがない。水の中をゆっくりと落ちながら、桐眞は歯噛みした。視認は出来ないが、胴には太い水でできた縄が巻き付いたままだ。弾力を感じるが、両腕も一纏めにしっかりと巻き付いているため身じろぎ一つ叶わない。手首から先だけは自由になるものの、それだけではなんともならない。
薄い光が揺らぐ水面が、次第に遠ざかっていく。視界がどんどん暗くなって、そして、すぐに闇に変わった。
(『あわい』だよな)
水中の『あわい』など初めてだ。周囲から圧しつけられる力を感じるのに、体重がなくなってしまったかのような浮遊感も感じられて、それがなんともいえない心地よさだ。熱くもなく寒くもない。風呂に潜っている気分に似ているが、目を開けていても痛くならないし、呼吸も普通にできる。自分がどうやって息をしているかはわからないが、気泡が上がっていくのが見える。不思議でしかない。
(夢の中にいるみたいだ……)
しかし、どんなに心地よくとも、これは悪夢だ。脳に生じた小さな雷が、桐眞の本能的な危機感を刺激した。この感覚に浸り過ぎれば、そのぶん人の身からも遠ざかる――突然、そんな恐怖に襲われて、拳を握り掌に爪を立てた。わずかでも、人の感覚を維持しようと抵抗をしてみる。口の中で一通り祝詞などを唱えてみたが、なんの気配も感じない。神の助力も得られないようだ。
(ということは『場』か。万事休すだな)
通常の『あわい』と違い、『場』はそこを支配するモノの領域で、異界だ。ただの結界の中とは、似て非なる場所だ。
木栖家は、人の手、父による結界を張ったまるおの縄張りであるが、暁葉や浜路が出入りできるなど、比較的に自由だ。もっとがちがちに固めることもできるが、そうすると普段の生活にも支障が出るので、最低限まで緩く調整してある。その点、『場』は外部から不可侵の領域であり、基本、何者も出入りが不可。支配する主の招きがなければ入れないとされている。
ああ、と桐眞は嘆息した。
(どうしたものか)
まさか、こんなことになるとは思ってもみなかった。
(この年で攫われるとは……)
恥だ。家の中で油断していたとはいえ、抵抗ひとつできなかった。モノに攫われるのは、年端もいかない子供というのが定番だ。噺として伝わる分には、大人、特に色事が関わると、モノの方から訪うばかりだ。神隠しもあるが、本当のところは、何が起きたかわからない。人がいなくなった悲しみを物の怪のせいにすることも多いし、そう公言して密かに人が殺めている場合だってある。だが、実際、人ならずものの手による場合、『場』に引き込む際には、どういう形であれ意思確認がなされると伝わっている。だから、桐眞の現状は、完全に誰にとっても想定外だろう。
(どういうつもりだ?)
モノは恐ろしい。神と同じく、理不尽な存在だ。笑っていたそばから掌を返して牙を剥く。討伐で、そんな場面は幾度となく経験してきた。木栖家に出入りするモノたちは友好的ではあるが、そんなものは咲保がいるからで、妹がいなければどうなるかわかったものではない。招かれたしても、相手の気に障れば、どういう扱いをされてもおかしくはない。切り裂かれるか、喰われるか――たとえ友好的であったとしても、『場』で過ごすというだけで、何年、何十年と時間を無駄にしかねない。いくら楽しかろうとも、桐眞は浦島太郎にはなりたくはない。
途端、腹の奥から突き上げてくるものに、桐眞は呻いた。
(大丈夫だ、落ち着け、落ち着け……まだ何も決まったわけではない。冷静になれ!)
焦れば、勝機を見逃すことになりかねない。相手が油断すれば、隙をつくこともできるはずだ。伊達に、幼い頃より祖父の厳しい教えに耐えてきたわけではない。深く息を繰り返して恐れの感情を飲み込み、奥底に沈めていく。自分でも、そんなものがあることを忘れるくらいに、己に言い聞かせ制御していく。浮き沈みを何度も繰り返していくうち、なんとか高まる心臓の音が次第に収まっていった。
すい、と視界の端に、淡く光る何か動くものが見えた気がした。腹の上で低い唸り声があった。
「みぃ……」
さすが猫だ。不安定な位置でも袴の帯にしっかりしがみついている。ぐぅ、っと喉を絞りあげるような声で唸り続けている。明らかにか弱い生き物が、全身の毛を逆立て、尾を倍の太さにして勇ましく威嚇している。この飼い猫がなぜ桐眞についてきたのかわからないが、小さな存在が今は何より有難いと感じた。無性に、両手で撫でまわしたい気分だ。今はそれができないのが、悔しい。
「みぃ、ごめんな」
弟と妹が縁の下でみぃを見つけて飼い始めた時、桐眞は密かに犬だったらよかったのに、と思ったものだ。猫が嫌いなわけではない。ただ、犬なら番犬にもなるし、言うことをよく聞くし、散歩ついでに伴走するのも身体を鍛えるのにも楽しかろうと思った。猫も可愛いとは思うが、鼠を取る以外にそう役立つことはない。それどころか、忙しい時に限って「遊べ」としつこく邪魔しにきて困る。暇なとき遊んでやろうとすれば、見向きもしない。気まぐれな生き物だ。それが、今はこれほど頼もしい存在もいない。それは、上の妹にも言えることで。上の妹こそが、桐眞の命綱をいちばん先頭で握っているに違いない。不思議とそう信じられる。
(咲保……)
咲保は身内の目線からしても、どこか他の女性たちよりも浮世離れして感じる。普段の生活は、母の指導で華族の娘らしからぬ庶民に近いものであるのに、なぜか道楽でそうしているような印象を受ける。女性が持つ特有の土臭さや粘っこさみたいなものが、いっさい感じられないのだ。そのせいか、理解しようにも無理だと、最初から決めつけてしまうような雰囲気を持っている。それは、彼女の周囲に自然と集まってくるモノたちの影響もあるかもしれない――そう思うようになったのは、最近のことだ。
咲保の周りに集まった彼女たちが、どういう縁で咲保の側にいるのかは、桐眞は知らない。どういうつもりかも。が、彼女たちがいることで、咲保が、他人やほかのモノから守られていることもわかっている。それだけ、咲保の体質は、わかっている桐眞やほかの常人とも違う。
子供の頃は、妹が特別扱いされていることが、ただ気に食わなかった。心の衝動そのままを咲保に向けたことがある。結果、二度ほど殺しかけた。一度目は、咲保が物心もつかない赤ん坊の頃に、目の前で姉と喧嘩して。二度目は、桐眞が八歳の頃だ。拳を使ったわけではない。たった一言、心ない言葉を発しただけだ。それだけで妹は倒れて、心の臓を止めかけた。あの時、まるおがいなければ、咲保は死んでいた。
一度目はともかく、二度目は殺意はなくとも明確な意思があった。しかし、桐眞にそこまでのつもりはなく、精神の未熟さゆえの事故と言える。それでも、しでかしたことを、一生忘れることはないだろう。思い出すだけで、悔恨と恐ろしさに、身がすくむ。
その後、桐眞は急遽、輝陽の祖父のもとにやられ、専門知識の修得と稽古に明け暮れることになった。まだ同じ年頃の子どもたちが、何も考えずに遊んでいられる頃だ。『あわいの道』の使い方は、まるおや両親が付き添い往復する間に、徹底的に叩き込まれた。それに姉の知流耶もとばっちりのようにして道連れになった事には、いまだに文句を言われる。咲保に謝る機会も失った。そのせいか、溝も埋まり切らないままだ。
だとしても、血のつながった妹に対する情は、桐眞の中にある。おそらく、咲保の中にもあるのだろう。日々の心遣いに感じる。今は、それに縋る。
普通なら諦めるしかないこの状況でも、妹の持つ知識や手助けしてくれるモノたちが必ずなんとかしてくれるに違いないと、不思議と信じられる。糸のように細い希望だが、なにもないわけではない。
(焦るな、気を鎮めろ)
みぃがいなくなれば、弟や下の妹も悲しむだろう。そのためにも、無事に帰還しなければならない。最後まで抗ってみせる――そのためにもできることをすべきだ。
(なにもせず、折れるわけにはいかない。諦めるな!)
己を鼓舞する。まずは、『彼を知り己を知れば百戦胎うからず』だ。とにかく、生き残ることが第一目標。桐眞は頭の中にある玄武の知識を引っ張り出して復習する。『場』で戦うにおいて、どんな手が有効かは皆目見当もつかないが、なるべく臨機応変に対応できるよう準備しておいて損はないだろう。
(玄武は四神に於いては、北。山あるいは丘陵を表す。色は黒。五行に於いて季節は冬。水であり、水生木、土剋水……そういえば、蛇は金気を嫌うという話もあったな……玄武の蛇はどうなんだろう?)
『あわいの道』ではどんなに遠くても近くても、体感時間は四半刻――凡そ三十分ぐらいだ。ここは『場』だからそれも変わるのかは不明だが、到着までにもう少し時間がかかりそうだ。ゆっくりと沈みながら、桐眞は考えを巡らせた。その時、ふ、と心に引っ掛かるものを感じた。なにか大事なことを忘れている気がする……。
「あ、期末試験……」
悲鳴をあげた。
