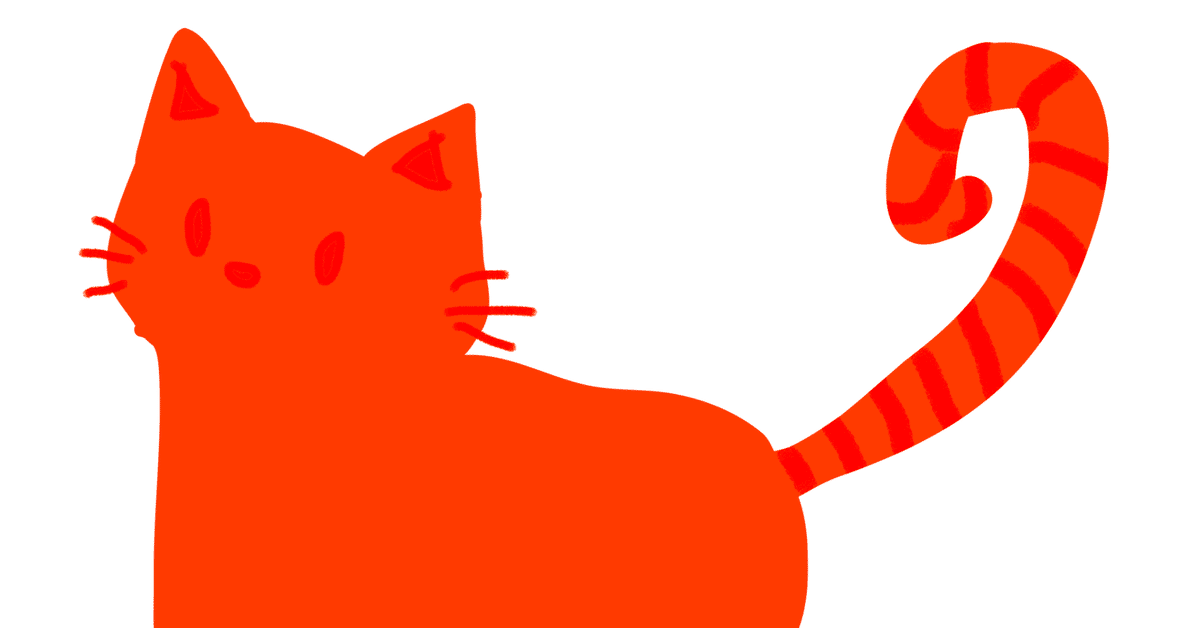
教育現場でどう読む?『わたしはあかねこ』の違和感
💡 わたしはあかねこの「らしさ」を考える 🌟
こんにちは!
投稿がかなり空いてしまいました・・・
初心に戻ってまた癖のあることを書いていきたいと思います。
今日は『わたしはあかねこ』という人気のある絵本について考えます。
皆さんはこのお話を知っているでしょうか?

簡単なあらすじです。
白い母猫と黒い父猫の間に生まれた赤い毛並みの「あかねこ」。その鮮やかな赤色は他の兄弟たちとは明らかに異なり、周囲の猫たちはその違いを心配します。かぞく家族の猫たちは白い牛乳をたくさん飲ませたり、模様がつくように色を塗ったりします。しかし、あかねこ自身は自分の赤い毛を気に入り、誇りに思っています。そのため、家族から色を変えるように促され続けどんどん居心地が悪くなっていきます。
やがて、自分の居場所を探すために家を出て旅に出たあかねこは、青い毛並みを持つ「あおねこ」という猫と出会い、意気投合します。あおねこに「あかいけなみ きれいだね」と言われ、深い絆を築いていきます。そして最終的に、二匹は新しい家族を作り、自分たちらしく幸せに暮らすのです。
一見、多様性や自己肯定をテーマにした美しい話に見えます。認知度も高く、評価もすばらしい作品です。
しかし、少し批判的な視点で見てしまうと、どうしても引っかかる点がありました。
それは、この物語が提示するテーマやメッセージが、表面的には美しく見えるものの、深く掘り下げると曖昧さや矛盾が残っているということです。
違和感が残ってしまったものはしかたがありません。それならば、その違和感の正体を解き明かすべく、あえて掘り下げて考えてみることにしました。
考えるきっかけ 🧐
この物語について考えるきっかけは、学校で行われた道徳の研究授業でした。その授業では『わたしはあかねこ』が教材として使われ、多様性の理解や個性の尊重といったテーマで授業が進められていました。一見すると納得のいく着地でしたが、私自身は「これで本当にいいのか?」と強い違和感を覚えたのです。
その違和感とは、物語の中で自己肯定や自分らしさがどのように描かれているかに対するものです。
絵本に突っ込むのもおかしいかもしれませんが、教育現場で使うからこそ、メッセージの深さやリアリティについて考える必要があると感じました。
1. 自分肯定のプロセスの描写不足 🔍
『わたしはあかねこ』では、主人公のあかねこが最初から自分の赤い毛を好きである状態で始まっています。この点にまず違和感を覚えました。
あんなに家族は色を変えさせようとしてきたのに。
誰もほめたり認めたりしてくれなかったのに。
それでも自分の色に自信をもって好きでいられるだと、、?
むしろそんなに強い個体なら、その時点でハッピーハッピーエンドにしてもいいくらいでは?
現実的な話、私たちが「自分を好きになる」ためには多くの過程が必要です。
とりわけ、葛藤や試練、他者との比較などがあると思います。
家庭で自分の個性が否定されるような環境にいる場合、自己肯定感を育むことは簡単ではありません。
それなのに、あかねこがどのようにして自分を肯定するに至ったのかという過程が描かれていないため、読者が共感し、学びを深める余地が薄れてしまっています。
((むしろそこが知りたいのに!!!))
例えば、もし物語の中で、あかねこが「自分の赤い毛が周りと違って変だ」と悩み、それを乗り越える経験が描かれていれば、自己肯定感について深い学びが得られると思います。
また家庭で、親や兄弟があかねこの毛をどう受け止めたのか、そしてそれがあかねこの自己肯定感にどう影響したのかが描かれていれば、物語によりリアリティが増していたでしょう。
私が授業をするなら、この自己肯定のプロセスを想像させる発問をしたいです。
・あかねこはどうして自分の赤い毛が好きなのだろう?
・もし自分の特徴が友だちと違っていたらどう感じるだろう?
逆に、「家族から毛の色を変えるように言われたあかねこの気持ちは?」
といったように安易に手前にあるものに飛びついてしまうと、自分の毛の色が好き、というおかしな前提を強化することになりかねません。
このあたりを考えるのは本当に楽しいですよね!
2. 他者の評価に依存した自己肯定感 🛠️
あかねこが最終的に落ち着いたのは、あおねこという受け入れてくれる存在に出会ったからです。安心感を得て、家族とは一緒に暮らさなかったあかねこは、あおねことは暮らしました。
この点においても、私は「本当にそれでいいのか?」と疑問を抱きました。
本当の自己肯定とは、他者に認められることに依存せず、自分自身の価値を認識することだと思います。
しかし、あかねこの場合、あおねこが「そのままでいい」と言ってくれたからこそ自分を肯定できたように描かれています。これでは、あおねこがいなければあかねこは自分を好きになれなかったのではないか、という印象を受けます。
人からダメと言われたら肯定できなくなるような脆弱な自分らしさってどうなんだろう?
私たちが自己肯定感を育む際には、他者からの評価に左右されずに自分自身を認める力を持つことが重要だと考えます。
他者依存型の自己肯定感は、他人に評価されない状況下では簡単に崩れてしまうリスクがあります。
物語の中で、あかねこがあおねこに依存せず、自己の中から肯定感を見つけ出すプロセスが描かれていれば、より力強いメッセージが伝わったのではないでしょうか。
3. 自分らしさとは 🤔
『わたしはあかねこ』が問いかける「自分らしさ」も、私には少し曖昧すぎると感じました。
この疑問を深く考えるきっかけになったのは、研究授業の本時のねらいが「自分らしさについて考える」というものであったためです。しかし、その授業で「自分らしさ」がどのように定義され、深められたのかについて、私は納得しきれませんでした。
同時に、自分らしさって何なんだろうという原初の問いを考える機会になりました。
「自分らしさ」とは、単に「他人と違う自分」という表面的な特徴ではないはずです。
身長や髪形など、見た目のことでもないでしょう。それは、もっと内面的な部分、つまり自分自身の核となる価値観や生き方に関わるものではないでしょうか。
難しすぎる問いですが、私は「自分らしさ」を以下の2つに定義してみました。
1、価値観(自分の心のブレない部分)
2、人とかかわるときに自分はどうありたいか
人間は他者との関係の中で成り立っています。相手に映る自分はどうありたいか。それを意識しながら、自分の内なる価値観と調和させていくことが「自分らしさ」の本質なのではないかと考えます。
「自分らしさ」という言葉は耳にする機会が多いものの、実際にそれをどう定義するのか、そしてどのように体現するのかは非常に曖昧です。
特に教育現場では、「そのままの自分でいい」といった言葉が一人歩きしやすく、成長や変化をしなくていいと曲解されてしまう危険性もあります。
「自分らしさ」を考えるときに、子どもたちに「そのままでいい」というメッセージを伝えるだけで終わってしまうと、「努力しなくても良い」という誤解を与える可能性があります。「自分らしさ」を理由に強調しない姿勢は、学校という場所において認められるものではありません。
「そのままの自分を認めつつ、より良い自分に向かって進むことが大切だ」というメッセージを伝えることまでセットで考えなければならないと思います。
授業での議論が「自分らしさ」に留まらず、「自分らしさをどう変化させていくべきか」や「他者との違いをどう受け入れ、関わっていくか」といった視点に広がれば、より実りある学びになるのではないかと感じます。
まとめ
ここまで述べてきた違和感に至るまで、私自身も多くの葛藤を抱えました。最初は、この物語を単純に「個性を尊重する素晴らしい話」と思っていました。実際に、多様性をテーマにした教育的価値が評価され、授業で使われるほどの物語です。しかし、物語を深く読み解くうちに、自己肯定感や自分らしさの描かれ方に問題があるのではないかと感じるようになりました。
特に、授業で「違いを認め合うことが大切だ」というメッセージに固執していたことに大きな違和感を覚えました。多様性の理解自体は非常に重要なテーマであり、教育現場でも強調されるべきです。しかし、それが本当に『わたしはあかねこ』という物語で作る最高の料理なのかという疑問が浮かびました。
具体的には、この物語を通じて「自己肯定とは何か」という根源的な問いを掘り下げることができるのではないかと考えました。特に、他者の評価に依存せずに自己を受け入れるという課題に焦点を当てることで、物語の持つ潜在的な教育的価値を引き出すことができると考えます。このようなアプローチは、子どもたちに対し、表面的な多様性理解を超えた深い自己探求を促すきっかけとなると思います。
物語をそのまま受け取るのではなく、「自己肯定感とは何か」「自分らしさとは何か」を子どもたちと一緒に深く考えるきっかけとして使うべきだと思いました。
この物語が提示する問いを通じて、私たちが改めて自分自身を見つめ直し、「自分らしさ」をどう定義し、体現していくかを深く考えることができれば、それが本当の学びにつながるのではないでしょうか。
ここまで長いこと読んでくれてありがとうございました!
ご意見あれば教えてください!!
