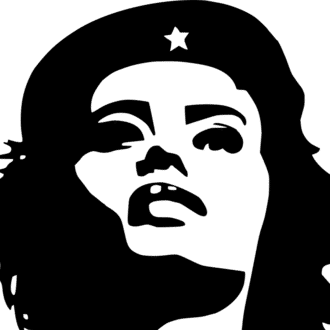西迫大祐『感染症と法の社会史』読書メモ
『感染症と法の社会史』読み終わった。
こちらの記事で軽く触れたように世界観としての感染症を記述するたいへん興味深い書物であった。
その世界観の変遷を主にフランスを中心に追っていくものだ。疫病がいまだに問題である現代において非常に重要な示唆を含んでいる。ものすごく雑にまとめると、私権の制限がどのように正当化されてきたかということであり、あるものは現代人から見れば非合理であったりする。そしてもしかして我々も相変わらず非合理的なことをしているのではないかということを考えさせる内容になっている。
以下、読書メモである。端折ってるところも多いのであくまで参考までに。
序章は古代から18世紀までの概説である。病原性微生物という概念がなかった時代だ。
その時代にはミアズマ(miasma)が病の原因と考えられていた。ミアズマには2つのイメージがある。
1つは汚れ(ケガレ、穢れ)であり、浄化や追放を必要とするもの。プラトンは病は汚れに対する罰と考えていた。トマス・アキナスは病を異端的な汚れを表示するものと述べた。それはたしかに伝染的である。
もう一つは空気の中に毒性のものが含まれている(瘴気)とする考え方だ。転地や換気が必要となる。ヒポクラテスは、教条的な汚れという考え方には反対し、合理的な思考を追求した。空気になにか良くないものが含まれていて、それが伝染していくと考えるのが彼にとっては自然であった。
汚れは当初は癩病がその典型であった。癩病患者が追放や隔離といった差別的処遇を受けることは近代まで残ったが、典型としての役割はやがてペストへと受け継がれる。
時代が降るにつれて、感染という考え方が確立して、汚れではなく疫病に感染するという概念の転倒がおきた。
汚れは触れなければよい。瘴気は吸わなければいい。しかし感染ならばどちらも不十分な対応ということになる。これによって空間的次元が代わり、対策も追放ではなく別の構造を持つようになった。
瘴気が問題であれば対応は逃げ出すことである。しかし空っぽになった都市は無法状態となり医者も逃げ出している。また病原体を地方へ拡散してしまう。
したがって感染説が確立してからは逃げ出すことは厳しく禁止される。
14世紀北イタリア諸都市でペストが流行した際は隔離、都市封鎖、衛生局設立といった処置がとられた。
フランスでは16世紀に衛生官吏が置かれるようになる。他にもペスト規則と呼ばれる細かいルールが作られていく。規律が各個人に浸透していく過程である。
ここまでが序章で、第1章は1720年マルセイユでのペストの最後の大流行の克明な記述だ。
ペストの大流行は最後になったが、それまでは疫病は中東からやってくるものだったペストのような疫病は、以降は都市に内在する危険と認識されるようになる。都市人口の増加、住環境の過密化がその原因であり、結果として衛生観念が浸透していくことになる。
衛生観念といっても18世紀はまだ空想に近いものも多かった。しかし空想上の病気の兆候が、都市の統治を駆動していく。
墓地の腐敗した空気、死体の腐敗による空気の悪化。監獄、病院、船舶などの湿った、動きの少ない汚染した空気から感染が広がるというイメージ。換気の徹底、それが無理なら郊外への移転が行われた。
18世紀は目に見えない物質が発見、分離されていく時代であった。しかしそれはミアズマという古いイメージに科学という新しい装いをもたらし再活性化した。
18世紀後半になると人々は健康のために散歩するようになる。そのため道路の汚さがクローズアップされる。
さらに交易の拡大と、都市への貧民、浮浪者の流入により、都市における精神の腐敗が問題となる。18世紀は精神の衛生が俎上に登った時代でもあった。
なぜ問題になったか。これらは悪徳だけでなく、悪臭の原因になる。当時は悪臭は病気と強く結び付けられていたのだ。
身体も精神も改善可能な、改善すべき領域となる。生権力の始まりだ。
18世紀は種痘接種が登場する。18世紀終わりから正式に許可されて種痘接種が一般的に実施されるようになる。とはいえ当時は種痘患者の膿をそのまま接種するという野蛮なことが行われていた。中には重症化して亡くなるものもいた。
しかし、種痘接種で子供が亡くなってもいい、免疫をつけた大人が生き残ればいい、大人が死ぬほうが損失が大きい。こうした統計学や確率の発想が種痘接種を正当化した。
しかし数学者ダランベールは母親たちは恐怖と期待を正確に比較できないから、国家の利益と個人の利益は一致しないと述べている。それが人間の心理なのだから非合理的とはいえないと。ただし種痘接種の危険性がほぼゼロになれば合理的になるとも言っている。
カントは、自己を危険にさらさぬよう種痘を避けるべきか、自己保存のために種痘接種すべきかについて答えなかった、無記である。政府が種痘接種を推奨すれば市民はこのような葛藤をしなくていいからである。政府がそうすべきなのは市民の福祉を実現するためである。カントは功利主義的な判断をしており、政府がリスク計算することを許容している。ミラボーも同じく期待値を計算すべしと述べた。
彼らがこのように考察したのは18世紀後半が時代の転換点だったからだ。種痘接種すべきかどうかは、いまや個人や狭い共同体の範疇を超えた、国家的なリスク管理の問題になっていた。著者はフーコーを引用している。
フーコーは述べている。「病気は、人口の中における事例の配分(une distribution de cas)として現れてくることになります。そしてその人口は、時と場所によって限定を加えられます。結果として、この事例という概念の登場によって、事例は、個人的事例を意味するのではなく、病気の集合的減少を個人化したり集合化したりする方法を意味するようになります。そして、この方法は、数量化や、位置の特定、現象の集合化、個人の現象を集合的な領域の中に統合するといった方式によって行われるようになるのです。」
19世紀はコレラが主に公衆衛生の対象となった。統計が整備されつつ有り、感染率や死亡率の高いエリアが明らかになる。水を媒介するコレラでは、それは都市の貧民街と重なる。ここから貧しい病人を助けようという慈善的な態度と、危険な要素を排除しようとする衛生的な態度という、2つの相反する方向性が生じることになる。
友愛のために私的財産の所有権を一部放棄すべきか否か、社会正義と自由の対立が生じてくる。公権力の介入はどこまで許されるか。
結局、フランスは他者危害原理という古い自由主義を再適用することでこの対立を乗り越えた。不衛生な住宅や下水道が他者に危害を及ぼすなら改善されるべきということになる。
公的な介入や立法を正当化するものとして連帯主義にも言及されている。人間は関係の中で生きており、感染症はその関係から生じる。問題が関係から生じるなら、対策もまた関係についてのものになるほかない。
そして、つながりは利益も生むが、感染症という負のつながりもある。負のつながりを避けることが可能ならば避ける責任が生じる。自由を制限するのは正義にかなっている。
というのが大まかな本書の内容だ。
私の印象としては、本書で述べられたような微生物学や統計学のもたらした転換は現在も進行中であると思われる。目に見えない病原体は汚れや瘴気として捉えられがちであるし、人間の脳は確立をうまく処理できないから統計と個人の実感はしばしば矛盾する。個人の自由と公益の対立は昨年から私達はたくさん見てきたし、そもそも公益とはなにかの対立は解消し難い。
本書を読んで、それらの対立を歴史的過程の一部として捉えられるようになったのが個人的にはよかったと思う。人間そんな簡単に変われないよね(KONAMI)
いいなと思ったら応援しよう!