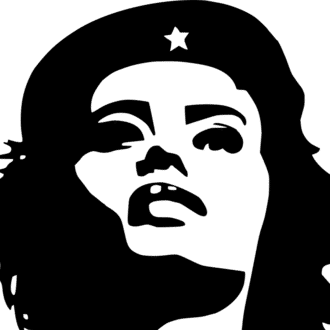ポール・モーランド『人口は未来を語る』読んだ
友人のSさんにおすすめされた本をようやく読んだのである。
早く読まなきゃと思っているうちに、白饅頭師匠が的確な書評を上げてしまわれて、もう読まなくていいかなと思ってしまったが、どうにか読んだのであった。
これからさらに3ヶ月たってるし、、、時間たつの早すぎやろ。。。
本書と似たような内容のものとして『格差の起源』がある。
同書は人口減少について、地球環境への負荷が減るからいい面もあるという捉え方だったが、『人口は未来を語る』はもっと暗い予想を語っている。
先進国もそれに続く途上国も出生率がどんどん下がっているのが現実である。
トップランナーは我が国を始めとする東アジア諸国だが、タイのような経済がまだまだキャッチアップできてない国々も急速に出生率が低下しているのは先日もとりあげたところである。
つまるところサブサハラ・アフリカ以外は一直線に出生率が低下しているし、そのサブサハラとて今後はどうなるかわからない。高い出生率を維持し続けるなら人類はアフリカに始まりアフリカに終わるということになろうか。
出生率の低下要因は、経済成長と教育水準の上昇である。特に女性の教育が進むと一生に産む人数が顕著に減る。乳幼児死亡率の低下が同時に進行することも、多産を控える要因となる。
出生率が低下しても、乳幼児死亡率の低下により成人する女性が増えているうちは、出生数はそんなに減らないが、しばらくすると成人女性も減り、出生率の低下とあいまって、人口減少に突入する。東アジア諸国はすでにこのスパイラスに入っている。
さらにやべえのが東欧諸国で、経済の水準に比して出生率がだいぶ下がってしまっており、西欧に経済的にキャッチアップできていないために、人口も西側に流出してしまうというダブルパンチを食らう。
ブルガリアが例として取り上げられているが、ブルガリアは戦後にトルコ系住民を追い出してしまったのが痛い。。。
より一般的には、女性の教育水準の上昇と、伝統的な家族観が同居している国がやばいらしい。こういう国では、女性は働くか家庭に入るかの二者択一を迫られる。そうして多くの女性が出産せずに働くことを選びがちである。また、これらの国々では婚外子が極めて少ないことも不利に働く。
東アジアがやばいのは、西洋の先進国と違って、教育水準の向上が急速におこったために、出生率低下も急激だったこと。だから日本はオーバーキルといってよいくらいに出生率が一気に低下した。韓国はさらに短期間に教育の浸透と経済成長がおこったので、いっそう激しく出生率が低下した。
韓国は教育水準が上がったのはいいが、若者たちは勉強しなきゃというプレッシャーを受けるようになった。その結果、OECD加盟国のなかで最も10代の自殺率が高い。
また日本は先進国で最も幸福度が低い。
だが人口が高齢化すると暴動や革命がおこりにくくなる。バスクや北アイルランドの暴力的な分離主義運動が沈静化した要因であろうと、筆者は指摘している。
治安が良くなるという意味ではけっこうなことだが、若者にとって幸福でない社会が持続するということなので、残念だなあと東アジアのおっさんである私は思うのであった。
サブサハラ以外でまともな出生率を維持しているのはイスラエルだけである。
山森みかさんの『乳と蜜の流れる地から』を読めばその理由がよくわかるし、真似できないなとも思う。
早い話が、イスラエルは国をあげてアーミッシュをやっているのである。
アーミッシュとてアメリカ合衆国の一部なので、長期的には出生率もそちらに引っ張られると思われるが、イスラエルは周りに敵対的な国を抱えていることもあってかそうはならないようだ。
そういうわけなので、我が国は出産が増えるということは期待できないし、増えないという前提で社会を作り変えていかないといけないが、どうも皆さん危機感が薄いようで、、、
低出生率で世界のトップを走る韓国、出生率は韓国よりましだが高齢化率がやべえ本邦がリーディングケースであるのは間違いなく、これからも注視していかなくてはいけないと思ったのである。
いいなと思ったら応援しよう!