
【本棚のある生活+α】2024年3月に読んで面白かった本
昨年(2023年度)から、思い付きで始めた月イチペースで、面白かった本と見応えがあった映画を、ご紹介してきました。
ここに、私達の、あなたの、私の「問い」があったとすれば、私達の、あなたの、私の「課題」が存在する。
「人間たちが理性の導きから生きるということは、稀にしか起こらず、むしろ彼らの多くはねたみ深く、互いに不快な存在となるようにできている。
にもかかわらず人間たちは孤独の生を貫くことはほとんどできず、その結果『人間は社会的動物である』というあの定義が多くの人々のお気に入りとなった。
そして実際に、人間の共同社会からは、害に比べれば、はるかに多く利便が生じるようになっているのである。
だから人の世を風刺家は好きなだけ笑いものにし、神学者は好きなだけ忌み嫌うがよい。
また憂鬱家は未開で野蛮な生を力いっぱい賞賛し、人間を軽蔑して獣に感嘆するがよい。
それでもなお彼らは経験によって思い知るであろう。
人間たちは助け合うことではるかに容易に必要なものを手に入れることができ、また結合された力によらなければ、いたるところに迫る危険を避けることはできないということを。
獣の所業により人間の所業を観想するほうがはるかに価値があり、われわれの認識にふさわしいことはいまは言わないにしてもである。」(スピノザ『エチカ』より)
そして、「理性」に立ち返ることになるのですが。
【参考図書①】
「The Power of Fun How to Feel Alive Again」(English Edition)Catherine Price(著)

【参考記事①】
その理性とか、通念とか、常識とか。
そんな鎧のようなものを着て、歩き疲れていないか。
重い鎧が、肩にのしかかって、毎日、ため息ばかり、ついてはいないか。
人が生きるために必要なもの。
それは、酸素と水と栄養と、自分ではない大切な誰か。
そして、美しいものを、美しいと感じる心。
それで、充分なのではないだろうか。
鎧を脱ごう。
身体と、心を、軽くしよう。
こびりついた理性の錆を洗い落とそう。
気持ちの命ずるままに。
幼児のように素直に。
まっすぐに生きよう。
本能というものの大切さを取り戻すために。
時には、好きな事に没頭してみよう。
自分を解放するという密やかな戦いは、思いのほか、身近にあるものなのでしょうね。
ということで、2024年3月に読めた本の中から、特に面白かった本(1冊)のご紹介です。
【特に面白かった本】
「知ってるつもり 無知の科学」(ハヤカワ文庫NF)スティーブン スローマン/フィリップ ファーンバック(著)土方奈美(訳)

私たちは、自分たちが思っているほど、物事を理解していない。
このことを示す簡単な実験がある。
トイレやファスナーなど、日々当たり前のように使っているモノについて、まず被験者に、
「その仕組みをどれだけ理解しているか」
を答えさせる。
この時点での回答は、
「理解している」
というものが多い。
だが具体的にどのような仕組みで動くのか説明を求めると、たいていの人は、ほとんど何も語れない。
知っていると思っているのに、実は、それほど知らないのだ。
とはいえ、無知、そのものが欠点というわけではない。
あまりにも複雑な世界を生きていくため、私たちは、こうした戦略・作法を身につけざるをえなかった。
しかし、問題は、私たちは、世界を理解したつもりで生きており、それが、ときとして、さまざまな錯誤や災厄をもたらすということだ。
私たちは、基本的に、「わかっていないことがわかっていない」。
これが無知の正体である。
■「無知」は、歓迎すべきものではないが、かならずしも悲嘆すべきものでもない。世界は、あまりにも複雑で、その全体像は、個人の理解を超える。無知は、人間にとって自然な状態だ。
■それにもかかわらず、私たちは、多くのことを知っている、理解しているという「知識の錯覚」に陥っている。
■知性は、個人に属していると思われているが、じつのところ、人は、「知識のコミュニティ」のなかに生きている。
「The Knowledge Illusion Why We Never Think Alone」(English Edition)Steven Sloman(著)

「Knowledge illusion(知識の錯覚)」とは、自分の知識を過大評価しまう傾向のことだ。
2人の認知科学者による本書は、人間の心のなかで、「Knowledge illusion(知識の錯覚)」が生じる理由、それが、引き起こす問題、それを踏まえてどうすべきかを論じた一冊となっている。
どうして、私たちは、実際以上に知っていると思ってしまうのか。
本書では、前半の各章でいくつかの理由が示される。
私たちは、無自覚に、直観的な推論(intuitive reasoning)に、頼ってしまうため(4章)
私たちは、無自覚に、身体知に頼っているため(5章)
私たちは、無自覚に、他人の知識(communal knowledge)に頼っているため(6章)
私たちは、無自覚に、テクノロジーに頼っているため(7章)
中盤では、「知識の錯覚」が問題になる2つの局面について論じている。
「知識の錯覚」は、科学的知識の普及を妨害する(8章)
「知識の錯覚」は、合理的な政治的判断を妨害する(9章)
後者の政治についての章では、"illusion of explanatory depth"を政治的イシューに応用した著者自身の研究を紹介している。
それによると、人々は自分が、
「ある政策の効果を説明できない」
と気づくことで、よりマイルドな政治的立場をとるようになることがわかったらしい。
これは、昨今の政治的分断を解消するためのヒントにもなりうる結果かもしれない。
最後の2つの章では、こうした「知識の錯覚」があることを前提として、どうしていくべきかについての著者らの考えが述べられており、個人の知識を増やすばかりの教育はいい加減やめて、人と協力する能力を育むべきではないか、という主張には頷けた。
私たちが、
「知識」
と言っているもののうち、自分一人の「脳」のなかにあるのは、たかが知れていて、その外側の
「身体」
「他人」
「社会」
「技術」
に多くを負っている。
思ってみれば、当たり前のことだが、忘れがちなこのことを、「認知科学」(認知科学は「人間の知性の働きはどうなっているのか」、「その目的は何なのか」を解明しようとする学問)の視点で整理してリマインドしてくれる一冊だった。
人間の知性は、新たな状況下での意思決定に、もっとも役立つ情報の抽出を、最優先に進化してきた。
人間の脳は、しばしばコンピュータのように例えられるが、実際は、大量の情報を保持する記憶装置とも、その大量の情報を演算処理するように設計されたコンピュータとも、根本的に異なっている。
そもそも私たちは、なぜ思考するのか。
その目的は、
「行動」
にある。
この目的を達成するために必要なことを、より的確にできるようになるため、脳は、進化してきた。
そして、私たちにとっての最適な行動とは、複雑な世界の変化する状況に、もっともうまく適合することなのである。
【参考記事②】
【参考図書②】
「Languishing How to Feel Alive Again in a World That Wears Us Down」(English Edition)Corey Keyes(著)

【二言三言】
思考に、枠を、はめてない?
「常識とは、18歳までに身に付けた偏見のコレクションである」
ご存知の方も多いかと思いますが、これは、物理学者、アルベルト・アインシュタインの有名な名言です。
日々さまざまな偏見に基づいて行動してしまいますが、きっと私だけではないはず(^^;
これらは、確証バイアスの影響なのかもしれません。
認知バイアスとは、自分の思い込みや周囲の環境などによって無意識のうちに合理的ではない判断をしてしまう心理現象のこと。
思い込みを持っていると、ほかにどのような情報があっても最初の考えを支持する情報ばかりが目に付きます。これが「認知バイアス」で、確証バイアスは「認知バイアス」の一種です。
この誰もが陥る確証バイアスを避けるためには、どうすれば良いのでしょうか?
答えは簡単で、油断は禁物で、常に、反証することを心がけてみてください。
【参考記事③】
【参考図書③】
「超絵解本 だれもがもつ“考え方のくせ” バイアスの心理学」池田まさみ(監修)

「Newton 2024年3月号(特集)心にひそむ考え方のクセを徹底紹介!バイアス大図鑑」

「Newton 2023年2月号(特集)バイアスの心理学:先入観・偏見・思い込み―「認知バイアス」を徹底特集」
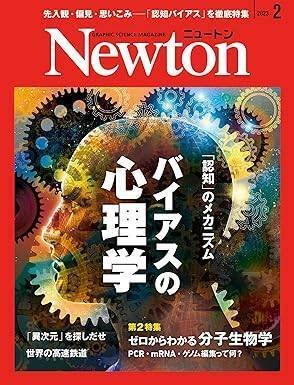
「バイアスの心理学 (Newton別冊)」

「イラストでサクッとわかる!認知バイアス――誰もが陥る思考の落とし穴80」池田まさみ/森津太子/高比良美詠子/宮本康司(著)

【補足情報】
「運命というならまだしも、宿命というのは実に嫌な言葉だねぇ。
二重の意味で人間を侮辱している。
一つには、状況を分析する思考を停止させ、もう一つには、人間の自由意志を価値の低いものとみなしてしまう」(出典:アニメ「銀河英雄伝説・本伝」シーズン3エピソード24第78話「春の嵐」より)
これは、「銀河英雄伝説」というSF小説の金字塔で、主人公の1人であるヤン・ウェンリーが発した言葉だ。
よく「銀英伝・名言集」としてネットにまとめられているが、このセリフには続きがある。
「宿命の対決なんて無いんだよ、ユリアン。
どんな状況の中にあっても、結局は当人が選択したことだ」
「すみません…」
「いやぁ、これは、私自身に戒めて言っていることさ。
宿命なんていう便利な言葉があるとつい、自分の選択をそのせいにして正当化したくなる。
私はべつに、いつも自分が正しいなんて思っちゃいないよ。
が、同じ間違えるにしても、自分の責任で間違えたいのさ」
ヤンのセリフに対して、私なりの解釈を加えてみると、宿命とは、
「状況を分析する思考を停止させる」
と同時に、
「状況にあらがわず諦める」
ことを肯定するための方便なのかもしれませんね。
自分の思い通りにならない状況を、いつも、何かのせいにしてしまわないように注意しないと(^^;
「私が〇〇を苦手なのは、〇〇が関係しているせい」
「何をしても上手くいかないのは、〇〇だから」
「結局、いつもこういう結果になってしまうのは、宿命なのよ」
そうやって、便利な言葉で、理由をつけて、
「まずは、現実を直視し、現状を受け入れる。
その上で、現実的な解決策を考えて、自ら行動を起こす」
ことを拒否している点に注意が必要ですね。
【リストアップした書籍】
「アダルトメディア年鑑2024 AIと規制に揺れる性の大変動レポート」安田理央/稀見理都(編)

「ノモレ」(新潮文庫)国分拓(著)

「知ってるつもり 無知の科学」(ハヤカワ文庫NF)スティーブン スローマン/フィリップ ファーンバック(著)土方奈美(訳)

「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」新井紀子(著)

「Science Fictions あなたが知らない科学の真実」スチュアート・リッチー(著)矢羽野薫(訳)
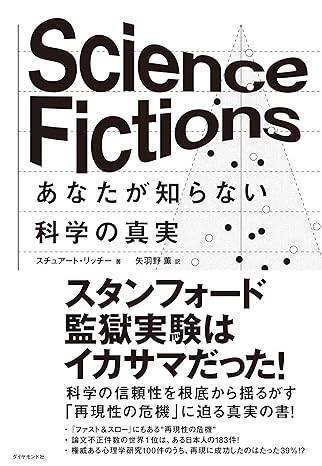
「WEIRD(ウィアード)「現代人」の奇妙な心理 上 経済的繁栄、民主制、個人主義の起源」ジョセフ・ヘンリック(著)今西康子(訳)

「WEIRD(ウィアード)「現代人」の奇妙な心理 下 経済的繁栄、民主制、個人主義の起源」ジョセフ・ヘンリック(著)今西康子(訳)

「チーズはどこへ消えた?」(扶桑社BOOKS)スペンサー・ジョンソン(著)門田美鈴(訳)

「イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」」安宅和人(著)

「WRAPを始める!―精神科看護師とのWRAP入門【リカバリーのキーコンセプトと元気に役立つ道具箱編】」増川ねてる/藤田茂治(編著)

「WRAPを始める!―精神科看護師とのWRAP入門【WRAP(元気回復行動プラン)編】」増川ねてる/藤田茂治(編著)

「上を向いてアルコール」小田嶋隆(著)

「安楽死が合法の国で起こっていること」(ちくま新書)児玉真美(著)

「東京都同情塔」九段理江(著)

「「自信がない」という価値」トマス・チャモロ-プリミュージク(著)桜田直美(訳)

「お尻の文化誌 人種、ファッション、科学、フィットネス、大衆文化」ヘザー・ラドケ(著)甲斐理恵子(訳)

【関連記事】
多読・濫読・雑読・精読・積読それとも?
https://note.com/bax36410/n/n17c08f767e73
【本棚のある生活+α】2023年1月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n076e2800381c
【本棚のある生活+α】2023年2月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n1e809f8ad981
【本棚のある生活+α】2023年3月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n5b9792df1aa9
【本棚のある生活+α】2023年4月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n1255ac2dcf12
【本棚のある生活+α】2023年5月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n72c887bf894a
【本棚のある生活+α】2023年6月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n81559c79dd80
【本棚のある生活+α】2023年7月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n0d1664588d07
【本棚のある生活+α】2023年8月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/nefb833a75642
【本棚のある生活+α】2023年9月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/nf3d7ecad89cc
【本棚のある生活+α】2023年10月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/nea4c59c8cadc
【本棚のある生活+α】2023年11月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/ndb4b28943a59
【本棚のある生活+α】2023年12月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n3b772659b3e0
【本棚のある生活+α】2024年1月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/n8250c4e76ef5
【本棚のある生活+α】2024年2月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/ndeba14335317
【本棚のある生活+α】2024年4月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/nee95d5081b8d
【本棚のある生活+α】2024年5月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/nb80b9e7d00b9
【本棚のある生活+α】2024年6月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/ne33ba3a3594e
【本棚のある生活+α】2024年7月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/nb56da32d79f9
