
【四季を彩る日本酒の嗜み方】日本酒にも「旬」があり、ものごとにも旬がある。

日本酒には、
「旬」
があるそうです。
そう聞いて、みなさんは、どんな季節を思い浮かべますか?
お米から作られる日本酒は、農業の延長と考えてみると、その年、お米の生育状況、つまり、同じ田んぼで同じ品種を作っても、毎年変わる夏の気候で、お米の出来が変わってしまう。
毎年、季節ごとに、味わいが異なっているため、そこに酒造りの真髄があるそうです。
自然の恵みを生かす、日本人の英知が結集しているためか、ちょっと、敷居が高いイメージがある日本酒ですが(^^;
例えば、こんな感じで、日本の四季に応じた楽しみ方を知ることで、一気に、身近な存在になるはず。
【春】フレッシュな生酒を春野菜と
【夏】「あえて常温」が新定番!?
【秋】熟成を終えた「秋上がり」を楽しむ
【冬】やっぱりお燗が身体においしい
梅雨時期だと、こんな日本酒が、合いそうですね(^^♪
そう、どんなことにも、手がけたり、取り組んだりするのに、ふさわしいタイミングが存在します。
例えば、自分自身が、
「面白そう!」
「やってみたい!」
と思ったこと。
「やりたい!」
と思ったそのときが、旬です(^^♪
まさに、
「鉄は熱いうちに打て」
で、旬を逃さずに、始めるしかありません。
「する/しない」」
「できる/できない」
「向いている/向いていない」
とか、考えるのも、ムダかなって、そう思います。
その旬の時間が、最高の始めどきです。
もし、旬を逃したら、
「時間もないしお金もかかるな」
という現実的な判断が働いて、せっかく、
「やりたい」
と思ったことも手をつけずに終わってしまいます(^^;
あるいは、お願いことをされたとき。
相手が誰であれ、
「これをやってくれませんか?」
と言われたら、その瞬間が、「旬」です。
さて、今週は、そんな「旬」な出来事が重なって、新潟県に出張に行っていたんです。
日本酒の生産量が、日本でもトップクラスの新潟。
新潟の日本酒が美味しい理由は、米作りに適した土壌と、澄んだ軟水があるから。
そして、移動日に、時間的な余裕が有ったので、思い切って、お店を探して、普段、飲むことのできない地酒を楽しんできたので、銘柄を紹介しておきますね(^^♪
【新潟の日本酒】
■越後高柳 純米さわがに 目覚め

■サビ猫ロック 銀サビ PHASE2 純米大吟醸

■鶴齢 純米吟醸

■緑川 雪洞貯蔵 純米吟醸

四季の移ろいとともに変わるその楽しみ方に、少し興味がわきましたか?(^^)
【お酒の歌】
「言葉にすれば虚辞となるゆえ風呂敷に包み提(さ)げゆく新酒一本」
(久々湊盈子『世界黄昏(せかいこうこん)』より)

「静かなる自嘲湧きたるこの夕べ酒一合のはや胃に沁みぬ」
(吉田直久『縄文の歌人』より)

「夏きざすやうに勇気はきざすのか飲酒ののちの蕎麦のつめたさ」
(大口玲子『東北』より)

「思うことなきときに酌みありて酌む遠き肥前の「六十餘州」」
(三枝昻之『それぞれの桜』より)

「酔ひにたりわれゑひにたり真心もこもれる酒にわれ酔ひにたり」
(佐佐木信綱『思草』より)
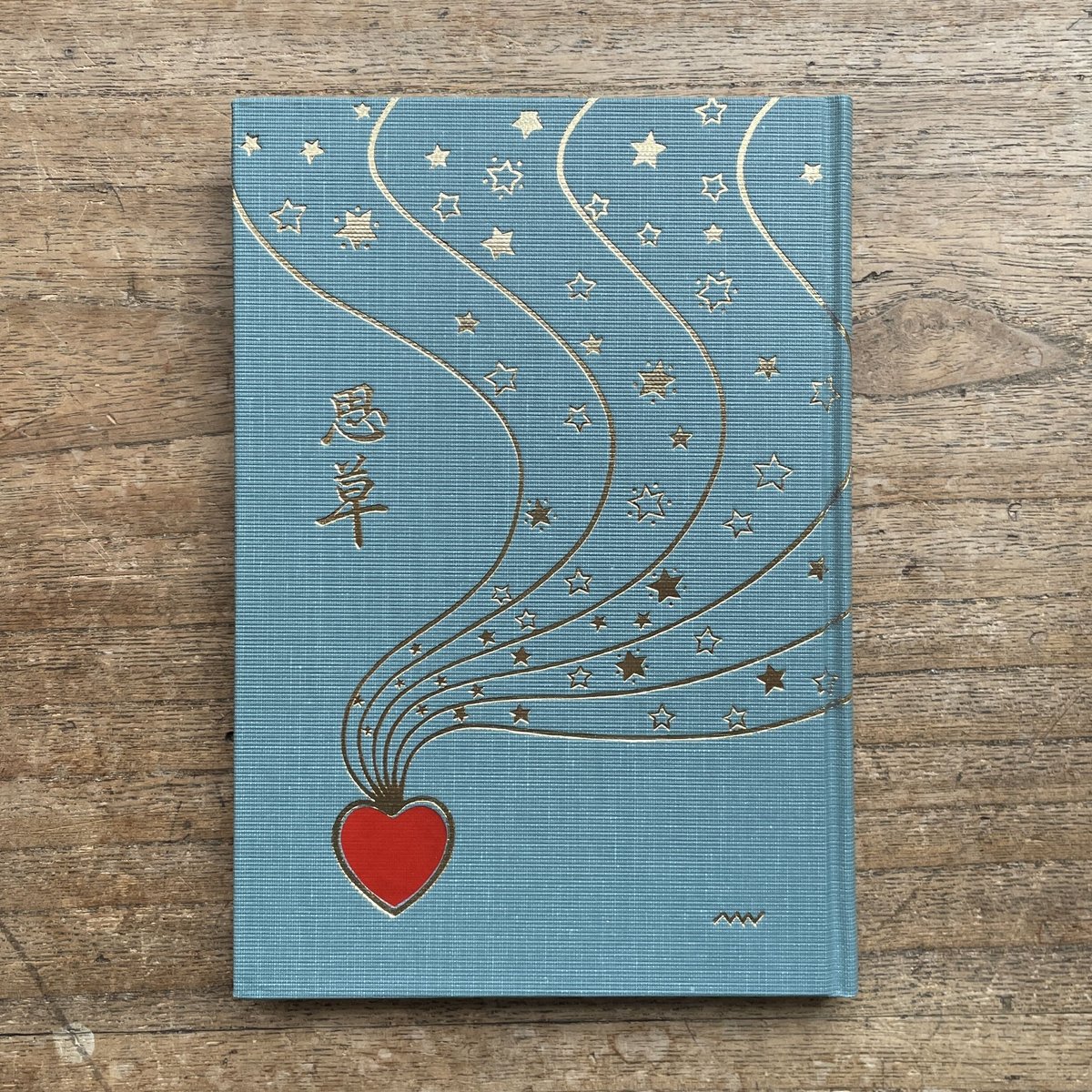
「山居にて一人遊びす股旅酒、山椒の擂りこ木、元の証拠干し」
(王紅花「夏暦かれき」54号より)
「君と君抱きあひたまへ酒杯(しゆはい)置き月の光に射(い)ぬかれながら」
(伊藤一彦『月の雫』より)

【モニュメント】
田中等/ムーン ダンス(Moon Dance)

【おまけ】
