
【宿題帳(自習用)】「「わかる」とはどういうことか」をやり直してみる(その1)

[テキスト]
「「わかる」とはどういうことか―認識の脳科学」(ちくま新書)山鳥重(著)

[参考図書]
「ものがわかるということ」養老孟司(著)

[ことばの疑問]
[ 内容 ]
われわれは、どんなときに「あ、わかった」「わけがわからない」「腑に落ちた!」などと感じるのだろうか。
また「わかった」途端に快感が生じたりする。
そのとき、脳ではなにが起こっているのか―脳の高次機能障害の臨床医である著者が、自身の経験(心像・知識・記憶)を総動員して、ヒトの認識のメカニズムを、きわめて平明に解き明かす刺激的な試み。
[ 目次 ]
第1章 「わかる」ための素材
第2章 「わかる」ための手がかり―記号
第3章 「わかる」ための土台―記憶
第4章 「わかる」にもいろいろある
第5章 どんな時に「わかった」と思うのか
第6章 「わかる」ためにはなにが必要か
終章 より大きく深く「わかる」ために
[ 発見(気づき) ]
機能障害の専門家であり、臨床医でもある著者が、「わかる」という心の動きについて、認知科学の側面から論じた本。
高校生くらいが対象であろうか。
とても平易に書かれているが、扱っている内容は面白い。
「分かる」とは、感情の動きであって、この原因となる心の動きが、「考える」ということ。
しかも、この心の動きにとって、重要なのは、客観的事実ではなく、「心像」(主観的現象)である、という著者の論には、大きく共感できます。
また、この「分かる」「考える」といった現象は、進化論的観点から見ると、(「分かった」とは、行為に移せる、という点で)知覚-運動過程の中間に挿入されたチェック機構であるとも考えることができます。
この心理表象は、一見知覚に近い現象に見えるけれども、実は、知覚-運動変換を省略したものだから、運動要因が含まれています。
つまり、いつでも、運動に繋がる仕組みになっています。
だから、心理表象とは、身体的運動が省略された運動と考えられ、運動の進化した状態とみることができる、という論は、興味深いものがあります。
「意味とは、とりもなおさず、わからないものをわかるようにする働きです。
・・・・・ 心は多様な心像から、意味というより高い秩序(別の水準の心像)を形成するために絶えず活動しているのです。
ですから、意味が分からないと、分かりたいと思うのは心の根本的な傾向です。
生きるということ自体が情報収集なのです。それが意識化された水準にまで高められたのが心理現象です。
意識は情報収集のための装置です。情報収集とは、結局のところ秩序を生み出すための働きです。」
「ある高名な日本画家が絵の極意は対象をひたすら見ることだ、と述べていました。
・・・・・ ひたすら見ることで対象がだんだん「見えてくる」というのです。
よく見えれば、よく描ける、と言っています。これを少し言い換えますと、しっかりした心像が形成できれば(表象できれば)、それはそのまま運動に変換出来るということです。
人間の心はそういう仕掛けになっているのです。
・・・・・ 表現は心にあるイメージをなぞることです。イメージが無ければなぞりようがありません。」
「知能とは、常に変化し続ける状況に合わせ、その時にもっとも適切な行動を選び取る能力だといえます。」
また、わかる・わからないという表現は、考えるからこそ、出てくる言葉である。
全てわかっていれば、考えることはありません。
わかるという表現すら必要ないでしょう。
わからないことがあるからこそ、わかったという事態も発生するのです。
わからないことがわかったと思えるようになるのは、考えたからです。
考えなければ、わからないままです。
心像、心に思い浮かべられる全ての現象。
人の心は、心像しか扱えない。
知覚心像と記憶心像。
心は、いつも心像に満たされている。
言葉(名前)は、記憶心像に貼り付けられた音声記号。
使われる必要のないことばは、生まれない。
「わかる」は、言葉の記憶から始まる。
言葉の記憶は、名前の記憶ではなく、意味の記憶。
「わかったこと」は、応用できる。
「わかったこと」は、行為に移せる。
「わかる」とはどういうことなのか?
”見当をつけられてわかる”
”分類できてわかる”
”説明できてわかる”
”空間関係がわかる”
”からくり(仕組み)がわかる”等、色んな「わかる」の形がありますが、結局は、自分のものにできたという感覚であり、秩序を生む心の働きであると。
自分のものにできた、整理できたという「すっきり感」が「わかる」ということだといえます。
「わからない」という状態があればこそ、「わかる」という状態があり、「わかる」ことが増えることで、知識の網の目がだんだんと細かくなり、この網の目が、また、わかることと、わからないことを区別してという繰り返しなわけです。
それから、言葉は、
”記憶心像に貼り付けられた音声記号”
という説明があったのですが、言葉が、どんどん増えだすと、本来心像を表しているはずの
”言葉”
が、心像を伴わない(もしくは曖昧)という事態が起こって、心の整理に役立つはずの
”言葉”
が、心を混乱させる原因となってしまうと書かれていて、なるほどと感じました。
[ 問題提起 ]
個人でも企業でも、コミュニケーションにおいて「わかる」ということが、すべての基本にある価値ではないかと思う。
「わからない」ものは面白くないし、使うことができない。
学校教育は、学年を追うごとに学問の内容が高度で複雑になっていく。
前の学年で「わかる」ことを部品にして、難しいことを構成していく。
このやり方にも一理ある。
やさしいことを組み合わせて、難しいことを語っていく。
しかし、この「わかる」ことの積み木方式では、常に、わからないことがある。
小学生は、中学生の内容がわからない。
高校生は、大学生の内容がわからない。
そして、大学生は、社会人の内容がわからない。
社会人は、今度は、専門家の内容がわからない。
中学生の頃、理科の教師が言った言葉がずっと記憶に残っている。
「君たちは大人になったら答えのない問題とぶつかるようになる。そういう問題を解けることが大切だよ」
正解のある練習問題と試験の毎日に、私もはやく大人になって、そういう問題と取り組みたいものだと思っていた。
大人になったら、本当に、答えのない問題ばかりだった。
学校教育的には、「わからない」ことだらけだが、「わかる」には、他のパターンが、たくさんあるのだと漠然と知ったが、どういうパターンなのか、幾つあるのか、モヤモヤしていた。
この本は、脳を専門とする医学博士が、わかることの意味を解説する本である。
私のモヤモヤに、ある視点における答えを与えてくれて、その方向性で、わかった気がした本。
まず、理解の前提となる認知や記憶のメカニズムも詳しく語られる。
実は、この部分が、最もデータも多くて、参考になる部分と感じた。
そして、この知識の上に、わかることの説明が構築されていく。
この本は、「わかる」には、幾つかの種類があるとして、次のように分類している。
・全体像が「わかる」
・整理すると「わかる」
・筋が通ると「わかる」
・空間関係が「わかる」
・仕組みが「わかる」
・規則に合えば「わかる」
著者は、脳が専門なので、上記の分類は恣意的ではなく、脳の機能にもとづいた分類に近いようだ。
例えば、大脳に障害が起きた人の中には、線で書いた立方体が平面的にしか見えず、描くことができないケースのあること等、脳の機能不全によって特定の理解が困難になる例が挙げられている。
このリストは、情報システムの設計や、データの可視化、わかりやすい文書の作成など、今の自分の仕事に使えそうだと思った。
著者が本当に伝えたかったのは、最終章の
「より深く大きくわかるために」
だろうと思う。
「わかる」にも水準があるというテーマで、著者の自論が展開される。
大局を理解したり、深く物事を知ったり、悟ったりという話。
・大きな意味と小さな意味
・浅い理解と深い理解
・重ね合わせ的理解と発見的理解
この本は、ノウハウ本ではないので、わかりやすくするにはどうしたらよいかという話はあまりでてこない。
タイトルどおり、わかるの意味が知りたい人に、専門家が、一般向けに書いた入門書。
[ 教訓 ]
例えば、「ネッカーの立方体」という図がある。
立体図というものを見知って、(箱などを体験的に見たりしたことがある)人には、立体に見える。
箱などを、縦に見たり、横に見たり、斜め下からみたり、斜め上から見たり、色々、見知っている人には、この立体図が上から見えたり、下から見えたり、動く。
その以前の“見知り”がないと、立体に見えないのである。
十分な“見知り”がある人には、違う角度からの立体も見える。
本来、2次元に表された12本の直線にすぎないのだから、立体という物を知らない人には、ただの重なり合った12本の線にしか見えない。
以前、心の中に、見知った箱型や立方体を、
「記憶心像」
といい、今・現在、ここで見ているネッカーの立方体を、
「知覚心像」
という。
ちょっと複雑なのは、
「知覚心像」
にしても、外界が、そのまま鏡に映されるように知覚されるわけではなく、
「いったん五感に分解して脳に取り込み、神経系で処理できる部分だけを組み立てなお」
すという。
線分でさえ、細かく千切られた線分として取り込み、組み立てなおすということを、猫の知覚実験で証明した脳研究事例を、他の書で読んだことがある。
「組み立てなおされたもののうち、意識化されるものが知覚心像」であるという。
1)物事がわかるためには、予め、いろいろな体験や知識吸収が行なわれて、記憶として脳内部に「心像」が形成されていなければならない。
2)「記憶心像」が増えれば増えるほどわかる割合が高くなるのだから、今現在自分の周りに起こっていることの取り込み「知覚心像」形成も、繰り返し絶えず行なわれる必要がある。
3)「記憶心像」形成にしても、「知覚心像」形成にしても、直接のものごとだけの「心像」だと入力されてもどんどん流れ去り、消えていく。
その時に人間は、音声記号で「記憶心像」に名前を貼り付ける「ことば」を創造し発明し(創発)、不安定だった「記憶心像」を安定させた。
4)「ことば」は、「記憶心像」と「知覚心像」をつなぐ重要な道具となった。
以上が、本書から私なりに掴んだ「分かる」仕組みである。
「わかる」にもいろいろレベルがある。
1.全体像が“わかる”
2.整理すると“わかる”
3.筋が通ると“わかる”
4.空間関係が“わかる”
5.仕組みが“わかる”
6.規則に合えば“わかる”
など。
幾重にも、応用問題的で大変ではあるが、誰かに、何かを身につけさせたい立場にある指導者や教育者必見の書である。
ここで、確率・統計は、人間の情報にどこまで迫れるか?
情報は、組み合わせのパタンに宿ります。
1斤のリネンと、それから作ったジャケットが燃やせば、同じ熱を出すのに、ジャケットは、ただの布よりも役に立ち、高い値段で取引されるように、ホワイトノイズと音楽は、エネルギー的には、同等でも、良い音楽には、高い値段がつくのである。
情報は、いたるところで生まれ、いたるところにあり、いたるところに移動し、いたるところで消費されて、次の情報を生み出します。
情報の学とは、この世界における情報の誕生、生産、加工、流通、消費のあり方を解明するとともに、それを支援し、高度化するものであると思う。
高度化の方向には、量的拡大と質的拡大がある。
情報システムが扱う情報の種類が時代とともに拡張されてきた様子を見ると、質的拡大の様子が少しわかるかもしれない。
これまでのところでは、情報の学の基盤としては、計算・アルゴリズムの学とデータの学の二つがあるように思われる。
前者は、例えば、チューリングマシンや、オートマトンに代表され、後者は、情報通信の理論や、各種のデータの確率モデルに代表される。
情報に関わる特定の現象を扱うために、この両方が使われることになる。
特に、後者においては、確率的情報観とも言うべきパラダイムが強力な基盤となってきた。
情報とは、確率変数の値の組み合わせであり、知識とは、確率変数の分布であり、ヒューリスティクスとは、確率分布の自由度の制約であり、推論とは、条件付確率の計算であり、学習とは、確率分布の推定、つまり、確率分布の母数の条件付確率の計算である、というようなものである。
この枠組みの中で、シャノンの情報量(特に相互情報量)や、フィッシャーの情報量(相互情報量の微分のような量)が活躍してきた。
音声言語情報を例にとれば、情報の保存や流通に関しては、ほぼ重要な問題は解決されているように思われる。
各種の情報圧縮法が提案され、実際に利用されている。
一方、音声認識に関しては、ニュースを読み上げるアナウンサーの音声のように、クリアでフォーマルな音声は、人間並みの認識率に達している。
これらの背景には、音声言語情報の確率統計的モデル化の進歩と、モデル学習のための大量のデータの蓄積がある。
ところで、ここまでは、よく知られたことをまとめただけであるが、この二つのパラダイムでよいのか?という疑問がある。
再び音声言語情報を例にとれば、未踏のエリアは広大である。
現在の枠組みの延長で、例えば、自由な話し言葉の認識に迫れるのであろうか?
人間の意図や感情の認識に迫れるのであろうか?
情報処理システムは、創造的な対話をするようになるのであろうか?
とりあえずできることは、地道にデータを収集し、分析し、モデル作成し、ヒューリスティクスを探求し、モデルを検証し、というようなことである。
それは、実際に、多くの優れた研究者によって精力的に行われている。
自由対話の記録、コミュニティの記録、見学行動の記録、そして、個人的にも、現時点で、これ以外の具体的なアイデアはない。
しかし、その一方で、漠然とした直観として、現在のパラダイムでは、上のような課題には、なかなか迫れないのではないか、という思いがある。
単に、地道な努力やヒューリスティクスが足りないだけなのか、それとも、新しい原理が必要なのか、あるいは、その中間なのか?
確率的情報観に基づくデータの学の立場から、人間の情報に向かって考えられる方策として、
1)現在の枠組み(確率的情報観)で地道にやる
2)新しいパラダイム・基盤を探す
3)別の方向を探す
4)原点に還る
という4つが考えられる。
こうした志向は、哲学、経済学、社会学、心理学などが、理系的に扱うことの難しい複雑系や、「こと」を扱う方法に苦しんできた過程を、繰り返しているのではないか、という気持ちもある。
また、文学の中でも形式の異なる韻文と散文を組み合わせ、短歌と散文に統一感がある本書を読みながら、
「神様の住所」九螺ささら(著)

「ゆめのほとり鳥」(新鋭短歌シリーズ)九螺ささら(著)

[自選5首]
「ハープとはゆめのほとり鳥の化身です」余命二ヶ月の館長は言う
《非常口》の緑のヒトは清潔なきっとわたしの運命の人
舫(もや)われた二艘の舟として生きるきみの存在がわたしの浮力
ドアスコープの魚眼レンズを覗いたら一滴(ひとしずく)のこの世が見えた
春を練りシナモンロールに焼き上げる仕方ないことを仕方なく思う
「きえもの」九螺ささら(著)

「漢数字の一を茹でるとひらがなのしになる人の初めから終わり」九螺ささら
「文学と科学の相関性」について、本書や資料等にも目を通してみると、
「文学の中の科学的要素」寺田寅彦(著)
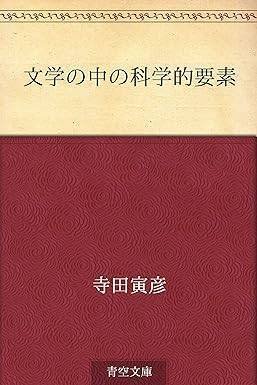
「文学のなかの科学―なぜ飛行機は「僕」の頭の上を通ったのか」千葉俊二(著)

これは、やはり、見果てぬ夢等ではないのだと感じられてくるし、
「ゆっくりとわかるのだろうほっとかれそのままでいるプラスティックを」
(柳谷あゆみ『ダマスカスへ行く 前・後・途中』より)

「ちゃんと歩いてここまで来たってわかるから靴は汚れているほうがいい」
(上澄眠『苺の心臓』より)

「遠目には宇宙のようで紫陽花は死後の僕たちにもわかる花」
(笹川諒『水の聖歌隊』より)

九螺ささらさんの座右の銘が、
「できるようになる唯一の方法は始めること」
を知り、正に、物事は、始めてみる事が肝要だなと思った次第である。
逆に、例えば、ベイトソンが、おそらく考えていたように、情報の学は、それらすべてに共通の基盤を与えるものかもしれない。
[ 結論 ]
ところで、「情報」、特に、知的ソフトウェアの研究が、「わかりにくい」と言われてしまうのは何故であろう。
目に見えないからだ、というのは、大きな理由の一つではあるが、他にも見えないものはたくさんある。
単に、物理的に見えない、というだけではなくて、個別の「もの」や、部分的な過程として切り出しにくいということも、大きいのではないかと思った。
無理に切り出してしまうと、嘘っぽくなってしまう。
「実践」するにしても、なんとなくはわかるものの、「実際に本当にやらないとわからない」わけである。
しかし、「こと」としての情報は、いたるところに生まれ、私たちは、呼吸をするように、あるいは、食べ物を食べるように、日々情報処理をしながら生きている。
つまり、私たちすべては、「こと」としての情報を、日々実践しているはずである。
だから、本当は、そんなにわからないはずはないのであるが、逆に、あまりにもあたりまえに、無意識に行っているがために、改めて研究すると言われても、何が問題で、どこが難しいのかわからない、という理由もある。
つまり、普段、何気なくやっていることを、高度な情報処理過程として眺めることを体得している人が少ない、ということかもしれない。
食事や栄養については、料理番組、グルメ番組、ダイエット番組、等々、これでもかというほどの情報があふれている。
「野菜をもっと取らないと」と誰もが言いう。
「人工甘味料や人工調味料は体に・・・」という話が、ごく普通の会話でなされいる。
人間にとって、食事・栄養素とは何であるのかが完全に解明されているわけではないが、そのごく基本的な部分は、小学校からしっかりと教えられ(給食だより)、更新されて、われわれの「常識」の一部となっているのも事実である。
情報についても、「この情報は古い、腐っている」、「このもうけ話は信用できない」、「漫画ばかり読んでいると・・・」といった会話はごく普通に行われている。
情報処理がわかりにくい、という人が多いのは、それらが「情報の問題」であることが明確に認知されていないためのようにも思う。
人間の情報処理について、最も巷にあふれている情報は、恋愛のハウツーかもしれない。
それが無いために、「情報=コンピュータ=難しい」、「ソフトウェア=プログラム=よくわからない」という反応図式が、一人歩きしている感じがする。
上のような会話や、ハウツーから、さらに先に進んで、例えば、見たものが何であるかわかるとはどういうことか?
人間にとって、豊かな情報環境とは何であるのか?
良い作品を作る、良い作品に触れる、とはどういうことか?
自然の情報と人工の情報は何が違うのか?
相互理解とはどういうことか?
集団で情報を共有するとはどういうことか?
といったことを、日々感得するための基盤が、「常識」の一部となることは無いのだろうか、と思う。
さらに、「情報」は、コンピュータやネットワークと一緒に語られることが多いのであるが、コンピュータやネットワークは、人間や生物の情報処理のごく一部を拡張するための道具である。
コンピュータを「使える」ようになるためには、人間の情報処理が、どのようなことであるかを理解することが大切である。
こうしたことが、理系情報学と同時に、文系情報学、「学」なのか?はともかく、なんらかの「知識」?の集積として重要だと思う。
これまで、こうした意味での「文系情報学」は、哲学者や経済学者、社会学者、芸術家、心理学者、経営学者などによって、比較的個別的に語られ、実践されてきたのだと思う。
そうした学問分野でも、「情報」の果たす役割は、どんどん大きくなっているようである。
そうしたものが、「情報」という共通の基盤の上のことがらとして捉えられて、多くの人の「常識」になってゆくとよいと思う。
そこには、生活を便利にしたり効率的にすることと同じくらい重要なことがありそうである。
世の中の問題で、人間のコミュニケーションの過程や情報処理の過程についての「理解」の不足から起こっているものも多いのではないかと思われる。
そして、理系情報学もまた、その過程において、自身(ホーム)の高度化の方向性を見出したり、多くの新しい活躍の場(アウェイ)を見出すことになれば素晴らしいと思う。
[ コメント ]
人間のものの分かり方、それを脳神経科学の内部から明らかにしている。
山鳥氏は脳神経科の臨床医である。
記憶障害、失語症、認知障害、脳機能障害などを専門とする臨床医。
人間が「あッわかった!」と思う時、脳の中で何が起こっているか、そのメカニズムが明らかにされている。
「心像」(=心理表象)がキーワード(イメージが近い言葉であるが、視覚映像のニュアンスが強い。
心像は触覚、聴覚、臭覚、味覚も含む。)
「太陽が東から昇り、西へ沈むのは、地球が自転しているせいで、太陽が動いているせいではありません。しかし、われわれには太陽が昇り、太陽が沈むとしか見えません。」
「地球の自転は事実で、太陽が動くのは心・像・です。」
これが“アッ、わかる!”という時のキーワードの「心像」である。
人間は、外界に起こっていることを絶えず知覚し続けている。
初めて見たり聞いたりすることもあるし、前に見知っていたり、聞き知っていたりすることもある。
前に見たり聞いたりして「すでに心に溜め込まれている心像」を「記憶心像」といい、「今・現在自分のまわりに起こっていることを知覚する」心像を「知覚心像」という。
「知覚心像」と「記憶心像」が脳の内部で一致した時に、人間は「アッわかった!」となるのだそうである。
