
【短い語で十分なら】裏時間の魔法をあなたへ
1日は、24時間。
でも、自分がちょっと意識するだけで。
その時間が、もっと長くなったように、感じられたら・・・
そのヒントになるのが、
「裏時間」
です。
「待ち時間」
の裏側で、他の
「To Do」
を片付けることができたなら、
・終了時間が決まっているので集中できる
・思っていたより手早く終われるタスクが多いことに気づける
ボーッと待っているときの倍のタスクを片付けることが可能に。
そんな、
「メインタスク」
の
「裏側(待ち時間)」
で活用できる時間こそが、
「裏時間」
なんです。
■「1分以内」でできること
▶キッチン
□ お米を計量する/お米を研ぐ
□ 水切りカゴの中の食器を食器棚へ戻す
□ シンクに置きっぱなしのグラスを洗う
□ 次の食事で使う食器を出しておく
□ シンクの水滴を拭く
etc.
▶バスルーム
□ 洗面台の鏡を磨く
□ 水道や鏡、壁にについた水滴を拭く
□ ソープやシャンプー、洗剤などを補充する
□ 排水溝にたまったゴミを取る
etc.
▶その他
□ ベッドメイキングをささっと行う
□ グリーンに水をやる
□ 靴を揃える/靴箱に入れる
□ 脱いだままの服をハンガーにかける
□ 郵便物を開封する
□ テーブル上に散らかったものをテーブルの隅にキレイに重ねる
□ トイレの便器を拭き上げる
etc.
■「10分以内」でできること
▶キッチン
□ 献立を考える
□ 食材をカットしておく
□ 棚や冷蔵庫の1エリアを見て賞味期限が切れた食材を処分する
□ 冷蔵庫の中を一段きれいに掃除する
□ ケトルや鍋を磨く
□ コンロを拭く
etc.
▶バスルーム
□ 洗濯物を干す
□ 洗面台下の収納を整理する
□ 洗濯機の汚れの気になる部分を1か所掃除する
□ 換気栓のフィルターを洗浄/交換する
etc.
▶その他
□ 棚や引き出しを1段整理・掃除する
□ 洋服ダンスの服を1段分畳みなおす
□ 提出物を処理する
□ 家計簿をつける
□ 家の中のゴミをまとめる
□ お財布の中身を整理する
□ バッグの中身を整理する
□ スマホ内のいらない写真やメールを整理する
□ 電池を交換する
□ ボタン付けなどの繕い物をする
□ アイロンや毛玉取り器をかける
etc.
■すきま時間
すきま時間を使った自分の時間の作りかたとして、以下の点を意識して実行してみては如何でしょうか。
1.「したいこと」を前もって意識しておこう
2.すきま時間がどこにあるか探してみよう
3.まとまった時間がほしいなら…家事にメリハリを
4.自分の時間を「To Do」リストに入れる
5.移動時間を活用しよう
6.朝、ちょっと早めに起きてみよう
7.あえて何もしない時間をつくってみよう
■裏時間
裏時間に気づき始めると、
「やらなくちゃ・・・」
から
「次はコレ!」
へと、
「わずかな隙」
にやれることを、
「ゲーム感覚」
で、ついつい探し始めるため、自分が変わる喜びを、感じられるかなと、そう思います。
「やらなくちゃ」
から、
「次はこれをやろう!」
と
「能動的」
に、ワクワク動ければ、フットワークも軽くなり、作業スピードも早くなるので、効率は、どんどんアップします。
見過ごしていた
「1分」
「10分」
で、気になっていたところが、スッキリ片付いたり、外出後、帰宅した自分が少し楽になったり・・・
そう考えると、
「裏時間」
を活用することは、実は、
「未来の自分への思いやり」
とも、言えるかもしれませんね(^^)
さぁ、そこで、明日の自分に、ご褒美をあげる。
そんな気持ちで、
「裏時間」
上手に使いながら、
「充実した日」
にしていきましょう、か(^^♪
■いま「本が読めない人」が増えているのはなぜ?
本を読むことは、心を豊かにしてくれる、ひとつのアイテムです。
慌ただしい毎日のリフレッシュにもなると思っています。
ただ、ビジネスパーソンには、そんな時間がない。
「本が読めない」
「内容が入ってこない」
そんな状態のとき。
以下に、一度試してみてほしいことを、紹介しておきますね。
①まずはゆっくり休む
「消費と労働の文化社会学 やりがい搾取以降の「批判」を考える」永田大輔/松永伸太朗/中村香住(編著)

労働者の実存は、教養ではなく労働によって埋め合わされるようになってしまった。
それ以前には、学歴のない人々が本を読んだりカルチャーセンターに通ったりして
「教養」
を高めることで自分の階級を上げようとする動きも確かに存在していた。
だが、
「新自由主義改革」
のもとではじまった教育において、私たちは、教養ではなく
「労働」
によって、自己実現を図るべきだ、という思想を、与えられてしまったのだ。
本は読めなくても、インターネットはできるのはなぜか?

また、2000年代は、
「IT革命」
が起こった時代だ。
インターネットによって生まれた
「情報」
の台頭と入れ替わるように
「読書」
時間は減少し、
「読書離れ」
が始まった。
「情報」
と
「読書」
の最も大きな差異は、
「知識のノイズ性」
である。
「読書して得る知識」
には
「ノイズ」
言い換えると、
「偶然性」
が含まれる。
実際、
「教養」
と呼ばれる
「古典的な知識」
や
「小説のようなフィクション」
には、
読者が予想していなかった展開や知識が登場する。
▶「「嘘をつく」とはどういうことか 哲学から考える」(ちくまプリマー新書)池田喬(著)

②オーディオブックを使ってみる
③本屋で興味のある本を探す
▶「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」(集英社新書)三宅香帆(著)

あなたの「文化」は、「労働」に搾取されている。
要点①現代日本では、本がじっくり読めない(=自分の人生に必要な「文化」に時間をさけない)働き方がマジョリティとなっている。
要点②インターネットなどによってすぐ得られる「情報」に対して、読書によって得られる「知識」にはノイズ(偶然性)が含まれる。余裕なく仕事にのめり込む労働者たちにとって、趣味もまた仕事のノイズとなる。
要点③「働きながら本を読める社会」をつくるために、私たちはさまざまな分野に「半身」で取り組むべきだ。
④カフェに行く
しんどい時は本の世界に逃げ込もう!
「くらくらのブックカフェ」(文学の扉)廣嶋玲子/まはら三桃/濱野 京子/工藤 純子/菅野雪虫(著)

主人公は、小学生で、蔵を改装したブックカフェが、主な舞台。
そのカフェは、普段子どもたちが足を向けないような場所にあり、主人公は、猫によって、カフェに導かれる。
カフェのマスターは、お客一人一人にふさわしい飲み物と、お菓子を出してくれる。
土蔵には本がたくさんあり、お客は好きな本を読むことができるが時間制限があり、出された飲み物がなくなったら終了。
続きを読みたくても、そこでストップせねばならない。
料金は大人500円、こども100円。
ただし、自分が持っている本を、1冊、カフェに置いていけば、お金を払わなくても良い。
以上のような設定のもと、5人の児童文学作家さんたちがそれぞれの主人公をカフェに送り出します。
それぞれの主人公と、マスターがその子どもに出した飲み物とお菓子をご紹介しましょう。
⚫︎まはら三桃さん『よつばが消えたら』
破天荒な友人と絶交したばかりの はるか。
カフェラテとよもぎカステラ。
⚫︎廣嶋玲子さん『呪いの行く末』
いじめられっ子の亜希。
ほうじ茶ラテと水まんじゅう。
⚫︎濱野京子さん『張り子のトラオ』
名前は強そうだけれど植物が大好きな優しい虎生。
キャラメルラテとスイートポテト。
⚫︎菅野雪虫さん『バッドエンドのむこうに』
古本屋さんで結末のない本を買ってしまった蓮。
カフェラテとくるみと黒砂糖の焼き菓子。
⚫︎工藤純子さん『もうひとつの世界へ』
好きな男子と、とても仲のいい女友達の間で板挟みの仁胡。
カフェモカとフォンダンショコラ。
⑤1ページだけ見る
一冊の本には、人を変える力がある。
「少女パレアナ」(角川文庫)エレナ・ポーター(著)村岡花子(訳)

みなしごになったパレアナは、叔母さんの家に引き取られることになる。
叔母さんに厳しく当たられ、辛い思いをするパレアナは、亡くなったお父さんとの約束に、勇気づけられていた。
それは、
「喜びの遊び」
というゲームをすることだ。
いつでもどんなときでも、喜びを見出そうとするゲームである。
やがてこのゲームは、町中に広がって、叔母さんも含めた街全体を明るく変えていく、というストーリーだ。
パレアナのように、辛いことがあっても常に喜びを見出し、ポジティブに乗り切る癖をつけていった。
それは大人になってからも変わらない。
新しい環境に飛び込むときなど、
「喜びの遊び」
を思い出して、前に進む力としているという。
誰もが、そうした本に出会えることを願って・・・、まずは、
「自由時間」
のうち、
「10分」
だけ、
「読書」
に充ててみることを、お勧めしたいと思う。
好きな場所、好きなタイミングで、一日のうちのほんの
「10分間」
だけ読書する。
それだけでも、あなたの未来は、着実に変わっていく可能性が秘められている。。
▶「明日の自分が確実に変わる 10分読書」吉田裕子(著)

要点①:
読書は時間・お金のどちらの面から見ても極めてコストパフォーマンスの良い自己投資だ。
その恩恵を受けるため、まずは1日10分の読書を取り入れてみよう。
要点②:
読書を通して、「語彙力」「客観力」「想像力」が鍛えられる。
すぐには効果を実感できずとも、じわじわと必ず効いてくるものだ。
要点③:
エモーショナルとロジカルを横軸に、フローとストックを縦軸にマトリックスを描くと、読書を4種類に分類することができる。
このマトリックスを活用して選書をし、さらなる読書の質向上を目指そう。
▶「はじめての文学講義 読む・書く・味わう」(岩波ジュニア新書)中村邦生(著)

⑥SNSやブログでアウトプットを始める
▶「大人の読解力トレーニング 一生モノの思考力を鍛える」(SB新書)福嶋隆史(著)

▶「読めば分かるは当たり前? 読解力の認知心理学」(ちくまプリマー新書)犬塚美輪(著)

▶「大人に必要な読解力が正しく身につく本」(だいわ文庫)吉田裕子(著)
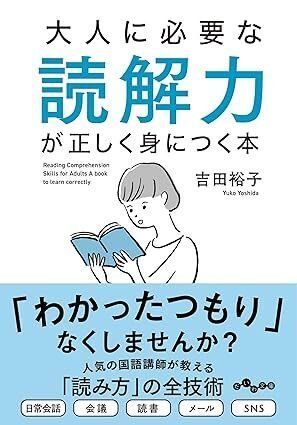
▶「わかったつもり 読解力がつかない本当の原因」(光文社新書)西林克彦(著)

▶「読解力を身につける」(岩波ジュニア新書)村上 慎一 (著)

⑦本に興味が出るまで待つ
▶「本を読めなくなった人のための読書論」若松英輔(著)

▶「読まれる覚悟」(ちくまプリマー新書)桜庭一樹(著)

