
【本棚のある生活+α】2024年12月に読んで面白かった本
昨年(2023年度)から、思い付きで始めた月イチペースで、面白かった本と見応えがあった映画を、ご紹介してきました。
さて、読書・・・
それは、ネット社会への抵抗だ!ぜ(ニヤリ)
ステップ1:「つながりすぎた世界」をどう生きるか?
読書が素晴らしいのは、情報を能動的に探すことができるから。
ウィリアム・H・ダビドウ「つながりすぎた世界」の中で、
「つながりすぎた世界」ウィリアム・H・ダビドウ(著)酒井泰介(訳)

「インターネットという名の非常に緻密に張り巡らされた情報網」
が社会に思考感染を広げ、脆弱性を生んだ結果だとしている。
結びつきの高まりは、ある程度までは繁栄を後押しするが、
あまりに急激な変化の場合、社会が制御不能になるとの分析だ。
人の弱さ(好み)に寄り添った・・・
自分だけの情報宇宙なんて必要なのか。
勝手に私の好みを判断されて・・・
受動的な情報収集になるのは嫌だ。
未知との出会いが、思い込みを一掃し、新たな発想を生むのだから。
ステップ2:世間と距離をおき視点を変える
人生の力の入れどころは、
「笑う」
と
「笑わせる」
の2つで十分だぜ(ニヤリ)
①群れない
「世間では普通と違う人間を異常と呼ぶ。私はそう呼ばれることを誇りに思っている。」(エリック・カントナ)
「世に従へば、心、ほかの塵に奪はれて惑ひやすく、人に交れば、言葉よその聞きに従ひて、さながら心にあらず。」(徒然草・第75段)
②媚びない
「一隅を照らす」(最澄)
③力まない
「色見えで 移ろふものは 世の中の 人の心の 花にぞありける」(小野小町)
人付き合いは、自分を頼ってくれる人に、誠意を尽くすだけでいい。
本当に有益な情報は、時の風化を免れた歴史から得るべきだ。
多くの人や情報と交わらず、社会との距離を、ほどほどに保つ。
ステップ3:知識分類のはじまり(16、17世紀)
「知識の社会史―知と情報はいかにして商品化したか」ピーター バーク(著)井山弘幸/城戸淳(訳)

本書の第5章「知識を分類する」から。
■知の分類に関する論争
▶1400年頃のミラノの大聖堂の建築における石工と建築家の論争
「幾何学の科学には、このような事柄に関して果たす役割がない。
なぜなら科学と技芸は別物だからである。」(石工)
「科学を欠く技芸は無価値である。」(建築家)
①科学:理論的な知識、哲学者の知識。
②技芸:実践的な知識、実践者の知識。
▶どのような種類の知識を公共のものとすべきかの論争
①公共的な知識:宗教改革・印刷出版の興隆とともに求める声が高まる
②私的な知識:特定のエリート集団に限定された知識
▶知的な好奇心はどの程度まで「虚栄心」つまり罪ではなく合法なのかの論争
①合法的な知識
②禁じられた知識:神の秘密は守られるべき(カルヴァンは好奇心を糾弾)
■学問の体系
ライムンドス・ルルス「学問の樹」(1515年)。
支配的なものと、従属的なもの区別、幹と枝の区別の方法で、文化を、あたかも自然であるように、発明を、あたかも発見であるように提示。
17世紀には、
「樹」
から
「体系」
が、知識の組織構造を記述するのに使われるようになった。
そして、体系は、
「カリキュラム」
「図書館」
「百科事典」
によって構成されていた。
▶大学のカリキュラム
15世紀のヨーロッパの大学で、最初に取る学位は文学士であった。
学生が、学士となるために学ぶのは、七つの
「自由学芸」
であり、
①言語に関わる初等の「三学科」:文法、論理学、修辞学
②数に関わる上級の「四学科」:算術、幾何学、天文学、音楽
最初の学位を取った後に、
・神学
・法学
・医学
の何れかに進むこともあったそうだ。
その後、18世紀までに、
「三学科」
よりも
「四学科」
の方が、重きが置かれるようになり、更に、
「三学科」
と
「四学科」
に代わる体系として、
「人文研究」
が現れることになった。
これは、
・文法
・修辞学
・詩学
・歴史
・倫理学で、構成されていたそうだ。
現在、主流の学問のひとつである
「経済学」
が、学問として認められるのは、18世紀半ば以降で、アダム・スミス(1723~90年)は、グラスゴー大学の道徳哲学の教授であり、彼の経済学の講義は、大学の正式な講義として認められておらず、「国富論」を出版したのも教授職を退職した後のことだったそうだ。
「国富論 上下合本版」(講談社学術文庫)アダム・スミス(著)高哲男(訳)

「国富論(上中下合本版) 国の豊かさの本質と原因についての研究」(日経ビジネス人文庫)アダム・スミス(著)山岡洋一(訳)

「超訳「国富論」 経済学の原点を2時間で理解する」大村大次郎(著)

「アダム・スミス 『道徳感情論』と『国富論』の世界」(中公新書)堂目卓生(著)

同時期のイスラム世界での学問体系は、
①異国の学問:算術と自然哲学
②イスラムの学問:コーランや予言者の言葉の研究、神学、詩学
となっており、神学を上位に置いたキリスト教世界とは異なり、イスラム世界では、宗教的知識を、世俗的な研究分野から区別していた。
▶図書館
コンラート・ゲスナーの「書誌目録」(1545年)に依れば、三千人の著者による数万冊の本を記載しており、分類の順序は、
①文法、論理学、修辞学、詩学(初等の三学科+1)
②算術、幾何学、天文学、音楽、占星術(上級の四学科+1)
③占い、魔術、地理学、歴史、機械技芸、自然哲学、形而上学、道徳哲学、経済学、哲学、政治学
④法学、医学、神学
図書カタログは、大学カリキュラムよりも、自由な体系を組んでいたようだ。
中国の書籍分類法は、乾隆帝の「四庫全書」(1782年)に見られるように、古典(経)、歴史(史)、哲学(子)、文学(集)の四分類に過ぎない。
ライプニッツ(1646~1716年)による新刊書の書評の分類は、以下の七つのカテゴリーに分類されていた。
①神学(教会史を含む)
②法学
③医学(物理学を含む)
読ん数学
⑤歴史(地理学を含む)
⑥哲学(文献学を含む)
⑦その他さまざま:書籍の管理統制の限界が見えはじめる。
▶百科事典
ギリシア語の
“encclopaedia”
は、
「学習の円環」
を意味しており、13世紀に出版されたヴァンサン・ド・ボヴェの百科事典
「鑑」
は、自然の世界、理論の世界、道徳の世界、歴史の世界を順々に扱っていた。
グレゴール・ライシュの百科事典(1501年)は、「三学科」「四学科」、自然哲学、道徳哲学の内容を要約するものであり、中国の百科事典の構成は、図書館の単純な分類法とは異なり、分類が細かく、天界の現象、地理学、皇帝、人間の本性と振舞い、政府、儀式、等々。
17世紀初頭からアルファベット順へ変更されており、知識を分類することへの断念とも捉えられる一方で、階層的な世界観から、個人主義・平等主義の世界観への転換の反映かとも思われ、
「近代初期における「書類国家」(paper states)とでも呼びうるものの興隆は、ヨーロッパの一般的な現象であった。
ルイ十四世は、回想録のなかで、「すべてについて知らされていた」と自慢した。
彼もまた長い時間を、デスクに向かって、あるいは審議会や委員会などの会議に出席して、過ごした。
啓蒙主義の指導的な支配者も同様であって、とりわけプロイセンの大フルードリヒ、ロシアの大エカテリーナ、オーストリアのマリア・テレジアとヨーゼフ二世などである。
委員会や役員会(多数決によって議決する小集団で、スウェーデンやロシアではカレッジとして知られていた)の増加は、この時代の行政上の主要な革新の一つである。
ライプニッツがピョートル一世に書き送ったように、「役員会なしには、よい行政はありえない。
役員会の機構は、歯車が互いに動かしつづけているような、時計の機構に似ている。」
ここで語られるべきは、情報の蓄積という物語である。
それは、課税するにせよ、軍隊に徴兵するにせよ、飢饉のときに食糧を与えるにせよ、全住民の生活を管理したいという支配者の欲求がいっそう高じてきたことに対応しているし、その欲求をさらに高めることにも繋がった。
しかしながら、情報が行政機関のどこかに蓄積されていたといっても、それは、情報を必要とする支配者や役に人までつねに情報が届いていたということではない。
組織が大きくなれば、組織に入る情報が最上部にまで届かないという危険もそれだけ大きくなる。
言い換えるなら、政府と同様に歴史家は、いうなれば情報の「流通」ということを心がける必要がある。(「第六章 知識を管理する」より)
多くの人や情報と交わらず、社会との距離を、ほどほどに保つことで、自身の知識を管理することも重要である。
ステップ4:情報汚染の時代
自分の外側の情報量が。
増えれば増えるほど・・・
自分の内側に確かな価値観が。
必要になってくる・・・
「情報を捨てるセンス 選ぶ技術」ノリーナ・ハーツ(著)中西真雄美(訳)

▶無常迅速な世界を読み解くための方法
①意識・無意識を問わず、私たちは一日に一万件もの決断をしている。
②だから普段の意思決定の方法を今一度、考え直してみるべきだ。
③自分が信頼、尊敬しているのは誰か? 影響を受けすぎていないか?
④時間と心の余裕がなければ、賢明な意思決定などできないだろう。
⑤未来は予測できない。ならば思わぬ出会いを楽しもう。
▶正しい情報を見落とさないための方法
①目を引くデータが真実とは限らない。引用元を確認せよ。
②数字は引用者が主張したい部分しか語っていない。全体ではない。
③楽観主義は天才の源だが、単なるお気楽バカなこともある。
④自分の信条を裏付ける情報ばかりを求めれば、真実から遠ざかる。
⑤のんびり考えること。そうすれば多くの選択肢をもって物事に臨める。
⑥過去が現在や未来を約束するものではない。過去にこだわるな。
⑦常に自分の関心や能力を広げる努力をしよう。
▶盲目的に専門家に従わないための方法
①専門家からは部分を学び、全体を構築するのは自分自身だ。
②肩書きを隠したら、その人の話は信用できるだろうか?
③無知の知。己の限界を認める専門家こそが本物だ。
▶自分の脳を正しく働かせるための方法
①一日三食と十分な睡眠が頭脳を明晰にしてくれる。
②喜怒哀楽の感情に振り回されているときの意思決定を控えよう。
③決断後に一晩寝てから行動するくらいの余裕を持とう。
④場合によっては決断の量を減らすことも考えるべきだ。
▶烏合の衆にならないための方法
①ネット上には利用者の好みを判断して表示する機能が満載だ。
②だから情報収集が受動的にならないように注意しよう。
③ソーシャルメディアを使うなら、似た者同士で群れてはならない。
④チームで行動するときは、多様性のあるメンバー構成にしよう。
ということで、2024年12月に読めた本の中から、特に面白かった本(1冊)のご紹介です。
【特に面白かった本】
「働きたくないイタチと言葉がわかるロボット 人工知能から考える「人と言葉」」川添愛(著)花松あゆみ(イラスト)

何故人間はいとも簡単に言語を理解できるのか?
著者は、次の3点を指摘しています。
①人間の言語習得は、生まれた後に接する言葉だけを手がかりにしているわけではない。
「生まれ持った能力」が関わっていると考えられる。
これはある意味進化の過程で培われてきた本能的な能力の一部と考えて差し支えないだろう。
②人間は言葉についてメタな認識(言葉というのは何かを表すものであるなど)を持っている。
③人間は「他人の知識や思考や感情の状態を推測できる能力」を持っている。
①及び②項は、チョムスキーの生得文法、そして、ピンカーの洞察による適応としての言語本能が、ヒトには、生得的に備わっているという指摘。
そして、③項は、いわゆる「心の理論」の問題。
さて、本書では、言葉が分かる機械を実現するための下記のような論点が、物語を通じて分かるようになっており、
▶言葉が分かる機械を実現するために必要な条件
①音声や文字の列を単語の列に置き換えられること
②文の内容の真偽が問えること
③言葉と外の世界を結びつけられること
④文と文との意味の違いが分かること
⑤言葉を使った推論ができること
⑥単語の意味についての知識を持っていること
⑦相手の意図が推測できること
▶その条件を満たすための課題
①機械のための「例題」や「知識源」となる、大量の信頼できるデータをどう集めるか?
②機械にとっての「正解」が正しく、かつ網羅的であることをどう保証するのか?
③見える形で表しにくい情報をどうやって機械に与えるか?
以上のような論点を示した上で、著者は、以下の様に纏めています。
「大量のデータからの機械学習という現在主流の方法の延長線上で、言葉を理解する機械を実現することは、きわめて難しいと考えられます。」
最後に、言葉を理解する機械の真の実現に向けて、
①人間は生まれた後で接する言葉だけを手がかりにして言語を習得するわけではない
②人間はどこかの段階で、言葉というものは、何かを表すものであると認識している
③人間は他人の知識や思考や感情の状態を推測する能力を持っていること
といった、人の思考回路を、数理的に解明する必要があるとしているのですが、なぜ、シンギュラリティが恐れられているかというと、
「西洋は人間中心主義の中で、「人工知能はサーバント(召使い)である」「人間とは一線を画す人間以下のものである」という考えが一般的です。
人間の知能を模倣するように人工知能を作り、人工知能と人間の上下の線引きを明確にし、同時に人間と人工知能の立場の逆転を恐れます。
一方、日本は自然中心主義の中で、人間とは異なる存在として人工知能を作り、同胞として強く受け入れようとします。
横並びの同列の存在であることを求めます。」(三宅陽一郎「人工知能が生命になるとき」より)

であり、西洋の人工知能開発の思想的背景が、人間の知能を機械に与える、
「神の似姿として作られた人間」
といった人間中心の思想
「神 ー 人 ー 人工知能」
という縦の関係性にあるからだそうです。
そのため、西洋では、
「人工知能」
と
「人間の位置関係」
が、常に、神経質に、議論されているんですね。
「シンギュラリティというのは、人工知能が自分の能力を超える人工知能を自ら生み出せるようになる時点を指す。
自分以下のものをいくら再生産しても、自分の能力を超えることはないが、自分の能力を少しでも上回るものがつくれるようになったとき、その人工知能はさらに賢いものをつくり、それがさらに賢いものをつくる。
それを無限に繰り返すことで、圧倒的な知能がいきなり誕生する、というストーリーである。」(松尾豊「人工知能は人間を超えるか」より)

「シンギュラリティは、技術開発により指数関数的な成長を遂げると信じる思想であり、「科学信奉」に近いものがあります。」(伊藤穰一「教養としてのテクノロジー」より)
「シンギュラリティ信仰に基づく「テクノロジー・イズ・エブリシング」の考え方が、資本主義的な「スケール・イズ・エブリシング」の考え方につながり、本来は社会を良くするためにある「情報技術の発展」や「規模の拡大」が自己目的化して、さまざまな場所で軋轢や弊害を生み出しているように思える。」(伊藤穰一「教養としてのテクノロジー」より)
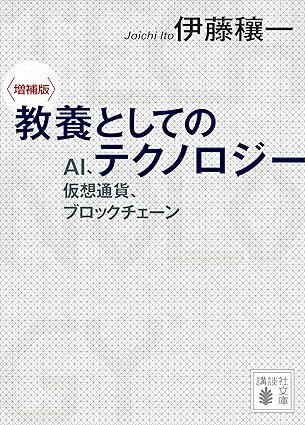
【二言三言】
言語化能力は決して万能ではない!
[参考記事]
言語表現は、本質的にフィクションである。
香西秀信さんの書籍に依れば、言葉による表現は、本来は、順序の付いていない事実であっても、そこに、何某かの順序を付けなければ、それを提示することができないと指摘していた。
例えば、
A子は美人だが性格が悪い。
A子は性格が悪いが美人だ。
というように情報として等価であっても同時に表現することができないため、それが提示される順序によって、聞き手・読み手に与える印象が異なってくる。
[参考図書]
「論理病をなおす! 処方箋としての詭弁」(ちくま新書)香西秀信(著)

「議論入門 負けないための5つの技術」(ちくま学芸文庫)香西秀信(著)

「レトリックと詭弁 禁断の議論術講座」(ちくま文庫)香西秀信(著)

【補足情報】
老子は、
「学問を修めるには日々知識を増やさなければならない。
道を修めるには、日々削ぎ落として行かなければならない」
と言っていましたね。
また、
「驕る者久しからず」
等、平家物語の時代から語り継がれており、読解力を磨くことの大切さを、痛感させられることもありました。
そこで、この数式を参考にして、
Behavior = Motivation × Ability × Prompt
何か学びたいものを見つけたら、無軌道に読書を重ねる前に、現代文の学び直しを優先して、まずは、中学・高校時代の勉強に戻って、土台を作るところから、また、初めてみる。
[テキスト]
「現代文 標準問題精講」神田邦彦(著)

第一章 言語と思考
1福岡伸一『世界は分けてもわからない』
2鈴木孝夫『ことばと文化』
3養老孟司『解剖学教室へようこそ』
4安井 泉『ことばから文化へ―文化がことばの中で息を潜めている―』
5香西秀信「事実は『配列』されているか?」
第二章 日本文化を考える
6鈴木孝夫『閉された言語・日本語の世界』
7河合隼雄『働きざかりの心理学』
8中根千枝『適応の条件』
9原研哉『日本のデザイン―美意識がつくる未来―』
10古市憲寿『絶望の国の幸福な若者たち』
第三章 現代社会を生きる
11香山リカ『「悩み」の正体』
12藤原新也「ネットが世界を縛る」
13平川克美『経済成長という病―退化に生きる、我ら―』
14鷲田清一「現代おとな考」
15岡真理「『文化が違う』とは何を意味するのか?」
第四章 近代的思考のかたち
16山崎正和『世紀末からの出発』
17見田宗介『社会学入門』
18河合隼雄『イメージの心理学』
19村上陽一郎『西欧近代科学』
20阪本俊生 『ポスト・プライバシー』
第五章 人間を洞察する
21小坂井敏晶『責任という虚構』
22日髙敏隆「代理本能論」
23中村雄二郎『哲学の現在』
(以下40講まで続く)
この参考書の特徴は、解説の幅が広く、文章全体の構成についてはもちろん、接続詞や指示語といった読解のポイントとなる単語を、どう利用していくかといった文法的なことや、「近代」などのよく論じられるテーマに関する知識まで書かれていて、時には、そのテーマに関する理解を深める参考文まで追加で乗せられていて、学び甲斐があります。
そのため、一つ一つの問題に対して、多様な観点から解説がしてあり、一つの文章で、読解力も、テクニックも、語彙力も身につくという、まさに一石三鳥の参考書です。
出典となる文章のレベルも高めで、一筋縄ではいかないような問題もあり、実践的な問題集と言えます。
【リストアップした書籍】
「響きと怒り」ウィリアム・フォークナー(著)桐山大介(訳)

「ヘルシンキ 生活の練習はつづく」朴沙羅(著)

「メトーデ 健康監視国家」ユーリ・ツェー(著)浅井晶子(訳)

「感情の海を泳ぎ、言葉と出会う」荒井裕樹(著)

「スマートシティとキノコとブッダ 人間中心「ではない」デザインの思考法」中西泰人/本江正茂/石川初(著)

「世界をちょっとよくするために知っておきたい英語100」キニマンス塚本ニキ(著)

「メランコリーで生きてみる」アラン・ド・ボトン(著)齋藤慎子(訳)

「擬人化する人間 脱人間主義的文学プログラム」藤井義允(著)
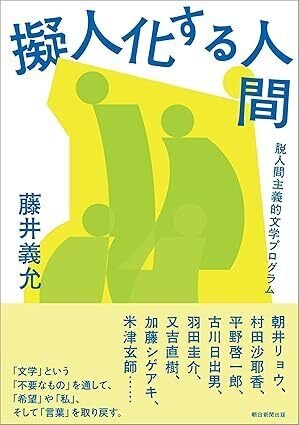
「饒舌な動植物たち ヒトの聴覚を超えて交わされる、クジラの恋の歌、ミツバチのダンス、魚を誘うサンゴ」カレン・バッカー(著)和田佐規子(訳)

「人が集まる、文化が集まる! まちの個性派映画館」美木麻穂(著)

「誰のためのアクセシビリティ? 障害のある人の経験と文化から考える」田中みゆき(著)

「なぜスナフキンは旅をし、ミイは他人を気にせず、ムーミン一家は水辺を好むのか」横道誠(著)

「カイエ 1957-1972」E.M.シオラン(著)金井裕(訳)

「ポイント経済圏20年戦争――100兆円ビジネスを巡る5大陣営の死闘」名古屋和希(著)
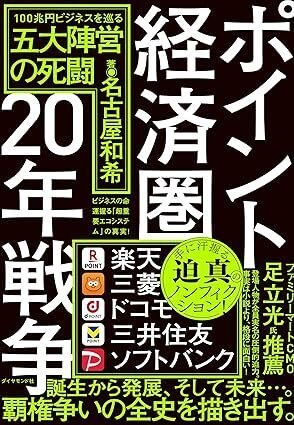
「SAME AS EVER この不確実な世界で成功する人生戦略の立て方 人の「行動原理」が未来を決める」モーガン・ハウセル(著)伊藤みさと(訳)
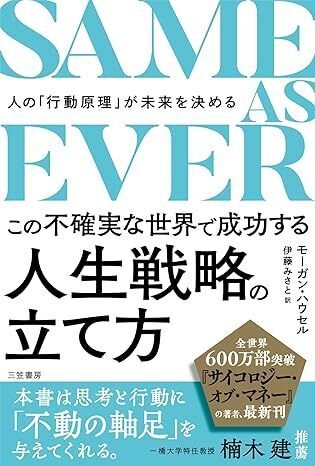
「〈迂回する経済〉の都市論 都市の主役の逆転から生まれるパブリックライフ」吉江俊(著)

「アファーマティブ・アクション 平等への切り札か、逆差別か」(中公新書)南川文里(著)

「料理人という仕事」(ちくまプリマー新書)稲田俊輔(著)

「生きるための最高の知恵 ビジョナリーが未来に伝えたい500の言葉」ケヴィン・ケリー(著)池村千秋(訳)服部桂(解説)

「NHK出版 学びのきほん 傷つきのこころ学」宮地尚子(著)

「宗教の起源」ロビン・ダンバー(著)小田哲(訳)

「カルトのことば なぜ人は魅了され、狂信してしまうのか」アマンダ・モンテル(著)青木音(訳)

「幻覚剤と精神医学の最前線」デヴィッド・ナット(著)鈴木・ファストアーベント・理恵(訳)

「働きたくないイタチと言葉がわかるロボット 人工知能から考える「人と言葉」」川添愛(著)花松あゆみ(イラスト)

「就職氷河期世代 データで読み解く所得・家族形成・格差」(中公新書)近藤絢子(著)

「テヘランのすてきな女」金井真紀(著)

「THE UNIVERSE IN A BOX 箱の中の宇宙 あたらしい宇宙138億年の歴史」アンドリュー・ポンチェン(著)竹内薫(訳)
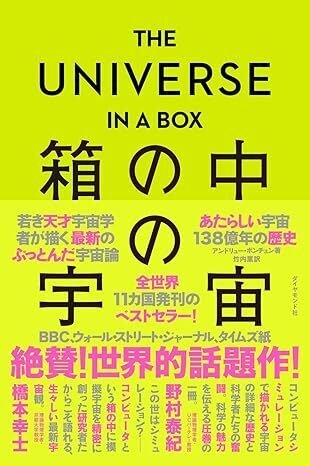
「働くということ 「能力主義」を超えて」(集英社新書)勅使川原真衣(著)

「企業変革のジレンマ 「構造的無能化」はなぜ起きるのか」宇田川元一(著)

「メメント・モモ 豚を育て、屠畜して、食べて、それから」八島良子(著, 写真)

「コモングッド 暴走する資本主義社会で倫理を語る」ロバート・B・ライシュ(著)雨宮寛/今井章子(訳)

「イノベーションの科学 創造する人・破壊される人」(中公新書)清水洋(著)

「なぜ、「怒る」のをやめられないのか~「怒り恐怖症」と受動的攻撃~」(光文社新書)片田珠美(著)

「メタフィジカルデザイン つくりながら哲学する」瀬尾浩二郎(著)

「エスノグラフィ入門」(ちくま新書)石岡丈昇(著)

「「対人関係療法」の精神科医が教える 「怒り」がスーッと消える本」 (大和出版)水島広子(著)
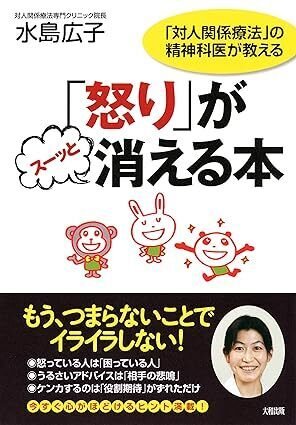
「みんなの都市 初心者のための都市計画マニュアル」オサム・オカムラ(著)ダヴィッド・ベーム/イジー・フランタ(イラスト)坂牛卓/邉見浩久(訳)

「生きることは頼ること 「自己責任」から「弱い責任」へ」(講談社現代新書)戸谷洋志(著)

「土と脂 微生物が回すフードシステム」デイビッド・モントゴメリー/アン・ビクレー(著)片岡夏実(訳)

「東大ファッション論集中講義」(ちくまプリマー新書)平芳裕子(著)

「名探偵の有害性」桜庭一樹(著)

「世界の本当の仕組み エネルギー、食料、材料、 グローバル化 、リスク、環境、そして未来」バーツラフ・シュミル(著)柴田裕之(訳)

「ニューヨーク精神科医の人間図書館」ナ・ジョンホ(著)米津篤八(訳)

「世代とは何か」ティム・インゴルド(著)奥野克巳/鹿野マティアス(訳)

「「怒り」を上手にコントロールする技術 アンガーマネジメント実践講座」(PHPビジネス新書)安藤俊介(著)

「遊びと利他」(集英社新書)北村匡平(著)

「人生が変わるゲームのつくりかた いいルールってどんなもの?」(ちくまQブックス)米光一成(著)

「図書館には人がいないほうがいい」内田樹(著)朴東燮(編訳)

「WAYS OF BEING 人間以外の知性」ジェームズ・ブライドル(著)岩崎晋也(訳)

「家の哲学 家空間と幸福」エマヌエーレ・コッチャ(著)松葉類(訳)

「「学び」がわからなくなったときに読む本」鳥羽和久(著)

「スマートシティはなぜ失敗するのか 都市の人類学」(ハヤカワ新書)シャノン・マターン(著)依田光江(訳)

「STATUS AND CULTURE 文化をかたちづくる〈ステイタス〉の力学 感性・慣習・流行はいかに生まれるか?」デーヴィッド・マークス(著)黒木章人(訳)

「ささる引用フレーズ辞典」堀越英美(著)

「読書効果の科学 読書の“穏やかな”力を活かす3原則」猪原敬介(著)

「わたしたちの担うもの」アマンダ・ゴーマン(著)鴻巣友季子(訳)

「15分都市 人にやさしいコンパクトな街を求めて」カルロス・モレノ(著)小林重裕(訳)

「発信する人のためのメディア・リテラシー」内田朋子/堤信子(著)

「書物とデザイン」松田行正(著)

「プロジェッティスタの控えめな創造力 イタリアンデザインの静かな革命」多木陽介(著)

「女の子のための西洋哲学入門 思考する人生へ」メリッサ・M・シュー/キンバリー・K・ガーチャー(編集)三木那由他/西條玲奈(監訳)青田麻未/安倍里美/飯塚理恵/鬼頭葉子/木下頌子/権瞳/酒井麻依子/ 清水晶子/筒井晴香/村上祐子/山森真衣子/横田祐美子(訳)

「詩探しの旅」四元康祐(著)

「編むことは力 ひび割れた世界のなかで、私たちの生をつなぎあわせる」ロレッタ・ナポリオーニ(著)佐久間裕美子(訳)

【関連記事】
多読・濫読・雑読・精読・積読それとも?
https://note.com/bax36410/n/n17c08f767e73
【本棚のある生活+α】2023年1月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n076e2800381c
【本棚のある生活+α】2023年2月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n1e809f8ad981
【本棚のある生活+α】2023年3月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n5b9792df1aa9
【本棚のある生活+α】2023年4月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n1255ac2dcf12
【本棚のある生活+α】2023年5月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n72c887bf894a
【本棚のある生活+α】2023年6月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n81559c79dd80
【本棚のある生活+α】2023年7月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n0d1664588d07
【本棚のある生活+α】2023年8月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/nefb833a75642
【本棚のある生活+α】2023年9月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/nf3d7ecad89cc
【本棚のある生活+α】2023年10月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/nea4c59c8cadc
【本棚のある生活+α】2023年11月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/ndb4b28943a59
【本棚のある生活+α】2023年12月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n3b772659b3e0
【本棚のある生活+α】2024年1月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/n8250c4e76ef5
【本棚のある生活+α】2024年2月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/ndeba14335317
【本棚のある生活+α】2024年3月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/nff7685e64fa8
【本棚のある生活+α】2024年4月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/nee95d5081b8d
【本棚のある生活+α】2024年5月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/nb80b9e7d00b9
【本棚のある生活+α】2024年6月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/ne33ba3a3594e
【本棚のある生活+α】2024年7月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/nb56da32d79f9
【本棚のある生活+α】2024年8月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/nbff2e6d45f4e
【本棚のある生活+α】2024年9月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/n762e06d4a1c7
【本棚のある生活+α】2024年10月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/n6ea7a3f64aa5
【本棚のある生活+α】2024年11月に読んで面白かった本
https://note.com/bax36410/n/nea31246856b1
