
【新書が好き】「あたりまえ」を疑う社会学
1.前書き
「学び」とは、あくなき探究のプロセスです。
単なる知識の習得でなく、新しい知識を生み出す「発見と創造」こそ、本質なのだと考えられます。
そこで、2024年6月から100日間連続で、生きた知識の学びについて考えるために、古い知識観(知識のドネルケバブ・モデル)を脱却し、自ら学ぶ力を呼び起こすために、新書を学びの玄関ホールと位置づけて、活用してみたいと思います。
2.新書はこんな本です
新書とは、新書判の本のことであり、縦約17cm・横約11cmです。
大きさに、厳密な決まりはなくて、新書のレーベル毎に、サイズが少し違っています。
なお、広い意味でとらえると、
「新書判の本はすべて新書」
なのですが、一般的に、
「新書」
という場合は、教養書や実用書を含めたノンフィクションのものを指しており、 新書判の小説は、
「ノベルズ」
と呼んで区別されていますので、今回は、ノンフィクションの新書を対象にしています。
また、新書は、専門書に比べて、入門的な内容だということです。
そのため、ある分野について学びたいときに、
「ネット記事の次に読む」
くらいのポジションとして、うってつけな本です。
3.新書を活用するメリット
「何を使って学びを始めるか」という部分から自分で考え、学びを組み立てないといけない場面が出てきた場合、自分で学ぶ力を身につける上で、新書は、手がかりの1つになります。
現代であれば、多くの人は、取り合えず、SNSを含めたインターネットで、軽く検索してみることでしょう。
よほどマイナーな内容でない限り、ニュースやブログの記事など、何かしらの情報は手に入るはずです。
その情報が質・量共に、十分なのであれば、そこでストップしても、特に、問題はありません。
しかし、もしそれらの情報では、物足りない場合、次のステージとして、新書を手がかりにするのは、理にかなっています。
内容が難しすぎず、その上で、一定の纏まった知識を得られるからです。
ネット記事が、あるトピックや分野への
「扉」
だとすると、新書は、
「玄関ホール」
に当たります。
建物の中の雰囲気を、ざっとつかむことができるイメージです。
つまり、そのトピックや分野では、
どんな内容を扱っているのか?
どんなことが課題になっているのか?
という基本知識を、大まかに把握することができます。
新書で土台固めをしたら、更なるレベルアップを目指して、専門書や論文を読む等して、建物の奥や上の階に進んでみてください。
4.何かを学ぶときには新書から入らないとダメなのか
結論をいうと、新書じゃなくても問題ありません。
むしろ、新書だけに拘るのは、選択肢や視野を狭め、かえってマイナスになる可能性があります。
新書は、前述の通り、
「学びの玄関ホール」
として、心強い味方になってくれます、万能ではありません。
例えば、様々な出版社が新書のレーベルを持っており、毎月のように、バラエティ豊かなラインナップが出ていますが、それでも、
「自分が学びたい内容をちょうどよく扱った新書がない」
という場合が殆どだと思われます。
そのため、新書は、あくまでも、
「入門的な学習材料」
の1つであり、ほかのアイテムとの組み合わせが必要です。
他のアイテムの例としては、新書ではない本の中にも、初学者向けに、優しい説明で書かれたものがあります。
マンガでも構いません。
5.新書選びで大切なこと
読書というのは、本を選ぶところから始まっています。
新書についても同様です。
これは重要なので、強調しておきます。
もちろん、使える時間が限られている以上、全ての本をチェックするわけにはいきませんが、それでも、最低限、次の2つの点をクリアする本を選んでみて下さい。
①興味を持てること
②内容がわかること
6.温故知新の考え方が学びに深みを与えてくれる
「温故知新」の意味を、広辞苑で改めて調べてみると、次のように書かれています。
「昔の物事を研究し吟味して、そこから新しい知識や見解を得ること」
「温故知新」は、もともとは、孔子の言葉であり、
「過去の歴史をしっかりと勉強して、物事の本質を知ることができるようになれば、師としてやっていける人物になる」
という意味で、孔子は、この言葉を使ったようです。
但し、ここでの「温故知新」は、そんなに大袈裟なものではなくて、
「自分が昔読んだ本や書いた文章をもう一回読み直すと、新しい発見がありますよ。」
というぐらいの意味で、この言葉を使いたいと思います。
人間は、どんどん成長や変化をしていますから、時間が経つと、同じものに対してでも、以前とは、違う見方や、印象を抱くことがあるのです。
また、過去の本やnote(またはノート)を読み返すことを習慣化しておくことで、新しい「アイデア」や「気づき」が生まれることが、すごく多いんですね。
過去に考えていたこと(過去の情報)と、今考えていること(今の情報)が結びついて、化学反応を起こし、新たな発想が湧きあがってくる。
そんな感じになるのです。
昔読んだ本や書いた文章が、本棚や机の中で眠っているのは、とてももったいないことだと思います。
みなさんも、ぜひ「温故知新」を実践されてみてはいかがでしょうか。
7.小説を読むことと新書などの啓蒙書を読むことには違いはあるのか
以下に、示唆的な言葉を、2つ引用してみます。
◆「クールヘッドとウォームハート」
マクロ経済学の理論と実践、および各国政府の経済政策を根本的に変え、最も影響力のある経済学者の1人であったケインズを育てた英国ケンブリッジ大学の経済学者アルフレッド・マーシャルの言葉です。
彼は、こう言っていたそうです。
「ケンブリッジが、世界に送り出す人物は、冷静な頭脳(Cool Head)と温かい心(Warm Heart)をもって、自分の周りの社会的苦悩に立ち向かうために、その全力の少なくとも一部を喜んで捧げよう」
クールヘッドが「知性・知識」に、ウォームハートが「情緒」に相当すると考えられ、また、新書も小説も、どちらも大切なものですが、新書は、主に前者に、小説は、主に後者に作用するように推定できます。
◆「焦ってはならない。情が育まれれば、意は生まれ、知は集まる」
執行草舟氏著作の「生くる」という本にある言葉です。
「生くる」執行草舟(著)
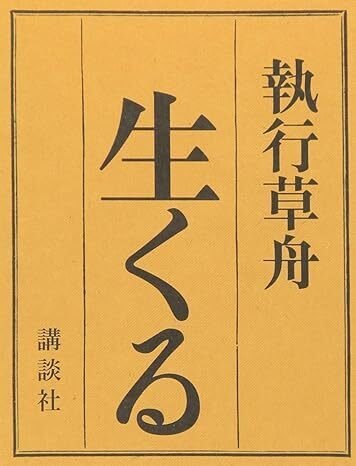
まず、情緒を育てることが大切で、それを基礎として、意志や知性が育つ、ということを言っており、おそらく、その通りではないかと考えます。
以上のことから、例えば、読書が、新書に偏ってしまうと、情緒面の育成が不足するかもしれないと推定でき、クールヘッドは、磨かれるかもしれないけども、ウォームハートが、疎かになってしまうのではないかと考えられます。
もちろん、ウォームハート(情緒)の育成は、当然、読書だけの問題ではなく、各種の人間関係によって大きな影響を受けるのも事実だと思われます。
しかし、年齢に左右されずに、情緒を養うためにも、ぜひとも文芸作品(小説、詩歌や随筆等の名作)を、たっぷり味わって欲しいなって思います。
これらは、様々に心を揺さぶるという感情体験を通じて、豊かな情緒を、何時からでも育む糧になるのではないかと考えられると共に、文学の必要性を強調したロングセラーの新書である桑原武夫氏著作の「文学入門」には、
「文学入門」(岩波新書)桑原武夫(著)

「文学以上に人生に必要なものはない」
と主張し、何故そう言えるのか、第1章で、その根拠がいくつか述べられておりますので、興味が有れば確認してみて下さい。
また、巻末に「名作50選」のリストも有って、参考になるのではないかと考えます。
8.【乱読No.48】「「あたりまえ」を疑う社会学 質的調査のセンス」(光文社新書)好井裕明(著)

[ 内容 ]
数字データでは語れないさまざまな現実を、いかに取り出すか。
[ 目次 ]
第1章 数字でどこまで語れるか
第2章 はいりこむ
第3章 あるものになる
第4章 聞き取る
第5章 語りだす
第6章 「あたりまえ」を疑う
第7章 「普通であること」に居直らない
[ 発見(気づき) ]
社会学における質的調査を、いくつかのモノグラフを筆者なりに読み解きながら紹介した本。
量的調査が、
「答える人々に対する想像力が確実に不足」(P23)
しがちなものであるのに対して、質的調査は、適切に行われた場合、
「人々が自らの生きてきた経験を語る言葉や、その場で思わずあふれ出る情緒、あるいは抑制された感情、私に向かう語りの力」(P35)
と出会うことを可能にするものである。
本書は、基本的な考えの中には疑問な点もあったが、断片的には非常に面白い部分があった。
面白かったのは、大衆演劇の劇団に1年2ヶ月入って書かれたフィールドワークを紹介している部分である。
その本自体は読んだことはなかったが、その筆者が書いたものは目にしたことがあったので、概要を多少は知っているつもりだったのだが、筆者の適切な紹介と読み解きで、その面白さは倍増したように思う。
その本の筆者は劇団員として、最初は不適応を起こしつつも、しだいに適応していき、多少なりとも大衆演劇の世界でそれなりの過ごし方ができるようになっていっているのではあるが、しかし、役者になりきることはできなかった、と考えているらしい。
それを受けて筆者は、普段の暮らしの中で我々も、何かになりきることはできておらず、だからこそ何者かになりきり続けようとしているのだ、と論じている。
これはなるほどであった。
私は大衆演劇の話を、「なりきれない」世界から「なりきる」世界の入り口に行った人のフィールドワークだと思っていた。
そうだとすれば、それはそれだけの話である。
しかし筆者は、
「おそらく、大衆演劇の世界で役者を生きる人々も、「なりきった」瞬間などないだろう」(P114)
と論じている。
そう考えるならば、私自身も、私の周りの人も、なりきる途上にいる人ということになる。
それはとても納得のいく説明である、とこの章を読んで感じた。
そういう部分はとてもよかったし、質的調査から見えてくるものの豊かさを感じることはできたのだが、しかし本書の基本的な語り口や、筆者の論の進め方というか考え方のなかには、ちょっと納得のできないところがいくつかあった。
[ 問題提起 ]
たとえば筆者は、本書の冒頭で、
「例外的な他者をつくり、それを自らの暮らしから排除することで、私たちの気持ちや暮らしは安定するのだろうか。/おそらくそうではないだろう。」(P11)
と延べ、それを(質的に)読み解いていく必要性を説いている。
あるいは最後のほうでは、
「世の中に流布している、さまざまなカテゴリーや、それにはりついている実践的な処方を"鵜呑み"にして生きていくことは、気持ちのいいものだろうか」(P202)
というような問いかけを何箇所かでしている。
要するに筆者にとっては「気持ちのよくない」ものであり、それを解き明かしてくれるのが質的調査、ということのようなのである。
しかしこのような考えには大きな疑問がある。
筆者は、例外的な他者を排除することは安定にはつながらないし、カテゴリーや実践的処方を鵜呑みにして生きていくことは気持ちのいいものではない、と論じる。
少なくとも筆者はそうなのだろう。
しかしそれはすべての人に当てはまることなのだろうか。
筆者にしても、いつもそうなのだろうか。
こういう風に無限定に断言してしまうということは、そういうことを気持ちのいいことだと感じる人に対する想像力が、筆者には不足してはいないだろうか。
そもそも、何も鵜呑みにせずに生きていくことなど可能なのだろうか。
本書、
「はじめて考えるときのように 「わかる」ための哲学的道案内」(PHP文庫)野矢茂樹(著)植田真(イラスト)

で野矢氏が論じるように、
「無数の見えない枠がなければ生活できない」
のではないだろうか。
このような、鵜呑みにすることの意味に関する筆者の考えは、質的調査のセンスが感じられないように私には感じられた。
本書が私にとって「断片的には」興味深かったというのは、そういうことである。
興味深い断片はとても興味深いだけに、それがとても残念であった。
[ 教訓 ]
本書は、社会学のフィールドワーク論である。
「聞き取るという営みは、単に相手から必要とする情報を効率よく収集する、という発想では、とてもできない。
相手を情報を得るためだけの源であるかのように見ていると、それが伝わった瞬間、おそらく聞き取りは硬直し、相手との<いま、ここ>での出会いは失われていくだろう。」
観測することが対象に影響を与えてしまう相互性という点では、量子物理学の観測とほとんど同じである。
自然科学の客観的な観察が成り立つのは、実は実験室でできるごく限られた世界に過ぎない。
「語りのちから」によって、聞き取る側の意見や価値観も変動していく。
「現代の社会学には、私たちの暮らしの大半をおおっている「あたりまえ」の世界を解きほぐして、そのなかにどのような問題があるのかを明らかにしていこうとする営みがある。
それはエスノメソドロジー(ethnomethodology)と呼ばれているものだ。」
たとえば男性と女性が会話をすると、一般に、女性の発話に男性が割り込む回数が多い。
女性は男性の話にあいづちをうったり、うなずく回数が多い。
男女同権がタテマエ的には成立している、「あたりまえの」私たちの社会でも、男女の間には隠れた権力関係が存在していることがうかがえる。
多くの人が、ニート問題や差別問題、犯罪者の経歴などについては、無意識のうちに高みや客観的な立場から発言してしまいがちだ。
たとえば「私は差別したことも差別されたこともない普通の人間なのですが、あなたの差別体験を教えてください」など発言してしまう人がいる。
その普通感が差別の源かもしれないのにである。
無意識のあたりまえがあることを著者はいくつもの事例を使って指摘している。
道具としての「カテゴリー化」、特定のコミュニティで特権的な地位を占める語り=「モデル・ストーリー」、全体社会の支配的言説=「マスター・ナラティブ」「ドミナント・ストーリー」が、聞き取りをするもの、されるもの両者の言説の背景にあることを理解する必要があると著者は書いている。
社会学の学生や教員向けに読み物として書かれているが、部外者として何かを当事者から聞き取る際のノウハウ本として読むことができる。
「どのような理屈を立てようとも、「はいりこむ」人は、人々の暮らしや現実にとって“余計な存在”である」
著者の言葉に思わず深く頷いた。
研究者は調査対象者にとって、邪魔な存在ではないにしろ、余計な存在なのである。
調査に協力したからといって、調査対象者の利益に直結するわけではないのである。
調査に基づいた論文を発表することで、研究業績が得られ、調査者の利益になることは確実だが。
調査者が得る利益と調査対象者が得る利益は非対称であるということを肝に銘じた上で、調査者は調査に臨まねばならない。
調査対象者の意思に合わせる配慮が調査者には求められる。
調査者の思い込みによる誘導尋問などは厳に慎まねばならない。
研究者よ、謙虚たれ。
このように著者のメッセージを自分なりに解釈した。
これまで以上に虚心坦懐に調査を行おうと思う。
[ 結論 ]
筑波大学教授で社会学者である著者による、社会学のすすめ。
質的調査の「リサーチ・マインド」をコンパクトに伝える本である。
各章では「はいりこむ」「あるものになる」「聞き取る」「語りだす」などのテーマを設定し、それぞれの方法の魅力や課題を描き出す。
章立てはおおよそ調査の手順に沿っており、読者はあたかも現場に入り、問題に直面しながら作業を進めていくかのような体験を味わう。
本書の魅力の一つは、エスノグラフィーについてのすぐれたブックガイドであること。
各章のテーマに合ったエスノグラフィーが次々と紹介され、いきいきとした記述が引用される。
引用元の本も読んでみたいと思わせる効果的なガイドだ。
また、著者自身の調査体験の想い出話も生々しく、読者をひきつける。
著者は本書について、書店の棚を占めるハウツー本とは違い、常識に絡めとられている私たちを解放しようとする辛気くさいものだと言う。
しかし、本書はかなり実用性の高い本なのでは、と私は見ている。
たとえば、教育、福祉、医療、開発など、対人的な支援業務につくことを目指すすべての学生に、これを読んでもらったらどうだろう。
「支援対象」というカテゴリーを一度こわし、他者の話を現場で聞いて考える姿勢を養うことができるのではなかろうか。
著者の控えめなことばに反して、これは根源的に人間観をゆさぶるハウツー本なのである。
社会調査を行うときに、質問を用意して回答してもらい、それを統計的に処理して結論を導く。
いかにも科学的に見えるけど、こうした方法に私はいつもなんとなく腑に落ちないものを感じていた。
この本を読んで、ああ、私の感じていた気持ち悪さはそういうことだったのか、と思った。
たとえば、次のような質問項目にどう答えるか?
「あなたは本当なら感じたくないような感情をいだいてしまうことがありますか?(とてもよくある 1-2-3-4-5-6-7 まったくない)」
まず、質問内容が曖昧だ。
それでも、1から7のどこかに○をつけなくてはならない。
こういうアンケートをどれだけたくさん集めても、その結果、何が明らかになるというのだろうか。
様々な社会問題について調べたいと思う。
差別の実態について聞き取りをしたい。
でも、誰がそんなことを好き好んで話すだろうか。
調査のためだけに何故こちらのプライバシーをさらけださねばならないのか。
調べようとする人は自分が「余計な存在」であることを自覚しなくてはいけない。
マイノリティと呼ばれる人々。
調査者が自分をその枠外におき、自分は「普通」の人間であり、対象者とは違う、という設定のもとで聞き取り調査を行ったらどうなるか。
部落解放運動をすすめている当事者とある評論家との対話で、評論家が切り出す。
「私は特に厳しい差別を受けた経験もないし、ひどい差別などしたことはありません。その意味で普通の人間なのですが、そうした立場から、いろいろお尋ねしたいとー」(P222)
相手はこの発言をそのまま承認し、対談が始まったのだそうだが、筆者はこれに驚いたという。
「普通の人間」は差別を受けたり、差別をしたりしない・・・この評論家の語りは暗にそういう見方を主張しているのだ。
普通って何か。
あたりまえって何か。
同性を愛してしまうゲイの人たちは「普通」ではないのか。
ひきこもる人たちは「普通」ではないのか。
そして、調査者自身も「普通」であることにどれほど自分がとらわれているかということについて自覚しているだろうか。
ジャーナリストと似たような動きする一群の社会学者がいる。
フィールドワークをしている人たちである。
ミルズの「社会学的想像力」を読んだときにも思ったが、本書を読み、あらためて彼ら・彼女らへの親近感を覚えた。
「社会学的想像力」(ちくま学芸文庫)C・ライト・ミルズ(著)伊奈正人/中村好孝(訳)

人と会って話を聞くという点ではジャーナリストにもアカデミシャンにも同じ技術や感覚が要求されるのだろう。
いや、両者をカテゴライズすることに、意味なんてないかもしれない。
「あたりまえ」とされていることを疑う目をもち、対象とする社会にはいりこみ、矛盾や不条理を公にしようとする点で、両者に差異はない。
本書のなかで鵜飼正樹の「大衆演劇の旅」が紹介されている。
「大衆演劇への旅 南條まさきの一年二カ月」鵜飼正樹(著)

この作品は、鵜飼氏が大衆演劇の一座にはいりこみフィールドワークをした壮絶な記録である。
京都大学大学院の大学院生だった鵜飼氏は参与観察をするため一座に入門する。
だが、教養豊かで品行方正な京大院生が飛び込んだ社会は想像を絶する世界だった。
しかし、時とともに鵜飼氏は劇団メンバーの一員となっていく。
本内容について著者が96頁に引用した部分を以下に孫引きしておく。
「夜中に、二代目さん、みつる兄と車で富山市内随一の盛り場、桜木町へ出てみるが、雑居ビルがポツポツ並んでいるだけのつまらないところだった。
『何かおもろいことないけ』帰り道、遠くに二人組の女の子の後ろ姿。近寄って卑猥なことばを投げかける。
女の子たちは知らんふり。
さらに車を近づけると、急に走って逃げだし、暗い路地に逃げ込んでしまった。
こんなことをするのは初めてだったが、おまえも何か言えと言われぼくも思わず『ねーちゃん、オメコしょーか』とスケベなことばを浴びせかけていた、ああ、良識ある大学院生のぼくはどこへ行ってしまったんだろう。
暑い一日だった。」
「客観報道」や「不偏不党」を標榜するジャーナリストなら、こうした性暴力的な行為について、鵜飼氏のように正直に書かないだろうと思う。
[ コメント ]
ジャーナリストの場合は、つねにどこか醒めていることが要請されるからだ。
すくなくとも「良識ある○○新聞記者のぼくはどこへ行ってしまったんだろう」などとは記事に書くまい。
この点、インタビューを相互行為ととらえ、作品を協働作業による構築物とみる?エスノメソドロジーに、わたしは愚直さを感じる。
つまり、いつも規範性を要求される(勝手に要求されていると信じている)ジャーナリストのほうが嘘をついてしまう危険性が高くなるということだ。
フィールドワーカーとジャーナリストが駆使する技法には大きな差異はないかもしれない。
個人の力量の負うところが大きい。
だが、作品の“語り”はずいぶん違いそうだ。
話者が立っている位置や対象に向ける眼差しも、かなり差異がありそうな気がする。
9.参考記事
<書評を書く5つのポイント>
1)その本を手にしたことのない人でもわかるように書く。
2)作者の他の作品との比較や、刊行された時代背景(災害や社会的な出来事など)について考えてみる。
3)その本の魅力的な点だけでなく、批判的な点も書いてよい。ただし、かならず客観的で論理的な理由を書く。好き嫌いという感情だけで書かない。
4)ポイントを絞って深く書く。
5)「本の概要→今回の書評で取り上げるポイント→そのポイントを取り上げ、評価する理由→まとめ」という流れがおすすめ。
10.関連記事
【新書が好き】行動分析学入門
https://note.com/bax36410/n/nf4d6f6ef7fec
【新書が好き】霊はあるか
https://note.com/bax36410/n/nb397602c06a8
【新書が好き】日本の「ミドルパワー」外交
https://note.com/bax36410/n/nff46698ea558
【新書が好き】狂気と犯罪
https://note.com/bax36410/n/nc00c2d42a6dc
【新書が好き】歴史認識を乗り越える
https://note.com/bax36410/n/n4e4225974b41
【新書が好き】父と娘の法入門
https://note.com/bax36410/n/nf261a09672ed
【新書が好き】アメリカ保守革命
https://note.com/bax36410/n/n968de29b9590
【新書が好き】自由とは何か
https://note.com/bax36410/n/nda37804ca159
【新書が好き】いきなりはじめる浄土真宗
https://note.com/bax36410/n/n1759ee81cac8
【新書が好き】はじめたばかりの浄土真宗
https://note.com/bax36410/n/n1c0fa6a39d79
【新書が好き】ナショナリズムの練習問題
https://note.com/bax36410/n/n4a636e80a2f9
【新書が好き】戦後和解
https://note.com/bax36410/n/nac7b70ea3bb5
【新書が好き】ブッダとそのダンマ
https://note.com/bax36410/n/ndc56a78b8a45
【新書が好き】動物化する世界の中で
https://note.com/bax36410/n/n02a8ab9d2f0a
【新書が好き】さまよう死生観
https://note.com/bax36410/n/ned739bc09ff8
【新書が好き】国際政治とは何か
https://note.com/bax36410/n/nca1243570704
【新書が好き】エコノミストは信用できるか
https://note.com/bax36410/n/n53922ed9f3a0
【新書が好き】正義を疑え!
https://note.com/bax36410/n/n44d4877b74aa
【新書が好き】ナショナリズム
https://note.com/bax36410/n/nfcacc73e1796
【新書が好き】劇場政治を超えて
https://note.com/bax36410/n/ned0b825e09ba
【新書が好き】テロ-現代暴力論
https://note.com/bax36410/n/nff7d0ca0f520
【新書が好き】アメリカ外交とは何か
https://note.com/bax36410/n/n462e59d83c69
【新書が好き】日露戦争
https://note.com/bax36410/n/n64b42ab78351
【新書が好き】不幸論
https://note.com/bax36410/n/nf3a4463523b2
【新書が好き】夢の科学
https://note.com/bax36410/n/n1a673641b34e
【新書が好き】戦争報道
https://note.com/bax36410/n/n20af0a5cc031
【新書が好き】少年犯罪実名報道
https://note.com/bax36410/n/nae1b010fa57e
【新書が好き】『葉隠』の武士道
https://note.com/bax36410/n/nd41c0936c4e1
【新書が好き】現代ロシアを読み解く
https://note.com/bax36410/n/n37490828476f
【新書が好き】キリスト教を問いなおす
https://note.com/bax36410/n/n3434dc659e6e
【新書が好き】上達の法則
https://note.com/bax36410/n/ndfe8bc72024d
【新書が好き】「快楽消費」する社会
https://note.com/bax36410/n/nb1f5d8a5bac0
【新書が好き】スナップ・ジャッジメント
https://note.com/bax36410/n/n1d3a69a1309f
【新書が好き】神道の逆襲
https://note.com/bax36410/n/n3589cd192387
【新書が好き】問題解決のための「社会技術」
https://note.com/bax36410/n/nd13dcff12b69
【新書が好き】数学的思考法
https://note.com/bax36410/n/nfb765b77035c
【新書が好き】現代アメリカのキーワード
https://note.com/bax36410/n/n9ff95c9826ba
【新書が好き】必笑小咄のテクニック
https://note.com/bax36410/n/n408ca700fbcb
【新書が好き】「格付け」市場を読む
https://note.com/bax36410/n/n79a2861b7d0f
【新書が好き】好かれる方法
https://note.com/bax36410/n/nee53c79c4bea
【新書が好き】スラスラ書ける!ビジネス文書
https://note.com/bax36410/n/nb79bb8c969f2
【新書が好き】宇宙人としての生き方
https://note.com/bax36410/n/n55082c27f019
【新書が好き】科学者が見つけた「人を惹きつける」文章方程式
https://note.com/bax36410/n/nb3c9fc87290d
【新書が好き】奇妙な情熱にかられて
https://note.com/bax36410/n/n13b2a0e52bc8
【新書が好き】科学者という仕事
https://note.com/bax36410/n/n0fabee964d47
【新書が好き】福祉工学の挑戦
https://note.com/bax36410/n/n1098e345f157
