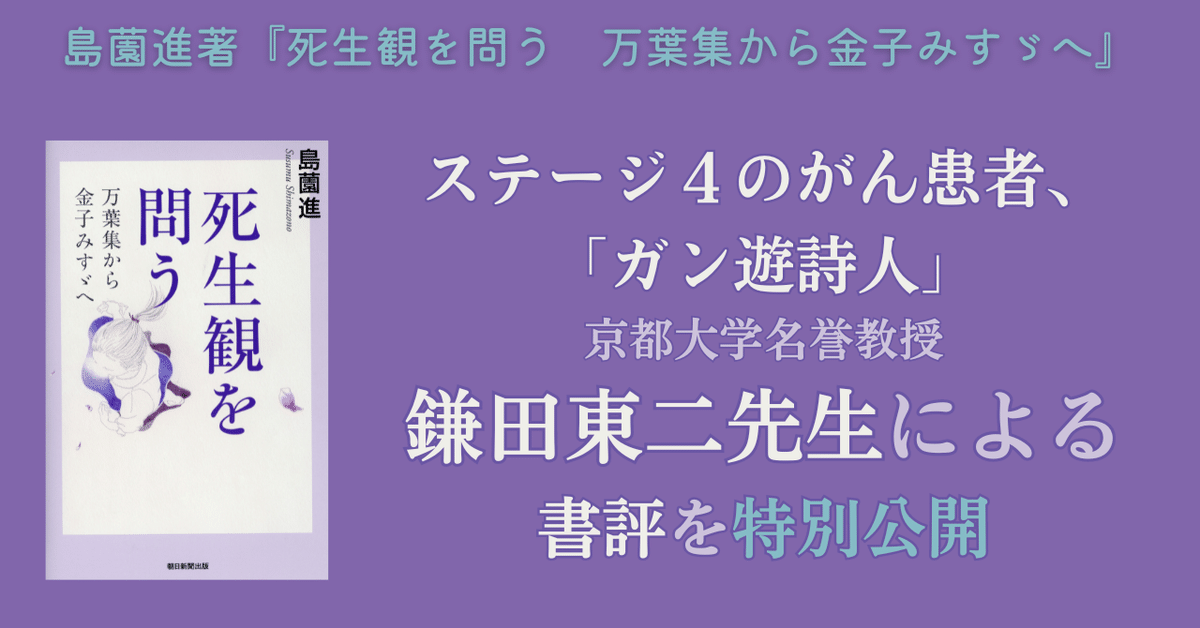
ステージ4のがん患者、「ガン遊詩人」の鎌田東二・京都大学名誉教授が、島薗進さんの『死生観を問う 万葉集から金子みすゞへ』を評す
宗教学、死生学の第一人者で、グリーフケア研究を担ってきた島薗進さんが、死、喪失、別れについて、「あなた自身の死生観」のために執筆した『死生観を問う 万葉集から金子みすゞへ』(朝日選書)。宗教の教える死生観、詩歌や物語を手がかりに、死の彼方を童謡歌詞で歌った金子みすゞ、子どもの死に親の哀切な心があふれる一茶、桜を通してはかない命をおしむ西行、漢詩で死の瀬戸際に安らぎを見いだした漱石などにふれています。本書の全体像を的確にまとめた、京都大学名誉教授・鎌田東二先生による「一冊の本」掲載の「最初の読者から」を特別に公開いたします。

「あなた自身の死生観」のために、多大なヒントと気づき
島薗進さんとは半世紀の付き合いだ。二十代の半ばに宗教社会学研究会で初めて出会って以来、さまざまな局面で伴走してきた。
その50年近くの島薗進の学道探究の旅路を間近に見て来た者として、最新著『死生観を問う 万葉集から金子みすゞへ』は、折口信夫研究(修士論文)から死生学研究(東京大学COE拠点リーダー)を経て、グリーフケア研究に参入してきた「島薗学」の総括とも集大成とも言える渾身の一冊であると受け止めている。島薗進の眼と心を通して透かし見えた日本の文学(童謡を含む)と宗教(死生観を焦点化した)のきらきらしい陰影豊かな風光。その熟成した味わい深い風光を提示し得た「島薗学」の研鑽と知情意に心からの敬意を表したい。
本書は、読者の死生観形成を促し支援する本であると同時に、著者自身の死生観の練成の過程をも垣間見せてくれる。いわば「島薗死生学」の形成過程を、四国遍路の旅のように、古代から現代までの時系列と各地域の空間系列と文学者や宗教家各人の人物系列を自由に往還し召喚しながら逍遥する、一種の「死生観絵巻物」である。その死生観ナラティブは、著者の等身大の関心と探究に即しているので、読者は弘法大師との同行二人のように歩行し、自分のペースで行きつ戻りつすることができる。
「現代人の死生観の探究の巡礼の旅を一巡して、還ってくる」という構成になっているので、「あなた自身の死生観のために」多大なヒントと気づきを与えてくれるだろう。
その際のキーワードは、魂のふるさと、無常、孤独、悲嘆、慰霊・追悼・鎮魂、桜、うき世であり、取り上げる人物群は、柳田國男、折口信夫、金子みすゞ、出口王仁三郎、太宰治(第1章)、野口雨情、小林一茶、鴨長明、蓮如、芭蕉、李白、大伴旅人、山上憶良(第2章)、紀貫之、杜甫、菅原道真(第3章)、紫式部、西行、井原西鶴、福沢諭吉(第4章)、夏目漱石(終章)など多様で多彩である。
特筆すべきは、一方では安心の拠り所とも言える「魂のふるさと」が、他方では「孤独」であるがゆえに思慕され求められるというアンビバレンツが鋭く示されている点。これこそ現代人のスピリチュアリティへの関心や探究の基盤にある裂け目である。それは、室生犀星の「ふるさとは遠きにありて思ふもの/そして悲しくうたふもの」(「小景異情」その二)であり、石川啄木の「ふるさとの訛なつかし停車場の人ごみの中にそを聴きにゆく」(『一握の砂』)心情である。文学も宗教もそのようなアンビバレンツや裂け目を埋めるサムシング・エロスのはたらきと言える。
このサムシング・エロス(ふるさと思慕と探究)は、必然的に「魂のふるさと」すなわち安心や信頼の拠り所と「孤独」との間の往還となり、そこに「無常」という世界観も、「悲嘆」の感情も、「慰霊・追悼・鎮魂」の儀礼のわざも生まれてくる。それらがさまざまな文学作品や宗教思想や宗教活動となって現われ出る。たとえば「マレビトという言葉は、『魂のふるさと』のよそ者、『魂のふるさと』から追放された人という意味合いも含むものだった」と折口信夫の「原初の孤独」を浮き彫りにする箇所など。
著者はそれらを確かな選択眼で取り上げ、親切な語り口で読者の心前にやさしく差し出す。その手つき、目配り、心配りに、「島薗学」五十年の発酵と熟成を見る。
本書には、随所に著者の視点、作品選択眼、独自の解釈と洞察が見られる。たとえば、漢詩と和歌や俳句との違い。鴨長明と小林一茶や野口雨情の無常の違い。折口信夫と出口王仁三郎と太宰治のスサノヲ観の共通項と微妙な差異。紀貫之の『土佐日記』の「悲嘆の文学」の側面のみならず「笑いの文学」や「憤りの文学」の側面の考察など、注意深く先行研究を参照しながらも著者独自の考察を上書きし、これまでとは異なる局面や文脈やフレームワークの中に位置付けていく。そこに半世紀の学道の熟成が滲み出る。
そして最初と最後に、『おらおらでひとりいぐも』の次の一節が取り上げられる。「帰る処があった。心の帰属する場所がある。無条件の信頼、絶対の安心がある。八角山へ寄せるこの思い、ほっと息をつき、胸をなでおろすこの心持ちを、もしかしたら信仰というのだろうか。八角山はおらにとって宗教にも匹敵するものなのだろうか」
だが「帰る処・心の帰属する場所」を持ち「無条件の信頼」を寄せ「絶対の安心」を抱くことは簡単ではない。現代の気候危機の中で世界中の山河が大きく変化しているからだ。いつ何どき土砂崩れや崩落に見舞われるかわからない危機的な状況にある。そうした中で「魂のふるさと」という定点に行き着けず、漂流する死生観を生きるほかない人びとへの次なるメッセージが必要であろう。
