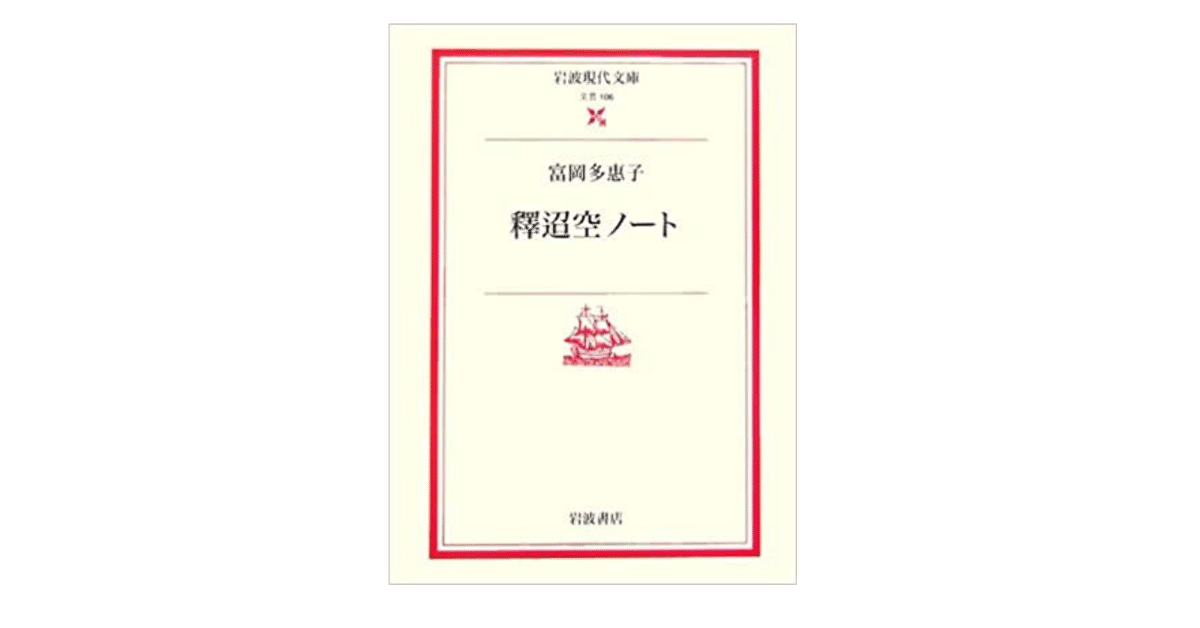
折口信夫の「明かしえぬ共同体」
『釋迢空ノート』富岡 多惠子 (岩波現代文庫)
戒名を筆名とした詩人・折口信夫(歌人・釋迢空)が秘していたもの,自ら葬り去ったこととは何か.虚と実,学問と創作,短詩型と自由詩の狭間に生きた折口の難問とは.日本の近代と格闘した巨人の軌跡を,その歌と小説にしかと向き合い,史料の発掘と確かな精読で描き出した渾身の評伝.毎日出版文化賞受賞作.
釋迢空という歌人をいくつかの歌とともに記憶している人も多いことでしょう.そして,釋迢空という筆名で歌人,詩人として活躍したのが,国文学・民俗学の分野で巨大な足跡を残した折口信夫,まさにその人であることも広く知られています. ただ,なぜ釋迢空という法名のような筆名を持っていたのか.釋迢空=折口信夫の生涯にはどのような謎が存在していたかについては,くわしい知識をもたれていない方も多いのではないでしょうか. 本書は,巨人折口信夫の仕事と人生に隠された謎に大胆に迫った力作です.釋迢空の詩歌をとくと味わい,史料を発掘し,鮮やかな手法で精読を試みています. 許されない恋愛の渦中にあり続けた釋迢空は,体験の作り替え,事実の韜晦に満ちた言説を発し続けましたが,著者はその錯綜を鮮やかに解明してみせました. 虚と実,学問と創作,短詩型と自由詩の狭間に生きた折口の難問とは何だったのでしょうか.日本の近代と格闘した巨人が自ら葬り去ったものとは何だったのでしょうか.本書はその生涯を,その歌と小説にしかと向き合って執筆した渾身の評伝です(本書は『世界』98年5月号から2000年9月号まで10回にわたって連載された後,2000年に岩波書店から刊行され,毎日出版文化賞を受賞しました).
大阪出身の詩人であった富岡多恵子が釈迢空の短歌から読み取ろとしたのは、釈迢空の「批評」性であり、それは短歌の韻律七五調が生み出す日本の叙情ということに対してである。同じ万葉調の短歌を目指しながら斎藤茂吉との分岐点は、それを当たり前のように受け入れるのか、そこに批評性を持って立ち向かのかという短歌の姿勢にあった。すでに釈迢空は五七調の韻律である短歌は滅びつつある定形詩だと見ていた。それを「ごーすと」性と呼ぶのだが、短歌は前近代の幽霊を呼び覚ます呪術という思考があったものと思われる。それは折口信夫の「明かしえぬ共同体」なのだ。
釈迢空という歌人が折口信夫なのかと知ったのは、この本を買ってからずいぶん後のこと。興味は富岡多恵子の方にあったのである。富岡多恵子『表現の風景』で障がい者の性欲ついて、その処理の仕方、母が手伝う、それらしき店に行く、ラブドール(ダッチワイフと昔は言っていたのだが、最近はこっちの方がオタク的?)を買う(作る人だったかな?)。とにかくそんなえげつないけど考えなくてはならない人もいることに衝撃を受けたのだ。あえて社会のタブーについて問題を探るその表現の手法。
それは淡々と語る富岡多恵子の文体かもしれない。今見たら「ダッチワイフの話」は第一章だけで、他は表現者のことだった。それだけ第一章が強烈だったわけだ。
性の話はとかく日本人は避ける傾向にある。それが同性愛だとなおさらなのかもしれない。折口信夫が歌人で「釈迢空」を使ったのはそれは生前に付けられた戒名であったからだという。折口の中で祀り去りたいもの、それが同性愛という当時はタブー視されたことなのであった。
それは三島由紀夫が同性愛を隠そうとして、平岡公威から三島由紀夫という仮面を被ったのに似ているのかもしれない。折口信夫の歌人としての仮面が釈迢空だったのだ。短歌をやるようになって、不思議と釈迢空の韻律に魅力を感じていた。それは言葉が少ないけど核心を付いている感じを受けたからだ。それは折口信夫の本心だったのかもしれない。それを葬る為に、呪術としての短歌を詠んだのかもしれない。
参考書籍:橋本治『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』
短歌に対する見識をアララギ時代の茂吉との悶着を通じて解き明かす。斎藤茂吉との「万葉調」の見識の違い。それは斎藤茂吉が東北出身者であり、釈迢空にしてみればまだ日本の前近代性が残存する世界だったのである。それは斎藤茂吉の最初の歌集『赤光』にある母の短歌との違い。釈迢空も茂吉『赤光』の「死にたまふ母」の歌を読んでいたいたと思われる。それは「母」なる語に次第に感情を高ぶらせてゆく叙情詩としての短歌だった。その叙情性が「万葉調」と重ね合わせたときに、短歌の手本となる日本人の古来からの叙情と言われるのだ。
それに対して釈迢空の母の死を歌った短歌には感情を繰り返し歌い上げるような叙情性を封印している。もともと釈迢空は繰り返し効果を多様する伝統歌人でもあるのだ。釈迢空の母の短歌は母に対しての感情を「歌い上げる」というせずに、どこか醒めている私性を見出している。母の死というもっとも主情的になりやすい歌なのに、それをあえてしなかったのは釈迢空の批評性があると見るのだ。それは最愛の息子(養子)春洋の死に対しても挽歌を詠むという姿勢は、己の感情よりも読者との共感を求めていたのだ。詩作の手法としては、作者にどっか冷静(客観性・批評性)の部分がないと読めないのは事実である。だから茂吉短歌もそれは写生というより創造という虚構性を塚本邦雄は茂吉『赤光』から読み取ったのだ。
折口信夫の教師時代の教え子との関係は、そのまま弟子たちの関係まで続いていた。
それは柳田國男が折口の弟子に言った言葉を富岡は深く考察している。
「加藤君、牝鶏になっちゃいけませんよ」
それを受けての折口信夫の言葉。
「同性愛を変態だと世間では言うけれど、そんなことはない。男女の間の愛情よりも、純粋だと思う。変態と考えるのは、常識論にすぎない」きっぱりした語調だった。
「柳田先生のおっしゃった意味は、ぼくには良くわからないけれど、師弟というものは、そこまでゆかないと、完全ではないのだ。単に師匠の学説をうけつぐと言うのでは、功利的なことになってしまう」
この傾向はすでに中学生教師時代に見られた折口信夫の性癖だったとする。それでも中学の先生を辞めた後に生徒との共同生活はちっとやりすぎかも。その前に夏休み旅行も行っているのだ。
町田康が富岡多恵子に「あんた折口のところにいたら、完全にやられるわよ」とか言ったとか?
その性癖を与えたのが釈迢空と戒名を与えた僧だと読み取るのだ。
そこに秘技的なものがあったのではないかと思う。それが秘技で無かったにしても折口信夫に取っては新たな異質性へ踏み込む契機となったのは間違いない。それは一方では死者の道であり、もう一方では生(性)の喜びなのである。釈迢空の「明かしえぬ共同体」があるならば、この時授けられた秘技(秘技と言ってしまうがごく一般的に言えば初夜ということなのだが。そこから日本の家父長制の制度が始めると思えば考えるに値すると思う)は別の共同体への儀式であったのだ。それによって折口信夫は独身を保っても養子として春洋を迎い入れたのである。そうしたタブー性を折口信夫としてはカミングアウトしていたのだが、釈迢空の短歌からそうしたタブー性を読み取る人はいなかった。それをあえて読み取ろうとするのは富岡多恵子の批評性である。
それは折口信夫が13歳の時の大和巡礼の旅での僧侶との出会いがもたらしたものだった。
また折口の古き時代の大阪には、まだ浄瑠璃の芸能が残っていた。その語り口が釈迢空の短歌に与えた影響も大きい。浄瑠璃というと近松の世界を想起させる。そうした不条理性が後に短歌から物語のほうへ歩み始める釈迢空の姿があるとする。
そして『死者の書』は、そうした折口信夫の決算ともいうべき書物なのである。それを捧げたのが藤無染(ふじむぜん)という折口に秘技を与えた僧なのである。
関連書籍
『釈迢空歌集』|感想・レビュー https://bookmeter.com/books/629849 #bookmeter @bookmeterより
『口訳万葉集/百人一首/新々百人一首』|感想・レビュー https://bookmeter.com/books/8322936 #bookmeter @bookmeterより
